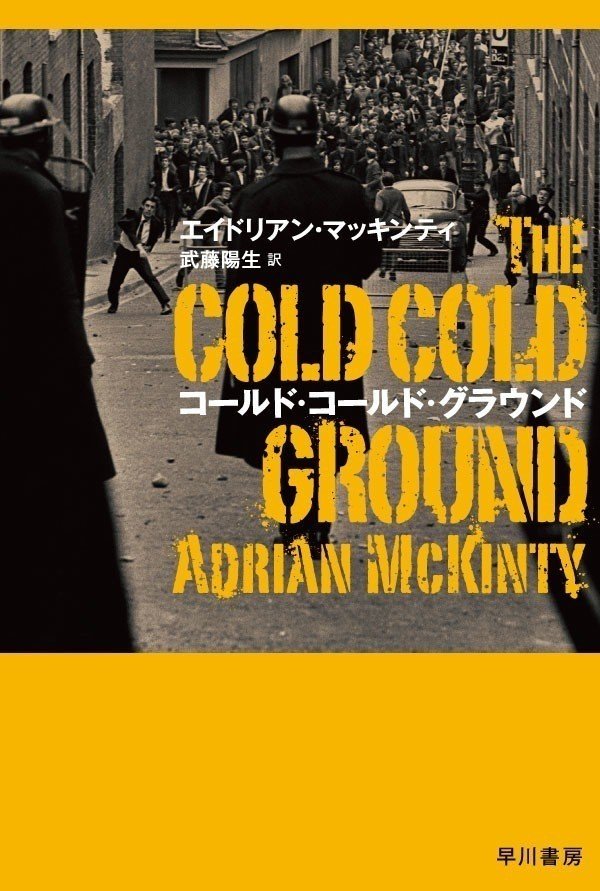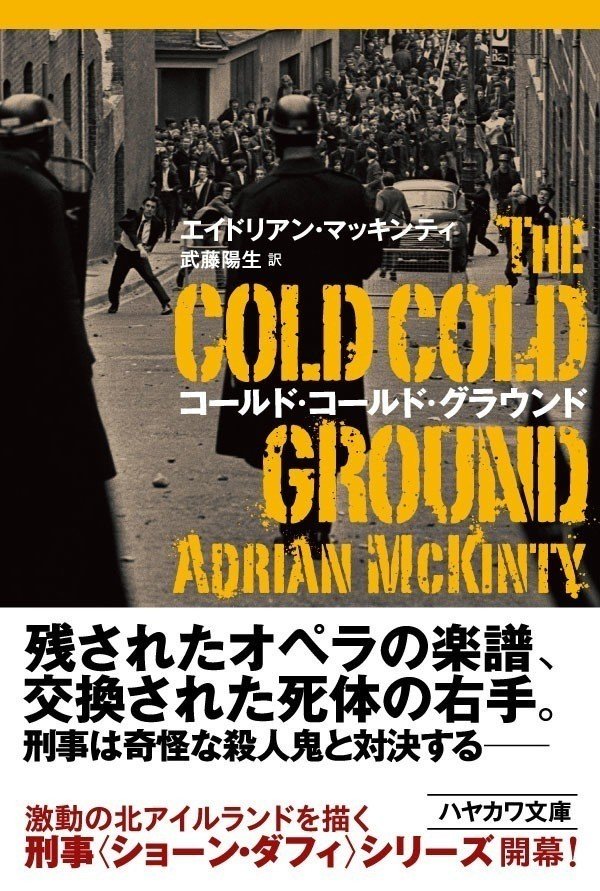特集『コールド・コールド・グラウンド』② 物語は暴動の真っ只中から始まる――冒頭部公開!
大好評発売中! 激動の北アイルランドを描いた大型警察小説『コールド・コールド・グラウンド』の特別試し読みを掲載いたします。
舞台は紛争下の1981年の英国領北アイルランド。カソリック系武装組織〈IRA〉の囚人が行っていたハンガーストライキ(※断食による抗議活動)でついに死者が発生してしまったことから、英国へのカソリック系住民の怒りが爆発してしまいます。ベルファスト近郊で暴徒と化した彼らを鎮圧すべく、駆りだされることになった王立アルスター警察の面々。その中には最近この地に赴任してきたばかりの巡査部長、ショーン・ダフィの姿も……。
コールド・コールド・グラウンド
1 シン・ブルー・ライン
暴動は今やそれ自身の美しさをまとっていた。三日月の下でガソリンの炎が描く弧。謎めく放物線のなかの深紅の光跡。プラスティック弾を吐き出す銃身(バレル)の燐光。魚雷攻撃を受けた囚人輸送船の船倉で男たちがあげる悲鳴にも似た、彼方の叫び声。厳格な地表と交わる火炎瓶(モロトフ)の緋色の響き。見渡すかぎりのヘリ。そのサーチライトが、来世の恋人同士のように、お互いの姿を見つけ出している。
そのすべてを、油っぽいベルファストの雨のレンズ越しに眺めていた。
ほかのみんなと一緒に、ノッカー山から、ランドローバーの脇に立ち。誰も何も言わなかった。言葉は無力だ。この光景にふさわしいのはピカソ。詩人ではなく。
プロテスタント系が大半を占める警察隊とカソリック系の暴徒たちが、通り十数本分におよぶふたつのいびつな前線のあちらとこちらに分かれ、にらみ合っている。ブン屋たちのカメラのフラッシュとガソリンをたっぷりはらんで燃える牛乳瓶とが相手方を照らし、暗闇のなかに浮かびあがらせ、両者の中間地帯を転がる牛乳瓶は、さながら曲線の神に捧げられた供物のよう。
ときおり一方が突撃すると、ふたつの前線がしばし触れ合い、また分かれ、もとの場所に戻っていく。
そのにおいは文明の悪臭。黒色火薬、無煙火薬(コルダイト)、導火線、灯油。
完璧だった。
それはジゼル。
白鳥の湖。
なのに……
なのに誰もが、これより上を見たことがあると感じていた。
実際、先週眼にしたばかりだった。カソリック系武装組織であるアイルランド共和軍(IRA)のハンガーストライキを指揮していたボビー・サンズが、メイズ刑務所の病院棟でいよいよくたばったときに。
ボビーは地元ニュータナビーの出身で、人っ子ひとり殺したことがなく、プロテスタントとカソリックの両方が入り交じった環境で育った。そんな彼はハンスト運動の象徴だった。ひげを生やした顔はイエス・キリストのようで、それもマイナスにはならなかった。
ボビー・サンズは弥勒菩薩(マイトレーヤ)、世界の導き手、自らが苦しみを引き受けることで衆生を救済する殉教者だった。
ハンスト開始から六十六日目にとうとうボビーが死ぬと、市内のカソリック系住民は自発的な怒りとフラストレーションを爆発させた。
といっても、それは一週間前の話だ。ハンストのふたり目の死者フランキー・ヒューズには、ボビーのような美徳はひとつもなかった。誰もフランキーをイエスになぞらえたりしなかった。彼は殺しを愉しみ、大の得意とした。子供が犠牲になろうと涙ひとつ見せなかった。たとえカメラのまえであっても。
フランキーの死を受けて起きた今回の暴動はどこか……お膳立てされているように感じられた。
たぶん、地上からは前回と同じ混沌に見えるだろし、ボストンから北京にいたる各地の明日の朝刊にもそう書かれるだろう……が、ここノッカー山から見れば、警察の優勢は明らかだった。暴徒たちは丘陵とプロテスタント居住区の狭間、市の西側の狭い一画に追い込まれていた。彼らの正面には千人の常勤警官のほか、二、三百人の予備警官、二百人からなるアルスター防衛連隊(UDR)、近接支援を担当する大隊規模のイギリス陸軍正規兵がいた。今回出動しているのは、イギリス陸軍のなかでも喧嘩に眼がないグラスゴーの荒くれぞろいと悪名高いスコットランド高地(ブラックウォッチ)連隊だ。対する暴徒は数百人──予想されていた数千人規模ではなかった。もともとのカソリック系住民の数を考慮に入れたとしても、一斉蜂起にはほど遠かったし、ましてやこれが約束された〝革命〟であるはずがなかった……とりあえず今晩のところは。
「連中は劣勢ですね」と若手のプライス巡査が口火を切った。
「だな、フランキーのためにはせいぜい半分の本気しか出せねえってこった」と、〝クラビー〟ことマクラバン巡査刑事が歯擦音の混じった、きついバリミーナ農民訛りで応じた。
「ハンストで二番目にくたばったところでお楽しみは残っちゃいないさ。ひとり目のことはみんな覚えてる。でも二番目じゃ駄目だ。フランキーのためには誰もフォークソングを書いちゃくれねえだろうな」とアラン・マカリスター巡査部長も同意した。
「ダフィ、あんたはどう思う?」プライス巡査が俺に訊いた。
俺は肩をすくめた。「クラビーの言うとおりだ。二番目じゃ大した祭りにはならない。おまけに雨も災いしたな」
「雨?」冗談だろ、とでもいうようにマカリスター巡査部長が言った。「雨なんか関係あるか! 教皇だよ。フランキーもつくづく運のないやつだ。教皇が暗殺未遂される数時間前におっ死(ち)んじまうとはな」
俺は一八七〇年から一九七〇年までにベルファストで起きた暴動について分析したことがあった。それによれば、雨と暴動は反比例する。雨量が多ければ多いほど、トラブルが起きる確率は低くなる。が、それは肚にしまっておくことにした──今この場に大卒者はいないし、学校教育をひけらかしたところでなんの得もない。それに、教皇ヨハネ・パウロ二世については大男のマカリスター巡査部長の言い分にも一理あった。ローマ教皇が誰かに撃たれるなんてのは、日ごろ耳にするようなニュースではない。
「フランキー・ヒューズは極悪人だった。あそこまでのやつはめったにいないよ。ウィル・ゴードンとその幼い娘は、あいつの現役実行部隊(A S U)に殺されたんだ」とマカリスター巡査部長はつけ加えた。
「殺されたのは男の子じゃありやせんでしたか?」とクラビー。
「いや。男の子は死ななかった。車内に爆弾が仕掛けられていて、男の子は重傷を負ったが、ウィルと幼い娘はばらばらになった」
マカリスターがそう説明すると、沈黙がおり、それは遠方から聞こえてくるプラスティック弾の発射音によってときおり中断された。
「フェニアンの馬鹿どもが」とプライスが言った。
アイルランド神話に登場するフィアナ騎士団(フェニアン)の名は、今でもカソリック教徒に対する蔑称として使われている。
マカリスター巡査部長が咳払いした。プライスは一、二秒ほど、その咳払いの意味について考え、ようやく俺がここにいることを思い出したようだった。
「すまん、悪気はなかったんだ、ダフィ」プライスは消え入りそうな声で言った。その薄い唇と困ったような顔つきが、ますます薄く、ますます困ったようになった。
「悪気はありませんでした、ダフィ巡査部長殿、だろ」とマカリスター巡査部長が言い、新米巡査をたしなめた。
「悪気はありませんでした、ダフィ巡査部長殿」プライスは不服そうに繰り返した。
「気にしないでくれ。俺も君の立場から物事を眺めてみたいものだが、そんなにおつむをお留守にもできないんでな」
みんな笑った。これを退場の台詞にして、俺はランドローバーの車内に引っ込み、《ベルファスト・テレグラフ》を読んだ。
新聞は教皇のニュースで持ちきりだった。暗殺を企てた男の名はメフメト・アリ・アジャ、トルコ人。サン・ピエトロ広場で教皇を撃った。この時点では《テレグラフ》にそれ以上の情報はなかったが、記事は衝撃を受けた地元住民や政治家の意見で水増しされていた。ジョージ・シーライトをはじめとする過激なプロテスタント右派議員数名の意見も載っていた。シーライトは、この暗殺未遂は「反キリスト者に対する重大な一撃」であると語っていた。
マカリスター巡査部長が腫れぼったい大きな顔と酒飲みに典型的な赤っ鼻を突き出し、ランドローバーの後部から車内を覗いていた。
「プライスに腹を立てたんじゃないだろうな、ショーン?」と彼はやさしい声で言った。
「まさか。雨に濡れたくなかっただけです」
マカリスター巡査部長は安堵の笑みを漏らした。こっちまで思わず口元がほころんでしまうような、俺には真似できない笑みだった。「そりゃ何より。なあ、今日はもうこのへんで切りあげないか? 俺たちの出番はなさそうだ。下で暴徒を相手にしてる連中の応援は十二分に足りてる。人手はあり余ってるよ。撤収といくか?」
「巡査部長としてはあなたが先輩ですから、あなたが決めてください」
「深夜番に登録するだけしておいて、サボっちまうことにしよう」
「アラン、それはここに登ってから耳にしたなかで、一番思慮深い発言です」
山をおりる道中、マカリスターが自作ミックステープをプレーヤーに入れ、俺たちはそれを聴いた。クリスタル・ゲイル、タミー・ウィネット、ドリー・パートン。まず俺がキャリックファーガスのコロネーション・ロードで降ろされた。「ここが新居ですか?」一一三番地の塗りたてのペンキを眺めながら、クラビーが尋ねた。
「あい。数週間前に越してきたばかりだ。時間がなくてね、ハウスウォーミング・パーティも何もできていないが」俺は口早に言った。
「買ったのか?」とマカリスター巡査部長。
俺はうなずいた。ここヴィクトリア団地では、まだほとんどの人が賃貸に住んでいる。サッチャー首相の民営化計画のもと、北アイルランド住宅機構から公営住宅を買った者はほんのわずかだ。俺は空き家だったこの家をたったの一万ポンドで購入した(もともと住んでいた一家は二年分の家賃を踏み倒したまま夜逃げした。アメリカに移住したんだ、と言う者もいるが、ほんとうのところは誰も知らない)。
「このピンクのペンキは自分で塗ったんすか?」プライスがにやにやしながら訊いた。
「ラベンダー色だよ、色のちがいもわからんのか、馬鹿たれが」と俺は言った。
プライスがきょとんとしているのを見て、マカリスターが言った。「みんな、プライスが警察の採用試験に落ちかけたわけを知ってるか? 多角形(ポリゴン)のことを死んだオウム(ポリー・ゴーン)と勘ちがいしてたんだよ」
みんな愛想笑いをして、誰かがプライスの肩を小突いた。
マカリスターが俺にウィンクした。「じゃあ、そろそろ行くよ」それを合図に、みんないっせいにローバーの後部ドアを閉めた。
「じゃあ!」と、走り去る彼らに向かって叫んだが、ローバーの防弾ガラスと装甲板越しに、その声は届かなかっただろう。
俺は暴徒鎮圧用のフル装備にヘルメット、スターリング・サブマシンガンという間抜けな格好で、そこに突っ立っていた。
小さな子供がひとり、ぽかんと口をあけてこっちを見ていた。「その銃、本物ですか?」
「だといいな」と答え、ゲートをあけて庭の小径に入った。悪い家ではない。長屋のようなテラスハウスのまんなかの一軒で、丁寧な仕事がされている。一九五〇年代に建てられた家で、ヴィクトリア団地のほかの家屋と同じく、プロテスタントの低所得労働者向けだ。もちろん、最近じゃ労働なんて、しているやつのほうが少ないが。去年、一九八〇年の秋、〈インペリアル・ケミカル・インダストリーズ〉の繊維工場が閉鎖された。キャリックファーガスの男の四人にひとりがそこで働いていた。今やこの街の失業率は二十パーセント。イギリスやオーストラリアへの移住、ベルファスト南西のダンマリーにできたばかりのデロリアンの新工場がなければ、もっとひどいことになっていただろう。デロリアンの売れ行きが大方の予想どおりなら、キャリックファーガスにも北アイルランドにも、まだ望みはある。でなければ……
「今晩はお忙しいんでしょう?」隣の玄関からキャンベル夫人が声をかけてきた。
キャンベル夫人……俺はほほえむだけにして、何も言わなかった。それが一番だ。彼女は人妻(トラブル)だ。三十二歳。赤毛。美人。旦那は北海で石油掘削の出稼ぎをしていて、留守にしている。十歳に満たない子供がふたり。絶対に駄目だ。
「ほら、暴動やら何やら、いろいろあったでしょう?」俺がドアの鍵を探しているあいだも夫人は粘っていた。
「あい」と俺は言った。
「教皇の件、お聞きになってるわよね?」
「ええ」
「この近所を探せば、容疑者が十人は見つかるでしょうね」そう言って、彼女はくっくと笑った。
「でしょうね」
「でもね、わたし個人としてはショックを受けてるわ。とてもショッキングな事件よ」
俺は何度かまばたきして、まっすぐまえを見据えた。なんだか胸騒ぎがする。夫人は俺に思いやりを示そうとしている。ということは、避けられない結論はこうだ。たぶん夫人は俺に好感を抱いていて、彼女(ならびにこの近所の住民全員)は俺がカソリックだと知っている。
越してきてから三週間と経っていないというのに。ほとんど誰とも会話していないというのに。こんなときだってのに、どうして正体がばれちまったんだ? 〝H〟の発音の仕方がまずかったか、それともコロネーション・ロードのプロテスタント連中のような辛気くささが少しばかり足りていなかったか?
錠に鍵を差し、かぶりを振って家に入った。コートをかけ、防弾ベストを脱いでリボルバーのバックルを外す。暴徒鎮圧任務に駆り出された場合にそなえ、催涙ガス弾、警棒、第二次世界大戦中に開発された物騒なサブマシンガンを支給されていた──道中でIRAに待ち伏せされた際に使えということなのだろう。そうした武器類をひとつ残らず、玄関テーブルの上にそっと置いた。
ヘルメットをフックにかけ、上階にあがった。
寝室が三つ。うちふたつを倉庫代わりにし、通りに面した寝室を自分用にしていた。そこが一番広くて、暖炉があり、眺めがよく、コロネーション・ロード一帯とその先のアントリム・ヒルズまで見晴らせるからだ。
ヴィクトリア団地はキャリックファーガスの端、つまり大ベルファスト都市圏の端っこに位置している。キャリックファーガスはじわじわとベルファストに吸収されつつあるが、今のところはまだ、いくぶん独特な性質を残している。人口一万三千人の中世の街。操業中の小さな港と、今では無人になった繊維工場が数棟。
コロネーション・ロードの北にはいかにもアイルランド的な田園地帯が、南と東には都市が広がっている。そこが気に入っていた。俺自身、その両方に属しているからだ。俺は一九五〇年、北アイルランド北東部のクシェンダンに生まれた。当時、あのあたりの地方は別の惑星のようだった。電話はなく、電気はなく、移動には馬が、料理と暖房には泥炭(ピート)が使われていた。日曜日にはプロテスタントのなかでもひときわ頭のおかしな連中が、小型の手漕ぎ
船や帆船でノース海峡を渡り、わざわざスコットランドの教会にまで足を運んでいた。
あい、俺は田舎者として世に生を享(う)けたが、ちょうど北アイルランド紛争(トラブルズ)が幕をあけた一九六九年には、心理学を勉強するため、全額の奨学金を受けてクイーンズ大学ベルファスト校にかようようになっていた。ベルファストも好きだった。あの街のバーが。路地が。性質が。それに、少なくともしばらくのあいだは、大学一帯は最悪の暴力を免れていた。
シェイマス・ヒーニー、ポール・マルドゥーン、キアラン・カーソンといった詩人たちの時代。クイーンズ大学ベルファスト校は濃さを増しつつある闇に向かって掲げられた、ささやかな蝋燭の灯だった。
自分で言うのもなんだが、優秀な学生だった。当時、心理学など誰も勉強しておらず、異彩を放っていた。まあ、ライバルがいなかっただけにしろ。優等の成績で卒業し、何人かの女性とつき合い、別れ、アイルランドの犯罪学機関誌にちょっとした論文を発表した。テーマは目撃者の証言がいかに当てにならないかについて。順当にいけば、そのまま研究者の道に留まるか、海の向こうで職を探していただろう。あの事件がなかったら。
あの事件。
それが今ここにいる理由だ。そもそも俺が警察に入った理由だ。
制服の最後の一枚を脱ぎ、戸棚のハンガーにかけた。暴動鎮圧用装備(ライオット・ギア)のベルトをつけていた部分は、大ミサに紛れ込んだ場ちがいなプロテスタント(プロディ)のように大汗をかいていた。手早くシャワーを浴び、染みついたオマワリのにおいを洗い落とした。体を乾かし、鏡に映る自分の裸体を眺める。
身長百七十七センチ。体重七十キロ。手足がひょろ長く、筋肉はあまりついていない。三十歳だが、日に六十本も煙草を吸う同僚たちとちがい、ちゃんと三十歳らしく見える。暗い色の肌、暗い色のくせっ毛、暗いブルーの瞳。鼻はケルト人らしからぬ鷲鼻で、日焼けしたばかりのころは、フランスやスペインから来た旅行者か何かと勘ちがいされることもあった(近ごろじゃ旅行に来るような物好きは多くないが)。知るかぎりでは、フランス系やスペイン系の血はこの体に一滴も流れていない。けれどクシェンダンには、昔からスペイン無敵艦隊の難破船の生き残りにまつわる眉唾ものの伝承があって……
白髪の本数を数えた。
十四本。
フランク・セルピコのひげについて考える。セルピコはニューヨーク市警の刑事で、警察の腐敗と戦った。その考えを振り払う。
鏡のなかの自分に向かって片眉をあげる。「キャンベルさん、ご主人が北海に出稼ぎに行ってしまわれていて、さぞ寂しい思いをされていることでしょう……」どういうわけか、フリオ・イグレシアスの声真似で言ってみる。
「とてもさみしいですわ。うちのなかだってこんなに寒いし……」キャンベル夫人が答える。
俺は笑い、この想像の産物に過ぎないはずのイベリア人気質の証しなのか、チェ・ゲバラのTシャツが眼に留まった。ゲバラのポスターをデザインしたジム・フィッツパトリックが、俺のために特別に印刷してくれたものだ。穿き古したジーンズとアディダスのスニーカーも見つけると、上階の灯油ヒーターに火をつけ、下階(した)に引き返した。
電気をつけ、キッチンに入る。冷蔵庫からパイントグラスを出し、ライムジュースを半分まで注ぎ、氷を入れ、居間に持っていった。居間、つまり、居心地のよい空間、リビング、ラウンジに。プロディどもにしかわからない深遠な理由により、コロネーション・ロードの住民は誰もリビングを使わない。彼らがリビングに置くのはピアノと家族用の聖書、それから警官や牧師といった賓客があったときにしか使わない硬い椅子だけだ。
そういうナンセンスには我慢がならなかった。俺はここにテレビとステレオを置いていた。やるべき飾りつけはまだ残っていたが、これまでの達成に満足していた。壁は実に非コロネーション・ロード的な、地中海を思わせる青色に塗り、デザイン系の職業訓練校で手に入れたアート──ほとんどが抽象画──の原画を何枚か飾った。本棚は小説と画集で埋め、スウェーデン製の洒落たランプを置いた。完全な構想はすでに頭のなかにできあがっている。正直いうと自分の構想ではないが、構想は構想だ。二年前、同郷のガールフレンド、グレシャの家に居候させてもらったことがあった。七〇年代初頭、紛争によって引き裂かれた北アイルランド(アルスター)を離れ、ニューヨークに渡った彼女は、向こうでプロの口達者兼有名人の取り巻きになったようで、アンディ・ウォーホルやアレン・ギンズバーグ、スーザン・ソンタグといった名前を会話の端々にちらつかせるようになっていた。そういったものには興味を感じなかったが、俺は短いながらパーティ三昧の日々を送るうちに、八丁目のセント・マークス・プレイスにある彼女の部屋にすっかり魅了されてしまった。たぶん、あの部屋の魅力の一部をここに再現しようとしているのだろう。北アイルランドのこんな僻地の、プロテスタントの掃き溜めじみた公営テラスハウスじゃ限界があるが、カーテンを閉め、音楽のボリュームをあげれば……
仕あげにアルコール度数四十五度のスミノフ・ウォッカをパイントグラスに注ぎ、ドリンクを混ぜ、本棚から適当に一冊を選んだ。
ジム・ジョーンズの『シン・レッド・ライン』。第二次世界大戦について熱心に調べていた時期に、『キャッチ゠22』『裸者と死者』『重力の虹』などと一緒に読んだ一冊だ。刑事というものはトラブルとトラブルのあいだの待ち時間のために、本を一冊、肌身離さず持ち歩いているものだ。が、目下のところ俺はその一冊を持っておらず、そのせいで神経質になっていた。折り目をつけてあったお気に入りのページをぱらぱらとめくっていると、こんな一節に出くわした。C(チャーリー)中隊のウェルシュ曹長が、兵員輸送船に乗り込む兵士たちをたっぷり二分間、ただ眺めるだけの場面だ。ウェルシュは兵士たちの質問を無視し、頭がおかしくなったと思われるのもおかまいなしに、ただ眺めている。なぜかといえば、彼はくそったれの曹長であり、望んだことはなんでもできるからだ。いい。実にいい。
その場面を読み終えると、テレビをつけ、教皇がまだ生きていることを確かめ、チャンネルをBBC2にまわした。聞いたことのないマイナーなスヌーカー・トーナメントをやっていた。酒がまわってきて、アレックス・ヒギンズ対クリフ・ソーバーン(ふたりとも五パイント目のビールを飲んでいた)の緊迫感のない試合をいい気分で楽しんでいると、電話が鳴った。
ベルの数を数えた。七回、八回、九回。十回目で玄関に出て、もう数回鳴るのを待った。
十五回目でようやく受話器を持ちあげた。
「あい?」と俺は用心しながら言った。
「いいニュースと悪いニュースがある」ブレナン警部の声だ。
「いいニュースはなんです?」
「近くだ。そこから歩いていける」
「悪いニュースは?」
「ひどい事件だってことだ」
俺はため息をついた。「やれやれ。子供ですか?」
「そういうのじゃない」
「じゃあ、どういうのです?」
「被害者の手首が片方、切り落とされとるんだ」
※
この後ショーン・ダフィが目にする、異様な殺人現場とは……?
続きはこちらの記事からどうぞ!
※書影はAmazonにリンクしております
本noteでは『コールド・コールド・グラウンド』を特集中。次回掲載は気鋭の書評家、小財満さんの入魂のレビューです。お楽しみに!
【特集リンク】
特集① 大型警察小説 刑事〈ショーン・ダフィ〉シリーズ開幕!
特集② 物語は暴動の真っ只中から始まる——冒頭部公開!
特集③ ——何が起きてもおかしくない、極限状態の警察小説【評者:小財満】
特集④——音楽が聴こえてくるミステリだ【評者:糸田屯】
特集⑤ 発見された奇妙な死体の謎とは?
【書誌情報】
タイトル:『コールド・コールド・グラウンド』
著者:エイドリアン・マッキンティ 訳者:武藤陽生
原題:THE COLD COLD GROUND
価格 :1,000円+税 ISBN:978-4-15-183301-4