
脳とは汎用の計算装置であり、眼、鼻、耳はヒトに備わったデバイスである。デイヴィッド・イーグルマン『脳の地図を書き換える』試し読み
5/24の発売直後からSNSを中心に話題を呼んでいるデイビッド・イーグルマン『脳の地図を書き換えるーー神経科学の冒険』(梶山あゆみ訳)。第4章「感覚入力を受け入れる」の一部を特別公開します。
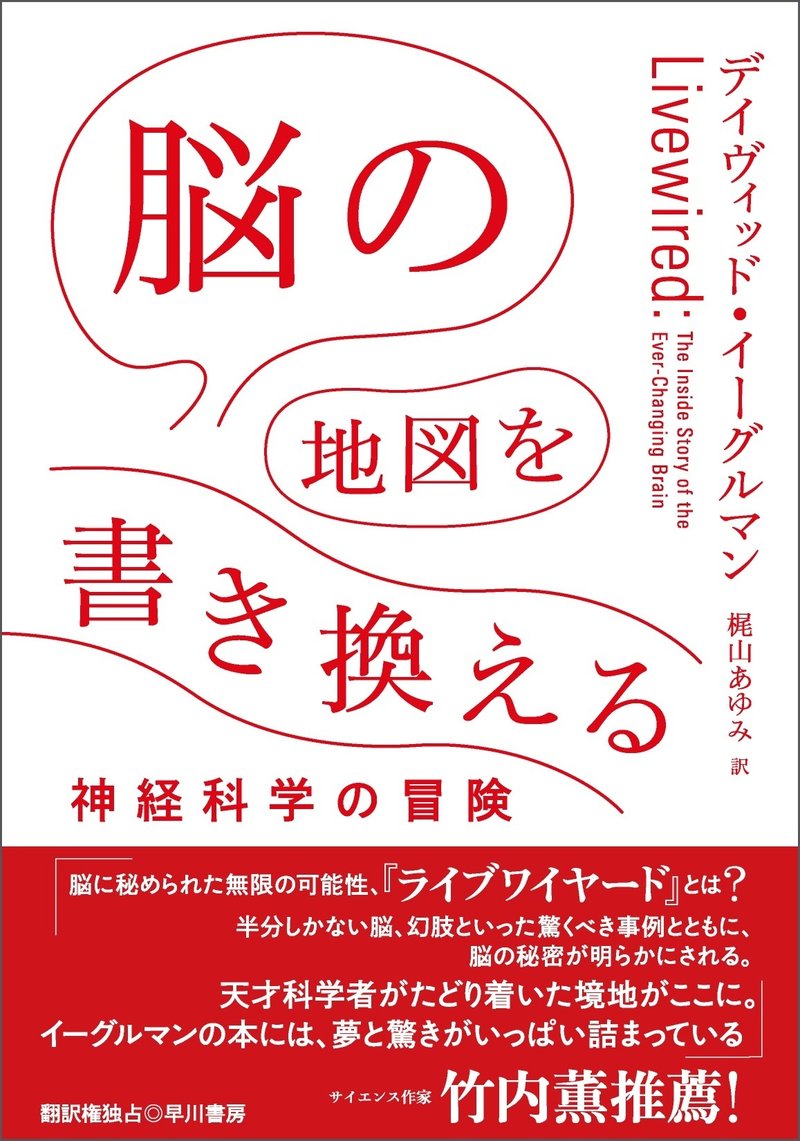
地球を席捲《せっけん》するポテトヘッドのテクノロジー
あなたがある島に出かけたとしよう。そこの住民はすべて生まれながらに目が見えない。住民はみな点字を読み、小さなパターンを指先に感じ取ることで脳に情報を入力している。あなたが見つめる前で彼らはわずかな点の突起に指を走らせては、いきなり笑い出したりすすり泣いたりしている。いったいどうすれば指先にそれだけの感情を詰め込めるのだろう。あなたは彼らにこう説明する。自分たちが小説を楽しむときには、顔についた2個の球体を特定の直線や曲線に向けるのだ、と。
それぞれの球体には細胞のびっしり生えた芝生のようなものが備わっており、それが光子の衝突を記録することで記号の形が認識される。記号の形によって表す音が異なるので、その規則はあらかじめ覚えておかないといけない。
こうして曲がりくねった個々の記号からひとつずつ小さな音が生じ、ほかの人が読み上げるのを聞くようにしてその音を頭の中に響かせる。結果として生まれる神経化学的な信号伝達のパターンが読者を弾けるように大笑いさせたり、にわかに涙に暮れさせたりする。説明がややこしいと島の住民に文句を言われたとしても、これでは責められまい。
あなたと住民はようやくひとつの真実を認めざるを得なくなる。指先にしろ眼球にしろただの周辺機器であり、外界からの情報を脳内の電気信号に変換しているにすぎないのだ、と。その意味を読み解く大変な作業はぜんぶ脳が受けもっている。突き詰めればすべては脳内を駆けめぐる数兆の電気信号に帰するのであって、どういう方法で情報が入ってくるかはまったく問題ではない。そのことに納得して住民とあなたは打ち解ける。
脳はどんな情報を与えられてもそれに適合するすべを学び、そこから可能な限りのものを引き出す。そのデータが外界の重要な何かを反映した構造をもってさえいれば(加えて次章以降で見ていく条件を備えてさえいれば)、脳はその暗号を読み解く方法を探し出す。
このことから興味深い結果がもたらされる。あなたの脳はデータがどこから来るかを知らないし、気にかけもしない。どんな情報が入ってこようと、脳はただその活用法を見つけ出すだけである。
おかげで脳という装置はじつに無駄がない。いわば汎用の計算装置だ。利用できる信号を単に吸い上げて、それで何ができるかを(ほぼ最適なかたちで)判断する。母なる自然はこうした戦略を用いることで、色々な種類の入力チャネルに工夫を凝らせるようになった。それが私の考えである。
私はこれを「ポテトヘッドの進化モデル」と呼んでいる〔訳注 「ポテトヘッド」とはジャガイモ形の人形のことで、体のパーツを好きなように差し込める〕。こういう名前にしたのは、私たちの愛するなじみ深い感覚器官が目も耳も指先もすべて、プラグ・アンド・プレイの周辺機器にすぎないという点を強調したかったからだ。機器を差し込みさえすれば準備は万端整う。入ってくるデータをどうするかは脳が考えてくれる。
こういう仕組みにしておけば、母なる自然は新しい周辺機器を組み立てるだけで新しい感覚を生み出せる。別の言い方をすると、脳の作動原理をひとたび把握してしまえば、あとは外界の様々なエネルギー源を拾い上げられるように入力チャネルをあれこれ工夫すればいい。電磁放射線の反射によって運ばれる情報は、眼球内の光子検出器に捕捉される。圧縮された空気の波なら、耳の音検出器にとらえられる。熱と触感に関する情報であれば、皮膚と呼ばれる大きなシート状の感覚素材によって集められる。化学物質の特徴は、鼻が嗅いだり舌が舐めたりする。そのすべてが翻訳されて電気信号のスパイクとなり、それが頭蓋内の暗い小部屋を駆け回る。
このように、脳がどんな感覚入力でも受けつけられる驚異の能力をもつおかげで、新しい感覚を研究開発する大変な作業は外側の感覚器官にだけ向ければいい。ポテトヘッド人形に鼻なり眼なり口なりを好きなように差し込めるのと同じで、自然も様々な機器を脳にプラグインすることで外界の多様なエネルギー源を検出している。
自分のコンピューターに接続されたプラグ・アンド・プレイ式の周辺機器を考えてみてほしい。「プラグ・アンド・プレイ」の何がありがたいかといえば、数年後に発明されるXJ‐3000スーパーウェブカメラのことをコンピューターが知らなくていっこうに構わない点である。コンピューターに求められるのは、誰かが好き勝手につくり出す未知のデバイスとすぐにつながれるインターフェイスを備えていること。そして、新しいデバイスが差し込まれたときに瞬時にデータの流れを受け取れることだ。こういう仕組みになっていれば、新しい周辺機器が発売されるたびにコンピューターを買い替えずに済む。中央装置は一台あればよく、標準化された方式で周辺器をつけ足せる穴がそこにあいてさえいればいい。
感覚器官を個別のスタンドアローン型周辺機器と見るなんて、常軌を逸した考えに思えるかもしれない。なんといっても、それらの機器を生み出すには何千もの遺伝子がかかわっているし、その遺伝子は体のほかの部分をつくる際にも重複して働いているのではないか。なのに鼻や眼や耳や舌を独立した機器ととらえて本当にいいのだろうか。私はこの問題の研究に没頭した。ポテトヘッド・モデルが正しいとしたら遺伝子の中に単純なスイッチが見つかり、それをオン・オフすることで周辺機器が現れたり消えたりするはずである。
結論からいうと、すべての遺伝子が同等なわけではない。遺伝子のプログラムが展開していく際には、精緻に定められた順番に厳密に従う。ひとつの遺伝子の発現が次の遺伝子の発現の引き金を引くといった具合に、フィードバックとフィードフォワードの織りなす高度なアルゴリズムをベースにしている。このため、たとえば鼻をつくり上げるための遺伝子プログラムにはいくつか決定的な分岐点があり、そこでプログラムのスイッチを入れたり切ったりできる。
なぜそう断言できるかといえば、遺伝子にたまたま不具合が生じたケースを見てみるといい。たとえば「無鼻症《むびしょう》」という先天性疾患の場合、子供は鼻のない状態で生まれてくる。文字どおり顔に鼻がついていないのだ。2015年にアラバマ州で生まれたイーライという赤ん坊は鼻を完全に欠いており、鼻腔や嗅覚系ももたなかった〔2017年に2歳で死亡〕。このような遺伝子変異は理解も想像も及ばないかに思えるものの、私たちのプラグ・アンド・プレイの枠組みで考えるなら当然予想がつく。遺伝子が少し変わってしまうだけで周辺機器はまったくつくられなくなる。
感覚器官をプラグ・アンド・プレイのデバイスととらえていいなら、眼球をもたずに生まれてくる疾患があってもおかしくはない。はたしてまさしくそういう状態は存在し、「無眼球症」と呼ばれる。ジョーディという赤ん坊は2014年にシカゴで生まれた。そのまぶたをめくっても、下にはなめらかでつややかな皮膚が見つかるだけである。ジョーディの行動や脳画像の結果から判断する限り、脳の残りの部分の機能にはまったく問題がない。ただ光子を捕捉する周辺機器が付属していないだけである。ジョーディの祖母は「この子は触れることで私たちを識別しています」と指摘する。母親のブラニア・ジャクソンは息子が成長したらさわれるようにと、「I love Jordy」という特殊な刺青を右の肩甲骨に――点字で――入れている。
生まれつき耳をもたないケースもある。「無耳症《むじしょう》」という稀な疾患の場合、子供は耳の外側の部分を完全に欠損した状態で生まれてくる。
それに関連した症状として、たった一個のタンパク質が変異しただけで内耳構造が消失するケースもある7。いうまでもないが、この種の遺伝子変異をもつ子供は耳がまったく聞こえない。適切な周辺機器をもたないために、圧縮された空気の波を電気信号に変換できないからである。
ではほかには何ひとつ問題がないのに、生まれつき舌だけを欠いている状態もあり得るのだろうか。もちろんだ。まさしくそういうことがアウリステラというブラジルの赤ん坊の身に起きた。アウリステラは食べるのにもしゃべるのにも、息をするのにも長年苦労していたが、大人になったいまは舌を形成する手術がうまくいき、舌のない状態で生まれ育つことがどういうものかをインタビューで力強く巧みに物語れるまでになっている。
私たちが分解可能であることを示す珍しい事例はほかにも色々ある。生まれつき皮膚と臓器に痛み受容体が存在しない子供もいて、人生の冴えない瞬間に痛みや苦痛に見舞われてもそれをまったく感じない(そう聞くといいことのように思うかもしれないが、そうではない。痛みを経験できない子供は何を避ければいいかがわからないので傷だらけになり、若くして命を落とすケースが多い)。皮膚には痛み以外にも、伸張、かゆみ、温度などを感知する受容体があり、その一部だけが欠けていてほかは無事ということは起こり得る。このような状態を総称して「触覚消失」という。
こうした数々の障害に目を向けると、私たちの周辺探知器がそれぞれ特有の遺伝子プログラムで組み立てられているのがわかる。関連する遺伝子に些細な異常がひとつ起きただけでもプログラムは停止しかねず、そうなれば脳は特定のデータの流れを受け取れなくなる。
*****
大脳皮質を汎用計算装置としてとらえると、進化の過程で新しい感覚技能がどのようにつけ足されてきたかが垣間見られる。遺伝子変異によって一個の周辺機器が誕生すると新しいデータの流れがどこかの脳領域に向かい、神経情報処理機構が仕事に取りかかる。つまり、新しい感覚技能を生み出すには新しい感覚デバイスを開発しさえすればいい。
動物界全体を見渡したときに、ありとあらゆる奇妙な周辺機器が見つかるのはそのためだ。そのひとつひとつは進化を通じて数百万年かけて形づくられている。あなたがヘビなら、DNA配列がピット器官をこしらえて赤外線情報をとらえる。あなたがブラックゴーストナイフフィッシュなら、遺伝子の文字が電気センサーを生み出して電場の乱れを感知する。ブラッドハウンド犬なら、遺伝暗号が読み解かれた末に嗅覚受容体の詰まった大きな鼻ができる。シャコであれば、遺伝子の指示で眼に16種類の光受容体がつくられる。ホシバナモグラだったら22本の指のような突起が鼻に生えて、それで辺りを探りながら自身のトンネルシステムの立体モデルを脳内に構築する。鳥、ウシ、昆虫には地磁気を感知できるものが多く、地球の磁場に体の向きを合わせるのにそれを役立てる。
こうした多種多様な周辺機器に対応させるために、そのつど脳を設計し直さなくてはいけないのだろうか。その必要はないと私は考えている。進化の過程でランダムな遺伝子変異が起きて未知の感覚器官が生まれても、情報を受け取る側の脳はただそれをどう活用するかを探り出すだけだ。脳の作動原理がひとたび定まってしまえば、自然は新しい感覚器官を設計することだけに腐心すればいい。
こういう角度から眺めると、ヒトに備わったデバイス――眼、鼻、耳、舌、指先――以外にも色々な機器があり得ることがわかる。現在の私たちがもっている周辺機器は、進化の長い紆余曲折からたまたま受け継いできたものにすぎない。
だとすれば、いまある感覚器官だけにしがみつく必要はないのではないか。
というのも、色々な入力データを脳が受け入れられるのならひとつ突飛な予想が成り立ち、一個の感覚経路を使って別の感覚情報を運ぶのも夢ではないことになるからだ。たとえば、ビデオカメラからのデータの流れを皮膚の触感に変換したらどうなるだろう。いずれは触れるだけで脳が視覚的な世界を解せるようになるだろうか。
小説より奇なる「感覚代行」の世界へようこそ。
(この続きは製品版でお読みください!)

