
「独学」が危険な理由。ジョセフ・ヒース『啓蒙思想2.0〔新版〕』試し読み
なぜ私たちは合理的思考を見失ってしまいがちなのか?
好評発売中の新刊『啓蒙思想2.0〔新版〕 政治・経済・生活を正気に戻すために』(ジョセフ・ヒース、栗原百代訳/ハヤカワ・ノンフィクション文庫)より、「正気」を取り戻すためのヒントを紹介します。
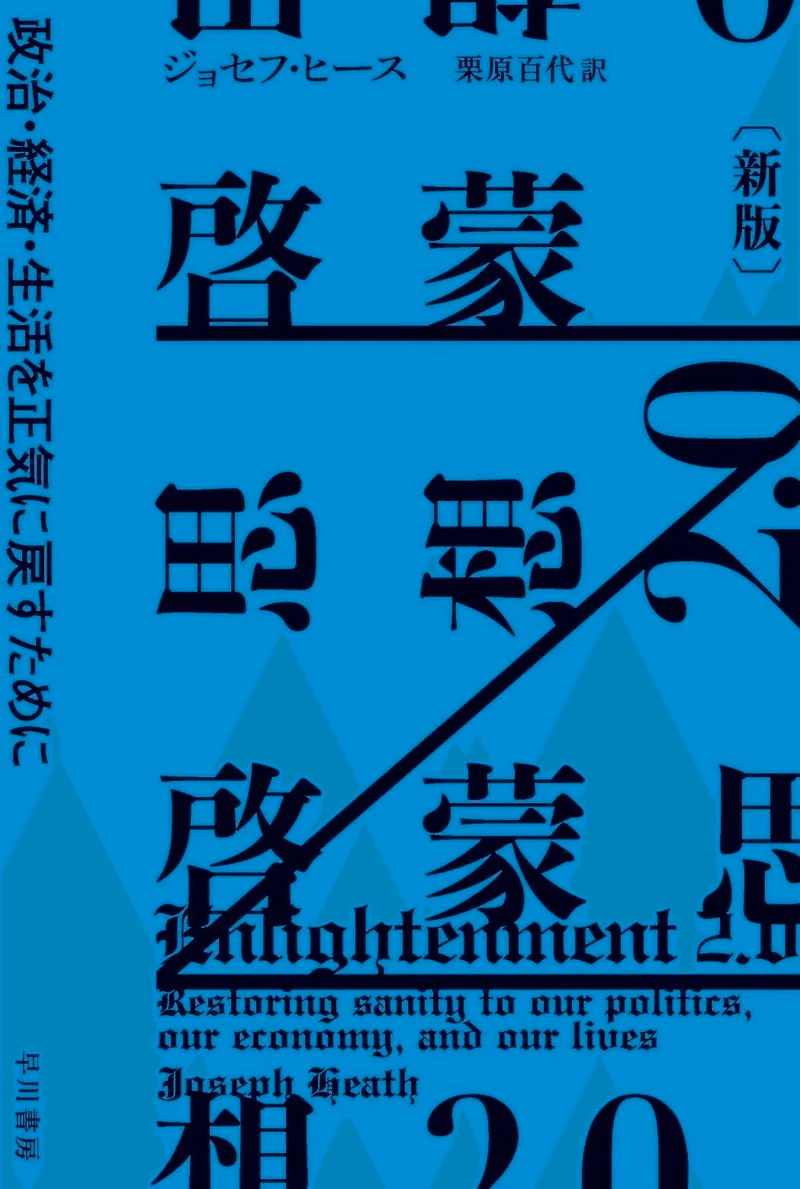
どうやって正気を取り戻すかを考えるとき、合理的思考の根本的な特徴をおさらいしておくことは役に立つ。時間がかかる。注意力が求められる。言葉に基づいている。意識的。非常に明示的。またワーキングメモリに依存しているせいで活動が妨げられやすい。したがって、推論の中間段階をメモ書きするといった外部化から恩恵を受ける。
どうしてこの思考様式がすっかり環境に支配されてしまっているのかはわかりやすい。スピードという単純な問題だ。理性の遅さについて考えてみよう。ある考えや主張はかなり簡単なものでも、説明するのに優に10分から15分はかかる。しかも教室という恵まれた環境の外で、きちんと座って、何かを説明する人に耳を傾けるよう強いられること(リモコンでチャンネルを変えたり、フェイスブックをチェックしたり、話の腰を折ったりはしないで)は驚くほどめったにない。宗教上の説教が大切な例外だ、という人もいる。ただし、話題の範囲はとても限られがちだ。
つまり、人は学校教育を終えると、断片的には伝えることのできない新しいものごとを学ぶ機会はほんのわずかしかない、ということだ。
例として、自由貿易という基本的な経済論議について考えよう。この議論はとりたてて複雑ではないが、一つには、賃金水準が大きく異なる二国間の貿易でも豊かな国の賃金に下げ圧力が生じないことを示しているせいで、きわめて反直感的である。デイヴィッド・リカードが1817年に基本的な分析をまとめ、以来それは経済学の定番カリキュラムとなった。残念なことに、たいていの人は正規の経済学の授業を受けないから、国際貿易の基本構造に対する誤解はほとんど世界共通である。
理屈の上では、人は本を読んだり映像を見たりして理解に努めることができる。しかしポール・クルーグマンの所見どおり、そんな人はめったにいない。クルーグマンはこれをちょっとした謎だと思う。「世界経済についてだらだら話すテレビを何百時間でも喜んで見ている政策屋は、なんでリカードの説明にかかる10分かそこら、じっと座っていたくないというのか?」
だがクルーグマンは観察するなかで、結局、自らの問いに自ら答えることになる。「リカードモデルをおとなしい学生に教えるのは別のことだ。学生は広範な経済学の研究のなかで、このモデルを頭に入れるし、どのみち試験に合格したければ、注意して聴いて、こちらが教えるとおりのことを学ばざるをえない。しかし一般成人に、特にすでにこのテーマについて意見をもっている人に説明しようとしたら、明白と思っていたあなたのもう一つの説も実は明白ではないのだと悟って、撤回を余儀なくされつづけることになる」
日常の社会環境にいる成人の問題は、ほとんど教えるのが不可能なことだ。クルーグマンが教室の社会的な面を、議論に適したコミュニケーションに欠かせないものと認めているのは、偶然ではない。聴き手がある程度の仮定を受け入れることは、議論の展開には不可欠だ。
また議論は脱文脈化されたシンプルなモデルに依拠する。世界について知るすべて、というか世界について知っていると思うすべてに注力するのではなく、あらゆることを棚上げにして、たとえば二つの財を交換する二人の関係を抽象的に考えるよう求められる。これは平均的な人物にとって、英雄的なレベルの精神抑制およびセルフコントロール(基本的演算バイアスに対抗する)が要求されるものだ。教室はこの負担をかなり減じる外部足場を提供している。
クルーグマンが学生を「おとなしい」と形容するのは、からかっているだけではない。教室の重要な特徴の一つが、学生は授業の邪魔をしてはならないことだ。質問があれば手を挙げさせられ、なおかつ教師には「あとで。このポイントを説明してから」と言える特権がある。これは議論の持続という点では、実は非常に重要なことだが、およそほかの社会的状況ではひどく不自然で落ちつかない。リカードでも、ほかのなんとなく込み入った議論でもそうだが、たとえばディナーパーティーの席で説明しようとしたら、いくつかの社会慣習を破らずにするのは不可能だとわかるだろう。
そもそも、なにしろそれだと長い時間しゃべりすぎて「退屈な人」にならざるをえない。それに、口を挟んでくる人というのは必ずいて、たいていは勇み足で異論を述べたり、冗談を言ったり、議論から脱線した問題を提起したりする。あいにく、間が悪くならずに10分間でも話しつづけられる「自然な」社会環境などはほとんどない。認識すべき重要なポイントは、こうしてそれがこの環境で伝えることのできる種類の考えかどうか、ふるいにかけられているということだ。
これらに対して一つ重要な例外がある。それは書き言葉だ。実際、ざっと一時間よりも長い議論にとって、本はかけがえのないツールである。たとえば、進化論について考えていこう。進化論はこれまた非常に反直感的なのだが、それは主として地球の年齢と進化の過程が進んできた長い時間のためだ。人は誰でも1年、10年、1世紀でさえもどれくらいの長さかという直感的な「感覚」をもっている。
しかし数十億年についての話となると、それは本のページに印刷されただけの数字と化す。どれぐらい長いかの「感覚」はなく、非常に長い時間だと知的に認識するだけだ。そのため、この時間尺度で何がありそうで何がなさそうかの判断はうんともすんとも働かない。進化論に対する「常識」的な反論のほとんどはリチャード・ドーキンスが「個人的懐疑に基づいた議論」と呼ぶもの、つまり「私には信じがたいので真実であるはずがない」という論法である。
だがこうした議論は一皮めくれば、それが信じがたいのは、起こりそうなことについての直感的感覚に反するからだとわかる。このために蓋然性(確からしさ)についての直感的判断は、最良の時でも信頼できないうえに、100万年とか、ましてや40億年にわたって起こったような問題については、まったく役に立たない。
私が思うに、進化論をきちんと(つまり自然選択のメカニズムと、理論を裏づける最も大切な証拠の数々を)説明するには、短くとも1時間はかかる。このために、本は理論を広めるのに非常に重要な役割を果たしている。今日まで、有効な代替手段は見つかっていない。たとえば注目すべきこととして、デイヴィッド・アッテンボローがナレーションを担当するBBCシリーズのような自然ドキュメンタリー番組は、その人気にもかかわらず、進化論が正しいことを前提としていながら、いっさい説明しようとしていない。
テレビの草創期には、この新しい技術が大衆に教育をもたらす強力な媒体になると考えられていた。人が学校に通うのではなく、授業を録画し配信することで、学校を届けられるのだ(現在、インターネット技術と遠隔教育をめぐって同じような熱狂が進行中だ)。だが、このプロジェクトは完全に失敗であった。それはなぜか。「学校」とはカリキュラムだけではない、社会環境でもあるからだ。
このため、社会で合理性を育むという点では、伝統的な正規学校教育に代わるものはない。旧式な教育慣習に関して権威主義だと批判されたことの多く──教師による教室管理、整然と並べられた机、読書課題、問題集、しめきり、テスト、そして成績評価──は、同時に集中力、計画性、目標達成についてセルフコントロールの不足を補うように作られた外部足場と見なすこともできる。
当然のことながら、特権を濫用する教師もいる。けれど教室での学習の利点を知るには、独学の人としばらく会話してみるだけでいい。独学者に最もよく見られる特徴は、規律のなさ──とかくよい考えと悪い考えを区別できないのに加えて、落ちつきのない認知スタイルである。
確証バイアスはとりわけ深刻な落とし穴だ。伝統的な教室とカリキュラムの利点の一つは、自分以外の人が系統立てたとおりに教材を学ばされ、最初から共感できることだけでなく抵抗のある考えをも理解できるようになることだ。自学自習には選り好みしたくなる誘惑があるから、そのせいで独学者はとりわけ確証バイアスと陰謀論に陥りやすいようだ。
学者は大学のゼミナールをひな型にした政治を行ないたがる、と非難されることがある。熟慮がどこかの時点で行動に移される必要がある、利害の政治の世界で、それは実行不能だし望ましくもないことを理解しなければならない。同時に、大学のゼミがそのように作られているのには理由がある。人は考えようとするとき、おのずと思考に役立つような環境を求める。
国民一般の熟慮を増進するためには、教室をひな型に世界を作り直すまでもないが、そのひな型の要素のいくつかは備えているべきだ。たとえば、理性はどうしようもなくのろいし、線形であるから注意を要する。しかし、私たちはこのような思考様式を可能にする環境の要素をしばしば破壊してしまう──ときにうっかりして、またときに、思考がどうなされるかについてのいろいろな誤った理論のせいで。
その例として、多くの企業が、広告代理店などの「クリエイティブな」会社の職場スタイルに感銘を受け、さまざまなやり方で再現しようとしてきた。新聞社に勤める友人は、ある日、会社の「改革」にあたっている経営コンサルタントの一団からの通告に戦慄した。職場の仕切りも個室もすべてなくして一台の巨大なアメーバ型のデスクを置き、ニュース編集室の全員がそこで仕事をするのだという。
これは、異なる部署間にできた「サイロ」[縦割りの組織構造]を切り崩し、書類仕事をやっつけ、就業時間中はとめどなく会話が「流れる」職場に変えることを意図していた。もっと「流動的な」職場環境を生み出すべく、個人の仕事スペースも奪われることになった。
このような仕様は広告代理店でブレインストーミングを促すのには有効かもしれないが、新聞社では事情がまったく違う。短くて歯切れのいいコピーやビジュアルが中心の広告とデザインは、直感的な思考様式にぐんと偏っている。これに対し、編集者とライターには集中することが必要だ。変更された職場ではそれがほとんど不可能になった。オフィスを取り上げられた友人は、印刷へ回す前に原稿を読み返すための静かで平和な空間を求めて、実際ときどきトイレに引きこもった。一年と経たないうちに、アメーバ型のデスクは消え去った。
この場合には、取るべき選択は明らかだった。新しい職場レイアウトでは、誰も仕事ができなかったのだ。それでも多くの職場で、これほど過激ではないにしても同種の改革が行なわれ、いまも効力を保っている。たとえば、社員はデスクをきれいにしておかないといけない、書類を山積みにしてはいけないという共通のルールは、多くの社員から、作業を体系化する非常に強力な外的メカニズムを奪っている。この制限は生産性を低下させるが、まったく不可能なほどにはならないから、労働者の認知に不利に働きながらも、このルールは存続するかもしれない。
こうした職場ルールの一部は、悪しき心理学の単純な結果である。だが残りは、直感的思考様式とそれを重視する「クリエイティブな」業界をほめそやす、文化の一般的傾向の産物である。仕事によっては、およそ正反対の環境が必要になることが認識されていない。不透明な木製ドアで閉ざされた旧式のオフィスは、とりたてて魅力的ではないかもしれないが、一つの作業に一分以上集中できる環境を作り出すことが目的なら、かなり大きなメリットがある。
(『啓蒙思想2.0〔新版〕』第12章「精神的環境を守る」より抜粋)

