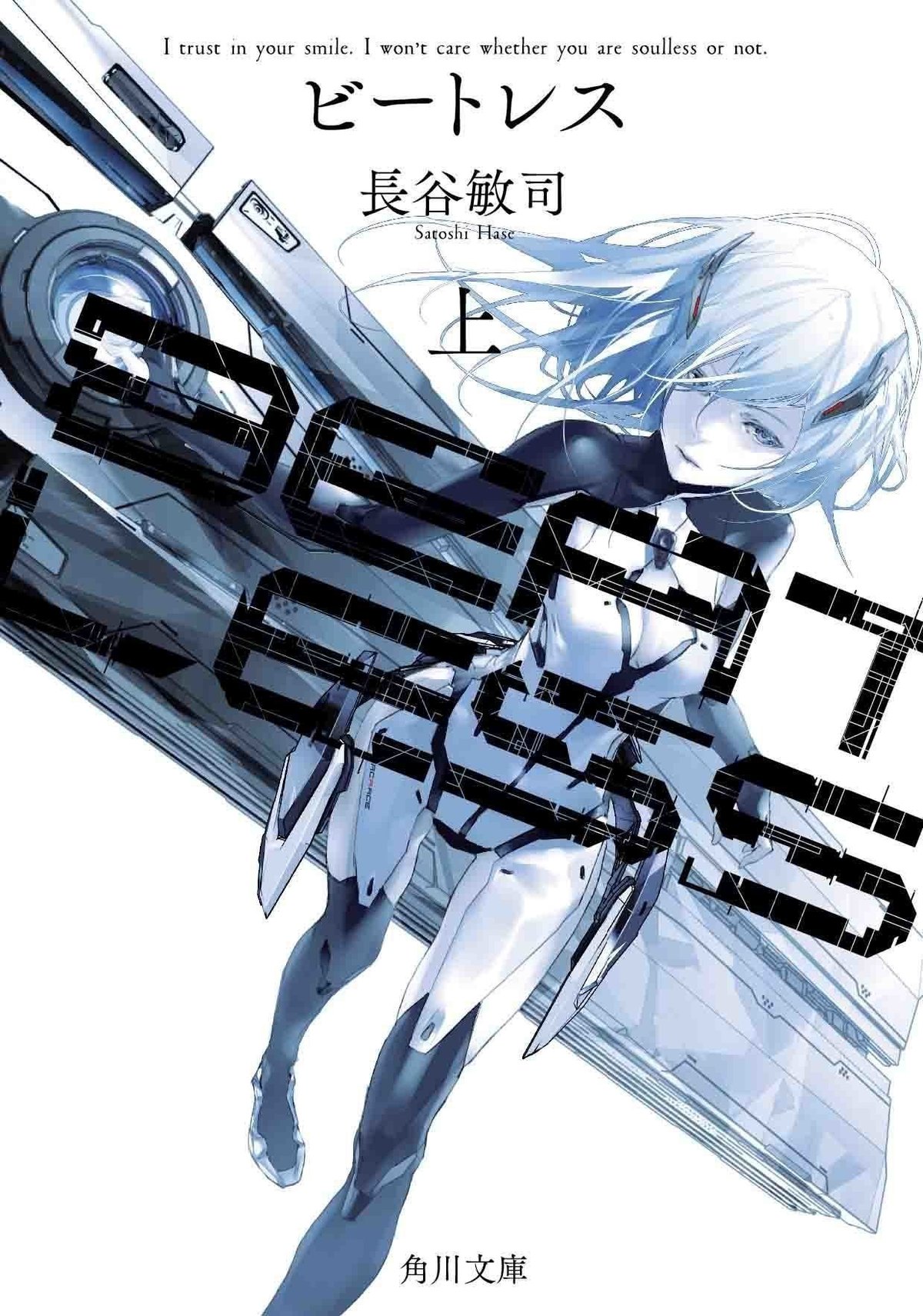現実がSF化していく時代の、SF作家のありかた。『BEATLESS』長谷敏司インタビュー
2月24日(土)発売のSFマガジン最新号より、現在TVアニメが好評放送中の『BEATLESS』原作者・長谷敏司氏へのインタビューを再録します。同誌には長谷氏による書き下ろしスピンオフ小説を含む『BEATLESS』特集を掲載! 本記事と合わせてお楽しみください。
■アニメのための物語
──『BEATLESS』は〈月刊ニュータイプ〉での連載が始まったのが2011年4月号、およそ6年半後のアニメ化という一大プロジェクトとなったわけですが、あらためて企画の発端からの経緯を教えていただけますか。
長谷 発端は、フィギュアと連動した小説企画ですね。駆け足で14話やって、夏前に連載が終わったら10月にもう本が出た(笑)。かなり大変な企画でした。
──アニメ化の話はいつごろから出ていたのでしょうか?
長谷 最初からメディアミックス展開には積極的でしたが、紆余曲折あって、今の座組みが固まったのが2016年の夏ぐらいです。監督が水島精二さんに決まって、水島監督が脚本に高橋龍也さんを指名し、高橋さんが雑破業さんを呼んで……という感じだったと記憶してます。雑破さんは大学の先輩で定期的にお会いするんですけど、「原作者って何したらいいの?」と聞いたら、「できあがったものをひっくり返されるとたいへんだ」と言われまして。原作者として意見を言うなら、脚本作成の段階なら対応しやすいし、作業も逆戻りにならないからと。それで、すべての脚本会議に参加させていただくことを決めたわけです。
──脚本にはどの程度関わっていらっしゃるのでしょうか。
長谷 脚本やシリーズ構成を書いているわけでは、もちろんないです。脚本家の人と相談しながら、原作をアニメ化したときにちゃんと映像に乗る部分、乗らない部分の説明を受け意見を言って議論して、最終的にはこれならいけるだろうという形で納得して首を縦に振るのが自分の役目です。
──とくにこだわった点はどこですか。
長谷 とにかく、間口を狭くしないように気をつけています。放送が続いていく途中で視聴者さんに「これは自分と関係がない話だ」と思われてしまうと、いくらその後の出来が素晴らしかったとしても、そこで止まってしまうわけですから。
『BEATLESS』はもともとアニメ誌に連載していた、アニメの構図を意識して作った話なので、SFファンだけではなくアニメファンにも受け入れてもらえる作品だと思っていました。それが実際にアニメ化されるというのは本当に面白いことで、放送されてからSNSの反応を観ていても、作中のアラトと同じようにヒロインのレイシアに惹かれている人がすごく多いんですよね。まさにそういう人にSF的な体験をしてほしくて作った話なので、ぜひ後半まで観続けてもらいたいんです。
そのためもあり、アニメではボーイ・ミーツ・ガールの要素をすごく大事にしています。SF的な視点だけで観なくても感じられるエモーショナル部分というか。若い方にはもちろん年季の入ったアニメファンでも、最後の着地点までついてきてくれれば「そういうことだったのか!」と思ってもらえるようなラストが用意されているので。
──アニメではhIE(humanoid Interface Elements)がいっそう人間っぽく見えますが、ここからだんだんヒトとの差が浮き彫りになっていくのでしょうか。
長谷 そこは僕にとっても未知数なところがあります。アニメとして映像が完成したとき、どこまで人間らしさというものを、外見だけで維持できるのか。最後の最後は誰にもまだわからないか、監督の頭にしかないかも。どこまで人間から離れても大丈夫かというのを商業アニメの文脈で、未踏の地をゆくように進んでいく。
アニメーションってキャラクターを人間に見せるように特徴をつける技術なので、逆にhIEを人間ではないように表現していくとどうなるのか。小説のときはあまり言われませんでしたが、映像体験で、ヒトと同じ形をしている存在をモノとして扱うのは差別的ではないかと考える方がけっこういらっしゃって興味深いです。でも、それなら人間と少し形を変えて印をつけたりするほうが身体権に関わる差別のはずなんですよね。区別するために人工的な標識をつけるということなので。
自分にとって人型ロボットのそういう描かれかたに違和感があって、まったく見分けがつかないほうが合理的だと思ったんです。そうやって記号を外してみた結果、物語にかかっていた無意識の差別性がいかに強かったかに気づけたので、ちょっと面白かったです。
──よくある「ロボットキャラ」のように、顔や体にパーツ分割の線を入れたり、喋り方を機械っぽくして記号を付けること自体が差別かもしれないと。
長谷 そうですね。人型として作っているのに、区別するために人間とあえて違う特徴を付けること自体差別ではないかと。マークをつけることによってモノとして扱うということですから、技術のレベルが充分に上がっても、pepperみたいにロボットだと一目で判別できる姿を作ることは、実はわりと問題があることなのかもしれない。
──アニメ版の物語の今後の展開としてはどのようになっていくのでしょうか。
長谷 原作通りにこれからライトノベル的なところからSF的なところへ進んでいくことになります。そのときhIEを見た視聴者さんは、アラトやリョウと一緒に「これは人間ではない」と揺さぶられていくかもしれません。7~8話ぐらいになると「hIEは本当に人間と同じだと思っていてもいいのか」という問いが出てくるので、人間的なものと非人間的なものががっつり交差していきます。キャラクターの設定的にそうである、というだけでなく、物語的にもhIEという存在の不確かさがクローズアップされ始めるので、そのときにアラトと一緒に、どこまでレイシアを信じられるか。
実際のところ、人間と人間でないモノの区別は体感的・社会的なものでもありますし、私たちがアニメキャラを人間だと思うこと自体も「アナログハック」という言葉で作中でギミック化されている。そのうえで、視聴者さんたちはキャラクターを信じられるか。こうして考えると、アニメという表現は『BEATLESS』という作品にとって、もともと想定していたテーマをいちばん直接的に問うことができる、ベストの舞台だと思いますね。
■いま、SFの未来を考える
──実際に最先端の現場に立たれてみて、SF小説のメディアミックスの可能性についてはどう思われましたか。
長谷 小説っていうのは抽象的なメディアですよね。あらゆるものに言葉でラベルを貼ることができる。それらの言葉に繋がるものをイメージ化して、脳内にヴィジョンをもってもらうということができる。これはアニメには絶対に不可能なことなので、小説にしかできないことと、アニメにしたほうが映えることは別と考えたほうがいいとわかりました。
たとえば映像にはドラマは乗るけど、言葉遊びは乗せにくい。SF小説は現実にないものでも言語の力で読者に想像させることができるのが明確な強みですよね。酉島伝法さんの作品世界なんかとくにそうですが、言語のラベル化能力と洒落によって世界の情感を表現している。
いっぽうで、映像は表現ひとつひとつに美術のレイアウトやキャラクターの設定、動作、声、BGMを乗せていく。それだけのカロリーをかけたうえに、さらに演出でどうシーンを見せるかも考えます。大変なことをやっているぶん、純粋に時間あたりに伝わる情報量、お客さんの意識を持っていく力が強い。そういった表現の違いに合わせた小説の書き方もあると思います。
──映像向きの小説の書き方があるということでしょうか。
長谷 僕自身は自作をアニメ化してもらう経験があっただけで、ゼロから脚本を作ったことはありません。だからアニメと比較してSF小説を語るというのは、僕は半分側からの体験しかないので少し言いにくいところです。でも、もし今後新しくアニメのシリーズ構成や脚本をやらせてもらえることがあったら、そのときはまた別の感覚が見えてくるかもしれないです。
最近よく思うのですが、SF作家たちがデビューしてからいろんなところで仕事ができるようにしていけるといいですよね。ストーリー創作にかかわる仕事や、取材になって小説と相乗効果のある仕事を続けて暮らしていけるようになってほしい。僕も今は理化学研究所のパートタイムで会議に出たりしているのですが、「SFが現実に追いつかれる」というのは、SFの論理が一般社会で役に立つ時代だという意味でもあるなと感じています。
SFが浸透と拡散を遂げたというのはネガティブな文脈でも使われがちですけど、単に一般化したことで信用を得たとも言えるんですよね。むしろこの可能性も限界まで広げていくのが現役のSF作家の仕事だと考えています。SFというのは面白いジャンルだ、できることがいっぱいあると世の中に思ってもらえたら、優秀な人がSFの世界を目指してくれるかもしれないし、今いる小説家にとってもキャリアプランが広がりますよね。
出版のありかたが大きく変わっていくであろうこれからの時代、小説家もあらゆる収入源を出版社に頼った状態を考え続けるよりは、自分にできることを使って全力で外に広がるほうがいいですよ。僕は小説屋なのでもちろん小説が仕事の核ですけど、小説の単著があるというのを名刺にして、外側に仕事を広げていくことは可能です。そうやって自分の名前を広げていって次に書く小説の読者を増やしていくとか。そういう自分なりのエコシステムを作りたい。いろいろ試行錯誤できそうだと思います。それが現実がSF化している時代の、SF作家のひとつのありかたなのかなと。
現実がSFになったからSF作家が役目を終えたのではなく、逆にSFに現実に通用する社会的信頼ができたと考えたい。SF的な想像力を面白いと信用してもらえる入口があるかぎり、本業として作家であるということは変わらないんです。読者の皆さんにとっての作家に対する求心力の源泉も小説なので、そこも昔と同じ。ただ、SFの持っている力を作家自身がメンテナンスしないといけない、そういう時代になってきているのだと思います。そのほうが10年・20年後に、才能のある人たちがSFを書き続けてくれている環境も作れるんじゃないか。あまり今の状況にあぐらをかいてばかりはいられないですよね。
──そうやって作家として実際に社会的に活動されてみて、たとえば世の中がSFに期待していることと、実際のSF創作との乖離を感じることはありますか。おそらくそこで期待されているSFは、多くが技術系だったり近未来寄りのものですよね。
長谷 SFの流行が現実の未来を意識した技術寄りになりすぎると、たしかに思弁的・言語的なSFが好きな人にとっては味気なかったりすると思います。クラーク的なSFばかりだとハインライン好きには味気ないということになっちゃうし、バラード好きだっていますからね。僕自身だって、書いている小説自体はあんまり社会的ではありません。
ただ、現実との繋がりを原点にして、SFを面白いと思ってくれる読者が一人でも増えてくれるかもしれないことは忘れてはいけないと思います。そういう人が賞に応募したりいろんなルートで作家になれば新人もさらに増えていきますし、現役作家が仕事の幅を拡げていけば、後に続く世代も自分なりの仕事の方法を新しく見つけやすくなるかもしれない。いろいろな小説家としての働き方があると思いますが、とにかくお互いをリスペクトしながら一つ一つの課題をちゃんとこなして、お客さんにも次を期待してもらえる仕事をしていきたいと思います。
──「SFとは」というジャンル全体論も時代にあわせてアップデートされていく、ということですね。
長谷 作家が全体論を語るのは、そうして考えないと5年後10年後の自分自身の生活のヴィジョンが描けないからですよ。どうしたらSF作家として仕事を続けていけるのかを考えることが、SFの未来を考えることに必然的に繋がっていく。
いま日本の理系研究職の現場も、学術政策の影響などで苦しい状況です。幕末に黒船が来てるみたいな状況で、今後のプランを作らないといけないということが、真剣に議論されている。選択肢は一つでも多いほうがいい状況ですから、SF的な想像力が役立てる機会も増えていくと思います。今後、世の中の科学に対する興味をもう一度取り戻そう、という運動は間違いなく出てくる。ですから早川書房もぜひ、科学や技術に強い作家たちを集めて新しいことをやってください。2010年も後半になって新しい才能が次々とデビューしていますけど、たとえば小川哲さんのような書き手が10年後、20年後もSFを書けるような環境であってほしい。それはそれで、ポスト伊藤計劃時代のさらに先を考えていく課題の一つだという気がします。
■新しい『BEATLESS』のかたち
──ちょうど2月24日に、単行本版の発売から5年以上を経て『BEATLESS』文庫版(角川文庫/上下巻)が発売になりますね。内容にはかなり手を入れられたのでしょうか。
長谷 単行本版ではキャラクター小説として読んでいた方から「後半がわからない」と言われがちだったので、そこを注意して直しました。説明や補足がかなり足されたため、わかりやすくなっただけではなく、新たな見方ができたりするかもしれない。文庫にして60ページぶんくらいは単行本から増えたと思います。原稿用紙の合計で2000枚くらいになったかも。
──初めて読む方はもちろん、単行本発売から5年ぶりに再読してみよう、という方も多そうですね。
長谷 これ結局何だったの、という部分に補足が入って鮮明になったほか、感情線のつながりを修正したり、ドラマ部分がスムーズになったり、アニメの脚本会議で出てきた原作への疑問点もクリアしたうえで、さらにアニメでは表現できなかったことを入れたりしているので、小説としてはより完成度があがって、完全版といえるくらいの加筆修正が入っています。単行本で読んでいただいた方にも、ぜひまた手にとってもらいたいです。
──最後に、読者の皆さんへのメッセージをお願いします。
長谷 アニメ版は間違いなく、読書体験とはまったく違う形の『BEATLESS』を楽しめます。文章で書かれるキャラクターとアニメで描かれるキャラクターは見え方が違いますが、原作の読者さんはその両方向を比べることができる。とくにキャラクターに特化したテーマをもった『BEATLESS』という作品でそれができるのは、なかなかない原作読者だけの特権だと思います。だから30分アニメの24話ぶん、人生における12時間ほどなら費やしてもらっても決して損はないんじゃないかと思います。原作者の欲目かもしれませんけど(笑)。
──ありがとうございました。
(2018年2月6日/千葉県某所)
ⓒ長谷敏司・monochrom 2012,2018