
【映画化原作】高級ブランドGUCCIの三代目社長が殺害された。容疑者は、元妻――。『ハウス・オブ・グッチ』試し読み
高級ブランドGUCCIの三代目社長が殺害された。容疑者は、元妻――。
1995年3月、GUCCIの三代目社長マウリツィオ・グッチが殺害された。マフィアや一族関係者、容疑者たちの中で捜査線上に浮かび上がった黒幕は、社長の元妻パトリツィア。
贅を尽くし豪奢に暮らす彼女は真犯人なのか? 華麗なる一族崩壊のきっかけとなるスキャンダルはなぜ起きたのか?
世界的ファッションブランドの華やかな表舞台と陰の抗争を炙りだすノンフィクション、『ハウス・オブ・グッチ』(サラ・ゲイ・フォーデン:著、実川元子:訳/早川書房)から、問題の銃殺事件を描いた冒頭部分を特別公開します。【本文試し読み】
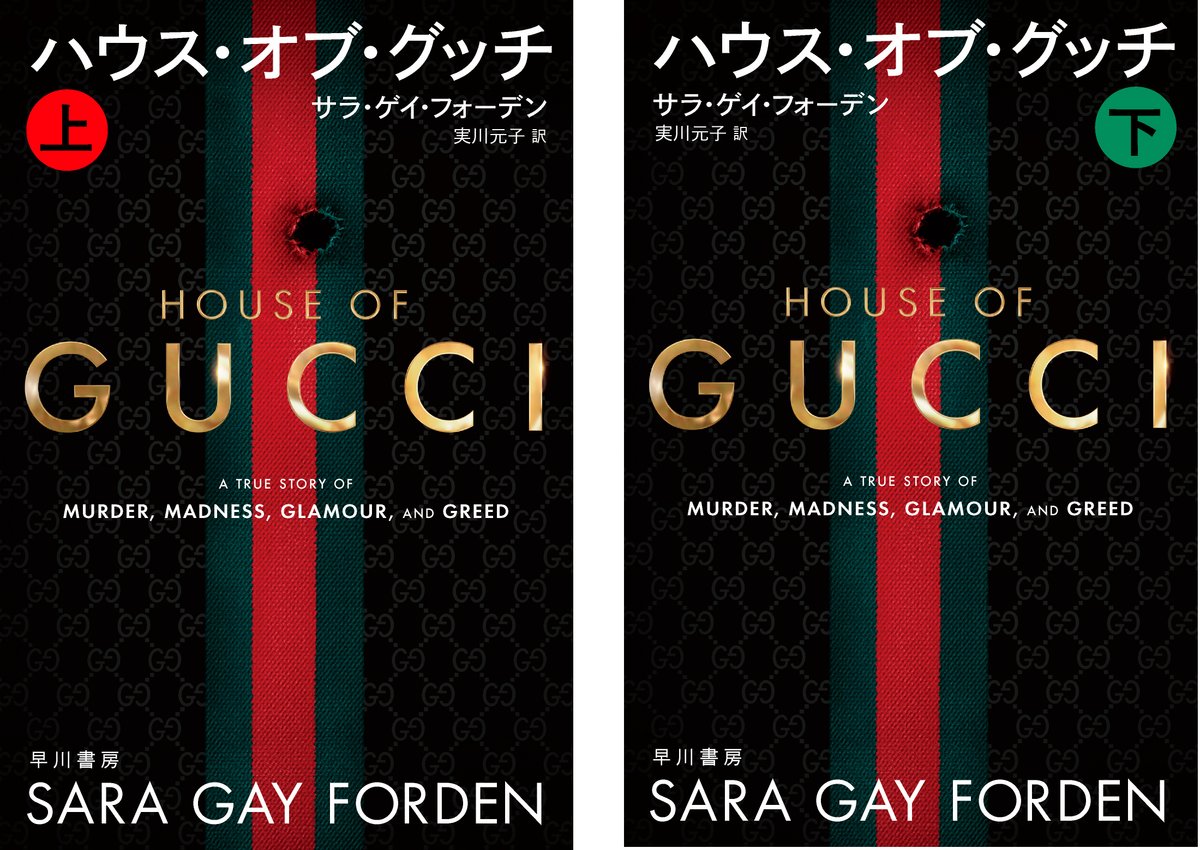
1章 それは死から始まった
1995年3月27日月曜日、午前8時30分。ジュゼッペ・オノラートは管理人をしている建物の入り口に吹き寄せられた落ち葉を掃いていた。その日、ふだんと変わらず8時に出勤すると、まずパレストロ通り20番地の大きな2つの木製ドアを開け放った。
ルネサンス様式の4階建てのビルは居住用アパートと事務所が入っていて、ミラノでもっとも洒落た通りに面している。通りを渡った正面には、なめらかに刈り込まれた芝生を背の高いヒマラヤ杉とポプラが取り囲むプッブリチ公園があり、スモッグにおおわれたせわしない都会でほっとひと息つける緑のオアシスとなっている。
オノラートは掃除の手をふと止めて顔をあげ、通りの向こう側に男が一人たたずんでいるのに目をやった。門を開いた瞬間から、その男の存在には気づいていた。公園のほうに向けて舗道の縁石に直角に停めた緑色の小型車の後ろに、男は立っていた。
ミラノのオフィス街にはめずらしくパレストロ通りは駐車が自由にできるため、ふだんは舗道に沿ってずらりと車が並ぶ。だが時間帯が早いせいで、停まっている車はそれ一台だけだ。オノラートの目を引いたのは、地面につきそうなほど低い位置につけられているナンバープレートだ。
こんな早い時間にいったいなんの用事だろうか、と彼はいぶかしんだ。髭をきれいにそり、身なりもきちんとしている男は、明るい茶系のコートをはおり、まるで誰かを待っているかのようにヴェネチア大通りのほうをじっとうかがっていた。薄くなっている頭のてっぺんに無意識に手をやったオノラートは、男の豊かな波打つ黒髪を多少うらやましく思った。
1993年7月、ミラノばかりかイタリア全土を揺るがしたマフィアによる連続爆弾事件以来、彼はつねに注意を怠らないようにしていた。通りに背を向けて掃除を続けるオノラートは、背後から、よく知っている声が「おはよう!」と挨拶するのを聞いた。
オノラートは振り返って、2階にオフィスがあるマウリツィオ・グッチがいつものように元気いっぱいの様子で、キャメルのコートをひるがえしながら玄関前の階段を駆け上がってくるのを見た。
「おはようございます」。オノラートは笑顔で応え、片手を挙げて挨拶した。
オノラートはマウリツィオ・グッチが高級ブランド、グッチを創設した有名なグッチ一族の一人であると知っていた。イタリアでグッチはつねにエレガンスとスタイルの代名詞である。マウリツィオ・グッチは2年前に、グッチ社を投資会社に売り渡して以来グッチのビジネスには関与せず、1994年からパレストロ通りに自分の事務所を構えていた。
マウリツィオ・グッチは事務所から角を曲ってすぐのところにある、ヴェネチア大通りに面した荘厳なパラッツォに住んでおり、毎朝たいてい8時から8時半の間に歩いて事務所にやってきた。ときにはオノラートより先にやってきて自分で鍵を開けて中に入り、オノラートが玄関の重い木製のドアを開け放つときには上で仕事をしていることもあった。
マウリツィオ・グッチが階段の最上段まで上り、まさにロビーに入ろうとしたとき、黒髪の男が正面の門を入ってくるのをオノラートは目撃した。瞬間的に、その男がマウリツィオを待っていたのだと彼は思った。それなのになぜ、階段下の足ふきマットのところで立ち止まったのか。彼はいぶかしく思った。マウリツィオは男が後ろからついてくるのに気がつかず、男も呼びとめなかった。
オノラートが見つめる中、男は片手でコートの前を開くと、もう一方の手で銃をつかみだした。その手をまっすぐに前に突き出すと、マウリツィオ・グッチの背中を狙って撃ち始めた。ほんの1メートル弱ほどのところに立っていたオノラートは箒を手にしたまま凍りついた。男を止められない自分の無力を感じつつ、ショックのあまり茫然と立ち尽くした。
3発、間を置かずに銃声が響きわたった。
オノラートはただ恐怖に目を見開いたままだ。最初の銃弾はマウリツィオの右腰あたりに命中した。2発目は左肩の下を射抜いた。弾があたっているのに、キャメルの布地が震えるだけなのにオノラートは気づいた。「映画で見るのとはずいぶんちがう」と彼は思った。
マウリツィオは何が起こったのかわからないという驚愕の表情で振り向いた。銃を持った男を見たが、見知らぬ人間だったようで、視線はオノラートに向けられ「いったい何が起こった? どうしてだ? なぜこんなことが私に起こるのだ?」という表情が浮かんでいた。
3発目は右腕をかすった。
マウリツィオがうめいてどさりと倒れると、男はとどめの一発を彼の右のこめかみに撃ち込んだ。殺し屋は踵を返して立ち去ろうとし、そこにオノラートが目に恐怖を浮かべて立っているのにはじめて気づいた。
オノラートは男の黒い眉毛が驚きで上がるのを見て、自分の存在に気づいていなかったことを知った。
銃を持った腕はまだ前に伸ばされたままで、銃口がオノラートのほうに向けられた。オノラートはそのときやっと、銃身に長いサイレンサーがつけられているのに気づいた。銃を握っている手の指が長く、爪はつい最近マニキュアを塗られたばかりのようだ。
永遠にも思えるほどの数秒がすぎ、オノラートは殺し屋の目を見た。自分の叫び声が耳に入った。
「やめろ──!」。わめきながら後ずさりし、「おれは何も関係ないぞ」と示すつもりで左手を上げた。
殺し屋はオノラートに向けて2発撃ち、正面の門から逃げ去った。オノラートはカチャンカチャンという音を聞き、それが花崗岩の敷石に薬莢が転がる音だとわかった。
「信じられん」彼は思った。「痛みを感じないぞ。撃たれたときに、痛くないとは知らなかったな」。マウリツィオも痛みを感じなかっただろうか、と彼は考えた。
「そうか、死ぬってのはこういうことなんだな」。ぼんやりと彼は思った。「おれはもうすぐ死ぬ。こんな死に方は残念だ。ひどいじゃないか」

しばらくして自分がまだ立っていることに気づいた。左手を見下ろすと、妙な形にぶらぶらしている。血が袖口からしたたり落ちていた。ゆっくりと階段の一段目に腰を下ろした。オノラートは助けを呼ぼうとしたが、口を開いても声が出なかった。
数分後、サイレンの音がしだいに大きくなり、警察の車がパレストロ通り20番地の前で鋭いブレーキ音を響かせて停まった。4人の制服警官が銃を構えながら飛び出した。
「男に銃で撃たれた」。階段の一段目に座ったオノラートは、駆けつけた警官たちに先ほど目の前で起こった出来事を弱々しい声で報告した。
2章 グッチ帝国

マウリツィオが倒れている通路の両側の白壁とドアに、まるでジャクソン・ポロックの抽象画のように赤い鮮血が飛び散っている。床には薬莢が散らばっていた。通りをへだてたところにあるプッブリチ公園のキオスクの売り子が、オノラートの叫び声を聞いてすぐに警察を呼んでくれた。
「その人がグッチさんです」とオノラートは撃たれた左手をだらりと下げたまま、右手を上げて階段上のマウリツィオの遺体を指差して警官たちに教えた。「亡くなられたのですか?」
警官の一人がマウリツィオのかたわらに膝をつき、首に指を押し当てて脈拍が感じられないのを確かめてからうなずいた。その朝、約束の時間よりも5分早く到着したマウリツィオの弁護士、ファビオ・フランキーニは、冷たい床の上に横たわる遺体のかたわらに絶望した表情でうずくまっていた。
警官と救急隊員がそれから4時間にわたって遺体周辺で働いた。救急車と警察車両が続々と到着し、建物の前には野次馬が集まってきた。救急隊員がすぐにオノラートを診察し、殺人課の刑事たちが到着する直前に彼を救急車の一台まで連れていった。
殺人課で12年のキャリアを持つジャンカルロ・トリアッティは、すぐにマウリツィオの遺体を調べた。過去数年間、トリアッティのおもな仕事はミラノに移住したアルバニア移民たちの派閥抗争による殺人事件の捜査だった。特権階級の殺人事件を扱うのは、彼にとってはじめての経験となる。街のど真ん中で、一流ビジネスマンが銃殺されるなどそう毎日起こることではない。
「犠牲者の名前は?」。トリアッティはしゃがみながら聞いた。
「マウリツィオ・グッチだ」。同僚の一人が教えた。
トリアッティは顔を上げ、いぶかしげに表情を崩した。「ということは、おれはヴァレンティノかな」。年がら年中日焼けしているローマ出身のデザイナーの名前を彼は皮肉っぽい口調で挙げた。グッチといえばフィレンツェの皮革製品を扱っている会社じゃないか。そのグッチがミラノで何をしているんだ?
「おれにとっちゃ、誰であろうと殺されてしまえば死体のひとつにすぎないんでね」。のちにトリアッティはいった。
トリアッティは、マウリツィオのだらりと伸びた手の近くにある、血が飛び散った新聞をそっと拾い上げ、まだときを刻んでいるティファニーの時計を外した。注意深くマウリツィオのポケットを探っているところに、ミラノ地方検事のカルロ・ノチェリーノが到着した。現場は混乱していた。カメラマンとジャーナリストたちが、押しとどめようとする救急隊員や警官と争っていた。
重要証拠が消されることを恐れたノチェリーノは、どの警察組織が最初に到着したのかとたずねた。イタリアでは、刑事問題や公安関係の任務につき、刑事問題や公安関係の任務につく憲兵カラビニエーレが属する特殊警察、ポリツィアと呼ばれる一般の国家警察とガルディア・ディ・フィナンツァと呼ばれる財務警察の3つの警察組織があり、それぞれ所属する省庁がちがう。そして法執行組織間の不文律として、最初に現場に到着した組織が事件を担当すると決められている。
カラビニエーレが最初に到着したと知ったノチェリーノは、ただちに一般警察の警官たちに命じて、時間を追うごとに増える野次馬や記者たちを追い出させ、玄関の大きな門を閉めさせ、正門周辺の舗道を立ち入り禁止にした。それから階段を上がると、遺体を調べているトリアッティのそばにかがんだ。
ノチェリーノと捜査官たちは、こめかみにとどめをさしたやり方がマフィアの処刑に似ていると考えた。傷口の周辺の皮膚と髪は焼けこげており、近距離から撃たれたことを物語っている。
「プロの殺し屋の仕事だね」とノチェリーノは傷口と、捜査班がチョークでしるしをつけた6個の薬莢の位置を確かめていった。
「とどめの一撃をさすこのやり方は、古典的なマフィアの復讐の手口だ」。トリアッティの同僚、アントネッロ・ブッチョルは同意した。それでも刑事たちはとまどっていた。撃ち込まれた弾丸が多すぎる上に、二人の目撃者を殺さないで逃走した。オノラートだけでなく、正門から走り出てきた犯人とぶつかりそうになった若い女性がいたのだ。そのあたりはプロの殺し屋が復讐を果たすときの伝統的なやり口ではない。
トリアッティは1時間半にわたってマウリツィオの遺体を調べたが、結局それから3年かかって彼の人生を詳しく調べ上げるまで、事件の真相は解明されなかった。
「マウリツィオ・グッチのことをそのとき私たちは何も知りませんでした」とトリアッティはのちにいった。「彼の人生をじっくりと洗い直し、ていねいにたどっていかねばならなかったのです」
ファッション業界最大のスキャンダルといわれるグッチ三代目社長の殺人事件はなぜ起きたのか? 衝撃の事実が明かされるこの続きは、ぜひ本書でご確認ください。
『ハウス・オブ・グッチ』映画予告映像は▶こちらから
【映画は2022年1月14日全国公開】[監督]リドリー・スコット [出演]レディー・ガガ、アダム・ドライバー、アル・パチーノ、ジャレッド・レト、ジェレミー・アイアンズ、サルマ・ハエック他

