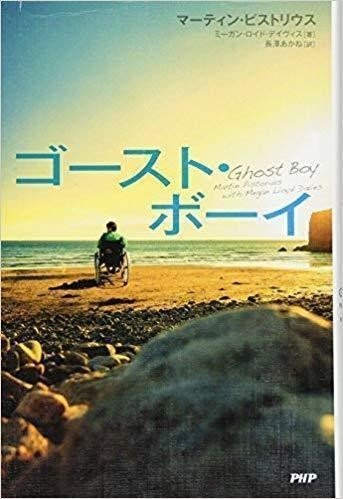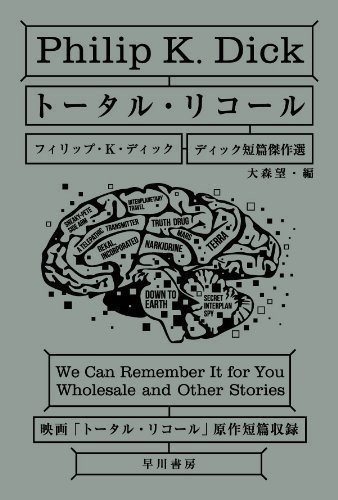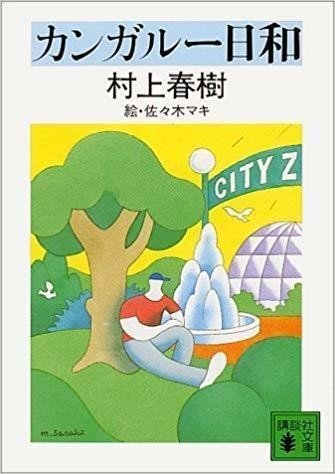『君の話』刊行記念 三秋縋インタビュウ
※本記事は2018年、単行本刊行時のインタビューとなります。
ーーーーー
――まずは、『君の話』という物語がどのようにして生まれたかをお教えください。
三秋 早川書房から執筆のご依頼を受けたとき、最初はまったく別の物語を考えていたんです。主人公は何者かに襲われてLIS(Locked-in Syndrome)になった少年で、数年間ずっと寝たきりで暗闇の中にいたのだけれど、ある日BMI(Brain-Machine Interface)を与えられてコンピュータを操作できるようになる。長い訓練の末にコンピュータ上で行えることは一通りできるようになった彼は、そこから十年かけて自身の少年時代を完全に再現した仮想世界を作り出し、疑似的な時間遡行によって自分を襲った犯人を突き止めようとする。しかし調査を進めるうちに、仮想的存在――しかも、よりにもよって最有力容疑者の少女──に恋をしてしまうというSF恋愛ミステリを構想していました。
マーティン・ピストリウスの『ゴースト・ボーイ』というノンフィクションで、奇病によって十年間一種の植物状態にあった少年の半生が描かれていたのですが、長いあいだ意識がないと思われていた彼は、ある介護士の気づきがきっかけでAAC(Augmentative & Alternative Communication)による外部との意思疎通が行えるようになります。その後コンピュータの扱いに習熟していき、最終的にはウェブデザインの事業を立ち上げるまでに成長するんです。『ゴースト・ボーイ』を読んだことで、LISとBMI、そして社会に浸透しつつあるヴァーチャル・リアリティ、そこで行われる疑似的な時間遡行、この四つはとても相性が良いと気づきました。
そうしてプロットは無事完成したのですが、完成品を見て直観的に、今の自分にこの物語は荷が重すぎると感じたんです。この物語は僕以外の誰かによって書かれるべきだ、と思いました。地力をつけてからではないとアイディアを台なしにしてしまう。もっと相応しい題材はないかと本棚のSFを読み漁っていったとき、ふとフィリップ・K・ディックの「追憶売ります」(編者注:「トータル・リコール」に改題されて、同名タイトルの『ディック短篇傑作選』に収録されています)を思い出して。直前まで少年時代への時間遡行ものを書いていたこともあって、「自分があの世界の住人なら、美しい青春時代の記憶を購入するかどうかで葛藤するだろうな」などとぼんやりと考えました。そうしているうちに、これほど今の自分に適した題材もないと悟ったんです。「追憶売ります」における「火星への憧れ」を、村上春樹の短篇「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子と出会うことについて」(『カンガルー日和』収録)における「100パーセントの女の子」のような青い感傷に挿げ替えたらどうなるだろう、というのは魅力的なifでした。
初期の構想では、〈感情教育〉という名の医療用ナノロボットが存在して、感情鈍麻の治療のために「美しい青春時代の記憶」が主人公に植えつけられるという設定でしたが、もっと切実な動機を抱えた人物を主人公にした方がよいと考え直し、青春コンプレックスの特効薬という直球の設定で再度練り直しました。そうして生まれたのが、『君の話』です。
――本作は、これまでメディアワークス文庫で活躍されてきた三秋さんの初の早川書房での刊行書籍となります。ご執筆の上で新しくチャレンジされたことはありますか?
三秋 理数系科目から逃げ続けた人生だったので、早川書房からの執筆依頼に応じるというのが何より大きなチャレンジだったと思います(笑)。それ以外で言えば、女性視点でしょうか。これまでにも物語の一部を女性視点から語るという試みは幾度か行っていたのですが、本作は男女それぞれの視点から描きつつ本命は女性視点という構成だったので、とても新鮮でした。
それで気づいたんですが、異性視点だと照れずに本音を書けるんです。同性視点だと語り手の思想=著者の思想と捉える読者が多いので、どうしても照れが出てしまう。本当に弱い部分を曝け出すことができず、どこかにエクスキューズを置いてしまう。ところが異性を視点人物に据えると、「これは僕の考えではなく彼女の考えだから」と無責任に書けて、結果的には本音が浮き彫りになる、という発見がありました。
――本作の重要なテーマとして「記憶(記憶すること)」と「物語(物語ること)」がありますが、それぞれ、三秋さんにとってはどのような「現象」なのでしょうか?
三秋 ファジー痕跡理論によれば、記憶というのは具体的な断片の記憶とそれらの断片を意味づける要旨の記憶のレベルに別れていて、この断片が誤った形で再結合したときに虚偽記憶が発生するらしいんですが、ここに他者の記憶の断片まで投入して意図的に誤った再結合を引き起こすことが「物語をつくる」ことだと思うんです。そもそも人間って、自分の物語を推敲し続ける生き物じゃないですか。冴えない記憶に最良の解釈を与えようと、つねに試行錯誤している。「昔は良かった」というのは、今より昔の記憶の方が物語として洗練されているという意味でもあるんでしょう。
この再結合を繰り返す中で、時に人は自分の物語に致命的に欠けているピースを把握してしまい、それまでは単に「得られなかったもの」だったはずの経験を「あらかじめ失われたもの」として捉えて不当な喪失感に苛まれるようになるんですが、僕はこの不当な喪失感を意図的に創出してそれを小説の題材にする、というマゾヒスティックなマッチポンプを繰り返しています。
――作家として、SFというジャンルはどのようなものだと捉えていらっしゃいますか?
三秋 この問題についてはすでに議論され尽くしていると思うので、あくまで門外漢として素朴にお答えすると、「現実に異物を投入して(もしくは異界に現実を投入して)シミュレーションを進め、異化された世界で徹底的に思索を行った先に見えてくるもの」を描いたジャンル、またそうした作品群から副次的に生まれた魅力的なガジェットを利用したジャンル、ではないでしょうか。『君の話』は思索を徹底せず感傷を突き詰めているので、後者に属していると思います。
――先程「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子と出会うことについて」についてお話をいただきました。この作品はラブストーリーでもある『君の話』を理解する上での重要な参考文献かと思いますが、いかがですか。
三秋 「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子と出会うことについて」を読んでいなかったら、本作は書かれていなかったと思います。要約すると、町ですれ違った女の子を「100%の女の子」だと感じた主人公がその理由についてあれこれ考えを巡らせ、「ひょっとしたら僕たちは記憶を失っているだけで、かつては100%の恋人同士だったのではないか」という飛躍した結論を捻り出すという短篇です。この話が面白いのは、「運命の相手がいるのではないか」ではなく、「運命の相手がいたのではないか」と過去に目を向けている点で、こちらの方が遙かにロマンチックなんですよね。「運命の相手なんていない、ただ運命の相手がいるはずだという感覚だけが一部の人にある、そこから遡行的に見いだされるファンタジイがセカイ系の本質だ」という意味のことを東浩紀さんが仰っていましたが、この〝遡行的に見いだされるファンタジイ〟の主要な感染源のひとつが「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子と出会うことについて」で、それが今、新海誠さんを介して日本中に広まっているように感じます。
『君の話』もまさにこの〝遡行的に見いだされるファンタジイ〟について書いた作品です。またそれだけではなく、「ヒロイン」という概念に宿命的につきまとう欺瞞や矛盾と向き合うことをも主題としています。自分を都合良く好きになってくれる人、無条件に愛してくれる人、その想いのためにすべてを捧げてくれる人、そんな人がいるはずない。でも何かの間違いでそんな「ヒロイン」が誰かの前に現れることがあるとしたら、そこには一体どのような物語が見出されるべきか、という問いが執筆中常に頭の中にありました。だから、本作の仮題は『ヒロイン』だったんです。
――十代~二十代の読者からの熱い支持に関しては、ご自身ではどのように捉えていらっしゃいますか?
三秋 僕は自分が十代の頃に読みたかったものを書いているだけなんですよね。こういう題材をこういう風に扱った本を読んでみたい、という当時の願望に自分自身で応えている。一人のニーズを完全に満たすものって、結果的には万単位のニーズを満たすことになるので、なんというか、そういうことではないかと思います。
――今後、どういう作家になり、どういう作品を書いていきたいとお考えでしょうか? チャレンジしてみたいSF的なテーマやモチーフがあれば、是非お聞かせください。
三秋 自分の読みたいものを書く作家でいたいですね。これまで執筆を義務のように感じたことは一度もありませんし、これからもそうあり続けたいです。誰かのため、社会のためなんかに書いたりしたら、僕の書く物語は一気に色彩を失うんじゃないでしょうか。100%自分のために書いた物語が、偶然誰かにとっての宝物になればいい。そう思います。
(SFマガジン2018年8月号掲載)
『君の話』のご予約はこちらの書影リンクから
インタビュウ記事内で言及された作品へのリンク
三秋縋関連作品リンク
原作:三秋縋×漫画:loundraw『あおぞらとくもりぞら1』(8/25発売)