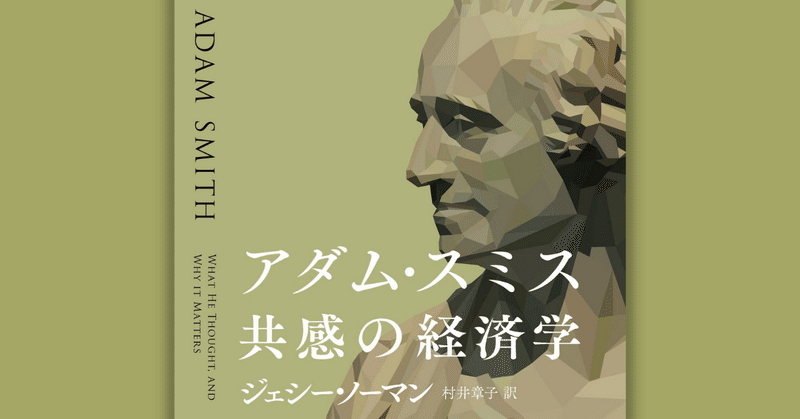
「最も理解されていない思想家」の実像に迫る!『アダム・スミス 共感の経済学』序文
2月16日に『アダム・スミス 共感の経済学』(ジェシー・ノーマン:著、村井章子:翻訳)が発売されます。
アダム・スミスは「近代経済学の父」として知られる一方、その思想があまりにも幅広い分野にまたがっていることもあり「世界で最も理解されていない思想家」と形容されることも。本書では「市場原理主義者」「不平等と利己主義の擁護者」「女性軽視」といったスミスにまつわる〝神話〟をそぎ落とし、経済学から政治学、倫理学、社会学、心理学にまで広がる思想的影響を俯瞰。スミスを理解する重要なキーワードである「共感」に代表される「人間の科学」への洞察を足がかりに、格差拡大やグローバル化などの課題に直面する現代へのヒントを提示します。
経済学や現代の経済課題に関心のあるすべての方に読んでいただきたい本書の序章を特別公開します。
アダム、アダム、アダム・スミス、
おいらの言い分よく聞きな!
あんたはたしかに言っただろ、
ある日あるとき教室で、
我が身大事は報われるってね?
いろいろ教わりゃしたけれど、あれが断然イチバンさ、
そうじゃないかい、スミスさん?
──スティーブン・リーコック(ユーモア作家兼政治経済学教授)
今日アダム・スミスを持ち出すと、往々にして正反対の反応を引き起こすことになる。とくに1980年代以降、スミスは経済学、市場、社会を巡るイデオロギー的な論争の中心人物となった感がある。政治的に右寄りの人にとっては、アダム・スミスは近代の礎を築いた人物であり、経済学者中の経済学者だ。共産主義と社会主義のユートピア幻想から覚醒した世界にあって、個人の自由の雄弁な擁護者であると同時に、国家の介入に対する頑強な反対者でもある。一方、左寄りの人にとってのアダム・スミス像はかなりちがう。いわゆる市場原理主義の元祖であって、その著作は、ジャーナリストのナオミ・クラインに言わせれば、「現代資本主義の教科書」だ。世界を蝕み、人間的価値の根源を脅かす物質主義イデオロギーの提唱者であると同時に、富と不平等と利己心の擁護者であり、おまけに女嫌いということになる。
とはいえ、一つたしかなことがある。経済学者と経済学がかつてない影響力を持つこの時代にあって、これまでに存在した中で最も影響力のある経済学者はアダム・スミスだということである。無作為抽出した経済学者299人を対象に2011年に行われた調査によると、引用回数でスミスは他を断然引き離しての1位だった。スミスの221回に対して、2位のケインズは134回である。しかもスミスの場合、学問的な評判は経済学界にとどまらない。主に英語で書かれた学術雑誌の総合データベースJSTOR(ジェイストア)を使って1930〜2005年に発行された雑誌全文の詳細分析をしたところ、スミスは経済分野における「偉人」として引用される例がきわめて多いことがわかった。最新の合計では、「偉人」と表現された回数はマルクス、マーシャル、ケインズを足し合わせたよりも多く、且つ現代の経済学者の合計の3倍を上回ったのである。
アダム・スミスの思想は幅広い分野にまたがっているだけに、その影響も広範だ。過去2世紀にわたり、哲学から政治学、社会学まで多くの偉大な思想家にスミスの何らかの痕跡が認められる。たとえばエドマンド・バーク、イマヌエル・カント、G・W・F・ヘーゲル、カール・マルクス、マックス・ウェーバー、フリードリヒ・ハイエク、タルコット・パーソンズ、ジョン・ロールズ、ユルゲン・ハーバーマス、そして最近ではアマルティア・センがそうだ。良い税金に関するスミスの4つの格言は世界の税制の基本となっているし、あの有名な「見えざる手」は講演やメディアのそこここに登場する。またアダム・スミスの名を冠した機関、専門誌、ソサエティの類いが世界中にあり、プーシキンの小説の中ではエフゲニ・オネーギンもスミスを勉強している。イギリスでは20ポンド紙幣の裏面に長らくアダム・スミスの横顔が使われてきた。
だが称賛や批判とは別に、並ぶ者のないスミスの名声を自分に都合のいいように援用する例が後を絶たない。ありとあらゆる党派の政治家が、スミスの堅牢な思想と確固たる評判の力を借りようとする。たとえばマーガレット・サッチャーは1988年のスコットランド保守党会議で、聴衆を挑発するかのようにこう述べた。「スコットランドでサッチャリズムは人気がないとよく言われますが、にわかには信じられません。なぜなら、私よりもずっと前にサッチャリズムを発明したのはスコットランド人なのですから」。サッチャーは自らの政治的信条のルーツはスミス、ファーガソン、ヒュームにあるとし、「これまで以上に多くの富が創造され、広く行き渡る……賢明な政府は個人の努力を社会全体の幸福に結びつける」という世界観を披瀝した。
一方、2000年代後半に首相を務めた労働党のゴードン・ブラウンはさらに一歩踏み込み、たまたま出身地が同じファイフ県カーコーディであることを利用して、自分とアダム・スミスの個人的な結びつきを強調した。財務相だった2005年にはアメリカ連邦準備理事会議長(退任後ブラウン財務相の名誉顧問に迎えられた)のアラン・グリーンスパンを招待し、カーコーディでアダム・スミス記念講演を行う機会を設けている。講演の中でグリーンスパンは「この土地が潜在意識に働きかける知的な効果により財務相の定評ある経済・金融運営の能力が育まれた」と述べて、ブラウンの思惑にみごとに応じた。ブラウン自身も同じ年の12月にヒューゴー・ヤング記念講演を行い、「アダム・スミスと同じくカーコーディ出身の私は、『国富論』を支える礎は『道徳感情論』であること、〝見えざる手〟は〝助ける手〟の存在あってこそだということを理解している」と熱弁を振るった。
これらの例からもわかるように、スミスの残した知的偉業があまりにゆたかで、多面的で、引用しやすいがために、多くの人がむやみに引用したくなったり、都合のいいようにねじ曲げて解釈したくなったりするのだろう。実際、最大限の拡大解釈をすれば、スミスは現代の出来事を驚異的な精度で予見していたと読めなくもない。たとえば、セレブリティ・ポリティクスの台頭がそうだ。情報技術の発達と金持ちや権力者を称賛する人間の気質とが結びつき、そこに互いに共感しやすい傾向が加われば、有名人の政治家が誕生してもふしぎではないが、なんとスミスは『道徳感情論』の中で技術についても気質についても論じているのである。もう一例挙げるなら、イギリスが欧州連合(EU)から離脱する可能性も、そうだ。スミスはアメリカ植民地について論じた箇所で、イギリスは厳然たる二者択一を迫られると述べた。アメリカときっぱり縁を切るか、帝国の連合を形成するか、いずれを選ぶにしても主権は最終的にはアメリカに移り、それに伴って政府の所在もアメリカになることは避けられないという。これ以外にもたくさんの例を挙げることが可能だ。
こうした過剰な引用や解釈の結果、誇張され、歪曲されたアダム・スミス像が拵え上げられ、さまざまな伝説がまことしやかに伝えられている。この種の神話まがいの伝説はスミス本人についてはほとんど何も語らず、話し手の関心の対象を雄弁に語るだけだ。スミスの解釈や研究でも同じパターンが見受けられる。たとえば19〜20世紀の自由貿易の問題を論じるときや、近年の行きすぎた専門化、とくに数学との関連が強くなった経済学の方向性を問題にするときなどには、「経済のスミス」、すなわち『国富論』の著者であるスミスにフォーカスする。この場合、ひょっとすると「政治のスミス」と呼んでよいかもしれない存在、具体的には権力、財産、統治の相互作用や商業社会の性格と影響を『国富論』と未発表の『法学講義』で論じたスミスや、「道徳のスミス」、すなわち道徳や社会規範が社会においてどのように形成され維持されるかについて驚くほど現代的な説明を『道徳感情論』の中で示したスミスは、脇に追いやられてしまう。本書の狙いの一つは、スミスの経済学者以外のさまざまな面を再発見し、スミスの全体像を描き出すことにある。スミスの経済学だけでなく、はるかに幅広い彼の知的業績を知るための扉を開きたいと考えている。
スミスの一面だけを都合よく取り上げる姿勢は、経済学者にも見られる。たとえばシカゴ学派の経済学者ジェイコブ・ヴァイナーは、『国富論』に言及した一文の中で「非常に広範囲を網羅したこの著作には、およそ考えつく限りの学説が盛り込まれている。独自の理論を打ち立てた経済学者の中で、その裏付けとして『国富論』を援用できないという学者は一人もいないだろう」と述べた。この指摘の正しさはすでに証明されている。
その例は一つ挙げれば十分だろう。それも、ヴァイナーの最も有名な弟子の例である。ミルトン・フリードマンは、ノーベル経済学賞をとったばかりの一九七七年に「アダム・スミスの今日的意義」と題する著名な論文をチャレンジ誌に発表した。フリードマンから見たアダム・スミスは、あの時代としては「過激で革命的」だった──当時のフリードマン自身と同じである。スミスは社会の「規制が多すぎる」と感じており、したがって政府の干渉に反対だったが、これもまたフリードマンに通じる。さらにスミスの「見えざる手の原理」は、人間の同情は当てにならず、限りがあるせいで出し惜しみされるのに対し、自由市場は幸福の創出に寄与するという見方の表れだという。スミスの長い学究生活はこうした思想の追究に捧げられたのだが、これもまさにフリードマン自身と重なる。
だがこうした基本的な考察を示したところまではよかったが、フリードマンはここで困難に突き当たる。というのも、スミスはいま挙げたことと矛盾するように見える主張もしているからだ。この点は否定できないとフリードマンは認める。たとえば金利に上限に設けるべきだと主張したし、国家にはある種の公共事業を実施し公的機関を運営する義務があるとも述べた。そこにはおそらく道路、橋梁、運河建設や学校運営が含まれるだろう。だがこうした主張はスミスの本質とは異なる瑕疵であって、全体の評価を押し下げるには当たらないとフリードマンはいう。
今日ではひどく有名なこの論文は、もともと学術論文ではない。モンペルラン・ソサエティに提出した自由市場に関する論文から抜粋したもので、アメリカの経済運営批判を行うことが当初の目的だった。当時のフリードマンは、1970年代のアメリカ経済が言わば動脈硬化に陥っていると考えていたのである。だがそうした位置づけの論文であるにしても、事実を自分の理論に都合よくフィットさせる技術はたいしたものだと言わねばなるまい。というのも、フリードマンの主張の多くはまるきり的外れなのである。アダム・スミスは過激ではないし、革命家を自認していたわけでもない。それに、「規制が多すぎる」とも感じていなかった。この言葉が何を意味するにせよ、当時イギリスの植民地だったアメリカに該当しないことはまちがいない。さらに、見えざる手を「原理」であるなどとはつゆ考えておらず、それどころか市場の働きを司る単一の原理があるとも考えていなかった。そもそもスミスは、市場がつねに人間の幸福に資するとも考えていなかった。さらに言えば、人間の同情や共感が本来的に限られているとか、だから出し惜しみする必要があるとも考えていなかったのである。
いま挙げたような問題を含めてスミスは実際に何を考えていたのか、そして彼の考えが今日なお重んじられるのはなぜかを解き明かすことが、本書の第一義的な目的である。さらに、スミスにまとわりつく神話を剥ぎ取り、スミスの思想全体を結び合わせたいと考えている。もちろん、ハイエク、ケインズ、マルクスといったさまざまな経済思想家に与えた影響も検討する。とはいえ、死してなおスミスは評伝作家に手を焼かせる。学究の人にありがちなことだが、何もこれといった事件が起きないのだ。死の直前に彼は渋る遺言執行人に対し、手稿の大半を燃やすよう強く命じた。だから、そこに何が書かれていたのかは想像するほかない。スミスの思想を知るうえで地味ながら重要なカギとなる『法学講義』の手稿が残ったのは、驚くべき幸運のおかげである。
スミスの思想の中で最も根源的な部分の多くは、親交のあった思想家デービッド・ヒュームに結びつく。多くの点で二人はなかなかない組み合わせだったと言えるだろう。ヒュームはスミスより12歳年上で、世故に長け、鷹揚で機知に富み、人を見る目があり、話し上手で社交的な人物だった。トランプのホイストをこよなく愛し、大食漢で、浮気者でもある。対照的にスミスは控えめで引っ込み思案である。公の場ではとかく堅苦しい人物と見られがちだったが、私的な場ではくつろいでよく話した。スミスは他のどの思想家よりもひんぱんにヒュームと心の中で対話した。二人の間で哲学的な手紙のやりとりがあったとしても残されていないが、スミスの著作を読んでいて、ヒュームの影響とは言わないまでも何らかの影を感じないページはほとんどないと言ってよい。ヒュームとスミスの間に相違点はたくさんあるにしても、スミスをヒュームの弟子と呼んでも差し支えなかろう。
当時の基準からすると、スミスの意見はおおむねホイッグ党(後の自由党)寄りだった。つまり立憲君主制、宗教的寛容、個人の自由を支持していた。とはいえスミスは自らの政治的見解について生涯を通じて頑に口をつぐんでいる。結婚もせず子供ももうけなかった。わかっている限りでは秘められた恋愛や隠れた悪行の形跡もない。学生時代の悪ふざけや大人になってからの不始末もないのだ。興味をそそるようなゴシップやエピソードに関する限り、スミスはサハラ砂漠のごとく無味乾燥である。スミスの最初の評伝を書いたデュガルド・ステュアートの言葉を借りるなら、スミスは「評伝作家に何も材料を残さないように気を配ったのではないかと思えるほどだ。残されたのは偉大な才能の記念碑となるような作品と模範となるような私生活の価値だけ」ということになる。
こうした材料不足にもかかわらず、スミスの評伝は数多く出版されている。とりわけ近年では、エジンバラの知識社会とスコットランド啓蒙思想を背景にスミスの人生をすみずみまで描き出した労作が少なくない。もちろん学術書も多数書かれているが、こうした評伝は読者に新しいスミス像を提出するとともに、彼の知的関心の広がりを示してくれる。私も深い感謝の念をもってこれらの評伝から自由に引用させてもらった。
本書はアダム・スミスの評伝である以上、これまでに書かれた評伝とカバーする範囲はほぼ重なる。最大限に公平で中立な書き手であろうと努めたが、先入観を完全に排除することはできなかったし、生半可な知識や視野の狭さの弊害も免れていまい。賢明な読者からのご指摘、ご教示を待つ次第である。ただし、本書にはこれまでの評伝と趣を異にする点が三つあると自負している。一つ目は、スミス研究を専門とする学者ではなく、現役の政治家が書いたということだ。とは言え私自身は哲学を修め、研究職に就いたこともあるので、本書は政治経済学というものの現代的な側面を理論と実践の両面から理解し解説する試みと位置づけることができるだろう。二つ目は、読者にスミスの思想を表面的に知るだけでなく、その幅広い思想がどのように組み合わさって全体を形成するのか感じてほしいという意図をもって書いたことだ。そして三つ目は、スミスの思想の重要性と今日的な意義を示す説得力のある論拠を示したことである(そう願っている)。
スコットランドのアダム・スミスとアイルランドの思想家エドマンド・バークがよき友であったことは、歴史の偶然としか言いようがない(ちなみに私は本書の前にエドマンド・バークの評伝 Edmund Burke: Philosopher, Politician, Prophet〔2013年〕を書いている)。二人は互いに相手を尊敬しており、その思想にはもちろん相違点もあるが、重なり合う点も少なくない。スミスは「経済に関して口に出さずとも同じことを考えられるのは彼だけだ」とバークについて語ったことがあるとされる。そして二人はいずれも、世界の歴史に稀有な瞬間を記した。それは、現代の政治学と経済学の骨格が初めて深く研究され、書物として公にされた瞬間である。バークは、近代的な政党と代議制を分析した最初の偉大な理論家だった。スミスは、市場を政治経済学ひいては経済学の中心に据え、また今日では社会学と呼ばれるものの軸として規範を論じた最初の思想家である。バークが現代的な意味での政治思想の支柱だったとすれば、スミスは経済学の、そして多くの意味で社会学の支柱になったと言えよう。
これらが類稀な功績であることは言うまでもないが、アダム・スミスは、そしてバークもそうだが、単なる歴史上の人物ではない。だから本書も、いわゆる歴史に残る偉人の伝記ではない。スミスは、その思想と深い影響を通じて今日でも生きている。今日の世界では、先進国か発展途上国かを問わず、どの国も多くの経済的社会的課題に直面している。経済成長をいかに生み出しいかに維持するか、グローバル化と拡大する不平等の問題にどう取り組むか、歴史も社会的関心も宗教も異なるさまざまな社会同士が理解し合うにはどうすればいいのか……。スミスの思想は、いまなおその大胆且つ明晰で単刀直入な着想と幅広い視野によって私たちを驚かせる。今日の世界が抱える課題に取り組むにあたっては、スミスの思想を広く深く理解することが欠かせない。スミスが何を考えたかだけでなく、なぜそれがいま重要なのかも理解し、彼の鋭い洞察を今日そして明日の問題に応用すべきだと強く感じる。
***
この続きは製品版でお読みください!
■著者紹介
ジェシー・ノーマン(JESSE NORMAN)
1962年生まれ。イギリス保守党の国会議員で、2019年に財務担当補佐官を務める。オックスフォード大学で古典を学び、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)で哲学の修士号と博士号を取得。政界に入る前は、共産主義の東欧で教育プロジェクトを運営し、バークレイズ銀行で管理職を務めた。UCL名誉研究員、国立経済社会研究所理事などを歴任。これまでの著書に、「保守思想の父」として知られるエドマンド・バークの評伝(未邦訳)などがある。
■訳者略歴
村井章子(むらい・あきこ)
翻訳者。上智大学文学部卒業。主な訳書に、カーネマン『ファスト&スロー』、カーネマン、シボニー、サンスティーン『NOISE』(以上早川書房刊)、スミス『道徳感情論』(共訳)、ミル『ミル自伝』、フリードマン『資本主義と自由』、バナジー&デュフロ『絶望を希望に変える経済学』など。

