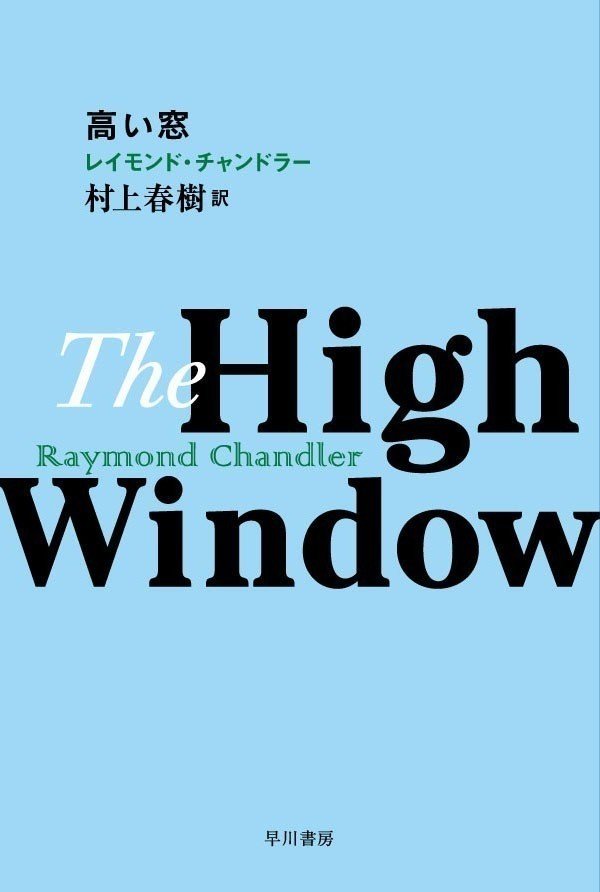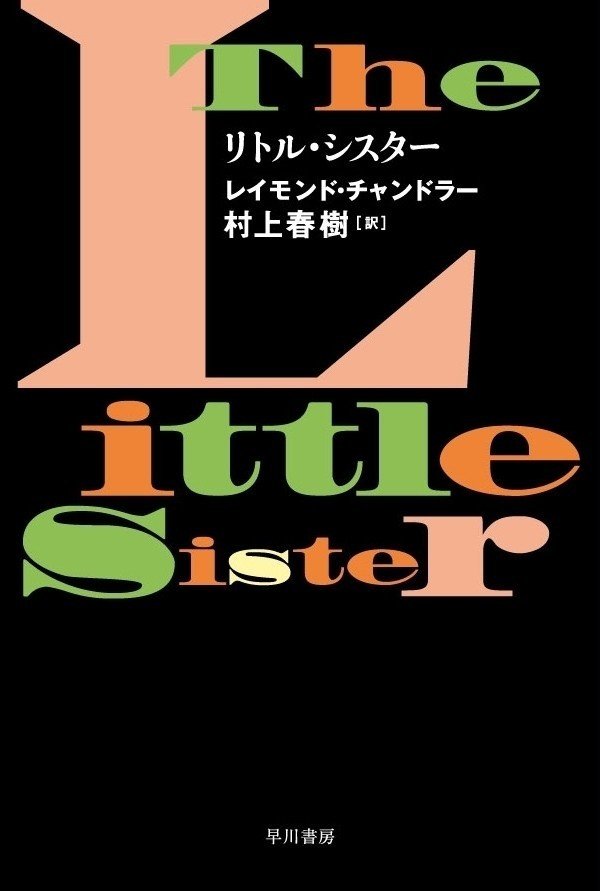『フィリップ・マーロウの教える生き方』村上春樹・訳者あとがき
『フィリップ・マーロウの教える生き方』
レイモンド・チャンドラー/村上春樹(訳)
マーティン・アッシャー(編)
エイドリアン・トミネ Adrian Tomine(イラスト)
2018年3月20日発売
訳者のあとがき
村上春樹
このPhilip Marlowe's Guide to Life(2005)という本はしばらく前から僕の家の本棚に置いてあったのだが、まさかこんなささやかな、そしてきわめて趣味的な書物が日本で翻訳出版されることになるとは思ってもみなかった。しかし十年かけてレイモンド・チャンドラーの七冊の長篇小説の個人訳を仕上げてしまったあと、「こういうのを記念品みたいなかたちで出してみても面白いんじゃないかな」という気持ちがだんだん高まってきて、早川書房の編集者である山口さんに「ひょっとして、どうでしょう?」と持ちかけてみたら、「いいですねえ、是非やりましょう」という返事がすぐに返ってきた。
この本をつくったマーティン・アッシャーは、実を言うと僕の個人的な友人である。親しい友人たちにはマーティーと呼ばれているが、場合に応じてマーティンとマーティーの名前を使い分けているようだ。ニューヨークの出版社クノップフ(ランダムハウス)に長年勤務し、同社のトレードペーパーバック部門であるヴィンテージの筆頭編集者(editor in chief)をつとめていた。僕がヴィンテージから出している作品は、ある時点まではすべて彼が担当してくれた(ほかにコーマック・マッカーシーやリチャード・フォードやフィリップ・ロスなんかの作品を担当していたようだ)。ニューヨークのやり手編集者というと、派手でアグレッシブで「俺こそが……」というタイプの人が少なくないのだが、マーティーはそういうタイプではまったくない。物静かで、知的で、少しくたびれたツイードのジャケットの似合う上品な人だった。きれいな白髪で、眼鏡をかけ、編集者というよりは名門大学の先生のように見える。生まれたのは1945年だから、僕より少し年上になる。
ある日、僕のエージェントであるアマンダ・アーバンの、アッパーイーストにあるアパートメントで夕食会があり、その帰り道マーティーと二人で並んで歩きながらいろんな話をした。家族の話をしたり、音楽の話をしたり、出版の話をしたりした。マーティーはクラシック音楽とジャズに詳しく、ニューヨークの中古レコード屋のこともよく知っていて、話は尽きなかった。穏やかな人だが、話題が興味のあることになると、けっこう熱心に話す。しかしなぜかレイモンド・チャンドラーの話は一度も出なかったような気がする。ヴィンテージはチャンドラーのほとんどすべての作品を独占出版しているし、その話がどこかで出てもよかったはずなのだが、彼とチャンドラーについて話をした記憶がまったくない。この本を手にして、彼がチャンドラーの熱烈なファンであることを知ったときには、彼は既にヴィンテージでの仕事を辞めていたので、それ以後顔を合わせることもなくなり、チャンドラーの話をする機会も持てないままになってしまった。残念なことをした。
マーティーが21年間にわたって勤めてきたヴィンテージを辞めたのは2008年のことだが、その理由は定かではない。僕のほうにもまったく連絡がなかった(彼らしくない)。何人かの共通の知人に「ねえ、どうしてマーティーはヴィンテージを急に辞めたの?」と尋ねてみたのだが、誰もがちょっと気まずい顔をして言葉を濁した。どうやら何か個人的な事情があったらしい。でも誰も詳しいことは教えてくれなかった。僕もあえては聞かなかった。
それはまったく突然のことであったらしく、ヴィンテージの創始者であるジェイソン・エプスタインは、ある日マーティーの辞職願を受け取って、驚愕している。「ランダムハウスにとってはまさに大きな痛手だ」と彼は言う。「これほどの喪失はない。彼に匹敵するような人物はほかにいないもの。本のラインナップをきちんと揃え、興味深い水準に保っておくのはとても難しいことだが、彼はそれをしっかり成し遂げていた。感情的にまったくムラのない人で、彼が興奮したところを私は一度として目にしたことがない。仕事をきちんと仕上げて、静かに家に帰っていく。彼はまさに誰もが求めるような人物なのだ」
そうだよな、それがまさにマーティーだよな、と僕も思う。日々静かに良い仕事をし、ある日静かにそこを去っていく。そして彼は密かに、静かに、個人的に、フィリップ・マーロウの世界を愛していたのだ。それがマーティーなのだ。
マーティーは2000年に『名もなきベビーブーマーの一生。 (The Boomer)』という小さな小説をクノップフから出版している。日本語にも翻訳され、アーティストハウスから2002年に出版されている(石田善彦訳)。題名通り、「団塊の世代」に生まれた一人の男が成長し、大人になり、平凡と言えば平凡な人生を送り、そして病を得て死んでいく話だ。その一生が百の短い文章で(だいたい三行か四行)、まるでスライドショーを見ているみたいに淡々と語られていく。とてもユニークでチャーミングな、そして趣味の良い本だ。訳書をみつけるのはちょっとむずかしいかもしれないが、興味のある方は手にとっていただきたいと思う。
この『フィリップ・マーロウの教える生き方』には、フィリップ・マーロウの登場する長篇小説と短篇小説から、マーティー・アッシャーの気に入った引用句が集められている。早川書房の編集者には「そこに村上さんの気に入った引用もプラスしてもらえませんか」と言われたのだが、ゲラにして通して読んでみると、マーティーがここに選んだものに僕があえて付け加えるべきものなんて何もないんじゃないかという気がだんだんしてきた。そんなことをしても屋上屋を重ねる、というようなことになるのではあるまいか。この本に集められたのは、あくまでマーティーが描いたフィリップ・マーロウ像なのであって、それだけできちんと完結させておくのがいちばん良いのではないかと思った。
しかしよく読んでみると、この『フィリップ・マーロウの教える生き方』には『高い窓』と『プレイバック』からの引用がまったくないことに気づいた。どうしてかはわからないが、ただのひとつもないのだ。しかしその二冊の小説の中にもなかなか愉快な、含蓄のある文章はある。だから──蛇足かもしれないが──その二作の中から僕なりにいくつかの「名文句」みたいなものを選んでみた。
GUN
銃
「銃ではなにごとも解決しない」と私は言った。「銃というのは、出来の悪い第二幕を早く切り上げるためのカーテンみたいなものだ」
『プレイバック』
「おれにそういう口の聞き方をしていると、今にチョッキに鉛のボタンをつけることになるぜ」
「それはそれは」と私は言った。「チョッキに鉛のボタンをつけた気の毒なマーロウ」
『高い窓』
DANCEFLOOR
ダンスフロア
ダンスフロアでは半ダースほどのカップルが、関節炎を患った夜警のような捨て鉢な身振りで自らの身体を振り回していたが、ほとんどは頬を寄せて静かにダンスをしていた。もしそれをダンスと呼ぶことができればだが。
『プレイバック』
音楽が終わり、まばらな拍手があった。楽団はそれに深く心を動かされ、別の曲を始めた。
『プレイバック』
「私は妻を愛している」と彼は唐突に言って、白く並んだ硬い歯の先を見せた。「古くさく聞こえるかもしれないが、本当のことだ」
「ロンバルドス楽団も古いが、まだ人気がある」
『高い窓』
彼の微笑みは、消防士たちのダンスパーティー会場の太ったご婦人のように心もとなかった。
『高い窓』
HARD
硬い心
「これほど厳しい心を持った人が、どうしてこれほど優しくなれるのかしら?」、彼女は感心したように尋ねた。
「厳しい心を持たずに生きのびてはいけない。優しくなれないようなら、生きるに値しない」
『プレイバック』
アルコールはこいつの治癒にはならない。誰も求めない、何も求めないという硬い心を持つほかに、治癒らしきものはない。
『プレイバック』
「状況はよくありません」と私は言った。「警察が私を追っています」
彼女は牛肉の片面ほども動揺しなかった。
『高い窓』
TOUGH GUYS
タフガイ
「マーロウ」と彼は言った。その声は前よりも更に熱気を帯びていた。「そうなるまいと努力はするつもりだが、私は君のことがだんだん癇に障ってきそうだ」
「こちらは怒りと苦痛で、悲鳴を上げかけているところだ」と私は言った。
「素直な言葉で言わせてもらえば、君のタフガイぶった演技はものすごく鼻につく」
「君の口からそういう言葉を聞くと、身を切られるようだ」
『高い窓』
VIEW
眺め
我々が芝生を横切って近づいていくと、女は気怠そうにこちらに目を向けた。十メートル手前から見ると、とびっきりの一級品に見えた。三メートル手前から見ると、彼女は十メートル手前から眺めるべくこしらえられていることがわかった。
『高い窓』
その家が視界から消えていくのを見ながら、私は不思議な気持ちを抱くことになった。どう言えばいいのだろう。詩をひとつ書き上げ、とても出来の良い詩だったのだが、それをなくしてしまい、思い出そうとしてもまるで思い出せないときのような気持ちだった。
『高い窓』
MODESTY
謙虚さ
「あなたは自分のことを知恵の働く人間だと思っているのかしら、ミスタ・マーロウ?」
「まあ、あふれてこぼれ落ちるほどでもありませんが」と私は言った。
『高い窓』
(了)
村上春樹訳のレイモンド・チャンドラー長篇7作
(書影をクリックするとAmazonにジャンプ)