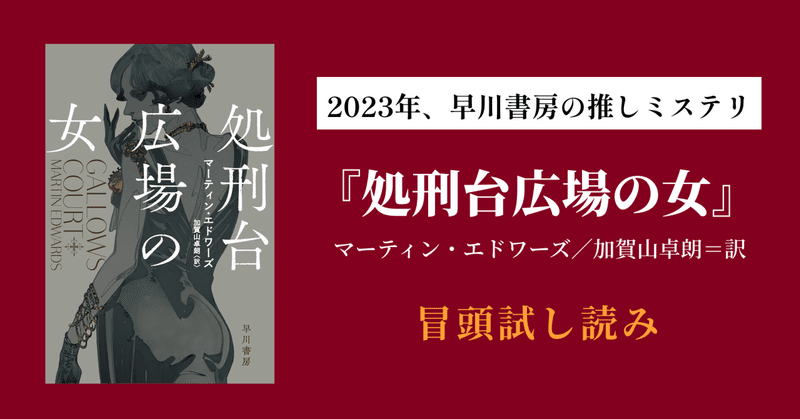
【試し読み】この女は名探偵か、悪魔か。この夏イチバンの話題作『処刑台広場の女』冒頭公開!
この夏イチバンの話題作『処刑台広場の女』(マーティン・エドワーズ/加賀山卓朗訳)は8月17日(木)発売!
黒い噂がつきまとう名探偵レイチェル・サヴァナク。果たして、この女は名探偵か、悪魔か。あなたはどちらだと思いますか? X(Twitter)にて冒頭を先読みされた方へ向けたプレゼントキャンペーンを実施中! 抽選で書籍『処刑台広場の女』があたる! 詳しくはこちらから→(https://twitter.com/Hayakawashobo/status/1687380352975990784?s=20)。キャンペーンは終了しました。

冒頭試し読み
ジュリエット・ブレンターノの日記
一九一九年一月三十日
両親が昨日死んだ。
ヘンリエッタから知らせを聞いたばかり。彼女は眼に涙を浮かべて、わたしの腕に触れた。わたしは何も言わず、泣きもしなかった。アイリッシュ海から島に吹きつける強い風が、わたしの代わりに叫んでくれた。
ヘンリエッタの話では、ハロルド・ブラウンがロンドンからサヴァナク判事に電報を送ってきたそうだ。わたしの両親が、ほかの何千もの人たちと同じようにスペイン風邪にやられたと。苦しむ間もなく、ふたりは抱き合って安らかにこの世を去ったらしい。
まるでおとぎ話。ヘンリエッタがそんなことをまったく信じていないのは、声のうつろな響きでわかった。
わたしも信じていない。母と父は殺されたのだ。まちがいなく。
悪いのはレイチェル・サヴァナク。
1
「ジェイコブ・フリントがまたこの家を見てますよ」家政婦の声が苛立った。「もしかして何か……」
「知ってるわけない」レイチェル・サヴァナクが言った。「心配しないで。わたしがなんとかする」
「いけません!」年配の家政婦はたしなめた。「そんな時間はありませんよ」
レイチェルは姿見のまえでクローシュ帽を整えた。鏡のなかの慎み深い顔が視線を返してきた。彼女の神経の末端がピリピリしているなどと想像する人はいないだろう。判事も黒い帽子をかぶるときに、こんな感覚になったのだろうか(かつてイギリスの法廷で死刑を宣告する際に着用した)。
「時間は充分あるわ。車が来るのは五分後だから」
レイチェルは夜会用の手袋をはめた。トルーマン夫人は彼女にハンドバッグを渡し、玄関のドアを開けた。応接間から鼻歌が聞こえる。マーサが新型の自動蓄音機でドーシー・ブラザーズの曲をかけているのだ。ポンパドール・ヒールをはいたレイチェルは、コール・ポーターの『レッツ・ドゥ・イット』を口ずさみながら、短い階段を軽やかにおりていった。
霧が這うように広場に流れこみ、一月の冷気が頬を刺した。黒貂(くろ てん)のコートを着ているのがありがたかった。街灯が汚れた灰色の風景を不気味な黄色に染めていた。レイチェルは小さな島で長年暮らしたので、海霧には慣れていた。海から紗幕のように波打って流れてきて、湿った大地に垂れかかる冬の霧には、奇妙な愛着がある。しかし、ロンドン名物のこの霧はまったく別物だ。煤や硫黄が混じって体に悪く、ライムハウス(イーストエンドの波止場地域)のごろつきのように人の息の根を止めることができる。脂っこい空気がレイチェルの眼に染み、ピリピリする刺激が喉を焼いた。それでも彼女は盲人が漆黒の闇を怖れないのと同様、汚れて粘つく空気の渦に悩まされることはなかった。今宵は無敵の気分だった。
影のなかから人の姿が浮かび出た。暗がりに眼を凝らすと、外套を着て中折れ帽をかぶった長身瘦軀の男が見えてきた。長いウールのマフラーをゆったりと巻いて、肩から垂らしている。足取りは溌剌としているが、ぎこちない。呼び鈴を鳴らす勇気を奮い起こしているのだろう。
「ミス・サヴァナク! 日曜の夜にすみません!」その声は若々しく熱心で、悪びれる様子は微塵もなかった。「ぼくの名前は──」
「知っています」
「ですが、正式に紹介されたことはないので」中折れ帽の下からブロンドの髪があちこち飛び出していた。もったいぶって咳払いをしても、不器用さは隠せない。二十四歳なのに、顔をごしごし洗ってさっぱりした小学生のような雰囲気だった。「ちなみにぼくは──」
「ジェイコブ・フリント、クラリオンの記者。わたしが報道機関に何も話さないことは知ってるはずよ」
「宿題はしてきました」彼は左右をすばやく見た。「ひとつ確かなのは、凶暴な殺人鬼がロンドンの街をうろついてるときに、レディが外出するのは危険だってことです」
「わたしはレディじゃないかもしれない」
ジェイコブの視線は彼女のダイヤモンドつきの帽子留めに張りついた。「あなたはどこからどう見ても──」
「外見じゃわからないものよ」
ジェイコブは彼女に身を寄せた。彼の肌からはコールタール石鹸がにおった。「かりにレディじゃないとしたら、なおさら気をつけないと」
「わたしを脅すのは利口な手じゃないわ、ミスター・フリント」
ジェイコブは一歩うしろに下がった。「どうしてもあなたと話したかったんです。このまえ家政婦にことづけた手紙を憶えていますか?」
もちろんレイチェルは憶えていた。彼がそれを預けるところを窓から見ていたのだから。あのときジェイコブは階段で待ちながら、そわそわとネクタイをいじっていた。レイチェル自身がドアを開けると思うほど世間知らずでもあるまいに。
「すぐに迎えの車が来るの。だから取材を受けるつもりはありません。とりわけ霧に包まれた舗道なんかでは」
「ぼくは信用できますよ、ミス・サヴァナク」
「冗談でしょ。あなたは記者よ」
「いや、本当に。ぼくたちには共通点がある」
「どこに?」レイチェルは手袋をはめた手でひとつずつ指摘していった。「あなたはヨークシャーで見習い記者になって、去年の秋、ロンドンにやってきた。アムウェル・ストリートに下宿していて、家主の娘から体と引き換えに結婚を迫られるんじゃないかと心配している。野心家なので、ちゃんとした新聞ではなく、クラリオンの醜聞あさりの連中に加わった。編集長はあなたのしつこさには感心しているけれど、無分別には頭を悩ませている」
ジェイコブは息を呑んだ。「どうしてそれを……?」
「あなたは犯罪に病的な興味を抱き、このまえのトマス・ベッツの事故を、不運な出来事ではあるけれど絶好の機会ととらえている。クラリオンの主任犯罪報道記者が瀕死の状態になったことで、出世のチャンスが訪れたと」彼女はそこでひと息ついた。「己の野望には気をつけることね。ウォール街が崩壊するなら、なんだって崩壊しうる。前途洋々たる将来がふいになったら、悔やんでも悔やみきれないでしょう、トマス・ベッツみたいに」
ジェイコブは頬に平手打ちをくらったかのようにたじろいだ。話しはじめた声はかすれていた。
「さすがはコーラスガール殺害事件を解決した人だ。名探偵ですね。警察を恥じ入らせただけのことはある」
「手紙を送りつけておいて、わたしが何もしないと思ったの?」
「ぼくのことをそこまで調べてもらって光栄です」ジェイコブは思いきって笑みを浮かべ、歯並びの悪いところを見せた。「それともその輝かしい知性で、ぼくのマフラーの結び方が雑だとか、靴が汚れてるといったことから、いまのすべてを導き出したんですか?」
「記事を書くならほかの人を見つけなさい、ミスター・フリント」
「醜聞あさりと呼ばれたことを知ったら、うちの編集長はショックを受けるだろうな」彼は落ち着きを失ったときと同じくらい早く取り戻した。「クラリオン紙は一般大衆に声を与えるんですよ。最新のスローガンは”読者は知る必要がある”で」
「わたしについて知る必要はない」
「手持ちの資産は別として、あなたとぼくはさほど変わりませんよ」ジェイコブはにやりとした。「どちらもロンドンに来たばかりだし、好奇心旺盛で、ラバみたいに頑固だ。コーラスガール事件を解決したということは否定しませんでしたね。なら最新の話題の事件についてどう思います? コヴェント・ガーデンで惨殺された気の毒なメアリ=ジェイン・ヘイズのことは?」
ジェイコブはそこで黙ったが、レイチェルは空白を埋めなかった。
「メアリ=ジェイン・ヘイズの首のない死体は袋に入っていた。頭部は見つかっていない」ジェイコブは小声で言った。「詳細は残酷すぎてとても新聞には書けません。彼女はまっとうな女性だった──だからうちの読者は夜眠れなくなる。あんな目に遭ってもしかたない女性ではなかったから」
レイチェル・サヴァナクの顔は陶器の仮面のようだった。「女性がその人にふさわしい扱いを受けることなんてある?」
「この狂人はひとりではやめません。それが彼らの習性です。だからほかの女性に被害が及ぶまえに、なんとしても裁判にかけないと」
彼女はじっと相手を見た。「あなたは裁判というものを信じてるの?」
ロールス・ロイス・ファントムのつややかな車体が汚れた茶色の霧のなかから現われ、若者は轢かれそうになって飛びのいた。車はレイチェルの横に停まった。
「ではこれで、ミスター・フリント」
身長百九十センチを超える肩幅の広い男が車から出てきた。後部座席のドアを開けた彼に、レイチェルはハンドバッグを渡した。ジェイコブ・フリントは男にちらっと怯えた視線を送った。運転手のお仕着せよりヘビー級ボクサーのガウンのほうが似合いそうだ。服のボタンが警告灯のように光っていた。
ジェイコブは軽く会釈した。「報道から逃げてもいいことはありませんよ、ミス・サヴァナク、ぼくが記事を書かなかったら、もっと無遠慮な誰かが書くだけだ。ぼくにスクープをくださいよ。後悔はさせません」
レイチェルは彼のマフラーの両端をつかんで引っ張り、きつく首に巻きつけた。不意をつかれたジェイコブは、あっと声を発した。
「わたしは後悔なんかで時間を無駄にしないの、ミスター・フリント」彼女はささやいた。
そしてマフラーを放すと、トルーマンからハンドバッグを受け取り、ファントムの後部座席に乗りこんだ。車はすべるように夜のなかへ走り出した。レイチェルは、ジェイコブ・フリントが首をさすりながら闇に消える車を見送っているところを意識した──彼は利用できるだろうか。欲しがっている記事のネタを与えるのは危険だろうが、これまで賭けを怖れたことはない。わたしにはそういう血が流れている。
「あの若者が面倒を起こしたとか?」トルーマンが送話管を通して訊いた。
「大丈夫。何か知ってたら、もらしてたはずだから」
後部座席の彼女の隣には、ワインレッドのビロードの座面を傷つけないように薄紙を巻いた包みが置いてあった。レイチェルは紙をむき取って制式のリボルバーをあらわにした。それがウェブリーの四五五口径マークⅥであることがわかるくらいには、火器のことを学んでいた。グリップの網目模様とニッケルメッキが目立つが、足のつかない銃かどうか尋ねる必要はなかった。トルーマンの配慮は行き届いている。ワニ革のハンドバッグの口を開いて、銃をなかに入れた。
ユーストン駅に向かうにつれ、舗道には一般の通行人より制服警官のほうが増えてきた。女性はひとりも歩いていない。コヴェント・ガーデンの殺人鬼が野放しになっているいま、よほどの理由がないかぎり、霧のロンドン中心部をうろつきたい人はいない。大気には汚臭さながら恐怖が満ちていた。
前方に駅入口のドリス様式のアーチが、ぬっと現われた。滅びた文明のグロテスクな記念碑だ。レイチェルは腕時計を見た。六時十分前。霧はあったが間に合った。
「ここで停めて」
彼女は車から飛びおり、敷石に靴音を響かせて駅に急いだ。駅構内の軽食堂の明るく青い光のまわりには人が群がっていた。レイチェルは手荷物預かり所に歩いていった。スタンリー・ボールドウィン(貴族の実業家。二十世紀前半に三度、イギリス首相を務めた)に驚くほどよく似た年配の男性が、相手もいないのに大声で文句を言っていた。彼が杖を振っている先には、大きな厚紙に黒い大文字でこう書かれていた。
閉鎖中。再開は追って通知
レイチェルはアルフレッド・ヒッチコック監督の映画『恐喝』の黄色いポスターの下で立ち止まった。あとは待つだけだ。不運なハエが引っかかるのを待つ優雅なクモのように。
六時ちょうど一分前、ローレンス・パードウが歩いてくるのが見えた。背が低くでっぷり太った男で、カシミアの外套を着て山高帽をかぶっている。安っぽいベニヤ板の箱を、ドレスデンの陶器が詰まっているかのように大事そうに抱えていた。棍棒を持った盗人に襲われそうといった態度で、眼をしきりにあちこちに向けている。
レイチェルは、彼が手荷物預かり所に近づいてくるのを見つめた。厚紙から二メートルほどのところまで来て、パードウはようやく表示に気づいたらしく、はっと息を呑んだ。木箱を地面に置き、ポケットからハンカチを取り出して額の汗をふく。群衆のなかからたくましい巡査が出てきて、つかつかと彼に近づいた。レイチェルは一歩踏み出した。巡査がパードウに何か耳打ちした。
パードウはどうにか見苦しい笑みを浮かべた。大丈夫です、お巡りさん、お気遣いはありがたいが助けは必要ありませんと言っているかのようだった。巡査は離れ際に木箱を一瞥し、明るくうなずくと、背を向けて去った。パードウは安心して体の力を抜いた。
いまので気が動転して、あわてて逃げ出すだろうか? 彼は病人だ。心臓発作を起こして倒れてもおかしくない。
否。起こさなかった。パードウは一瞬ためらったのち、木箱を拾い上げて出口に向かった。それがレイチェルの引き返す合図になった。彼女はパードウの二倍の速さで動いた。
駅の外に出ると、霧が濃くなっていたが、ロールス・ロイスの輪郭はまちがえようがない。トルーマンが後部座席のドアを開け、レイチェルは乗りこんだ。窓越しに見ると、パードウが荷物の重さによろめきながら、灰色の夜のなか、フェンダーが黒い臙脂色のファントムを探していた。
トルーマンが何も言わずに進み出て、パードウの木箱を取り上げ、トランクに入れて、車内に入るように彼に手を振った。
パードウは車に入り、ドアが閉まったところでレイチェルに気づいた。額に汗をかき、息を荒らげていた。顔は熟れすぎたプラム色だった。五十がらみで、運動には慣れていない。いつも誰かがものを取りに行ったり、運んだりしてくれるからだ。レイチェルはやさしく微笑んで、肝腎なときまでこの人が死なないようにと祈った。
「こんばんは、ミスター・パードウ」
「こ……こんばんは」暗号文を読み解こうとするかのように、眼を細めて彼女の顔を確かめた。「ひょっとして……ミス・サヴァナク?」
「家族と似ているところがあります?」
「ああ、ええ。わずかにですが、もちろん……立派なかたでした、亡くなられた父上は」絹のハンカチを取り出して、汗ばんだ額をふいた。「サヴァナク判事……本当に惜しいかたを亡くした」
「動揺してるみたいね」
パードウは咳払いをした。「すみません、ミス・サヴァナク。なんというか……このところつらいことが多くて」
彼はレイチェルの考えを読もうとしてか、眉間にしわを寄せた。そんなことをしても無駄だった。自分の運命は知りようがない。
トルーマンが車のエンジンをかけた。レイチェルは手をハンドバッグに置いた。ファントムのエンジンはきわめて静かなので、パードウの頭のギアが入って歯車がまわる音すら聞こえそうだった。
車がトッテナム・コート・ロードに入ると、パードウが言った。「これからどこへ?」
「サウス・オードリー・ストリートよ」
「まさか私の家に?」彼は当惑した。
「そう、あなたの家よ。言われたとおり、家で働く人たちに今晩はいなくていいと伝えたでしょうね?」
「信頼する友人から、ユーストン駅に行って手荷物預かり所に……あるものを預けるようにと指示する手紙が来たのです。この車が迎えに来るから、乗って若い女性に会うようにと──それがあなただとは知らなかった、ミス・サヴァナク。その女性が友人のところへ連れていってくれると書いてあった。なぜ家にいる者たち全員を外出させたいのかは、説明がなくて……」
「ごめんなさいね」レイチェルは言った。「その手紙を送ったのはわたし」
パードウの眼に恐怖が燃え上がった。「ありえない!」
「ありえないことなんてない」彼女は静かに言った。「肝に銘じておきなさい、たとえそれがあなたの最後の仕事になっても」
「理解できない」
レイチェルはバッグからリボルバーを取り出し、パードウの脇腹に銃口を押しつけた。「理解する必要はないわ。もう黙って」
パードウの書斎には、鼻につんとくる艶出しのにおいが満ちていた。ドアはひとつで、窓はない。唯一の明かりは金の燭台で燃える蠟燭の光だけだった。大きな振り子時計の時を刻む音が不自然に大きく聞こえた。パードウはロールトップデスクのまえに坐り、背を丸めていた。両手は痙攣を起こしたように震えている。机の上にはペン一本と、何も書かれていないフールスキャップ紙数枚、封筒二枚に、黒いインクの壺があった。
トルーマンは革張りのウィングバックチェアに坐り、右手に銃、左手に刃が光る肉切りナイフを持っていた。足元にはコダックのブローニー・カメラ。床には熊毛の敷物が広がっている。そのまんなかに、パードウがレイチェルに銃でうながされて運びこんだ木箱が置いてあった。
レイチェルはハンドバッグに手を入れて、チェスの駒を取り出した。黒のポーンだ。パードウは低くうめいた。彼女は机に近づき、その駒をインク壺の隣に置いて、フールスキャップ紙と封筒を一枚ずつ取り、自分のバッグに入れた。
「どうしてこんなことをするんです」パードウはまばたきして涙を押し戻した。「隣の部屋にはミルナー金庫がある。組み合わせの数字は……」
「どうしてわたしがあなたの財産を盗まなきゃならないの? いまでも使い途(みち)に困るほどあるのに」
「ならば……何が望みなんです?」
「殺人の自白書を書いてもらう」レイチェルは言った。「文言については心配しないで。わたしが一言一句指示するから」
パードウのふっくらした両頬から最後の血色が消えた。「殺人の自白? 頭がおかしくなったのでは?」
トルーマンが椅子で身を乗り出した。脅しをたっぷり含んだ動きだった。レイチェルは銃をパードウの胸に向けた。
「お願いだ」パードウは、喉をうがいのように鳴らした。「父上はこんなことは望まな──」
「判事は死んだわ」レイチェルは微笑んだ。「でもわたしは、物事をドラマチックにする趣味を受け継いでいる」
「わ……私はもっとも忠実な──」
「最後にあなたが署名したら、わたしたちはここから出ていく。あなたは部屋の鍵をかけ、鍵は穴に挿しっぱなしにしておく。机のいちばん下の抽斗──留め具は壊れてる──に弾がひとつだけ入った銃がある。それをこめかみに当てるなり、口にくわえるなり、好きにして。手っ取り早い終わり方よ。もうひとつの方法よりはるかに望ましい」
パードウは生体解剖をする者のまえに出たモルモットのように体をよじらせた。「私に自殺を命じるなんて無茶だ!」
「それが最善の道よ」レイチェルは言った。「あなたはすでに死の宣告を受けている。ハーレー街(一流の開業医や医学関係者が多く住むロンドン中心部の通り)のお友だちには余命どのくらいだと言われた? せいぜい半年?」
パードウは驚いて眼をぱちくりさせた。「どうしてそれを! 誰にも言ってないのに。サー・ユースタスがもらすわけはないし……」
「サー・ユースタスの診断結果を思い出しなさい。これは彼が予言した長い苦痛から逃れるチャンスなの。一発の弾を無駄にしないで」
「だが……なぜ?」
「ジュリエット・ブレンターノに起きたことを知ってる?」
「なんの話だ?」パードウは眼をぎゅっと閉じた。「わからない」
「そう。あなたはわからないまま墓に入るの」レイチェルはトルーマンに合図した。トルーマンはナイフの切っ先を年上の男の喉に向けた。
「やらなきゃいけないことを、ずるずる引き伸ばさないで」レイチェルは言った。「すぐ終わるということを慈悲だと思いなさい。六十秒、わたしたちが部屋を出てからそれだけあげる。それ以上は認めない」
パードウは彼女の眼をのぞきこみ、見えたものにぶるっと身を震わせた。
そして長い沈黙のあと、しわがれ声で言った。「わかった」
「ペンにインクを吸い上げて」
ゆっくりと、パードウは言われたとおりにした。
「さあ、書きなさい」彼女はソフトノーズの弾を相手の脳に撃ちこむように、一語一語をゆっくりと伝えた。「”私はメアリ=ジェイン・ヘイズを彼女のマフラーで締め殺し、弓鋸で切断した。あれは私ひとりの犯行で……”」
2
ジェイコブ・フリントは徒歩で家に向かった。歩くことが考えを整理するのに役立った。待ちに待ったレイチェル・サヴァナクとの会話で、頭のなかには新たな疑問が渦巻いていた。知りたい答えがたくさんあったのだが。
落胆に押しつぶされそうだった。それは背中にのった大きな岩のように重かった。取材力には自信があったし、暇さえあれば『英国著名裁判』を熟読して、交互尋問のテクニックも学んでいる。この日の午後は、寝室の鏡のまえで下稽古までしたのに、本人と向き合うと、そうした準備はなんの役にも立たなかった。彼の質問を無意味な雑談に変えてしまったレイチェルの冷たく射貫くような視線を思い出して、ジェイコブは己の不甲斐なさに顔が熱くなった。
何がわかったか? メアリ=ジェイン・ヘイズの殺害については、何ひとつわからなかった。女性を絞め殺して首を切断し、頭部をどこかへ隠すような非道な男の捜索に加わっている刑事をジェイコブはひとり知っていた。友人であるそのスタン・サーロウがもらした話によると、スコットランド・ヤード(ロンドン警視庁本部)は、あのコヴェント・ガーデン殺人事件にレイチェル・サヴァナクが興味を示すのを期待しているという。レイチェルは最新の殺人事件について彼女なりの推理をしているのかもしれないが、なんのヒントも与えてくれなかった。夢見ていたスクープ記事はまだ月ほども遠いままだった。
アムウェル・ストリートに曲がりながら、ジェイコブは時間を無駄にしたわけではないと自分に言い聞かせた。いっとき恥ずかしい思いはしたが、レイチェル・サヴァナクの注意深さが徹底していることはわかった。タイムズ紙の社説かと思うほど入念なことば遣いでしたためた手紙が功を奏して、彼のことを調べ上げていたではないか。エレイン・ダウドに結婚を迫られていることまで知っていた。
ただコメントを拒否すればいいだけなのに、なぜそこまでする? マウント・プレザントの巨大な郵便局のまえを歩いていたときに、暗闇を貫く懐中電灯の光のように突然答えが閃いた。
あれは良心が咎めている証拠だ。レイチェル・サヴァナクは何か隠している。
ジェイコブの家主のダウド夫人は、家を番地の数字で呼ぶことを拒み、亡き夫にちなんで〈エドガー館〉と名づけていた。エドガー・ダウドは、先の大戦のツェッペリン飛行船による無音空襲の爆弾に当たって死んでいた。羽振りのいい会計士だったので、妻と若い娘が快適に暮らせる蓄えを遺したが、ダウド夫人の資金は時とともに減ってきた。減る勢いは彼女が愛好するフランス製の高級服とロンドンのジンへの出費で加速して、ついに家計をやりくりするために下宿人を入れることにしたのだった。
ジェイコブのクラリオン社の同僚で、以前ここに住んでいたオリヴァー・マカリンデンから、エドガー館はフリート街(多くの新聞社の本社がある)に近いし、家賃も驚くほど安いぞと勧められた。ダウド夫人は”いい借り手”と見なす若い男たちの家賃を気前よく割り引いてくれるのだ。その代償としてジェイコブは、夫人のとめどないおしゃべりとあからさまな結婚の仲介に耐えなければならなかった。
これだけ家賃が安いのに下宿人はジェイコブだけで、ダウド夫人は娘のエレインとの夕食にしつこく彼を誘った。長年、娘が地元の裕福な服地屋のにきび面の息子と仲よくなることを後押ししてきたが、ほとんど進展はなかったというのがジェイコブの読みだった。“オイリー”・マカリンデンとくっつけようという試みもうまくいかなかった。もっとも、オイリーの趣味に女性は含まれないようだが。エレインは最近までつき合っていた愛しの君を断じて母親に紹介しなかった。どうやら相手は既婚者で、秘密にするしかなかったのだろう。彼女がもらした話は、ジェイコブがロンドンに来る直前にその男と別れたということだけだった。おそらく彼が妻を捨てるのを待つのに疲れたのだ。お母さんの言うことは正しかった、そろそろ身を固めるときだ、と決意したのかもしれない。しかし、世の中で名をなしたい若い記者は、アムウェル・ストリートでスリッパをはいてパイプをくゆらす生活よりはるか先の地平を見ていた。
ジェイコブは三階の自分の砦にまっすぐ駆け上がるつもりだったが、台所のドアがいきなり開いて足止めをくらった。ソーセージを焼くにおいが漂ってきて、すぐあとからダウド夫人が出てきた。昔は色っぽい体つきだったのだろうが、いまはただ大きくて肉が波打っている。夕食を作る家主に似つかわしくないシフォンドレスの深い襟ぐりがやたらと眼を惹いた。
「お帰りなさい、ジェイコブ! 霧も寒さもひどい夜よね! わたしたちといっしょに食べない? あったまるわよ」
ジェイコブはためらった。においがたまらない。「ありがとうございます、ミセス・ダウド」
夫人は太い指を振った。「何度言えばわかるの? わたしの名前はペイシェンス。忍耐なんて柄じゃないけどね」
胃がグルグル鳴って、ジェイコブは降参した。それに、エレインは愉しい話し相手だ。もしかすると、レイチェル・サヴァナクのことを忘れさせてくれるかもしれない。
*
「女性の友だちとはうまくいったの?」エレインが暖炉で両手を温めながら訊いた。
「話してくれなかった」
「噓でしょ! こんなに素敵な男性なのに? いったい何を考えてるんだか」
ふたりは客間にいた。その小さい部屋にいるのは彼らだけで、エレインが職場の花屋から持ってきたヒヤシンスが彩りを添えていた。ダウド夫人は、きちんと片づいた台所に引きあげるという見え見えの戦略を用いた。若いふたりを見張る仕事は、マントルピースの上の亡夫──口ひげをたっぷり蓄えた厳めしい顔──にまかせたのだ。彼の額入りの写真が誇らしい位置を占め、その左右には、遠い昔に家族が休暇をすごしたディールやウェストクリフの色とりどりの小さな土産物が並んでいる。ジェイコブは紅茶をひと口飲み、仕事のことをエレインに気軽に話すのではなかったと後悔した。ついやってしまったのだ。ロンドンに来てから、新たに得た仕事に身も心も捧げていた。たまにではあれ長い手紙を、ヨークシャー州アームリーにいる寡婦の母親に書くことはあったが、クラリオンで欠くべからざる人材になるために日夜努力しているので、新しい友だちを探す時間はないに等しかった。
エレインは燃えるような赤毛で、そばかすがあり、色目を使う。最初は挨拶を交わす程度だったのが、徐々に友情に変わり、ついにある日、彼女が大の芝居好きであることを知っている花屋の得意客のひとりからイナニティ劇場のチケットを二枚譲り受けたので、と誘われることになった。エレインとジェイコブは、劇場でシンドバッドと姉妹たちといっしょに歌い、空飛ぶフィネガン一家の綱渡りの芸にハラハラし、ヌビアの魔法と神秘の女王ネフェルティティの奇術に息を呑んだ。ネフェルティティは美しかったが、ジェイコブは舞台上の彼女のしなやかな動きにうっとりしながらも、エレインの引き締まった体が誤解の余地なく横から押しつけられるのにも同じくらい興奮した。
その後、彼はエレインをリージェント劇場に誘って、エドガー・ウォーレス作の『密告者』を鑑賞し(そのときエレインは、シンドバッドとネフェルティティに加えて今度はどうしてもバーナード・リーのサインが欲しいと言って、楽屋待ちをした)、映画も二本観た。エレインがあまりにも熱心に彼自身と彼の仕事に興味を示すので、ジェイコブはうれしくなり、このまえの夜、ダウド夫人が寝室に引きあげたあとで、レイチェル・サヴァナクに関するスクープで調査報道記者としての名声を確立したいという野望を打ち明けたのだった。エレインにキスをすると、彼女は熱く応えた。その熱意にジェイコブはクラクラし、彼女の憧れの人、アイヴァー・ノヴェロとまちがわれているのではないかと思った。既婚の恋人からひとつふたつ学んだことがあったようだ。エレインの健康的なイギリスふうの顔立ちは、ネフェルティティの彫刻芸術のような輝かしい洗練には欠けるけれど、未来に希望を感じさせる線を描いている。エレインは彼のイングランド北部の訛りが大好きで、聞くと胸がドキドキすると言っていた。
結婚指輪をつけるまで体は許さないとエレインが主張することはなさそうだったが、ジェイコブは、彼女を妊娠させて道義上結婚しなければならなくなるのが怖かった。ダウド夫人は折に触れて、女性は二十三歳にもなればすっかり妻と母になる準備ができていると仄めかしていた。ジェイコブに忍び寄る不安は、家族に記者を迎え入れるという夫人の冗談めかした発言と、それに続くぞっとするほどこれ見よがしのウインクで、警戒警報に変わった。エドガー館で幸せな家庭を築くという見通しは、ジェイコブにとって終身刑のようなものだった。”ただの仲よし”の関係にとどまるほうがいいに決まっている。
「信じられないだろう? ぼくもそう思う」
エレインは笑って、長椅子の彼の隣に腰かけた。ふたりはごくわずかな緩衝地帯を隔てて坐っている。「彼女、婚約者がいるとか?」
「ぼくが知るかぎり、いないよ」
「それでも一流記者? わたしの考えを言いましょうか。彼女は謎の女を演じたいんだと思う」
「演じてるとは思えないけどな」
「話を聞いてると、あなたに魔法をかける魔女みたいだけど。さあ、もっと話して。わたしにライバルがいるなら、何もかも聞いておきたい!」
ジェイコブは、まいったというふうに両手を広げた。「本当にあまり知らないんだ。誰も知らない」
「逃げられると思ったら大まちがいよ、ジェイコブ・フリント。わたしは馬鹿じゃない。さあ、秘密を明かして!」
ジェイコブはため息をつきそうになるのをこらえた。たしかにエレインは馬鹿からほど遠い。簡単にあきらめる女性でもない。レイチェル・サヴァナクに対する興味をかき立てたのは大失敗だった。
「最初に彼女の名前を聞いたのは、知り合いの刑事からだった。ある晩、スタン・サーロウと一杯やりながらコーラスガール殺害事件について話していたときに、彼の口が軽くなったんだ」
エレインは顔をしかめた。あまりにも暗いニュースばかりなので、もう新聞は読まなくなったと言っている。ウォール街が破綻し、恐慌が迫っていて、世界はむちゃくちゃになり、庶民はそのどれに対しても何もできない……。
「それはあの気の毒な……」
「そう、ドリー・ベンソンだ。絞め殺されて……凌辱された。犯人は自殺したらしいね、とぼくが言ったら、サーロウがその話をしてくれた。レイチェル・サヴァナクと名乗る女性が突然スコットランド・ヤードにやってきて、犯人の名前を知っていると言ったそうだ。警察はすでにドリーの元婚約者を逮捕して、殺人容疑で起訴していた。レイチェル・サヴァナクは高名な判事の娘だ。でなきゃ門前払いをくらってた。素人探偵で、おまけに若い女性だ。誇り高い警官がまじめに取り合うわけがないだろう?」
エレインは彼の腕をなでた。「女性を見くびっちゃだめよ」
「レイチェル・サヴァナクは、殺人があった夜のクロード・リナカーの行動をどうか調べてほしいと言った。リナカーは裕福な美術愛好家、現役閣僚の弟で、自分のことを芸術家だと思ってる。ウォルター・シッカートの作品を褒めたたえ、同じように禍々しい死に興味を抱いていたものの、シッカートのような才能はなかった。ドリーが働いていた劇場の理事会に所属し、彼女を直接知っていた。ドリーは当時のボーイフレンドを袖にして、億万長者とつき合いはじめたと友人たちに自慢していた。レイチェルは、ドリーのその恋人はリナカーだったと主張した。ドリーが身ごもったせいでリナカーが暴力をふるうようになったというのが、彼女の見立てだった」
「本当に身ごもってたの?」
「ああ。ドリーは妊娠してた。警察はその情報を公にしてなかったけどね。それでもレイチェルの推理は少々乱暴に思えた。捜査にぜひ協力したいという熱意は示していたけど、ヤードの上層部は、彼女がリナカーに恨みを抱いているんだろうと考えた。たぶんリナカーに拒絶されて仕返ししたいのだ、彼女はただの詮索好きで時間があり余っているんだろう、とね。そこでレイチェルに丁重に感謝して、お引き取り願った。ところがその二十四時間後、リナカーがストリキニーネをのんだ。馬一頭を殺せるほどの量をね。人間などひとたまりもない」
「なんてこと」エレインはぶるっと震えた。「自白書が残ってたとか?」
「いや、でも警察の捜査で、チェルシーの彼の自宅から決定的な証拠が見つかったんだ。死んだ女性の髪の房が半ダースほど煙草ケースのなかに入っていた。アトリエには描きかけのドリーの裸体画があって、そこに猥褻なことばが書き殴ってあった」
「つまり、あなたの友人のレイチェルが正しかったの?」
「友人じゃないよ。警察は彼女がリナカーに送った電報も見つけた。ふたりが電話でした会話に触れて、レイチェルが彼の家を訪ねるという内容だった」
エレインは眼を見開いた。「リナカーが万事休すと感じて自殺したように聞こえるけど」
「かもしれないよ。レイチェルが死因審問に呼ばれて証言することはなかった。医学的証拠から心神喪失だろうということになり、評決は自殺だった。リナカーの兄が手をまわして、報道機関は黙らされた。ドリー・ベンソン殺害の容疑をかけられていた男は釈放され、こうして捜査はひっそりと終了した。ぼくはサーロウからこの情報を仕入れたあと、トム・ベッツに事件のことを尋ねて──」
「トム・ベッツって、このまえ車に轢かれた人?」
「ああ、気の毒にね。うちの主任犯罪報道記者だ。彼はぼくの話を聞いても驚かなかった。レイチェル・サヴァナクがリナカーを殺人者だと名指ししたこともすでに耳にしてた。誰も公式取材には応じてくれなかったけどね。リナカーの兄は首相の右腕だ。かなり権力がある」
「だからほかの記者はこの話を記事にしようと思わないのね?」
「ああ、たとえ同じ噂を聞いてたとしてもだ。だけど、トムはレイチェルに興味を持った。なぜ彼女は探偵を演じたがるのか、そしてなぜリナカーを疑うに至ったのか。彼女は現代美術の蒐集家だから、その関係でリナカーのことを聞きつけたのかもしれない。リナカーは大口を叩くことで有名だったから、ひょっとすると自分のほうから何かもらしたのかも」
「あら」エレインは馬鹿にしたように笑った。「だとしたら、レイチェル・サヴァナクはそんなにすぐれた探偵でもないんじゃない?」
「犯罪者が決してまちがいを犯さないなら刑務所は空っぽだよ。レイチェルが正しくて、ヤードがまちがってたのは事実だ。クラリオンにとってどれほどの特ダネになったか、想像してごらん。けど彼女はトムの取材の申しこみを無視した。わが社には彼女の写真すらなかったんだ。だからトムはぼくにゴシップ欄の記事を書かせた。そこで彼女の名前を出せってね。とにかく彼女を引っ張り出したかったが、もとから見込み薄だ。なんの成果もなかった。トムはまだこの件を掘り下げてる最中に車にはねられた。そしてロンドン中央部でまた別の女性が無残に殺された。ぼくはレイチェル・サヴァナクが首を突っこんでくるだろうかと思った。友人のサーロウによると、ヤードもそう思ったらしい」
エレインは彼をちらっと見た。「ふたつの事件はつながってないんでしょう?」
「つながってるわけないだろう? でも、彼女が犯罪にことさら魅了されるなら……まあ、トムとはそりが合わなかったみたいだけど、ぼくが話したらどうだろうと思ったんだ」
「でも嫌味を言われて追い払われた? 安息日に気の毒な女性につきまとったんだから、当然よね」エレインはくすっと笑った。「彼女、きれいなの?」
「まあね」ジェイコブは慎重に答えた。「好みにもよるけど」
「男の人がひと目惚れしたときの言いわけに聞こえる」エレインはわざとらしくため息をついた。「だったら続けなさいな。あなたがきれいな顔に抵抗できないことはわかってる。ネフェルティティ女王にメロメロになったの憶えてる?」
「メロメロになんてなってないよ!」
「ご冗談を。とにかく、その妖婦セイレーンについて、すべて知りたいの。どんな人?」
「もし判事として裁判に出たら、被告席の悪党をひとり残らず葬り去るだろうね」
「でも、きれいなの?」
ジェイコブはその質問を、ラグビー選手がフルバックのタックルをかわすようにはぐらかした。「少なくとも、サヴァナク家の鼻は受け継いでいない。サヴァナク判事が裁判長になったときには、パンチ誌が漫画で長い鉤鼻を馬鹿にしてたからね」
「判事については聞いたことがないわ」
「〝処刑台のサヴァナク〟と呼ばれてたよ。厳しいことで悪名を轟かせた。奥さんが戦前に亡くなって、そこから精神がおかしくなった。法廷で奇矯な行動をとりだして、判決はますます過激になった。最後はスキャンダルだ。中央刑事裁判所の休廷期間中に、自分の手首を切ったんだ」
「なんて恐ろしい!」
エレインが震え上がり、ジェイコブは彼女に腕をまわした。服の袖が彼女の胸をかすめた。「死ななかったけどね。司法の場からは引退するしかなかった。そこで、ゴーントと呼ばれる島にある家族の屋敷〈サヴァナク荘〉に戻った」
エレインの温かい息が彼の頬にかかった。「それはどこ?」
「アイリッシュ海にある。カンバーランド西岸の先だ。どこからどう見ても僻地(へき ち)さ。潮が引いたときには、海上に現われる土手道を通って本土から往き来できるけど、あとは船を出すしかない。あそこの海流は危険だ。レイチェルはその島で育った。頭がおかしくなった父親と、何人かの使用人といっしょにね」
エレインはまた震えた。「ペントンヴィル刑務所に入れられるよりひどそう」
「父親が去年死んだから、彼女は自立して新しい生活を始めた。いまの家はロンドンでも最高級の住宅地にある。まえの家主は会社設立者だった。過去一年半のあいだに、彼はその家にあらゆる現代的な改良を加えた。ジムに始まって、地下には暗室、最上階にはプールというふうにね」
「だったらなぜ他人に売ったの?」
ジェイコブは笑った。「リフォームに使ったのが自分の金じゃなかったからさ。彼は詐欺で有罪になり、禁固十年を言い渡された。うち二年は重い労役つきだ。レイチェルは破産管財人からその家を買い、〈ゴーント館〉と名づけた」
エレインは温かい脚を彼の脚に押しつけた。ジェイコブはラベンダーの香水のにおいを吸いこんだ。「どうして彼女は、わざわざ海のまんなかのとんでもなく寂しい島で、文明から切り離されて暮らすことを選んだのかしら」
「牧歌的な島だと聞いたけどね」
「牧歌的!」エレインは大きなため息をもらした。「ねえ、もう彼女のことがうらやましくなくなった」
ジェイコブはにやりとした。「レイチェルがカスタム仕様のロールス・ロイスに乗っていて、家具はパリのルールマンにデザインさせたと聞いたら、気が変わるんじゃないかな。彼女が買いあさってるけばけばしい現代アートの値段を聞いたら涙が出ると思うよ。ほかの趣味でわかってるのは、おそらく素人探偵だけだ。上流社会とのつき合いは避けてるし、報道機関は大嫌いだしね」
「それはあなたの責任じゃないって言える?」エレインは言い返した。「クラリオンに写真をどんどん載せられたいと誰もが思ってるわけじゃないわ。わたしも、もし大金持ちだったら、あなたみたいな詮索好きに自分のお金の使い途を知られたくないもの」
「ぼくが関心を抱いてるのは、ほかのことさ。あの家にはほとんど使用人がいない。夫婦ひと組と、メイドがひとりだけ。プライバシーを大切にしたいのはわかるよ。でも、家事をこなす人手をどうしてそこまで削らなきゃならない?」ジェイコブは束の間、眼を閉じた。「彼女についてはひとつ逸話がある。教えてあげよう」
「見出しが見える」エレインは息を吸った。「“探偵界のガルボ(アメリカの女優。隠遁生活を好んだ)”ってね」
ジェイコブは愉しげに笑った。「そりゃいい! いただくかもしれないよ。花屋を馘になったら、副編集長の輝かしい未来が待ってるぞ」
「褒めことばとして受け取っておくわ」エレインはさらにすり寄った。ジェイコブは空いた手をピンクのカーディガンのなかにすべりこませた。
玄関のドアを激しく叩く音がして、目的地に向かう彼の指が止まった。廊下にダウド夫人の足音が響き、夫人がぶつくさ文句を言いながらドアの鍵をあけ、えっと驚く声が聞こえた。
エレインがもつれた髪をほどいていると、ほどなく家主が封筒を手に威勢よく入ってきた。封筒の表には美しい手蹟でジェイコブの名前が書かれていた。
「誰かから手紙ですよ。こんな天気なのに! 届けに来た人をしっかり見ようとしたんだけど、すぐ霧のなかに消えてしまって」
ジェイコブは封を開けた。
「誰からだった?」エレインが訊いた。
ジェイコブは手紙を読んで、ダウド夫人に眼を上げた。
「署名がありません」
「匿名なの!」家主はがぜん興味を示した。「嫌がらせの手紙でなきゃいいけど」
「いや、それはちがいます……」
「でも顔が赤いし、困ってるように見えますよ」ダウド夫人の青い眼が興奮で輝いた。「どうかやきもきさせないで! なんて書いてあるの?」
ジェイコブは内心舌打ちしながら、どうしてこの家主と娘に自分の職業を話してしまったのだろうと思った。だがしかたない。彼は咳払いをした。
「“サウス・オードリー・ストリート一九九番地でスクープを提供する。九時ちょうど”」
がっしりした体型で鼻の折れた若い警官が、煉瓦の壁よろしく舗道の行く手をふさいでいた。シャベルのような手を上げて、「すみませんが、ここから先には行けません」と言った。
ジェイコブは自転車からおりた。道は封鎖されていて、霧の向こうに警察車三台と救急車が見えた。並ぶ邸宅の一軒のドアが開いており、制服と私服の警官がせわしなく出入りしていた。近所の家の窓には明かりがついている。なんの騒ぎだろうと人々がカーテンをずらして外をのぞいていた。
「ぼくがわからないか、スタン? 霧は濃いが、ぼくの不細工な顔はまさか忘れてないだろう?」
「フリンティ?」警官の声に驚きが表われた。「いったいどうしてこんなに早く嗅ぎつけた?」
「嗅ぎつけたって、何を?」
「またいつもの悲しい子犬の顔か。やめとけ。そのおとぼけはレディには効くかもしれないが、おれには効果なしだ、とくに勤務中はな。新進の犯罪報道記者がこういう事件にたまたま出くわすなんてことはない」
「こういう事件とは?」
スタンリー・サーロウ刑事は眉根を寄せた。「本当に知らないと言うつもりか?」
ジェイコブは刑事のカリフラワーのような耳に顔を寄せた。「正直に言う。ここで何か起きてるという情報は得たんだが、それがなんなのかはまったく知らない」
「誰がそんな情報を? おい、フリンティ、言えよ。チャドウィック警視に内通者を知らせれば、おれの覚えがめでたくなる。いつも機嫌をとっとかないとな」
「悪いが言えない。言いたくても黙っていないと。記者が情報源を明かせないのはわかってるだろう。いずれにしろ、匿名だった」
サーロウはしかめ面をした。「そんなことをおれに信じろと?」
「なぜ信じられない? 真実だよ」
「ならおれの名前はラムゼイ・マクドナルド(当時の労働党党首でイギリス首相)だ」
気分を害したジェイコブは外套のポケットに手を突っこみ、見ろとばかりに手紙を取り出した。サーロウは一歩近づいて、街灯の下でしわくちゃの便箋をのぞきこんだ。
「ほらな?」ジェイコブは言った。「これで誰に送りこまれたと訊かれても、見当もつかない」
「きれいな字だ。男じゃないな」ぶっきらぼうな態度がどことなく尊大な感じに変わった。「おまえの愛人のひとりじゃないか、フリンティ? じつのところ、誰だってかまわない。この件の関係者を捜してるわけでもないしな」
沈黙が流れた。家からふたりの救急隊員が担架を運び出してきた。上にのった人には頭から足先までシーツがかかっている。
ジェイコブは息を呑んだ。「死んだのか?」
「まちがいなく」サーロウは声を落とした。「いいか、ここだけの話だぞ。あれはこの家の住人だ。パードウという」
「殺人? 事故? それとも自殺?」ジェイコブはためらった。「関係者を捜してないってことは、自殺だろうな」
「ご名答」サーロウは親指を家のほうに振った。「なかに警部がいるから、仕事が終わったときにひと言、話を聞くといい」
「誰も手を貸さなかったのは確かなのか?」
「確かに決まってる。書斎に鍵をかけて閉じこもり、やたらと長い遺書を書いたあとで、自分に銃を向けて撃ったんだから。おかげで警察は大助かりだ」
「どういう意味だ?」
「自白書を残したのさ。コヴェント・ガーデンで例の女性を殺したのは自分だって」
レイチェルにマフラーを巻きつけられたときと同じように、ジェイコブの喉が締めつけられた。「彼は何者なんだ? 精神錯乱かもしれないぞ。どうして真実を語っているとわかる?」
サーロウは笑った。「まちがえようがないさ、フリンティ、名誉にかけて。おれの言うことが信じられないなら、上官から直接話を聞けよ。彼が話す気になればだが」
「もちろん」ジェイコブは小声で言った。
「ブン屋の言う〝決定的な〟証拠があるのさ。われわれが密室のドアを打ち破ったときに、それがまっすぐこっちを見てた」
「それって?」
「木の箱に入った気の毒な女性の首だよ」
3
「満足ですか?」トルーマン夫人が訊いた。
レイチェル・サヴァナクは肘掛け椅子から顔を上げ、クラリオン紙の最新版を脇に置いた。ジェイコブ・フリントのめざましいスクープ記事を読んでいたのだ。夜勤の法務担当が一文おきに〝と考えられる〟や〝と推定される〟を振りまいているが、博愛主義者と評される著名な銀行家が殺人を告白して自殺したことの衝撃は、どんな但し書きがつこうと弱まることはなかった。若い記者は特ダネをつかんだのだ。
「満足?」レイチェルは皮肉な笑みを浮かべた。「まだ始めたばかりよ」
家政婦は首を振った。「昨夜は何もかもうまくいきました。パードウの使用人が予想外に帰ってくることはなかったし、手荷物預かり所の職員も袖の下を受け取って、窓口を閉めてくれた。パードウは、みずから命を絶たなければ、女性の頭部を戦利品みたいに持っているところをトルーマンが撮った写真が出まわって破滅すると思いつめたんでしょう。いつもこんな幸運に恵まれるとはかぎりませんよ」
「幸運?」レイチェルは新聞記事を指差した。「わたしたちは幸運をこの手で作り出したの。手なずけた記者がわたしたちの代わりに仕事をしてくれた。この最後の段落を読んだ?」
トルーマン夫人はレイチェルの肩越しに首を伸ばして、記事を読み上げた。
「“故人は慈善事業への援助を惜しまなかったことで広く知られる。彼の個人資産の源は、みずからの名を冠した家族経営の銀行だった。長年、かぎられた一流顧客向けの銀行業を営んできたが、その顧客リストには貴族、政治家、そして故サヴァナク判事のような著名な公人が含まれる”」
トルーマン夫人はそこでちょっと考えた。「フリントはどうやって判事とパードウのつながりを探り出したんでしょうね」
「宿題をやる人だから」
「気に入りませんね。判事の名前を出す必要はなかったのに」
「関係ないことで字数を満たしたように見せかけて、じつは手がかりなのよ」レイチェルは暖炉でめらめらと燃える炎を見つめながら言った。「ここまで推論したぞというメッセージを、わたしに送ってるの。パードウの家に彼を送りこむ手紙を書いたのはわたしだろうって」
「あの記者を焚きつけるべきじゃありませんでしたよ」
家政婦は腕組みをして暖炉のまえに毅然と立っていた。三十代で髪は灰色になり、心労で額には深いしわが刻まれていたが、しっかりした体格と角張った顎は、地震が来てもびくともしないという印象を与えた。
レイチェルはあくびをした。「この件はおしまい」
広大な居間からは広場を見おろすことができた。中央の庭園に林立する樫と楡の尖った枝にうっすらと日が射し、昨夜の霧は噓のように消えていた。室内の家具はどれも繊細でたおやかなカーブを描き、異国を思わせる木目に象牙やシャークスキンの装飾が映えた。暖炉の両横のアルコーブは本棚で、本がぎっしり詰まっている。反対側の壁には、暗く不吉な印象派の絵がかかっていた。トルーマン夫人は咳払いをして、ハロルド・ギルマンが描いた、乱れたベッドに横たわる女性の裸体像を不満げにひと睨みした。
「トマス・ベッツよりしつこくつきまとってきたらどうするんです? ジュリエット・ブレンターノのことを知られでもしたら……」
「それはない」レイチェルの声は無感情で有無を言わさぬ調子だった。「彼女はもういない。忘れ去られた」
「きっとあなたの手紙をスコットランド・ヤードの友だちに見せますよ」
「もちろんよ。でなきゃ、サウス・オードリー・ストリートに九時にいた理由を説明できないでしょう?」
「困ってないように聞こえますけど」
「むしろすごくうれしいの、リナカーとパードウが死んだから。スコットランド・ヤードには、勝手にわたしのことを想像させておけばいい」
「次は誰かしら」家政婦は火かき棒を取った。「ジェイコブ・フリントでしょうね、わたしに言わせれば。愚かにもパードウと同じ記事で判事の名前を出すようなまねをしたから。自分の首に輪縄をかけてもおかしくない」
「彼は火遊びが好きなの。それを言えば、わたしもそう」
年配の女性は燃える石炭を火かき棒で突いた。「いつかあなたも火傷しますよ」
レイチェルの眼は、クラリオン紙のおどろおどろしい見出しにちらっと戻った。“「首なし死体」の殺人鬼、銃で死亡。富豪の慈善家が自殺か”。
「危険があるからこそ」彼女は静かに言った。「人生は生きるに値する」
「悪くない」ウォルター・ゴマーソルが言った。
クラリオンの編集長の口から出ることばとしては、手放しの称賛に等しかった。祖先の出身地であるペナイン山脈のようにごつごつして頑固そうなゴマーソルの顔からは何も読み取れなかったが、ジェイコブは年長者のうなり声からかすかな喜びを感じ取った。編集長は競争紙を出し抜くのが何よりも好きなのだ。
「ありがとうございます」
ゴマーソルは椅子に親指を振った。「まあ腰かけたまえ」
ジェイコブは主人の指示を待つ子犬のように、おとなしく坐った。ゴマーソルは荒々しい一本気のランカスター出身者だが、古来、赤い薔薇(ランカシャー州の紋章)と白い薔薇(ヨーク州の紋章)の対立があるにもかかわらず、トム・ベッツが事故で危篤になったあと、リーズ出身のこの若者に代理を務めさせたのだった。グレンジ・オーバー・サンズ出身のベッツは、かつてジェイコブに、編集長はロンドンの成り上がりより北部人に時間を割くとこぼしていた。
「ひとつ質問」ゴマーソルは自分の左の耳たぶを引っ張った。彼の耳は異様に大きく、ジャーナリストとしてこれほど偉大な資産はないとよく言っている。「どうしていち早く犯行現場に着くことができた?」
ジェイコブはしばしためらって答えた。「情報を入手したんです」
彼の知る口の堅い警官はみな好んでこう言う。はぐらかしたことをゴマーソルが恨まず、むしろとっさの機知を評価してくれることを祈った。
編集長は腕を組んだ。ジェイコブは息を詰めた。もしかすると生意気な答えだったかもしれない。
「いいだろう。直接答えられないようだから、別の質問をする。なぜサヴァナク判事の名を出した?」
ジェイコブは訊かれるだろうと思って答えを用意していた。「判事は去年亡くなりました。パードウのいま生きている友人や顧客の名前をあげたら大騒ぎになります。殺人を自白した人とのつながりを指摘されて喜ぶ人は、上流階級にはひとりもいませんから」
ゴマーソルは渋い顔をした。「わかった。パードウはなぜあんなことをした?」
「事件を担当する警部と話しました。自白書は見せてもらえませんでしたが、警察は動機を……その、性的なものと考えているようです。パードウは狂気に駆られて被害者を殺し、頭部を切断したものの、その戦利品を始末する段になってパニックに陥った」
「被害者は看護師で品行方正だったと考えられる。加害者も銀行家で、人格に一点の染みもなかった──まあ、そういう形容矛盾をよしとすればだが。余暇とちょっとした財産を〝善行〟のために使っていた。知るかぎり彼女に性的不品行の前歴はなく、彼に暴行の前科もない」ゴマーソルは首を振った。「筋が通らんな」
「まったくおっしゃるとおりです」お世辞は記者の武器庫に欠かせない武器である、とトム・ベッツがたびたび言っていた。新聞社の編集長ですら甘いことばの愛撫に屈するのだろうか。「オークス警部も困惑しているようでした」
「あの若いオークスは切れ者だな。ヤードのトップにいるお飾りの年寄りなんかとちがって」ゴマーソルは口をすぼめて考えた。「もしパードウが無実で、これが仕組まれた事件だったとしたら?」
ジェイコブは眼をぱちくりさせた。「密室で自分を撃ったんですよ」
「何事も額面どおりに受け取ってはならんものさ」
戦術的撤退の頃合いだった。「記事の続きを書こうと思っています。スコットランド・ヤードに電話して、オークス警部と面会の予約をとりました。死んだ女性の家族と、パードウの知り合いからも話を聞きたい」
ウォルター・ゴマーソルが持ち上げた眉毛は、背中を丸く曲げた黒いもじゃもじゃの毛虫に似ていた。「それできみもほかのいたずらをしなくてすむわけだ」
「もちろん編集長の許可があればです。ウィットネス紙より一歩、ヘラルド紙より二歩先んじたいので。そう思われませんか?」
「なら、どんどん進めたまえ。だが用心してな」
「真相がわかったらお知らせします」ジェイコブは言った。「パードウも死んだ判事と同じくらい無害です。どちらも名誉毀損の訴訟なんて起こせませんから」
「自信過剰は禁物だ」ゴマーソルは言った。「私が考えていたのは、パードウのことでも、頭部を失った不幸な女性のことでもない。トム・ベッツの身に起きたことだ」
*
毎日、レイチェル・サヴァナクは運動のために、地下のジムと最上階のプールで一時間を費やしていた。木製のトレッドミルで汗を流していたとき、足音が聞こえた。うしろを振り返ると、メイドのマーサが階段をおりてきていた。
「お客さん?」レイチェルは荒い息をつきながら訊いた。
マーサはうなずいた。身ぶりで用が足りるときには、めったに話さない。体型は堅苦しい灰色のお仕着せに隠れてわからないし、豊かな栗色の髪も不恰好な帽子の下に押しこめられている。彼女の右の横顔を見た人はみな、その美しさに心を奪われるが、人目を避けるのが本人の習慣だった。左頬の醜い窪みを初めて見た人の顔に浮かぶ嫌悪の表情が怖くてたまらないからだ。
レイチェルはトレッドミルを踏む足を止めた。「ゲイブリエル・ハナウェイ?」
勢いよくうなずいた。
「ご老人をすぐにお通しして」レイチェルは額をふいた。「わたしを待つあいだ、ウイスキーを出してあげて。気持ちを落ち着かせるのに強い飲み物が必要だろうから」
狭苦しく騒々しい若手記者の部屋に戻るジェイコブの頭のなかで、ウォルター・ゴマーソルの別れ際のことばが響いていた。編集長は、不満の多い配偶者にヒヨス(有毒植物)を調合する薬剤師の慎重さでことばを選んでいた。彼はベッツが意図的な攻撃の対象になったと思っているのか?
ベッツの犯罪記者歴は二十五年前にさかのぼる。はるか昔、ホーリー・ハーヴェイ・クリッペン(妻を毒殺した罪で一九一〇年に絞首刑にされた)とセドン夫妻(フレデリック・ヘンリー・セドンは下宿人の女性を毒殺した罪で一九一二年に絞首刑。妻も起訴されたが無罪放免だった)の裁判を傍聴し、何人もの花嫁を浴槽で溺死させたジョージ・ジョゼフ・スミスが有罪宣告を受けたときにも、かぶりつきの席で見ていた(スミスは一九一五年に絞首刑にされた)。ベッツは幼いころにポリオに罹り、片脚が麻痺していたので軍役にはつけなかった。ポリオと闘った気丈さが、どうしても権威にしたがえない反骨精神につながった。好条件の職を得ても、上司を我慢の限界まで追いやったあと、馘になるまえに辞職することが相次いだ。ほかの記者が何も感じないところからたびたびスクープを嗅ぎつけたが、新聞事業家のビーヴァーブルック男爵も、新聞王ノースクリフ子爵も彼の態度を肚にすえかね、ヘラルド紙の財布の紐を握っている労働組合の大物たちも、綱領を守ろうとしないベッツに愛想を尽かした。なんとしても発行部数を伸ばしたいゴマーソルだけが、フリート街で彼に最後のチャンスを与えたのだった。ふたりは一度ならず衝突しかけたものの、ベッツは解雇されないだけの働きを見せていた。
寡黙で短気なベッツは人に嫌われることを怖れなかったが、ジェイコブには粘り強く取材することの大切さを教えた。ヤードの情報源から、謎の女性レイチェル・サヴァナクがなんらかの方法でリナカーをコーラスガール殺害事件の犯人と特定したことを聞きつけると、骨をくわえた犬のように離そうとしなかった。全貌を解明してクラリオンの読者に示そうと張りきっていたところで、ペルメルのはずれの脇道で車にはねられ、道路沿いに放置されたのだ。
その事故が起きたのは霧が濃い夜で、ウェールズ人の若い街路清掃人が目撃した。救急車と警察が現場に到着すると、清掃人は、ベッツがつまずいて、通りに入ってきた車の車輪に巻きこまれ、地面に打ち倒されるのを見たと言った。車は視界が悪いのでゆっくり運転していたが、停まることはできなかった。ひどい霧だから、人ではなくちょっとした障害物にぶつかったと思ったのかもしれないと清掃人は言った。車はフォードだったかもしれないが、はねられた男に駆け寄ったので、ナンバープレートは見なかった。最初、男は死んだと思ったらしい。ベッツの両肘の骨は折れ、頭が割れて、大量の血が流れていた。即死ではなかったが体内の損傷がひどく、予後は思わしくなかった。
ジェイコブはその街路清掃人に取材しなければならなかった。彼の頭のなかで、そのような清掃の仕事は、貧乏人が都市の汚れた通りを掃除して裕福な通行人から施しを受けていたディケンズ時代の産物だったが、まだその手のことに精を出す人間もいるにはいた。清掃人は真実を語っているように思えた。ベッツは脚が悪かったので歩きながらバランスを崩すことがあり、暗闇と霧のなかで水たまりかすべりやすい泥を踏んで、走る車の車輪のまえに倒れることは充分考えられた。だが、清掃人がもしまちがっていたら? あるいは、噓をついていたら?
「お知らせもせず押しかけて申しわけありません、お嬢さん」ゲイブリエル・ハナウェイが、しわがれたぜいぜい声で言った。「近所に所用で来ましたところ、ここにひとりで閉じこめられたあなたのことがふと頭に浮かび、良心が痛みまして。気が利かないことでした。ゴーントで長年世間から切り離されて暮らしたあなたがロンドンで幸せな生活を送られるように見守ると、亡き父上にあれほど約束したというのに」
レイチェルは微笑んだ。ゲイブリエル・ハナウェイに良心とは傑作だ。
「それはご親切に」彼女はつぶやいた。「ですが、わたしはひとり暮らしを愉しんでいます。必要なことはトルーマン夫妻とマーサが全部してくれますし」
ハナウェイは判事の親友で、個人的な法律顧問でもあった。ゴーント島を訪ねてくることはめったになかったが、レイチェルはそのまれな訪問で初めて、一張羅の黒いフロックコートを過去四十年にわたって着ていそうな、このしなびた小男に会ったのだった。その後の年月と肺気腫の無慈悲な進行は、彼の魅力を増す役には立っていなかった。黄色とも茶色ともつかない肌はなめし革のようで、レイチェルの記憶にあるかぎり最初からしわが寄っている。小さな黒い眼はきょろきょろと動いて、つねに逃げ道を──または法の抜け穴を──探しているかのようだ。その姿は彼女に邪悪な爬虫類を想起させた。砂漠の岩陰に身を隠し、獲物がいたら飛びかかろうと小さな鼻先で空中のにおいを嗅いでいる、鋭い歯のイグアナを。
「これほど若くて美しいレディが使用人といっしょにいるだけではもったいない」不満を言い立てるように入れ歯がカチカチ鳴った。「あなたがこの街においでになってから今回一度しかお目にかかっていないのは、まったくもって私の落ち度ですが、忘れていたわけではないのです」
「ごめんなさい、わたしは救いようがないくらい人づき合いが悪いので。アクロスティック(詩や文の先頭か末尾の文字をつなげると、ある語句になることば遊び )を解いているか、トルケマダ(十五世紀スペインの異端審問官。書評家・パズル作家E・P・マザーズの筆名だった)の悪魔のようなクロスワードパズルと格闘しているときがいちばん幸せなんです。蓄音機で最新のレコードを聴きながら。とくに好きなのが現代のアメリカ音楽」レイチェルは無垢な笑みを浮かべた。「『メイキン・ウーピー』はお好き?」
ハナウェイはふんと鼻を鳴らした「ジャズ、ですかな? 何を指すのかよくわかりませんが。まったくのゴミでしょう、お嬢さん!」
レイチェルの眼がすっと細くなり、弁護士は一瞬たじろいだ。「いやとにかく……パズルゲームやレコード音楽は体の悪い人や弱った人には恰好の趣味ですが、あなたのようなかたがひとりでそういう寂しい時間をすごしているのはよろしくない。またこちらに招待していただけますか? 息子のヴィンセントとまいります。いっしょに食事でも?」
そこでハナウェイは間を置いたが、レイチェルは何も言わなかった。「ヴィンセントとあなたは馬が合うと思います。友情が別のものに発展するかもしれませんぞ。息子は快活な女性が大好きですから」
「なんてご親切な」
「慣れない街に越してきたばかりの裕福な若い女性は、素直な性格につけこもうとするいかさま師の餌食になりやすいのです。信頼できる友人の支援の手をしっかりつかんでおくに越したことはありません」
「ゴーントで自分の面倒を見ることは学びました」レイチェルは言った。「まったく軟弱というわけでもないんですよ」
イグアナの眼がきらりと光った。「どうか気を悪くなさらないで、お嬢さん。先を急ぎすぎたようです。まあ、こんなこともありますから、そろそろあなたの信頼できる顧問の役まわりをもっと若く健康な男にまかせたほうがいいように思います。ヴィンセントはロンドンでも指折りの事務弁護士で、その才能はすぐれた起草技術と訴訟時の集中力にとどまりません。彼の判断は非の打ちどころがない。安心してすべてをまかせられます」
「とても心強いご提案ね。ですが、いまのところ息子さんの賢明な判断に頼らなければならない火急の用件はありません。ご記憶でしょうが、判事の遺志にしたがって、わたしは二十五歳の誕生日に遺産の完全な管理権を得ましたので」
「まさしく!」ハナウェイは息をあえがせた。「父上が亡くなってまだまもないのに、あなたがパードウの銀行から資金を引きあげたと聞いて肝を冷やしたのです。あなたはあの島で過保護に育てられて……」
「そう思うの?」レイチェルは訊いた。
「ゴーントは子育てにふさわしい場所ではありません。この王国のどこよりも孤絶している」彼は人差し指を上げて爪を閃かせた。「いまは未曾有の経済危機です。わが国の政府が万が一にも金本位制を捨てたりしたら……いや、こう言えば充分でしょう。事前にあなたの意図をひと言相談してくださっていたら、目立たず利益率の高い財産の避難先をご提案できましたのに」
レイチェルは歯をむいた。「昨夜の出来事があったから、わたしの先見の明を祝福しに来られたのかと思ったわ」
イグアナの顔にしわが寄った。「いやまことに、お嬢さん! しかし、パードウの銀行はいまも最高の人々が経営しております。会長があんな……不幸な亡くなり方をしてもです。ヴィンセントと私はたまたまあそこの取締役でして、ほかの役員も同じくらい金融に精通しています。会長の死で銀行の経営が暗礁に乗り上げることはありますまい。パードウに投資している人々は選りすぐりの目利きですから、愚かな衝動に駆られてパニックを起こしたりはしません」
「だといいけど」
「もうひとつ残念だったのは、保有株式をすべて現金化なさったことです。率直な物言いをお許しいただきたい。若い女性は、いかに自信と独立心にあふれていようと、世知に長(た)けるまでに時間がかかるのですな」
「男性ならもっと信頼できるというわけ?」レイチェルはまたダージリンをひと口飲んだ。「毎朝新聞を読むと、また別の株式仲買人が青酸カリをのんだとか、ペントンヴィルに投獄されたという記事が載ってますけど」
「父上は確固たる信念をお持ちだった」ハナウェイはつぶやいた。「こういうしゃれたフランスの家具に投資するあなたの趣味について判事がなんと言われるか、あえて想像しようとは思いませんが。それとこの……芸術作品と称する品々に」
彼は黒と金色とピンクが派手に散ったシッカートの絵を睨みつけた。金縁の姿見に映った自分の体をうっとりと眺める官能的な高級娼婦の絵だった。
「市場を襲った大災害を考えると、彼もわたしのすぐれた投資の才覚に感心するんじゃないかしら。ルールマンの家具や画家たちの人間洞察から得られる喜びは、配当としては充分すぎるくらい」レイチェルはほっそりした手をシッカートの絵に振った。「クロード・リナカーは、あなたにカムデン・タウン・グループ(一九一〇年代に活動したポスト印象派の芸術家集団。シッカートのアトリエによく集まっていた)の美徳を売りこんだんじゃありませんでした?」
「美徳?」ハナウェイは咳払いをした。「私ならそうは言いませんね。あの若いリナカーは無責任でした。聞いたところでは、麻薬中毒だったとか」
「ローレンス・パードウも同じくらい……弱みがあったことがわかるかも」
ハナウェイはごくりと唾を飲んだ。「そんな、ありえない! ローレンス・パードウが殺人を犯して自殺したですと?」
「一時的に正気を完全に失ってしまったのかもしれない。われに返ったとき、犯した罪に対する恐怖に耐えられず、名誉ある解決法を選んだとか」
痰がからんだようなため息。「あまりにもぞっとする話です。とりわけ、あの不道徳なくず新聞のクラリオンに載った記事は。今朝起きたときに知らせを聞いて、最初に現場に着いたという男が書いた記事を読んだのです」
「そうなの?」
イグアナの眼が彼女を見すえた。「驚いたのは、あなたの亡き父上のお名前がいきなり出てきたことでした」
「判事は会った人全員に強い印象を残したから」
「その記者はあなたと同じ年代ですぞ」ハナウェイの声が引きつった。「判事に会っているわけがないし、法廷でも見ていません。記者がこういう態度では……みなが困る」
ハナウェイは大儀そうに立ち上がり、また咳をして唾を飛ばしそうになるのをこらえた。ハーレー街のサー・ユースタス・ライヴァースがこの人を診たら、ローレンス・パードウのときより明るい診断結果を出すだろうか、とレイチェルは思った。たぶん出さないだろう。ハナウェイは部屋のなかをぐるりと見まわし、遠い隅にあるマホガニーの机に眼をとめた。美しい彫刻がほどこされたその机には、チェス盤がはめこまれている。そこにそろそろと近づいて背を屈め、駒の配置をじっくりと眺めた。
「チェス・プロブレムを解くのも、わたしの孤独な暇つぶしなんです」レイチェルは言った。「あなたもなさるんでしょう? タヴァナーの有名なパズルはご存じよね。名作だと思いません? 麗しいまでに厳しくて」
老いた弁護士のしみだらけの顔が色を失った。
レイチェルはチェス盤を指差した。「次の手で〝ツークツワンク〟になる。黒は駒を動かさざるをえないけれど、何をしようと、いっそう危険な状態に追いこまれる」
偶然からか、ハナウェイのフロックコートが白のクイーンに当たって、駒が床に落ちた。
「どんなゲームをするにしろ、お嬢さん、ひとりでなさるのはまちがいです」
「街路清掃人の名前はシアーだ」ニュース編集者のジョージ・ポイザーがジェイコブに言った。なんでも記憶していることで有名なベテラン記者だ。同僚が命にもかかわる事故に遭ったという一報がクラリオンに入るやいなや、真っ先に現場に駆けつけた。
「彼に会ったんですか?」
「感謝の印に何シリングか渡したよ。ちゃんとした若者だが、彼がいなければトムは病院のベッドにもたどり着けなかったかもしれない」
「彼が言うには、でしょう」
ポイザーの渾名は〝ギョロ眼〟だった。巨大な角縁眼鏡の奥で飛び出した眼をいつもぱちくりさせている。太って頭は禿げており、その不恰好な外見から何かにつけジョークのネタにされるが、彼のギョロ眼はたいていのことを見逃さない。
「話をふくらませたと言うのか? ヒーローになりたいがために?」
「念のため訊いただけです」ジェイコブは波風を立てたくはなかった。「トムを訪ねてミドルセックスに行くつもりなので。命を救ってくれた若者について、トムもまちがいなく知りたいでしょう」
ポイザーは団子鼻にしわを寄せた。「あまり期待しないほうがいい。おととい見舞ってきたが、とても生き延びるとは思えないな」
「シアーのフルネームと住所はわかりますか?」
「ちょっと待ってくれよ」ポイザーはゲラ刷りがあふれている抽斗のなかを探り、ページの角が折られた手帳を掘り出した。「あった。整理整頓が大事、だろう? ヨーワース・シアー、そう、これだ。キルバーン、バラクラバ・ミューズ、二十九番」
三十分後には実情が明らかになっていた。ジェイコブが調べたところ、ヨーワース・シアーなる人物の痕跡はロンドンのどこにも見当たらなかった。バラクラバ・ミューズという場所も、キルバーンはおろか、ロンドンのどこにもない。街路清掃人として生計を立てている若者は、当人にしかわからない理由で当局と報道機関から身元を隠したのかもしれない。しかし、金をもらってトム・ベッツの事故について噓をついたのだとしたら?
ジェイコブの脳裡に、レイチェル・サヴァナクの冷ややかなことばがこだました。
”前途洋々たる将来がふいになったら、悔やんでも悔やみきれないでしょう、トマス・ベッツみたいに”
──本篇に続く
校了前の原稿を基に掲載しています。製品版と異なる点があることをご了承ください。
書誌情報
■タイトル:『処刑台広場の女』
■著訳者:マーティン・エドワーズ/加賀山卓朗訳
■発売日:2023年8月17日
■レーベル:ハヤカワ・ミステリ文庫
■本体価格:1200円(+税)
■ISBN:978-4-15-185651-8

