
【SFマガジン インタビュー】人間と呼べる者がいなくなったあとも、音楽は生み出されるか──電子音楽家OPNに聞く創作論とSF愛
Oneohtrix Point Never(ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー、以下OPN)こと、ダニエル・ロパティンは、現代最高峰の電子音楽家として知られる。機械と身体性の境界、記憶という不確かなものと向き合い続ける唯一無二の創造性を、一つの音楽ジャンルの枠に収めるのはもはや不可能であり、それは芸術の域に達している。そんなOPNの第十作目のアルバム『Again』のツアー初日公演が今年2月、東京で行われた。
チケットはソールドアウトとなり、観客の誰もの予想をはるかに超える人形劇形式の斬新なVJによって、伝説の夜を作り上げたOPN。果たして彼の創造性の背後には何があるのか──ライブ前日のOPNを直撃したインタビューから、一部を抜粋してお届けする。(2024年2月27日/於・都内某所)

Photo by Yukitaka Amemiya
■音楽とともに刻まれた記憶を再編するということ
── 今回のツアーについて教えてください。
OPN まったく新しいショーになるよ。フリーカ・テット(註:実験的な表現を得意とするデジタルアーティスト)とのコラボレーションをするんだ。彼と一緒にできるのは夢のよう。僕が何千年をかけても決して思いつかなかったであろうことを作り上げることができる天才なんだ。僕らはいいチームだし、みんながどう思うか楽しみだよ。

── アルバム『Again』について、ダニエルさんご自身では「スペキュレイティヴな自叙伝」と捉えられていますが、その概念について詳しく教えていただけますか?
OPN 『Again』の前に2つのアルバム『Garden of Delete』『Magic Oneohtrix Point Never』があって、今回はそれにつながる三部作なんだ。三作は僕の人生における音楽の記憶──というテーマでつながっていて、『Garden of Delete』はティーネイジャーの時、思春期の頃の記憶。『Magic Oneohtrix Point Never』は、ラジオを介して音楽と出会った幼少期の記憶をテーマにしている。ラジオを、音楽的欲求が流れ出てくる魔法の送信機のようなものとしてイメージしながら作ったんだ。
それで今回の『Again』では僕の20代前半、青年期の音楽の記憶について、僕なりに向き合ってみた。僕なりの方法というのは「記憶を信頼しない」という姿勢、方法論のこと。なぜなら、まず第一に僕は記憶力がよくない方だし、それに記憶って本来スペキュレイティヴなものだから。
記憶には詩的な要素やフィクションが含まれていて、さまざまな解釈の仕方がありえる。だからスペキュレイティヴな自伝というのは、僕という人間がどういう人だったか、そして、どういう生き方がありえたかという可能性についても描いている。当時興味を持っていたいろいろなジャンルの音楽を思い出すことで、あったかもしれない僕自身の音楽性についても見つめたんだ。20代前半は本格的に録音を始めた時期で、膨大な量の音楽を聞きまくっていたからね。とにかくこの三部作は、僕が雷に打たれたように音楽的衝撃を受けた、人生の三つの重要なタイミングを描いている。そして今回の『Again』で完結するんだ。

マティース・ファルドバッケンの作品を使用
スピーカーがベルトで縛り上げられている
■機械と身体性、リアルとフェイクの境界
── 一貫して音源では人工的な音色を取りあつかっている一方で、過去のライブを拝見した際には非常にグルーヴィなもので驚いた記憶があります。人工的なものと身体性の関係について、ライブという表現の場ではどう考えていますか?
OPN 僕にはロックスターみたいなことはできなくて、コンピューターが仕事相手。10年間ずっと挑戦してきたのは、機械の直線的で冷たい要素を取り出して、そこから温かみのあるものを作っていけるか、要はいかに"人間的"にできるかっていうことだった。フランケンシュタインみたいに、死んでいたはずのものを生き返らせようってね。でも、今回のツアーでコラボしているフリーカ・テットに出会ってから、逆方向の可能性についても考えるようになったんだ。
【今回のツアーで使用されている人形劇セットの実態。フリーカ氏のインスタグラムより】
つまり、あえて肉体を使って偽を真似るっていうことをやってみたいんだ。例えば、「A Barely Lit Path」という曲のミュージックビデオ(下記YouTube参照)は、僕とフリーカ・テットが実際のセットで、本物の車と、ゴム素材のCPR人形(心肺蘇生の訓練用の人形)を使って作った映像だけど、多くの人がCG映像だと勘違いしている。僕が面白いなと思うのは、最近はみんな「これは偽物だ」とすぐに判断したがっていること。だから、リアルとされている側が偽物を真似ようとしたとき何が起こるかにものすごく興味があるし、難易度の高いことだとも思っている。
■図書館が遊び場だった幼少期とSF趣味
── アルバムのお話の時に出ていた「どんな生き方がありえたか」という問いから派生しますが、ミュージシャンになっていなかったら、何をしていたと思いますか?
OPN 一番可能性が高いのはアーキビスト(註:保存価値のある情報を収集して管理する専門家)か、図書館司書だね。おそらくどちらかになっていたんじゃないかと思う。いまでも、そういう仕事をしているような気分になることもあるしね。どこかの公立図書館に勤めているか、さもなければライターになって、文学的でジャーナリスティックな文章を書いていた可能性もある。でも図書館の司書になっていた可能性が一番高いかな。
──とても興味深いです。「収集」がキーワードですね。
OPN 僕はScour(註:なにかを探すため、丁寧に細やかに調査することを指す英単語)するのが好きだ。すべての底なし沼の中に入ってみるみたいな感覚のことだよ。そこで見つけた大量の情報を使って一枚の絵を作り上げる、というのが僕の音楽制作のイメージ。音楽専門の学校に通っていたわけじゃないから僕にとって音楽は理論的なものではなく、むしろ感情的で、概念的なもの。音楽を"音楽的ではない"方法でとらえながら、僕なりの絵を作り上げているんだ。

── 図書館司書になる世界線もあったというお話も踏まえ、ぜひお好きなSF小説についても教えてください。
OPN フィリップ・K・ディック『ヴァリス』(ハヤカワ文庫SF)。もう多すぎて答えられないよ。子供の頃の話でいうと僕はヤング・アダルトのSF小説で育ったんだ。『エンダーのゲーム』(オースン・スコット・カード、ハヤカワ文庫SF)が大好きだった。若い人が読むべき物語だと思うよ。『銀河ヒッチハイク・ガイド』(ダグラス・アダムス、河出文庫)とか。
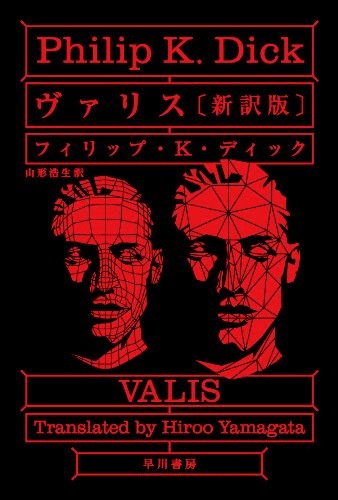
友人グロリアの自殺をきっかけにして、作家ホースラヴァー・ファットの日常は狂い始める。麻薬におぼれ、孤独に落ち込むファットは、ピンク色の光線を脳内に照射され、ある重要な情報を知った。それを神の啓示と捉えた彼は、日誌に記録し友人らと神学談義に耽るようになる。さらに自らの妄想と一致する謎めいた映画『ヴァリス』に出会ったファットは……。ディック自身の神秘体験をもとに書かれた最大の問題作!

容赦なく人々を殺戮し、地球人の呼びかけにまったく答えようとしない昆虫型異星人バガー。地球はバガーの二度にわたる侵攻をかろうじて撃退した。その第三次攻撃に備え、優秀な艦隊指揮官を育成すべく、バトル・スクールは設立された。そこで、コンピュータ・ゲームから無重力訓練エリアでの模擬戦闘まで、あらゆる訓練で最高の成績をおさめた天才少年エンダーの成長を描いた、ヒューゴー賞/ネビュラ賞受賞作!

銀河バイパス建設のため、ある日突然地球が消滅。地球最後の生き残りであるアーサーは、宇宙人フォードと銀河でヒッチハイクするはめに。抱腹絶倒SFコメディ「銀河ヒッチハイク・ガイド」シリーズ第一弾!
── それはご両親から紹介されたものだったのでしょうか?
OPN いや、僕のベビーシッターは図書館司書だったんだ。学校の後に車で迎えに来てもらって図書館で降ろされて。仕方ないから図書館で一番面白そうな棚を探すしかないでしょ?(笑)。そこでSF小説に出会ったんだ。子供の頃は多くの時間を図書館で過ごしていたんだよ。
── 映画についてもぜひ。収録曲の「Gray Subviolet」を聴いてスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』のモノリスのシーンを連想しましたが、お好きなSF映画はありますか?
OPN あの映画は大好きだし、それは僕にとって最高峰の誉め言葉だよ。好きなSF映画ね……考えないとな。タルコフスキーの『惑星ソラリス』、リドリー・スコットの『エイリアン』『ブレードランナー』あたりが挙げられるけど、一番好きなのはジェームズ・キャメロンの『ターミネーター2』。ブラッド・フィーデルのサウンドトラックも本当に素晴らしい。挙げたなかの映画のサントラはすべて傑作だし、無意識のうちに僕の音楽にも影響を及ぼしているはず。
── SF映画に惹かれる部分はどのあたりでしょうか?
OPN 宇宙飛行士がたった一人で宇宙に放り出される映画が好き。デヴィッド・ボウイの息子(註:ダンカン・ジョーンズ)が作った『月に囚われた男』という映画もよかったな。あれはもっと注目されるべきだと思う。僕は宇宙に取り残されるというコンセプトが大好きなんだ。
*****
続きは4/25発売のSFマガジン2024年6月号にて!

【OPNインタビュークレジット】
聞き手・構成=茅野らら(早川書房編集部)
取材協力=樋口恭介
通訳協力=染谷和美
写真提供=Beatink

