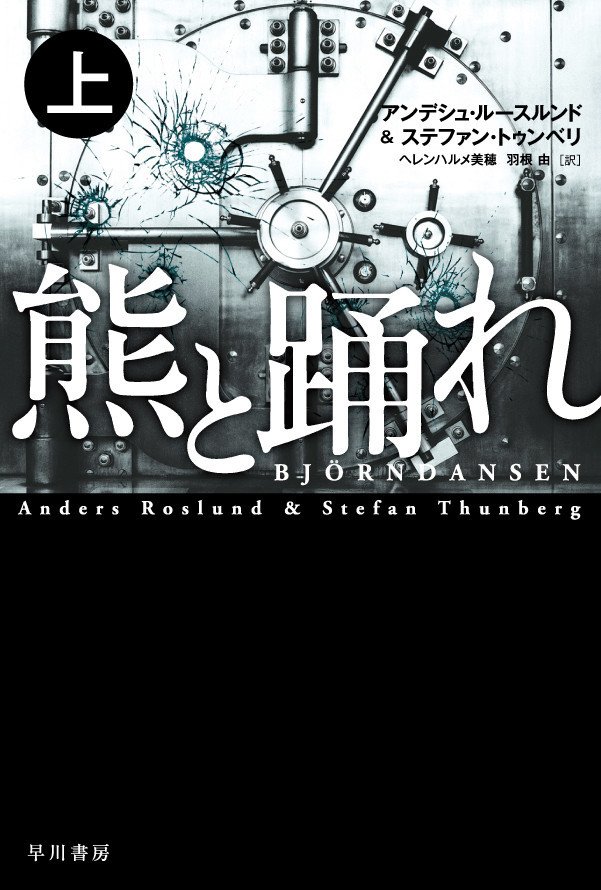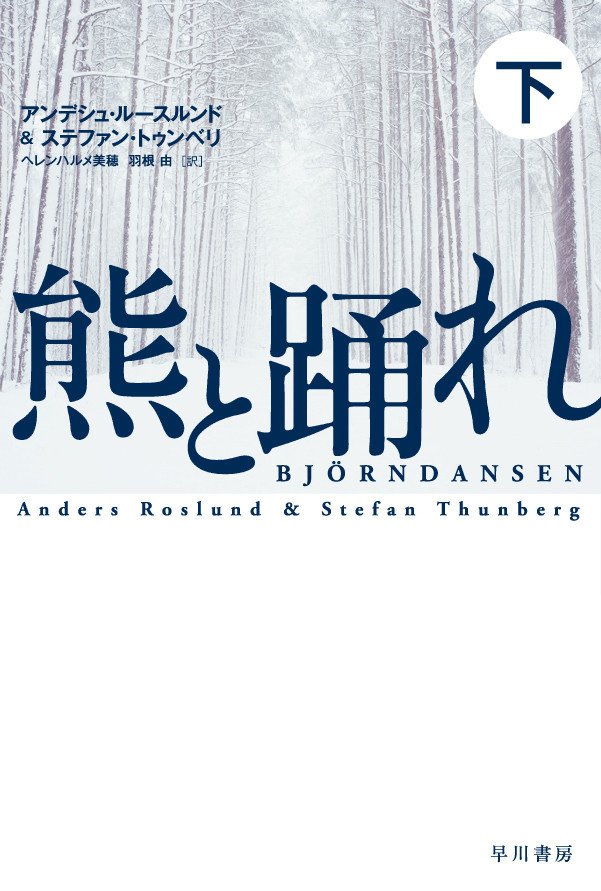人気作家・深緑野分の解説を特別公開! 大ヒット中の北欧ミステリ『熊と踊れ』
解説
作家 深緑野分
私たちは暴力と共に生きている。人類がこの原始的な道具を忘れたことはなく、程度の差はあれ、誰もがその被害者で、加害者だ。殴打や殺人、戦争など見かけの激しい行為だけでなく、威嚇や罵声、虐めなど。そのすべてが悪いものだとわかっていながら、冷めた目で受け入れてしまう。
だが、暴力と真正面から対峙し、小説を通じて問いかけ続けている作家がいる。それが本書の著者のひとり、アンデシュ・ルースルンドだ。ステファン・トゥンベリと共に執筆した『熊と踊れ』の主人公は、暴力そのものである。
物語の冒頭、レオ、フェリックス、ヴィンセントの三兄弟に、幼なじみのヤスペルを加えた四人組が、ストックホルム防衛管区の動員用武器庫に侵入する。二個中隊分の装備がまかなえるほどの銃や爆薬を入手すると、現金輸送車や銀行を襲いはじめた。男たちは二十代から十代後半とまだ若いが、リーダーである長兄レオが立てる緻密な計画と冷静な指揮により、強奪は順調に進む。事件を捜査し彼らを追う警部ヨンも優秀だが、手を替え品を替える手口で翻弄し、尻尾を摑ませない。
これだけでも充分に面白い犯罪小説になる。カリスマ的リーダーのレオ、一度決めたら譲らないフェリックス、まだ無邪気さが残るヴィンセント、軍隊から抜けた後、尊敬するレオに従い仲間になるヤスペル。強盗や警察側だけでなく犯行現場に居合わせた被害者も含め、登場人物は全員、複雑で多面的な個性を持ち、読者の共感を誘う。周到に準備を整える場面や、突入し犯行に及ぶ一部始終などの、微に入り細を穿つ描写にも舌を巻いた。読者に四人の息づかいを感じさせ、自分も共犯者のひとりとしてこれから強盗に行くのだと錯覚させるほど、筆致は巧みだ。
しかし本作の核心は別にある。それは、まだ幼かった頃のレオと弟たちに〝熊〟との踊り方を教えた人物、すなわち父親の存在だ。
そばに立つと実際よりも大きく威圧的に見える父、イヴァン。マチズモの権化のような男で、家族だけが味方、それ以外はすべて敵であるという信念に凝り固まっている。近所の悪ガキに殴られたレオに暴力の使い方を教え、家族を裏切ることの罪深さを説く。だが、ある出来事をきっかけにイヴァンは妻を激しく暴行してしまう。
レオと弟たちは母親の味方で、支配的で粗暴な父親を憎み、拒絶している。レオは十代の終わりまで父と共に働いた後、決別して離れた土地に住まい、自分の工務店を開く。そして弟たちの面倒をみつつ、強盗を計画する。
精神的にも安定し、賢く冷静な男に成長したレオは、コントロールさえできれば、憎い父から学んだ暴力も、非常に有効な道具になると考えた。暴力をうまく使いこなせたら、人の命を奪わずに、前代未聞の大規模な略奪も可能なはずだ。おれはあいつとは違う。自分を慕うふたりの弟も幼なじみのヤスペルも、父のようにはさせない。そしておれは仲間を裏切らない──その思いは何度となくレオの心に去来し、兄として、リーダーとして、コントロールしようとする。
だが暴力や人間を制御することなど不可能だ。他者を屈服させる快感と昂揚の虜になるのは容易く、自らの大きさを勘違いする。回数を重ねるごとに猜疑心が強くなり、いつか誰かを殺してしまうかもしれないという恐怖に汗ばむ。読者は登場人物に共感し、苛立ち、ある場面では衝動的に「こんなやつ殴ってしまえ」という気になって、はっとする。安全圏で読書していたはずなのに、いつの間にか理性を疑い、暴力を必要悪として肯定してしまうのだ。
本作品の筋立て自体はシンプルだが、底はどこまでも深い。暴力に取り憑かれた物語は、今にも炸裂しそうな壊れた爆弾を抱えたまま、光が差さない断崖絶壁の淵を疾駆する。
ではここで、ふたりの著者について触れておきたいと思う。
アンデシュ・ルースルンドは1961年生まれ。服役経験のあるベリエ・ヘルストレムと組み、エーヴェルト・グレーンス警部を主人公とするシリーズ作を2004年から発表している。ふたりが出会った経緯はヘレンハルメ美穂氏の訳者あとがきを一読頂きたい。
日本では2007年に『制裁』(ランダムハウス講談社)、09年『ボックス21』(同)、一一年『死刑囚』(RHブックス・プラス)が刊行され、注目を集める。08年に『ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女』(早川書房)が発売され人気を博して以降、日本では多数の北欧ミステリが紹介され、ルースルンド&ヘルストレム作品もその波に乗るかと思われるが、版元の武田ランダムハウスジャパンが倒産したことにより、一時邦訳の継続が危ぶまれる。しかし2013年KADOKAWAから、第五作目にあたる『三秒間の死角』(角川文庫)が出版された。同作は日本国内の読者の支持を集め、翻訳ミステリー読者賞を獲得した。邦訳を待ち望む根強いファンがいる作家だ。また『三秒間の死角』は英国推理作家協会CWAの、非英語圏の優秀作に与えられるインターナショナル・ダガーを受賞した。
ルースルンド&ヘルストレムによるグレーンス警部シリーズの第一作『制裁』は、小児性愛者による凄惨な幼女殺人事件をきっかけに、かつて性的虐待を受けた児童と被害者遺族の、怒りと復讐の是非が描かれた。人身売買がテーマの『ボックス21』、死刑制度や司法機構の問題を扱った『死刑囚』共々、綿密な調査と取材に基づいた骨太の社会派小説である『三秒間の死角』は、刑務所内に極秘で潜入した捜査官の絶体絶命の窮地を、エンターテインメント色濃く仕上げた。いずれも、北欧ミステリの十八番である警察捜査小説の形をとっているものの、既存作品の主流とは一線を画す異色作ばかりだ。
特筆すべきは第二作『ボックス21』だろう。リトアニアから連れて来られ、意に沿わない形で男たちに肉体を蹂躙される、未成年の少女たちの叫び。バルト三国からの人身売買というスウェーデンの根深い問題を取り上げた本作は、ファンの間でも特に最悪な話として知られている。捜査小説の約束ごとを覆すような展開は、読了後、吐き気を催すほどだ。これが現実だと思うと一層気が滅入るのだが、著者たちが状況を深く理解している証左でもある。あとがきで「女性が服を脱ぐよう強いられていることを知りながら勃起する連中を、われわれは男として恥ずかしいと思う」と断言し、問題に対する激しい怒りを表明した。彼らは決して「無知な女が悪い」などと濁さない。『制裁』でも被害者の幼女について「挑発的な服装をしているのがいた」と述べた参審員に対し、「人間どうしの出会いの責任は双方にあるとか、もっともらしいことをしれっと言いやがって」と、主要人物がはらわたを煮えくりかえらせる描写を入れた。著者たちの聡明な見識に敬服する。
一時中断していたシリーズだが、『三秒間の死角』の続編にあたるTre minuter が、2016年6月に刊行されたそうだ。いまだ未訳のシリーズ四作目Flickan under gantan と共に、日本での翻訳出版を鶴首して待ちたい。
ルースルンドは10年以上にわたり、暴力や犯罪、社会問題を扱った小説を書き続けてきた。新たにステファン・トゥンベリと組んだ本作、『熊と踊れ』では、ドメスティックな問題を掘り下げ、疑問を提示している。今回もCWAのインターナショナル・ダガーのロング・リスト入りを果たした(英語版タイトルはThe Father で、ペンネームをAnton Svesson としたのは、新しいシリーズをはじめるにあたり、新たな名義を本人たちがつけたらしい)。傑作と名高い『三秒間の死角』にも比肩すると、私は断言する。
もうひとりの著者ステファン・トゥンベリは1968年生まれの脚本家で、去る2015年に惜しくも亡くなったヘニング・マンケル原作クルト・ヴァランダー・シリーズの、数多く作られたドラマのひとつに関わっている。ただし日本でも放送されたケネス・ブラナー主演のBBC作品ではなく、俳優クリスター・ヘンリクソンがヴァランダーを演じるスウェーデン版Wallander(2005から2013年まで断続的に三シーズン放映)で、六エピソード分の脚本を担当した。なおこのドラマは基本的にオリジナル・ストーリーで撮られているため、トゥンベリもヴァランダーを使った独自の物語を生み出したことになるのだが、残念ながら日本未放映である。小山正氏による『ミステリ映画の大海の中で』(アルファベータ刊)の「ヘニング・マンケルの映像世界」に詳しいので、参照されたい。
ヘルストレムが元服役囚だったように、トゥンベリ自身もまた、特殊な経験をしてきた。1991年から93年にかけて、スウェーデンでは本物の〝軍人ギャング〟が現れた。現金輸送車や銀行を襲い、駅に爆弾をしかけ……つまり『熊と踊れ』は事実を元にしたフィクションで、しかもトゥンベリは、強盗団と血の繋がった兄弟なのである。
実際の兄弟は四人で、次男のトゥンベリ自身は当時アートスクールに通っており、犯行には加わっていない。ウェブ掲載された2016年4月19日付の『STRAND MAGAZINE』や2015年8月8日付の『The Guardian』のインタビューを読んでみると、作中で描かれるエピソードの多くが事実に則していることがわかる。本編終了後を無闇に想起させて興を削がないよう、ここでは詳しく触れないが、一部分だけ引用したい。ある人物のモデルとなった男が、『熊と踊れ』を読んだ後で発した感想だという。
「この本のおかげで前に進めるだろう。そしてお互いを、ただの血の繋がりでなく、ひとりの個人として見ることができるはずだ」
家族の名の下にがんじがらめになった男たちの物語に、光を照らす言葉である。
トゥンベリとの共著は続く予定で、本作で起きた犯罪のその後を描く話になるそうだ。兄弟の話を続けるのか、警部ヨンとその兄にまつわるエピソードがさらに掘り下げられるのか、具体的な展開は不明だが、いずれにせよ読むのが楽しみだ。
実在した事件の当事者と組んだことにより、『熊と踊れ』は過去のルースルンド作品の中でも最も事実に肉薄し、ノンフィクションとの境界が一層曖昧になった小説と言える。だが、もし事実をただ事実として記しただけであれば、これほど深い感動は得られなかっただろう。作中で何度となく繰り返される問いかけ──あの時、ドアを開けたのは誰だったんだ?──に対するそれぞれの答えが、これほどまでに痛烈に胸に刺さり、本を閉じた後も余韻をもたらすのは、著者が卓越した物語の紡ぎ手だからだ。
いつかルースルンドはノンフィクション作品を発表するかもしれない。しかしどんなジャンルで書こうと、誰と組もうと、ルースルンドは今後も、暴力に根ざしたテーマを追求していくのだろう。彼が投じる一石を正面から受け止めたいと願い、解説の結びとしたい。
2016年 8月