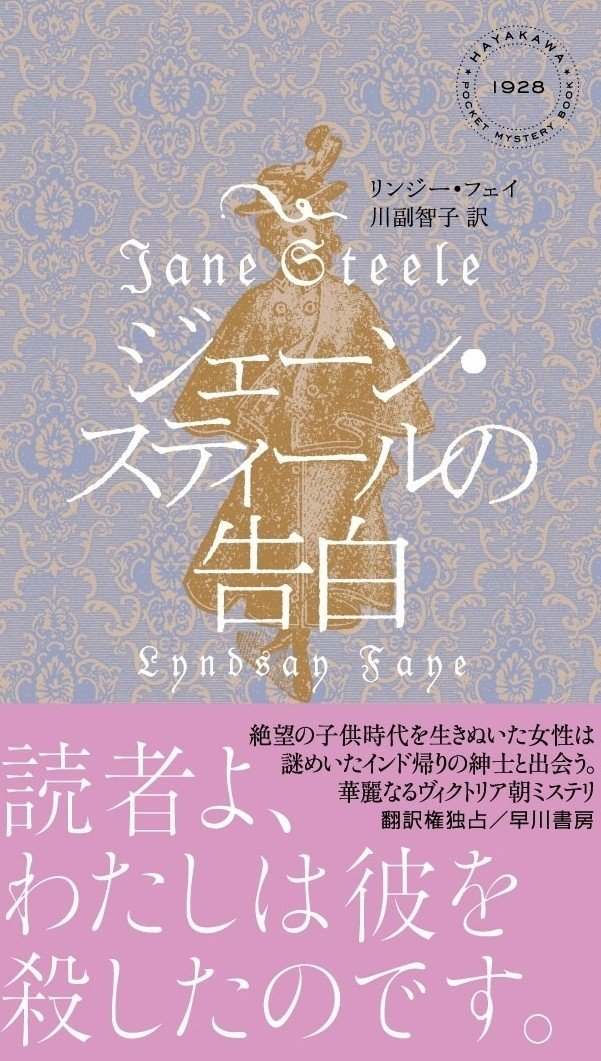「読者よ、わたしは彼を殺したのです」19世紀英国を舞台に繰り広げられる、女殺人者の闘いと恋。『ジェーン・スティールの告白』衝撃の第1章!
ヴィクトリア朝の英国を舞台に、異色のヒロインの活躍を描いた『ジェーン・スティールの告白』。著者は『ニューヨーク最初の警官 ゴッサムの神々』の作者で、シャーロキアンとしても知られるリンジー・フェイです。アメリカ探偵作家クラブ賞(エドガー賞)最優秀長篇賞候補ともなったこの話題作の発売を記念して、第1章を特別公開します。
リンジー・フェイ/川副智子訳/ハヤカワ・ミステリ
※書影をクリックするとAmazonページにジャンプ
第1章
〈なにをもらったって、こんな子はごめんだわ。ひとりになったらお祈りをしなさいね、ミス・エア。悔い改めないと恐ろしいものが煙突から降りてきて、さらわれてしまうかもしれませんよ。〉(『ジェーン・エア』第二章より)
愛のために、また折々のやむなき事情から、わたしが犯した数々の殺人のうち、もっとも重要な意味をもつのは最初の殺人だった。
本書の執筆が想像した以上に難しいということは早くもわかっている。自叙伝は真実に基づいて書かれなくてはならないのに、わたしはかくも長き孤独な年月を、嘘に嘘を重ねて生きてきたからだ。
「また友達になってくれるかい、ジェーン?」とエドウィン・バーバリーは言った。
噛みしめた唇が赤くなっていた。激しい動きと欲情で皮膚がぎらついていた。従兄のぽってりとした唇がつぎに動いたとき、蛙の鳴くような声が口から漏れた。
そのあと、きっかり五回、彼は息を吸い、段になった腹の肉を、破れたチョッキの下でぷるぷると震わせた。それから、ぜんまい仕掛けの玩具が止まるように動かなくなった。
わたしが犯した殺人の詳細は遠からず語るとして──明敏な読者が知りたいのは、そもそもなぜ血も涙もない女悪党がペンと原稿用紙を手にしているのかということだろう。『ジェーン・エア』という表題の魅力にあふれた本を幾度読み返したかしれない。あの本を読むたびに模倣したい思いに駆られる。手もとにある第二版は、初版を批評した人々にあてて著者がしたためた強烈な抗議の序文が呼び物となっている。わたしと『ジェーン・エア』との関係は友達、あるいは恋人とのそれに近い。そこに綴られたアルファベットをひとつ残らず肺に吸いこみたくなることもあれば、それらを全部、部屋の向こうへ投げつけたくなることもある。実体のない声が、よりにもよって家庭教師に呼びかけるという、あのジェーンの作り事めいた話を聞いたことのある人間がどこにいるというのか。
ここに明言しよう。わたくしことジェーン・スティールは、家庭教師として働いた日々において、北風の強靭な肩越しに運ばれるこの世のものとは思われぬ叫び声を聞いたことなど、ただの一度もない。かりに聞いたとしても、頭がおかしいと決めつけられるのが怖くて、口には出せなかったはずだ。
とはいえ、そうした荒唐無稽な空想のみを取りあげて『ジェーン・エア』を批判するのはいささか狭量に思える。あの本には信じられないほどすばらしいところもあるのだから。たとえば、わたし自身がかつて書いたのかと思うような個所さえある。
〈どうしてわたしはつらい目に遭ってばかりなんだろう? どうしていつも脅されたり、責められたり、咎められたりしなければならないんだろう? どうして人に気に入られないんだろう? いくら好かれようとしてもだめなんだろう?〉(『ジェーン・エア』第二章より)
そんな内省は子ども時代に置いてきた。従兄が最後にごぼごぼと息を吸いこんだ、あの小さな谷の底に。けれど、気がつくとあの小説の、生い立ちがあまりにも自分と似ている風変わりで心優しいジェーンに同情している。彼女もまた伯母の家で、教会の聖櫃に忍びこんだ鼠も同然の扱いを受けたのち、女子寄宿学校という体裁をした地獄へ送りこまれた。もっとも、あちらのジェーンは心がねじ曲がっているという不当な非難を受けたが、わたしを誹謗する人たちには、わかりきったことをあえて口にする彼らの苦痛に感謝を捧げるしかない。
少女の服をまとった狼のようにふるまうことをわたしに教えたのは、くすんだ風景のなかではよりいっそうくすんだ影となって身を隠すことを教えたのは、寄宿学校だった。わたしを素っ頓狂な声で笑う、青白い顔と大きな目をもつ生き物にしたのは、生きることと口汚い言葉に飢えて、ポケットにナイフをひそませる女にしたのは、ロンドンだった。そうしたすべてをチャールズが変えた。素性を隠したまま、いまいましい良心の呵責に苛まれながら、彼に恋をしたその瞬間に。回想録はどこからでも始められる。だが、親愛なる従兄、エドウィン・バーバリーがいなければ、ほかの何事も起こらなかっただろう。というわけで、この物語はいっさいの脚色なしに、ありのままの事実から始めることにする。
読者よ、わたしは彼を殺したのです。
なるほどわたしも昔から心がねじ曲がっていたかもしれない。でも、いつもいつも嫌われるばかりだったわけではない。たとえば、五歳のときに母がこう訊いてくれたことを覚えている。「怪我はしなかった、シェリー(愛しい子)?」
ひどく青白い顔と、榛色のゆるい巻き毛は当時から変わらない。ハイゲート・ハウスの敷地のはずれにある、わたしたちの小さな住まいの裏の庭でまえのめりに転んだわたしは、泣くべきかどうか思案した。庭で摘んだ苺がエプロンの下でつぶれ、わたしを甘い血の色に染めた。あのころのわたしは、母の関心を絶えず自分に向けさせようと懸命に知恵を絞っていた。自分は罰せられてもしかたのない悪い子だとしても、これからもずっとそうではないはずだと信じていた。
その日はたまたま、朝から母の調子がよかった。めそめそ泣くことも、阿片チンキが登場することも、すでに血がにじんでいる指の爪を噛むこともなく、わたしたちふたりの時間は過ぎていた。母はわたしの片手をつかむと、からかうような、ねだるような調子で、ビスケットに苺を載せて採れたての蜂蜜をかけ、即席のピクニックでもしましょうか、と言ったのだった。
だから、わたしは泣く必要はないと判断し、そのかわりに意地悪な木の根っこにあかんべえをして、喉までこみ上げていたものを飲みくだした。
「平気よ。手首がひりひりするけど」
母は枝を滝のように垂らした柳の木の下に刺し子の敷物を広げて座ると、にっこり笑ってわたしを呼んだ。
「こっちへ来て、見せてちょうだい」
母はフランス人で、わたしと話すときはよくフランス語を遣った。それがわたしは嬉しかった。母がほかの人に自分の国の言葉で話しかけることはめったになく、そうするのは相手の無知を示してやりたいと思ったときだけだった。わたしには母が予測不能で、仄かな光を振りまく蝶に見えた。それも、蒐集されてガラスの下に飾られる価値のある蝶だ。そんな母が誇らしかった。自分がその母の娘であることが。ほかのだれもかまってくれなくても、母はわたしに気を配ってくれた。そしてわたしは、母がほかのだれにも我慢ならなくなっても、笑わせてあげられた。
マ・メール(母)はわたしの手首をしげしげと見て、エプロンに飛んだ苺の汁や果肉を手で払い落としてから、冷めたまなざしをわたしの目に向けた。
「たいしたことはないわ」と、フランス語でそっけなく言った。「これぐらいなら、ふわふわの綿菓子みたいな女の子でも大丈夫」
「痛いの」やっぱり泣いたほうがよかったかもしれないと思いながら、わたしは言い張った。
「あらあら、それじゃたいしたことだわね」母はまたフランス語で言ってから、キスをした。わたしがくすくす笑いださずにはいられなくなるまで。
「苺がみんな、なくなっちゃった」
「でも、いいこと──なんでもないでしょ? 苺はまた摘みにいけばいいんだもの。なにか大事な用事でもあって?」
なかった。大事な用事なんか、なにひとつ。この園遊会が開かれるのは、青白い月が用心深く空に浮かぶ夜更けなのだから。生まれてからずっと母とふたりで暮らしてきたわたしは、このことが変だと考えたことは一度もなかった。ただ、木の根に気づかずに転んだことが恨めしい。ほかの少女たちはレースの縁取りがあるドレスを着て、宝石をちりばめた天蓋のような星明かりの下で母さまたちと一緒に、トライフルやティーケーキのあるピクニックを愉しんでいるにちがいなかった。冷たい露が降りて、わたしたち母娘が震えだすころまで、眠りたいなんて夢にも思わずに。
ちがうのかしら? 不安な思いでわたしはよく自問していた。
それは、最愛の母、アンヌ=ロール・スティールが、一族の地所に住みながら露骨に嫌われていたことと関係しており、母が嫌われるもっともな理由もふたつあった。ひとつは、先に述べたように母がフランス人であるという、悲劇的にして決定的な事実、もうひとつは、母の美しさだった。
昔ながらの退屈な意味で美人だったといっているのではない。母はほんとうに、浮世離れしていて思わず見とれてしまうという意味で、異様なくらい美しかった。いかにも意思が強そうな四角い顎はわたしも受け継いでいるが、母はその顎のために、このうえもなく温和な表情をしているときでも意地を張っているように見えた。暗めの赤煉瓦色の髪は艶やかで、アーモンド型の目は収まるべき位置にきれいに収まっていた。真珠の光沢をもつ腕輪のように、両の手首にうっすらと残る傷がなにを意味するのかは、当時のわたしは理解していなかった。
おぼろな月夜に、母が亡き父を想ってフランス語で叫ぶことがときどきあった。そうかと思うと、寝床から離れることを拒み、午後の陽が傾きかけたころにようやく、うめき声をあげながら、わたしたちが住む離れの料理人兼家ハウスメイドであるアガサにお茶を淹れさせる日もあった。
〝どうしたの、母さま?〟わたしは優しく問いかけた。おとなになった今は、あのころよりははるかに、母の返した答えが理解できる。
〝昨日があんまり長すぎただけよ〟
〝目が疲れているから、おもしろいだろうと思って読みはじめた小説のどこも期待したほどにはおもしろいと思えないだけよ〟
〝役に立つ時間の過ごし方が思いつかなくて、思いつくと今度はその務めを果たすのが恐ろしくなって、だから、どのみち試すことができずにいるだけよ、可愛い子〟
母の微笑みがいつまた戻ってくるのか予測がつかず、母が額にしてくれる──わたしには無条件にその資格があるといいたげに──鳥の羽根がかすめるようなキスも、いつも受けられるわけではなかった。
要するに母とわたし、仲良しの怪物ふたりは、互いに愛すべき存在であることを認め合い、ほかの人々にも認めてもらいたいと日々願っていたのだ。
彼らはそうしてはくれなかったけれど。
わたしが不名誉な人生の船出をすることになった経緯についてはこれから語るつもりだが、そのまえにまず、わたしの相続財産に関して母から聞かされたことに触れておこう。
わたしが六歳の八月、影がまだらに落ちた庭で、母はフランス語でこう宣言した。「いつか、なにもかもがあなたの手に渡るのよ、シェリー(愛しい子)、母屋のお屋敷もね。あなたのお父さまのものだったのだから、かならずあなたのものになるんです。そういうことがきちんと書かれた書類もあるわ。娘が財産を相続するには複雑で厄介な問題がつきまとうものだとしても。それに、この離れでの暮らしは貧しくて質素なものかもしれないけれど、難しい問題がたくさんあるということは理解しておきなさいね」
わたしはその難しいたくさんの問題を充分に理解してはいなかったけれど、まさにその屋敷に住む伯母と従兄にはそのへんがよくわかっているのだろうとは察しがついた。なぜなら彼らは高慢ちきで、あの苔むした石造りの館を、不機嫌な使用人たちも壁に掛かった埋葬布のようなタペストリーも、なにもかもを独占したがっていたから。また、中仕切りがされたガラス窓や、音をたてて勢いよく燃える暖炉や、明るい張り出し窓のある離れでの暮らしが貧しいとも質素だとも思わなかったが、特殊な種類の難しい問題がひとつならずあるということ、それらが、母とわたしが親戚といかに折り合いよくやるかに関わっている問題だということは理解できた。
「伯母さまがわたしを見る目つきでわかるでしょう。わたしたちは母屋には住めないのよ。ここなら安全で、暖かくて、人心地つけて、自分らしく過ごせるわ」母は腹立たしげに言い足した。左手の親指の甘皮をいじり、目に涙を溜めて。
「ジュ・デテスト・ラ・メゾン・プランシパル(あのおうちは嫌い)」わたしはきっぱりと言った。
それから、いつも持っている自分のハンカチを手渡しながら、母の涙を拭いてあげた。酸葉を摘んで夕食の魚料理の上に散らし、耳を貸す人みんなに──といっても、母と疲れ果てた親切なアガサのふたりだけだけれど──こう宣言した。「これからもここで愉しく暮らすんだわ。あたしはふたりのことが大好きだもの」
その願いは叶わなかった。
伯母のミセス・ペイシェンス・バーバリー──エドウィン・バーバリーの母親──は母と同じく未亡人だった。彼女が結婚した相手はミスター・リチャード・バーバリーで、わたしの父、ジョナサン・スティールの異父兄だ。ハイゲート・ハウスに対して父は完全なる権利を有しており、わたしがここで暮らすことになんら疑問が差し挟まれる余地はなかった。バーバリー家の人たちがわたしたち母娘とこの地所に住んでいるのは財政的な必要があってのことであろうと推測できた。伯母にすれば、いついかなる状況でも、わたしたちとの交流を愉しんでいるとされるのは許しがたいことのようだったから。
実際、わたしの九回めの誕生日の直後に母と母屋を訪問した折りには、とんでもない口論が始まった。
「ご親切にもお茶にお招きいただきまして」アンヌ=ロール・スティールはきらきらした笑みをさりげなく浮かべた。「ジェーンにはよく話していますのよ、スティール家のお屋敷には慣れておきなさいと。成人したらこちらで暮らすのだからと。それに、モン・デュー(ああ神さま)、管理上のどんな手違いが起こらないともかぎりませんもの、この子がもし、こみ入った事情──と英語ではいうのかしら?──を知らずにいたら」
ペイシェンス伯母はがっしりした体つきの女性で年がら年じゅう喪服を着ていたが、その習慣以外には夫の死を悼む様子は見られなかった。彼女の悼みの対象はまったくべつのものだったのかもしれない。失われた若さとか、キリストを知らぬがために滅びた暗愚なアフリカの異教徒とか。
リチャード伯父の話題が伯母の口にのぼったことは一度もないし、伯父がいないことを寂しく思っているふうでもなかった。そのことがわたしの興味を惹いたのは、屋敷のそこここに伯父の肖像画が飾られていたためだ。客間には友人から贈られた婚礼の日の水彩画が、書庫には堂々たる風貌の実業家をモデルとした油彩の習作があった。リチャード伯父は、輪郭のくっきりとした、ほとんど尖らせているといってもいいような唇と、生え際が弓なりの曲線を描いた額と、豊かな黒髪の持ち主で、その目にたたえた洒脱な表情のせいで、わたしが思い描く〝実業家〟──うつむいて足早に歩く蟻の群れ、特徴のない雨傘の連なり──よりも颯爽として見えた。生前の伯父を知っていたら、きっと好きになったにちがいない。この伯父がなぜ、人もあろうにペイシェンス伯母を結婚相手に選んだのかが不思議でならなかった。
幸いにもペイシェンス・バーバリーは、夫婦の契りという侮辱が二度と起こらないことを保証する容貌に恵まれ、結果的に寡婦としての評価はとてつもなく高まっていた──少なくとも、彼女はつねに美貌を目の敵にしていた。つまりは母の美貌を。母は母で、伯母からひどいしっぺ返しを食らっても冷ややかに微笑んでいた。ペイシェンス伯母の顔は蛙みたいに横に広がっていて、肌は赤みを帯び、唇は石積みの壁の目地のようだった。
「あなたも偉大な帝国で暮らしてもうずいぶん経つのに」母の語彙のおぼつかなさに、ペイシェンス伯母はため息をついてみせた。「そのわりには、この国の言葉がまるで習得できていないのね。ちょっとお尋ねしてもいいかしら。それが──あなたの主張するところの──ハイゲート・ハウスの将来の女主に用意されたお手本なの?」
「そんなことはないでしょうけれど」と答える母の口調には雪のレースの縁取りがされていた。「たびたびお招きにあずかるわけではないので、あなたの国の言葉を練習できないのですわ」
「あらま!」伯母は考えこむように言った。「それはたいそうお困りにちがいないわね」
わたしは座っている場所から飛び出して母を守りたかったが、ただ惚けたように動けずにいた。伯母がわたしに向ける憎悪は母に対するそれと大差なかったから。つまるところ、わたしは、母譲りの細すぎる首と思慮に富みすぎる表情しかもたない、痩せっぽちのみっともない子どもにすぎなかった。目も母と同じように猫の目に似ていたが──さらにいうなら蠱惑的でもあったが──色はいたって平凡なヒマラヤ杉のくすんだ茶色だ。もっときれいに産んでくれたらよかったのにと思うこともたまにあった。母の目の虹彩は凍った蜂蜜のかけらのような、ひんやりした不思議なトパーズ色をしていた。
自分の容姿の弱点を父のジョナサン・スティールのせいだと思ったことは一度もなかった。父に期待したこともなにひとつない。そもそも覚えていないのだから、期待のしようがなかった。
「エム・テュ・トン・ガトー(そのケーキのお味はいかが)?」母はつぎにわたしに質問した。
「ス・ネ・パ・トレ・ビアン(あまりおいしくないわ)、ママン(母さま)」
黒い喪服の下でペイシェンス伯母が怒りをたぎらせた。伯母はわたしたちが交わすフランス語を脅威と見なしていて、今にして思えば、伯母の考えは正しかったかもしれない。
「あら、ポーヴル・プティット(可哀相な子)」母は同情するように言った。
母とペイシェンス伯母は雄弁かつ声高な沈黙に移行した。わたしは従兄のエドウィンの視線が熱した針のように自分に突き刺さるのを感じた。おとなたちが礼儀を捨て去り、心にもないお世辞と本音の非難を互いに向けて吐きはじめると、彼はちょっかいを出してきた。
「新しい弓矢が手にはいったから、見せてやらなくちゃな、ジェーン」と彼はつぶやいた。
子どものくせにエドウィンは妙に遠まわしな物言いをする子だった。本能的な仲間意識が一瞬生まれても、従兄がじつはどういう人間であるかを思い起こしたとたんに気持ちがしぼむのはいつものことだ。一方で、彼の新しい弓矢はぜひとも試してみたかった。ただし、エドウィン抜きで。まったくべつのエドウィンとならもっといい。
従兄はわたしより四歳年長で、当時は十三歳。わたしたちの関係は以前からずっとおかしかったが、一八三七年のこのときには、より暗い影を帯びはじめていた。彼がおかしくなったという意味だけでこんな言い方をしているのではない。わたしのほうも彼を無視するのと彼の関心を惹くのを交互にやっており、その気まぐれをハイゲート・ハウスに住むおとなの全員から咎められていた。わたしのことを鼻持ちならないというより、むら気のある子だと言うおとなたちにはそう思わせておいた。実際にはその両方だったけれど。たしかに、わたしには彼の存在が必要だった。ほかのだれよりも歳が近かったし、わたしがおとなたちの吐き出した空気を吸いこんでいるということに母以外のだれも気づいていないときでも、彼はわたしの関心を求めて今にも溺れ死にしそうだった。
それでいてエドウィンは、彼の母親が考える模範的な子どもそのものだった。茶色の髪と上気した顔をもち、牧羊犬顔負けに単純で、ひっきりなしに下唇を噛んでいた。そうしないと下唇が突然どこかへ行ってしまうとでもいうように。
「新しく来た雌馬をもう見たか?」と彼がまた言った。「明日、馬車で出かけてもいいな」
わたしはだんまりを決めこんだ。最後にエドウィンと馬車に乗ったとき、クローバーの甘ったるい香りが鼻をかすめるなかで、彼はズボンの前立てを開いて、木綿の下穿きに包まれた地虫のような肉棒を見せ、それの使い途を知っているかと尋ねてきたのだった(むろん今は知っているが、当時のわたしは知らなかった)。そのひくひく動いている肉の組織が元の場所に戻されるのを、わたしは馬鹿みたいに口をぽかんと開けて見守るしかなく、今起こったことを黙殺することにした。従兄のエドウィンの洞察力はわたしが集めていた鳥の羽根と同程度の軽さだったから、自分の賢さにやましさにも似た気恥ずかしさを感じていた。自分より歳が上なのに、しかも、子ども時代特有の近しさという太い綱で互いにきつく結ばれているのに、彼をそんなふうに見下すのは恥ずかしいことだった。
馬車が屋敷に着く直前、今度森へ行ったらそれにさわりたくないかと彼は尋ねた。わたしが思わず笑い転げると、彼の紅潮した顔が黒みがかって紫色になった。「肉親が話しかけてるのに無視するとはずいぶん意地悪だね、ジェーン」エドウィンはしつこかった。
肉親、肉親、肉親。彼は聖歌隊の合唱曲よろしく、なにかというとその一語を持ち出した。まるで、わたしたちはただの親戚ではなくて、ふたりのあいだに濃い血のつながりがあるとでもいうように。わたしがなおも反応せずにいると、難解な判じ物でも解こうとするような視線をよこすので、ほんとうにわたしのことを判じ物──生命のない、感覚のないもの──だと思っているのかもしれないと不安になった。自分に良心があるとはもはや思わないが、感情がなかったことはいまだかつて一度もない。
「でも、今はちょっと機嫌が悪いだけだろうな。わかってるさ! じゃあ、お茶のあとでゲームをするのはどう?」
ゲームは母が好きなことのひとつで、わたしも好きだった。それに、従兄のことは警戒していたが、恐れてはいなかった。彼はわたしが好きでたまらないのだから。
「どんなゲーム?」
「秘密の交換」エドウィンの声がしわがれた。「ぼくにはいっぱいあるぜ。ものすごいのが。きみだって秘密はあるに決まってる。交換したら愉快じゃないか」
自分が貯めこんでいる秘密のことを考えると、あまり気乗りがしなかった。
アガサには毎晩お祈りをすると言ってあるけれど、六カ月まえにお祈りを怠けてもなにも起こらなかったので、それからはしていない。
阿片チンキはどんなことでもよいほうへ変えてくれると母さまが言ったから、一度試してみたら具合が悪くなり、そのことを隠す嘘をついた。
子猫に引っ掻かれて癇癪を起こし、外にほっぽり出したら、それから二度と戻ってこなくなり、暗くて寒い森のなかで子猫が震えている姿を思い浮かべるたびに、お腹が痛くなる。
そうした秘密のどのひとつもエドウィンには知られたくなかった。
「くだらない! おつむが悪いから、秘密にしておく値打ちがある秘密なんか知らないくせに」わたしは小馬鹿にして、皿のまわりのパン屑を指で押しつぶした。
頭の悪さを痛いほど自覚しているエドウィンの頬が真っ赤になった。わたしはその場で即座に謝ろうとした。行儀のよい子ならそうしなくてはいけないとわかっていたし、謝るだけの余裕を示してもいいと思ったのだ。ところが、彼は食卓からぱっと立ち上がった。金箔の縁取りがあるティーカップを口に運びながら喜々として敵意を発散させているおとなたちは、わたしたちにはまったく注意を払っていなかった。
「知ってるさ、もちろん」彼は小声で唸るように言った。「たとえばの話、自分の母親が居候でしかないのが恥ずかしくないかい?」
わたしは従兄に向かってあんぐりと口を開けた。
「そうなんだよ。それとも、きみも噂話を聞いたりするのか? だれか訪ねてくる客でもいるのかい?」
これは痛烈な一撃だった。「そんな人がいないことはわかってるでしょ。お客なんかひとりも訪ねてこないことは」
「なぜだろう、ジェーン? ぼくはいつも不思議でしょうがなかった」
「なぜなら、あたしたちは家畜みたいにここに飼われてるからよ! ここは自分の地所なのに!」わたしは叫び、ついバター皿に拳を打ちつけた。
磁器の皿が宙に吹っ飛び、堅木の床の上に落ちて割れると、従兄の顔に間の抜けた狼狽の表情が浮かんだ。母も同じくらい驚いていたが、わたしに賛同していた。わたしは、母がひどく体調の悪い夜に呂律のまわらぬ舌で一度だけ口走ったことを繰り返しただけなのだから。
ペイシェンス伯母の顔は歓喜のあまり、文字どおり裂けそうだった。自分の主張を敵がみずから証明してくれれば嬉しいに決まっている。
「せっかくお茶に招待したのに、娘がこれではねえ……度しがたい無作法ではないこと?」伯母は甲高い声で抗議した。「わたしの娘だったら、その曲がった根性を叩きなおしてやるところだわ。今、この場で。無作法を止めるための頑丈なヒッコリーの鞭が一番なんだけれど」
母は立ち上がり、薄手のコットンドレスの皺を手で伸ばすような仕種をした。差し迫った用事がほかにあるとでもいうように。「わたくしの度しがたい娘は聡明で活発なんですの」
「いいえ。ひねこびたじゃじゃ馬よ。今のうちにあなたが正してやらないと、この子の狡猾さが不幸な結末を招くでしょうよ」
「そう言うあなたのお子さんはどうでしょうね?」ミセス・スティールはナプキンを投げ捨てると、歯を食いしばって言った。「餌を与えすぎたお馬鹿さんではなくて? ジェーンにおたくの息子より劣っているところがひとつもないことは請け合いますわ。わたくしたちがこちらにお邪魔することは二度とございません」
「こちらが歓迎することも二度とありません」ペイシェンス伯母は吐き捨てるように言った。「おめでとうとあなたに言わなくてはいけないわ、アンヌ=ロール。上流社会との縁を完全に断ち切るとは、そのうえ、慈悲深くも同じ食卓につくことを許すたったひとりの人間を怒らせるとは──あなたがなさった努力も相当なものね。よろしくてよ。お互いに分別を働かせましょう。あなたが娘と呼ぶ、その質の悪い子を躾けられないのであれば、金輪際、ご自分の住まいからお出ましにならないでくださいな。わたしはもちろん、これからも自分の住まいで過ごします」
そのひとことで母の抵抗はもろくも崩れ、陰鬱なまなざしだけが残った。ペイシェンス伯母に多少なりとも才気が、あるいは優しさがあったなら、その融通の利かない性質も許せただろう、とわたしは思った。でも、彼女は粗野で意地が悪く、だから自分は彼女が嫌いなのだし、これからもずっと憎みつづけるだろうと。
母は両手の指をそっと丸めて小さな握り拳をつくった。
「いつの日か、わたくしの娘の権利を思い出してくださいましね。娘に与えられた権利のすべてを。さもないと、ご自身が後悔することになりますわよ」ミセス・スティールは、食卓を囲む面々に一回だけうなずいてみせた。
そして一顧だにせず立ち去った。だが、母がそんなふうに憤然として席を立つことはよくあり、嵐のような退出はむしろ母の流儀だったから、今のことで自分たちがもたらした被害の状況を確かめるのはわたしの役目だった。
ペイシェンス伯母は顔を紫色にして、わなわなと怒りに身を震わせながらも、なんとかこう言った。「ケーキのおかわりはいらなくて? エドウィン、ジェーン?」
「ジェーンを刺激するようなことを言ってしまったんだ、母さま。さっきは、あんなこと言って悪かったよ」エドウィンは付け足しのようにわたしに言った。下唇を噛みしめながら。あの午後、彼が着ていた茶色のチョッキと栗色の上着の上に見える襟に堅い芯がはいっていたことを覚えている。締めつけられた首がいやらしいほど膨らんでいたことも。
「もういいわ、エドウィン。お茶をごちそうさまでした、ペイシェンス伯母さま」多くの子どもがそうであるように、わたしもきまりの悪い思いをするのはなによりいやだった。自分が割った皿を見ると吐き気がして、腰を上げた。「あたしももう……お暇します」
部屋を出るわたしを、ペイシェンス伯母の怒りに燃えた目が追いかけた。
夕方、わたしは厩舎へ足を向けた。おとなしい雌馬たちのところへ行き、潤んだ穏やかな目を覗きこむと、ようやく従兄のことを考えるのをやめることができた。エドウィンのことを考えるのは、自己嫌悪の特殊な領域にはいる感情だった。彼の騾馬のような性欲を満たしている自分に嫌悪を感じていたのだ。ただ、それは、気が進まぬながらも何年もかけて彼とのあいだに育んできた仲間意識が生んだ、潮の流れのようなものでもあった。
生まれつき自己中心的な人間にとっては追従が最高のごちそうだということを、今はもう知っている。
厩舎に立ち、子守歌のような優しいいななきに耳を澄まし、筋張った馬の首に頬を押しつけるのは百回め、いや、千回めだった。ハイゲート・ハウスの馬たちが好きなのがわたしなのか、わたしの持ってくる角砂糖なのかはわからないが、彼らがにらみつけることはけっしてなく、おまえは地獄に通じる髪の毛ほどにも細い綱を渡っているのだと脅すこともなかった。干し草の甘いにおいと、馬たちの体を豊かに覆うごわごわした毛のにおいを嗅ぐと、かならず心が鎮まり、お返しにわたしも彼らの心を鎮めてやっていた。ひどく落ち着きのない雄の子馬までも、わたしが厩舎にいるときはおとなしくなった。
馬のことを考えているうちに、やがて、自分ならどんなふうに馬を使うだろうと思い描いた。林檎の花が咲く草地まで馬を駆るのはどうだろう。そこでは、母もわたしもなにもしてはいけなくて、ただ食べたり笑ったりするだけ。戦に向かう自分の姿も夢想した。ペイシェンス伯母とエドウィンの頭が足もとに転がっているさまも。
その春、母とわたしの食事はいつも軽い夕食でおしまいだった。また、その日おこなったような突然の退席のあとの母は、決まって小説と気付けの酒をかたわらにして部屋に閉じこもるとわかっていた。それでわたしはずっと外に出ていたのだ。厩舎の大きな扉の小割板の隙間から風が吹きこみはじめ、体を撫でてやっている馬たちが声をたてなくなるまで……自分が正真正銘、天涯孤独の身の上になっていたとは、翌日を迎えるまで露知らず。
八時に戻ると、こぼれた阿片チンキにふくまれる甘草の不穏な芳香がわたしたちの離れを満たしていた。母は七時に床についたのだとわかったが、その間の悪さのおかげで、わたしは二度と生きている母に会えなくなってしまった。翌朝、まだ寝床にいる母をアガサが見つけたときには、母は大理石のような目を窓に向けて冷たくなっていた。
©Lyndsay Faye ©Tomoko Kawazoe 禁転載
『ジェーン・スティールの告白』(リンジー・フェイ、川副智子訳)
ハヤカワ・ミステリより好評発売中