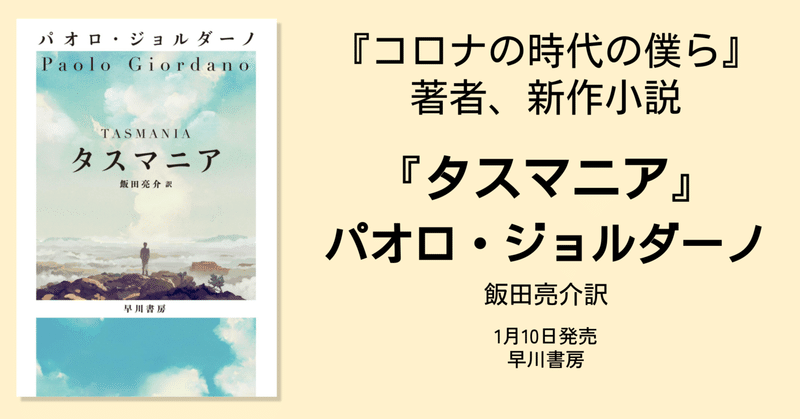
『コロナの時代の僕ら』著者が語る、現代人が抱える不安の正体とは? 『タスマニア』(パオロ・ジョルダーノ)訳者の飯田亮介あとがき
イタリアの作家、パオロ・ジョルダーノの新作小説『タスマニア』が2024年1月10日より発売中です
『コロナの時代の僕ら』で知られる著者が2021年9月から書きはじめたという本作。訳者の飯田亮介氏は、本作がそれまでの作品とは大きく異なるといいます。パンデミックは何をもたらし、著者はどんな道を選んだのでしょうか。ジョルダーノの作品を日本語に訳し続けてきた飯田氏が本作の魅力を語ります。

パオロ・ジョルダーノ、飯田亮介訳
2024年1月10日発売(紙・電子同時)
訳者あとがき
飯田亮介
本作はイタリア人作家パオロ・ジョルダーノ(1982年、トリノ生まれ)が2022年10月にエイナウディ社より発表した小説の全訳だ。
『タスマニア』はひとことで言えば、わたしたちが生きるこの奇妙な時代の写し鏡的な小説だ。コロナ禍を経てまだ間もない今しか書けない種類の文学であり、おそらくはジョルダーノにしか書けない希有な作品だと思う。
その理由はのちほど詳述する。
もしもあなたがジョルダーノの小説を初めて読むのであれば、できれば余計な前知識抜きに読み始めてほしい。それは彼の作品をこれまで何度も訳してきた訳者のわたしには二度とあり得ない条件であり、ひとりの本好きとして心から羨ましく思う。
また、もしもあなたが既にジョルダーノの熱心な読者であっても、やはりこの解題は後回しにして、とにかく先に本篇を読んでみてほしい。各国のジョルダーノファンが本作における彼のある文学的選択に新鮮な驚きを覚え、彼の文学が新しい地平に達したことを喜んでいるからで、その驚きをみなさんにも味わっていただきたい。
でも読み進めるうちに(初めて読んだ時のわたし自身がそうであったように)戸惑いを覚え、気になって仕方のない疑問が湧いたならば、いったんこのあとがきに戻って、続きを読んでみるのもいいだろう。おそらくその疑問の答えをわたしは知っているし、説明してみるつもりだ。
なお、ジョルダーノの小説作品としては2018年の『天に焦がれて』(早川書房)以来、4年ぶりとなる『タスマニア』は、イタリアの歴史ある本の情報誌『ラ・レットゥーラ』が選ぶ「2022年の良書ランキング」で首位となったほか、2023年度エルバ島国際文学賞、2023年度アンドレ・マルロー文学賞のフィクション部門を受賞するなど、国内外で既に高い評価を受けている。
物語は2015年11月のパリで幕を開ける。バタクラン劇場でイスラム過激派によるテロがあってからまだ数日という時期で、町は戒厳状態にある。
主人公はローマ在住のひとりの作家。彼がパリにやってきたのは国連の気候変動会議COPを新聞特派員として取材するためだが、それは表向きの理由で、本当は妻とのあいだに生じた個人的な問題から目をそらすための逃避行だ。彼は作家としても苦境にあった。第二次大戦末期に広島と長崎に投下された原子爆弾をテーマとした本を書きあぐねていたのだ。
作家は家庭の問題を解消できぬまま、その後の数年間、執筆を口実になかば家出も同然の状態で、パリ、ローマ、トリエステ、その他の町を転々として暮らすことになる。
彼がその道程で出会う友人たち(親権争い中の物理学者、自爆テロ事件を追うフリージャーナリスト、雲を研究する気象学者、禁断の恋に落ちた司祭、研究の末に心の病に冒された宇宙物理学者)もまた、やはり個人的だが切実な問題にそれぞれ直面している。作家は彼らの声に耳を傾け、時に介入も試みるが、基本的に無力な観察者であり続ける。
そんな主人公らのごく個人的な不安の背景には、いつだってもっと重大な世界的危機や新しい社会現象(気候変動、テロ、核の脅威、パンデミック、戦争、#MeToo運動、ネット炎上……)の影がちらついており、時おり不意の嵐のように彼らの日常を圧倒する。
はたして主人公らはそれぞれの嵐を無事、乗り切ることができるだろうか。そしてどこかに救いの地を見つけることができるのだろうか。
タイトルにもなっているオーストラリアのタスマニア島は、作中で気象学者のノヴェッリが、このまま地球温暖化が進んだ場合の避難先候補として挙げている地名だ。つまりタスマニアは救いの地の一例であり、ひとつの希望を象徴しているのだろう。しかしそれは同時に、大半の人類にとって、あらゆる意味であまりに遠い場所でもある。だから、わたしたちの誰もが自分なりの「タスマニア」を見つける大切さも訴えるタイトルでもあるのかもしれない。
このように『タスマニア』とは、ひとりの作家の視点から彼とその周囲の人間の物語を数年に渡って追い、断続的にスケッチすることで、現代人の多くが抱える不安の正体を見極め、わたしたち今どこに立っており、どこに向かいつつあるのかを再確認させてくれる小説だ。
さて、そろそろこの文章の冒頭で匂わせるに留めた、ジョルダーノの「ある文学的選択」について触れねばなるまい。
それはこの作品が彼にとっては初めてのオートフィクション(autofiction)であるということだ。耳慣れない言葉だと思う読者もいるかもしれない。「私小説」と訳されることもある言葉だが、日本で私小説というと、作者自身を主人公とし、極力虚飾を避けた、実話に近い小説であるという定義が一般的ではないだろうか。それに対しオートフィクションは、作者自身または作者に似た人物が主人公となるところまでは私小説と同じで、一見、作者の自伝(autobiography)風だが、あくまでもフィクション(fiction)であり、虚構の物語として提示される点が異なっている。だから「自伝的小説」という訳語がふさわしいように思う。2022年のノーベル文学賞を受賞したフランスの作家、アニー・エルノーもこの文学ジャンルの有名な書き手だ。
ただしフィクションとはいっても、オートフィクションは一般の小説に比べて作者本人の個性や実体験が主人公と物語にずっと強く投影され、虚実が入り交じり、区別がつかなくなるのが当たり前のようだ。そもそもそんな区別をする必要はない、真偽は詮索するだけ野暮だ、という姿勢が読者には要求されているのかもしれない。
『タスマニア』の場合、主人公の作家「僕」の名前はしばらく明かされないし、本作がオートフィクションである旨はどこにも記されていない。しかし、ジョルダーノの作品の熱心な読者であれば、トリノ出身の作家で、元物理学研究者で、今はローマに暮らし、『コリエレ・デッラ・セーラ』紙の寄稿者でもあるという主人公の人物設定が作者のプロフィールと一致することにすぐに気づくはずだ。だからこれは実話なのか、あるいは本人をモデルにしているだけなのか、という疑問が湧くのはある意味、自然なことだ。
こうしたことをくどくどと書いているのは、実は、訳者のわたし自身、このオートフィクションという分野にあまり馴染みがなかったため、初めてこの作品を読んだ時はジョルダーノにそっくりな主人公の行為に何度か驚いてしまったからだ。パオロ君、これは本当の話なのかい、ここまで書いてしまって大丈夫なのかい? と読んでいる途中から作者に訊いてみたくてたまらなかった。
わたしが混乱した理由はもうひとつある。自分の話ばかりで恐縮だが、今回の作品にわたしは訳者である前に、作中にも登場する被爆者へのインタビューの通訳としてまず関わっていたからだ。
2022年2月頭、わたしはジョルダーノから、今書いている新作のために被爆者を取材したい、できれば科学畑出身の被爆者を探してくれないか、というリクエストを受けた。そして3月、わたしたちは田中煕巳(てるみ)氏と田上月恵氏へのインタビューを行った。1932年生まれの田中氏は長崎の原爆の被爆者であり、元東北大学工学部助教授にして日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)代表委員。1969年生まれの田上氏は長崎の被爆者を両親に持つ被爆二世だ。コロナ禍の影響で作者の日本渡航がまだ困難であったため、残念ながらオンラインインタビューとなったが、その後、わたしは作者からインタビューの内容をまとめた原稿を受け取り、両氏に対して事実関係の確認も行った。
だから同年8月にジョルダーノが日本を訪れ、広島と長崎の慰霊式に出席したこともイタリアでTasmaniaが刊行される前からわたしは知っていた(彼が田中氏へのお土産に何故かキャンドルを買ったことも、非常にラフな格好で慰霊式に出席してしまったことも、田上氏に連れていかれた豆腐懐石がとても美味であったことも)。それで、新作はきっと原爆にまつわるノンフィクションに違いない、と思いこんでしまったのだ。
念のために書けば、両氏へのインタビューの場面も含め、広島・長崎の原爆に関する叙述、引用される被爆証言の数々はフィクションではない。
ところで、相当に内気な性格であることを公の場でたびたび告白し、本質的に自分は引っ込み思案なオタク(ナード)だとまで言うジョルダーノが、なぜ本作に限りオートフィクションというかたちでここまで自分をさらすような真似をしたのか。
その選択には2019年末からの新型コロナウイルスの世界的パンデミックが強く影響した。作者は複数のインタビューでそう明かしている。
彼が本作の執筆に着手した2021年9月当時、パンデミックは既に終息に向かっていたが、ああも強烈な現実に圧倒されたあとでは、純粋なフィクションを書く気にはもうなれなかったのだそうだ。これは多くの作家に共通する感慨だろう。
だが、それと同時にパンデミックはジョルダーノに今までにない自由を与えた。あの災厄を乗り越えた今ならば、もう自分をさらすのが恥ずかしいなどという小さな意識は捨てて、なんだって書くことができる、そう思ったのだそうだ。この思いは本篇の次の言葉にも見てとれる。
なぜならあれから今まで想像を絶する事件が世界でいくつも起きたせいで、僕らはみんなますます生存者(サバイバー)めいてきているからで、そんな生き残りの視点からならばなんでも語れる気がするからだ。
興味深いのは、コロナ禍を生き抜いた体験が執筆の大きな動機となった『タスマニア』だというのに、パンデミックが本格的に猛威を振るった約2年間が物語からすっぽり欠落している点だ。
事実、第二部はイタリアでパンデミックが本格化する直前の2020年1月に終わり、第三部は緊急事態がほぼ沈静化した2022年の8月に話がいきなり飛んでいる。これは間違いなく意図的な選択だろう。コロナ禍については2020年のエッセイ集『コロナの時代の僕ら』(早川書房)とその後の新聞記事や講演の場で既に書き尽くし、語り尽くしてしまったからなのだろうか。
にもかかわらず、不思議なことに、本作を初めて読んだ時にわたしが受けた印象は、ジョルダーノは最初のページから最後のページまで終始「コロナの時代」について語っている、あのころのわたしたちの不安と恐怖がここにはすべて描かれている、というものだった。「今まで色々あったよね、覚えているかい?」と彼が語りかける声が聞こえる気さえした。
ジョルダーノはきっと、パンデミックそのものよりも、そこにいたるまでの近年の流れを丁寧に描くことで、彼と同じサバイバーであるわたしたちがあの日々に抱いた不安と恐怖がけっして新しい感情ではなかったことを示そうとしたのだ。
そして「コロナの時代」だけではなく、わたしたちがさらに深刻な「気候変動の時代」をずっと前から生きていること、さらには「核兵器の時代」がまだ終わっていないことも思い出させようとしたのではないだろうか。
だからこそ「僕」は物語の最後に広島と長崎の慰霊式におもむき、過去の悲劇と改めて向きあう覚悟を行動で示したのだ。そこで運よくタナカさんとの邂逅を果たし、深く感動した作家の胸に湧いたのはこんな言葉だった。
ひとはたったひとりの男の子の物語を通じて全人類の運命を嘆くことができる。
大きすぎて漠然としか見えなかった物語をぐっと身近な物語にする感動の力。ジョルダーノはそこに人類の未来への希望を見つけたのかもしれない。
2023年師走
モントットーネ村にて
***
◆著者紹介 パオロ・ジョルダーノ

Paolo Giordano
1982年、トリノ生まれ。国際的に評価されるイタリアの小説家。トリノ大学大学院博士課程修了。専攻は素粒子物理学。2008年のデビュー長篇『素数たちの孤独』(ハヤカワepi文庫)は、イタリアで最高峰の文学賞であるストレーガ賞、カンピエッロ文学賞新人賞など、数々の賞を受賞し、世界的なベストセラーとなった。2020年、新型コロナウイルスの感染が広がるなか、エッセイ集『コロナの時代の僕ら』(早川書房)を発表し、イタリアや日本をはじめ世界各地で話題となった。2022年に刊行した本書『タスマニア』は、歴史ある本の情報誌ラ・レットゥーラが選ぶ良書ランキングで首位となったほか、2023年度エルバ島国際文学賞、同年度アンドレ・マルロー文学賞のフィクション部門を受賞するなど、イタリア内外から賞賛を得る。他の著作に『兵士たちの肉体』(2012年)、『天に焦がれて』(2018年、すべて早川書房)などがある。
『タスマニア』は、2024年1月10日より全国書店で発売中です(紙・電子同時)。

