
あらゆる分野におよぶ「貨幣の文明論」 『貨幣の「新」世界史』解説・根井雅弘(京都大学大学院教授)
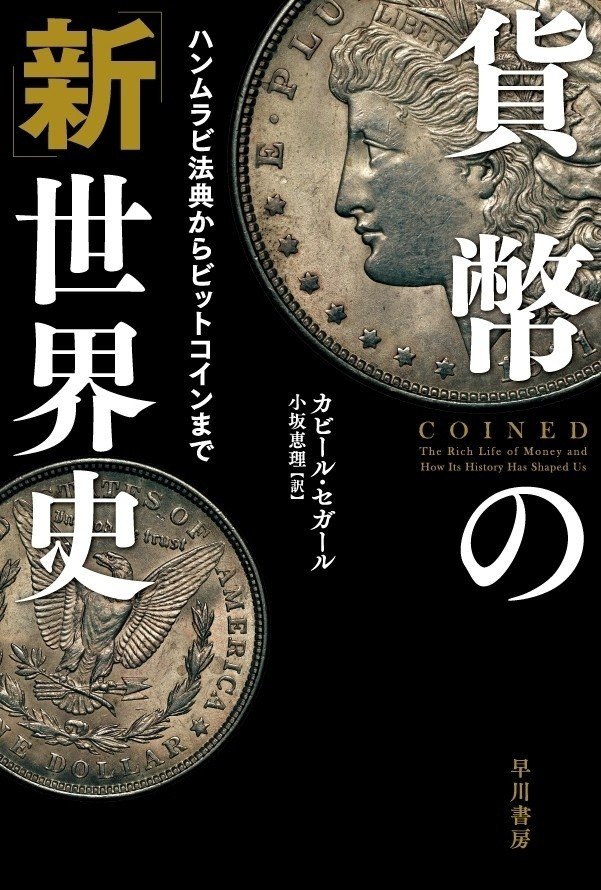
『貨幣の「新」世界史――ハンムラビ法典からビットコインまで』
カビール・セガール/小坂恵理 訳
ハヤカワ・ノンフィクション文庫 好評発売中
私たちはなぜこんなにも「お金」に翻弄されてしまうのか? ウォール街の元投資銀行家が、リーマン・ショックの渦中に抱いた疑問の解明に挑む『貨幣の「新」世界史――ハンムラビ法典からビットコインまで』が文庫化されました。今回新たに収録された、京都大学大学院の根井雅弘教授による巻末解説を公開します。
解説 根井雅弘(京都大学大学院教授)
本書の原著(Coined: The Rich Life of Money and How Its History Has Shaped Us)が刊行されたのは2015年だが、海外では、いち早くニューヨーク・タイムズ紙の電子版に書評が載った(2015年3月20日付)。その後、早川書房から日本語版(『貨幣の「新」世界史 ──ハンムラビ法典からビットコインまで』2016年)が出たとき、たまたま私も日本経 済新聞に書評を書く機会があった(2016年6月5日付)。その2年後にまた文庫版で刊行されるというのは、本書に対する世間の関心がよほど高いのだろう。
原題のCoined というのは、「貨幣の起源」か「貨幣の創造」というくらいの意味だが、 このテーマで学者に本を書かせてもあまり面白いものにはならない。彼らは貨幣の歴史や理 論などについては誰よりも詳しいのだけれども、一般の読者を飽きさせないようにする工夫には長けていない。その点、本書の著者カビール・セガールは企業戦略を担当する実務家なので、退屈な貨幣論にはなっていない。もちろん、急いで補足しなければならないが、これは著者の文献渉猟が十分ではないという意味ではない。著者がこの問題に関心をもったきっかけが2008年の金融危機だったとしても、使われている文献は、経済史、生物学、心理学、脳科学、人類学、宗教、芸術などあらゆる分野に及んでいる。これだけの文献が必要だったのは、ふつうの「貨幣論」と違って、いわば貨幣の「文明論」を展開したかったからだ ろう。
本書を丁寧に読んでいけば、タイトルにあるような「貨幣の世界史」についての広い知見が得られることは間違いない。だが、そう言っただけでは、本書の面白みは半減する。 著者によれば、人類は生き残るという生物学的な目標を達成するための象徴的かつ社会的な道具として貨幣を創造した。貨幣は、最初は「商品貨幣」だったが、時代の流れとともに 「硬貨」や「紙幣」へと姿を変えるとともに、次第に価値の「象徴」としての意味を持ち始めたと。これが著者の着眼点である。そして、貨幣の表面には芸術的なシンボルが描かれるようになったが、それは、「人類の生み出した文明や文化の歴史について貴重な情報を教えてくれる一方、いまや国家の価値を象徴する手段として採用されている」という。
「象徴」としての貨幣観は、貨幣の「モノ」としての価値ではなく、誰もがそれを「貨幣」 として受け取ってくれるという予想の自己循環論法から独自の貨幣論を展開した岩井克人氏の見解に似ていなくもない(『貨幣論』ちくま学芸文庫、1998年)。岩井説では、恐慌よりはハイパーインフレこそがそのような予想の自己循環論法を崩壊させ、「貨幣」が「貨幣」でなくなる危機を招くということになるのだが、実務家の著者の関心はそのような本質論には向かわず、もっと日常生活にかかわる問題を取り上げる。ここでも、著者の幅広い読書が役に立っている。
例えば、最先端の経済学の一つに神経経済学という分野があるが、その実験によって、本人が自覚せずとも、報酬が期待されるとき、人間の脳は具体的な行動を促すことが明らかになった。他方で、お金の使い方は、社会規範や文化的儀式などにも左右される。具体例として挙げられているのは、日本における中元や歳暮のような「贈与経済」である。お金のやり取りが、独自のギブ・アンド・テークの社会的習慣から生み出されたというのは、日本人にはわかりやすい。
もっと実践的な関心をもつ読者は、最近の仮想通貨、「ビットコイン」の動向に関心をもっているかもしれない。意外なことに、本書にはビットコインへの言及は比較的少ない。ただ、一つ言えるのは、ビットコインが「象徴」としての役割を超えて、それ自体がモノとしての価値をもつ資産として受けとられているなら、それがいまの「貨幣」に取って代わるものにはなりにくいのではないか、ということである。たしかに、新聞や雑誌はビットコインの価値の騰落の記事であふれているのだが、それが新しい「貨幣」になる兆候とは決して言えないと思われる。イェール大学教授でノーベル経済学賞受賞者のロバート・J・シラーはもっと辛辣で、ビットコインのような例は歴史上何度もあり、興味深い社会現象ではあるものの、それが「新通貨」になるというのは「幻想」に過ぎないと断言している(『プロジェクト・シンジケート』2018年5月21日)。
さて、著者の関心は、お金と宗教との関係にも及んでいるが、ここでは、世界三大宗教 (キリスト教、イスラム教、仏教)のいずれも、お金が「多いほどよい」という経済的論理 に否定的で、「足るを知る」という精神的論理(「論理」というより「倫理」かもしれないが)を強調していることに注目している。興味深いのは、ある人類学者(デイヴィッド・グレーバー)が、影響力の大きな宗教指導者が、紀元前8世紀に硬貨が発明された地域(ギリシャ、インド、中国)に暮らしていた事実を紹介している件である。「お金も永続的な宗教 も、どちらも紀元前800年から紀元600年にかけて誕生したのは、決して偶然ではないという。市場の重要性が高まるにつれ、組織的な宗教が広がったのではないかと考えている。 たとえば、イエス・キリストの初期の弟子たちの多くは貧しかったので、物質的な富に関して逆説的かつ開放的な見識を素直に受け入れたのかもしれない」と。
だが、そうだからといって、著者はお金の「効用」を否定する見方には与していない。 「使い方さえ間違えなければ、お金は誰もが共有できる手段となり、人類の繁栄を促してくれる。矛盾するようだが、お金は他人と共有するために稼ぐものなのかもしれない」と。
著者はもちろんマイクロクレジットで有名なグラミン銀行の創設者、ムハマド・ユヌス氏のことをよく知っているに違いないが、ユヌス氏も本書を読んで何らかの示唆を得たので、原著に序文を寄せたのだろう。
ところで、毎年、多少の書評を書いてきたせいか、私は、本書のような広い意味でのビジネス書を読むコツについて尋ねられることがある。学術書であろうとビジネス書であろうと、本の読み方は基本的に変わりはない。だが、書評を依頼された本についていえば、私はまず巻末の参考文献をながめることにしている。決して序文やあとがきや日本語版解説などからは読まない。本書のように文献の渉猟範囲が広い場合と、参考文献が比較的少ない読み物の場合とでは、読んでいくスピードが変わる。もちろん、前者より後者のほうが数倍速く読んでも正確に意味がとれる。だが、後者のような本ばかり読んでは頭の訓練にならないので、ときには前者のような本(本書もその一つだが)を丁寧に読んだほうがよい。
最後になったが、文庫版として生まれ変わった本書が、学生、社会人、研究者など、さまざまなバックグラウンドをもつ人たちに広く読まれることを願ってやまない。
* * *
『貨幣の「新」世界史――ハンムラビ法典からビットコインまで』
カビール・セガール
小坂恵理 訳
ハヤカワ・ノンフィクション文庫 好評発売中

