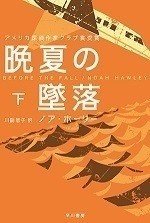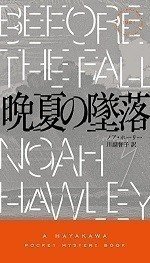エドガー賞受賞作『晩夏の墜落』が文庫&ポケット判の2形態で7月6日同時発売! 人気海外ドラマ『ファーゴ』『BONES』のクリエイターが執筆した社会派サスペンス傑作から、衝撃の冒頭部分を公開
全米最高のミステリ小説に与えられるアメリカ探偵作家クラブ賞(通称「エドガー賞」)の最優秀長篇賞を受賞した『晩夏の墜落』(ノア・ホーリー著/川副智子訳)が、ポケット判と文庫で2つの判型で7月6日同時発売となりました。
※文庫版・ポケット判の内容は同一です。
本書を執筆したのは、話題の人気海外ドラマ『FARGO/ファーゴ』『BONES―骨は語る―』『レギオン』などを手掛けたドラマクリエイターのノア・ホーリー。ゴールデングローブ賞・エミー賞を総なめにした著者による傑作サスペンスから、衝撃の冒頭部分の試し読みを公開いたします。
***
晩夏の墜落
マーサズ・ヴィンヤード島の飛行場に機体前部の内蔵タラップを引き出されたプライベートジェットが駐機している。機種はオスプライ700SL。座席は九席。二〇〇一年にカンザス州ウィチタで製造された。名簿上の所有は、郵送先住所をケイマン諸島とするオランダの持株会社だが、機体には英語でガルウィング・エアと記されている。機長のジェームズ・メロディーはイギリス人、副操縦士のチャーリー・ブッシュはテキサス州のオデッサ出身。客室乗務員のエマ・ライトナーはドイツのマンハイムで生まれた。エマの父は米国空軍中尉で、母は十代で彼女を生み、エマが九歳のときに一家はサンディエゴへ引っ越した。
だれにでも歩んできた道がある。さまざまな選択の結果がある。ふたりの人間がたまたま同じときに同じ場所に居合わせることになる経緯に説明はつかない。見知らぬ十二人と同じエレベーターに乗り合わせる。一台のバスに同乗する。トイレの順番待ちの列に並ぶ。そうしたことが日々起こっている。自分の行く末や出会う人を予測したところでなんの意味もない。
ルーバー式の乗降扉の通風装置からハロゲンランプの柔らかな光が漏れている。民間機の蛍光灯のぎらついた不快な光とはまるでちがう。この数週間後、スコット・バローズは《ニューヨーク・マガジン》のインタビューで、プライベートジェットにはじめて乗って一番驚いたのは、脚をゆったりと伸ばせる座席でも本格的なバーカウンター設備でもなく、誂えたようにしっくりくる機内装飾だったと語ることになる。一定レベルの所得がある人にとっては空の旅も自宅での過ごし方のひとつにすぎないのだろうと。
ヴィンヤード島の穏やかな夜。現在の気温は三十度。南西からかすかに風が吹いている。出発予定時刻は午後十時。海岸線で発生した濃霧がこの三時間でさらに深まり、雑音を消している。濃密な白い巻きひげのような霧がライトに照らされたアスファルト舗装の飛行場をゆっくりと横切る。
ベイトマン一家がこの島専用のレンジ・ローバーに乗って最初に到着する。父親のデイヴィッドと母親のマギー、そして、レイチェルとJJのふたり。今は八月の下旬で、マギーと子どもたちは今月の最初からヴィンヤード島にいる。デイヴィッドは週末ごとにニューヨークからやってきていた。もっとひんぱんにこちらへ来たいのだが、それ以上ニューヨークを離れることは難しい。デイヴィッドは〝エンターテインメント〟の仕事をしている。業界では最近、テレビのニュースをそのように称する。情報と意見をごたまぜにした見世物という意味で。
デイヴィッドは背が高く、電話では威圧的な口調で話す。初対面の相手はしばしば彼の手の大きさに圧倒される。息子のJJは車のなかで眠ってしまった。マギーとレイチェルがジェット機に向かって歩きだすと、デイヴィッドは車の後部座席に身を乗り出し、片腕でJJの体重を支えて座席からそっと抱き上げる。JJは熟睡していても本能的に父親の首に腕をまわす。頭は垂らしたままだ。首筋にかかる息子の息の温かさにデイヴィッドはぞくりとする。片手の掌には息子の尻の骨の感触がある。息子の両脚が脇腹にあたっている。JJは四歳。人は死ぬものだということはもうわかる歳だが、いつか自分も死ぬと
いうことを理解するには幼すぎる。デイヴィッドとマギーが息子を〝永久機関〟と呼ぶのは、実際、JJが一日じゅうノンストップで動きまわっているからだ。三歳のとき、JJの主たるコミュニケーションの手段は恐竜顔負けの声で吠えることだった。四歳となった今は人の邪魔をする王者となり、両親が口にするあらゆる言葉に対して疑問を投げかける。そのしつこさたるや、相手が答えるか自分が黙らされるかするまで永遠に訊きつづけるのではないかと思えるほどである。
息子の重みにバランスを奪われながらも、デイヴィッドは車のドアを片足で蹴って閉める。空いているほうの手で携帯電話を耳にあてている。
「やつに言っておけ、このことをひとことでも喋ったら」JJが目を覚まさないように通話の声を落とす。「訴えるぞと。弁護士どもが聖書の蛙みたいに空から降ってくると思わせてやると」
五十六歳のデイヴィッドの体は、まるで防弾チョッキでも着ているかのように硬い脂肪の層に覆われている。顎は頑丈で、頭髪も充分にある。一九九〇年代には数々の選挙運動──州知事や上院議員、大統領の一期と二期──に関わって名前を売ったが、二〇〇〇年にはそれらの活動から身を引き、ワシントンD.C.のKストリートにロビー団体の事務所を構えた。その二年後、ある億万長者の長老から、二十四時間放送のニュース専門局を立ち上げる話が持ちこまれた。十三年の歳月をかけて百三十億ドルの共同収益を実現した今、デイヴィッドは耐爆弾構造のガラス張りの最上階のオフィスと、このビジネスジェット機を自由に利用する立場を手にしている。
子どもたちとはなかなか時間をともにできない。そのことについて夫婦の合意があるとはいえ、言い争いはしょっちゅうだ。要は、マギーが蒸し返して、デイヴィッドが守勢にまわるわけだが、内心では彼も妻と同じように感じている。しかし、結婚とはそもそもそういうものではないのか? ふたりの人間が十八センチの陣地をめぐって争うようなものではないのか?
飛行場に一陣の風が起こる。デイヴィッドは携帯電話を耳にあてたまま、マギーに視線をやり、にっこりと笑う。笑顔の意味はこうだ。こうしてきみのそばにいられて嬉しいよ。愛している。だが、その笑顔は同時にこうも語っている。そうさ、また仕事の電話なんだ。大目に見てくれ。大事なのは今わたしがここにいること、家族みんなが一緒にいることなんだからな。
それは謝罪の笑みでありながら、一歩も譲らぬ非情さをふくんでいる。
マギーも笑みを返すが、彼女の笑みはもっと投げやりで、もっと悲しげだ。夫を許すのか許さないのか、自分でももうわからなくなっている。
ふたりが結婚して十年足らず。現在三十六歳のマギーは、結婚するまでプレスクール(日本の幼稚園・保育園にあたる)の教師をしていた。それも、男の子たちが夢想するきれいな先生そのものだ。夢想とはなにを意味するのかを、つまり、先生の胸を見つめるという、幼児とティーンに共通の習性であることを、彼らはまだ知らないけれども。プレスクールでミス・マギーと呼ばれていた彼女は、快活で愛らしい先生だった。毎朝六時半に登校して教室を整頓し、夜は遅くまで起きて保育記録をつけ、授業プランを練った。カリフォルニア州ピードモント出身の二十六歳のミス・マギーは教職を愛していた。愛していたのだ。プレスクールにかよう三歳児たちにとって、彼女は生まれてはじめて出会う、自分をまともに扱ってくれる、自分の言うことに耳を傾け、おとなになったような気持ちを味わわせてくれるおとなだった。
そして運命が──といってもいいだろう──二〇〇五年早春の木曜日、ニューヨークの高級ホテル、ウォルドーフ・アストリアの舞踏室でマギーとデイヴィッドを引き合わせた。その準礼装指定の舞踏会はある教育基金のための集金パーティで、マギーは友人とともに出席していた。基金の設立メンバーのなかにデイヴィッドもいた。花柄のドレス姿の彼女はプレスクール帰りで、右膝の裏のくぼみにフィンガーペイントの青い絵の具の跡を残した慎ましい美人、彼はツーボタンのスーツに身を包んだ重量級のチャーミングな〝鮫〟だった。マギーはそのパーティで一番若い女ではなく、一番美しい女でさえなかった。ただ、ハンドバッグにチョークを入れている女は彼女のほかにいなかった。張り子の火山を作ることができるのも、毎年ドクター・スースの誕生日にかぶるために『キャット・イン・ザ・ハット』の赤い横縞のシルクハットを持っているのも彼女だけだった。いいかえれば、彼女はデイヴィッドが妻に求めるすべての条件を満たしていた。彼は、高価な被せ物をした歯を見せて微笑みながらマギーに声をかけた。
今にして思えば彼女には抗いようもなかったのだ。
十年後の今、デイヴィッドとマギーはふたりの子の親となり、イースト川に面するグレイシー・スクエアのタウンハウスに住んでいる。九歳のレイチェルは自宅に近いブリアリー女子校にかよっている。教師を辞めたマギーはいつもJJと家にいるが、その経歴によって、同じ境遇にある女たち──仕事中毒の億万長者を夫にもつ哀れな専業主婦たち──から浮いた存在になっている。朝、息子を連れて公園へ行っても、子どもの遊び場にいる専業主婦はマギーしかいない。ほかの子どもたちはみなヨーロッパのデザインの乳母車に乗せられてやってきて、そうした乳母車を、携帯電話で会話しながら押しているのはカリブ海出身のベビーシッターだ。
風に肌寒さを覚え、マギーはサマー・カーディガンのまえをかき合わせる。巻きひげのような海霧は今はゆるやかに波打ちながら、冷ややかな執拗さで飛行場の上を流れている。
「フライトして大丈夫なの?」マギーは夫の背中に問いかける。デイヴィッドはもうタラップを昇りきっている。細身のブルーのスカートスーツを着こなした客室乗務員のエマ・ライトナーが、笑顔で夫妻を迎える。
「大丈夫だって、ママ」マギーのうしろを歩きながら、九歳のレイチェルが言う。「みんな、飛行機に乗るのにいちいち確かめたりしないでしょ」
「そうね、わかってるけど」
「飛行機にはいろんな計器がついてるし」
そのとおりだというようにマギーは娘に笑みを送る。レイチェルは緑のバックパックを背負っている。なかにはいっているのは、『ハンガー・ゲーム』の本とバービー人形とiPad。それらがレイチェルの歩みに合わせ、小さな背中にリズミカルにぶつかる。娘はこんなに大きくなったのだ。まだ九歳でも、将来この子がどんなおとなの女性になるのか、すでにその兆しが現われている。学生がまちがいに気づくまで待つことができる忍耐強い教授。べつの表現をするなら、場ちがいなまでに賢い人物。だが、目立ちたがりではない。断じて目立ちたがりではなく、思いやりと心地よい笑い声をもつ女性。それは娘がもって生まれた資質なのか、それとも過去の出来事が娘の内面に植えつけたものなのか? 幼い娘を巻きこんだあの事件によるものなのか? オンラインのどこかに、その完全な冒険譚(サーガ)が言葉と画像で記録されている。YouTubeに保存されたニュース映像。番記者たちの膨大な仕事の成果が1と0の巨大な集合記憶ですべて保管されているのだ。去年、《ニューヨーカー》のあるライターが本を出したがったが、デイヴィッドはひそかに握りつぶした。しっかりしているようでもレイチェルはまだ子どもだ。一歩まちがえばとんでもないことになっていたかもしれないと思うと、マギーの心は不安で壊れそうになることがある。
マギーは無意識にレンジ・ローバーに目をやる。車のなかではギルが先発の警護チームと無線連絡を取っている。どんなときにもけっして上着を脱がない大柄なイスラエル人のギルは、デイヴィッドとマギーの影の存在だ。夫妻と同じ所得層に属する人々はギルのような人間を家族付きガードマン(ドメスティック・セキュリティ)と呼ぶ。身長約百八十八センチ、体重八十六キロ。上着を脱がないのには理由があり、その理由が上流社会で問題視されることはない。ベイトマン家がギルを雇って今年で四年になる。ギルのまえにはミシャを、ミシャのまえには愛想のないスーツ姿の突撃班の男たちを雇っていた。彼らは自動火器を車のトランクに詰めこんでいた。教師時代のマギーだったら、家族の生活にこんな軍隊じみた男たちが割りこんできたら一蹴しただろう。金持ちだから暴力の対象にされるなどと考えるのは自己陶酔的だと嘲笑っただろう。けれど、それは、二〇〇八年七月の一連の出来事、娘の誘拐と娘を取り返すまでの三日間の苦しみを経験するまでのことだった。
タラップを昇りきったレイチェルはくるっとうしろを振り返り、王室の人々を真似て、人気(ひとけ)のない飛行場に手を振ってみせる。ワンピースの上にブルーのフリース、ポニーテールには蝶結びにしたリボン。あの三日間でレイチェルが負った心身の傷──閉所恐怖症や見知らぬ男に対する恐怖感──は傍目にはほとんどうかがえない。それでも、レイチェルが愉快な子どもなのは、お茶目な笑顔をもつ陽気ないたずらっ子なのは昔と変わらない。娘がその笑顔を失っていないことにマギーは毎日感謝せずにはいられない。
「ようこそお越しくださいました、ミセス・ベイトマン」タラップの上に立ったマギーにエマが声をかける。「ええ、どうも」マギーは条件反射的に応じる。自分たち家族が裕福であることを詫びたい衝動に駆られるのもいつものことだ。夫はともかく、自分が裕福なのはまったく信じがたいことだから。プレスクールの教師を職業にして、エレベーターのない六階建てのアパートメントハウスに意地悪なふたりの女と同居し、さながらシンデレラのような生活を送っていたのはそれほど昔のことではないのだから。
「スコットはもう来ている?」マギーは尋ねる。
「いいえ、まだ。みなさまが一番乗りです。ピノ・グリを用意させていただきました。グラスでお持ちしましょうか?」
「まだ結構よ。ありがとう」
機内は豪華だが派手さを抑えた設(しつら)えで、壁にはトネリコの羽目板が畝模様に張られている。さりげなく配置されたグレイの革張りのふたり掛けのシートは、旅のパートナーがいらっしゃれば、この旅をよりいっそう愉しめますよと言いたげだ。客室には、大統領の書斎と同じく、金をかけて確保した静けさがある。マギーはこのプライベートジェットに何回も乗っているが、こうした甘やかされた環境にはいまだに馴染じめない。ジェット機がまるごと自分たちのものだなんて。
デイヴィッドは息子を自分のシートに寝かせ、毛布を掛けてやる。今はまたべつの電話に出ている。今度の電話は深刻そうだ。夫の下顎に力がはいっているのを見れば察しがつく。JJがもぞもぞ動くが、目は覚まさない。
レイチェルは操縦室(コックピット)のそばで立ち止まり、パイロットたちに話しかけている。行く先々でレイチェルはそうする。その場所を支配する人間を見つけ、質問攻めにするのだ。マギーは、九歳の娘を視野に入れながら、操縦室のドアのまえにいるギルに視線を据える。ギルは拳銃のほかにテーザー銃(電流で一時的に麻痺させる銃)とプラスチックの手錠を携行している。ギルはマギーがこれまで出会った人間のなかでもっとも物静かな男だ。
デイヴィッドは携帯電話を耳に押しあてながら、片手で妻の肩をぎゅっとつかむ。
「うちへ帰れるのが嬉しいだろう?」もう一方の手で送話口を覆って言う。
「どうかしら」とマギーは答える。「この島の生活はとても快適だもの」
「残りたければ残ってもいいぞ。来週末は抜けられない用事があるが、それだけだ。そうするか?」
「無理よ。子どもたちには学校があるし、わたしも木曜日には美術館の理事会に出なくちゃならないから」
マギーは夫に微笑みかける。
「ゆうべあまり眠れなかったので、ちょっと疲れたわ」
デイヴィッドの視線がマギーの肩の向こうに移る。眉間に皺が寄る。
マギーも振り向く。ベンとサラのキプリング夫妻がタラップの一番上に立っている。金持ちのカップル。どちらかといえばマギーの友達というよりデイヴィッドの友達。それでもやはり、サラはマギーの姿が目にはいると甲高い声を発する。
「ダーリン」と言って、両腕を大きく広げる。
そしてマギーをハグする。飲み物のトレイを手にした客室乗務員が気まずそうにふたりのうしろに突っ立っている。
「素敵だわ、そのドレス」とサラ。
ベンは巧みに妻を脇にどけてデイヴィッドに近づき、熱っぽい握手をする。彼はウォール街の四大投資銀行のひとつの共同出資者(パートナー)であり、仕立てのいいブルーのボタンダウンのシャツにベルト付きの白いショートパンツという出で立ちの、青い目をした鮫である。
「昨日の情けない試合を見たか?」ベンはデイヴィッドに訊く。「なんだってあのボールを受けられないかね?」
「その話を始めさせないでくれ」とデイヴィッド。
「いやつまり、おれならあんなボールを受けるぐらい屁でもないぜ。この馬鹿でかい手がありゃ」
ふたりの男はふざけて向き合い、二頭の雄牛が大きな角を突き合わせる戦闘のポーズを取る。
「ライトがまぶしくて見失ったんだろうよ」デイヴィッドはそこで携帯電話が振動していることに気づく。画面をちらりと見て、顔をしかめ、メールで返信を始める。ベンはデイヴィッドの肩越しにすばやい視線を走らせ、とたんに酔いが醒めたような表情になる。女たちはお喋りに忙しい。ベンはデイヴィッドに顔を寄せる。
「話があるんだ」
なおも文字を打ちながら、デイヴィッドは首を横に振る。
「今はだめだ」
「ずっと電話をかけてたんだぞ」ベン・キプリングはそう言って、言葉を続けようとするが、飲み物を運んできたエマがそばにいる。
「グレンリヴェットのロックをお持ちいたしました。こちらでよろしいでしょうか?」エマはベンにグラスを手渡す。
「相変わらずきれいだね」ベンはスコッチをあおり、ひと息でグラスの半分を空ける。
「わたしは水にしてくれ」エマがトレイの上のウォッカのグラスを持ち上げると、デイヴィッドが言う。
「かしこまりました」エマは笑顔で応じる。「すぐにお持ちいたします」
一メートルほど離れたところに世間話の終わったサラ・キプリングがいる。サラはマギーの腕をぎゅっとつかむ。
「大丈夫なの?」と心配そうに訊くのは、これで二度めだ。
「ええ、大丈夫」とマギーは答える。「なんでもないのよ。旅の疲れが出ただけ。うちに帰れば治るわ」
「そうね。わたしはビーチが大好きだけど、ほんとうのところはどうかしら。やっぱり退屈なだけかもしれないわ。陽が沈むのだって何回か見れば飽きてしまうし、やっぱり〈バーニーズ〉にでも行きたくなってくるのよ」
マギーは開かれたままの乗降扉を落ち着かなげにちらちらと見る。サラはその視線をとらえる。
「どうかした?」
「どうもしないけど、たぶんもうすぐ──」
レイチェルのおかげでマギーはその先を言わずにすむ。
「ママ」レイチェルが座席からマギーを呼ぶ。「忘れないで。明日はタマラのパーティよ。まだプレゼントを買ってないのよ」
「そうだったわね」マギーは気をそらされる。「午前中に買いにいきましょう」
マギーの目は娘を素通りして、肩を寄せ合って話しているデイヴィッドとベンに向かう。
デイヴィッドは渋い顔をしている。そのことはあとでデイヴィッドに訊くとしても、最近の夫はひどくよそよそしい。喧嘩だけはしたくない。
客室乗務員がマギーの脇をすり抜けてデイヴィッドに水のはいったグラスを手渡す。
「ライムはいかがいたします?」
デイヴィッドは首を横に振る。ベンは禿げあがった頭をしきりにさすり、操縦室を見やる。
「だれかを待ってるのか? そろそろ出発しようじゃないか」
「もうおひとかたいらっしゃるはずですの」乗客名簿を見ながらエマが言う。「スコット・バローズさまが」
ベンはデイヴィッドをちらりと見る。「だれだい?」
デイヴィッドは肩をすくめる。「マギーの友達かな」
「友達というわけじゃないわ」マギーが夫の答えを小耳に挟む。「子どもたちの知り合いなのよ。今朝、島の市場(いちば)で会ったときにニューヨークへ行く用事があると聞いたから、ご一緒にどうぞとお誘いしたの。画家なんですって」
マギーは夫を見る。
「彼の絵のことはあなたにも話したじゃないの」
デイヴィッドは腕時計で時刻を確かめる。
「十時出発だと言ったんだろうな?」
マギーはうなずく。
「だったら」デイヴィッドは座席に腰をおろす。「あと五分待って来なければ、ほかの連中と一緒にフェリーに乗って帰ってもらうとしよう」
機長が飛行場でジェット機の翼の裏を確認しているのが、丸い機窓から見える。機長はアルミニウムのなめらかな翼に目を凝らしてから、ゆっくりと胴体のほうに歩きはじめる。
マギーのうしろでJJが口を少し開いて、眠ったまま姿勢を変える。マギーは毛布を掛けなおし、息子の額にキスをする。寝ているときのJJはいつも心配そうな表情をしていると思う。
座席の背もたれの向こうに目をやると、機長がふたたびジェット機に乗りこむところだ。握手をしに機長がやってくる。クォーターバックを務められそうな背丈があり、軍隊で鍛えたような体つきをしている。
「ようこそ、みなさま。本日の短いフライトにおつきあいください。弱い風が吹いておりますが、たいへん良好な運行をお約束できると思います」
「外に出ているところをお見かけしたけど」マギーが声をかける。
「目視による通常の点検です」と機長は答える。「フライトのまえに毎回おこなうことになっているのです。機体状況にも問題はございません」
「霧はどうなのかしら?」とマギー。
レイチェルが目をぐるっとまわす。
「当機のような精度の高い機においては、海霧が飛行の阻害要因とはなりません」機長は乗客に告げる。「海抜数十メートルまで上がれば、霧を抜けられるでしょう」
「ということなら、このチーズでもつまむとするかな」とベン。「音楽でもかけたほうがいいかね? テレビにするか? レッドソックスがボストンでホワイトソックスと試合をやってるだろう」
エマが機内のエンターテインメント・システムでその試合が視聴可能かどうかを調べる。各自が座席に落ち着き、荷物を納めるのにしばらくかかる。操縦室ではパイロットたちが離陸まえの計器の最終点検を始める。
デイヴィッドの携帯電話がまた鳴りだす。発信者を見て、彼は顔をしかめる。
「よし、もういいだろう」と、そわそわしながら言う。「これ以上、画家のために使う時間はない」
デイヴィッドはエマに向かってうなずく。エマがやってきてキャビンの扉を閉める。操縦室の機長にはテレパシーでもあるのか、同時にエンジンをかける。「待ってくれ!」と、乗降扉が今しも閉まろうとしたとき、男の叫ぶ声がする。
タラップを昇ってくる最後の乗客のせいで機体が揺れる。意に反してマギーの顔が火照る。なにかを期待するようなうずきが下腹に走る。その男、スコット・バローズが姿を現わす。歳のころは四十代なかば、顔を真っ赤にして息を切らしている。髪はぼさぼさで、白いものがまじりかけているが、肌はすべすべだ。ケッズの白いスニーカーに不透明水彩(グワッシュ)絵の具がついている。薄められた白と夏空の青。片方の肩に引っ掛けたダッフルバッグは暗い緑。身のこなしにはまだ、ほとばしる若さの名残があるものの、目尻には深い皺が刻まれている。
「申し訳ない。タクシーがなかなかつかまらなくて、結局バスに乗ってきたんです」
「とにかく、たどり着いたわけだ」デイヴィッドは乗降扉を閉めるよう副操縦士に合図を送る。「肝腎なのはそこだよ」
「お荷物をおあずかりいたしましょうか?」エマが訊く。
「え?」スコットは訊き返す。客室乗務員が音もたてずに自分のそばまで来たことに一瞬驚く。「いや、持っています」
エマは空いている座席を手振りで示す。そこへ向かって歩きながら、スコットははじめて機内の様子を目に収める。
「すごいな、これは」とつぶやく。
「ベン・キプリングです」ベンが立ち上がり、スコットに握手を求める。
「どうも。スコット・バローズです」
スコットはマギーを一瞥して、柔和わな笑みを顔に広げる。「ありがとう、あらためてお礼を言います」
マギーは顔を赤らめて微笑む。
「お礼なんて。どうせ空いていたんですもの」
スコットはサラの隣に座る。シートベルトも締めないうちに、エマがワインのグラスを差し出す。
「ああ、それは遠慮しとく。ええと──水をもらえますか?」
エマは笑顔で応じて引き返す。
スコットはサラのほうを見る。
「あなたはこういう旅に慣れていらっしゃるんですか?」
「正直な方ですこと」とサラ・キプリングは応じる。
エンジン音が鳴り響く。マギーはジェット機が動きだすのを感じる。メロディー機長の声がスピーカーから流れる。
「ご搭乗のみなさま、ただいま離陸の準備にはいっております」
マギーは子どもたちふたりに視線をやる。レイチェルは片脚を座席の上で曲げ、ヘッドフォンから流れる曲に合わせて体をくねらせている。小さなJJはまえかがみに体を丸め、口を半開きにして眠りこけている。子どもならではの忘却の寝顔だ。毎日、刻一刻と母性愛が自分のなかで膨らんで、はち切れそうになっているのを感じる。レイチェルとJJ、この子たちは自分の命だ。自分を証明するものだ。マギーはもう一度、息子の毛布を整える。そのとき、機体がふわりと浮かぶあの瞬間が訪れ、ジェット機の車輪が地面を離れる。ありえない希望を生み出すこの動きが、人間を下へ引こうとする物理法則によるこの一瞬の宙ぶらりんが、彼女を元気づけ、そして恐れさせる。これから飛ぶのだ。自分たちは飛ぼうとしているのだ。ジェット機が白い霧のなかを上昇する。彼らは言葉を交わし、笑い声をあげる。一九五〇年代の歌手が歌う優しいバラードと、打者が打席についたあとの長いホワイトノイズをBGMにして。十八分後、この機が海に突っこむとは、だれひとり夢にも思わずに。
***
この飛行機の墜落が全米を揺るがせる事態となることに――。はたして何が起き、そして何が起きなかったのか?
この続きははぜひ本篇でお楽しみください!
お買上げは全国書店またはネット書店にて ※文庫版・ポケット判の内容は同一です
【文庫版】
amazon 上/下
楽天ブックス 上/下
紀伊國屋書店ウェブストア 上/下
セブンネットショッピング 上/下
honto 上/下
【ポケット判】
amazon
楽天ブックス
紀伊國屋書店ウェブストア
セブンネットショッピング
honto
***
ノア・ホーリー著/川副智子訳
『晩夏の墜落』は2017年7月6日発売
ハヤカワ・ミステリ版 2200円+税
ハヤカワ・ミステリ文庫版 (上下)各760円+税
著者紹介
ノア・ホーリー Noah Hawley
1967年生まれ。アメリカの小説家、脚本家、映像プロデューサー。1998年に小説家としてデビューした後、00年代から主に映画・TVドラマ界においてもマルチな才能を発揮して活躍。『BONES―骨は語る―』『レギオン』などの作品の脚本・プロデューサー・演出を担当している。特に製作総指揮を担当したドラマ作品『FARGO/ファーゴ』はエミー賞、ゴールデン・グローブ賞を獲得するなど絶賛を浴びた。2017年、本書『晩夏の墜落』でアメリカのミステリ小説界最高の栄誉であるアメリカ探偵作家クラブ賞最優秀長篇賞を受賞。今もっとも注目すべき世界的なクリエイターである。