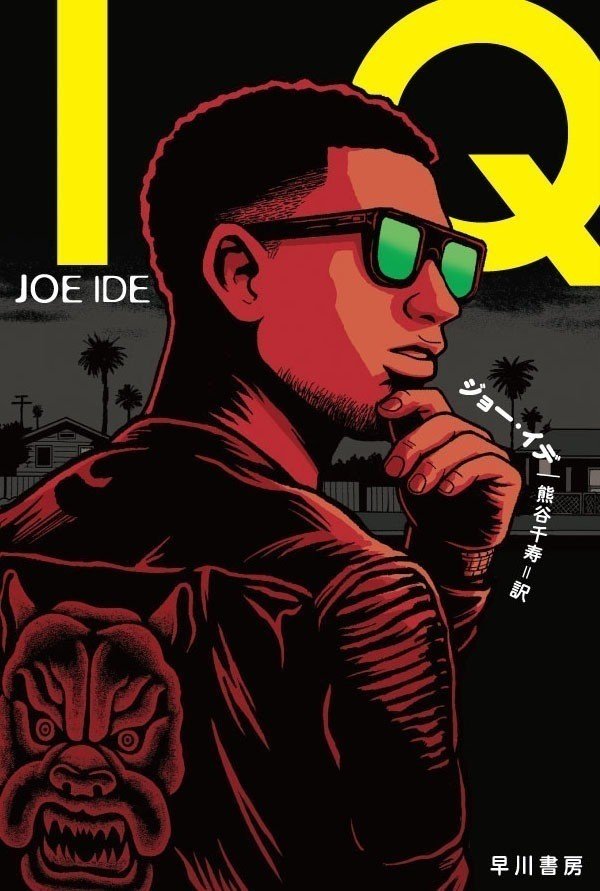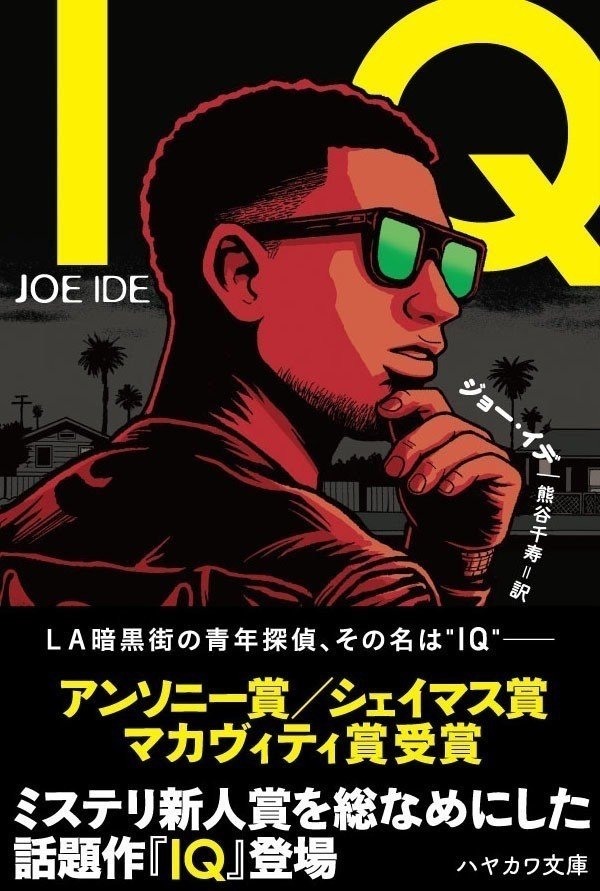特集 ジョー・イデ『IQ』③探偵アイゼイア・クィンターベイ登場――冒頭試し読み掲載(1/3)
好評発売中のミステリ『IQ』より、冒頭部分の試し読み第一弾を掲載します!
プロローグ
ボイドは学校の向かいにトラックを駐め、チャイムが鳴るのを待っていた。外の気温は三十五度近くで、運転席の空気は墓の中のように息苦しくよどんでいる。汗がボイドのフィッシング・キャップに黒い染みをつくり、だらだらと顔に垂れ、目に入り、日焼けした肌にしみた。いくらかでもましになるかとTシャツの襟を揺すったものの、腋の下から饐えたにおいが押し寄せて思わず笑ってしまった。
ボイドはさっきまで何時間もバスタブに入っていた。濁った生ぬるい湯から頭を出し、手立てをイメージした。〝くそ、なんてばかだ。ほかの手を考えろ、ボイド。どうした、どうしたんだよ、くそ、ばかなまねはよせ〟
前歯を折ったとき、すぱっとやめようかと思った。キッチンでクロロフォルムをつくろうとしていて折ったのだ。クロロフォルムは医者か研究者でもなければ買えないが、オンラインでつくりかたを見つけた。必要なのはアセトンとプール用の薬品だ。そいつらを混ぜるだけだから簡単だが、ガスを吸い過ぎて気絶し、床にくずおれるときに歯をシンクにぶつけてしまった。
その後、ふらつきが収まると、出血した歯茎の痛みを和らげるために〈チャンキーモンキー〉のアイスクリームをいくらか食べながら、もし女の子に怖がられなかったり、笑われたり、冗談だと受け取られたりしたらどうしようと思った。歯医者に診てもらうことも考えたが、腸の中でいらいらと闇雲に暴れている、飢えたサナダムシのような欲求が先決だ。ふたつ目のパイント容器入りチャンキーモンキーを半分くらい食べたころ、腹が立ちはじめた。歯が一本折れたからってどうした? もともと気味悪い面(つら)だ。口は大きな丸顔に引いた波線のようで、残っている歯はぎざぎざ、コーヒーの染みがついている。黒いボタンみたいな目は離れ過ぎている。首から下はまるで卵の形だ。
十一歳のとき、ヨランダといういかれた少女とそのサッカー仲間から脚が痣だらけになるまで蹴られているあいだ、ボイドはくそったれの卵野郎(ハンプティ・ファッキング・ダンプティ)とののしられた。〝ハローーー、ヨランダ〟なんていってこないで、とヨランダに注意されていたが、結局いってしまう。トレードマークみたいなもので、人が嫌がるとわかっていても、やってしまう。〝ハローーー、アーネスト。ハローーー、ラキーシャ。ハローーー、ミスター・ブリーカーマン〟
ボイドは今でも人をいらつかせる。リーグ戦の夜、レーンの先にあるのがなんなのか思い出そうとしているかのようにピンを見つめながらラインに立っていると、チームのみんなが不満の声を上げ、〝ボイド〟といい、早く投げろ、ボケ、とニックがいう。ようやくボールを投げるが、指がなかなか抜けずにボールが宙を飛んでレールの上を跳ねたり、ガーターに落ちたり、六番ピンにだけ当たったりする。そんなときには脇で拳を握りしめて〝ファーーーック〟と声を上げたあと、ボイドは打ちのめされるとそれしか話せないかのように、〝どうした、ボイド、どうしたんだよ!〟と呟きつつ、足を踏みならして座席に戻るが、〝どこを狙ってんだ、アホ、空でも狙ってんのか?〟とニックにいわれる。そのひと言でみんな笑う。
チャイムが鳴った。ボイドはハンドルをボンゴのように叩き、子供たちが校舎から続々と出てくる様子を見ていた。バックパックを背負い、携帯を指でいじり、ふざけ合い、猿のように金切り声を上げている。〝アキーム! こっちだぞ、おい! マジか、頭おかしいんじゃね! メッセージ送れよ? 忘れんなよ!〟。子供たちが発散しているエネルギーにはじめこそぞくぞくしたが、じきに腹が立ち、悲しくなった。眼鏡にかなう少女がひとりもいない。好みより歳上だったり、体が大きかったり、大人びていたり。〝どうした、どうしたんだよ、誰かいるはずだろう〟。そして、見つけた。かわいいやせっぽち。三つ編みにした長い髪が腰下まで届き、笑い声は祖母宅の玄関にあった風鈴の音に似ている。少年たちがその子の気を引こうと、手で突つき合っている。
誰かがその子の名を呼んだ。「カーメラ! カーメラ! あたしたち行くからね?」
カーメラという名前か。
ボイドは薄汚いアパートメントに帰り、風呂に入った。あの子が暗がりで目を覚ましたら、口がダクトテープでふさがれ、抜けた歯の隙間から漏れるボイドの熱い吐息が聞こえ、冷たい光を放つ黒いボタンのような目が見える。そのとき、あの子の目にどんな恐怖が浮かんでいるのだろうか、とボイドは死体のように湯船に浮かびながら考えた。
〝ハローーー、カーメラ〟
1 無許可のもぐり 二〇一三年七月
芝生が刈りそろえられ塗装が真新しく、玄関が少し変わっている点を除けば、アイゼイアの自宅は街区(ブロック)のほかの家とよく似ていた。防犯用の網戸は、ロング・ビーチの警察署でクラック常用者や銀行強盗を留置するところに使われているものと同じ頑丈(ヘビー・デューティー)なメッシュでできている。玄関のドアにはクルミ材の薄板が張ってあるが、その内側には二十ゲージの鉄板が挟まれ、鋼鉄の枠で固定され、さらに、こじあけも打ち壊しも突き通しもできないメデコ・ダブル・シリンダー・ハイ・セキュリティー・マクサム・デッドボルトがついている。こういうものをすべて突破するには、本格的な電動工具が必要となるし、突破しても、どんなところに足を踏み入れてしまうかわかったものではない。噂では、罠が仕掛けてあるらしい。新車で買って八年になるアウディS4が私道(ドライブウェイ)に駐まっている。ダークグレーの小さくて目立たない車だが、大型のV8エンジンを積み、スポーツ・サスペンションがついている。近所の少年たちには、リムくらいつけろよとしきりに声をかけられる。
アイゼイアがリビングルームでマックブックのメールを読みつつ、二杯目のエスプレッソを飲んでいると、車の防犯アラームが鳴った。コーヒー・テーブルから折り畳み式の警棒を素早くつかみ取り、玄関に行ってドアをあけた。デロンダがワールド・クラスの巨尻をボンネットにもたせかけ、ヘッドライトからフロントグリルの一部までを覆い隠していた。デブ女(ビッグ・ガール)ではないが、男物の短パンと二サイズばかり小さ過ぎるピンクのチューブ・トップという格好では、かぎりなくそれに近い。水色の爪に付いているきらりと光るものを見て顔をしかめ、何度も溜息をついたりと、すねたふりをしている。アイゼイアは午後のぎらつく光が目に入らないように片手を掲げ、アラームを消した。
「連絡しなかったのは番号を忘れたからじゃない」アイゼイアはいった。「連絡する気がなかったからだ」
「少しも?」デロンダがいった。
「おまえは子供の父親にしてもいい男を探してるだけだし、おれがそうならないこともわかってるんだろ」
「あたしが何を探してるかなんて知らないくせに。だったとしてもあんたじゃないわ」ただ、デロンダはたしかにいくらかカネを出してくれそうな男を漁っているし、それがアイゼイアでもかまわない。まあ、でも、アイゼイアを前にして落ち着かなくなっている。誰だって落ち着かなくなる。こっちの芝居を見抜いて、その理由を探っているかのようにじっと目を向けられたら。顔はふつうで、不細工ではないけれど、クラブやパーティーで人の目を引くことはほとんどない。身長百八十ちょっと、痩せぎす、首飾りの鎖も耳のスタッドもつけず、時計はアルミのフライパンのような色。刺青を入れているのかもしれないけど、デロンダの見えるところにはない。この前ばったり出会ったときも、今と同じ服を着ていた。水色の半袖シャツ、ジーンズ、ティンバーランドの靴。あの目は好き。アーモンド形で、まつげが女の子みたいに長い。「中に入れてくれないの?」デロンダがいった。「ママの家からここまでずっと歩いてきたのよ」
「噓をつくのはやめろ」アイゼイアはいった。「どこから来たのかは知らないが、おまえが歩いてきたんじゃないことはわかっている」
「どうしてわかるの?」
「おまえのママはマグノリアの向こう側に住んでいる。この炎天下にサンダル履きで、外反母趾まで抱えているのに、十キロ以上も歩いてきたというのか? ティーシャに車で送ってもらったんだろ」
「何でも知ってると思ってるのね。誰が送ってくれたかなんてわからないくせに」
「おまえのママは仕事、ノナも仕事、アイラはまだ足にギプスをはめている、デショーンはこの前の酔っ払い運転(DUI)で免許取り消し。押収車両保管場であいつの車を見た。フロント部分が壊れた白のニッサンだろ。残ってるのはティーシャだけだ」
「アイラが足にギプスをはめてるからって、運転できないとはかぎらないじゃない」
アイゼイアは戸口に寄り掛かった。「歩いてきたといっていたような気がするんだが」
「ちゃんと歩いてきたわよ」デロンダがいった。「まあ、途中までだけど。そしたら、ある人が通りかかって──」デロンダがボンネットから尻を下ろし、足を踏みならした。「ほんとむかつくわね、アイゼイア!」デロンダがいった。「どうしていつも人をむかつかせるの? 仲良くしようと思って来ただけでしょ? どうやって来たかなんて関係なくない?」
まったく関係ないが、どうしても彼にはいろいろと見えてしまう。ちがう点、おかしな点、辻褄が合わない点。あるいは、辻褄など合うはずがなかったり、相手のいっていることとちがうはずなのに、バッチリ合っている点。
「それで?」デロンダがいった。「あたしをここに立たせっぱなしにして、熱射病にさせるつもりなの? 中に入れて、カクテルでも注いでくれないの? ひょっとして、いいことが起こるかもしれないわよ」
デロンダは彼女の足首のあたりに目を落とし、横に何かがくっついているかのように足首の側面を見た。アイゼイアの目がこっちに向いているのかとでも思っているのだろう。カリフォルニアの日差しを受けてきらめくダーク・チョコレート色の太股か、チューブ・トップから懸命にこぼれ出そうとしているチョコレート色のおっぱいか。ふたりにこれから何が起こるのかわからずに気まずくなり、アイゼイアは目を背けた。デロンダはアイゼイアのタイプではない。好きな女のタイプがあるわけでもない。性生活はもっぱら好奇心から転がり込むセックスだ。薄気味悪いくらい頭がいい控え目な男に引かれる女ばかり。ここのところはご無沙汰だが。アイゼイアは網戸をあけた。
「まあ、なら入れば」アイゼイアはいった。
アイゼイアは安楽椅子に座ってメールを読み直した。見逃していたメールはないものかと期待しながら。カネになる仕事が必要だが、届いているのはそんなものとはほど遠い。
やあ(オラ)、セニョール・クィンターベイ
おれはベニートの友だちだ。あんたは信用できると聞いた。職場のやつ がしつこく脅迫してくるんだ。カネをよこさないと、おれがグリーンカードを持ってないことを入国帰化局にばらすと。そうなると息子は学校にも通えない。力になってくれないか?
愛なるミスター・クィンターベイ
夜遅くにベッドで寝ていると、男が入ってきてわたしの大事なところを触ってくるようなんです。朝、ナイトガウンがめくれ上がっていて、下半身におかしな感覚が残っているんですから、きっとそうです。このことは人にはいわないでください。前にばかにされたので。日曜日、教会に行ったあとで来てくれませんか?
アイゼイアはウェブサイトも、フェイスブック・ページも、ツイッター・アカウントも持っていないが、なぜか人はアイゼイアを見つける。アイゼイアは警察が手を出せない、あるいは出さない地元の事件を優先的に引き受けている。処理しきれないほどの仕事があるものの、依頼主の多くは、サツマイモのパイとか、庭掃除とか、一本の真新しいラジアル・タイヤなどで仕事の報酬を支払う。支払わないやつもいるけれど。日当を払えるクライアントなら、ひとりで食っていけて、フラーコの費用の足しにもなるのだが。
「ちょっと」冷蔵庫の中のフィジー・ウォーターとクランベリー・ジュースを見て、デロンダがいった。「飲み物は何もないの?」
「そこにあるものだけだ」アイゼイアはリビングルームからいった。
つまみもない。プレーン・ヨーグルトを使ったレシピを知っていたら、デロンダは何かを混ぜていたかもしれない。プラム少々、M&Mなしのトレイルミックスひと袋、〈アイ・キャント・ビリーブ・イッツ・ノット・バター!〉、表面に細かいシリアルがまぶしてあるパン、平飼い卵(ケージ・フリー・エッグズ)とかいうよくわからないもの。カウンターに複雑な機械があった。ステンレス・スチール製で大きさは電子レンジくらいだが、把手やボタンがついていて、ソーダ・マシンのような格子網の真上にふたつの蛇口が垂れ下がっている。やたら小さいコーヒー・カップと小さな金属のピッチャーが、格子網に載っている。「これがあんたのコーヒー・マシン?」デロンダがいった。
「エスプレッソだ」
「もっと大きいカップが要るんじゃないの」
アイゼイアはメールを読み続け、プラムのように熟れておいしそうなデロンダのことは考えないようにした。しかたなくディーゼルのパンツのジッパーを上げたままにしていた。楽な決断ではなかった。もしデロンダと寝たりしてみろ、夜に帰ると彼女がペットのアレハンドロをフライにして食べながら『アイドル』を見ているそばで、彼女の三歳の息子がここをめちゃくちゃにしている場面に出くわすことになる。アイゼイアがデロンダに服を脱ぐんじゃないぞというと、デロンダは腹を立てたというより、驚いていた。
「何を逃したかわかってないわね」デロンダがいった。「あたし、すんごいのよ」
親愛なるミスター・クィンターベイ
娘が二週間も家に帰っていません。娘の相手にしては歳を食い過ぎているオレン・ウォーターズという男と駆け落ちしたようなのです。手遅れにならないうちに、そいつから娘を取り戻さなければなりません。連れ戻していただけませんか? あまりお金は出せませんが。
親愛なるミスター・クィンターベイ
二カ月前、わたしのかわいい息子ジェロームが自分のベッドで撃ち殺されました。警察は逮捕できるだけの証拠がないといっていますが、妻のクローディアが引き金を引いたのはみんな知っています。あなたを雇いたいのです、ミスター・クィンターベイ。あの女に裁きを受けさせたいのです。
リビングルームはひんやりとほの暗く、柔らかい陽光と影の帯が防犯の鉄格子越しに伸びている。ここは埃が宙に舞ってさえいないほどきれいだ。アイゼイアが顔を上げると、デロンダが素足でぺたぺたとオープン・キッチンから出てきて、磨き上げられたセメントの床を横切った。床は予想とはちがった仕上げになったが、気に入っている。熱帯雨林の衛星写真のような、形にならない灰色と緑色のまだら模様。デロンダがアイゼイアの向かいのソファーに腰を下ろし、両足をコーヒー・テーブルにのせた。ガラス天板には、車のキー、携帯電話、ハーバード大学のロゴ入り帽子、折り畳み式の警棒が散らばっている。
デロンダがテーブル下の黒い箱に気付いた。「これは何?」デロンダがいった。何かの仕掛けかもしれないと思っているようだ。
「サブウーファーだ。コーヒー・テーブルから足をどけろ」
「誰がハーバードに行ってたの?」
「誰も」
「テレビを観ちゃだめ?」
「テレビがあるように見えるのか?」
「プレイステーションもないの?」
「ああ、プレイステーションもない」
「もっと家具が要るんじゃないの」
バーガンディー色の革張りソファーと肘掛け椅子をのぞくと、クロム・メッキとガラスのコーヒー・テーブル、ラッカー塗装の籐のオットーマン、サクラ材のサイド・テーブル、アンティーク風のロングネック読書ランプ。床から天井まで壁一面を占める本棚を含めなければ、それだけだ。バーコードのようにきれいに並んでいるLPやCDの膨大なコレクションと凝ったステレオがある。とげとげしくしわがれたコルトレーンのサックスが、スピーカーからがなり立てている。
「ちがうレコードをかけていい?」デロンダがいい、生ごみ処理機の音でも聞いているかのように顔をしかめた。
「だめだ」
アイゼイアはうつむき、別のメールを読んだ。デロンダは頼みごとがあるようだ。中に入れてすぐにそんな気配を感じていた。その目つきが、必要なのは都合のいい男だけではないと物語っていた。セックスをパスしたせいで切り出すきっかけを逃したらしく、今では、デロンダがタイミングを見計らいながらソファーでもぞもぞし、頬をきしらせる音さえ聞こえるほどだ。しばらく相手にしなければ、先に折れてくれるかもしれない。
「ひとつお願いできないかな?」デロンダがいった。
「だめだ」
「ちょっとさ、紹介とかしてくれないかな?」
「紹介って、誰に?」
「ブラーゼイに。けっこう親しいんでしょ」しばらく間を置いてから、デロンダがいった。「IQ」
《ザ・シーン》誌にこんな見出しの記事が躍ったことがある。
IQ アイゼイア・クィンターベイは無許可のもぐり
記事は近隣で発生した数多くの事件を詳述しているが、タブロイド紙に載ったのはいちばん楽に解決できた事件だった。R&Bシンガーのブラーゼイ絡みだ。パーティーの最中に何者かがブラーゼイのカメラを盗んだ。その中には、ブラーゼイがアイロン台に身を乗り出し、同居しているキーボード・プレーヤーにうしろからスパンキングされている動画が入っていた。それが表に出れば、ただのスキャンダル以上の騒ぎになる。ブラーゼイは〝ノーマル〟なセックス・シンボルとして売り出していた。最新アルバム『太さを確かめさせて(キャン・アイ・ウィットネス・トゥ・ユア・シックネス)』のカバー・アートでは、ひも状ビキニと神父の詰襟といういでたちのブラーゼイが、いかれたブロンドのかつらと丈の短い聖歌隊ローブを身に着けた、赤ん坊でも入っているのかと思えるほど尻が突き出た女三人の聖歌隊を率いている。ブラーゼイはこんな脅迫状を受け取った。〝こっちの要求は追って知らせる。呑まなければ、おまえの罪(トランスグレッション)を明かし、キャリアを潰す〟
「言葉遣い」アイゼイアはいった。「〝おまえの罪(トランスグレッション)を明かす〟。聖書の言葉です。客の中に信心深い人はいませんでした?」
「いない」ブラーゼイがいった。そして、大きく息をした。「でも、ぼくの母親は信心深い」
ブラーゼイの母親はジョージアの小さな街の生まれで、原理主義のバプティスト派だった。アイゼイアが問い詰めると、母親はブラーゼイのカメラでバラ園の動画を撮ろうとしたところ、息が止まるほどびっくりしたのだと白状した。気を落ち着けて、カノコソウ根のお茶を飲んだあと、罪悪の暮らしから抜け出るように息子を脅迫することにした。
「ぼくはこういう人間なんだ、母さん」ブラーゼイがいった。「でも、ぼくだって自分自身を受け入れられないんだから、母さんが受け入れられなくても不思議はないよ」
ブラーゼイはこんなひとときをもたらしてくれたといってアイゼイアに感謝したが、アイゼイアは脅迫状を読む以外に何をしたのかわからなかった。ブラーゼイは『ザ・ションダ・シモンズ・ショー』でカミングアウトした。アルバムの売り上げには響いたが、アルバムを買った人々は、オンラインで三十九ドル九十五セントで売られているセックス・テープを買った。収益の半分は母親の教会に寄付された。
「ブラーゼイにあたしのキャリア・アップの手伝いをしてほしいの」デロンダがいった。「彼はゲイかもしれないけど、セレブだし、ちょっと手を貸してもらえればいいの。だってさ、上のほうで顔が売れさえすれば、お偉方はあたしのスタイルを間近でじっくり見られるでしょ? だから大ヒットまちがいなし」
デロンダがこっちを見ていて、時間の問題だなとか、あきらめるなよとか、そんな戯言(たわごと)を待っているのはわかっているが、アイゼイアは目をマックブックに落としたままにしていた。デロンダがふくれた。今度は芝居ではなかった。「あたしにはこんなスター性があるんだから、とっくの昔にここから出ていかなきゃいけなかったのよ」デロンダがいった。「期待の新人っていうの? セレブになる星のもとに生まれたんだもの。とっくにスポットライトを浴びてなきゃいけなかったのに」
「スポットライトを浴びて──どうなる?」アイゼイアはいった。
「どうなるってどういうこと? あのキム・カーダシアンって子のお尻はあたしのにはかなわないのに、どうなるかだなんて。あの子が去年三千万ドル稼いだって知ってる?」
アイゼイアはほかにもそう思っている女を知っていた。でかいケツをしているのが、不動産を所有しているとか大学の学位を持っているのと同じで、職探しのときに履歴書に書けるようなものだと信じきっている。
ペットのアレハンドロが頭をひょこひょこ動かし、床をくちばしで突つきながら廊下からペタペタやってきて、赤いビーズのような目でデロンダを一瞥した。デロンダが怯えた様子で足を床から持ち上げた。「そんなのに家の中を歩き回らせてるの?」デロンダが訊いた。
「おまえがちょっかいを出さなけりゃ、あいつもちょっかいを出さない」アイゼイアはいった。
アイゼイアは仕事の報酬としてミセス・マルケスからアレハンドロとアロスコンポーリョ(鶏料理)のレシピをもらった。鶏の糞の始末は好きになれないが、床に染みがつくわけでもないし、鶏を一日中ガレージに閉じこめておくのは気が引けた。ある朝、ベッドルームのドアを閉め忘れていたら、アレハンドロがクローゼットのバーに止まって、服という服に糞を落としていた。
「お願いよ、アイゼイア、力になって」デロンダがいった。「ちょっと手を貸してくれるだけでいい」
「手を貸すのはおれの仕事じゃない」
「それはまちがいよ、アイゼイア」
「おれは毎日まちがう」アイゼイアはいった。ラップトップを閉じ、車のキーと折り畳み式警棒を持ち、ハーバードの帽子をかぶると、立ち上がった。
「どこかへ連れていってくれるの?」デロンダがいった。
「ああ。家まで送ってやるよ」
(次回更新につづく)
本noteでは『IQ』を特集中。今後の更新をどうぞお楽しみに!
【書誌情報】
タイトル:『IQ』
原題:IQ
著者:ジョー・イデ
訳者:熊谷千寿
本体価格 : 1,060円+税/発売中
ISBN : 9784151834516
レーベル名 : ハヤカワ・ミステリ文庫