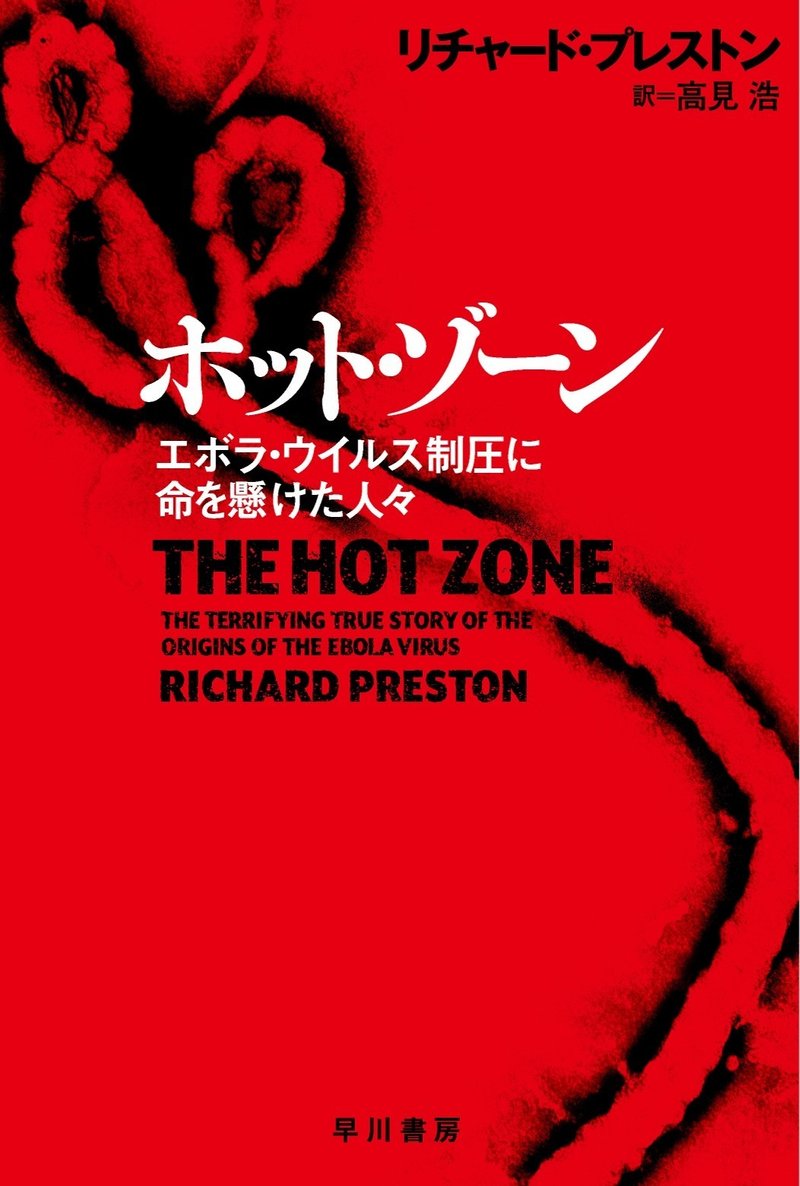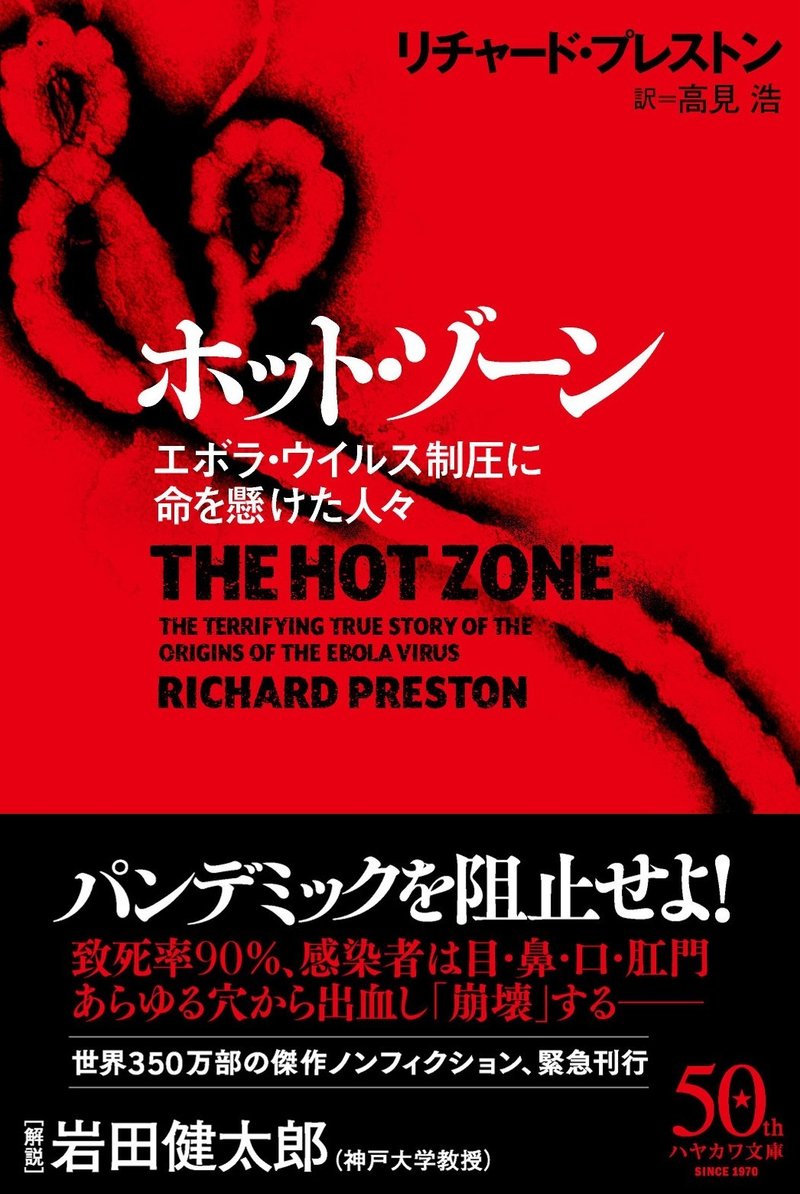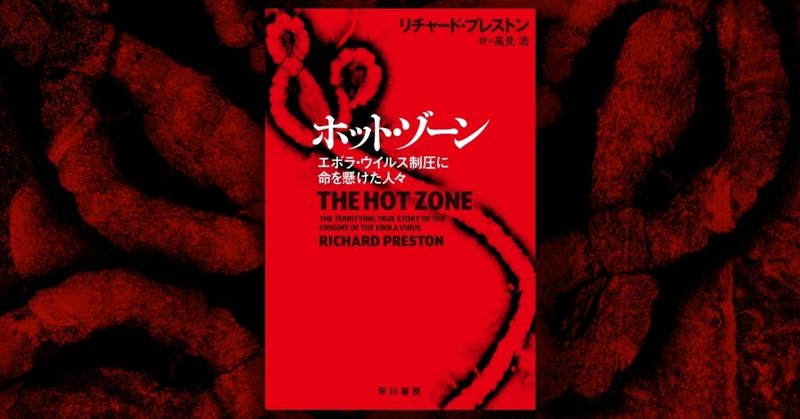
”ホラーの帝王”スティーヴン・キングに「人生で読んだ中で最も恐ろしい」と言わしめた、『ホット・ゾーン』第1章「森の中に何かがいる」先行公開
ウイルス・ノンフィクションの名作、リチャード・プレストン『ホット・ゾーン』が5月22日(金)に早川書房より緊急文庫化。『IT』『シャイニング』などで知られる”ホラーの帝王”スティーヴン・キングは、本書にこんな賛辞を寄せています。
「本書の第1章は、私が生まれてこのかた読んだ最も恐ろしいものの一つである──しかも、その恐怖は章を追うにつれて深まってくる。驚嘆すべきはその点だ。恐怖はいや増す一方なのだから。実際、なんと稀有なノンフィクションだろう。貪るように読み終えたいま、ここに描かれた事実はこの先長く自分の脳裡から離れないだろうという予感がしている」
本記事ではこの第1章を全文公開します。本当にすさまじいですが、名作の名作たるゆえんをご堪能いただければ幸いです。
***
森の中に何かがいる
1980年1月1日
シャルル・モネは孤独なフランス人だった。彼はヌツォイア川沿いに広がるケニア西部の大農園、ヌツォイア砂糖工場私有地内の小さなコテッジで、一人暮らしをしていた。その付近一帯からは、アフリカ大地溝帯の端にそそり立つ高さ一万四千フィートの死火山の巨峰、エルゴン山の威容を仰ぎ見ることができる。
モネがなぜアフリカにやってきたのかは、定かでない。アフリカに流れ着く多くの祖国放棄者の例に洩れず、彼の経歴にも曖昧な面がすくなからずあるからだ。母国フランスで何らかのトラブルに巻き込まれたのが原因だったのかもしれないし、ただ単にケニアの美しい風土に魅かれたのかもしれない。彼はアマチュアの博物学者で、小鳥や動物たちを愛していた。が、人間はあまり好きではなかったらしい。このときの年齢は五十六歳。中肉中背で、なめらかな茶色い髪の優男だった。彼と格別親しかったのは山の麓の町に住む女性たちに限られていたようだが、その女性たちにしても、後に彼の死因を調査した医師団に対して、彼の人となりの多くを語ることはできなかった。
モネの仕事は、ヌツォイア川から汲みとった水を広大な砂糖きび畑に送りだす水道ポンプ装置の管理だった。人々の証言によれば、彼は一日の大半を川のたもとのポンプ小屋ですごしていた。機械の作動する様を見たり、その音に聞き入ったりするのが楽しかったらしい。
こういうケースの常として、事件の細部まではっきり特定することは難しい。もちろん、彼の示した症状は医師たちが鮮明に記憶している。なぜなら、“微生物危険レヴェル4”に属するホットな(危険な)ウイルスに感染した人間の症状を一度でも目にした者なら、それを忘れることなど不可能だからだ。が、それらの症状が次々に積み重なっていくうちに、それを患っている当人の人柄はだんだんぼやけてしまうのである。シャルル・モネのケースは冷厳な医療上の事実としてわれわれの前に現われるのだが、そこにはあたかも奇怪な色彩の異星を目の当りにするような、ついのけぞって瞬きしてしまうほど鮮明で不快な恐怖の映像もないまぜになっている。
モネがその大農園にやってきたのは、一九七九年の夏だった。ちょうど、エイズを惹き起こすHIV(ヒト免疫不全ウイルス)が中部アフリカの熱帯雨林から姿を現わして、人類を汚染させてゆく長い旅路の緒についた頃である。エイズはすでにそのとき、中部アフリカの住民たちの上に黒い影を落していたのだが、その存在をはっきり認識している者はまだ皆無だった。それはキンシャサ・ハイウェイ沿いに静かに広まりつつあった。キンシャサ・ハイウェイとは、アフリカを東西に横断して、エルゴン山を見はるかすヴィクトリア湖岸沿いを通過する大陸横断道路である。HIVは、致死性こそかなり高くとも伝染性はさほどでもない“微生物危険レヴェル2”に属するウイルスだ。それは容易には伝染しないし、空気感染もしない。HIVに感染した血液を扱うに際して、バイオハザード(微生物災害)用防護服を着る必要はないのだ。
モネは毎日ポンプ小屋で勤勉に働き、週末や休日ともなると砂糖工場の近くの森林地帯を訪れるのを常としていた。彼は餌を持っていって周囲にばらまき、小鳥たちや野生の動物たちがそれを食べる様を眺めては楽しんでいたらしい。動物を観察しているあいだは、完き静寂の中にいくらでもすわっていることができたようだ。モネを知る者は、彼が野生のサルに並々ならぬ愛着を抱いていたことを記憶している。彼はサルを手なずけることができたというのだ。彼が餌を手にすわっていると、サルが近寄ってきて、彼の手から食べたという。
夜になると、彼は自分のコテッジに閉じこもった。ジョニーという名の家政婦を雇っていて、家の中の清掃や食事の準備は彼女に任せていた。彼はアフリカの各種の鳥の識別法を自己流で習っていた。家の近くの木にハタオリドリの集団が棲みついていて、彼らが袋のような巣作りをする様を、飽きずに観察してすごした。クリスマスを目前にしたある日、彼は病気にかかった小鳥を自宅に持ち込んだことがあったという。それは彼の掌の上で死んだらしい。断定はできないが、その小鳥はハタオリドリだったかもしれず、死因は“微生物危険レヴェル4”に属するウイルスによる感染だったかもしれない。それはだれにもわからない。モネはまたカラスとも仲が良かった。それはアフリカの人々がよくペットにする、白と黒のマダラカラスだった。とても人なつこく頭のいい鳥で、モネの小屋の屋根にとまるのを好み、彼が出たり入ったりするのを眺めていた。腹を空かしたときにはヴェランダに降りて、家の中に入ってゆくこともあっただろう。モネはテーブルに散らばった食べ物のかけらを、やはり手から与えていたかもしれない。
彼は毎朝砂糖きび畑を歩いて仕事に通った。二マイルの道のりだった。そのクリスマス・シーズン、畑は砂糖労働者の手で焼かれていたので黒く焦げていた。黒焦げの畑の北、二十五マイルの彼方にはエルゴン山の二つの峰が見えた。雨と陽光、天候の変転と共に山は絶えずその貌を変え、アフリカの光と影の饗宴を演じて見せた。暁のエルゴン山は、押しつぶされたような灰色の尾根が麓から迫る靄に包まれ、二つの峰を備えた頂上が截然たるシルエットを刻む。二つの峰は、侵食された噴火口の相対する縁なのだ。日が昇るにつれて山は麓の雨林の色、銀色がかった緑色を帯びる。そして昼が近づくと共に雲が現われて山容を隠してしまう。やがて日が午後に移ろい、夕暮れどきになるにつれて雲が厚さを増してゆく。もくもくと湧きあがった雲は雷雲に変じたと見るまに、音もなく稲光りがひらめく。雲の底は炭の色だ。一方、上層の気流に向かって羽のようにのびた雲の上縁は夕日に照らされて鈍いオレンジ色に照り映える。その上の空は深い紺色に染まり、そこには早くも熱帯の星がいくつか瞬いている。
モネには、エルゴン山の南東、エルドレトの町に住む大勢のガールフレンドがいた。その町の住民は一様に貧しく、いまもベニヤ板とトタン屋根の小屋で暮らしている。彼はガールフレンドたちに金を与え、彼女たちはその返礼に喜んで彼と寝た。その年のクリスマス休暇が訪れたとき、モネはエルゴン山にキャンプに出かける計画を立て、エルドレトに住むガールフレンドの一人を誘って同伴した。その女性の名前を記憶している者は一人もいない。
モネとそのガールフレンドは、ランドローヴァーでエンデベス・ブラフに至る赤土の直線道路を登っていった。エンデベス・ブラフとは、エルゴン山の東面にある険しい断崖のことである。道は乾いた血のように赤い火山土に覆われていた。エルゴン山の低い山麓に達した二人は、そこからトウモロコシ畑やコーヒー農園の間を縫って、なおも走りつづけた。道はやがて動物たちが草をはむ草原に変わる。その両側に立ち並ぶユーカリの木の背後には、半ば廃墟と化したイギリス植民地時代の農園が隠されていた。なおも道を登るにつれて大気は冷たくなり、ヒマラヤスギの枝の間からカンムリワシがパタパタと飛びだした。エルゴン山を訪れる観光客は、さほど多くはない。おそらく、そのとき、その道を走っていたのは、モネとそのガールフレンドの車くらいのものだっただろう。だが、同じ道を徒歩で登っている人々は大勢いた。エルゴン山の麓で小さな畑を耕している村人たちだった。二人は熱帯雨林の入り組んだ外縁部に達し、ほんの二、三本連なった木々や島のように密集した樹林のそばを通過した。今世紀初頭に建てられたイギリス風の旅荘、マウント・エルゴン・ロッジの前も通過したが、そこはいまや修復不可能なまでに荒れはてて、暑い陽光や雨に打たれるままに壁はひび割れ、ペンキも剥げ落ちていた。
エルゴン山はウガンダとケニアの境界にまたがっており、スーダンからもさほど隔たっていない。その山麓は、中部アフリカにおける熱帯雨林の島と呼んでもいいだろう。幅八十キロに及ぶ乾燥地の上にそそり立つその隔絶した世界は、各種の樹木、竹、湿原等に隈なく覆われている。それは中部アフリカの背骨の、一つの節でもある。エルゴン山は、いまから一千万年ないし七百万年前まで火山活動をつづけていた。その間、激しい噴火によって噴き上げられた火山灰は、その山麓に生じていた森林をいくたびとなく消滅させた。休みない火山灰の堆積によって、その山頂はとてつもない高さ、おそらくは今日のキリマンジャロ山をもしのぐ高さにまで達したことだろう。
その後の長期にわたる侵食作用によって山頂が削られるまで、エルゴン山はアフリカで最も高い山だった可能性もある。その山麓の広大さという点では、いまもこの山はアフリカ一の座を保持しているのだ。太陽が東から昇るとき、エルゴン山の投げる影ははるか西方のウガンダにまで達するし、日が没すると、東方のケニアまでその影に覆われてしまう。広大なその影の中に点在する村々に住んでいるのは、草原の民、エルゴン・マサイ族の人々だ。彼らは数世紀前、北部から移住してきてこの山麓に住みつき、牛を育てて生計を立てている。エルゴン山の低部の山麓は常におだやかな雨に洗われて大気は清涼だ。火山性の土壌はトウモロコシの豊かな収穫を保証し、放牧に適した草の生育にも良いため、多数の人間の暮らしを支えてくれる。各村落は、この死火山の周囲を定住地の輪でとりまいていると言ってもいい。だが、その輪は近年、山麓の雨林の周囲に徐々にすぼまりつつある。いわば縛り首の輪のようにこの山の生態系を絞め殺しつつあるのだ。樹林は開墾され、巨大な樹木は薪をつくったり放牧地を広げるために、つぎつぎに伐採されつつある。雨林に棲む象の群も、しだいに姿を消しつつあるのが現状である。
エルゴン山のごく一部は、国立公園になっている。モネとそのガールフレンドは公園のゲートに止まって入園料を払った。当時はゲートの周辺にサル、もしくはヒヒが──そのどちらだったのか、正確に記憶している者はいない──うろつきまわって、餌を与えてくれる人間を捜していた。モネはバナナを見せて、その動物を肩にすわらせた。見ていたガールフレンドはおかしそうに笑った。その動物がバナナを食べているあいだ、二人は微動もしなかった。そこからすこし山を登ったところで、二人はテントを張った。小川に向かってなだらかに下降している濡れた草地だった。小川は原生林から勢いよく流れだしていて、不思議な色をしていた。火山灰で白濁していたのである。ケープ・バッファローに食べられるため、空き地の草は常に短く、そこかしこに彼らの糞が散らばっていた。
二人の野営地は、鬱蒼たるエルゴン雨林にとりまかれていた。節くれだったアフリカ・オリーヴの木が網の目のように密生し、蔦や苔類が枝から垂れ下がっている。その間に覗いている実は、人間には有毒だった。カサカサとサルが枝の間を飛び移る音や、昆虫の羽音が二人の耳に聞こえた。かと思うとオリーヴ・ハトがいっせいに木から飛び立って急降下してゆく。目にも止まらぬ速さで彼らが飛翔するのは、はるか上空から垂直降下して彼らの羽を引き裂いてしまうタカの一種、チュウヒの攻撃を逃れるための戦術なのである。樹木の種類も多様だった。クスノキ、チーク、アフリカ・シーダー、それに各種の赤い臭木群。ところどころ、暗緑色の葉が自然の天蓋のように森の頭上を覆っている。それはカリフォルニアのセコイアの木にも匹敵するアフリカ最大の木、ポドの木の梢なのだ。当時この山麓には何千頭という象の群がいたから、彼らがパリパリと枝を折ったり、樹皮を剥いだりしながら雨林の中を移動する音も、二人の耳には聞こえただろう。
エルゴン山の常で午後には雨が降ったろうから、二人はテントの中に留まっただろう。キャンヴァスに打ちつける雷雨の音を聞きながら、セックスもしたかもしれない。日が落ちると、雨音はしだいに遠のいてゆく。二人は火をおこして夕食をこしらえた。その日は大晦日だった。二人はたぶんシャンペンを飲んで祝ったことだろう。例によって数時間もすると雲も消え、天の川の下の黒い影のようにエルゴン山が浮かびあがった。深夜、モネはおそらく草の上に立ち、シャンペンの酔いでフラつきながらも、大きく首をのけぞらせて星を見あげたのではあるまいか。
明ければ元旦の朝だった。気温は摂氏七、八度、草は冷たい朝露に濡れていた。モネとそのガールフレンドは再びランドローヴァーで泥濘の道を登りはじめ、キタム洞窟の下の小さな谷間で車を止めた。
それから二人は、雑草を薙ぎ払いつつ渓谷を登って、キタム洞窟を目指した。オリーヴの木や草原の間を流れる小川沿いの象の道を、二人はたどっていったのである。ケープ・バッファローに出会うと危険なので、それには絶えず目を配っていた。渓谷を登りつめたところにキタム洞窟が口を覗かせており、その入口を覆うように上から水がほとばしっていた。象の道は洞窟に達して、その中に呑み込まれている。モネとそのガールフレンドも洞窟の中に入り、元日のほとんどをそこですごした。その日は雨が降っていただろうから、二人は入口に何時間もすわって、ヴェールのように上から降り注ぐ水越しに外を眺めていたことだろう。彼らが用心していたのはケープ・バッファローとミズカモシカだった。ずんぐりしたリスのような毛深い動物、ロック・ハイラックスが洞窟の入口近くの岩を駆け登ったり降りたりしている姿も、見えたにちがいない。
夜になると、このキタム洞窟にはミネラルや塩を求めて象の群が入ってくる。草原に棲む象は、硬い岩盤や乾いた水たまりなどで容易に塩分を見つけることができる。が、雨林にあっては、塩は貴重な摂取物なのである。この洞窟は、いちどきに七十頭もの象が入れるほどの広さがある。ここに入ってきた象は、立ったまま眠ったり、牙で岩壁を剥がしたりして夜をすごすのだ。そうしてこそぎ落した岩を、彼らは丹念に噛み砕き、小さな破片を呑み込んでしまう。洞窟内のそこかしこに残されている象の糞には、小さな岩の破片がたくさんまじっている。
モネとそのガールフレンドは懐中電灯を手に、洞窟の奥の探検をはじめた。洞窟の入口は巨大だが──幅、約五十メートル──奥にいくにつれてさらに広がっている。粉のように乾燥した象の糞にまみれた平らな岩盤を、二人は横断していった。進むにつれて、足元から塵がパッパッと舞いあがる。光はしだいに薄れてゆき、岩盤は徐々に上り勾配を描いてゆく。段々状の岩盤は緑色の粘ついた物体で覆われていた。それはコウモリの糞だった。洞窟の天井にとまっているオオコウモリの集団が排泄する、消化された植物の残滓が主体の糞だった。
天井の穴から飛びだしたコウモリが、懐中電灯の光芒をよぎり、甲高い鳴き声をあげながら二人の頭の周囲を飛び交った。二人のかざす懐中電灯がコウモリたちを刺激するらしく、ますます多くのコウモリが眠りからさめた。数百もの、赤い宝石のようなコウモリたちの目が、洞窟の天井から二人を見下ろした。油の切れた蝶番のドアが、いくつもいっせいにひらいたようなキーキーという音。コウモリ独特の鳴き声が、洞窟の天井に谺して走った。次の瞬間、二人の目には息を呑むような光景が飛び込んだ。そこは化石の森だったのである。洞窟の天井や壁から突き出ている、さまざまな形の鉱物化した枝。それは石と化した熱帯雨林の樹木だった──チーク、ポド、各種の常緑樹。七百万年前に起きたエルゴン山の噴火によって雨林は灰の中に埋まり、木々はオパールや石英に変身したのだった。樹木は、岩の変形した白い針のような鉱物、すなわち水晶に囲まれていた。注射針のように鋭い水晶は、懐中電灯に照らされてキラキラと輝いた。
モネとそのガールフレンドは、化石の森を電灯で照らしながら、洞窟の中をさまよった。その際モネは、石の木を撫でさするうちに水晶で指を傷つけることがなかったろうか?
二人は天井や岩壁から突き出ている石化した骨を見つけた。ワニや古代のカバ、はては象の先祖の骨。石の枝からは蜘蛛が吊りさがっていた。蜘蛛は蛾や昆虫を食べていたのだ。やがて二人は岩盤がわずかに上向いている箇所、左右の幅が百メートル以上、並のフットボール場よりも広い場所に出た。そこでクレヴァスを見つけ、その底を懐中電灯で照らしてみた。クレヴァスの底には奇妙なもの、灰色と茶色がかった何かの塊があった。それは象の子供のミイラ化した死体だった。夜間、この洞窟内を歩きまわる象たちはもっぱら触覚に頼り、鼻の先端で岩盤をさぐりつつ移動する。子象たちの中には、ときどきクレヴァスに転落してしまうものも出るのだ。
モネとそのガールフレンドは、さらに洞窟の奥深くを目指した。ゆるやかなスロープを下ると、洞窟の天井を支えていると覚しい柱の前に出た。その柱の表面には大小の溝や削り跡がついていた。いずれも、象が牙でえぐった跡だった──ここまでやってきた象たちは柱の周囲を牙で削り、その破片を噛んで塩分を摂取していたのである。このまま象たちが柱の基部を削りつづければ、いずれ柱は崩れてキタム洞窟の天井は崩落してしまうかもしれない。さらに一段奥に入ったところで、二人はもう一本の柱を見つけた。その柱はすでに崩れており、その上の天井にはビロードの塊のようなコウモリの一団がぶらさがっていた。それらのコウモリは黒い糞で柱を汚していた──洞窟の入口近くの岩盤にこびりついていた、緑色の糞とは別種の糞だった。そこにいるコウモリの群は昆虫を主食にしているため、消化された昆虫の残滓が糞に滲んでいたのだ。モネはその糞に手を突っ込んだりしただろうか?
モネと同行したこの女性は、エルゴン山へのこの旅の後、数年間行方を絶った。そのうち突然、モンバサの酒場に姿を現わした。そこで体を売っていたのである。たまたま、その後モネを診断したケニア人の医師がその酒場でビールを飲んでいて、彼女と世間話をはじめた。そこで何気なくモネの名前を出したところ、彼女は言った。「その話なら知ってるわ。あたしはケニア西部の出身なの。そのときシャルル・モネと一緒だった女って、あたしだったのよ」
医師は愕然とした。彼女の話が信じられなかった。が、その女が当事者でなければ知らないような事実まで話すに及んで、彼女が事実を述べているのだと確信した。酒場でのその遭遇の後、彼女は再び姿を消し、モンバサのスラムに呑み込まれて消息を絶った。彼女はたぶんエイズで死亡しただろう、といまでは推測されている。
シャルル・モネはその後、砂糖工場の水道ポンプを管理する仕事にもどった。彼は毎日焼け焦げた砂糖きび畑を通り、エルゴン山の雄姿を賛嘆の眼差しで眺めながら仕事に通った。エルゴン山が雲に隠れても、おそらく彼は、見えない星の引力のように自分を引きつけるものを感じていただろう。そのとき彼の体中では、何かが、それ自身の複製をつくりはじめていた。何らかの生物単位がシャルル・モネを宿主として獲得し、その体内で増殖しはじめていたのである。
頭痛はきまって感染後七日目にはじまる。キタム洞窟を訪ねて七日後──一九八〇年一月八日──モネは眼球の奥に疼くような痛みを覚えた。で、勤めを休むことにし、自宅のベッドに横たわった。頭痛はひどくなる一方だった。眼球が痛み、こめかみも痛みはじめた。痛みは頭の内部をぐるぐる回転しているようだった。アスピリンを服んでも、いっこうにひかない。そのうち背中にまで激痛を覚えるようになった。家政婦のジョニーにはクリスマス休暇を与えていたので、モネはつい最近臨時の家政婦を雇ったばかりだった。彼女はなんとかモネを看病しようとしたが、どうしていいかわからなかった。そのうち、頭痛がはじまって三日後、モネは吐き気を覚え、熱が出て、嘔吐しはじめた。嘔吐はしだいにひどくなり、吐くものがなくなっても発作がつづいた。
それと同時に、彼は奇妙に受動的になった。生き生きとした表情が顔から失われ、眼球が麻痺したように固定した結果、顔全体が仮面に似てきた。おまけに目蓋がやや垂れ下がり、目が半ば閉じながら飛びだしたような、妙な様相を帯びた。眼球自体は眼窩の中で凍結したかのようで、しかも真っ赤に充血していた。顔の皮膚は全体に黄ばみ、赤い星のような斑点がぽつぽつと出てきた。一言で言えば、彼はゾンビに似てきたのである。臨時の家政婦は震えあがった。自分の雇い主の変貌ぶりが、理解できなかった。外見のみならず、モネは人柄までが変わってきた。むっつりとふさぎこみ、やたらと怒りっぽくなったばかりか、物忘れがひどくなった。といって、まだ譫妄状態にまで陥ってはいないようだった。訊かれたことには答えるのだが、自分がどこにいるのかわからないらしいのだ。
モネの無断欠勤に不審を抱いた同僚たちは、様子を見に彼の自宅を訪れた。中に入る彼らを、屋根にとまった黒と白のまだらのカラスが見守っていた。モネを一目見て、同僚たちは、彼を入院させる必要があると判断した。モネはもはや車を運転できなかったので、同僚たちの一人が自分の車で彼をヴィクトリア湖畔の町キスムの私立病院につれていった。モネを診断した医師たちには、彼の顔や目の症状、不安定な精神状態の原因がまったくつかめなかった。ある種のバクテリアに感染したのかもしれないと考えて、彼らはモネに抗生物質の注射をした。が、効果はなかった。
こうなったら、東アフリカ屈指の私立病院であるナイロビ病院に送るほかない、と医師たちは判断した。が、その地方の電話は故障しがちで、モネが診断を仰ぎにいくことを事前にナイロビ病院に知らせることはできなかった。奇妙な症状を呈しているとはいえ、モネはまだ歩くことができたし、一人で空の旅もできそうだった。それに、金にも困っていない。自分がナイロビにいく必要があることを、彼は理解した。モネはタクシーに乗せられて空港にゆき、ケニア航空のナイロビ行きの定期便に搭乗した。
熱帯雨林に生じたホットなウイルスは、地球のどの都市からだろうと二十四時間以内の空の旅には優に耐えられる。地球のすべての都市は、網の目のような空路で連結されている。ひとたびウイルスがその網に乗れば、一日のうちに、どの街をも襲うことができる──パリ、東京、ニューヨーク、ロス・アンゼルス、空路の通じている都市ならどこにでも移動できるのだ。シャルル・モネとその体内に巣くった生命体は、かくしてその網の目にまぎれこんだのだった。
モネが乗ったのは、三十五人乗りのプロペラ機、フォッカー・フレンドシップだった。滑走路を離陸した同機は、漁師たちの丸木船が点々と浮かんだ、青くきらめくヴィクトリア湖の上に舞いあがった。そこで翼を傾けると東に方向を転じ、高度をあげながら茶畑や小さな農場が綴れ織りをなしている緑の丘の上を飛んでいった。アフリカの上空を飛ぶ定期便の飛行機は、満席になることが多い。この飛行機も、おそらく満員だっただろう。円形の小屋の集落、トタン屋根の家の集まる村、大森林の帯の上を、フレンドシップ機は通過してゆく。
そのうち大地が急に下降し、深くえぐれた峡谷に変じて、緑から褐色へと色彩も変わってゆく。機はアフリカ大地溝帯の上にさしかかったのだ。乗客はいっせいに窓を覗いて、人類の始祖が誕生した地を見下ろしたことだろう。茨の木々の輪の内側には住民の小屋の集落が点在し、それぞれの小屋の前から家畜の牛の通る道がのびている。プロペラは轟音をあげ、フレンドシップ機はこの空域独特の分厚い雲の連なりの中に突入する。機体は縦に、また横に、激しく揺れだした。モネは酔いはじめた。
定期便の飛行機内には、狭いシートがぎっしりつまっている。客席内で起きていることは、だれの目にも入るはずだ。機内は気密性が高く、空気は常に循環している。もし機中に何らかの臭気があれば、気づかれずにはすまない。客の中に吐き気を催している人間がいれば、すぐに気づかれたにちがいない。モネは上体を折っている。何かがおかしい。だが、いったい何が起きているのか、だれにもわからない。
彼は乗り物酔い用の袋を口に押し当てている。そして大きく咳き込み、袋の中に何かを吐きだす。袋はたちまちふくれあがる。彼はたぶん、こっそりと周囲を見まわしたことだろう。そのとき、唇に何かしら赤い粘ついたものが付着しているのを周囲の人間に見られる。その赤い粘ついたものには、彼がコーヒーの豆でも噛んでいたかのように、黒い斑点も混じっている。彼の目はルビー色で、無表情な顔は打撲傷を負ったように変色している。数日前、星の形で現われた斑点は、いまや赤みを増して拡大し、紫色の影と混ざりあっている。頭部全体が、青黒く変色している。顔の筋肉も弛緩していた。顔の結合組織が溶解しかけているため、あたかも顔が頭蓋骨から剥離しはじめたかのように、表面の皮膚が骨から垂れ下がって見える。
モネは口をあけて、袋の中に嘔吐する。それはいつまでもつづいて止むことがない。胃が空になったあとも、なお液体が吐きだされる。乗り物酔い用の袋は、“黒色吐物”と呼ばれるものでいっぱいにふくれあがる。“黒色吐物”は黒一色ではない。黒と赤、二つの色がまだらに混ざり合った液体だ。それは黒い顆粒が新鮮な動脈血とシチューのように混ざり合ったものなのである。それは出血にほかならず、さながら食肉処理場のような臭気を伴う。“黒色吐物”には、致死性の高い大量のウイルスが含まれている。感染性もすこぶる高い。軍の微生物専門家が見たら、恐怖のあまりすくみあがってしまうような液体だ。この“黒色吐物”の臭いが、ほどなく客席に充満する。乗り物酔い用の袋は“黒色吐物”で溢れそうになるので、モネは袋の口を閉じてぐるぐるねじる。ふくれあがった袋は紙も柔らかくなり、いまにも中身が洩れだしそうになる。モネはそれを機の接客係に手わたす。
ある宿主の中で活発なウイルスが増殖するとき、その宿主の肉体は脳から皮膚に至るまでウイルス粒子で飽和させられてしまう。軍事専門家はそれを、ウイルスが“究極的拡大”をとげた、と言う。それは、人がインフルエンザにかかったときのような症状とはまるでちがう。究極的拡大が峠を越えたとき、犠牲者の血一滴の中には一億個ものウイルス粒子が存在するかもしれないのである。このプロセスが進行している間に、肉体は部分的にウイルス粒子そのものに変換させられてゆく。言い換えると、宿主は、その肉体を自分と同じ姿に変えてしまおうとする生命体に乗っとられたも同然なのだ。が、その変換は完璧に成功するわけではなく、その結果はウイルスを含んだ肉体の融解現象となって現われる。それはある種の生物学的な事故とも言えるだろう。モネの体内ではウイルスの究極的な拡大が起こった。その徴候が“黒色吐物”なのだ。
彼は、すこしでも動いたが最後その体が破裂しかねないかのように、微動だにしない。そのとき、彼の血液は凝固しようとしている──血管の中に血栓が生じ、それが至るところで血の流れをせきとめている。彼の肝臓、腎臓、肺、両手足、それに頭の中は、血栓で詰まりつつある。要するに、彼は全身を通じて発作を起こしつつあると言っていいだろう。腸筋肉内にも血栓が生じて、腸への血液の供給が遮断される。腸筋肉は死にはじめ、腸は緊張を失って弛緩しはじめる。彼はもはや、痛みを感じているようにも見えない。なぜなら、脳の中の血栓が血の流れを遮断して、軽い脳発作を起こさせているからだ。
脳の障害によって、彼の人格も失われてしまう。これは離人化と呼ばれる現象だが、それが起きると、こまやかな感情や精神の活力が消えてしまい、彼はロボットも同然になってしまう。脳の細部もまた融解しはじめているのだ。意識の高度な機能がまず失われ、脳幹のより深い部分(ネズミの脳やトカゲの脳)のみがまだ活動をつづける。それは要するに、シャルル・モネの精神がすでに死に、その形骸のみが生きつづけている状態と言えようか。
嘔吐の発作によって鼻の内部の血管が破裂したらしく、モネは鼻血を出しはじめる。両方の鼻孔から流れ落ちる血は、色鮮やかな動脈血で、彼の歯や顎の上に滴り落ちる。この血は凝固せずに流れつづける。彼は接客係からもらったペーパー・タオルで、その血を抑えようとする。が、血は依然として固まらず、タオルは血でぐっしょりと濡れそぼってしまう。
飛行機内に乗っていて、隣席の客の様子が変だったら、あなたはどうするだろう? 彼はベルトでシートに括りつけられているし、あなたもシートに括りつけられている。フレンドシップ機はなおも揺れながら飛行しつづける。彼の肘がこちらの肘にぶつかる。きっと大丈夫だろう、とあなたは内心呟く。彼はたぶん空の旅が性に合ってないだけなんだ。可哀相に、乗り物酔いにかかっているんだろう。飛行機に乗って鼻血を出す人はたくさんいるからな。空気が希薄で乾いているから、鼻血が出やすいんだ──そしてあなたは小さな声で、どこかお悪いんですか、と彼にたずねる。答はない。彼は意味不明の言葉を呟くばかりなので、あなたは見て見ないふりをしようとする。飛行機が着陸態勢に移る気配はいっこうにない。
そのうち接客係がやってきて、どうなさいました、とたずねる。だが、この種の危険なウイルスの犠牲者は、日頃とは態度が変わってしまって、そういう問いかけにも応えることができない。彼らはむしろ敵意をむき出しにし、体にさわられるのをいやがるのだ。話すことすら億劫がる。何を訊かれても、低く唸るか、ああ、とか、うん、とか、単純な受け答えしかできない。適当な言葉が見つからないらしい。自分の名前は答えられるが、その日が何曜日なのかわからないし、自分がなぜそういう状態になったか、説明することもできない。
フレンドシップ機は大地溝帯に沿って、爆音をあげつつ雲の中を飛びつづける。モネはぐったりとシートにもたれかかり、うたた寝しているように見える──とうとう死んだのだろうか? いや、彼はまだ死んではいない。動いている。赤い目はひらかれているし、眼窩の中でわずかに動いてもいる。
時は夕方に近い。日は大地溝帯の西側の丘陵に沈みかけ、鮮烈な光の矢があらゆる方向に走っている。あたかも太陽が赤道上で破裂しかかっているかのようだ。フレンドシップ機はゆるやかに旋回し、大地溝帯の東の山麓の上を横断する。大地が高く隆起しはじめ、その色も褐色から緑に変わってゆく。数分後、機は降下を開始し、やがてジョモ・ケニアッタ国際空港に着陸する。モネはすこし身じろぎする。
彼はまだ歩くことができる。血を流しつつ、彼は立ちあがる。よろめきながらタラップを降りて、滑走路の上に立つ。シャツは真っ赤に濡れそぼっている。荷物はさげていない。彼の唯一の荷物は体内にある。すなわち、増殖したウイルスだ。モネは“人間ウイルス爆弾”に変身したのである。彼はゆっくりとターミナル・ビルに入ってゆく。搭乗客のゲートをくぐってラウンジを通り抜け、なだらかに弧を描いている道路の端、タクシーがいつも客待ちをしている区画に出る。運転手たちが彼をとりかこむ──「タクシー?」 「ナイロビ……病院」モネは呟く。
運転手たちの一人が、自分の車に彼を乗り込ませる。ナイロビのタクシー運転手は話し好きだ。この運転手もおそらく、お客さん、気分でも悪いんですか、とたずねただろう。答は明白だったはずだ。が、このとき、モネの腹具合はすこし良くなっている。カッカと火照っているような、胃の内部が引き裂かれたような感じではなく、ちょっとした食事をしたように重い膨満感に包まれているからだ。
タクシーはウールー・ハイウェイに乗ってナイロビを目指す。ハニー・アカシアが点々と立つ草地を抜け、工場群の前を通過してからロータリーに出て、にぎやかなナイロビ市街に入ってゆく。道路の両側は人で溢れている。堅く踏みしめられた小道を歩いている女たちや、あてもなくブラついている男たち。子供たちは自転車で走りまわっている。道端には靴の修理屋が陣どり、炭を満載した荷車をトラクターが引っ張っている。
タクシーは左折してヌゴン・ロードに入り、市立公園の前を通過してから、背の高いユーカリの木の立ち並ぶ上り坂にさしかかる。それから細い道に入って門衛所の前を通り抜け、ナイロビ病院の構内に入る。モネを乗せた車は花の売店の隣のタクシー乗り場に止まる。すぐ前のガラスのドアには、“救急外来”と書いてある。運転手になにがしかの金を渡してからモネはタクシーを降りる。ガラスのドアをあけ、受付の窓口に歩み寄って、とても気分が悪いのだ、と告げる。彼は満足に話すこともできない。
出血していることは一目でわかるので、すぐに中に入れられる。先生がくるまでちょっと待っててくださいね。心配要りませんよ、すぐに見えますから。モネは待合室のベンチにすわり込む。
狭い待合室には、クッションのついたベンチが何列も並んでいる。東アフリカ独特の、澄み切った強烈な光が一列に並んだ窓から射さし込み、汚れた雑誌の積まれたテーブルの上をよぎる。中央に排水溝がある砂利敷きの灰色の床に、テーブルの四角い影が落ちている。汗と薪の煙の臭いがうっすらと漂っている待合室には、アフリカ人とヨーロッパ人が肩を寄せ合ってすわっている。
救急外来の待合室には常に、切傷をこしらえて縫合を待っている者がいる。人々は頭にタオルを押しあてたり、包帯を指で押えたりしながら辛抱強く待っている。タオルには血の斑点が滲んでいる。その待合室のベンチに、シャルル・モネもすわっている。皮膚の変色した無表情な顔と赤い目を除けば、彼は周囲の人間たちとさほど変わらない。待合室の壁には、“スリに注意”という注意書きが貼ってある。もう一つの注意書きには、こう書いてある。
お静かに
皆様のご協力を感謝いたします。ここは救急外来です。緊急を要する方の診察が優先されます。そういう方の手当てが終ったあとで、診察を受けてください。
モネは自分の番がまわってくるのを待つ。と、突然、彼は最終段階に移行する。“人間ウイルス爆弾”はついに爆発する。軍のバイオハザード専門家たちは、この現象を独特の言い回しで表現する。彼らは、患者が“崩壊し、大出血した”と称するのだ。より穏健な言い回しとしては、患者が“屈服した”という表現を用いることもある。
モネは眩暈と共に完全な脱力感に襲われ、背筋がぐったりして感覚がなくなる。次いで、バランス感覚が完全に失われてしまう。部屋がぐるぐる回りはじめる。彼はショック状態に陥ろうとしている。“崩壊”しつつある。もはや、自分ではそれを止めることはできない。彼はがくっと前にのめり、膝に顔をのせると同時に、信じられないほど大量の血を胃から吐きだして、苦しげな呻き声と共に床にまき散らす。次の瞬間意識を失って、前のめりに床に倒れる。唯一聞こえるのは、失神しながらも喉を詰まらせて吐きつづける音だ。次いで、シーツを真っ二つに引き裂いたような音がする。それは肛門の括約筋がひらいて、大量の血を排出した音だ。その血には腸の内層も混じっている。彼は自分の内臓まで壊死させたのだ。剥がれ落ちた彼の腸の内層は、大量の血と共に排出されつつある。モネは“崩壊”し、“大出血”しつつある。周囲にいた男女はいっせいに立ちあがり、床に倒れた男から離れて医者を呼ぶ。モネの周囲には血だまりが生じて急速に広がってゆく。その宿主を破壊した病原体は、いまや彼の体のあらゆる孔から外に出て、新たな宿主を捜そうと“努めて”いる。
(第1章 了)
続きは製品版でお楽しみください!
リチャード・プレストン『ホット・ゾーンーーエボラ・ウイルス制圧に命を懸けた人々』(高見浩訳、ハヤカワ・ノンフィクション文庫、本体1060円+税)は5月22日(金)発売です。