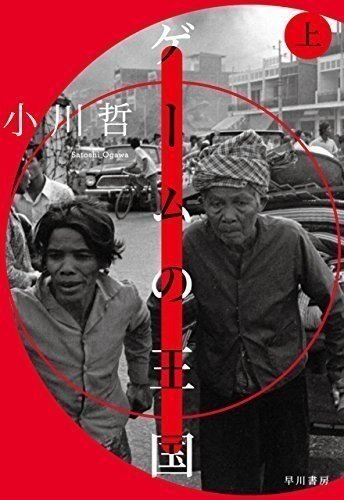第31回山本周五郎賞、第38回日本SF大賞受賞! 小川哲『ゲームの王国』本篇冒頭「サロト・サル 一九五六年四月」公開
※書影は無償配信中の電子体験版にリンクしています
第一章 1
サロト・サル 一九五六年四月
プノンペン郊外、トゥールスバイプレイ
闇の中からは、光がよく見える。チョムラウン・ビチア高校の歴史科教師サロト・サルは、子どものころからその諺を気に入っていた。暗闇から明るいものはよく見えるが、明るい場所から暗闇はほとんど何も見えない。この諺から「輝いているときこそ、足元の落とし穴に気をつけなければならない」という教訓を引きだした国語教師は残念ながら二流だった。正しい解釈は「足元の穴に落ちたくなければ、そもそも輝いてはいけない」ということだ。輝けばかならず闇から撃たれる。それが世の摂理だ。
その日いつものように授業を終えたサルは、校舎の近くでシクロを拾い、慎重に二回乗り継いでから、プノンペン南西にあるトゥールスバイプレイの小屋に向かった。道中いつもの癖で数分ごとに後ろを振り返った。この習慣によって誰かの尾行に気がついたことは一度もなかったが、中断した瞬間に致命的な結果を生んでしまう気がして、いつまでもやめられずにいた。同志からは、今のところ自分が疑われているという合理的な疑いはないと聞いている。いや、大事なのは他人のことを過度に信頼しないということだろう。本当に信頼できるのは自分の目だけだ。用心に越したことはない。兄はそうやって逮捕されたし、志を同じくする多くの仲間たちも警察によって排除されていった。
バラック小屋の近くで乗り継いだ三台目のシクロから降り、懐中電灯で足元を照らした運転手についていく。サルは何も喋らなかったが、運転手が後ろにきちんとついてきているか確認するために振り向いた際は、「大丈夫、ここにいるよ」という意味のこもった微笑を返した。静かな夜だった。シクロが停まった場所からずっと月明かりの中に霧が満ちていて、周囲には何も見えない。しかしそれは決して悪いことではない。なぜなら暗闇は敵を守るが、自分も守ってくれるからだ。このことの重要性をわかっている者は少ない。見つかりたくなければ、まずは見ないことが大事なのだ。
サルは足音を立てずに歩き続けた。耳をすませると遠くから赤子の泣き声が聞こえたが、別段怪しむほどでもないだろう。まっさらな赤子は資本主義という病にもかからないし、忌まわしきスパイにもならない。風に運ばれたアモックの香ばしいココナッツの匂いは、おそらく近隣の住民が作っている料理だ。大丈夫、いつもと変わりはない。うまくやっている。
三分ほど歩くと、ウォータータマリンドの生垣で護衛の男に呼びとめられた。運転手は手にしていた明かりでサルの顔を照らした。サルが名乗る前に護衛は合掌し、承認の身振りを見せて入り口を譲った。家の中に入ることを許可されたサルは足元に目を凝らしながら、一歩ずつ慎重に木材で組まれた階段を上った。ドアを開けると、部屋の中にはヌオン・チアとトゥー・サムートが古くなったテーブルを囲んでいた。
カンボジアがフランスから独立してすぐ、組織(オンカー)は自らを三つの部門にわけた。合法部門、準合法部門、秘密部門だ。サルが合法部門、ヌオン・チアが準合法部門、トゥー・サムートが秘密部門の担当者だった。サルの仕事は、選挙で圧勝することが予想されていた民主党に潜りこみ、共産党員として政党活動を裏から操ることだった。
サルにとって、民主党内部で自分がスパイであることを隠すのは造作なかった。どんなに気難しい相手でも簡単に仲良くなることができたし、権力を持つ人物の信用を勝ち得るのも得意だった。誰かに疑われることも、嫌われることさえもなかった。温和な顔、慎重な言葉遣い、尊大なところがなく常に誠実な態度、人当たりのよさ。サルはそれを自分の才能だと考えていた。政治家や権力者だけではない。高校の教え子たちからも好かれていることには自分でも気がついている。どういうわけか自分には悪評が立たない。黙っているだけで思惑通りに事態が進展していく。
しかし、いかに自分の評判がよかったとしても、そんなものはたった一日でひっくり返る。それくらいよく知っている。現に今日、自分はある人物の評判をひっくり返そうとしている。こういった世界では、風向きが変わってしまえばすべて終わりだ。たった一度の間違いも許されないし、たった一度の不運も許されない。すべての任務を成功させる必要がある。一見簡単そうな任務でも、案外落とし穴があるものだ。民主党に潜りこむという任務においては、二つの要素が複雑に絡みあっていた。民主党へ目立たずに潜りこむことと、実際に影響を及ぼすこと。もちろんその二つはまったくの別物で、前者と後者のどちらかに偏ればどちらかが失敗する。バランスが重要なのだ。その点で、民主党の事務局長補佐だったケン・バンサクがフランス留学時代からの友人だったのは幸いだった。サルは彼を盾にしつつ、民主党がアメリカに対し強硬路線を取り、反米路線を党内の共通認識とするために奔走した。アメリカはかならず「革命」の邪魔をする。彼らの影響力を国内から排除しなければならない。そのため、自然な会話の中に虚実入りまじった情報を織りこみ、ときには挑発的な言葉で民主党の上層部を刺激した。党内でも意見が割れていたが、サルの工作で着実に反米派が力を増していた。バンサクはサルの拡声器になり、民主党は正しい方向へ進みつつあった。「合法」活動は成功しつつあったのだ。
だが、すべてがうまくいっているように見えた工作も、結果的に無駄に終わった。大事なのは失敗ではなく、無駄だったという点だ。自分はしくじらなかったし、最後までベストを尽くしたが、結局なんの成果も残らなかった。完全なゼロだ。そのことは認めなくてはならない。
思えば、その兆候はノロドム・シハヌークが国王を退位した瞬間から始まっていた。国政選挙の直前、シハヌークは国王の地位を彼の父スラマリットに譲った。それは彼が本格的に政治に介入するために必要な行為だった。手始めにシハヌークは自らが主導する超党派団体「人民社会主義共同体(サンクム)」を組織し、選挙に名乗りをあげた。この段階では単にライバルが増えただけだった。問題は、元国王のシハヌークが国政に深く関与できたことと、その権利を明け渡したくなかったことだ。民主党の影響力が思っていたよりも強く選挙の旗色が悪いと見るや、シハヌークはサンクムと民主党による連立政権の道を探るようになった。民主党は当然のようにシハヌークの提案を断った。元国王の後ろ盾がなくとも選挙に勝つことは明白だったからだ。その結果、シハヌークは民主党やその他の敵対政党に対する弾圧を始めた。
共産党の準合法部門が指揮していた政党組織、人民派(プラチアチョン)の広報誌は発行禁止になり、編集長は逮捕された。左翼雑誌を編集していたサルの兄が逮捕されたのもその時期だ。選挙を前にプラチアチョンの各候補者は射殺され、射殺を逃れた残りの多くは投票日までに逮捕された。投票前夜、集会に出ていた民主党のバンサクは、目の前で関係者が射殺されるのを見た。そしてどういうわけか、バンサクはその関係者を殺した罪で逮捕された。捕まった狙撃犯が「バンサクの依頼だ」と証言したという話だった。バンサクが「二度と政治に関わらない」ことを誓うと、彼はすぐに釈放された。
選挙はシハヌーク率いるサンクムの圧勝だった。当初勝利が予想されていた民主党や、躍進が期待されたプラチアチョンは一人の当選者を出すこともできなかった。民主的な選挙など存在しなかったのだ。ほとんどすべての投票所で不正が行われたし、正当な勝者が暗殺された選挙区もあった。
プラチアチョンは一票も獲得していない。そう結果を出した選挙区もあった。サルはその選挙区でプラチアチョンに投票した人間を、少なくとも数十人は直接的に知っていた。カンボジア中の誰もが不正に気づいていたが、そのことを指摘すると命に危険が及んだ。こうしてサルの任務はすべて無駄になった。
茶番だった。無意味だった。しかし、この選挙の経験そのものは無駄ではなかった。サルはこの壮大な茶番を通じて、ある重要な真理を強く認識した。結局のところ、権力を握った者がすべてのルールを決めるのだ。サッカーの試合をしていたら、審判が「ゴールを決めるな」と命令してくる。審判に反抗してゴールを決めた選手は退場させられ、ゴールは無効にされる。結果的に、誰もゴールを決めようとはしなくなる。試合終了。五対〇、シハヌークの勝ち。いったいどうすればいい?
答えは簡単だ。自分たちがルールを支配すればいい。選挙の顛末を受けて、カンボジア共産党は即座に合法部門の撤廃を決めた。権力者の定めたルールに従ってフェアプレイを行っても絶対に勝つことはできない。相手がルールを変更することで勝利を盤石にしようとするならば、自分たちもルールを逸脱してそれに応じなければならない。そのために手段を選んでいる場合ではない。残念ながら、革命が闘争であるという格言は正しい。驚くほど正しい。
……続きはこちらでお楽しみ下さい。
……書影は電子書籍版にリンクしています。
小川哲氏のデビュー作、第三回ハヤカワSFコンテスト〈大賞〉受賞作『ユートロニカのこちら側』の電子書籍版も絶賛配信中です。