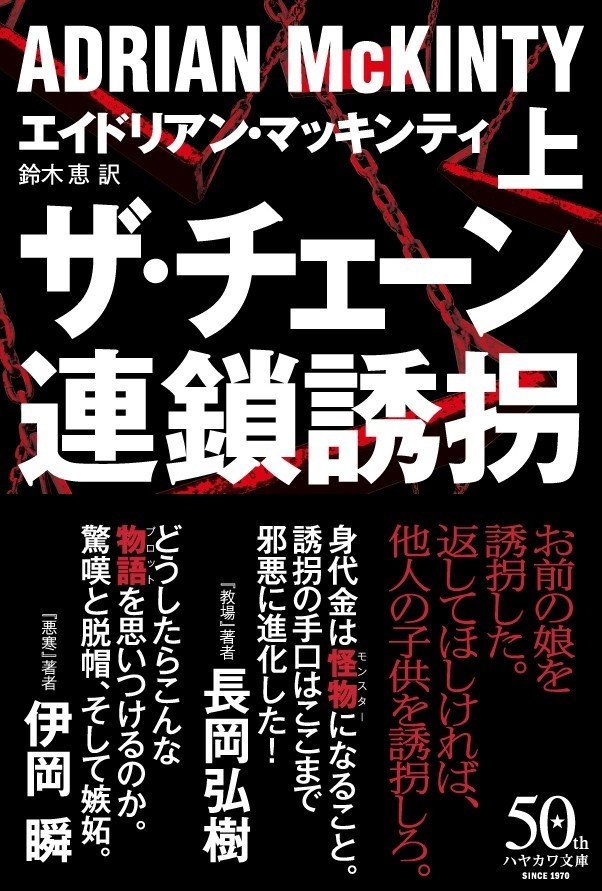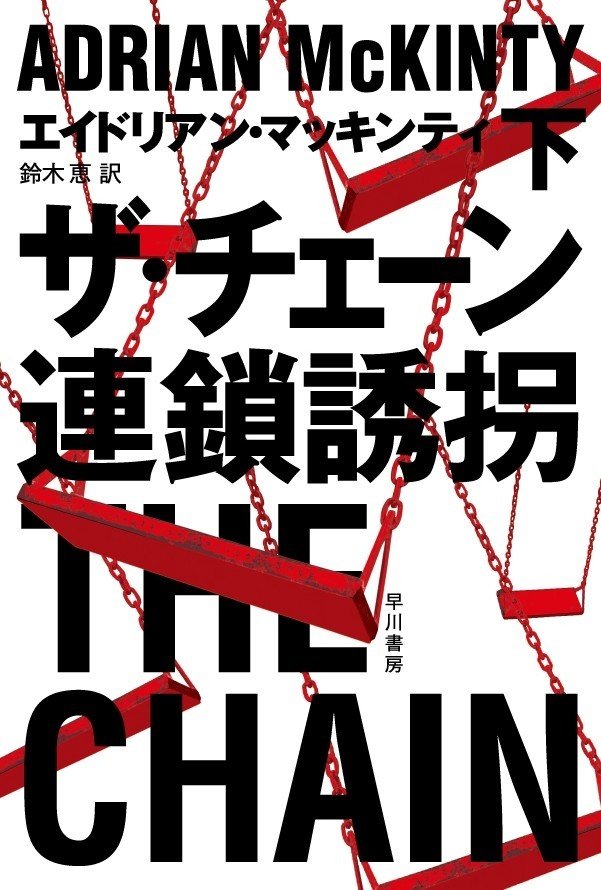〝第一級の誘拐小説として、自信をもってお薦めすることができる〟――書評家 杉江松恋氏による『ザ・チェーン 連鎖誘拐』解説を公開
好評発売中の『ザ・チェーン 連鎖誘拐』(エイドリアン・マッキンティ著/鈴木恵訳)より、書評家 杉江松恋氏の解説を掲載いたします。
解説 杉江松恋(書評家)
エイドリアン・マッキンティの根底には怒りがある。
それが内に向かえば苦い自己否定、外に向かえばくだらない社会への憎悪。
激しい感情のうねりを、極力制御し、冷ややかな文章へと置き換える。
そういう過程を経て、マッキンティ作品は出来上がるのだろうと思う。
『ザ・チェーン 連鎖誘拐』は二〇一九年に刊行された、彼の新たなる代表作である。
邦題が示すように、これは誘拐を扱った犯罪小説だ。誘拐、しかも極めて悪質な。
ある朝、十三歳の少女カイリーは、スクールバスの停留所でスキーマスクを被った男に拳銃をつきつけられ、車で連れ去られる。男は言う。「きみのお母さんがこれから二十四時間以内にすることが、きみの生死を分けることになる」と。
カイリーの母親、レイチェル・クラインは抗癌剤治療を終え、念願の再就職も決まってこれから人生をやり直そうとしている。そのすべてを打ち砕く電話がかかってくる。カイリーを連れ去った誘拐犯からのものだ。ボイスチェンジャーでゆがめられた声は言う。「ひとつ。おまえは最初ではないし、断じて最後でもない。ふたつ。目的は金ではなく――〈チェーン〉だ」。
『ザ・チェーン 連鎖誘拐』は二部構成の小説である。第一部「行方不明の少女たち」はこのようにして始まるのだが、読むのがしばしば困難になるほどの緊迫感を覚える。誘拐という犯罪の卑劣さ、そして弱者が強者に振るわれる暴力の無慈悲さ、理不尽さがこれでもかと描かれるためだ。事件に巻き込まれた者たちが絶望感によって引き裂かれ、人生がどぶ泥の中に沈み切ったところで第二部「迷宮にひそむ怪物」が始まる。事件の全容が見えてきて、憎むべき犯罪を引き起こした者の正体が明らかになるのはそこからだ。
誘拐ミステリには長い歴史がある。ここでその系譜について細かく紹介している余裕はないが、子供などの弱い者が標的とされ、生命を換金するように要求されるという仕組みが、時として殺人以上に悪質と感じられること、いくつかの過程を経なければ犯行が終わらないため、犯人と警察・探偵との間に知恵比べが繰り広げられ、ゲーム要素が強くなること、などが犯罪小説の一ジャンルとして人気がある理由ではないだろうか。
思いつくままに作例を挙げても、人質の取り違えという不測の事態や意外な手段を使っての身代金奪取など斬新なアイデアをいくつも盛り込んだエド・マクベイン『キングの身代金』(一九五九年。ハヤカワ・ミステリ文庫)、よりによって宗教の最高権威者を人質に選ぶというジョン・クリアリー『法王の身代金』(一九七四年。角川文庫)、架空の誘拐小説を参考書にして強盗が実際の犯行に及ぶというメタ誘拐小説、ドナルド・E・ウエストレイク『ジミー・ザ・キッド』(一九七四年。同)など秀作揃いである。付け加えるならこの上ない奇手を用いたフレドリック・ブラウン『悪夢の五日間』(一九六二年。創元推理文庫)。酷薄な作風から笑いを誘う小説まで幅広く、未成年を狙う性犯罪を扱ったものまで含めれば、さらに作例は広がる。
そうした厖大な数の先行作があるのだから、おそらくその中に似たものはあるだろう。だが、『ザ・チェーン 連鎖誘拐』にはこの作品にしかない着想がある。扱われている題材の中に、マッキンティならではの悪についての洞察があるのだ。暴力と悪がいかに残虐に人間性を破壊するかということがこの小説には書かれている。
早々に明かされるので、これは書いてもかまわないだろう。愛娘を誘拐されたレイチェルが犯人から指示されたのは、別の誰かの子供を誘拐することであった。そして、その誘拐した子供の親にまた同じような犯行を繰り返させる。つまりカイリーを誘拐したのも、同じように我が子を奪われた親なのである。もしレイチェルが誘拐に失敗したらその親はカイリーを殺し、別の子供を標的にしてまた同じことをする。我が子を解放するための唯一の手段は、自分自身が誘拐という同じ犯罪に手を染めることなのだ。そうしたシステムが〈チェーン〉なのである。
本書を読んで連想したのが、二〇一二年に発覚したいわゆる尼崎事件だ。複数の家族が一人の人間によって乗っ取られて支配下に置かれるという状態が、二十余年にわたって続けられていたという事件である。そうした体制が長期間続けられたのは、被害者の家族が主犯によって虐待や殺人などの行為を強制的に担わされたために共犯関係に陥ったことも大きいとされる。そうした悪の連鎖がいかに成し遂げられたかは、主犯が自殺したため、全貌が明らかにされていない。本書の第一部が読者の心に呼び起こすであろう暗い感情は、この事件について知ったときの茫洋とした不安と通底するものがある。
おそらくそれは、人間が人間ではなくなってしまうという非常事態が描かれているからだろう。〈チェーン〉のような、あるいは尼崎事件のような犯罪は特殊例として非日常化したものだが、実はそれは日常と無縁ではない。社会というシステムには本質的に、個人から自由と独立を奪う可能性が備わっているからである。戦争という最終形を挙げるまでもなく、そうなりかねない例をいくつも想像できるはずだ。
選択の自由が与えられず、システムの中に組み入れられる。マッキンティの視線は、誘拐という犯罪を通し、その先に人間を人間でなくしてしまう社会というシステムを見る。個人と社会とは常に対立する可能性を秘めているが、犯罪小説は暴力によって前者が後者に反抗する機会を描き、関係性を極限まで突き詰めていく。先述したように誘拐小説は強者が弱者を蹂躙する、最も卑劣な犯罪を題材として扱う。犯罪者による暴力の残酷さを描くだけではなく、社会全体に敷衍可能な暗喩として読者の胸に刻みつけた。それが誘拐小説史の中でも本書にしか成し遂げられなかった偉業なのである。
本音を言えば、〈チェーン〉が浮かび上がらせる底知れぬ恐怖感を味わったまま、第一部でこの小説を読むのを止めてしまおうと私は何度か思った。そうすれば小説の印象は強烈なままで永遠に残ったはずである。しかし、それでは物語が完結しないし、第一そういう小説は嫌だという読者も多いはずだ。ご安心を。第二部をもって本作はミステリとしての整合性を保ってきちんと完結する。これまた本音を言えば、マッキンティは私の好みとしては少し書きすぎるところがある。エンターテインメント作家たろうとして、ちょっとサービスしすぎなのだ。しかしこれも好き好きだろう。第一級の誘拐小説として、自信をもってお薦めすることができる。他では絶対に読んだことのない物語を堪能できるはずだ。
作者について少し書いておく。エイドリアン・マッキンティは一九六八年に北アイルランドの都市キャリックファーガスで生まれた。彼の父親は溶接工や船員などの職歴があり、労働者階級の出身である。ウォリック大学で法律、オックスフォード大学で政治と哲学を専攻し、一九九三年に同大を卒業後はニューヨークに移住してさまざまな職に就いている。作家としてのデビュー作は二〇〇三年に発表した Dead I Well May Be であり、同作でCWA(英国推理作家協会)の二〇〇四年度スティール・ダガー賞候補になっている。これはベルファスト出身の犯罪者マイケル・フォーサイスを主人公とした犯罪小説で、二作の続篇が書かれて三部作として完結している。ベルファスト出身で後にニューヨークに渡ることになるという身上など、フォーサイスの造形にはマッキンティ自身がかなり投影されているように思われる。
その後はヤングアダルト作品のライトハウス・トリロジー(二〇〇六~二〇〇八年)など複数の作品を手掛け、二〇一二年にベルファストの警察官ショーン・ダフィものの第一作『コールド・コールド・グラウンド』(ハヤカワ・ミステリ文庫。以下同)を発表する。北アイルランドには英国からの独立を目指す運動の長い歴史があるが、テロ活動が最も激化していた一九八〇年代に時計の針は設定されている。ダフィは警察官はほぼプロテスタントである中で黒い羊のようなカソリック信者であり、IRAのようなカソリック系のテロ組織からは、何かがあれば即裏切者の烙印を押されて処刑の対象にされかねない存在だ。そのように本質的に孤独で寄る辺なき存在である男が、事件解決のために孤軍奮闘するというのがシリーズの基調になっている。『コールド・コールド・グラウンド』がまさにそういう作品だったが、警察は暴動鎮圧や政治犯取り締まりで手一杯で、たった一人が犠牲者になっただけの殺人事件に手を焼いている場合ではないのである。個よりもシステム全体の維持が常に優先される社会で個に執着し続ける主人公、という図式は第一作で明確になった。
先に書いたように、マッキンティには書きすぎる、筆が走りすぎるという惜しい点があり、そこが持ち味にもなっている。『コールド・コールド・グラウンド』を読んだときに私が連想したのはコリン・デクスターが創造したモース主任警部で、次々に仮説を立ててはスクラップ・アンド・ビルドを繰り返す(しかもモースにとってのルイス部長刑事という補佐役なしに)姿は新しい世代の名探偵像なのかもしれないと感じた。しかし走りすぎを反省した気配もあり、第二作の『サイレンズ・イン・ザ・ストリート』(二〇一三年)は前作の欠点を克服した良作となった。シリーズ邦訳作の中では、今のところこれがいちばんいいと思う。
第三作の『アイル・ビー・ゴーン』(二〇一四年)は英訳された島田荘司『占星術殺人事件』(一九八一年。講談社文庫)の影響を受けたとされる作品である。島田自身による同作の文庫解説によれば、『サイレンズ・イン・ザ・ストリート』執筆中にマッキンティは英訳版を読んだとのことで、感化を受けているのは以降の作品なのだという。その読書体験が新鮮だったのか、『アイル・ビー・ゴーン』内には謎解き小説のいろはについてダフィが講釈を垂れる場面などがあって、ミステリ研究会の先輩と後輩の会話を見ているようで微笑ましい。実際に読んでみた印象としては、『アイル・ビー・ゴーン』は密室構成トリックなどもごく初歩的なものである。マッキンティはこのシリーズの第五作Rain Dogsでアメリカ探偵作家クラブ(MWA)賞最優秀ペイパーバック部門を受賞しており、同作もやはり探偵小説的なアプローチが試みられた作品である。これは訳者の武藤陽生氏に直接指摘されて気づいたのだが、『アイル・ビー・ゴーン』には本歌である『占星術殺人事件』のプロットの換骨奪胎に挑んだ形跡があり、そうした構造などにも着目しなければ真価はわかりにくい面がある。いずれにせよ、以降の続刊で島田ショック以降のダフィ・シリーズがどう変貌したかについては再確認したいところだ。
マッキンティについては衝撃的な出来事がある。ダフィ・シリーズの第六作である Police at the Station and They Don't Look Friendly を発表したあと、小説執筆では労働の対価に満たない収入しか得られないから、という理由で彼は作家廃業を宣言し、ウーバードライバーに転職してしまったのだ。その現状を聞きつけたドン・ウィンズロウがマッキンティの才能を惜しみ、自身のエージェントでもあるシェイン・サレルノを彼に紹介した。サレルノがマッキンティを説得し、アメリカを舞台にした小説を書くように勧めた結果、できあがったのがこの『ザ・チェーン 連鎖誘拐』なのだ。マッキンティがどこから連鎖誘拐という着想を得たかは作者あとがきに書かれているし、ドン・ウィンズロウによる彼のインタビューがこのあと早川書房の媒体にも掲載される予定だというので、ここでは筆を重ねる愚は避けておこう。インタビューを読むと、マッキンティが若いときに吸収したアメリカ産ドラマや犯罪小説が、彼の思惟を繰り広げるための土壌になっているということが理解できる。
怒りを燃やして走る男、エイドリアン・マッキンティ。これからどこに行くんだろう。
ウーバーのドライバーだって悪い職業ではないと思うけど、あんたにはいろいろな犯罪をもう少し書いてもらいたいと思うんだ。
なあ、いいだろう?
二〇二〇年一月
【書誌情報】
タイトル:『ザ・チェーン 連鎖誘拐』上下
著者:エイドリアン・マッキンティ 訳者:鈴木恵
原題:THE CHAIN
価格 :各780円+税 ISBN:9784151833045/9784151833052
※書影等はAmazonにリンクしています。