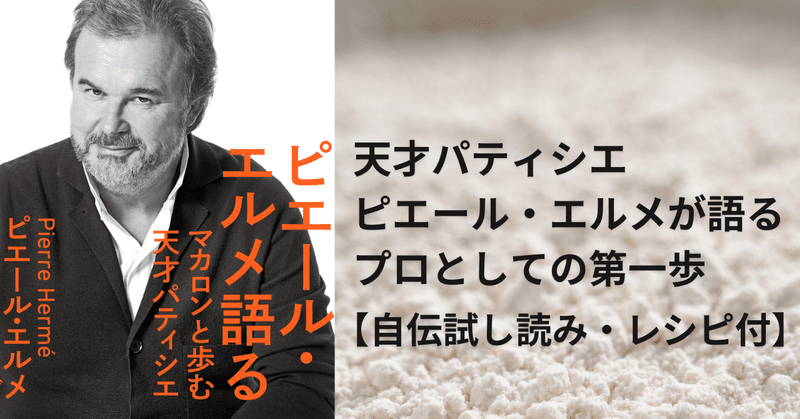
天才パティシエ ピエール・エルメが語る、幼少期の記憶とレシピ
「パティスリー界のピカソ」とも称される有名パティシエが自身の半生を明かす話題の本、『ピエール・エルメ語る マカロンと歩む天才パティシエ』(ピエール・エルメ&カトリーヌ・ロワグ、佐野ゆか訳、早川書房)から、幼少期の思い出の味や「パティシエとしての第一歩」を意識した記憶を語る、本書冒頭部分を試し読み公開します。

第1章 浸透
思い出とミルティーユ
2歳か3歳の夏のことです。森の中、太陽の光がブナとモミの木々の間から射していました。その道を、私は手をつないだ乳母のそばでよちよち歩いています。私たちは一緒に、野生のミルティーユ(ブルーベリーの野生種)を摘みに来たのです。ヴォージュ山脈のひんやりとした酸性の土のおかげで、ミルティーユは豊富にとれます。ジャック・ママは私にとって甘さを体現した存在です。ラバロシュ村のパン屋に嫁ぎ、森の果実を使った見事なタルトとジャムを作っていました。
「全部食べちゃダメよ!」と笑いながらママは言うのですが、私ときたらミルティーユの木から両手いっぱいにつかみ取って、欲張って全部を口の中に詰め込むのです。ベリーの甘い果汁が指の間にしたたって、唇をべとべとにして、食い意地のはった私の味蕾をうっとりさせています。
野生のミルティーユが、私が覚えている最初の味です。
この小さな黒い果物の深い味わいは、永遠に私の奥底に刻み込まれました。その深みは、栽培されたミルティーユにはまったく感じられません。奥行きがないのです。そのことを考えると、あんなに繊細なあの味が、たちまち口の中に広がります。でも自分の創作には、一度もミルティーユを使ったことがありません。失望してしまうことを恐れ過ぎているのかもしれません。あの味に触れてはならないのです。思い出の中だけのものにしておかなければならないのですから。
あの味は、たくさんのことを思い出させてくれます。まざまざと浮かぶ情景、感動、そして豊かな味わいの数々が、まだほんの小さな子どもだった頃のことを、印象派の絵のようなタッチで、甘く苦く描き出してくれます。生後3か月から3歳まで、私はラバロシュ村で乳母に預けられていました。両親が働いて暮らしているコルマールから、約20キロのところにある村です。父方の祖母は、息子の嫁、つまり私の母が、家族経営のパンとパティスリー(小麦粉の生地をベースに作ったケーキ、パイ、タルト、クッキーなどの菓子全般のこと)の店と、乳児の面倒をいっぺんにみるのは無理だと決めつけていました。祖母は独断的で気難しい性格で、私たちの住まいの上に住んでいました。母が庶民の出だというだけで、自らを私の母より優れていると思っているような人でした。
記憶している限り、母と離れていて私が特別苦しんだということはありませんでした。幼な過ぎたからです。それとは反対に、母は身を切られる思いだったことでしょう。母は苦しみ抜きました。そのことで性格はきつくなり、おそらく人生に亀裂が入りさえもしました。両親は私以外に子どもを持つことはありませんでした。母が、子どもと引き離される悪夢をもう一度経験することを恐れたからです。そのことで母は、常に父と祖母をとがめていました。家族関係は損なわれ、重苦しいものになっていました。
母はいつも私の世話をあれこれと焼いていました。厳しく、教育熱心で、向上心を持つことをおしえてくれました。しかし愛情深い人ではありませんでした。ほんの乳飲み児のわが子と引き離されたという事実が、母から感情を切り取ってしまったのです。私に贈り物をすることも、その腕に抱くこともしませんでした。ただし私には、母に取りついたあの冷たさのせいで傷ついた、という感情はありませんでした。ずっとそうだったので、それが普通だと思っていました。
私の妻のヴァレリーが、30歳を越えている息子のアドリアンをいまだに甘やかし、彼の安らぎや幸せに対してどれほど気を配っているのかを見て、自分にはそんな経験がなかったことに、はっきり気づきました。1960年代の親たちは、今とは違う態度だったのだと私は考えています。おそらくそのことで、逆に、私がとてもあからさまに、近しい人たちにすぐに感情を表に出すことの説明がつきます。そしてきっと、私が人生を甘さに捧げてきたことの説明も……。
ミルティーユに話を戻すと、ルノートルにいた頃に作っていた初期のもので思い出すのは、ミルティーユのタルトです。サブレ生地でできているタルトの底は、信じられないようなバターの味がしました。当時私は、父が使っていたマーガリンの生地しか知らなかったのです。大半のパンとパティスリーの店も同様でした。ミルティーユはポーランド産で、クラクスというメーカーの瓶詰めのものでした。丁寧に水切りをして、果汁はゼリーを作るのにとっておきました。その味は、森で集めたミルティーユに驚くほど近いものでした。
思い出というのは、まったくもって妙なものです。
クエッチのタルトと相棒
子どもの頃の環境については、とてもよく覚えています。私たちは、家族経営の店の上のアパルトマンにずっと長い間住んでいました。私の部屋は、ダイニングとバスルームの間にあって、くすんだベージュ色の壁紙が貼られていました。角には本棚付きの民芸調のベッド、古い家具、小さなテーブル、そして私が使うことのないライティング・ビューローがありました。機関車の模型とポリュックス(フランスのアニメのキャラクター。耳の毛の長いイギリス犬で砂糖が好物)のぬいぐるみが、いちばん大切な宝物でした。バルコニーには、アルザス地方ではお決まりの赤いゼラニウムが飾ってありました。隣が葬式だってお構いなしです。でも肝心なのは、私の部屋が父のパン工房の真上にあったということです。
毎日、パンとブリオッシュの匂いが私の鼻を刺激して、目覚めました。金曜日になると、クグロフ〔ページ下部のレシピを参照〕の香りが、週末だと知らせてくれました。毎日、父ジョルジュは午前2時に製パン室に下りて行きました。母シュザンヌは4時頃に行きます。両親共に1930年生まれで、高祖父母(父の祖父母の祖父母)が作ったパンとパティスリーの店を経営していました。はっきり言われることはなかったにせよ、将来私が商売を継ぐことは、ほとんど決まりきったことでした。
私たちは、コルマール市の中心街に近いジャン・マセ地区に住んでいました。ついでながら、ジャン・マセというのは19世紀の偉大な教育者であり教育学者で、『ひと口のパンの物語』の作者です。だから私たちは、うってつけの町に住んでいたわけです。中心街に行くときは「町に行く」と言っていましたが、たった600メートルしか離れていませんでした。母は店を朝5時に開けます。近くの繊維工場の工員たちが仕事を始める前に、パンや軽食を買いに来るからです。
この当時父は、主としてポーリッシュ法(ポーランドで考案された水種でパンを作る製法)で、身が白く、大きくて長く、柔らかくて味わいのあるパンを作っていました。後にライ麦パンや穀物入りのパンを作り始めましたが、今日好まれる酵母パンとはまったくの別物です。父はパン職人の仕事は、生活のために習慣的にやっていましたが、パティシエの仕事は愛していました。特に、フォレ・ノワール(サクランボ入りチョコレート・ケーキ)、フルーツ・タルト、ヴァシュラン(メレンゲとアイスクリームのケーキ)、スタンダードな、あるいは砂糖がけのクグロフなどを売っていました。なじみ客のための型どおりの品も同様に売っていました。
父は好奇心旺盛で、納入業者がすすめる講習も迷わず受けていました。そのことが父に新商品を作りたいという気にさせましたが、残念なことに、定番のものほど売れることはありませんでした。客が新しいケーキに興味を示しても、結局はいつも、「まあ、独創的! でもやっぱりフォレ・ノワールをひとつください」ってなるのよ、と母は笑いながら言っていました。そして、本日の新商品は売れ残ってしまいます。私はそのおこぼれにあずかることができたのですが、自分の名誉にかけて私の食生活を監督するのが当然と思っていた母は、その度ごとに嘆いていました。
私の子ども時代は、パンよりもケーキと密接に結びついています。パンは夜に作られ、両親は、私が自分たちよりも長い時間眠ることを強く望んでいたからです。
父と一緒に過ごすには仕事場に行かなければならないことは、すぐにわかりました。父がいちばん幸せを感じる場所です。父は夢中になって、何でも一人でやってのけていて、繊細なものを作るときはなおさらでした。私たちにとって特別な時間は、祭の前の週末でした。そのとき父は、いつもとは違うものを作ります。型抜きやさまざまなチョコレート、そして「ブルデル」です。このクリスマス用のサブレは、アルザス地方の人間にはなくてはならないものです。
「マナラ」を思い出すと、胸がときめきます。ブリオッシュのような、人の形をしたこの小さなパンは、聖ニコラウスの日に食べます。最近、私達の工房クレアシオンで作ってみましたが、ケーキを食べ過ぎないように日々気をつけているのに、3つは平らげてしまいました。その味わいが、たちまち父のパティスリーへと私をいざなうものですから……。
感謝祭には、アルザス地方伝統の「ラマラ」が欠かせません。羊の形をしたビスキュイ・ド・サヴォア(油脂を使わず小麦粉とコーンスターチを使用した菓子)で、素焼きの型に入れて焼き上げて粉砂糖をふりかけたものが、小さな旗を飾り付けた袋に入っています。私はロイヤルモンソー・ホテルの感謝祭のブランチのための一品を、長らくこのレシピで作りました。
父はまた、ウサギの形をしたレモン・サブレを作っていました。今もそのサブレが見えます。匂いも、味わいも、よみがえってきます。生地はとても美味しいのですが、マーガリンがベースです。父は、当時のアルザス人の基準であったスイスで修行して、こんなふうに作ることを学んでしまったのです。おそらくバターはあまりに高価だったのでしょう。とにかく父は、バターはクグロフにしか使いませんでした。
平日学校から帰ると、聖アントワーヌ教会の裏手か団地の中庭で、友達とサッカーをしました。友達のほとんどが、当時そこで生活していたイタリア人コミュニティー出身でした。しかし週末と祝日には、私の頭にあるのはひとつの考えだけでした。パティスリー工房で過ごすことです。母方の祖母は、私に前掛けとコック帽を作ってくれていました。
私の飽くなき好奇心と生地を扱いたいという欲求を満たすために、父はこまごました仕事を言いつけました。加熱板の掃除や、栗の「トーチ」(アルザス地方のモンブランの呼び名)のための栗の皮むきなどです。しかしどうしてモンブランを「トーチ」と呼ぶのかはわかりません。多分あの細いパスタのような形状のせいでしょうか。父はいつもトーチをたくさん作りましたから、私は生栗を何キロも、何キロも、むかなければならず、本当にイヤでした。私はどこにでも鼻をつっこみ、観察し、何にでも触っていました。ある日、パン生地を切る機械で親指を深く切ってしまいました。今も傷痕が残っているほどです。指を失ってしまうと思い込み、そのうえ、こっぴどくどなりつけられました。
父から言いつけられた単調な仕事とこの“名誉の負傷”で、嫌気がさすどころか、好奇心はいやまし、この仕事をしたいという気持ちはいっそう高まりました。
父は私のこのモチベーションにかなり早くに気づき、だんだんとより興味深い仕事を任せてくれるようになっていきました。パティスリーでは、一つのケーキを一人で初めから終わりまで作ることは稀です。ですから、私が最初に完成させたケーキはこれだ、と言うことができません。最初に父に任されたのは、ヴァシュランの組み立てでした。ディスク状のメレンゲとアイスクリームを組み合わせなければなりませんでした。それから父は、タルトにどのようにフルーツを載せるのかを見せてくれました。
年が経つにつれ、好奇心は増すばかりでした。いつも学んでいたくて、父と、シェフ・パティシエのベルナール・セサに、ずっと質問を浴びせ続けていました。二人をうんざりさせるのは覚悟の上で。ベルナール・セサは父と一緒に働いていて、後に両親からパンとパティスリーの店を買い取りました。このようにして、タルト生地を型に敷き詰める、生クリームをバラの花の形に絞る、ケーキにマスクをする(クリームを塗り、ケーキの側面にコームで筋を入れること)、卵形やコポー(薄く削ったもの)や成型のチョコレートを作る、などのことを学びました。
それからまた、父と一緒に2CVのバンで配達に回りました。バンは後にディアーヌ(シトロエンの後継モデル)に買い替えられました。父は大のシトロエン派でした。当時だったら、プジョー派かルノー派でもあり得たでしょう。いずれにせよ、父はこのメーカーに忠実でした。シトロエンSMが発売されたとき、父が買い替えたらいいなと夢見たのですが、わが家の財力を超えていました。家族でのお出かけ用は、シトロエンDSでした。父とディアーヌで、パン、タルト、砂糖菓子を注文した客に配達し、コルマールの西と南西部の野菜栽培地区のすべてをカバーしていました。父は顔が広く、おかげで皆と顔見知りになりました。車から降りて箱を下ろすのは私だったからです。私はこの仕事が大好きでした。人びとにケーキを届けることで、幸せも届けているような気がしました。これほど素晴らしい仕事を、他に想像することなどできたでしょうか。
夏の終わりは、クエッチ(スモモの一種)のタルトに祝福された時期でした。父はとても上手く作りました。それはおそらく私にとって、父を最も思い出させるもののひとつです。
レシピは再現できるのに、父と同じタルトを再現できたことはありません。その主な材料はシンプルなのにです。水と小麦粉とマーガリンと砂糖と塩。それで作ったタルトの基礎の敷き込み用生地は、かなり硬く、サクサクではなくてほぼ“ハードカバー”のようでした。その上に、少し乾いたビスキュイ・キュイエール(油脂を使わない軽いビスケット生地)を、それからアルザス産のクエッチを載せます。
クエッチは、8月の半ばから9月の終わりまでの5、6週間しか収穫できません。そして父は、タルトにシナモン入りの砂糖をふりかけます。父はシナモンを量ることはなく、ましてやその産地を調べることなどありませんでした。このタルトを窯式オーブンに入れると、出来上がりは格別です。とにかくフルーツそのもの! いまだにこのクエッチ・タルトの味、そして質感を再現できたことはなく、その説明はつきませんが、このタルトは父と過ごした美しい時間と結びついています。
確かに、体面を重んじるこの世代のアルザス人が皆そうであるように、父も自分の感情を表に出すことはしませんでした。しかし私たちは相棒でした。父は仕事をするのが幸せという人間でした。仕事以外では、切手収集家で、家族や仲間たちとの山歩きが好きでした。月曜日の午後は、コルマールのパン屋合唱団で歌い、その催しは同業者たちとの夕食で締めくくられました。
無意識のうちに、父のケーキ作りへの情熱は、私にとっての模範となっていました。父は多くのことをおしえてくれました。修行を始めたとき、自分は何でも知っているのだと思っていたほどです。もちろんそれは間違いで、原材料について学ぶべきことがたくさんあったのです。父が使っていた果物は格別でした。わが家の二つの果樹園で拾い集めたものです。果樹園は家から2キロのところにありました。スグリの実、クエッチ、ミラベル(スモモの一種)にサクランボ。サクランボは、柄を傷めないように摘む必要がありました。アルコールと一緒に瓶に入れなければならないからです。よく漬かったら、糖衣をかけて、最後にチョコレートでコーティングします。しかし当時のほとんどのパティシエがそうであったように、果物以外の原材料については、父は具体的な研究をしませんでした。
父の仕事場で、バニラ・ビーンズを見たことはありません。父はバニラ・エッセンスしか使っていなかったのです。レモン・ピールも同じで、ドイツで買った香料で代用していました。私が高品質の原材料と出会うためには、ルノートルにたどり着かなければなりませんでした。ルノートルでの経験は、私の視野を無限に広げてくれました。そして今日も探求し続けているのです。
[レシピ1]私の父風クグロフ
クグロフ2つ 6人分(直径18cmの陶製クグロフ型を2つ用意する)
準備時間 45分
焼き時間 40分
休ませる時間 2時間30分
・クグロフ生地
小麦粉……250g
グラニュー糖……35g
パン用生酵母……8g
卵(大)……3個(小の場合は4個)
無塩バター……225g
ゲランドの塩の花……6g
ゴールデン・レーズン……185g
・成形と型取り
クリーム状にした無塩バター……25g
皮無しホール・アーモンド……35g
・アーモンドとオレンジの花のシロップ
ミネラルウォーター……500cc
グラニュー糖……750g
アーモンド・パウダー(白)……65g
オレンジの花の天然香料……5g
・仕上げ
澄ましバター……200g
粉砂糖……200g
スタンド・ミキサー用のボウルに、小麦粉、グラニュー糖、細かく砕いた酵母、7割(130g)の卵を入れて、ミキサーにフックを装着してゆっくりと攪拌します。生地に弾力が出てきたら、残りの卵を入れて、中程度の速度(決して強にしない)で回します。生地がボウルからきれいにはがれるようになったら、バターと塩の花を入れて、再び生地がボウルからはがれるようになるまで、約20分間回します。回し終えたときの生地の温度は24 〜25℃です。レーズンを加えて、1〜2分回して生地に均等に散らします。生地にはりつけるようにしてラップをかけて、生地全体が冷たくなるまで、冷蔵庫で2 時間30分休ませます。
次は成形と型取りです。
バターを電子レンジで温めてクリーム状にします。刷毛を使って、型にバターを塗り、型の溝ごとにアーモンドを置いていきます。生地を2つに分けて、球状にします。手に小麦粉をふって、各々の真ん中に生地を押しわけながら穴を作り、焼き型に入れます。28℃に保った場所に約3時間置いておきます。乾燥した場所なら、型を湿った布で覆ってください。
アーモンドとオレンジの花のシロップを準備します。
片手鍋にミネラルウォーターとグラニュー糖を入れ、沸騰させます。アーモンド・パウダーとオレンジの花の香料を入れて、冷まします。密封容器に移し、冷蔵庫に入れておきます。
クグロフを焼成します。
あらかじめ170℃に温めておいたオーブンに生地を入れて、35〜40分間焼成します。シロップを冷蔵庫から出します。クグロフを型から抜いて熱いうちに、澄ましバターに浸けて、ステンレス製の網の上に縦に置きます。5分間休ませたら、アーモンドとオレンジの花のシロップに浸けます。ステンレス製の網の上に縦に置いて、5分間休ませます。休ませている間、クグロフの穴は必ずしもバターやシロップで満たす必要はありません。粉砂糖をふりかけて、全体が冷えるまで置いておきます。
必ず陶製の型を使ってください。最高の仕上がりになります。型は最初に使う前に、バターを塗って、250℃のオーブンに7 〜8分入れて焼いてなじませておいてください。決して水で洗わずに、布で拭くだけにしてください。6 〜7回使った後に、クグロフ独特の味わいがしてきます。
この続きはぜひ本書でご確認ください。
著者紹介:ピエール・エルメ (Pierre Hermé)
1961 年生まれ。パティシエ・ショコラティエ・企業家。仏アルザスのパティスリーに生まれ、14 歳のときに「現代フランス菓子界の父」ことガストン・ルノートルのもとで修行を始める。1986 年、26 歳でフォションのシェフ・パティシエに就任。1996 年にフォションを去り、ラデュレの改革に携わった後、1998 年に自身のブランド「ピエール・エルメ・パリ」を東京赤坂のホテルニューオータニ内に初出店する。2007 年、レジオンドヌール勲章(シュヴァリエ章)を受賞。2016 年、《世界のベストレストラン50》より「世界の最優秀パティシエ賞」を受賞。現在「ピエール・エルメ・パリ」は、パリ、ストラスブール、ニース、ロンドン、モナコ、ドーハ、東京、横浜、名古屋、神戸などにある。

