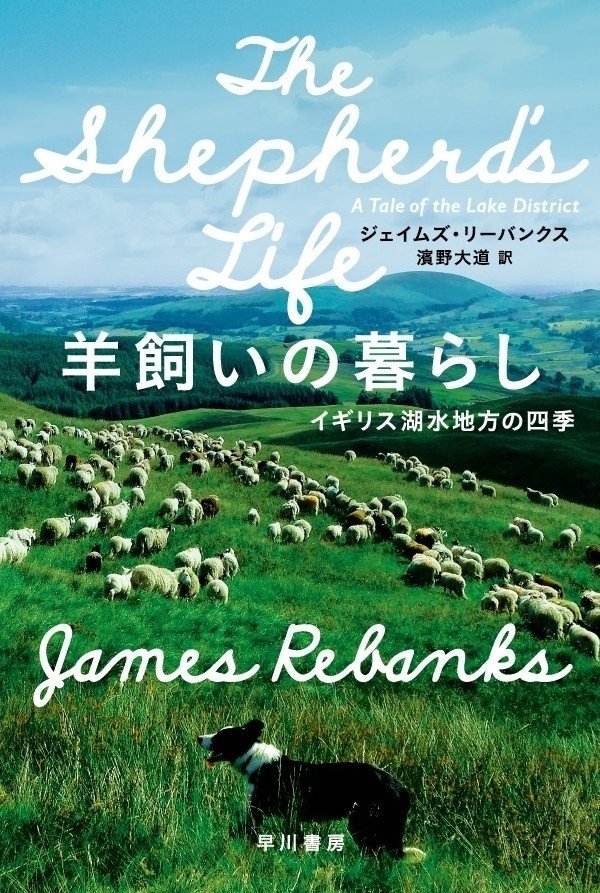多くの人が『こう生きたい』と心のどこかで願っている生活――『羊飼いの暮らし イギリス湖水地方の四季』文庫解説(河﨑秋子:羊飼い・作家)
湖水地方で600年以上続く羊飼いの家系に生まれた著者が、厳しくも喜びと誇りに満ちた農場の日々を綴った世界的ベストセラー『羊飼いの暮らし――イギリス湖水地方の四季』が文庫になりました。本書の魅力を、『颶風の王』で三浦綾子文学賞を受賞した作家であり、北海道在住の羊飼いでもある河﨑秋子氏の解説でご紹介します。
途切れることない伝統と明日も明後日も続く日常
河﨑秋子(羊飼い・作家)
「英国のハードウィック種はなぜ毛が赤いのか」。いつか日本の羊飼い同士の集まりで、そんな話になったことがある。まさか本来あの色であるはずがない。何かの薬剤なのか。赤い土などに自発的に体をこすりつけているのか。人工的に着色しているなら何のためにやっているのか。毛の品質は落ちないんだろうか。そんな声がいくつか挙がったが、結局誰も答えを出せないままだった。
本書はそんなハードウィック種のふるさと、湖水地方で600年以上続く羊飼いの家系に生まれた著者が綴る、静かな情熱に満ちた日々の記録である。日本人にとって湖水地方といえば、高校の教科書でも取り上げられたビアトリクス・ポターによるナショナル・トラスト運動が名高い。日本からも多くの観光客が訪れる、美しい丘陵地帯だ(そのポターが当地では絵本作家や自然保護運動家よりも畜産家として今も羊飼いから尊敬を受けているということを、私は恥ずかしいことに本書で初めて知った)。
著者のジェイムズ・リーバンクス氏は羊飼いの他、ユネスコのアドバイザーや文筆活動 を行い、PCやiPhone を駆使して日々の牧場の様子を発信している。牧場とはいっても、 従業員を大量に雇用し、大規模な土地で多数の群れをシステマチックに管理する効率最優 先の畜産業ではない。代々大事に繁殖させてきた羊を家族と少しの犬とで養う、伝統的な 小規模経営の牧場だ。Twitter で公開されている写真や文章は実に活き活きとしていて、彼がいかに自分の農場を大切にしているかが分かる。
リーバンクス氏の経歴で着目すべきは、オックスフォード大学を卒業していることにある。しかも、農家の優秀な後継者が幼少期から順当に高等教育を受けた結果の最終学歴なのではなく、地元の学校を卒業後、一度は実家で働き、その過程で学ぶことに意義を見つけ、努力の果てにオックスフォード大に入学したというのだから驚きだ。それが彼の故郷でもイレギュラーな経歴であることは、周囲の人の反応として繰り返し本文中で語られて いる。
大学に通う間、彼はいわゆる都会の生活を体験している。家畜の世話で追い立てられるように働くこともなく、柵の修理などというすぐに収入に結びつかない作業に何日も費やさなくてもよい生活だ。彼は卒業後、清潔なオフィスで働き、二度と農場と縁を結ばずに高い収入を得て暮らしていくことは可能だったろう。しかしリーバンクス氏はそれを選ばなかった。こまめに帰省しては農作業を助け、大学在籍時から卒業後は農場に戻ることを周囲にも一貫して伝え続けていた。
文中で幾度も言及される通り、湖水地方で農業を営むことは一般の人が考えるようなロマンに満ちた仕事ではない。しかも、父から息子へと譲られる予定の農場という限定された場所において、そこに発生したと綴られる軋轢や喧嘩は、深いリアリティをもって読者の胸に迫る。おそらくこれらは地域や時代を越えて繰り返されてきたものであり、本書の舞台である湖水地方でも、かつて同じように羊飼いの息子達は葛藤を越えて羊の群れを発展させてきたことだろう。
そうして数百年、数世代を経て、21世紀の現在を生きる著者が牧草地で空を見上げ、自ら選んだ仕事に誇りと満足を抱く最後の描写は、読み手の胸へと静かに染み入ってくる。 リーバンクス氏は、多くの人が『こう生きたい』と心のどこかで願っている生活を静かに継続させている。その事実は、ある種の憧憬と共に、人の心をゆるやかに温めてくれるのだ。本書が刊行されるとすぐに各国で多くの読者から好評を得たという最大の理由は、ここにあるのではないかと思う。
さて、日本では家畜としての羊や、ましてや職業としての羊飼いというのはあまり馴染みがないため、日本の読者諸兄姉は羊飼いならではの独特な生活や仕事の記述についても、新鮮な驚きを得られるだろう。
著者が本書の中で“日本ではスミット・マークはどう受け止められるんだろう?”と疑問を抱いているが、おそらく一般の日本人は羊に縁がなさ過ぎて、「なんか羊に印がついている。そういうものなんだろう」としか感じないと思われる。また、羊の頭数が国内で2万頭を切る現状では、飼育できる農家は各地でぽつりぽつりと点在している程度に過ぎず“羊飼い同士が隣り合っている=自分の羊に特徴をつける”意味がなく、スミット・マークそのものが必要とされないのだ。ちなみに英国各地で盛んに行われるという競り市や品評会も、大きなものは東北で年1回行われるだけだ。
細々とした日本の緬羊飼育だが、実は英国との縁は切っても切れない。日本では各地の畜産試験場で試行錯誤の末、現代緬羊飼育の基礎が確立された。その際に参考とされたのが英国の飼育書だったようだ。農家1軒あたり数百~数千頭を広大な土地で通年放牧をするオセアニア方式は日本では導入し辛い。それに比べ、比較的少ない頭数を、気候的な理由で放牧しつつ畜舎も有効に利用していく英国のスタイルは日本に向くという判断だったのだろう。
現在でも畜産技術協会が配布している基本のマニュアルの一部は当時の翻訳をベースにしており、身近にいる経験者の蓄積を頼りにできないまま羊の飼育を開始する新米羊飼いたちにとって貴重な資料であり続けている。その意味で英国の羊飼いは日本の羊飼いにとって偉大な大先輩といえる(もっとも、極東の島国にも羊が存在し、せいぜい1、2万頭の羊を飼うのにも試行錯誤していると英国の羊飼いが知っているかは分からないが)。
個人的には、リーバンクス氏によって語られる日々の記述は逐一勉強になった。文中、誰かが誤って放してしまった飼い犬が農場の敷地内で羊を傷つけてしまうエピソードがある。私がニュージーランドの牧場に住み込みで羊の飼育を学んでいた時、師匠に「もし町の人や隣の羊飼いの犬が放牧地に入りこんで、うちの羊に危害を与えたらどうします?」と聞いたことがある。師匠は迷わず「ライフルで撃つね。逆に、うちの牧羊犬がよその羊を傷つけたら、即座に殺されても文句は言えない」と答えた。言うまでもなくニュージーランド・オーストラリアの緬羊飼育はイギリスをルーツにしている。『羊飼いは自分のプロパティを守り、それを侵すものに容赦すべきではない』。本書の闖入者は処される運命を免れてはいたが、羊飼いの大原則は大海を挟んでも共有され続けていることを雄弁に証明している。
また、死んだ子羊の皮を剥ぎ、母を亡くした子に着せて疑似親子をつくるのだという記述も、まさに私がニュージーランドで教わったこととまったく同じで、不思議な感動を覚えた(余談だが、この疑似親子関係を成立させる際、近くに牧羊犬を一頭繋いでおくと母子成立の成功率が上がる。母親が義子を守ろうという防衛本能が芽生えるようだ)。
このように緬羊飼育に関する興味深い具体例をいくつも垣間見せてくれる本書だが、おそらく著者にとって最悪の時期についても惜しげもなく記されている。2001年、英国で口蹄疫が発生した際の痛々しい体験についてだ。まだ健康そうに見えるにもかかわらず、大事に育てた羊を殺処分し、ただ死体を焼いて埋めなければならないという悔しさはいかばかりだっただろうか。政府から補償金が支払われたとはいえ、無為に家畜を屠らねばならない痛苦はそんなもので贖われはしない。もし私の地元で同様のことが起きれば、実際の損失以上に精神的な虚しさから離農を決断する農家が続出するのではないかと思う。
しかし著者と、その周りの羊飼い達は驚くべき辛抱強さでこの難局を乗り越えている。互いに助け合い、むしろ結束が強まったとさえ言いながら、家畜の声が消えた畜舎を黙々と清掃・消毒し、次に導入すべき群れについて思いを馳せる。そこにはもちろん農家をやめるという選択肢もあったはずだが、多くの羊飼いはこの誘惑を断ち切り、この困難を乗り越えて再び優秀な羊を育てるのだという力強さに満ちている。そこには、個人や家族の意志といったものを越えて、この湖水地方で存続されるべき役割を果たすという強い信念が横たわっているように思える。
冒頭の疑問に戻ろう。ハードウィックはなぜ赤い色をつけるのか。著者は、本書の中で見事にこの疑問に答えを出してくれていた。有り体にいえば『伝統だから』というその答えを読んで、私は思わず声を出して笑ってしまった(もっとも、より思わしい理由は具体的に二例挙げられてはいるが)。結局、なぜ染めるかという理由よりは、古くからのこの習慣を現代でも守り、実行し続けていることこそが、彼らを21世紀の今もって愛すべき湖水地方の羊飼いたらしめているのではないだろうか。
実利と同時に伝統あれかし。その両方なくして、羊飼いという職業は成立しない。本書から垣間見える大先輩達の誇りに、極東の末端にある羊飼いとして敬意を抱かずにはいられない。そして、本書にてその心意気を教示してくれた著者に深く感謝を捧げたい。
***
『羊飼いの暮らし――イギリス湖水地方の四季』
ジェイムズ・リーバンクス
濱野大道 訳
ハヤカワ・ノンフィクション文庫
発売中