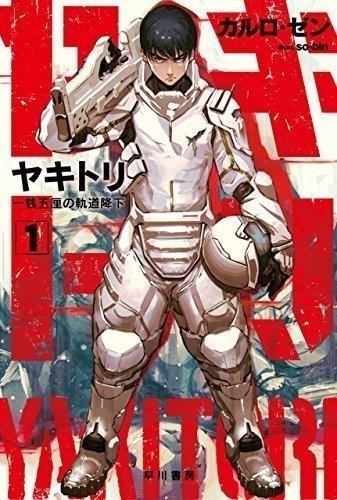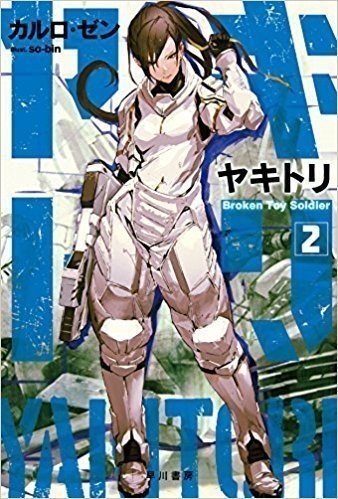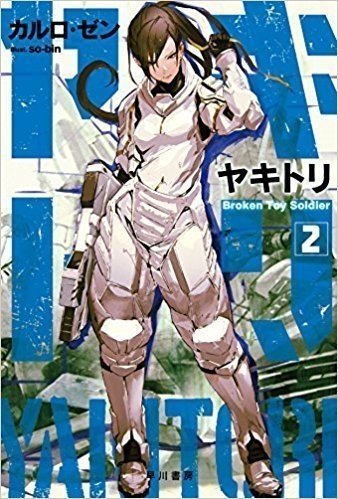【2巻発売!】「遥かな未来、地球人は使い捨ての兵隊になった……」『幼女戦記』カルロ・ゼンの戦争SF新シリーズ『ヤキトリ1 一銭五厘の軌道降下』第二章「貨物」全文公開
第二章『貨物』
エコノミークラスとは? とどのつまり『経済的理由』により『貨物』となることを選んだ階級の事である。——商連標準『貨物』船クルーの戯言
地球──火星間の定期運航貨物船TUE‐2171は、星系内での運用を主眼として商連で広く運用されているKP‐37シリーズに属する標準的な貨物船である。運用者・運航当事者の両者から手放しで歓迎されている同シリーズの評判は、完全自動運航も広く行われるほどの優秀船として伝説的ですらある。
徹底的な省力化と効率化の追求を行いつつも、商連の奇特な設計主任技師は枯れた技術だけでKP‐37を設計してのけた。商連人の気質を知っていれば、驚愕しかない。
いつだって、連中は統計とコストを最優先にする。だというのに、同シリーズはそのようなコスト意識最優先の伝統的商連式設計と信頼性・安全性を両立した。
堅実で、運用が容易で、整備性に優れた星系内貨物船は引く手あまた。地球──火星間の定期航路にTUE‐2171を投入するに際しては、商連内部で『そんな辺境航路にあんな優秀船を投入するのは勿体ない』という反対意見が噴出したほどだ。
そんな裏事情を、俺は、後ほど出世に伴い嫌というほど知る機会に恵まれた。
信じがたいことだが、地球の商連総督府としてみれば、ヤキトリの搬送に際して『格別の配慮』に心を砕いていたのだ。俺が茶の味ってやつを覚えたのも、その一環だったんだろう。
だが、商連の諸氏族と違い、属州民とかいう扱いで乗り込んだ側だった俺としては言わざるを得ない。初めてTUE‐2171に乗り込んだとき、俺は商連が『ふざけている』としか思わなかったということを。
ロンドン郊外──商連管轄宇宙港関連宿泊待機施設
乗船までの段取りは、酷く単純だ。寝床で惰眠を貪るか、タブレットで何か読むか、或いは軽く腕立て伏せでもするか。要するに、部屋で時間をつぶすだけだ。
てっきり、不愉快な社交の時間が必要になるかとも覚悟していたんだが、当てが外れたらしい。パプキンの奴が前口上で『お互いを知っておけ』などと尤もらしく嘯いたせいで覚悟させられていたんだが……ロンドン郊外にある待機用の施設に足を運んでみれば、人影どころか空室だらけ。
まぁ、理由なんて見ればわかる。
商連の用意したのは食堂とちょっとした寝床だけの施設だ。歩いて回ったところで、見るべきものなんて碌にない。暇を持て余す。すぐ近くに、大崩壊以前に栄華を誇った大ロンドンの史跡が多数だ。そりゃ、金さえあればしけた施設なんて飛び出し、観光に行く。誰だってそうするし、俺だって金さえあればそうしただろう。
空室だらけの状況から察するに、俺以外の四人とやらは小金程度は持っているってことになる。ロンドンの物価がどれほどかは知らないが、自由に使える金ってやつだ。パプキンの奴から給料の前借をしておくべきだったかもしれない。だが、そこまで考えて俺は首を横に振った。金を借りるってのは首輪をつけられるようなもんでもある。
正直、電子手錠と腰縄から解放され自由を得たと思った瞬間に、首輪を嵌は
めてもらう趣味はない。
ありもので満足しろってことだろう。慣れた話だ。それに、他の連中が大ロンドン観光に繰り出しているのも、悪いことばかりじゃない。ろくでもない連中に顔を合わせる時間を先送りにできた挙句、5人部屋を広々と使わせて貰えたことには感謝すべきだろう。
パプキンのいうように人となりを知った方がいいという考え方も、理屈の上では一理あるにせよ、俺に言わせればそいつは馬鹿げた空想でしかない。
どうせ、屑ばかりだ。
他人ってやつは、期待すると裏切るし、信用すると裏切るし、警戒しても襲い掛かってくる。馴れ合うっていうのは、自分の死刑執行書類にサインするようなもんだ。
とはいえ、俺はまともな人間で、『妥協』が必要だっていうのも理解しちゃいる。緊張緩和ってやつは欠かせない。不愉快だが、そのためにも意思疎通を避ける訳にもいかないってやつだ。
受験勉強で学んだアルファベットだけで外国語マスターって訳にもいかない。困ったことに、他の連中が日本語を話せるって保証もなしだ。まぁ、幸いなことにというべきか。流石に商連の連中も、その辺は理解しているんだろう。
俺を火星行の船へ詰め込む乗船直前に、肩掛け式の翻訳機と耳栓のようなレシーバーを支給してくれた。パプキンが絶賛していた型と同じやつだ。
そいつを受け取り、指定されたブースで矢鱈と職員に勧められた炭酸飲料のフリードリンクとやらを呷っているうちにぽつぽつと人が顔を出す。同じユニットの連中と顔合わせって試練である。
最初に顔を出したのは妙に陽気な黒人だ。ガタイはしっかりしているし、四角い表情からすれば威圧感すら放ってもいいだろうに、表情の明るさがそれを打ち消していた。
なにより、調子のいい声で奴が英語で何事かを話すと、耳に突っ込んであるレシーバーから女性風の機械音声が、妙に丁寧な発音の日本語でまくし立てるのは変なアンバランスさで笑うしかない。
まぁ、それは、お互い様なんだろう。
一応のお愛想でもって、俺が投げやりに返事をしたところで、奴もこっちと同じように笑い出していた。
「妙になよなよした奴だな。そっちの人間か?」
「お前の言葉も女声だよ」
「なんだ、こいつのせいか」
ぽんぽんと肩に吊るした翻訳機を小突き、男は気障に肩を竦めるとブースのラックから適当な雑誌を取り出し読み始める。
お互い、過剰な干渉はなしだ。
これぐらいならば、まぁ、と思っているうちに姿を現すのは、やや色黒で寡黙な男とアジア系らしい愛想のいい女性。
「ご一緒することになるのかな? まぁ、よろしく」
新しい来訪者二人の片割れが手を上げ、もう片方の女は礼儀正しくぺこりと頭を下げる。
正直、こういうタイプの女はガミガミと煩いのだろうかと覚悟したが……幸い、こいつも、
ついでに言えば新しく入ってきた男も煩くはなかった。
ご丁寧なことに、聞かれてもいない自己紹介を始めるあたりは気に障らなくもない。
だとしても、まぁ、色黒なこいつはスウェーデン人だと自己紹介されねば想像しようがないのも事実だ。てっきり、資源貿易で潤った中東辺りの暇を持て余した小金持ちが、冒険気分で首を突っ込んできたのかと変な誤解をするところだった。
ついでに言えばこれは意外なのだが……女は中国人らしい。黒人がアメリカ人、俺は日本人だ。ここにスウェーデン人を入れれば、かつての先進諸国出身者が勢ぞろい。
軒並み没落した国家に未来なんてない。俺たちは未来を掴もうとおもえば、宇宙で傭兵の真似事なんてやるしかないのだ。対照的に、巨大な埋蔵資源と人口を力に富裕さを楽しんでいる新先進国の中国人が、なんだって傭兵稼業になんて顔を出すのやら。
とはいえ、人それぞれ。
俺は礼儀正しいし、他の連中もそんなことを明け透けに踏み込むほど馬鹿でもなかった。
問題は、残り一人。
そいつは、時間ぎりぎりに姿を現すなり室内を見渡し盛大に溜息すら零して見せる、いけ好かない白人女だった。
外見は、まぁ、整っているというべきなのだろう。背筋はしゃんと伸びていたし、意志の強そうな碧眼だって悪いものじゃない。
とはいえ、乗船直前に初っ端から喧嘩腰!
なにしろ一番最後にやってきた挙句、溜息を零すにとどまらず、『パプキンの奴ったら、
一体、どんな基準でこいつらを選んだの?』なんてほざきやがった。
全く、なんて物事が早いんだ。呆れという感情は侮蔑への第一歩なのだろうが、突き詰めた馬鹿に対しては違う感想も抱きうる。あまりといえば、あまりの衝撃から俺は思わず感心すらしてしまう。いっそ、糞度胸と褒めるべきか?
その女がずかずかと入室するなり、室内の雰囲気が見事に変わっていた。険悪、剣呑、何より最悪極まりないことに疑心暗鬼。
初対面の人間ってやつは、危険度が分かりにくいのが気に入らない。何を言い出すかも分からず、距離感もさっぱり見当が付かないと来た。無関心を全員が装っているにせよ、こいつは一触即発。触れたくもない爆弾だ。
奇妙な緊張感がブースに漂い始める中、前触れなく響く『こんこん』、という音がそのにらみ合いを吹き飛ばす。投げやりなノックだと気が付いたときには、もう、扉は開いていた。
姿を現したのは、船員と思しき制服姿のくたびれた男。室内から浴びせられる視線をものともせず、そいつは軽く手をかざす。
「失礼するよ」
何系かさっぱりだが、耳のレシーバーからは相変わらず無個性な翻訳された柔らかい女性の声が流れてくる。そうして、その男はそっけなく名簿と思しき紙の束を取り出すや、俺たちの顔を見渡し始める。
「全員、時間通りに揃っているとはな。やれやれ、珍しいパターンか」
納得がいったのだろう。小さく勝手に頷くや、そいつは肩を回し始める。
「パプキンさんのユニットだね? 手間がかからなくて結構だ」
確認の態だが、実際のところ、こちらが何かを言う間もない。そいつは勝手に話を進めていく。
「荷物を持ってついてきてくれ。寝床に案内する」
それ以上の言葉も、それ以上の説明もなし。ぐちゃぐちゃ言わない態度は酷くそっけない。とはいえ、制服姿の連中なんて大体そんなものだ。サービス精神旺盛なのは、こっちを嵌めるときぐらいなんだから、むしろ落ち着く。
身一つだと、こういう時に楽だ。
さっさとブースを出ていく船員の背中を俺は機敏に追う。残された連中が慌てふためくのを尻目に、ちょっとばかり乗船まで周囲をぐるりと観察できた。
軌道エレベーターと宇宙港が直結した複合港湾施設ともなれば、音に聞く商連人も一人や二人ぐらいは目にするかと期待したが、影も姿も見当たらない。大方、現地人とは別のスペースに居るか、まぁ、居ないかのどっちかだろう。
どうせ、訓練施設のあるという火星に行けば、嫌でも目にすることになるはずだ。
道中、せめてもの無問題を期待していた俺だが、その願望は船に乗り込むなり別の懸念にとってかわられる。
船内に足を踏み入れた瞬間から目につくのは、殺風景な船内通路だ。収容所を思い出させるような無機質な床。ついでに、酷く粗雑な仕切りで船室というよりもコンテナというほかにないような部屋は『快適さ』とは無縁の旅になるだろうと覚悟させてくれる。
はぁ、とため息をこぼしたくなるに十分だ。
とはいえ、仕方ないとばかりに案内された船室に足を運びこもうとしたところで、俺は不愉快な金切り声を耳にしてしまう。
「冗談じゃないわ! こんな狭い部屋で、なんで、男と一緒なの!」
翻訳機越しにまき散らされるヒステリックな叫び声は、乗船早々気持ちを萎えさせてくれる代物だ。白人女に対する俺の評価が、白い騒音源(ホワイトノイズ)になり果てるのも当然の帰結だろう。
まぁ、確かに、広いとはお世辞にも言えないが……そんなところで騒ぎの種と同室だ。全く、なんてことだろうか。先が思いやられてしかたない。
ため息交じりに俺が天を仰ぎかけたところで、船員の言葉がトドメを刺してくれた。
「TUE‐2171へようこそ、貨物諸君」
狭い寝床、呆れるほど簡素な船室というか、スペースを前にこれ以上は望めないほどに簡潔な説明だ。
つまるところ、俺たちは火星へ運ばれる生きた貨物というわけか。薄っぺらい建前で取り繕わない船員の言葉に対し、俺としてはむしろ感心すらしちまう。そりゃ、貨物船に詰め込めるだけ詰め込むわけだ。下手に嘘くさい建前を口に出されるよりは、よほど、気分がいい。
まぁ、翻訳された無機質な単語の羅列が愉快かといえば……程遠いのも事実ではあるのだが。
「はぁ!?」
冗談じゃないわと叫ぶ未来まで予想できるほど顔面に血を昇らせる白人の女に対し、船員の男は慣れた素振りで呆れたように吐き捨てる。
「君には、女性用Tシャツと男性用Tシャツのコンテナを隔離して積み荷する奇妙な習癖でもあるのかね?」
そんなわけはないだろうと言外にあざ笑い、億劫そうに彼は手を振る。
「勝手にやってくれ」
「はぁ!? なんて無責任なの!?」
制服を纏った人間に噛みついたところで、そいつが意見を変えるなんてありえない。
ついでにいえば、まともな制服組に喧嘩を売るのはアホだけだ。この制服野郎がこっちを騙そうとか嵌めようとかしているならばいざ知らず、そいつはきちんと説明をしている。
先行きの暗さを感じ取り、俺は頭を振る。最初こそ威勢のよさとある種の気骨に感心もしたが、こいつ、ひょっとするとひょっとして……どうしようもないアホなだけかもしれない。
だから、俺は物事を推し進めるために横から口を挟んでいた。
「時間が惜しい。ほかに、こっちが注意すべきことは?」
「ちょっと!?」
翻訳機で訳されるまでもなく、女が怒り狂っているのは理解できた。こいつの碧眼が何よりも良い証拠だ。射殺さんばかりの視線に晒されるが俺も船員も気にせず話を進めていく。
「続けても?」
「もちろん」
構わない、と俺が応じかけたところで横からくだらない邪魔が入る。
「人の話を遮らないで!」
「君たち同士で解決してくれ。具体的には、後で若い紳士淑女として礼儀正しく話し合え。どうせ、火星までの時間は他にやることもないのだからな」
続けても、と視線で問われたので俺は頷く。バカに時間を割いて得をすることなんて、何一つない。
「君たちには、パプキンさんの指定によって火星までの道中、軽い研修と講義がある。それだけは、さぼらないように」
そこで男は更に何事かを思い出したとばかりに、手を叩く。
「おっと、いかん。忘れる前に付け足しておこう」
白人女にさっと向き合うなり、彼はため息交じりに淡々と言葉を継ぎ足す。
「規則上、君たちはお互いに自己紹介することが推奨されているが、それ以上は船室を移ろうが、同衾しようが、お互いに殺し合いでもしない限り我々が何か言うことはない」
以上だ、と一言を残すなり、これ見よがしに疲れたぞと肩を回し、頭を振って見せている
素振りと共に男は港でブースに足を踏み込んできたときと同じ無造作さで立ち去っていく。
その制服姿は、あっという間に俺の視界から消えていった。
かくして、怒り狂った一人が猛然と口を開く。
「……じゃ、続けさせていただいてもいいかしら?」
案件はわかるでしょうとばかりに俺たちを睥睨する碧眼は、自信と確信に満ちている。いったい、何をどう勘違いすればこんな傲慢さが身につくのやら。
「何をだ。自己紹介でも始めるのかい」
スウェーデン人は前向きに話を進めようとするが、彼の努力は無駄というやつだ。はん、
と鼻で笑い飛ばすなり白人女はのたまいやがる。
「部屋を分けるわよ」
「なんだって? 君は、本気かい?」
「スウェーデンでどうなのかは知らない。けれど、普通は男女の寝室を一緒になんてしないのよ」
言外の意味は明白だ。どうせ、性別で分けるから出ていけということだろう。人を舐めた話だが、こいつは、それが正しいと信じ切っているらしい。
だから、後ろから蹴り飛ばしてやろう。
「ああ、良い提案だ」
「日本人?」
どうしたんだ、と目線で問うてくる黒人を無視しつつ、俺は慇懃無礼に『僕』という単語を繰り出す。
「実は、僕もそうすべきだと思っていたんだ。言い出しにくかったが、君から言い出してくれて気が楽になったよ、イギリス人」
嘲るように『僕』は言葉を継ぐ。
「じゃ、君たち、荷物を持って出て行ってくれ。代わりに紳士二人を受け入れることはやるから、まぁ、交代してくれる親切な紳士をみつけるんだな」
「ちょっと待ちなさい!」
冗談じゃないとばかりにいきり立つ彼女は、酷くわかりやすい。
「なんで、私が、出ていく前提なの!? 逆でしょ、逆!」
「僕らが言い出したわけじゃないだろう? というか、言いだしっぺは君だ。……なんだって、俺が出ていくんだ」
出ていけとばかりに俺は扉を指さすと、寝床に飛び込む。硬いマットレスとも言い難い代物だが、まぁ、慣れている。
「男は男で適当にやっているさ」
そっちも、好きにやってくれと手を振ってやる。
「日本人のいうとおりだ。我儘を言っているのは、そっちだろう、ジョンブル野郎。パプキンのやつだって、豪華客船で火星旅行なんていってない。ありもので我慢するか、出てくかだ。引き留めはしないぞ」
道理が分かった言葉だと俺は頷く。
最初から割と好印象だったこの黒人とは、うまくやっていけるかもしれない。
もう一人の、なんといったか、とにかくスウェーデン人も今まで余計な口をきいていないのは評価に値する。
そこで、俺はもう一人を思い出す。
「そっちは、どうするんだ?」
旗幟を示せよと俺と黒人の視線に晒された中国人は軽く肩をすくめて見せる。気障な所作というほかにないが、奴がやるとなぜか、様になっていた。
「どうするも、こうするも、どうするの?」
「なんだって?」
理解できないとばかりに問い返す俺に対し、そいつは軽く黒髪に手を這わせながら呆れたソプラノの声で呟く。
「何? さっきから、『君たち』って私も追いだすつもり? それはフェアじゃないわ」
ちらり、と俺を睨みつけてくる黒い瞳に浮かぶのは苛立ち。
はた、と俺はそこで気づく。
確かに、その通りだった。
わめきたてているのは白いゴミであって、中国人は関係ない。
「……それもそうだ。別に、こっちも追い出したいわけじゃないしな」
深々と頷き、俺は自分の誤りを認める。俺だけが突出すれば、背中ががら空きだ。正直、しくじりだった。こいつは、どうにも気まずい。……矛を収める頃合いだろう。
言葉の応酬がひと段落したところで、パン、と手が叩かれる。誰だと見やれば、困ったような表情のスウェーデン人だ。
「仲間内というには気が早いが、同室で殺伐とするのもやめてほしい」
「俺だって、戦争には反対だ。だがなぁ、こういうのは筋がある。文句があるにしても、始めた間抜けに言ってくれ」
スウェーデン人が仲介し、黒人が同感だとばかりに頷きつつ、黙りこくっている白人の女へ視線を向ける。あいつが始めたトラブルなんだが、と言いたいのだろう。
困ったことに、スウェーデン人は玉虫色ってやつが大好きらしい。反論が噴き出す前に、如才なく話を適当にまとめてしまう。
「別に揉めたくはないんだな?」
その通りだと俺と黒人が頷くや、パンと奴は再び手を叩いて話を勝手に進めていく。
「じゃあ、無駄な時間を使ったということにしよう。翻訳機械の問題か何かだったということにしようじゃないか」
そして、今しがたまで曖昧に微笑んで見せていた中国人が同調し始める。決まったわねとばかりに、彼女は話を継ぐのだ。
「よくわからないけれど、とりあえず自己紹介を始めるのでいいかしら。勿論、皆がよければ、ということだけれども」
同時に彼女はそっと目くばせを白人女に飛ばす。
どうやら、情勢の不利を悟れる程度に、頭はあるのだろう。四対の視線に晒されていたそいつは、作り物とわかる見事な笑顔で微笑むと頷いて見せる。
「そうさせていただければ、幸いね。ご面識を得られて、光栄だわ」
これで、ひと段落。
ああそうかい、と手を振るなり黒人が口を開く。
「では、まぁ、よろしく。紳士淑女の皆様。タイロン・バクスターだ」
自己紹介の時間というやつだ。名前で呼び合う仲ではないし、本音で言えば馴れ合う腹なんて微塵もないにせよ、知っておくに越したこともない。
他の連中も思惑がどうであれ、似たようなことを考えているんだろう。名乗った黒人に続く形で時計回りに他の面々も口を開き始める。
「楊紫涵(ヤンズーハン)。ズーハンでいいわ。そっちが名前」
「エルランド・マルトネン。よろしく頼む」
順がめぐってきた際、そうだな、と俺も口を開く。
「伊保津明だ」
最後の最後になって、白人の女も愛想よく笑う。
「私はアマリヤ。ああ、アマリヤ・シュルツよ」
もっとも、台無しにするのも一瞬だ。
「あまり、馴れ馴れしくしないでくれればいいわ」
つっけんどんなセリフは、まぁ、こいつと仲良くやっていこうという奇特な人間がいたとしても突き放すには十二分すぎる。端から、見下した台詞っていうのには感激だ。くそ野郎め。
外見はさておき、中身はヘドロのような性格もいいところだろう。性根が腐りきっているに違いない。折を見てゴミに出すしかないかもしれん。
にも拘らず、というべきか。
諦めない中国人が場を取り繕うのには驚かされる。
「まぁ、ちょっとばかり尖った発言だけれども、彼女の言い分にも一理はあると思うわね。
実際のところ、私たちはお互いのことをよく知らないもの」
そうでしょう、と彼女はスウェーデン人に話を振る。案に相違せず、スウェーデン人は骨折りの労を惜しまないらしい。見た目こそ中東系だが、こいつも平和愛好家のスウェーデン人ってことなんだろう。なんで宇宙へ傭兵稼業に来るんだか。
「そうだな。彼女たちの言い分も分からなくはない。追々にせよ、お互いを知っていこうじゃないか」
「俺たちが仲良くおしゃべりでもするってか? 一体、なんについて語り合えばいいかご教示いただけますかね」
皮肉気に哂う黒人の突っ込みに対し、平然とした表情でスウェーデン人は返す。
「例えば、そうだな、なんだって僕たちがヤキトリと呼ばれるかとかは? 僕は気になっているし、折角だ。皆の意見を聞いてみたい」
ピンポイントな話題選びだった。全員が関心を持つ部分であり、それでいながら差し障りのない無難なテーマ。
反論するのも馬鹿馬鹿しくなったのだろう。キョトンとしていた黒人は苦笑しつつ、負けたとばかりに軽く頭を振る。
「じゃあ、スウェーデン人に倣って知恵を寄せ集めてみようじゃないか」
だがなぁ、と同時に黒人から放たれるのは根本的なぼやきだ。
「この稼業で俺たちがヤキトリと呼ばれるらしいってのは、まぁ、聞いている。てっきり、外国語か何かで翻訳されれば分かるかと思っていたんだが、どうもこの翻訳機はヤキトリ= ヤキトリと認識しているみたいでな。意味がさっぱり分からん」
誰か知っているか、と問うような目線に応じたのは白い騒音源だった。
「ヨーロッパ由来の言葉には思えないわ。……少なくとも、ラテン語由来ではない。外来語かしら? でも、聞き覚えがないわね」
ああ、そうですかと流した俺とは裏腹に、スウェーデン人は興味深そうに頷いていた。きっと、その気になればいくらでも無駄話に頷くことができる精神構造なんだろう。
この手の人間というのは、あまり信用するべきでないかもしれない。……すぐ付和雷同するタイプかはさておくにしても、どうも、気に入らないのだ。
「そうだな、僕も聞いたことがない。中東やヨーロッパじゃないとすればアジアかアフリカだろう。そっちはどうだ?」
スウェーデン人に話を振られズー、なんといったか、とにかく中国人が頷く。
「正直、奇妙な発音ね。……ただ、日本語の発音に聞こえなくもないわ。悪いけれど、あなたは、知らないかしら」
俺はそこで自分が問われていると気づき、口を開く。
「ヤキトリ……ああ、畜生、翻訳されたのが分かる。こいつは、ヤキトリ、ヤキトリ、違う、焼き鳥だ!」
「焼いた鳥?」
キョトンと問い返してくる中国人に対し、俺は頷く。
「そうだ、焼いたチキンだ。日本語でそういう意味になる」
「ジャパニーズ、僕たちは焼かれたチキンだということか?」
「俺に聞かれても分からん。すくなくとも、日本語としてはそういう意味だ」
焼き鳥という単語ぐらいは知っている。俺の配給券や収入じゃ碌に食べることもできず、代わりに三食共に合成プラント製のゴム味じみたゴミを食っていたが。
どちらにしたところで、一体全体なんだって、傭兵がヤキトリと呼ばれているのかなんて由来まで俺が知るわけもないだろう。パプキンに聞いておけばよかった。
「つまり、日本語とスリランカ語で焼かれたチキンって意味?」
白い騒音源も、普通に会話することができるらしい、まともな音量で会話しえるなんて、
商連の連中が地球に来訪した時以来の衝撃じゃないだろうか。
だが、そこで俺は引っ掛かりを覚える。
「スリランカ語? ああ、いや、聞いた覚えがあるような……」
「商連での公用語だぞ、日本人」
説明してくれる黒人に、俺は頭を下げる。そうか、そういえば、そんな話を聞いたことがあるような気がしたんだ。
「それは、本当なのかしら」
ああ、またか。なんだって、この女はと俺は軽い苛立ちを込めて白い騒音源に視線を向ける。
「どうして疑うんだ。こいつの言っていることが間違っているのか?」
違うわ、とそいつは金髪頭を横に振りながら言葉を継ぐ。
「……わざわざ宇宙からきた連中が、常識的に考えて地球の言語を利用する理由なんてないはずよ。そもそも、スリランカ語なんてあったかしら」
「はぁ?」
よく分からないことを言い出す奴だなと、俺はそこで匙を投げだす。
分かっていたことだが、こいつらと議論したところで何一つ進歩しない。仮にしたところで、むき出しの暴力でぶつかり合いにならないだけ、マシだと割り切るべきなのだろう。
「まぁ、何はともあれ落ち着いたようで何よりだ」
「ええ、それが一番よ」
スウェーデン人と中国人が取り持った平和というやつだろうか。
何よりであるという点には同感だが、果たしてこれでトラブルの芽が摘めたかは酷く疑わしい。それでも、進捗ではある。一歩、前進というわけだ。
分からないことが、分かったぞと不承不承ながら全員で一致できるのは、まぁ、仮初にせよ部屋の雰囲気をよくする。
どんな連中とだって、最初からけんか腰で殴り合うことは稀なんだ。だが最初こそよくたって、後から悪化するのはありふれている。ほどなくして罵りあい、手が出るに至るものだ。
笑顔で和やかな談笑とまではいかずとも、俺たちは狭い5人部屋のモニターで船が火星へ飛び立つのを視聴して過ごす。
「船長より乗員ならびにヤキトリ諸君、本船は只今より出航する」
全艦放送で船長が宣言し、ハッチが閉じられるや船内は閉鎖環境系に移行する。
管制の誘導灯に導かれ、火星への旅路に出発だ。景気づけか、前途を祝うためか、兎にも角にも威勢の良い調べを艦内スピーカーが流し始める。
そうして、定期運航貨物船TUE‐2171は定刻通りに宇宙港のドックより離床した。
かくして、俺は『ヤキトリ』なる珍妙な呼び方をされる傭兵として宇宙への旅に乗り出していくことになる。
地球から突き出たポートから離れた瞬間、旅立ちを意識したのも束の間のこと。港湾施設とチューブで連結されていた際には気が付きもしなかった問題が、出航した瞬間から押し寄せてくる。
ただ、まぁ、認めるのは癪なんだが……俺も幾らかは油断していたんだろう。マジものの喧嘩に至るまでは、いくらなんでも、ちょっとばかり、多少にせよ、だ。落ち着く時間くらいはあるだろうと。
ハッキリ言えば、全然、時間なんてなかった。
狭い船内が混むのは当然予想できていたが、俺は人混みには慣れていた。福祉ってやつは、いつでも密集した狭苦しい団地、公共食堂の混雑、きわめつけはどうしようもない過収容の慢性化した収容所のセットだ。
人混みは、いうなれば俺が生まれた日本では、生まれた瞬間から所与の前提だった。
だから、軽く考えていたのだと認めよう。宇宙に出れば、嫌でも狭い空間で生活を他人と共にすると聞いた時も……我慢できると単純に考えていた、と。
俺にはどうにも、想像力とやらが乏しかったらしい。
宇宙船という閉鎖密集空間は、悪夢だ。これに貨物として乗るという時点で懲罰に等しい。それこそ、信じられないことにベッドだけで言えば、社会福祉公団の収容所を恋しくさせるにすら十分だ。
人工重力の気持ち悪さは、三半規管にとって我慢の限度を凌駕している。
脱臭装置が機能し、機内の空気は正常だと表示されるのは癪に障る。正常であって、清浄ではないのだ。
直ちに影響がなければ、問題ではないらしい。奴隷貿易船とやらだという黒人の評価に、俺は心底から同意する。詰め込まれた千人単位の呼気が中途半端に循環するなど、他に例えようもない気持ち悪さだ。
挙句、騒音が付きまとう。
いや、白い騒音源のことじゃない。あいつも頭痛の種ではあるが、もっと悪いのは出航と同時になり始めた『モーツァルト』とやらの曲だ。
最初こそは、威勢のいい音楽だと歓迎もしえたが、これが四六時中となると話は別になってくる。ただでさえ悪い気分のところに、エンドレスリピートされれば殺意も湧き起こるのは必然だ。
乗り合わせたほかの連中だって、そういう気分になるのは当然だろう。スピーカーをぶち壊そうという努力が払われたのは自然な現象だった。くそ野郎をぶちのめしたいのは、誰だって同じだろう?
が、破壊活動への意欲は一瞬で散華していた。
呆れたことに商連人は、音楽を流すスピーカーを軍用の装甲板か何かで防護しているらしい。それどころか、攻撃されると音量を増す仕組みが組み込まれていた。つまるところ、叩けば叩くほど、音量が増える素敵なシステムだ。
散々にモーツァルトの曲が氾濫する船内で、状況を把握した船長がスピーカーの音量を調整しなければ、全員が睡眠不足で倒れることになっただろう。酷い話じゃないか。宇宙に出る際、散々、リスク説明とやらは受けた。だが、誰一人として宇宙船生活がここまで過酷だと語らなかったのは許しがたい詐欺も同然じゃないか。
一刻も早く、惑星におりたい。本物の重力が、まともな寝床が恋しくて仕方がなかった。
そんな願望にもかかわらず、TUE‐2171は航程の半分を通過したに過ぎないのだ。こんな状況でパプキンのいうところの、新しい教育プログラムとやらに基づき、基礎的なガイダンスとやらをK321ユニットこと俺と残り4人だけが受けさせられたのは、事態を最悪にする。
教育プログラムとやらが翻訳機で5言語をまき散らす騒音の中で、知識を暗記するように求められる! 正気とは思えぬ所業だった。レシーバーの設定を変え、耳元に直接届くように改善されるまで、これに耐えた俺の忍耐力は勲章物だ。
ただでさえ頭が回らず、はっきりといえば気持ち悪い気だるさに詰め込み教育が加わる感覚は形容しがたい。一言でいえば、最低だ。
しいて言えば徹夜した時の感覚に近いのだろうが、眠気の酷さと、体のダルさは比較にならないほどに億劫きわまりない。
トドメは、船内の食事だ。劣悪、その一言に尽きる。無重力空間でも食べられるようなチューブ食だというのは、まぁ、良い。宇宙で食べるんだから、そういうものだと言われれば理解できるし、我慢もする。
問題は、中身だ。
バリエーションがなし。僅か一種類の味とくれば、せめて味わいだけでも期待したいところだが、こいつに至っては最底辺決勝戦に相応しい代物。
完璧な栄養バランスを謳っているパッケージラベル曰く、商品名は『大満足』。でかでかと、数か国語で『大満足』なんて印刷されていやがる。なにをどうすれば、どこに満足の欠片があるのか聞きたい代物とはこいつのことだ。
そんな食生活と閉鎖環境へ訳の分からない特別な教育プログラムの三重苦だ。まともな俺が被るストレスってやつは、計り知れないほど深刻だった。
俺ですら、そうだ。フラストレーションを溜め込んだ人間が狭い船室に詰め込まれているとくれば。トラブルなんぞ、それだけでも時間の問題だろう。
「空気がだるすぎる。おい、ジャパニーズ。冷却器を動かしてくれ」
「もしくは、スピーカーを黙らせる方法を探そう」
「大賛成だ。なんとかしよう。モーツァルトに対する殺意で頭がおかしくなりそうなところだったんだ」
俺と黒人が軽く愚痴をこぼしながら、船室でわずかな自由時間を平和に過ごしていた際、白い騒音源が噛みついてきたのもある種の必然だった。
「やめなさい。冗談じゃないわ。それ以上、学習もせずにまたスピーカーを煩くしたいの?」
そんなわけないだろうに、なんだって吠えるんだか。冗談も分からないとは、それこそ冗談じゃない。
はぁ、と黒人がため息をこぼしつつ口を開く。
「イギリス人、頼み方ってやつがあるだろ」
「まったくの同感だ」
礼儀ってやつを弁えろと俺は促してやる。
「ええ、ええ、そうね。では、親愛なる愚者紳士諸賢、まことに僭越ながら愚行はおやめあそばしいただけるかしら?」
翻訳機越しにせよ、嘲るような言葉はあからさまだった。なにより、本当になによりも俺の癪に障るのはあいつの表情。
見下し、平然と侮蔑している姿は捨て置けない。
「黙れ、ホワイトトラッシュ。騒ぐだけならば、お前もスピーカーも同じだ」
カチンときた俺は、短く吐き捨てていた。
きょとん、と一瞬耳のレシーバーを押さえたあいつはそこで表情を怒りで沸騰させるや、爆発する。
「ジャップ、そっちこそ黙りなさい!」
一触即発の空気。
いっそ、殴り飛ばして黙らせてやろうかと実力行使を俺が考えたところでぽん、と肩に手が置かれる。
「……別に我慢できない温度じゃないだろう? 無理にもめる必要はない」
「スウェーデン人、放っておいてくれないか」
「そうしたいのはやまやまだが、時間をみてほしい。お勉強の時間だ。移動しなければ」
TUE‐2171は貨物船だ。したがって、講義室なんて気の利いたものも本来であればあるはずがない。だが、幸か不幸か、ヤキトリの搬送船として長らく活用されているうちに小さなスペースくらいは誰かが設ける必要性に思い至ったらしい。
おかげで、俺たちは、くだらない勉強を延々と繰り返す羽目になっている。
「教育AIのマグナスです。いつものように授業を始めましょう」
機械的な合成音声。それが耳元のレシーバーから流れてくる。まぁ、英語、中国語、スウェーデン語、日本語と音声が混じるよりはヘッドホンから流れる方がましだ。
モニターを映し出す都合か、室内の光源が消灯してるため奇妙な眠さに誘われる。そして繰り返されている授業内容だが、こちらも眠気を誘うに十二分な代物ときている。
なにしろ一度聞けば分かることの繰り返しで、殆ど真新しいものがない。基礎的なガイダンスとかいうやつは、大したことを俺たちに教えてはくれないのだ。
例えば商連は現在、複数のいわゆる列強と微妙な関係にあるらしい。列強、要するに宇宙の覇権をも握りうる存在。もっとも、実際のところ宇宙は広漠極まりない。領土をめぐり争うという発想自体が、狭い惑星上での思考なんだろうか? 宇宙の場合、列強同士は戦争なんて『高すぎる』という発想で、冷戦状態らしい。
直接的な衝突は回避しつつ、大植民時代ってやつだ。地球のように、列強が発見した惑星に『統一政体』がない場合、早い者勝ちということもあって熾烈な競争の真っ只中だとか。だから、ゴタゴタも多い。対応のために俺のように『商連市民』じゃない地球人にお声が掛かるってわけだ。
ここまで俺が理解する限り、主として三つの主要な勢力が商連にとって目下のライバルらしいが……正直なところ、その何れもがどういう存在なのかさっぱり理解が難しい。
そこらの説明を求めようにも、教育AIとは名ばかりのマグナスは碌に答えもしないのだ。こっちは、こいつがまくし立てる言葉を記憶する以上にやることがない。
「ヤキトリに求められるのは、惑星地表における地上戦への対応です。商連艦隊司令部は、惑星上の事態に対応するためのありとあらゆるソリューションを模索しており、その一手段としてヤキトリは期待されています」
要するに、鉄砲玉。商連の高貴な商連人様は、惑星がお好きじゃないのだ。汚く、きつく、危険な3Kは自分たち以外にやらせるというのは宇宙人も日本人も変わらないらしい。
ああ、いや、と俺はそこで皮肉気に哂う。この点でいえば、商連人はフェアだ。強制するわけでもなく、代価も支払ってくれるってんだ。
ついでにいえば、パプキンの奴も比較的誠実だったってことなんだろう。今の今まで、説明された話はちゃんと奴からも聞かされている。
パプキンといい、商連といい、好きになれないにしても、最低限は我慢できる連中らしいじゃないか。……とはいえ、こんな授業はだるくて仕方ない。
いや、授業そのものが億劫なのは事実だが、それ以上にこれを無意味だと感じさせるのはもっと根本的なところに理由がある。
船内の噂話だが、なんでも、火星には『記憶転写装置』とやらがあるらしい。噂というよりは、半ば公然の事実というべきだろうか。
船員ですら、聞かれさえすればそれが事実であると肯定している。
火星にある設備を使えば、必要な知識は脳に転写されるという話だった。つまるところ、こうして無駄に努力して暗記するまでもなく、きちんと知識は向こうで頭に詰め込めるということだ。そんなものがあれば、俺の受験勉強もずっと捗っただろうに。
おかげでこっちは、偶に通路ですれ違うような他のユニット連中から『無駄なご苦労』だと軽く同情すらされる羽目になっている。
「軌道よりの突入作戦は、主として三つの段階的な進捗に基づくものとなります」
最初に学習を始めたときは、まだ、真新しい情報と呼べた戦術ガイダンスも似たようなことを繰り返されれば既知の知識となる。俺は小さな欠伸と共に、モニターへ映し出される映像へおざなりに視線を向けていた。
俺に限らず、全員がそうだろう。
「第一段階は、軌道への進入です。商連艦隊が敵の防御を突破し、惑星上への進入路を確保しおえた段階で突入作戦が発令されます」
惑星と思しきホロ画像が浮かび上がり、その軌道上で商連のものらしき艦艇が陣形を構築しだす。
要するに、ヤキトリを下ろす準備というやつだろう。
「第二段階は、準備砲撃になります。ただし、戦時交戦規程並びに戦局の状況によりこれら
は省略される場合があります」
ホロ上で商連艦艇が惑星に何かを射出し、敵の抵抗と思しきものを排除するシーンが映し出されるも、正直、こんなに物事が順調に進むとは信じられない。教科書に書いてあったり、教育AIとやらの記述や説明は『理屈上では』ということに過ぎないのだ。
要するに、建前だ。
信じて馬鹿を見るのは、あほだ。それは、自己責任も良いところでしかない。迂闊に信じるから、簡単に裏切られる。当然の真理だ。
俺の気も知らずに、教育AIマグナスは淡々と言葉を続けていく。
「最終段階において、各ヤキトリは軌道上に展開する進攻降下母艦のTUF‐32型突入ランチャーより、TUFLEに包まれて惑星に向けて射出されます」
TUFLEは、三種類のパッケージを組み合わせた卵型の一人用突入支援装備とのことだ。ヤキトリは、黄身の部分に相当する『兵員区画』と大げさな名前の付けられた中に乗り込む。
当然、説明されている限りから察するだけでも酷く狭苦しい。なにしろ、この貨物船の寝台よりも狭いらしいのだ。想像は容易だろう。
さて、肝心の卵だが白身の部分には主成分が商連軍指定軍事機密とやらで明らかにされていない『保護ジェル』が充てんされており、薄っぺらい真っ黒な殻が大気圏に突入する際に割れた後も黄身を守ってくれる……らしい。
商連の管制AI曰く、ヤキトリに対する安全性は確立されており、問題が起きたというクレームは『ただの一例』もないとのこと。
事実であれば実に喜ばしい。本当に。幸か不幸か、まともな知性と理性のある俺は少し違った見方をしているが。
文句がないって謳い文句の裏を返すとすれば、文句を言おうにも、TUFLEでトラブルが起きたやつは全員が死んでいるかもしれないのだ。
死人に口なしとはよくいうものじゃないか。
「TUFLEを活用しての降下作戦は、ヤキトリの損耗率を劇的に減少させており、従来の被撃墜率は八割から四割へと改善を見ました。事実上、損耗率の半減という偉業です」
……文字通りの全滅から、軍事的な全滅への改善。
げんなりとしたこっち、ああ、五人分のため息からなる重たい空気が室内に漂うが、空気を読まない教育AIのマグナスは構うことなく機械音声で続ける。
「以上で、本日のレクチャーを終了いたします。この後は標準教育プログラム通り、学習時間終了までの間、皆さんでのフリーディスカッションを推奨しています」
その言葉と共に、モニターの電源が落ち、室内の電源が回復する。意味するところは、見たくもない素敵な隣人の顰め顔が見られるようになるということだ。
気まずい沈黙が支配する室内で、俺は知ったことかと自分の爪を眺め始める。苛立たしさを紛らわすために、こいつを噛むのが果たして有益だろうか?
どうでもいいことか、と頭を振る前に場の雰囲気を取り持つのはチャイニーズだ。
「おしゃべりしろ、と授業中に言われるのは相変わらず慣れないわね」
困ったように語る言葉に、中身なんてない。
単に中国での生活を振り返っての感想だろう。厄介なことに、俺にとっては古傷を刺激する嫌な回顧だが。……腐りきった学校を懐かしめる奴が眩しくて仕方ない。平静を装うのも一苦労だ。だが、それが呼び水となって言葉が交わされ始める。
「理解したかお互いに確認しなさいということでしょ? 学校でやったことと同じよ」
分かりきったことじゃないとイギリス人が嘯く。
自分は、教育を受けているという自慢だろうか? 相変わらず、鼻持ちならない奴だ。どっちつかずな態度をとる中国人といい、この白いゴミじみたイギリス人といい、気に入らない。
なんだっていいと暫く気にせず、俺はただただこの時間が過ぎてくれることを願っていた。授業時間が終われば、後は飯という名の餌を流し込んで、自由時間だ。そんなことを考えながら、口を開かずにいた。
「ジャパニーズ、そういう無関心な態度はいけない。軽くで構わないから、会話にも参加してくれ。一応、我々は共にやっていくことになっている」
スウェーデン人の言葉に俺は顔を顰める。
何度も何度も胡散臭い言葉を繰り返す奴だと気に障っていたが、どうにも辛抱の限界を超えそうだ。共にやっていくだって? 正気か、こいつ。
理解しがたいぞと睨む俺に対し、しかし、そいつは一歩も譲らず睨み返してくる。
呆れたことに、どうも本気のようだ。
「足を引っ張るつもりはないし、引っ張られない限りは上手くやれるはずだ」
俺の言葉は、どうやら、感銘を与えたらしい。ただし、眉を顰しか
めているスウェーデン人にではなく、笑い出している黒人にだが。
「日本人はいつも小気味良いな。気に入った。そういうやり方はフェアだ」
そういうなり、そいつは手を差し出してくる。
「タイロンと親しく呼んでくれ」
首を突っ込み過ぎず、お互いに弁えた関係であれば拒否する理由もない。まぁ、こいつならばと俺は手を握り返す。
「伊保津だ。そっち流だとアキラか?」
「よろしく、アキラ。うまくやれそうで何よりだ」
ああ、そうだなと俺は笑う。
「そんな関係でいいならば、私も混ぜてもらいたいかな」
「チャイニーズ?」
「自己紹介したでしょう? 紫涵よ。呼びにくいならば、崩してズーハンでもいいから名前を呼んで。チャイニーズとひとくくりにされるよりは、幾分なりとも親しみを込められるでしょ?」
割って入ってくるのは厚かましい中国人。細い手を差し出し、私とも握手なんて平気で言える神経の太さには驚かされる。愛想こそいいが、腹の底で何を考えているか分からないやつだ。手を握れば、何を奪われるかも分かったものじゃない。
「ズーハン、悪いが、俺はお互いのことをよく知らないんだ。分かるだろう?」
俺の譲歩たっぷりな言葉に対し、中国人は軽く眉を顰めるも丁寧な笑みで応じる。
それだ、その作った表情! 気持ち悪いといったらありゃしない。新先進国の連中なんて、腹の底で一体、何を考えているんだか!
「では、友情を深めるために共に食事と洒落こもうじゃないか。皆で行くとしよう」
立ち上がりながら戯言を口に出すスウェーデン人に、俺は呆れ顔で指摘してやる。
「親睦が深められる食事だっていうのか、あれが?」
「共通の苦難を乗り越えるのは、団結への第一歩だよ、ジャパニーズ」
ああ、なるほど。つまり、酷い経験を共に分かち合おうということだ。それだけは、いけ好かないイギリス人とも共有しようって腹になれる。ただ、イギリスは飯のまずさで伝説的だ。タイロンの言葉じゃないが、フェアなダメージか疑わしいが。
そういう次第で、俺と不愉快な同室のメンツは連れ立って、運命共同体とばかりにTUE‐2171内部の食堂スペースに移動する。
とにかく大量のヤキトリを詰め込むことだけを目的としている貨物船だけに、食堂スペースといったところでチューブ食を受け取る自販機のような機械が数台並んでいるほかは、固定された机があるぐらいだ。
時間割通りに入室し、交代で給餌されるというわけである。
「……相変わらず、ひどい味だわ」
珍しいことに、俺は、イギリス人に同意すらしてしまう。
口の悪いイギリス人をさえ閉口させる味。この騒音源を黙らせるためならば、いくら払っても惜しくないつもりだが……この食事の味だけはない。
福祉の食事だって、まだ、これよりはましだ。
黙って流し込もうにも、気持ち悪い粘度があるそれは嚥下前に少しばかりの咀嚼を必要とするという、拷問じみた食事だ。
どのテーブルも、例外はない。俺のユニット以外だって、黙々と不景気な顔で食事を流し込み続ける。こんな作業に耐え続けるのは不可能だ。そんなわけで気分転換を兼ね、隣のグループに話しかけたり、話しかけられたりする。飯のまずさが促す交流ってやつだ。
今日、俺たちに話しかけてきたのも食事に耐えかねたらしい一人の男だった。
「相変わらず、酷い味だよな。おまけに、酷いホスピタリティ! 時間を持て余して仕方がない。そっちのグループはなんか、暇をつぶすやり方でもあるのか?」
「ご存知の通りだ。船中が知っている話だろう? 愉快痛烈極まりないお勉強会が設定されている。後は、最近、茶とかを呑んでいるさ。そっちは?」
タイロンの皮肉にそいつは笑い出し、笑い終えたところで口を開く。
「すまん、すまん。噂通りだったとはな。こっちは『大満足』を洗い流すために茶を啜りつつ、端末にあるメディア・アーカイブを見たりだな。良い暇つぶしになるぞ」
映像を再生しているときは、モーツァルトもある程度は無視できるしな……とそいつは苦笑する。延々とリピート放送されている忌まわしい音楽を紛らわせるならば、なるほど、そいつは悪い知らせじゃない。
良いことを聞いたと俺は感謝を示すために、小さく頭を下げておく。
「あとは、一日、1分30秒ぶんだけ地球と無料でビデオ・メッセージをやり取りするサービスがあるからな。ほんのわずかだが家族と連絡さ。叔母さんに怒鳴られるのは癪だが、弟共が元気なのを知れるのは気分が上がるってもんだ」
お前たちはやらないのか、と何気なく問うてくるそいつはアホだろうか。なんだって、そんなことをしないといけない?
「こんなところじゃ、息も詰まるだろ」
詰まるが、家族と面を合わせるのも同じだろうと思っていた俺は次の瞬間、大いに驚かされる。意外なことに、タイロンが尤もだとばかりに頷いているじゃないか!
「確かに、送れるならば送ってもいいか」
「おいおい、その感じだと使ってないのか? 勿体ないな。誰か、枠が余ってれば売ってくれ」
家族との面会時間を欲しがる奴がいるというのは、俺には理解の範疇外だ。しかも、金を払ってでも欲しがってやがる。
「いくらだ?」
好奇心をそそられた俺の言葉に対し、そいつは軽く首を振って釘を刺してくる。
「おいおい兄弟、使わないやつを高く売りつけるのはやめてくれよ。別に、こっちがどうしても買わなきゃいけないほどの理由はないんだぞ」
確かに、俺には必要のない枠だが……さて、どうしたものだろうか。相場が分からないだ
けに、これはちょっと難しい。
とはいえ、一日分の枠なのだから、一日分と等価だろう。
商連ってのは律儀なことに、火星への移動途中も『契約により移動』なのだから賃金ってやつを払ってくれている。訓練を終えるまでは大した金額じゃないにせよ、きちんと契約と同時に開設された商連の電子口座に振り込まれていた。
「三日分の枠を、三日分の給料でどうだ? もしくは、三日分の茶葉」
「高すぎだ。話にならん」
呆れた表情でそいつが席を立っていくところからすると、見込みなしか。本当に、相場以上だったのだろう。とはいえ、別に、俺も無理をして売らねばならない事情があるわけじゃない。面会が義務であれば、金を払ってでも人に押し付けたかもしれないが、そうじゃなきゃ別に売らなきゃいけない切羽詰まった理由もなし。
やれやれ、と食事という名の拷問を再開しかけたところでテーブルの中から声が発せられた。
「ちょっといいか」
「どうした、タイロン」
「誰か、俺に売ってくれるか? 俺もブラザー共の声が聞きたいんだ。もちろん、さっきのアキラみたいな馬鹿げたレートはやめてくれよ?」
取引のオファーを申し出たタイロンに対し、テーブルの輪の面々の中で中国人が即座に反応する。
「貸し一つで売るわ」
「金じゃだめか?」
「いいえ、貸しを一つでしか売らない」
少し頭を抱え、タイロンはそこでぽつりとつぶやく。
「……チャイニーズから借りを作ると怖いな」
尤もな発言だろう。
俺だって、腹の底が分からないやつに借りなんて作りたくはない。まして、自分の意見を隠しているようなこいつには猶更だ。
「じゃ、いらないの?」
「迷うが……ほしい。高くつくだろうが、納得できるフェアなディールだろう」
思わず、俺はタイロンに問うていた。
「本気か、タイロン?」
「たまには、故郷に連絡したい。ブラザー共にも挨拶ぐらいはな。通信室の割り当て次第だな。北米時間が上手く自由時間と重なればいいんだが」
「北米時間?」
「おいおい、こっちと地球じゃ時差ってやつがあるんだよ」
そりゃ、そうだと俺は苦笑する。ついでにいえば、一度以上忠告する道理もない。こいつが作った借りだ。
俺が知ったことでもない。
だから、俺は味覚に対する拷問のような食事に専念し、何とか飲み干したチューブを回収箱に放り込む。
食事を終えれば、集団行動の義務も解けるのは幸いだった。
とはいえ、やれることも多くはない。先に割り当てられた船室に戻るか、糞のように混雑した『交流スペース』で翻訳機から漏れ出す多言語の奔流に耳をやられながら、噂話に耳を傾けるかぐらいだろう。
何度かは、噂に耳を傾けようと交流スペースに足を運んだこともあるが、あれは、ろくでもない経験でしかない。裏付けもない噂話が飛び交うだけで、かえって疲れてしまう。
結果的に、というべきか、俺としては、中々に不本意ながらも同室の連中と行動を共にする羽目になっていた。
五人で仲良くお手々をつなぎ、お散歩って風じゃないにせよ、癪には障る。だが、今日は少しばかり変化ありってな。一人、タイロンの奴が途中で向きを変えるんだ。マシなのが減って、最悪純度が高まるというべきか、人数が減ったことを喜ぶべきか悩ましいなんて考えている俺の前で手を振り、奴は通信施設へ向っていく。
足取り軽く鼻歌混じりで進んでいく陽気な背中からして、心底から楽しんでいる証左なんだろう。一体、何がそんなに楽しいのかさっぱりだが。
家族が麗しいってやつだとしたら、どうして、学校で『そういうものなのです』と散々に教えられる必要があったんだか。
親のことなど、思い出したくもない。頭を振り船室に戻ったところで、俺は軽く思案していた。そんなに奴が家族と顔を合わせるとかいう苦行に楽しみを見出しているならば、今度は俺の持ち時間を適正レートか貸一つで買わないかと取引してみるのも良いかもしれない。
需要がある理由は全くもって理解できないのだが。
「やれやれ、家族ってのは、そんなに大事かねぇ」
俺のぼやきに応じたのは中国人だった。
「……家族を大切にすることそのものが、悪いとは言わないわ」
意見をぼかす彼女としては珍しいことに、小さく言葉を付け足す。
「大切にできるとき、するべきかもしれない。ただ、無条件に良いことだとも、断言はできないけれど」
ふん、と俺は哂う。
意見を言っているようで、その実、どうとでも取れる言い口だ。
「相変わらず、奥歯にものの挟まった言い方だな」
そして、俺の言い分に対して噛みついてくる人間も決まっていた。
「野蛮人よりも繊細ということが、分からない?」
白い騒音源ことイギリス人。こいつが、俺の言葉遣いを気に入る日はないのだろう。奇遇なことに、俺も、こいつのしゃべり方が気に入らない。
たとえ翻訳機越しだとしても、癪なものは癪なのだ。
「高貴な野蛮人というやつだろ? 嘘つきで腐敗しきった連中よりも、俺の腹はきれいなんだ」
「やめてくれ、二人とも。どうせ、腹の中に入っているのは同じペーストだろう?」
スウェーデン人のセンスの良さだけは、認めるべきだろう。
ペーストが同じなのは違いない。
豪華な船旅、素敵なお食事、愉快なお仲間までいる最高の宇宙旅行だ。商連には、心底から感謝している。道理で、火星へ行くまでの船旅で給料が出るわけなんだ。一発で苦痛に対する補てんだと理解できるほどに素晴らしい経験だろう。
「違うものを食べているっていうならば、正直に申告してくれ」
違うはずもなく、沈黙が漂うのを上手く拾い奴は手を叩く。
これで終いだと示すときの癖なのだろうか。
「同じ船に乗っているんだ。上手くやろう」
「上手く?」
冗談じゃないぞ、と俺は軽く反論の釘を刺しておく。勝手に上手くやりたいのはスウェーデン人の自由だろうが、上手くやれと俺が命じられるなら話は別だ。それが、マトモってやつだろう。
「足を引っ張らない。それ以上はこっちも期待していないし、そっちも求めないでくれ。勝手な期待をされるのは、本当に迷惑だ」
所詮は他人だ。自分じゃない。
「お互い、良い距離感を保とうじゃないか」
「前々から思っていたが、随分と他人行儀だな。アジア人は、みんな、そうなのか?」
スウェーデン人のキョトンとした問いかけに対し、俺はため息をこぼす。
一体、どうして、信じるなんてできる? だが、俺だって全員を敵としたいわけじゃない。無謀だということぐらいは余程の馬鹿じゃない限り理解できる。
「信用ってのは口で稼ぐものじゃない」
信用してくれというやつほど、信用できない。
当たり前だ。
「裏切らないのであれば、それでよしね」
「ズーハン?」
意外だな、と中国人をスウェーデン人が見つめるも俺としてはそれ以上の会話を交わす気分じゃなかった。
正直、価値観の違いが強すぎて会話するだけでも疲弊する。
「とにかく、お互いに迷惑を掛けずにやろうじゃないか」
そうだろうと俺は口に出し、議論を打ち切って寝台に身を投げ出し、そこで耳障りな音に気が付く。それは耳をつんざくような爆音ではないものの、無限に繰り返されている音楽だ。
モーツァルトである。
どうにも神経を逆なでしてくれる音量と言い、心情とは裏腹に妙に陽気な曲の種類といい、本当に気に入らない。
誰かが言い出した噂じゃ、商連人が俺たちにストレス耐性を持たせようと意図的に軽い拷問を行っているって説まであった。パラノイア一歩手前の妄想と乗船当初は笑い飛ばした仮説だが、今では真剣に検討すらしてしまう。
これは、本当に、癪に障る。
「モーツァルトってのは、本当に、いい迷惑だな」
俺のぼやきに対し、中国人が余計な知識をひけらかしてくれる。
「フィガロも嫌いじゃないのだけど、そうね、モーツァルトの曲も寝る前ぐらいは切ってくれたら完璧なのだけど」
ああ、まったくだ。ついでに、お前らが静かに黙っていてくれればもっと完璧だがなと心中で呟きつつ、俺は寝台と眠気に身を預ける。
火星までの道のりは、まだ、忌々しいまでに長い。
……第三章「火星」はこちらから。