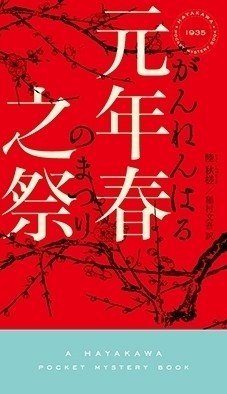【インタヴュー】華文ミステリに花開く〈新本格〉の遺伝子 ――『元年春之祭』著者、陸秋槎氏大いに語る
(書影は『元年春之祭』ポケミス版にリンクしています)
この秋、ポケミス65周年記念作品として、いま勢いを強める華文ミステリの新たなる傑作『元年春之祭(がんねんはるのまつり)』が翻訳刊行された。日本の新本格に影響を受け、その他海外の様々なミステリを吸収して、漢文学の素地から独自の本格ミステリに昇華した、著者の陸秋槎氏が、その思いを語る。(編集部)
インタヴュアー・文/杉江松恋(書評家・ライター)
■〈新本格〉の遺伝子を受け継ぐ
――1990年代に日本では〈新本格ムーヴメント〉と後に呼ばれることになる、謎解き小説の新しい潮流が起きました。陸さんは、そこから影響を受けたことを明言しておられます。翻訳の出た『元年春之祭』あとがきによると、構想・執筆の期間中に麻耶雄嵩『隻眼の少女』は日本語で、三津田信三『厭魅(まじもの)の如き憑くもの』を中国語でそれぞれお読みになられたとか。
陸 はい、今から8年前のことですね。麻耶先生は『鴉』が台湾で翻訳されたのですが、そのころはもう絶版になっていて、ミステリファンにとっては気になって仕方ない存在でした。ミステリの構成を壊す人という噂があったんです。私は当時大学生だったのですが、友人が日本から『隻眼の少女』を持ち帰ってきたので、日本語を勉強して読みました。たいへん素晴らしい作品です。私はもともとエラリイ・クイーンが好きなのですが、今の時代にこのような作品が読める幸せを感じました。
――エラリイ・クイーンはどのような作品がお好きなんでしょうか。
陸 当時は初期の国名シリーズでした。最近は後期作品で、『十日間の不思議』や『九尾の猫』のようなものに好みが移っています。でも、全部好きです。
――では、すべてのクイーン中最もお好きなクイーンは何ですか。
陸 『ダブル・ダブル』はヒロインが可愛いのでいいのですが(笑)、今は『九尾の猫』です。自分の中にアイデアが無いときは、クイーンを読み返します。
――どのような部分に刺激を受けますか。
陸 変な言い方になりますが、やはり手がかりの使い方ですね。
――手がかりをどこに出して、どのように見せておくか、ということですね。もう一冊お読みになられた、『厭魅の如き憑くもの』についてもご感想をお伺いしたいです。
陸 あのころ台湾で〈刀城言耶〉シリーズが何冊か翻訳されまして、『首無(くびなし)の如き祟るもの』が大人気になったんです。『厭魅の如き憑くもの』はシリーズ最初の作品で、もっとも複雑な構造を持っています。大満足しました。伏線が至る所にあり、それをすべて回収していくのが素晴らしい。
――これは余談ですが、三津田さんはプロットを最初に作らずに長篇を書かれる方なんです。もちろん、どこに着地する、程度は決めておられますが、途中は細かく決めない。
陸 ええっ、あれほど構成が美しい作品なのに。ああー、天才ですね。
――その話を聞く度に、プロットなしによくあれを書くな、と感心するんです。三津田さんがおっしゃるには毎回、舞台となる村が出てきますが、あの架空の舞台の設定に時間がかかるのだそうです。どんな民俗があり、それはいかなる歴史に基づいているのか、それを考えてからじゃないと書けないとおっしゃっていました。
陸 納得です。民俗ミステリのジャンルはだいたいそうですよね。
■歴史ミステリを書くという苦労
――陸さんの『元年春之祭』ですが、こちらの舞台となる雲夢澤(うんぼうたく)が実在するのか、架空のものなのか、恥ずかしながら私は知識がないのです。そこで祭祀をとりおこなう観(かん)氏一族にまつわる悲劇ですよね。おそらく、雲夢澤の民俗と歴史がきっちり設定されていないと話が進められないタイプのミステリだと思うのです。
陸 雲夢は、中国文学上の有名な場所なんです。女神と王のエロティックな関係を描いたものなど、いくつかの伝説、神話が『文選』の中にも記されています。
――実在の場所なんですね。そうした伝承豊かな場所であるがゆえに舞台にされたと。
陸 はい。現代中国にはあまりない場所です。そして観氏も、古代の楚文化ではとても重要な一族です。ただ、今の読者にはよく知らない人も多いですから、おもしろく読んでもらえるのではないか、と思って書いたわけです。私自身は国文学(漢文学)専攻なので、大学時代は古典文学や漢詩をよく読んでいました。
――私は漢文学の素養がないのでお恥ずかしいのですが、読んでいてこの物語のどこからどこまでが史実に沿っていて、何が架空なのか、わからない部分がありました。
陸 登場人物はもちろん架空ですが、彼らの先祖はすべて実在します。
――現代の中国の読者が本書を読んだ場合、どの程度そのことがわかるものでしょうか。
陸 雲夢くらいは有名でしょう。ただ、今は知らない人も多いかもしれません。楚の文化は現代の読者にとっては少し遠いと思います。
――日本の読者は、漢と楚というと劉邦と項羽の戦いにはなじみが深いんです。ただ、それ以外となると、ちょっと危ないかもしれません。
陸 この時代で知名度が高いのはやはり武帝(前漢第七代皇帝)ですね。武帝は古代中国のなかでももっとも治世が長いですし、いろんな制度を作った、歴史上で有名な皇帝です。だから、武帝の時代と言えば中国の読者はだいたい、ああ、あのへんか、とわかってくれるんです。
――なるほど。あとがきを読むと、小説の構成要素では最初にトリックというか、全体の仕掛けのほうがあった、という印象でした。それが先にあって、後から前漢に時代設定した感じなのでしょうか。
陸 そうです。もっとも、昔考えたトリックはもっと複雑でしたが、自分には書けないと思ったので現在のような形になったのです。
――そのときの筆力では難しいと思われたと。
陸 いまでも難しいですね(苦笑)。
――そんなに!
陸 もしこのシリーズに続篇が出るなら、書くかもしれません。
――これもあとがきにありましたが、古代を舞台にしたのは本書だけで、以降はほぼ現代中国の物語を書いておられるんですよね。
陸 やはり現代ものは読者の共感を得やすいですし、売れますから(笑)。本国のミステリ読者は中学生から大学生の若い世代なので、こういう話は重すぎるかなと思います。
■小説の技法を一から勉強した
――興味深かったのは、本書の自然描写です。たとえばいろいろな草木が岸辺に生えているというようなことを、その名を列挙して表現する。そうしたやり方は漢詩のものですよね。欧米的な小説作法ではあまりやらない。そうした技法が、現代の中国小説では当たり前なのか、それとも陸さんの特殊なやり方なのか、ぜひお聞きしたかったんです。
陸 ……あのころは自然の描写がとても苦手だったんです。どう書いていいかわからなかったので、古典の文章をお手本にして書いていったんですよね。この作品を書いたあとで、自然や人物の描写をどうすればいいのか、改めて学びました。『元年春之祭』に参考資料として載せましたが、各種の考古学の研究、それから『漢代物質文化資料図説』や『楚辞植物図鑑』などを調べて描写しました。ただ、この小説、今見ると文章はちょっと変ですね。
――ええっ(笑)。でも、古典が文中に引用するような例は現代の小説ではあまり見ないので、新鮮には感じました。こういうやり方をされる方は他にもいらっしゃいますか。
陸 人によってそれぞれですが、引用される方もいます。僕と同様に前漢時代のミステリ小説を書いた人がいまして、その方は大学の先生です。木簡の研究者ですから、さらにマニアックな内容ですよ。
――陸さんはいざ書こうと思ったときに小説の書き方はわからなかったけど、大学までに学ばれたことを応用して組み立てていくという戦術をとられたわけですね。
陸 そうです。小説の書き方はわからなかったのだけど、論文の書き方はわかっていましたから。それを応用して書いたわけです。
――ただ、現行のものは数年後に改稿されたバージョンなんですよね。最初とはどう違うのでしょうか。
陸 昔のヴァージョンは今よりマニアックでしんどい感じでした(笑)。冒頭の歴史についての会話はもっと長くて、最後はもっとライトノベルっぽい。もっとコミカルな感じに終わっていたんです。四年前の事件に関する推理も修正しています。

■根底にあったもう一つの情熱
――今、ライトノベルという話題が出ました。またあとがきを引用しますが、陸さんは作品執筆の動機に「アニメ的なキャラクター描写への情熱」があったとも書かれていますね。
陸 ライトノベルはあまり読んでいないんですが、あのころのアニメでは「ストロベリー・パニック」が好きでした。あとは「マリア様がみてる」「ARIA」とか。「ラブライブ!」……はまだなかったですね(陸氏のツイッターアイコンは「ラブライブ!」)。
――なるほど。女子同士の会話は、読んでいて楽しいですからね。
陸 そうです。本格ミステリには女の子の話が少ないですよね。
――その通りです。
陸 男同士、あるいは女と男、そういうパターンは多いですが、探偵役とワトソン役でも、女の子のパターンはあまりない。だから書いたんです。誰も書いたことがない小説を書きたかったですから。でも、最近はこういう小説がどんどん増えていますね。麻耶雄嵩先生は最近、『友達以上探偵未満』を出されました。柾木政宗先生の『NO推理、NO探偵?』もそうですし、階知彦先生の『シャーベット・ゲーム オレンジ色の研究』もあります。だんだん書かれるようになってきましたが、僕のほうが早かったのかなと(笑)。
――女子二人を活躍させたいという強い動機があったわけですね。
陸 その後に書いた学園ミステリものも、そういうパターンです。ただ、『元年春之祭』の場合は、探偵もワトソン役も読者から不評でした。もうこの二人の出番は一生ないだろうと言われて。たぶん二人の感情の起伏が激しすぎるからでしょう。たとえば葵(き)は、侍女の小休(しょうきゅう)を折檻しますが、それは前漢時代では普通のことでした。ですが、今の読者にとってみれば残酷すぎるんです。
――特別残酷な人間に見えると。
陸 そうです。なので他のキャラクターが好きな人はいますが、この二人はあまり人気がないんです。でも、僕は葵みたいなタイプが好きなんですよ。物知りで、ドSという。
――葵はある登場人物から「中国の君子は礼儀にあきらかなれど、人の心を知るにつたなし」と荘子を引用する形で諫められます。つまり他人の感情がわからないと。
陸 いわゆるKYですよね。その彼女が、事件を経て成長していく話なんです。
■ビルドゥングスロマンへの傾倒
――そうしたキャラクター設定は狙ってのものなんですか。
陸 はい。教養小説、ビルドゥングスロマンが好きなので、登場人物には成長させたい。エピファニー(頓悟)のようなシーンがあればいいなと思っています。ちなみに長篇第二作のキーワードも「エピファニー」ですよ。
――そういった教養小説的な構造を自作の中に入れたかったと。
陸 探偵役が事件によって成長する。いわゆるクイーン的ですね。
――『九尾の猫』といった作品も、失敗によって成長する話ですよね。
陸 大好きですね。法月綸太郎先生の『ふたたび赤い悪夢』もそうです。
――自分の作品でも、そういった探偵であってほしいと考えたわけですね。
陸 でも、ちょっとやり過ぎたのかもしれません。本格ミステリのなかでは探偵役はだいたい成長できない感じですよね。
――金田一耕助も、何度事件解決に失敗しても本質的な部分はあまり変わりません。
陸 でも、ちょっと足りないと思います。それだけでは私は満足できない。欧米ミステリでは、たとえばローレンス・ブロックの創造したマット・スカダーは、どん底のみじめさを味わいます。成長というよりも絶望しているようにさえ見えますが。
――そういった人々が推理を通じてどう変わるか、ということに関心がおありなんですね。
陸 そうなれば面白いですよね。
――もう一人のヒロインである露申(ろしん)は、非常に保守的といいますか、自分の世界から出たがらず、引っ張り出そうとする者を憎悪さえしますね。彼女はどのような意図で造形されたのでしょうか。
陸 彼女も最後に成長します。外の世界を拒否していたわけですが、その考えを改めていきます。
――本書は前漢時代の物語ですから、女性は地元や一族の掟に縛られながら生きるしかない。たとえば露申の姉のように、子供を産むということに徹しなければいけない。でも、そういう不自由さは現代にも通底するといいますか、現代の女性がまだまだ自由ではない状態であることに通じるものがあります。この一致は狙ったものでしょうか。それとも結果としてそうなった偶然の産物ですか。
陸 私が第一に考えていたのは、どうやって歴史ものを書こうかということでした。検討の結果、本格ミステリの構造にしてしまおうと思いついた。そうなると、クローズドサークルのような舞台は便利なんです。前漢時代の社会や政治について詳しく描写していったら、絶対に駄作になってしまいますから。
――もっといろいろなことを書かなければいけなくなりますからね。舞台を限定しさえすれば、小説として書けると。
陸 そうです。限られた舞台の方が便利ですね。
――作中では時間もそれほど経過しませんね。せいぜい、数日の出来事です。
陸 ええ。劇の作法でいうところの「三一致の法則(時と場所と行為を単一のものに設定する)」、ギリシャ悲劇のような形式です。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』も、実は数週間の中ですべての事件が起こります。そうすると悲劇の舞台感が生まれます。
――なるほど。
陸 もう一つ問題があって、歴史ものを書くとすると時間経過が長いし移動する場所も多い、そのすべてを読者に見せなければいけませんが、本格ミステリの書き方は逆なんです。もっと要素を限定します。だから歴史ものと本格ミステリ的な書き方をどうバランスをとるかということも考えなければなりませんでした。
■二度の「読者への挑戦」
――帯にも書かれていますが、この作品には二度の「読者への挑戦」が入ります。つまり読む前から多重解決があると示唆されているわけですが、その要素は最初から前提条件としておありでしたか。それとも書いていくうちに入ってきたものでしょうか。
陸 私はプロットを綿密に作ってから書くのですが、最初から多重解決と、二つの「読者への挑戦」を入れることは決めていました。
――二度の「読者への挑戦」があり、最後に真相がわかります。第一の「読者への挑戦」前に出た情報で犯人を特定することは可能です。つまり謎解きとしてはフェアなのですが、完全には解明できないものがそこまでの情報だと残るようになっています。それが何かについては未読の方のために伏せますが、第二の「読者への挑戦」がある意味はそこですよね。犯人当てだけではなく、その割り切れなかった部分の疑問について読者は考えることを求められる。つまり二段階の謎解きが楽しめるわけです。
陸 第一の「読者への挑戦」前の部分を友人に読ませたら、作中人物が引っかかった偽の解決とほぼ同じ推理をしたんです。そこで、その偽推理を排除する段階が必要だと考えました。だから二つの挑戦状が必要だったということでもありますね。
――二つの挑戦状の間に推理の余詰めを置いたわけですね。余詰めによってその可能性を排除してから先に進む。これもお聞きしたかったのですが、本書には現在と四年前の過去と、二つの事件が起きますが、「読者への挑戦」の中で解答を求めるのは前者だけですね。そちらについて挑戦されなかったのはなぜなのでしょうか。
陸 作者としては、本作は伏線が多くて、その回収率も高いと思っているんです。すべての伏線に気づけば、読者が真相を指摘することは可能だと。ただ、四年前の事件については現在のものほど伏線がないので、選択肢が多くなってしまいます。現在の事件の真相を推理すれば四年前の事件について想像することはできますが、それは想像であって推理ではない。
――だから挑戦からは外したと。なるほど。こうしたクローズドサークルの謎解きは、以降もお書きになっておられるのですか。
陸 書いています。第二長篇は、ちょっとハードボイルドですね、一人称小説ではないですが。事件は学校で起こるんですが、昔の事件に遠因があるために、インタヴューが多い。今書いている作品もインタヴュー小説のパターンになっています。私は、ロス・マクドナルドが好きなんです。デビュー前は、作家の存在は知っていましたが作品を読んだことはなかった。だから『ウィチャリー家の女』を読んで衝撃を受けました。キャラクターの造形、登場人物の背後に置かれた人生が素晴らしいですね。
――同感です。最後になりますが、これから陸さんの作品を手に取られる日本の読者に、ひとことメッセージをいただけますか。
陸 はい。日本のミステリの影響、特に新本格の、ゼロ年代以降の作品の影響を受けた海外ミステリを読む機会は、あまりないと思います。とても斬新な体験になるかもしれません。ぜひ楽しんでください。
――ありがとうございます。お忙しいところをわざわざお越しいただいて感謝します。
陸 こちらこそ。うまく話せたでしょうか。いろいろ忘れてしまったような気がします。私がもともと巫女が好きで、巫女さんが探偵役の話を書きたいと思っていたこととか。
――最後にそんなおいしい話が! また改めて聞かせてください(笑)。
(2018年9月11日、於・早川書房会議室)
陸 秋槎 プロフィール
1988年中国、北京生まれ。復旦大学古籍研究所在学中の2014年に短篇ミステリ「前奏曲」を発表し、第二回華文推理大奨賽(華文ミステリ大賞)の最優秀新人賞を受賞した。2016年に本書で長篇デビュー。
Copyright(C) Hayakawa Publishing Corporation All rights reserved.