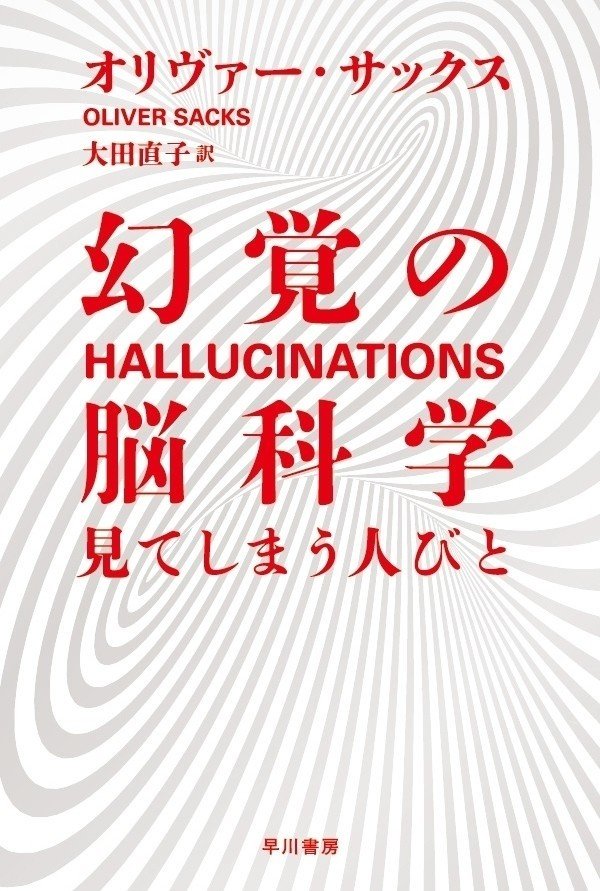「オリヴァー・サックスの著作を読むたびに気になっていたことがある」『幻覚の脳科学』精神科医・春日武彦文庫解説
(書影はAmazonにリンクしています)
宙を舞う青いハンカチや楽譜、体長15センチの小人、光り輝く幾何学模様。話し声や音楽、悪臭、失った手足の感覚——現実には存在しないものを知覚してしまう「幻覚」。これらの多くは狂気の兆候などではなく、脳のメカニズムを解明する上で貴重な手がかりとなる現象であることを、脳神経科医サックス先生が豊富な実例を挙げながら解説してくれる『幻覚の脳科学』(大田直子訳、ハヤカワ・ノンフィクション文庫)。精神科医・春日武彦先生による解説を掲載します。
解説 精神科医・春日武彦
本書を著したドクター・オリヴァー・サックス(以下、OSと記します)について、著作を読むたびに気になっていたことがある。それは、なぜ彼は精神科医ではなく脳神経科医になったのか、という疑問だ。
兄の一人マイケルは統合失調症を患い、結果として、持って生まれた素晴らしい能力を発揮出来ずに終わっている。病気の苦しさや悲惨さをOSは目の当たりにしてきた。しかも当時の精神科医療には人道的にもかなり問題があった筈だ。熱血漢の彼としては、自分こそが兄を治療しなければ、といった発想には至らなかったのだろうか。
18歳のときには、同性愛を告白した結果、母から「おまえは憎むべきもの。おまえなんか生まれてこなければよかったのに」などと冷酷な言葉を浴びせられている。そうした辛い記憶について精神科医の立ち位置からあらためて対峙し、自身の心に決着をつけようとは考えなかったのか。
ベッドから幻覚によって転がり落ちた患者が床に座り込んだまま喚いていたとき、駆け付けたOSは患者の横に座り込み、同じ高さの視線で話し掛けた。まだ新米医師の頃である。こういった振る舞いを反射的に行えるのは、精神科医に相応しい素養である。
そして彼は患者の人生そのものに深い関心を寄せた。疾患をただそれだけで眺めようとはせず、人生において「病」がどのような位置づけとなっているかを見据えつつ理解に努めている。病の意味や、生育史や生活史の把握に重点を置くのは精神科の伝統だ。
今回の解説を書くに当たって、『道程──オリヴァー・サックス自伝』を読み返してみた。すると以前にはうっかり読み落としていた部分に気が付いた。OSが2009年に、強烈な座骨神経痛に悩まされた際の記述である。
「12月には座骨神経痛があまりにもひどくなって、読むことも考えることも書くこともできなくなり、生まれてはじめて自殺を考えた。」
この箇所には驚かされた。
OSはエネルギッシュな正義漢であるぶん、いささか情動に不安定なところがあったようだ(年齢を重ねると安定してきたようだが)。本書にもある通り、メスカリンやLSDやアンフェタミン(いわゆる覚醒剤)も経験している。時代を考慮すれば同性愛であることはかなり深刻な悩みであったに違いないし、キャリアは必ずしも順風満帆とは限らなかった。そうした人物は、往々にして自殺に魅入られる時期があるものだ。ましてや文学にも傾倒していたのだから、なおさら自殺には惹かれるところがあったのではないのか。たとえ文章には書いていなくとも、きっとそうであったに違いないと勝手に決めつけていた。だが実際には、76歳になるまで自殺なんて考えたことがなかったのである。
まことに意外であった(若い頃の無鉄砲さが、希釈され変形された自殺願望だったなどと言い出したら、それはあまりにも深読みだろう)。
自殺を考えたがるような人間が精神科医に向いているとは限らないし、自殺なんか考えもしない人間のほうがかえって患者に安心感や希望をもたらすことだってあるだろう。しかしおそらくOSは、精神科医になったとしたら自分のタフな生き方を逆に悩んだのではないか。相手に共感することの限界に、あるいは密かに抱え込んだ自らの屈託を語らないまま相手と向き合うことに、自己嫌悪に近いものを覚える可能性すらありそうに思える。そんな愚直なところが、彼の本から垣間見られるのである。
OSは本書で、「医師の資格を取った1958年末には、私は神経科医になりたい、そして脳がいかにして意識と自己を具現するかを研究し、知覚と創造力と記憶と幻覚の驚異的な力を理解したいと思っていた」と述べている(130頁)。彼は精神医学といった曖昧なものよりも、神経科学の明快さを選んだ。だがもしかするとそうした選択の裏側には、わたしたちには窺い知れないような複雑な思いが「わだかまって」いたような気もするのである。
彼が著した精神科版の『幻覚の脳科学』や『妻を帽子とまちがえた男』はどんな本なのだろうか──そんな能天気なことを、無責任な立場のわたしはつい考えてしまう。
さてOSが医師の資格を取った時代には、精神科においても脳神経科においても劇的なことが起きていた。まず1952年に、世界初の抗精神病薬(メジャートランキライザー)が発見されている。クロルプロマジンが一般名で、商品名はウインタミンないしはコントミン。現在につながる精神科薬物療法の嚆矢であり、今でも処方されている。さらに1957年には特に幻覚妄想に大きな効果を発揮するハロペリドールが発見された。統合失調症患者の症状は画期的に改善し、しかし副作用として薬剤性パーキンソン症候群が大きな問題としてクローズアップされてきた。まさに脳神経科と精神科とがクロスし、また統合失調症の薬物治療にはかなり楽天的で高揚した空気が病院を覆っていた時代である。
そしてOSは、自らドラッグの使用にのめり込み、1964年には友人をニセモノだと主張し(替え玉妄想)、1965年には譫妄(幻覚妄想と興奮とが混ざり合い、寝ぼけたような状態)を呈している。無茶というか無防備なことをするものだと呆れたくなるけれど、たとえばサイケデリックロックは1966年が始まりとされており、時代の雰囲気そのものが浮足立っていた。そんな時期でもOSは医療と研究への熱意が途切れることはなかった。
本書の第6章で、譫妄については彼自身の体験を含めて詳しく述べられている。が、書かれていないのが意外に思われた症状があるので、ひとつわたしから補足しておきたい。
譫妄の中でも、作業譫妄と呼ばれるものがある。アルコール依存症者が、アルコールの離脱症状として現出させる場合があって、その際には「普段行っている仕事の仕草を、意識変容下で行う」というものである。たとえば寿司職人だった患者が、パントマイムのように寿司を握る動作を繰り返したり、大工が鉋を掛ける動作をひたすら演じる、といった類である。
さてある精神科病院で当直をしていたら、夜中に興奮著しい患者A氏が運び込まれた。アルコール離脱に伴う症状であるのはすぐに判明したので、身体を抑制して点滴を行うことにした。薬剤とともにビタミンB群を混ぜないと、脳に重篤な後遺症が残りかねない。で、点滴の用意をしたりベッドの手配をするまで、とりあえず保護室(興奮する患者を収容するための、外から鍵の掛かる小部屋。頭を打たないようにベッドは置かれていないことが多く、内部は空っぽで、独房のようだと悪口を言う人もいる)に入ってもらうことにした。
用意が整ったので保護室を覗いてみると、A氏はなぜか床に正座し、黙したまま、さながらイスラム教徒が祈っているかのように上半身を前屈させている。ただし両腕は前方に突き出して握り拳を作っている。その奇妙なポーズに当方は首を捻るばかりだった。
遅れて病院にやって来た妻から話を聞き、さらに後日、ギャンブル好きの友人に知識を与えられてその謎は氷解した。
A氏は競艇でボートを操縦していた。水上でスピードを競うのが彼の仕事だった。そこまでは妻から聞き取ったわけだが、友人によれば、ボートに選手(ボートレーサー)は正座した形で乗り組むのだそうである。F1のように脚を前に投げ出す姿勢で乗るわけではないらしい。それが分かれば、あの晩の祈祷をしていたみたいなA氏は、実はボートを猛スピードで操縦しているつもりだったのではないかと推察されるのである。それで辻褄が合う。
意識の変容しているA氏は、主観的には、高速でボートを操縦していた。わたしの目には殺風景そのものに感じられる灰色の保護室は、A氏にとっては青空の下に広がる水面とカラフルな観客席とで構成された華やかな空間へと拡大され、耳には豪快なエンジン音と歓声とが響き渡っていたに違いないのだ。
主観と客観とのあまりにも大きな落差に、わたしは眩暈がするような気がしたものである。今にして思えば、OSへ手紙を書いて「こんなケースがありました」と報告してみればよかった(アメリカには競艇がないだろうから、興味を持ってくれたかもしれない)。返事が来たら、それは大いに自慢の種になりそうだ。
けれども手紙を出すチャンスは永遠に失われてしまった。本書(翻訳版)がハードカバーで出たのが2014年、その翌年にOSは亡くなってしまったのである。まだ82歳であった。幻覚百科とでも称したくなる本書はもっとも彼らしさの凝縮された一冊であるけれど、OSにはもはや幻覚の中でしか会うことが出来ない。
***
『幻覚の脳科学——見てしまう人びと』
オリヴァー・サックス
大田直子 訳
ハヤカワ・ノンフィクション文庫
発売中