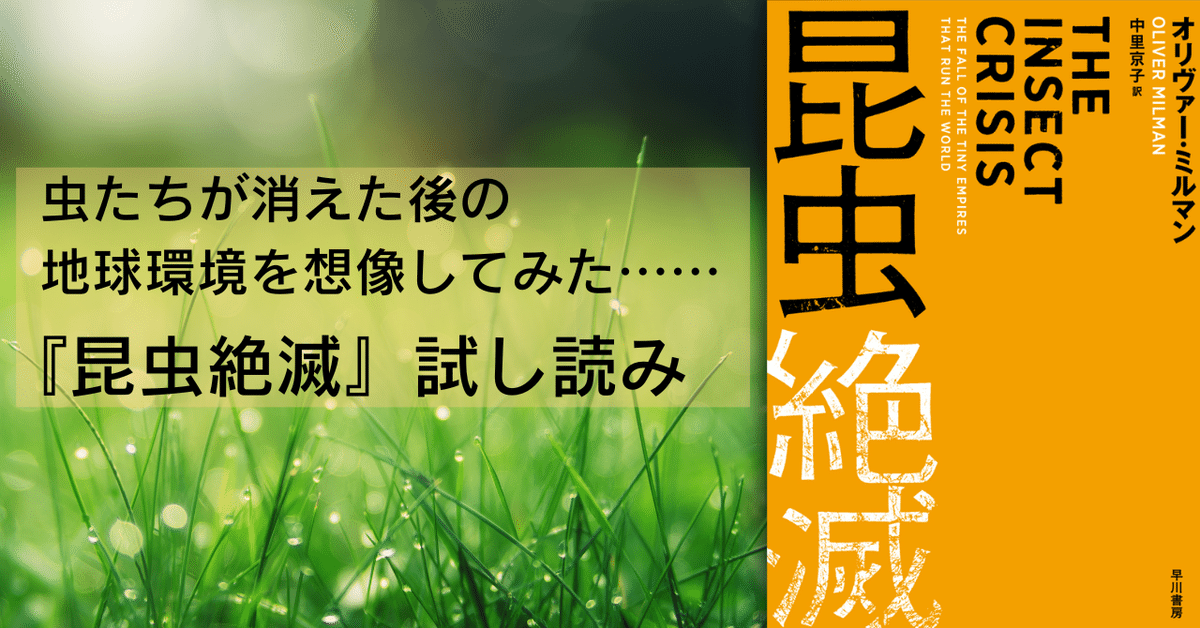
昆虫絶滅が人類に与えるインパクトとは?『昆虫絶滅』本文試し読み
気候変動、森林伐採、過剰な農薬使用……地球環境の悪化により、昆虫の個体数が激減している現状は、人類にとってどのような影響を及ぼすのか?
虫たちは私たちにとって厄介者ではなく、重要な共生者であると説く話題の新刊『昆虫絶滅』(オリヴァー・ミルマン、中里京子訳、早川書房)から、本書プロローグ部分を特別公開します。
昆虫絶滅後の“様変わりした地球環境”を覗いてみると――

◆ ◆ ◆書評・メディア紹介多数◆ ◆ ◆
毎日新聞(2023年12月30日号)「2023年の3冊」(養老孟司・東京大学名誉教授)
honz(2024年1月27日号)書評(仲野徹・生命科学者)
日経新聞(2024年2月3日号)書評(丸山宗利・昆虫学者)
東京新聞(2024年2月4日号)書評(尾嶋好美・サイエンスコーディネーター)
『昆虫絶滅』プロローグ
激変の最初の兆候は不気味な静けさだった。田園地帯も郊外の庭も都会の公園も、サウンドトラックを失って生気のないイミテーションと化し、通りすがりのミツバチの羽音も、規則正しいコオロギの鳴き声も、飢えた蚊のしつこい羽音も、もはや聞こえなくなった。
風景は、にわかにそれを描いた平面的な油絵のように見え始めたが、その絵の鮮やかさは、生態系のパレットから玉虫色の輝きを放つ蝶やまばゆい甲虫がもぎ取られたために褪せていた。
世界中の昆虫が姿を消したというのに、人間はすぐには反応せず、最初に恐怖の叫び声を上げたのは、奇妙なことに鳥だった。空や森は、消えてしまったアブラムシや蛾などの餌を必死に探し回るルリツグミ、ヨタカ、キツツキ、スズメなどでひしめいた。損失は甚大だった。ツバメのヒナ一羽が成鳥になるには約20万匹の昆虫を必要とする。それが皆無になったのだ。合計すると、地球上に存在するおよそ1万種の鳥類の半数が飢えて絶滅し、痩せ細った死骸が地面や不毛の巣の中に散乱した。
鳥、リス、ハリネズミ、ヒトをはじめ、およそ地球に生まれて死する運命にある、ありとあらゆるものの死骸が、谷間や丘、公園、放置された都会のアパートなどに積み重なり始めた。人間の死体の60パーセントを一週間で消化できるウジ虫の卵を産むクロバエは姿を消し、蛾やカツオブシムシ科の甲虫など、それまで死骸を分解しようとやってきていた様々な虫たちも同じ運命を辿った。バクテリアや菌類はまだ残っていたものの、仕事のペースははるかに遅く、それらだけでは不十分だった。腐った死骸とその腐敗臭は嫌悪感をもたらしたが、やがて人々はそれにも慣れていった。
まるで周囲の世界が吐き気を催させようと企んでいるかのように、肉片や骨が始末されずに残ることに加えて、糞便の津波が押し寄せてきた。どこを見ても、落ちたところにそのまま留まっている排泄物があるように思えた。かつてオーストラリアの農家は、ヨーロッパからの入植者が最初に家畜を導入した際に、適切な種類の糞虫が存在することがいかに重要であるかを思い知らされた。有袋類の動物の糞になじんでいた在来種の糞虫は家畜の糞が分解できず、オーストラリア大陸は、乾いて固化した家畜の糞が積もる不毛な土壌に覆われたのだ。
だが、少なくとも6500万年前から感謝されずに清掃作業を行なってきた8000種におよぶ糞虫が全世界から姿を消した今、この災害は、はるかに大きな規模で再び浮上し、地球の肌は、止めようのない不快な疫病にかかったかのように、野生動物と家畜の糞によってあばただらけになってしまった。おびただしい土地が荒廃し、頑なに土に還ることを拒む倒木や落ち葉も堆積し始めた。
世界中にまず嫌悪感が、そして次に警戒感が広がった。環境保護団体が動き出し、参加者にハチの格好をさせて集会を開き、政治家たちは緊急会議を開いて早急な対応を約束した。何らかの手は打てるように思えた。
だが次に、食糧供給が崩壊した。世界の農作物の三分の一以上は、その受粉を数千種類のハナバチや、蝶、ハエ、蛾、カリバチ、甲虫などに頼っていた。花粉を媒介する昆虫がいなくなると、世界中の食糧生産のベルトコンベアが音を立てて停止し、広大な果物や野菜の畑は朽ちるにまかされた。農家は、害虫を駆除するために農薬を撒布する必要こそなくなったものの、たとえ害虫がやって来たところで、彼らが食べるものなどほとんどないと嘆いた。
スーパーから消え始めたリンゴ、ハチミツ、コーヒーは高価な贅沢品になった。カカオの木の無名の送粉者〔花粉を運ぶ動物〕であるタマバエ科やヌカカ科の小虫がいなくなったことで、チョコレートの供給も途絶えた。人々はこうした喪失を街頭で公然と嘆き、うつ病や不安にさいなまれる人が急増した。
ハナバチがいなくなったために、イチゴ、プラム、モモ、メロン、ブロッコリーなどの身近な食材も失われ、その他の野菜や果物も奇妙な形に変わったり、哀れに縮んでしまったりした。幸いなことに、破局的な飢餓はかろうじて免れることができた。小麦、米、トウモロコシなどの主食作物は、風によって受粉するからだ。
とはいえ、裕福な国でさえ食事は味気ないものになり、栄養状態も低下した。果物、野菜、ナッツ、種子などが手に入らなくなり、膨大な数の人々がオーツ麦や米を中心としたわびしい食事でやりくりしなければならなくなった。マンゴーやアーモンドを口にするのは退廃的な空想となり、かつてそうしていた経験も、やがて人々の記憶から消えてしまった。唐辛子もカルダモンもコリアンダーもクミンもないなか、カレーは過去の料理となった。様々なタイプのレストランも、トマトやタマネギなどの調達に苦労するようになって、一斉に店を閉じた。今では乏しくなったアルファルファを食べていた牛も数を減らしていった。牛の減少は牛乳や乳製品の不足をもたらし、チーズやヨーグルト、アイスクリームも姿を消した。
政府は労働者を大量動員して作物の人工受粉を始めたが、送粉昆虫と植物の間に1億年間にわたって進化してきた共依存関係に比べると、それは甚だしく高額につき、しかも非効率であることが判明した。そんななか、大量の新興企業が勃興して、本物の受粉を再現しようと、ドローンやロボットハナバチの大群を発売した。だが、そうした取り組みも不十分なものに終わった。
ほとんどの災害と同じく、最も甚大な被害を受けたのは、貧しい人々や弱い立場の人々だった。昆虫がいなくなる前から栄養失調に陥っていた八億を超える世界の人々は、受粉作物からの栄養素が不足した今、多くが餓死寸前に追い込まれた。開発途上国では、主に果物や野菜から摂っていたビタミンAが不足して失明する子供が急増した。マラリアと西ナイル熱の呪縛は、嫌われ者の蚊とともに地球上から排除されたが、柑橘類の不足は壊血病の復活をもたらすことになった。飢餓が人間の命を徐々に奪っていくなか、他の病気も蔓延していった。
昆虫は、インド、ブラジル、中国、アフリカ各地をはじめとする世界の様々な地域において、代替医療の基本材料となっていた。ハチミツは抗酸化物質および抗菌物質として心臓病の治療に使われてきていたし、カリバチの毒にはがん細胞を殺す効果があることが判明していた。また、抗生物質耐性の増加に伴い、昆虫は、広く普及することが望める新たな資源として研究者たちに期待され、もしかしたら、次に襲い来るパンデミックを撃退するための特効薬になるのではないかとさえ思われていた。というのも、ノババックス社製の新型コロナウイルス用ワクチンは、ツマジロクサヨトウ〔蛾の一種〕の細胞を利用して開発されたものだったからだ。だが今回の大惨事は、そのような期待も打ち消してしまった。
ほどなくして、地球に暮らす大部分の生命を支えていた支柱が引き抜かれてしまった。野生の顕花植物〔花をつける植物〕のほぼ90パーセントは送粉昆虫に受粉を依存している。この手助けを奪われたうえに昆虫がリサイクルして土壌に戻していた栄養分を失った植物は枯れ果ててしまった。庭は荒涼とした砂漠と化し、野生の草原が消え、やがて熱帯雨林の木々も消えていった。人類は、その食物の半分以上を、かつて花を咲かせていた植物から直接得ていたため、飢餓率はさらに高まった。生態系全体が崩壊し、気候変動が加速し、絶滅の連鎖は荒廃した地球に波及していった。残された者たちの苦悩は、ついに極限に達した。
――この続きは本書でご確認ください(電子書籍も同時発売)。
この記事で紹介した本の概要
『昆虫絶滅』
著者:オリヴァー・ミルマン
訳者:中里京子
出版社:早川書房
発売日:2024年12月5日
本体価格:2,300円(税抜)
著者紹介
オリヴァー・ミルマン (Oliver Milman)
英国ベッドフォードシャー州出身のジャーナリスト。英国サウサンプトンにあるソレント大学でメディア・ライティングを専攻し、いくつかのメディア企業で経験を積んだあと、十数年前から英国《ガーディアン》紙の専属記者として、オーストラリア、次に米国で環境問題の報道を担当。ビジネス、スポーツ、メディア業界にも造詣が深い。現在ニューヨーク市在住。本作は初の著書である。

