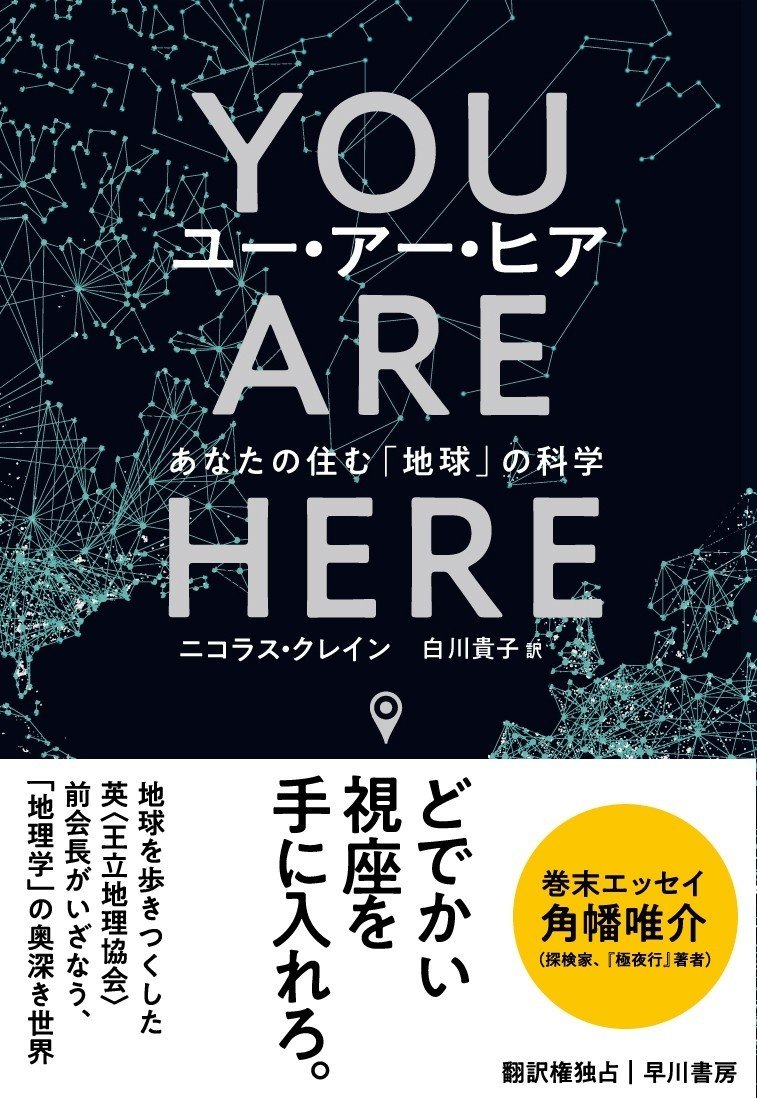人間にとって地図とは何か?『ユー・アー・ヒア あなたの住む「地球」の科学』特別エッセイ/角幡唯介(探検家)
【特別エッセイ】
位置を求めるということ
角幡唯介(探検家、『極夜行』著者)
森羅万象のおりなすこの地球という天体のなかで、人間はいったいどのようにして、自分は今ここにいるということを知ることができるのだろうか。
……などという気障なセリフを大真面目に言ったら、お前は何を馬鹿なこと言っているんだ? と笑われるだろうか。
テクノロジー全盛のこの時代、そんなものはGPSの座標データが教えてくれるにきまっている。GPSが北緯四十五度三十二分五秒、東経七十八度十六分三秒と示せば、そこがお前の地球上の位置だ。カーナビが次の信号を右にまがってくださいと言えば、お前はそのとおりに進めばいい、今いる場所など空間内部のとある地点の情報を数学的表現に置きかえたものにすぎない、それ以上の何があるというのか、と。
しかし、それでも私はあえて問いたい気持ちになる。自分が今どこにいるのかを知ることは、本当に客観的な座標データを知ることと同じことなのだろうか。位置を求めることのなかには、われわれの実存とかかわる何か本質的なことが隠されてはいないのだろうか。
本書との絡みでいえば、この問いは、人間にとって地図とは何かという問いとかなり重なるかもしれない。
たとえば山登りをするとき、登山者はまず地図を見て自分の位置を把握し、その結果をもとにして次の行動を判断する。このとき登山者が何をやっているのかというと、周囲の地形と自分とのあいだの関係の把握だ。ちょうど北東に顕著な三角形の頂が見え、その斜め右には深くえぐれた谷がある、そして地図を見るとそれに相当する地形がここに描かれている、だからおそらく自分は今、地図のなかのこの場所にいるだろう、などと推測しているわけである。
登山者はこうした作業を特に意識することもなく、常時、連続的におこなっているのだが、このとき考えなければならないのはランドマークの役割をはたしている、この〝顕著な三角形の頂〟なるものである。
この頂は登山者にとって、ただ単に物理的にそう存在しているという意味での〝顕著な三角形の頂〟なのだろうか?
そうではあるまい。その頂には、そのような形状で存在しているという以上の意味があるはずだ。なぜなら、この頂を目印に登っている登山者にとっては、その目印はとても切実な存在となっているからだ。
登山者が地図で目印を見つけて、それを手がかりに位置関係を知るとき、その現状把握のなかには空間的な把握だけでなく、時間的な把握もふくまれている。どういうことかといえば、登山者はその三角形の頂を見ることで、ああ、あれが北東に見えるということは、目的の山頂まではあと三時間ぐらいだなぁ、それなら何とか日没までには下山できそうだから、このまま登山をつづけよう、などと判断することが可能となり、その結果、登山行為をつづけることができているわけである。要するにこの三角形の頂は現在位置を知らしめてくれるだけでなく、未来への見通しを与えてくれるという意味で、まさに登山者の命運をにぎっており、その意味で切実なのだ。だからその頂は岩盤の隆起した山頂という物理的な範疇を超え出て、登山者の生と直に結びついた主観的な存在としてそこで現象しているのである。地図を見て山に登る行為の裏側には、じつはこうした生にかんする非常に興味深い構造がひそんでいる。
もちろん、近代的な測量地図が完備された現代登山だから話はこの程度でおさまっているが、これがもし測量地図のない、たとえば二万年前の狩猟民の時代であれば、周辺の山や谷などとの関係はさらにいっそう緊密かつ切実なものとなり、位置を知ることがダイレクトに生きることだという世界が広がっていただろう。
地図のない原始の人々が知らない土地を探検するときは、きっと川の二股や巨大な樹木や岩、切りたった白亜の岩壁等々といった様々な自然物を目印に歩きまわったはずだ。地図がないので、彼らはそれらの目印を頭に叩き込むか、途中の木に刻み目をつけたり、方向を示す木片をおいたりといった、今の紙の地図とはことなる手法でマッピングをほどこさなければならなかった。そしてこの行為には文字通り命がかかっていた。生きて仲間のもとに帰るためにも、彼らはこれらの目印がどこにあるのか記憶にとどめ、常に見落としがないように地域全体の自然環境を俯瞰的にとらえなければならない。日々、山や谷を動きまわるなかで、人々はこうした馴染みのある自然物を目にしては、この川の二股に出たということは自分は今、あそこにいる、だから村にもどれる、嗚呼よかったなどといった安心感を与えられただろう。やがて自分たちを生かしてくれる切実な自然の対象は神聖な場所となって崇められ、精霊の棲む場所や聖地として信仰の対象になったにちがいない。
地図を描くことは周辺の景観や目印を概念化して、未知で混沌とした土地を秩序づけ、理解可能な世界に塗りかえていく作業にほかならなかった。物理的に考えたら単なる木でしかないものも、目印となってその人の命にとって切実なものとなった途端、その木は人々の主観のなかで意味化されて、木という範囲を超えた木以上のものとして結晶化する。
原生的な自然のなかで暮らしていたとき、人間はそうした意味化された物体をまわりにたくさん配置して、無秩序に散乱するカオスの場としての風景を構造化し、自分の世界の内部に取り込んでいった。周辺の環境のなかに自分と関係する自然物が増え、目に見えない糸で結ばれれば結ばれるほど、人はその環境のなかで自分を安定した実体として把握できた。土地に散在する自然物との関わりをつうじてできあがった網の目構造を、人は地図というかたちで表現したのである。
本書を読んで私が強く感じたのは、地図とはそもそも、当人や、その人が属するコミュニティにとってのみ意味をもちうる、とても局所的な表象体系だったのかもしれないということだ。
われわれが今、使用する測量をもとにした近代的な地図は、少し訓練すれば誰にでも理解できる客観的な手法で描きだされている。でも大昔の地図はそれとは全然ちがって、当人たちにしか意味を理解できない主観的なものだったのではないだろうか。よく考えたら、その土地のなかで生きることはじつは地域を限定する営みであり、決して普遍的なものではない。だからこそ人はそれぞれの土地との絡みのなかで、そこで見合った生き方を模索し、独自の文化をはぐくむことができたのである。
周辺の自然環境を構造化して秩序づけたとき、その世界の中心にいるのはまぎれもなく自分であり、自分が属するコミュニティだ。世界とは自分を中心において周辺を意味化した認識体系のことである。地図はそのような自分中心の世界というものを可視化したメディアであり、その土地に存在する自然物との連関のなかで、自分たちがどのように土地にとりこまれ、そして土地を理解しているのかを記す物語だった。だから地図を見たら、それを描いた人がその土地とどのようなつきあい方をしているかが即座にわかる。地図とは元来そういったものであったはずだ。
もちろんこうした人と土地との固有のつながりは原始の人々だけにあてはまる話ではなくて、現代のわれわれにも同じことがいえる。
たしかにわれわれはもう、周辺の地域を自分で地図におこして理解することをあまりしなくなった。自分で描かなくても地図が与えられているからだ。だが、人間がある土地から次の土地へと移動する空間にしばられた存在であること、そして人生の少なくない時間を移動行為についやしていること、こういった事実は今も昔もあまり変化はない。移動するときわれわれは今も無意識に自分だけの目印を見つけて、それを手がかりにして次の土地に進むし、住んでいる場所の周辺にいくつもの目印をもうけて、そのネットワークのなかで土地を面的に把握している。土地を把握すればするほど、人はその土地との間につながりを感じ、この大地のなかで自分は生きているという奇妙な感覚を得るようになる。われわれが今も自分の住む場所からあまり離れたがらないのは、このつながりの感覚があるからに相違なく、人間は大昔から慣れ親しんだ土地に固執し、それに安らぎをおぼえる生き物なのである。
原始の時代から人間には馴染みのある自然物をたくさん配置することで生きのびてきた歴史があり、だからこそ知っている土地に安らぎをおぼえるようにプログラミングされている。そしてそのすべての大元をつかさどっているのが、位置を求めるという移動行為の際に不可欠なプロセスだ。不確かな場所で正確な位置がわかったとき、人は生きていることを実感できる。位置を教えてくれる自然物を見つけたとき、このうえもなく安心できる。位置を求めることには、人が生きるために欠かせない根源的な土地とのつながりがひそんでいるのである。
だから私は探検のときは不用意にテクノロジーに頼らず、自分の力で位置を求めるということを大切にしている。おかげで自分がどこにいるのかわからなくなって死にそうなほどの恐ろしい目に陥ることもあるが、それも土地の実相を知るための重要な契機なので仕方のないことである。本書が訴えたいことも、たぶんそこらあたりにあるのではないかと私は理解した。つまり地理学とは人間と土地とのつながりを記述する学問であり、現代人は自分自身の経験や身体感覚をつうじて大地や地球とのつきあい方をそろそろ見つめ直すべきだということである。
***
ニコラス・クレイン『ユー・アー・ヒア あなたの住む「地球」の科学』(白川貴子訳、本体1700円+税)は、早川書房より好評発売中です。
【著者紹介】ニコラス・クレイン(Nicholas Crane)
1954年生まれ。紀行家として、BBC(英国放送協会)でMap Man、Great British Journeys、Britannia、Town and Coastなど数多くの冠番組を持ち人気を博する。1986年、いとことともにユーラシア到達不能極に史上初めて到達。1992年から1993年にかけてヨーロッパを歩いて横断、大西洋から黒海まで約1 万キロメートルを踏破した。16世紀の地理学者ゲラルドゥス・メルカトルの伝記Mercator: The Man Who Mapped the Planet、全英ベストセラーとなった絵本『WORLD ATLAS 世界をぼうけん! 地図の絵本』など著書多数。本書『ユー・アー・ヒア』は《ニュー・ステイツマン》紙の年間ベストブックに選出されるなど高い評価を得た。地理学に際だった貢献を果たしたとして、王立スコットランド地理協会よりムンゴ・パークメダルを受賞、またイギリスの地理にかかわる知識を広く世間に紹介した功績をたたえ、王立地理協会よりネス賞を受賞している。2015年から2018年まで、王立地理協会の会長を務めた。