
全米170万部の話題作がうまれた背景は? 現代アメリカを理解するための必読小説『ひとりの双子』解説(新田啓子)
「入れ替わっても気づかれない」とさえ言われた双子が、ある選択によって、正反対の人生を送ることになる。
アメリカの小説家、ブリット・ベネットが『ひとりの双子(原題:The Vanishing Half)』で描くのは、そんな姉妹。姉のもとから突如消えた妹は、自由をもとめて、素性を偽り、故郷から遠くのどこかで暮らしているという。姉は噂しか知らず、もう何年も会っていない。
妹を追いかける物語は、サスペンスと驚きに満ち、ページをめくる手がとまりません。それと同時に、家族・社会の束縛のなかで「自分らしくありたい」と懸命に挑みつづける女性たちの姿は痛切で、胸に迫ります。
そんな本作は、どんな背景から生まれたのか? 作品が書かれた現代アメリカ社会とその歴史、そして著者ベネットの問題意識を、立教大学・教授の新田啓子氏が解説します。
※この解説では、物語の展開に触れています。
◉あらすじ
アメリカ南部、肌の色の薄い黒人ばかりが住む小さな町。
自由をもとめて、16歳の双子は都会をめざした。より多くを望んだ姉のデジレーは、失意のうちに都会を離れ、みなが自分を知る故郷に帰った。
妹のステラは、その何年も前に、デジレーのもとから姿を消していた。いまは、誰も自分を知らない場所で、裕福に暮らしているという。白人になりすまして。
いつもいっしょだった、よく似た2人は、分断された世界に生きる。
だが、切れたように見えたつながりが、ふいに彼女たちの人生を揺さぶる。
人種、貧富、性差――社会の束縛のなかで懸命に生きる女性たちを描く長篇小説。
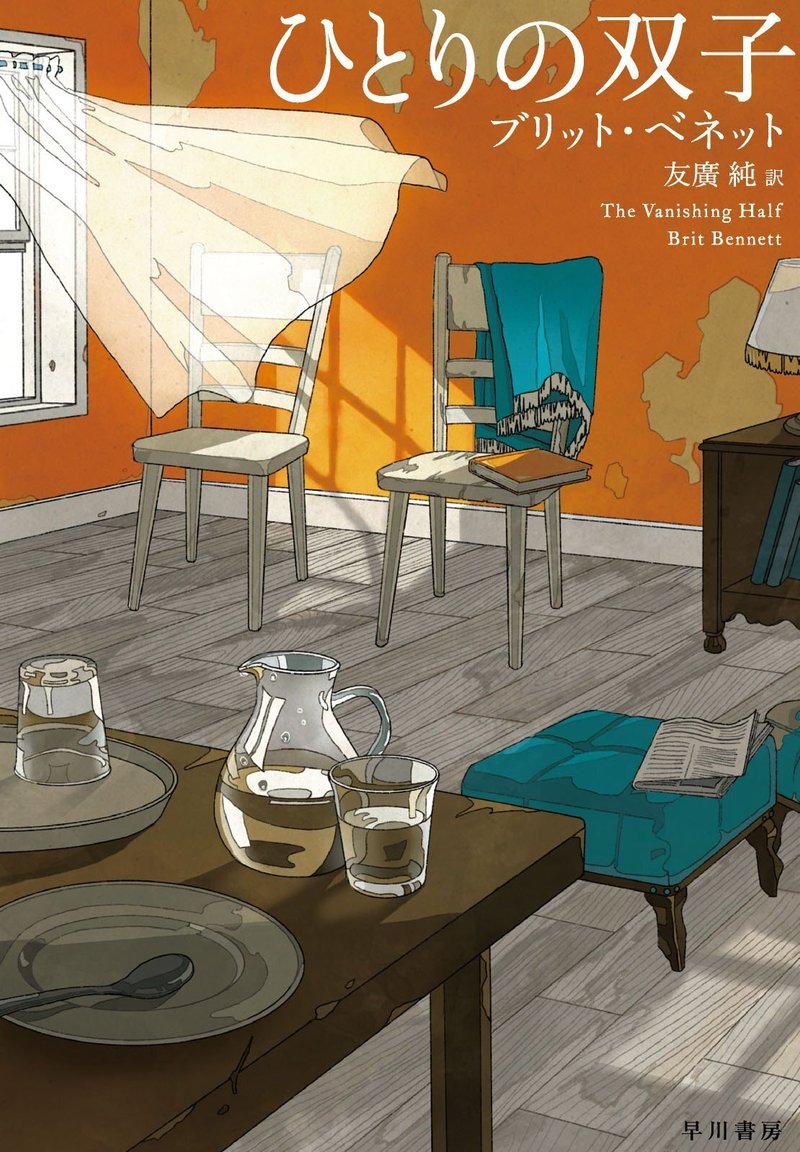
早川書 好評発売中
装画:カチナツミ 装幀:早川書房デザイン室
乱反射する片割れたち
新田啓子(立教大学教授)
1619年、ヴァージニアの人口調査に黒人奴隷が初めて記録された時、アメリカ人は、その自己認識が「人種」に支配されるという宿命を負い、宿命は、誰ひとり逃れられない暴力をアメリカ社会に構造化した。異種と説かれた「黒人」と「白人」は、にもかかわらず混交し、その結果、2つの血統がもはや視覚的には峻別できない子孫が生まれることになる。だが、大西洋奴隷貿易でアフリカから連行された「黒人」は、動産である以上、「白人」と混同されてはならないものと定められた。「黒人」の血が1滴でも入っていれば、その人はいかに「白人」的に見えたとしても、「黒人」であると判断された。人種はこうして捏造された。が、そもそもこの2つの色はいったいなにを指しているのか。人間が「白」や「黒」であるのではない。人間を序列化する観念のほうが、そうした色に塗られているのだ。
消えゆく片割れ──これが本書の原タイトル The Vanishing Half(ヴァニシング・ハーフ)の字義的な意味である。白い肌をもつ黒人家系のヴィーン家、そこに生まれた双子のうち、妹のステラが、白人として生きることを決意して姉デジレーのもとを去った時、ほんらい分割できないものが「片割れ」として切断される。片割れとは、もとはひとつであったものとの関係をふまえた比喩である。だからそれは、消えたステラ自身を指し、同時に彼女が葬り去ろうと試みた「黒人」としてのおのれの半生、ひいてはそうした選択をする必要性がなかったとしたら、彼女が享受し得たはずの人生を指している。彼女は無論、黒人に許された人生には見切りをつけて、みずからそれを捨てたのであるが。
ステラが自分を白人として詐称する時、それは、彼女の家族、つまりデジレーと母のアデル、さらには故郷マラードに生きる人々や、彼らが代々培った歴史が、アメリカ社会の日の目を見ない片割れに過ぎないことを黙認する行為となる。ステラが同化するにいたったアッパーミドルの白人社会で、その地について知る者はおらず、地図にすら載っていないという設定は象徴的だ。社会の中枢から見れば、忘れられ、切り捨てられ、なかったことにされてしまう経験や集団が存在するということに対する、批判的な問題意識がここに垣間見えるだろう。そしてそれは、本書において片割れの比喩がもつ意味を、さらに拡大してもいる。
挫折ないしは隠蔽された人生の片割れたち──それは、ステラ以外の主要登場人物たちの人となりを別の次元でも彩っているのだ。失踪から14年後、マラードに戻ったデジレーが、首都ワシントンで指紋鑑定官として活躍していた経歴は、筋書きからすらかき消えてしまう。黒人検事の夫サムの家庭内暴力で傷つけられた経験についても、心にしまわれたままである。また、年を経て、再びデジレーとめぐり逢う初恋の男アーリーは、正当な理由もなしに収監された刑務所で受けた虐待のトラウマを隠しているし、デジレーの娘ジュードのパートナーとなるリースは、「女性」とされつつ生きた日々から逃走中の人物である。
表向きの人生の陰に潜行する片割れの境涯──しかしそれらは、実は消滅していない。消滅せずに生き残り、別のかたちで他の人生の糧として再生される空間を、著者ブリット・ベネットは創造している。その最も劇的なあらわれは、デジレーとステラの潰えてしまった夢の成就の仕方であろう。デジレーが得意としていた演劇は、やがてステラの娘ケネディの生業となり、大学で学ぶことを望んでいたステラの夢は、医学生として歩み始めるジュードによって、交差的に引き継がれている。誰かが忍んだつらい経験、消してしまいたい過去もすべて、別のかたちの因果となって往還するのがヴィーン一家三代の物語にほかならない。いうなれば、彼女たちが自己のストーリーから除外した片割れが、プリズムのように乱反射しつつ生み出すドラマを、この小説は描いている。そしてその乱反射は、ひとつの論理で割り切れない人生を照らし出すのだ。
ひとつの論理で説明できない輻輳性、それはまさに、この一家に数奇な閲歴を強いたアメリカの人種関係それ自体の本質である。すべての起源は、アデルの父祖アルフォンス・デキューアが開いた街、マラードの特異性だ。ステラが白人になるために、この地に育ったおのれの出自を隠す行為が、黒人の社会的存在の、ある種の消去となることには先にも触れた。が、それ以前にこの街は、それそのものが、より肌の黒い同胞を蔑視する人種主義に基づいていた。マラードは虚構の地名であるが、実はこの設定には、相応の歴史的根拠が仕込まれている。
もとは奴隷だったアルフォンスが、1848年、彼の所有者兼「父親」だったアメリカ南部、ルイジアナの白人農園領主(プランター)より受け継いだ地所から始まったのが、マラードである。プランターの屋敷では、白人主人の女性奴隷への強姦を介した混血児の再生産が横行したが、アルフォンスもその「繁殖行為」の帰結を匂わす人物だ。奴隷制下、奴隷の腹から生まれた子は、いかに主人の面影を継いだとしても奴隷であり、認知されることはなかった。だが、情のかかった女性奴隷やその子供たちが、財産を分与されて解放されることはあった。色が白く気位の高い自由黒人アルフォンスの造形は、その背景に根ざしている。またルイジアナは、奇しくもその典型例で記憶される州でもある。1872年にたった36日ながら、黒人初の州知事として同州再建政府を率いた黒人政治家P・B・S・ピンチバックも、似た背景の持ち主であった。
アルフォンスのような人物は、実際に奴隷制廃止(1865)後の数十年間、民族の指導者をみずから任じた黒人エリート集団の一角を担っていた。高等教育、経済的安定、文化的なたしなみを有したこの層は、黒人としての自己認識はあくまで保つが、白人支配者階層の気質と人種的な序列意識を受け継いだ、一般的な黒人とは連帯しない「貴族aristocrat」と呼ばれた。白人とも黒人とも違う、いわば「第三の人種」を成したこのエリート層は、人種差別とも闘った。彼らの主張は、しかし、黒人の民衆が、自分たちのように人種を超越することができれば差別はなくなるという理想、いわゆるカラーブラインド主義を旨としていた。
ちなみに彼らが人種を超越していたというのは自己誤認だが、本書はそれを直視している。双子の父レオンの死因は白人によるリンチであり、この娘たちが最初に就けた仕事といえば、白人家庭のメイド、つまり汚れ物掃除であった。どちらも人種主義ゆえの黒人的な境遇だ。けれども「黒人貴族」たちは、そんな苦境に目を閉ざし、黒い同胞をさげすむことで、人種を超えた自分たちを夢想した。そのやや痛々しい自己欺瞞の装置こそが︑マラードに特有の人種主義、つまり黒人同士が色の薄さを誇りあい、黒い者を排除する、俗にいう「カラリズムcolorism」である──「より完璧なニグロ。世代を重ねるたびに色は薄くなっていく」(本書11頁)。
ところでステラが人種的出自をいつわり、白人になりすます行為は「パッシング」といい、人種関係の輻輳性を先鋭的に証言してきたアメリカ文学伝統の主題ともなってきた。この言葉の語幹である英語のpassとは、誰かがある人格として「通用する」状況を表す動詞である。今年出版170周年となるハリエット・ビーチャー・ストウ『アンクル・トムの小屋』(1852)を皮切りに、20世紀転換期に活躍した黒人作家のパイオニア、チャールズ・W・チェスナットがそのプロトタイプを作って以来、パッシング小説は、混血が進んでも人種主義は残る社会で個々人がとる生存戦略、そしてそのおうおうにして悲劇的な結末を活写してきた。
1920年代の黒人芸術隆盛期ハーレム・ルネサンスの時代にはさらに、同性愛的欲望にも斬り込んだネラ・ラーセン、教育者・外交官・人権活動家としても活躍したジェームズ・ウェルドン・ジョンソン、そして前述のP・B・S・ピンチバックを祖父にもつジーン・トゥーマーといった作家が、「なりすまし」の心理をより精密に描き、モダニズム文学の域に昇華させた。現代では、ユダヤ系作家フィリップ・ロスが、ユダヤ人にパッシングしていた黒人古典学教授の悲劇を主題とした『ヒューマン・ステイン』(2000)を書いている。ベネットが、デビューから5年足らずで書き上げた本作は、このような文学史的流れのなかに位置づけられる。
しかしこの作品は、パッシング小説の既存の型を、おそらくは意識的に解体しているところがある。その最大の特徴は、本書におけるパッシングが、これといった悲劇を招いていないことだ。登場人物たちは無論、それなりの苦悩を味わっている。だが彼らはそれ以上に、傷ついたり、傷つけたり、自己の不遇を悲観したり、逆におのれの欺瞞に気づき激しい自責を経験したりするプロセスで、存分に自己を凝視している。そうした内面の観照が、果たして、おのれの片割れの生き方に対する寛容性に転化している。
また、より重要なこととして、作家はパッシングをおそらく初めて、先に見たカラーブラインド主義とともに構造として示すことで、人種的欺瞞とはなにかという問題を、提起し得ているといえる。
人種を超越することを目指すカラーブラインドという理念は、まさにここ10年あまりのアメリカが、人種をめぐる政策に失敗してきた主因であったと見なされている。2009年、バラク・オバマが初の「黒人」大統領に就任すると、それをあたかも同国から人種主義が解消した証のように捉える議論が続出した。これを「ポスト人種論」というが、現実はもちろん違った。オバマはむしろ、リベラル社会の普遍的な善は語るが、人種に端を発するとみえる犯罪等へは不介入を貫いたため、結局それがKKKなど極右団体の増長と、ドナルド・トランプの台頭を許すことになったといわれる。小説におけるマラードが、選民意識とカラリズムに貫かれたコミュニティであったように、リベラリズムは、人種的思考法とそれがもたらす特定の人々への不利益を、うわすべりしてしまうのである。「人種」にいまだ縛られた層は存在する。「ブラック・ライヴズ・マター(BLM=黒人の生を尊重せよ)」が訴えてきたように、制度的人種主義(システミック・レイシズム)は、そうした層を狙い撃つのだ。
本書はこうした状況に真っ向から論争を挑む作品ではない。しかし、主人公を当事者として、カラーブラインドの問題性に多方向から斬り込むという着想は、まず読者のうちの「私は人種差別において潔白だ」という信念をずらし、各々が抑圧している人種的思考法、ないしはおのれの良心の片割れと、出会うことを要請しているように見える。著者は2014年、黒人少年を射殺したミズーリ州ファーガソンの警官の無罪評決に際し、フェミニスト系ウェブ誌に、論説「善良な白人たちとの折り合い方がわからない」を寄稿し、同問題を論じたことでも知られている("I Don't Know What to Do with Good White People,” Jezebel, 17 December 2014)。小説では、ヴィーン家が忘れ去った「黒さ」という問題を漆黒のジュードに回帰させたが、彼女の自己探求を通し、母や祖母が見落としたものを見せる技巧に、同様の問題意識が溶け込んでいる。
2020年、ミネソタ州でジョージ・フロイド殺害事件が起きた翌週、はからずもベネットが世に送った本作は、よりよい生を求める個人を、彼らにまるで重力のように取り憑いた家族、すなわち人種の力とともに写実する。140年にもおよぶ歴史的背景には、奴隷制、大恐慌、人種隔離(ジム・クロウ)、公民権運動、レーガン政権時代の空気に注意を向ける仕掛けがある。それにより、作家はアメリカ史がいかに人種的事件に満ちていたのかを刻み、かつ返す刀で、1978年、UCLAに進学したジュードの出会うトランス男性リースの姿を削り出し、ポスト公民権時代ではおそらくより切実なジェンダー・パッシングの問題を、人種に重ねて投影するのだ。
人種主義がトランスナショナルな問題として再び深刻化する今日、アメリカでは非ヨーロッパ系の作家が続々と登場し、秀作を発表しているが、アフリカ系女性作家ベネットは、そのまぎれもない1人である。カラーラインに分かたれた双子が、片割れ同士を求める心の先に広がる多彩な景色と展開のスリルを楽しみたい。技巧的にも野心あふれる作品であるが、語りの目線を精確に捉えた揺るぎのない翻訳が、読書の助けになってくれるはずである。
さらにアメリカ文学ファンには、物語に仕込まれた、他作品のアリュージョンを見つけるという楽しみ方ができるのも、この作品の特徴である。マーク・トウェイン、ゾラ・ニール・ハーストン、トニ・モリスン、そしてなにより、19世紀の終盤に短い創作人生を送ったルイジアナのクレオール作家ケイト・ショパンに、この作品は多くを負っているようだ。デジレーの名前は、おそらく彼女のパッシング小説「デジレの赤ちゃん」("Désirée's Baby," 1893)に由来しており、双子の両親レオンとアデルは、ともに『目覚め』(The Awakening, 1899)の主要登場人物から来ているはずだ。ルイジアナ州は、ベネットの母の故郷とのことであるが、フランス系クレオール文化の遺物にもあふれた本作は、ある種の「地方色(ローカルカラー)文学」としても意匠されているのかも知れない。
このように、社会小説や人種文学とは一概に括れない『ひとりの双子』は、生きづらさを抱えた人が、それでもいかにみずからの人生を日々生き延びているか、また社会が見捨てた問題を、どう乗り越えていこうとするかを繊細に描き出している。その風景があるからこそ、この作品は、キャラクターたちに吹き込まれた尊厳が物語からほとばしり出てくるような感覚に満ちているのに違いない。
***
対立と分断に揺れ動くアメリカ社会からあらわれた、新たな声。ぜひ聴いてください。
『ひとりの双子』( ブリット・ベネット 友廣 純 訳)は、早川書房より好評発売中です(紙・電子書籍同時発売)。

