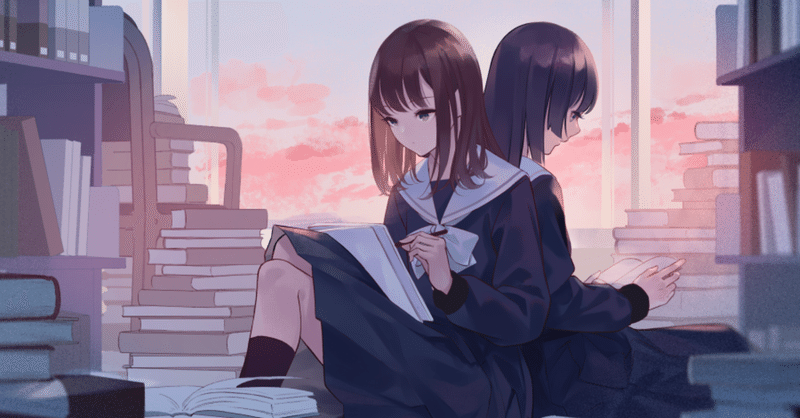
こういう面倒くさい事をやりたがる人が大好きで、応援したくなる。『文学少女対数学少女』解説:麻耶雄嵩
ハヤカワ・ミステリ文庫の新刊、陸秋槎『文学少女対数学少女』より、作家の麻耶雄嵩さんによる巻末解説を公開します。日本の新本格ブームの影響を受けて書かれた華文ミステリの傑作、書籍と合わせてお楽しみください。(本篇の核心にはふれませんが、軽いネタバレを含みます)
解説
麻耶雄嵩
数年前に『タイムトラベル少女』というテレビアニメが放映されていた。早瀬真理と水城和花の二人の女子中学生がとある理由でタイムスリップして、過去の偉大な科学者たちと巡り逢い成長するという内容だった。今風の味付けはしてあるが、昭和の子供向け教育アニメに近いテイストで面白かった。
「マリ・ワカと8人の科学者たち」という副題の通り、アニメには八人の科学者が登場する。電気工学の父・ギルバートから始まりフランクリンやボルタ、そしてベルやエジソンなど、科学者の中でも主に電気畑の偉人が選ばれていた。
フランクリンの雷中の凧あげなどの有名なエピソードなどを経て、ファラデーが中学でも習う電磁誘導の実験をして、ようやく電磁気学の基礎というか入口にやってきた感がした。番組はその後、難解な理論よりもベルやエジソンなどの発明家主体になっていく。
ところでそのファラデーが電磁誘導を発見したのが一八三一年のこと。また最終話に出てくるエジソンが電球の実用化に成功したのが一八七九年。前々世紀のことなので、そんなものかと思われる人も多いだろう。
アニメには出てこないが、他の科学分野、たとえばワットが蒸気機関を製作し産業革命の口火を切ったのが一七六九年。ダーウィンが『種の起源』を発表したのが一八五九年になる。ちなみにポーが『モルグ街の殺人』を発表したのが一八四一年で、ドイルが『緋色の研究』を発表したのが一八八八年。
長々と書いてしまったが、翻って数学の話。eiπ+1=0というオイラーの等式がある。自然対数の底と虚数と円周率が指数によって一堂に会した、なんだか狐につままれたような等式である。数学史上で最も美しい公式と称讃されているが、それをオイラーが導いたのが一七四八年のこと。
つまりオイラーは電球(どころかガス灯すら)も蒸気機関も進化論も、電磁誘導すら知らない世界でeiπ+1=0をはじめとする有名な公式や定理を生み出したのだ。ちなみに芸術では、絵画はロココ、音楽ではバッハの晩年にあたる。マリー・アントワネットはまだ生まれてもいない。
またオイラーの等式の元になったネイピア数を定義したネイピアや、本書に登場するフェルマーの定理で有名なフェルマーは、オイラーの百年以上前に活躍している。
中学で習う電磁誘導より難解なオイラーの等式のほうが、遥かに昔に発見されたわけである。物理や他の科学の分野と比べても、いかに数学が早熟だったことか。
原因はある意味単純で、数学は頭の中で考えられ、出力は紙とペンだけあればいい。証明するために実験装置などが要らなかったからだろう。つまり思考さえできれば、人はいくらでも先鋭化するのだ。
これは文学とも相似する。プロットを頭の中で考え、紙に出力するだけ。特に社会性よりもパズル要素に重きを置く本格ミステリではなおさらだ。頭の中でいかに立派な密室や巧みなアリバイトリックを作りあげるか。「できそう」であればあえて実験する必要もない。多少浮世離れしていても問題ない。
もちろんその前提となる指紋や血液型、DNAといった基礎的な科学が必要で、数学ほど先鋭化はできないだろう。しかし数学のラディカルさを見習うことはできる。
『文学少女対数学少女』はまさにその思考のために書かれた本だ。
作者の陸秋槎はデビュー作の『元年春之祭』では新本格風の歴史ミステリ。次の『雪が白いとき、かつその時に限り』では一転、新本格風の学園百合ミステリと舞台を変えた。謎解きの手つきの綺麗さは、前の二作を読んだ方には周知のことだろう。
本作は短篇集で、ミステリ好きで犯人当て小説を書く女子高生・陸秋槎(りくしゅうさ)と同級生で数学の天才少女・韓采蘆(かんさいろ)が主軸となっている。これに秋槎のルームメイトの陳姝琳が絡み、陸秋槎作品おなじみの百合の三角関係も匂わされたりもするが、短篇集ということもあり、次々と現れる事件に追われて百合成分は控えめ。
文学(本格ミステリ)と数学。これらは文系と理系の正反対の対比に見えて、どちらも頭の中だけで先鋭化できる相似性を持つ。それゆえ本書の内容が、理想の暴走ともいうべき後期クイーン的問題になるのは必然だった。もっとも後期クイーン的問題を扱うために、二人の少女たちは駆り出されたんだろうけど。
後期クイーン的問題の一つの大きなテーマに偽の手がかり問題がある。探偵は残された手がかりを拾って推理を組み立て犯人を指摘するが、もし真犯人が偽の手がかりを細工して探偵に別の人物を犯人と名指しさせようと誘導したとき、果たして探偵は手がかりの真偽、ひいては真犯人を見破れるかというもの。
一見Xが犯人に見えるこの手がかりは、実は真犯人YがXに罪を着せようとしたものだが、もしかすると真の真犯人Zが、そう推理させてXに罪をなすりつけようとしているのではないか?
それとも真の真の真犯人Wが探偵にそう推理させて、Zに罪をなすりつけようとしているのではないか?
いやいや、本当はYが真の真の真の真犯人で、一見Y自身が疑われる手がかりによって、Xに罪を着せようとしたZを陥れようとしたWを真犯人と思わせようとしたのではないか?
ようはキリがなくなってしまう。
もちろん小説である以上、現実に基づいた落としどころというものはある。だがいままで頭の中で組み上げてきたパズルを、現実というジョーカーで打ち切っていいものか?
理想と現実のせめぎあいだ。
本格ミステリはヴァン・ダインが二十則で提唱したモラルの上に、クイーンが持ち込んだフェアプレイの理念によって、作者対読者という形を明確にアピールするようになった。くわえて初期の国名シリーズで顕著だが、推理レースを競っているのは実は読者と探偵という構図になっている。
最初こそマックと名乗る謎のおっさんが挑戦状を書いていたが、やがてクイーン本人が直々に挑戦するようになった。はたしてこのクイーンは作者のほうなのか探偵のほうなのか?
いずれにせよページを開いた読者はスタートラインに立たされ、トラックを探偵と競走することになる。
この手がかりを拾って探偵は見事犯人を指摘できました。ところであなたはどうでしたか? 作者は挑発してくる。それゆえ作者が探偵と読者のどちらかにだけヒントを与えることは、フェアプレイ精神に反してしまう。ヒントはどちらも平等に示さないといけない。
手がかりの無限の反転を避けるために、作者が現実的な落としどころを恣意的に作ったとする。対決である以上、読者もレースがフェアに行われたか、不服を申し立てることができる。この手がかりも罠ではないのか、罠でないとは証明されていないぞ、と理想を突き詰めようとする厄介な読者(だいたいは自分自身だ)に反駁されたとき、クレームを退けられるだろうか。
やがて記述者トリックや叙述トリックなどで作者対読者の構図が前面に出てきたが、作者の恣意性の問題は残されたままだった。リアルを強調すれば問題をいくらでも矮小化できる。しかし同時に対決も後退することになる。
*
思うに、後期クイーン的問題の中でも、偽の手がかり問題というのはただの結論にすぎない。証明された命題なので、否定することも解決することもできない。論理学を包括した数学でも不可能が証明されているのに、遥かに緩いロジックしか用いないミステリで覆せるわけがない。
理屈で云えばこうなる。しかし緩いからこそできることもある。白旗をあげずに誤魔化す方法が。何事もないようにとりつくろったり、逆にこれみよがしに戯れたり。
『文学少女対数学少女』一話の「連続体仮説」では、一見きちんとしている犯人当てに作者の恣意がたくさん隠されていたことが韓采蘆によって暴かれる。
しかし采蘆は最後に恣意性こそミステリの醍醐味であり、前作のタイトルを流用した「君がそう言ったとき、かつそのときに限り」に続き「君が作者なんだから、君が真相だと言ったものが、君が犯人だと言った人間が犯人であり、つまり真相である」と力強く宣言する。
作者は作品の創造主である。しかし創造主といえど恣意は排除できない。ならばいかにしてつき合うか? 多くの作品がそうなように自然にみせかけるのが本流だが、あえて宣言した以上は積極的な道を選ぶしかない。恣意を隠すのではなく、利用し戯れる方向に。問題提起とエンターテインメントの両立。
現実的な作者の恣意は、理想的である厄介な読者と対峙する。本書ではこの二者を併置することで対比を鮮明にしている。そのため二話以降は作中作だけでなく、外側の秋槎や采蘆も事件に遭遇することになった。作中作で理想を求め、外側で現実を語る。
作中作は一話同様普通の犯人当てだが、厄介な読者である采蘆を通して、様々なイレギュラーな推理を並べていく。それは姑息な抜け道というより、理想空間での興味深くも厄介な可能性と呼ぶべきものだろう。本来なら一つの真実に絞るべきだが、原理的に排除できない綻びたち。その中でもピックアップする価値があるものが選ばれ提示されている。
そして外側の事件。作者はこれみよがしに恣意的に幕を下ろす。外側の事件は犯罪の種類が様々で、罪の重さに呼応した恣意的な処理が行われる。最終話の「グランディ級数」でとうとう殺人事件が起こるのだが、ぜひ作者が用意した現実を体感してほしい。偽の手がかり問題というのは、内と外の両側からの挟撃によって、そもそもが幻想であるかのように思わされるだろう。
創作の最中は、厄介な読者も現実で対処する作者もすべて自らの分身だ。理想と現実のはざまでエンドマークの模索をするしかないが、あまたの可能性のはざまでたゆたっているときが、作者にとって最も幸福なのかもしれない。秋槎と采蘆が作中作についてあれこれ討論しているときが一番楽しそうなように。
おそらく偽の手がかり問題にいち早く自覚的だったのはヴァン・ダインだろう。『ベンスン殺人事件』で、物理的な手がかりはいくらでも偽装できるからと、個性に直結する心理的手がかりをよりどころとする天才探偵を生み出した。後の作品では犯人が出した偽の手がかりに気づきすらしないというパロディめいたこともやっている。
評論家肌のヴァン・ダインは偽の手がかり問題に先はないと直感的に回避したわけだが、だからといってヴァンスが用いる心理的手がかりが面白いかはまた別だ。
クイーンは逆にそこにこそミステリの醍醐味が潜んでいると、あえて火中の栗を拾ったわけである。クイーンの目論見は間違ってなかった。〝平成のヴァン・ダイン〟はついぞ耳にしなかったが、クイーンは今なお多くのフォロワーを産み出している。
ただ同時にヴァン・ダインが危惧した問題にも突き当たってしまったわけだが、時代はそれすらもエンターテインメントとして楽しもうとしている。
手間ばかりかかる二部構成で、数学のアナロジーまで絡めて後期クイーン的問題と戯れた陸秋槎も、もちろんその遺伝子を確実に継承している。
こういう面倒くさい事をやりたがる人が大好きで、応援したくなる。
『文学少女対数学少女』
陸秋槎/稲村文吾訳
装画:爽々/装幀:坂野公一(welle design)
高校2年生の“文学少女”陸秋槎は自作の推理小説をきっかけに、孤高の天才“数学少女”韓采蘆と出逢う。彼女は作者の陸さえ予想だにしない真相を導き出して……“犯人当て”をめぐる論理の探求「連続体仮説」、数学史上最大の難問を小説化してしまう「フェルマー最後の事件」のほか、ふたりが出逢う様々な謎とともに新たな作中作が提示されていく全4篇の連作集。華文青春本格ミステリの新たなる傑作!


