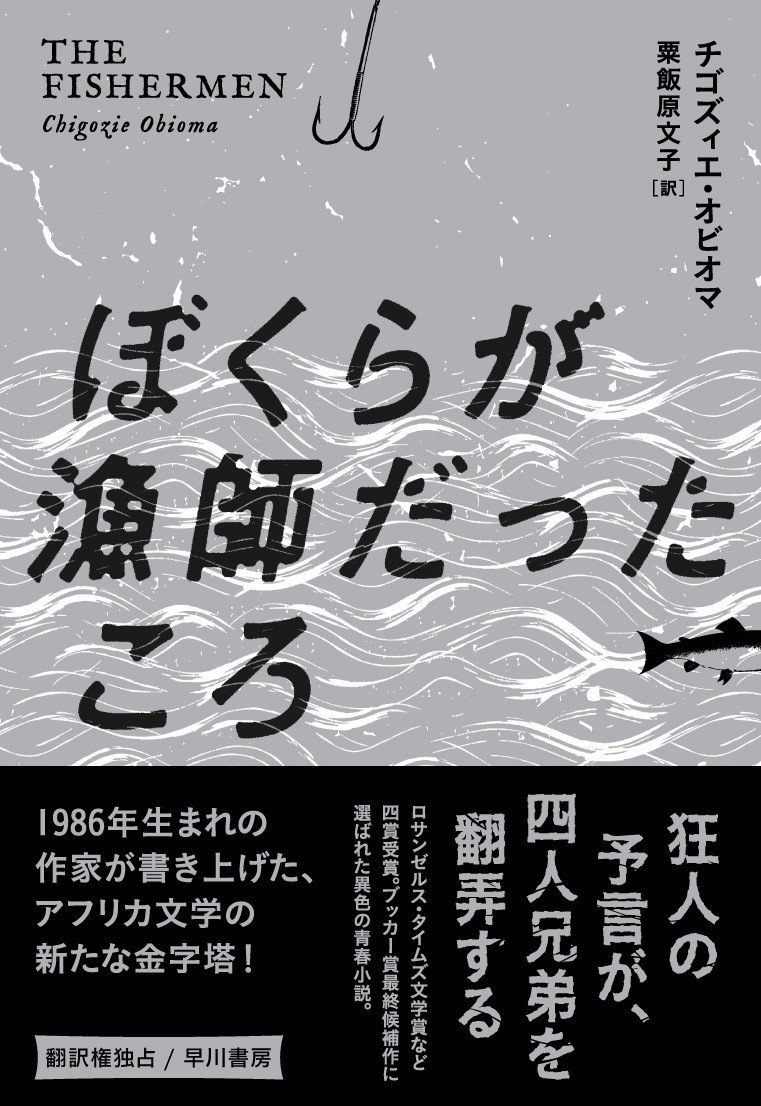29歳のデビュー作がブッカー賞最終候補に! 胸をうつ少年たちの物語『ぼくらが漁師だったころ』、訳者あとがきを特別公開
(書影をクリックするとAmazonページにジャンプ)
「アフリカはもはやアフリカ大陸だけに存在するのではない。アフリカ人たちが世界に散り散りになっていき、さまざまなアフリカを生み出し、さまざまな冒険に乗り出している。おそらくこのことこそ、黒い大陸がもつ文化的価値を判断する一助となるはずだ」──コンゴ共和国出身の作家アラン・マバンクはそう述べる。
「アフリカのベケット」と呼ばれるマバンク自身も、コンゴそしてフランスで学業を修め、フランスで教鞭を執ったのちにアメリカにわたり、現在はカリフォルニアに身を置いて、大学で教えながらフランス語で創作している。アフリカ文学がアフリカ大陸の国家独立、脱植民地化の流れのなかで、「アフリカ文学」というひとつの軸に結集し、歩んでいった時代から半世紀以上が経過したいま、アフリカに出自をもつ作家たちが、主流の移住先である旧宗主国に限らず、さまざまな移動の軌跡をたどりつつ世界じゅうに広がっている。作家自身と作品の帰属のカテゴリーが国や大陸、言語をまたいでいる状況において──連綿と続く頭脳流出ともとれるうえ、アフリカに暮らし、活動するポテンシャルを否定する現象にも見えるにせよ──アフリカ文学という定義が多様化、複雑化しているとともに、その新たな可能性と展望が開かれ、新しい才能が続々と誕生している。イギリス、フランス(そして相対的に規模は小さいながらもポルトガル)は言わずもがな、現在では──明らかに大学での雇用をはじめ経済的な理由によって──マバンクのようにアメリカ合衆国にわたる作家たちが多いうえ、イタリア、ドイツ、ベルギー、オランダ、スペイン、メキシコ、南アフリカなど、あらゆる場所で、そしてあらゆる言語(ときに2言語以上)で創作活動をおこなっている作家の活躍が著しい。
チゴズィエ・オビオマはまさにこの新しい潮流、新しい世代を代表する才能である。ナイジェリア南西部のオンド州アクレで生まれ育ったオビオマは、2007年に地中海に浮かぶ島、キプロスにわたって学業を修める。その後アメリカへ移住、現在はネブラスカに暮らして、大学で教鞭を執りながら創作をおこなっている。アメリカでは、すでに触れたマバンクのほか、チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ(ナイジェリア)、クリス・アバニ(ナイジェリア)、ディナウ・メンゲストゥ(エチオピア)、パトリス・ンガナン(カメルーン)、ノヴァイオレット・ブラワヨ(ジンバブウェ、『あたらしい名前』谷崎由依訳、早川書房、2016年)など、多くの錚々たる「アフリカ人」作家たちが活躍しているが、そのなかでもオビオマは1986年生まれともっとも若い作家のひとりである。長篇デビュー作の本作『ぼくらが漁師だったころ』(原題はThe Fishermen)は、2015年に出版されるや、同年のブッカー賞最終選考に残ったことをはじめ、多方面から高い評価を受けて大きな反響を呼んだ。
オビオマ自身によれば、この小説は移動の経験なくしては生まれなかったという。あるインタビューで、彼はイボ語の言い回しを用いてこんなふうに表現している。「太鼓の音は近くよりも遠くから聞くほうがよりはっきり聞きとれる」。つまり、ナイジェリアから遠く離れ、外側から国家、故郷、家族を見つめなおすことで物語が形をとり始めたのである。2009年、キプロスで暮らして2年が経過したころ、突然ホームシックに襲われた。そのとき、しばらく前に父親が電話で嬉しそうに語っていたことを思い出す──総勢12人きょうだいの「大連隊」において、成長過程でしばしばぶつかり合い、殴り合いの喧嘩もしていた上の2人の兄たちが強い絆で結ばれるようになったということだった。そこから、きょうだい愛や家族の絆について思いを巡らせるうちに、その対極の最悪の状態とはどういうものだろうと想像を膨らませ、アグウ家の悲劇の物語が浮かび上がってきたのだそうだ。
『ぼくらが漁師だったころ』は普遍的な家族の絆とその崩壊の物語である、とオビオマは述べている。しかし同時に、ひとつの家族の運命のプリズムをとおして、ナイジェリアという大国が抱える、政治的、経済的、社会的なさまざまな矛盾が意識的に、しかも巧みに描かれてもいる。1990年代のナイジェリア、著者が生まれ育った南西部の町アクレを舞台に、アグウ家の物語は、直接、間接に激動のナイジェリア現代史と絡み合いながら展開していく。小説では固く結束した家族がアブルという“狂人”の予言によって引き裂かれることになるが、ナイジェリアという国家自体も、英国といういわば“狂人”の放ったことばで恣意的に作り出され、人びとがその存在を信じるようになったがために悲劇に見舞われてしまった──オビオマは自らそう解説を加えている。
現在ナイジェリアと呼ばれる地域は、歴史的、文化的にまったく異なる社会が複数存在している場であり、とうていひとつの国としては成立しえないはずであった。一般的に言われるような、北部はイスラームのハウサ人、南西部はヨルバ人、南東部はイボ人が主流の地域という単純化された見方をとってみても、一国ではありえない複雑さを呈していることがわかる。そもそもの問題のもとをたどると、19世紀のイギリス植民地支配の開始にまでさかのぼり、1914年、北部と南部の保護領がナイジェリア植民地保護領として統合されたことに行き着く。1960年に連邦共和国として独立を遂げるが、その複雑さゆえに、独立後も長きにわたって政治的混乱が続いてきた。
物語の中心的な成分であると同時に、歴史的にも重要なモメントであるのは、1993年の出来事である。小説では、この年、4人の兄弟が偶然にも大統領候補の実業家、M・K・Oの愛称で知られるモシュード・アビオラに出会う。選挙戦のスローガン「希望93」のとおり、アビオラは民政移管が期待されていた国政だけではなく、兄弟にとっても未来の希望の象徴となった。ところが、アビオラが同年の大統領選で勝利したにもかかわらず、85年のクーデターでの政権奪取以来、大統領の座についていたイブラヒム・ババンギダによって選挙結果が破棄されてしまう。それを機に各地で暴動が起こり、ババンギダは引責して大統領を辞任、ショネカン暫定政権が発足するも、わずか一カ月ほどでサニ・アバチャがクーデターを起こして実権を掌握する。アバチャ軍事政権のもとでは、アビオラが国家反逆罪で逮捕・投獄されるなど政治弾圧が激化していった。小説でも触れられているように、アビオラはその後、釈放の前日に悲劇的な獄中死を遂げることになる。
ナイジェリアが混乱に陥っていくのと同時に、アグウ家の絆も、幼い夢も、希望も、なにもかもが崩壊の一途をたどっていく。95年の終わりに”父さん”が北部の町ヨラに転勤になったことを境に、夢がいっぱい詰まったかれらの未来予想図にたちまち暗雲が垂れこめる。厳格な”父さん”が不在であるのをいいことに、不穏な噂が絶えない川で魚釣りを始めた兄弟たちは、家路につく際、狂人のアブルに遭遇し、悲劇のもととなる予言を告げられるのである。無邪気で微笑ましい子ども時代の記憶が語られる前半部分から一転、これ以後、アグウ一家は途方もない不幸に飲み込まれていく。とりわけ、自身に対する予言を重く受け止めた長兄イケンナが、兄弟たちの希望が託された”M・K・Oカレンダー”を破り捨てる一件は、同時代のナイジェリアの希望の喪失に重ね合わせられており、核心的な出来事として描かれている。だからこそ、ナイジェリアの作家ヘロン・ハビラが述べるように、この小説は「失われた希望への挽歌」となっている。
もう一点、何度か言及されるだけではあるものの、家族史とナイジェリア史が交差する地点として重要なのは、ビアフラ戦争と呼ばれるナイジェリア内戦の記憶である。1967年、主にイボの人びとが暮らす東部州が連邦共和国から分離、ビアフラ共和国の樹立を宣言した。それをきっかけとして、前年にクーデターで政権を奪取していたヤクブ・ゴウォンが東部州に侵攻、その後2年半におよぶ内戦が続き、多数の餓死者を含む200万もの死者を出した。そして1970年、ゴウォンの内戦終結宣言とともに、事実上ビアフラ共和国は崩壊する。なお、ビアフラ戦争はこれまでも多数の小説で扱われており、なかでも2007年に出版されたアディーチェによる見事な長篇小説『半分のぼった黄色い太陽』(くぼたのぞみ訳、河出書房新社、2010年)はもっとも広く知られている作品である。本作においては、”父さん”の少年時代の話や”母さん”の幻覚のなかに悲惨な戦争の一断面が浮かび上がり、物語の不可欠な背景をなしている。アグウ家のみならず、ナイジェリアの、とりわけイボの人びとのトラウマとして、過去の戦争の記憶が立ち現れ、現在にも暗い影を投げかけていることが見てとれるだろう。
さらに小説の理解に欠かせないのは、登場人物たちの、あるいはナイジェリアの言語状況である。注目すべき点は、イボ語を話すアグウ家が、ヨルバ語が主流の南西部地域で暮らしていること、そして登場人物それぞれがひとつの言語と結びついていることである。4兄弟は地元の友だちと話すヨルバ語、西洋教育を崇めている”父さん”は英語、”母さん”はイボ語というように。家族のあいだではふだんイボ語が話されるが、両親は子どもたちを叱る際に、意図的に距離を作り、より厳格な響きをもたせるため英語を用いる。兄弟たちはイボ語とヨルバ語をごく自然に、器用に使い分けている。また、広く庶民に用いられる言語としてピジン英語も出てくる。オビオマによれば、さまざまな言語を織りまぜたのは、ナイジェリアに生きるリアリティとそのニュアンスを表現したかったためということだ。
登場人物が何語を話しているかについては、そのつど文脈化されてほぼ明確にされているため、読者にとってそれほど理解は困難ではないだろう。ただし、イボ語から英語に直訳された言い回しには、多少のつまずきやなんらかの違和をおぼえるかもしれない。語りに長けた”母さん”がイボ語の慣用表現やことわざ、話術を頻繁に用いるだけではなく、会話文でイボ語特有の表現がそのまま英語に移し替えられているところが少なからずある(たとえば、「ぼくの心が証明している」というのはその一例)。訳者がその違和をうまく表現できているのかは心もとないが、ぜひ読者のみなさんには著者の思惑どおり、大いにつまずきを感じていただきたい。「英語小説」のなかに含まれるイボ語、ヨルバ語、ピジン英語をどう日本語の文脈に移すか、あるいはどう表記するかというのは、非常に難しく、悩みに悩みぬいたことのひとつであるが、その一方で訳者冥利に尽きる──というよりむしろ、アフリカ文学研究者冥利に尽きるところであった。
作品中のこうしたイボ語の使用にも関連するが、そもそも小説の構造自体がイボの想像力や思想に依拠しているとオビオマは述べている。物語の底流をなしているのは、死者と生者の世界に往来がある、運命はすべてあらかじめ定められ、偶然の出来事はない、人びとの行動は超自然的な力にコントロールされている、といった思想である。事実、アグウ家の人びとは、なんとかして運命を変えようと努力し行動にうつすも、結局はどうにもならず、不幸のどん底へと転落していってしまう。
この思想は小説でも触れられているイボの「チ」という概念に深くかかわりをもつ。守り神という訳語をつけているとおり、「チ」はだれもが生まれる前からもっている神であり、生涯をとおして個人の成功や運を左右すると考えられている(ちなみに、”母さん”の「チネケー」や「チネケーム」という叫びは、「チ」がもとになった間投詞である。また、チゴズィエという名もそれに由来し、「神がわれわれに祝福を与えてくれますように」という意味である)。信じなくていい予言を信じてしまったのが不運の原因であるように見えるが、実際には、イケンナの運命はどうあがこうと、そもそも本人にも、だれにも変えられなかったのである。「……自分の運命を自分で決められない存在。運命はすでに決められていた。彼のチ、だれもが持っているとイボ人が信じる守り神は脆弱だった」
このように小説の支柱となっているイボ語やイボの思想の使用からも想像できるが、作品では直接的に、1958年出版のアフリカ文学の金字塔的作品、イボ人作家チヌア・アチェベによる『崩れゆく絆』(粟飯原文子訳、光文社古典新訳文庫、2013年)が言及されており、明らかにオビオマがアチェベから汲み取った文学的な影響は大きいと考えられる。『ニューヨーク・タイムズ』紙もオビオマに対して「アチェベの後継者」という讃辞を贈っているほどである。ところが、さまざまなインタビューでの発言をみると、アチェベの影響は強調されておらず(なお、一番影響を受けたアチェベ作品は1964年の3作目『神の矢』とのこと)、かわりにあらゆる作家や作品名があげられているのは興味深い。真っ先に名前があがっているのはナイジェリアのエイモス・トゥトゥオラ(『やし酒飲み』、土屋哲訳、晶文社/岩波文庫)、そして、ナイジェリアのノーベル文学賞受賞作家ウォレ・ショインカ、シプリアン・エクウェンシ、ヨルバ語作家D・O・ファグンワ、ギニア共和国のカマラ・ライ、さらに、ガルシア゠マルケス、トマス・ハーディ、ジョン・バニヤン、シェイクスピア、ホメロス、ギリシャ神話……とリストは延々と続いていく。アフリカの作家たちにはより強い共感をおぼえていると言ってはいるものの、アチェベについて熱心に触れないことからも、そしてこのリストを一瞥するだけでも、オビオマの作家としてのスタンスが見てとれる。レッテル貼りを嫌い、自分の作品がナイジェリア文学やアフリカ文学というカテゴリーに押し込められることを拒絶しているのである。さらに、「だれに向けて書いているのか」という質問に対しては──おそらく、ナイジェリアやアフリカの人びとという返答を期待した問いであろうが──あらゆる読者に開かれた作品である、と切り返している。
たしかに、文学作品があらゆる読者に開かれているのは当然であり、市場や流通にも深く関係する「アフリカ文学」というカテゴリー化に拘るのはナンセンスであるともいえる。しかしながら、実のところ、オビオマをはじめとして、冒頭にもあげた新世代のさまざまなアフリカ出身の作家たちの営みは、ほとんどの場合、アフリカという場からも、アフリカ文学という「伝統」からも、切り離されているわけではない。むしろ、アフリカ文学という単一性を掲げて積み重ねられてきた歴史の重みを引き受けつつ、今日的な状況を思考して、そこに多様性を付加し、刷新していく試みであるというほうが正しい。そもそもアフリカのローカルな思想や文化的資源と西洋文学の要素を練り合わせて、新しい形式や表現を産み出そうとする努力と営為こそ、アフリカ文学のいわば「伝統」であり続けてきた。オビオマがトゥトゥオラに敬意を払うのも、トゥトゥオラの一般的には「土着的」と評される作品のなかに、「ギリシャ悲劇とシェイクスピア悲劇の混在」が読み取れるからである。
『ぼくらが漁師だったころ』は、イボの悲劇であるとともにギリシャ悲劇の特徴を含みこむ──著者本人のことばによれば──「アフリカとヨーロッパの悲劇の形式が混ざり合った」作品である。そして、物語の中心的な主題には、普遍的な家族愛が据えられているとしても、別の位相においてそれはナイジェリアの運命のメタファーとなっている。オビオマの作品は「失われた希望への挽歌」である。と同時に、最後には希望の象徴と新しい時代の前触れとして、シラサギが悲運と混沌のただなかから姿を現し、翼を広げることにより、ナイジェリアという矛盾だらけの国の「輝かしい未来への予感」(ヘロン・ハビラ)をも表している。──ここにこそ古くて、新しい「アフリカ文学」のかたちを見ることができるのである。
『ぼくらが漁師だったころ』
チゴズィエ・オビオマ、粟飯原文子訳
早川書房より好評発売中
http://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000013636/