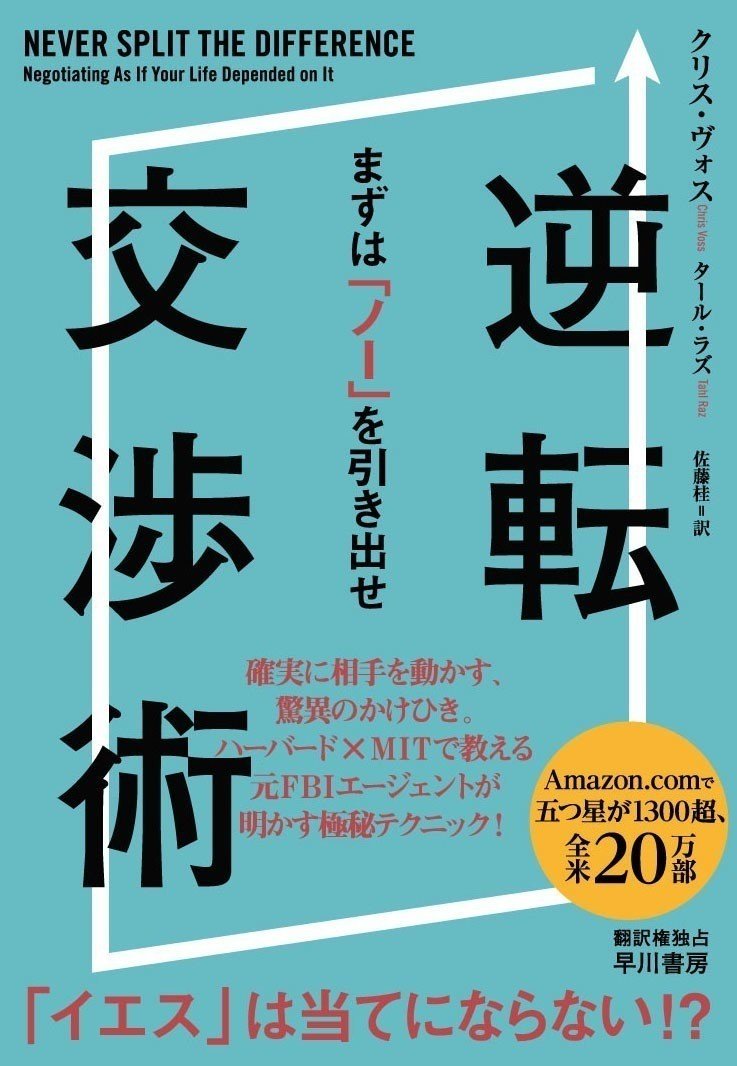ハーバード大教授を出し抜いた、FBIの最強交渉技術を披露!『逆転交渉術』試し読み①
※画像はAmazonにリンクしています。
元FBIエージェントが極秘テクニックを余すところなく語った『逆転交渉術――まずは「ノー」を引き出せ』。20年以上にわたる人質交渉で培ってきた技術は、交渉術の本場ハーバード大学の教授も驚かせました。ここでは、その一端をご紹介します。
***
わたしは怖じけづいていた。
FBIに20年以上も身をおいて、うち15年はニューヨークやフィリピン、中東で人質事件の交渉にあたってきたわたしは、業界の第一人者だった。FBIには常時1万人の捜査官がいるが、国際的誘拐を担当する首席交渉人はただひとりである。それがわたしだった。
しかし、これほど緊迫した、個人的な人質事件は経験がなかった。
「きみの息子を預かったよ、ヴォス。100万ドルよこさなければ、息子は死ぬ」
息を呑む。目をしばたたく。意識して心拍数を正常にもどそうと努める。
たしかに、こういった状況に立たされたことは過去にもある。多すぎるほどだ。命と引き換えに金。だが、それも今回とはわけがちがう。息子の命がかかっていたわけではない。100万ドルでもない。そしてこれまでの相手は、立派な学位をもち、長年のあいだ交渉を専門としてきた人々ではなかった。
なにしろ、わたしが相対していた人々は──すなわち交渉相手は、ハーバード・ロースクールの交渉学の教授たちだったのである。
わたしがハーバードへやって来たのは、ビジネス界のアプローチから何かを学べないだろうかと思い、短期の経営者向け交渉学講座を受けるためだった。視野をひろげたいFBIの人間としては、騒ぐことなくおとなしく、これを職務上のささやかな進展につなげることを期待していた。
ところが〈ハーバード交渉学研究プロジェクト〉の責任者であるロバート・ムヌーキンは、わたしが大学に来ていると聞きおよび、コーヒーでもどうかと研究室へ招いてくれた。ちょっと世間話でも、と教授は言った。
わたしは誇らしかった。同時に怯えてもいた。ムヌーキンは卓越した人物で、わたしも長きにわたり信奉してきた。ハーバード・ロースクールの教授というだけでなく、紛争解決の分野では重鎮であり、『悪魔との取り引き──交渉すべきとき、戦うべきとき』(未訳)の著者でもある。
はっきり言って、ムヌーキンがカンザスシティのパトロール警官あがりのわたしと交渉学を論じようなんて、不当なことに思われた。しかし、事態はさらに悪化した。ムヌーキンとわたしが腰をおろした直後、ドアが開いて、またべつのハーバード大学教授がはいってきたからだ。その人はガブリエラ・ブルームといい、国際交渉や武力衝突、テロ対策の専門家であり、イスラエル国家安全保障会議およびイスラエル国防軍の交渉担当を八年間務めた人物だった。あのタフで知られるイスラエル国防軍である。
タイミングをはかったかのように、ムヌーキンの秘書が現れてテーブルにテープレコーダーをおいた。ムヌーキンとブルームはわたしに微笑みかけた。
はめられたのだ。
「きみの息子を預かったよ、ヴォス。100万ドルよこさなければ、息子は死ぬ」ムヌーキンは笑顔で言った。「わたしは誘拐犯だ。きみならどうする?」
一瞬のパニックに襲われたものの、想定内のことだった。これはけっして変わることがない。人命のための交渉を20年もつづけてもなお、恐怖は感じるものである。ロールプレイング中でも同じだ。
わたしは自分を落ち着かせた。たしかに、相手は正真正銘の大物であり、対するわたしは元パトロール警官のFBI捜査官にすぎない。もちろん天才でもない。けれど、わたしがこの部屋にいるのは理由がある。長い年月をかけ、技術や戦術や、人間同士の交流への包括的なアプローチを習得してきたが、それは人命を救う力となるだけでなく、いまになって思い返すなら、わたし自身の人生をも変貌させようとしていた。長年の交渉経験が、カスタマーサービスとの接し方から子育ての流儀まで、あらゆるものごとにすっかりしみこんでいた。
「さあ。金をもってくるんだ、さもないといますぐ息子の喉をかっ切るぞ」ムヌーキンは言った。
いらだたしげに。
わたしはのっそりとムヌーキンに視線を投げ、じっと見つめた。そして微笑んだ。
「どうしたらわたしにそんなことができるというのですか?」
ムヌーキンは息を止めた。その表情には、追いこんだ相手が反撃に転じようとするのを面白がるような、かすかな哀れみが浮かんだ。まるで双方がルールの異なる別のゲームをしているかのようだった。
ムヌーキンは落ち着きを取りもどし、まだゲームの途中であることをわたしに思い出させるように、眉をつりあげて見せた。
「つまり、わたしが息子さんを殺しても構わないのかね、ミスター・ヴォス」
「すみませんが、ロバート、どうしたら、生きているとわかるのですか」わたしは言った。詫びのことばと相手のファーストネームを使い、会話にあたたかみを添えることで、わたしを脅迫する最初の一手を攪乱しようとした。「ほんとうに申し訳ないのですが、息子が生きていることがわからないのに、どうしたらいますぐ金を渡せるというのでしょう、しかも100万ドルも」
これほどの傑物が、いかにも愚直な反応に面喰らっているというのは、なかなかの見ものだった。そうはいってもこちらの打った手は、けっして愚かなものではなかった。わたしはFBIにおける最強の交渉技術のひとつを採りいれていた。すなわち、自由回答式の質問である。
この戦術は、わたしのコンサルタント会社〈ザ・ブラック・スワン・グループ〉の民間部門において数年かけて発展させ、現在では〈狙いを定めた質問〉と呼んでいる。返答はできるが、決まった答えがない質問だ。これを使うと時間が稼げる。相手は自分が主導権を握っている──結論も力もわが手にある──と錯覚し、しかもこの質問のせいでどれほどの制約を受けるのか、まったく気づかない。
案の定、ムヌーキンはまごつきだした。いまや論点は、息子を殺害するという脅迫にわたしがどう答えるかという点から、金を得るまでの段取りという課題に自分がどう対処するかという点へ移っていた。わたしの問題を、教授がどのように解決するかである。わたしはどんな脅迫や要求に対しても、「どうしたら金を渡せるのか」、「どうしたら息子が生きているとわかるのか」と、質問しつづけた。
そんなやり取りを三分間つづけたところで、ガブリエラ・ブルームが口をはさんだ。
「やられっぱなしはだめですよ」ブルームはムヌーキンに言った。
「じゃ、きみがやってみるんだな」ムヌーキンは両手をあげてみせた。
ブルームはすぐに取りかかった。何年も中東にいたとあって、いっそう手強かった。しかし、やはり威圧的なやり方をつづけたため、結局はわたしから同じ質問を食らうだけだった。
ふたたびムヌーキンが加わったが、まるで進歩はなかった。その顔は焦りから赤く染まった。いらだっているせいで、頭がうまく働いていないのがわかる。
「さあ、もういいですね、ボブ。ここまでにしましょう」わたしは哀れなムヌーキンを救ってやることにした。
ムヌーキンはうなずいた。わたしの息子は生き延びたようだ。
「なるほど」ムヌーキンは言った。「FBIには、わたしたちが学ぶべき何かがあるのかもしれないな」
わたしはハーバードの高名な大人物ふたりにも屈しなかった。それどころか、一流中の一流を相手にしながら出し抜いたのだった。
とはいえ、これはただのまぐれ当たりだったのだろうか。30年以上のあいだ、ハーバードは交渉の理論と実践にかけては世界の中心だった。一方で、FBIで使われていた技術についてわたしが知っていたのは、それが機能するという事実だけだ。わたしが在籍していた20年のあいだに、FBIはひとつのシステムを作りあげ、それを適用したほとんどの誘拐事件をぶじに解決してきた。だが、一般理論というものはもっていなかった。
わたしたちの技術とは、経験にもとづく学習の産物だった。現場の捜査員たちが、重大な局面で交渉にあたり、何が成功して何が失敗したのかという体験談を共有しあうところから編み出されてきた。日々技術を使いながら磨いていくのだから、知的なプロセスというよりくり返し作業だ。しかも切迫していた。わたしたちのツールは、必ず機能しなくてはならなかった。さもなくば、だれかが死ぬからだ。
しかし、なぜそれが機能したのだろう? その疑問が、わたしをハーバードへ、ムヌーキンとブルームの研究室へと引き寄せた。自分のせまい世界の外では、自信がなかったのだ。そして何よりも、自分の知見をはっきりとことばにし、教授たちの深い知識と組み合わせる方法を学ぶことで、それを整理し、体系づけ、拡張したかったのである。
たしかにわたしたちの技術は、金目当ての犯人や麻薬の売人、テロリスト、凶悪殺人犯には、まちがいなく有効だった。けれどわたしは思った。普通の人々に対してはどうなのだろう。
その技術が理論のうえでも大変な意義をもち、あらゆる場面で通用することを、わたしはまもなくハーバードの階段状の講堂で知ることになる。
わたしたちの交渉へのアプローチは、人生のあらゆる領域で、あらゆる対話のなかで、あらゆる関係のなかで、人々の交流を実りあるものにする鍵を握っていることが明らかになった。
本書では、それがどのように機能するかを述べている。
* * *
『逆転交渉術』(クリス・ヴォス、タール・ラズ、佐藤桂訳、46判並製、定価1800円)は早川書房より刊行中です。