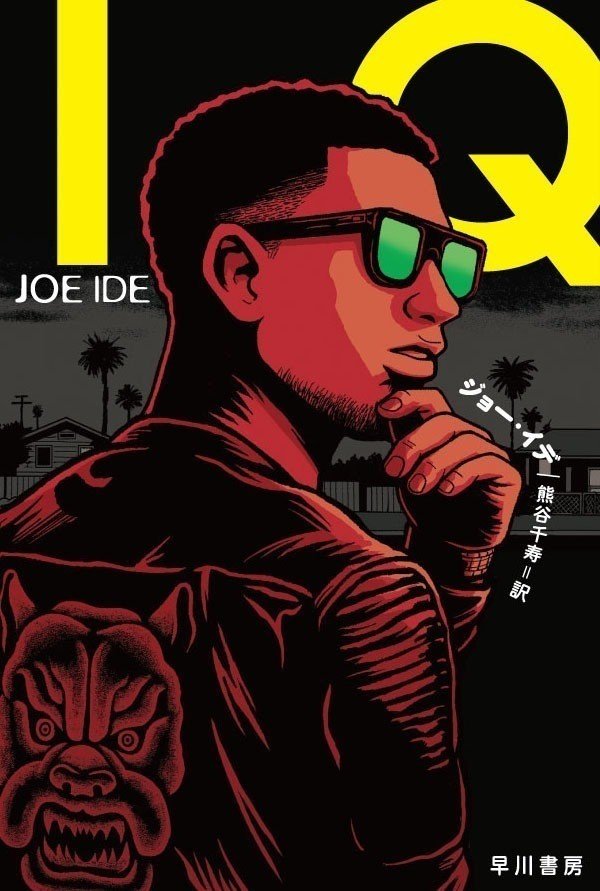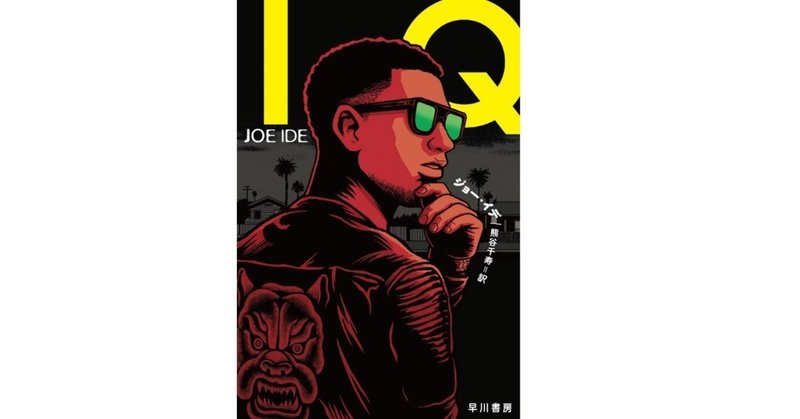
特集 ジョー・イデ『IQ』④――アイゼイアが遭遇した事件とは? 冒頭試し読み掲載(2/3)
好評発売中のミステリ『IQ』より、冒頭部分の試し読み第二弾を掲載します!
・試し読み第一弾はこちらから
ボイドはきのうと同じ場所にトラックを駐めた。やたらぴりぴりしているが、腹は決まっている。必要なのは、横のシートに置いてあるトカゲのような緑色のボウリング用バッグだけだ。ダクトテープ、ゴム手袋、熟れたトマトを透けて見えるくらい薄くスライスできる切れ味鋭い骨取り用ナイフ。そのほか、大きな青いスポンジと自家製のクロロフォルムを入れた水筒もバッグに入っている。
ボイドは〈F&Sマリーン〉という中国製船舶用品の卸業者のところで働いていた。セメント・ブロック造りの社屋は荒涼とした工業地区にあり、プロパンガス・タンクの貯蔵場と、レーザー・ワイヤーがフェンスの上でとぐろを巻いている名もない倉庫に挟まれている。ロサンゼルス・リバーがそばを流れ、広い緑色に縁取られた流域がイースト・ロングビーチを分断し、ロングビーチ・ハーバーに流れ出る。
〈F&S〉の店長、ニック・バンコウスキーはつんつんにとがった髪形で、アロハ・シャツを着ているが、筋肉が盛り上がった巨体で張り裂けそうだった。五年前、ニックはドラフト二巡目でサンディエゴ・チャージャーズの指名を受けた。トレーニング・キャンプも首尾よく終え、開幕戦のラインバッカー候補に上がっていたが、プレシーズン・ゲームがはじまる一週間前、チーム・バスから降りたときに前十字靭帯をやってしまった。
「おれはそこまで行ったんだ」ニックは最初の六本パック・ビールを飲んだあと、よくそういったものだ。「そこまで行ったんだ。ロッカーももらった。名前の入ったユニフォームももらった。おれはくされチームに入った。おれはくされチームに入ったんだ」
ニックはくさい仕事をぜんぶボイドにやらせた。小汚いトイレの糞詰まりを直させたり、フォークリフトのチェーンに油を差させたり、駐車場のビールの空き缶や使用済みコンドームを拾わせたり、連動スイッチ、六角ボルト、ピストン・ピン、クランク軸受けなど、何千もある部品の一覧表をつくらせたりだ。ボイドは愚痴をこぼすが、キレたりはしない。ニックにボウリング・チームから追い出されたときでさえも。「おまえを切らないといけなくなったんだ、ボイド」ニックはいった。「ロンが休暇から戻ってきた。あいつのアベレージは、いくらだっけ、百七十五か? おまえは調子がいい夜でもめったに百を超えない」
「マクシーンは?」ボイドはいった。「あいつのスコアはおれより悪いよ」
「まあ、たしかに、スコア的にはそうだが、あの子にはなかなかいいオッパイがついてる。士気の高揚に役立つ」
「でも、おれもやりたいんだ」
ニックはボイドの肩をぽんと叩いた。そんなことをされたのははじめてだった。「気持ちはわかるが、近々トーナメントがあるし、おまえだって負けたくないだろ? どうだ、ボイド? チームのために耐えてくれねえか? みんな恩に着るんだが、どうだ?」
リーグ・トーナメントの夜、ニックはしばらく事務所に残り、バドワイザーを何本か飲んでからボウリング場に向かった。駐車場に行き、アルティマに乗り込もうとしたとき、ボイドは漫画のネコのように背後から忍び寄り、南京袋に包んだ重さ三キロの錨で殴った。
「どうだ、ニック、チームのために耐えてくれねえか?」そういいながら、ボイドは何度も打ち付けた。
〈F&S〉の者はみな、人ちがいで襲われたか、腹を立てた夫の仕業だと思った。ニックがボウリング場にいる人妻とやりまくっていたのは周知の事実だった。ボイドに疑いの目を向ける者はいなかった。変わり者で頭の発育が少し遅れているが、人を傷つけたりはしないと。マクシーンが病院に見舞いに行った。袋に入れられた生焼きのハンバーガーみたいな姿になっていて、マクシーンが誰かも覚えていないらしい。ボイドも見舞いの(ゲット・ウェル)カードに名前を寄せた。
チャイムが鳴った。ボイドは心臓が飛び出るほど驚き、首を伸ばして少女を探した。どこだ、カーメラ? どこにいるんだ? 早く来るんだ、早く。さあ、カーメラ、来いよ。
カーメラは数人の友だちと一緒だった。丈の短いデニム・スカートと白いトップスという格好で、髪は長い三つ編みにしていた。ボイドはほっとした。髪形を変えていたらどうしようと思っていた。カーメラはぐずぐずテキスト・メッセージを送ったり、届いたテキストを読みながら笑ったり、それを友だちに見せてまた笑い、もう一通送ってまた笑っている。
「早く早く!」ボイドは叫んだ。「何をしてるんだ? とっとと家に帰れよ。まったく、帰れよ」カーメラがついに友だちから離れ、バイバイと手を振ると、通りに向かって歩いてきた。「ようし」ボイドはいった。「いいぞ」
アイゼイアはハーストンに住んでいる。イースト・ロングビーチ西端の小さな地区で、ロサンゼルス・リバーから車で二分、州間高速道路710号線から二分半の距離だ。アイゼイアはアナハイム・ストリートに入り、スヌープ・ドッグが『ザ・クロニック』でラップに乗せて歌っていた界隈を抜けた。このあたりで有名なものといえば、そのラップくらいだ。ストリップ・モール、酒屋、車の修理工場、美容院、格安の歯科医院、草の生えた空き地からなる街区(ブロック)ばかり。
「まじめな話よ、アイゼイア」デロンダがいった。「あたしはどうしても社会での立ち位置を変えたいの。文化環境を変えたい。住所を変えたいの」
デロンダは十八のとき、カルバー・シティーの〈ビッグ・ミーティー・バーガー(BMB)〉レストラン主催の〝ミス〈ビッグ・ミーティー・バーガー〉〟コンテストで優勝した。チャンネル5のテレビ・レポーターがいて、朝の番組で七秒間だけテレビ画面に映った。デロンダの名前と写真が《ロングビーチ・プレステレグラム》に載ると、人々がプラスチックのティアラと、赤と金色の〝ビッグ・ミーティー・バーガー〟のたすきを見に来た。
KHOPでインタビューも受けた。その巨大な尻を健康的に保つために何か特別なことをしてるのか、自然にそこまで育ったのか、それとも努力したのか、最後に盛ったのはいつか、とDJに訊かれた。この一連の経験のハイライトは、実際の写真撮影と、そのときの写真が〈BMB〉の広告に使われたことだった。広告写真には、肉汁が滴り落ちる巨大な三段重ねバーガーが写っている。デロンダが肩越しに振り返り、磨き上げられたマホガニーのようなぴかぴかの頬で愛想よくにっこりほほ笑んでいる。蛍光ピンクのビキニのあたりまでの写真だ。キャプションにはこうある──
〈ビッグ・ミーティー・バーガー〉
LAでいちばんジューシー
きっと食べたくなる
当時、デロンダは今しかないと思った。ここからはじまるのだと。誰かがあたしに気付き、カリスマ性と可能性を感じとるに決まってると思ったが、誰も連絡してこない。あれ以来、インタビューも新聞記事もなく、数カ月後には〈BMB〉が広告に起用する女を変えた。デロンダは希望を保ち続けた。きっと何かが起きる。起きないわけがない。セレブになるのはあたしの夢、運命だ。理由はないけど、今やっていることを続けてもいい、続けるほうがいいとさえ思っていた。髪のセットとネイルをきれいにやってもらい、ノーナたちと遊び回り、『ジャージー・ショア』や『ザ・リアル・ハウスワイブズ・オブ・アトランタ』や『バッド・ガールズ』や『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』や『ザ・リアル・ハウスワイブズ・オブ・オレンジ・カウンティー』や『ザ・バチェラレット』を見続けた。その帳尻合わせに、たすきとティアラだけという格好で〈キャンディー・ケイン〉のストリップ・ショーに出た。〈メトロ・トランジット〉の保線係を二十年務めている父親には、人生を無駄にすり減らしたりしないで別の道を探したらどうだといわれたが、デロンダはますますかたくなになり、白熱の稲妻が空を切り裂き、デロンダを大爆発させるときを待ち続ける覚悟を固めた。
「この界隈から抜け出たくないの?」デロンダがいった。
「さあな」アイゼイアはいった。「出てもいい」
「出てもいい? 噓でしょ、いかれてる。だってさ、あたしにあんたくらいのプロフィールがあれば、今ごろはブランドになってるのに」
アイゼイアはアナハイム・ストリートからキンボールに折れた。
「あたしの家の方向じゃないけど」デロンダがいった。
「ボーモントの店に寄っていかないといけない」アイゼイアはいった。〈六時‐十時半(シックス・トゥ・テン・サーティ)〉という街角の小さな店だ。冷えたビールから電子レンジで温めるブリトーからピニャータから『スカーフェイス』のポスターまで、雑多なものを売っている。
「変わらないものはないっていうでしょ?」デロンダがいった。「でも、どこが? 変化なんてどこにもないじゃない」
「物事は変わっても、同じままともいえる」アイゼイアはいった。
ふたりはカプリというセクション8のアパートメントにやってきた。住宅都市開発省(HUD)の規則では、そこの居住要件は、銀行口座残高、持ち株の明細、保有する不動産の総額が同地域の平均資産額の五十パーセントである四万ドル前後を超えていないことだ。長い空室待ちのリストがある。
〈イースト・サイド・スレーニョス・ロコ13〉の連中が入り口前の草地でたむろしている。彼らが入念に選んだ場所だ。シンダーブロックの低い壁で身を隠せるし、大きな葉をつけているバナナの木で拳銃も見えにくい。彼らのメンバーの多くは拳銃所持で郡刑務所に入っている。大半のメンバーは十代(ティーンズ)だが、紛れもない筋金入りの殺し屋だ。今日はみんな〝制服〟姿だ。バギーパンツ、特大サイズのTシャツかフットボール・ジャージー、そして、赤い色の小物。リストバンド、帽子、ポケットからはみ出している旗。赤は連中の色だ。
「あれ見て」デロンダがいい、小便にも似た〈ミラー〉を四十オンスボトルのまま飲んでいるやつ(ロ コ)を顎先で示した。「〝ロコ4ライフ〟(死ぬまでロコ)なんて〝墨〟を額のあちこちに入れたりして、どこをどう見てもいかれた犯罪者よね?」
〈ロコ〉の連中はアイゼイアが何者かは知っているが、彼らはギャングのハンドサインを掲げると、それがルールだといわんばかりに悪態をついてきた。スキンヘッドにヘアネットをつけているヒスパニック系の若者が、大げさにうなずいている。「ここはもうてめえらのシマじゃねえぞ、おい(エセイ)」その男がいった。「失せろ」アイゼイアは恐れも見下しもせず、ただ男を見た。アイゼイアは筋金入りのギャング(OG)たちと育ったがこの手のガキは気にもしていない。〈ロコ〉でなければカモだ。
アイゼイアの携帯電話が鳴った。着信番号を見て、ためらった。ラジオから流れてくるオールディーズのようなやつ。別の時、別の場所、その当時の自分を呼び起こさせる。ドッドソンの声と口調が、胸の奥底で黒く焦げたごたまぜの記憶を揺り動かした。前回、話をしたのはモジークの葬式のときだったが、口の中の焦げた味が消えるまで一、二日かかった。
「誰なの?」デロンダがいった。「女からなんでしょ?」
アイゼイアはこのまま留守番電話に応答させようかと思ったが、ドッドソンはほしいものがあれば、いつまでも電話してくるし、家に押しかけてくるかもしれない。アイゼイアはスピーカー・モードにした。「おい」彼はいった。
「調子はどうだ、アイゼイア?」ドッドソンがいった。「えらいご無沙汰だな。モジークを永眠の床につかせたときから、顔を見てないけどよ。むちゃくちゃ悲しい日だったな? あれだけの悪党だから、ずっと喧嘩沙汰で死ぬと思ってたら、どうなったよ? サンタ・アニタで三連単を当てたあと、ちょっと草(ウィード)を買いにラファエルに戻ろうとしたら、アムトラックの列車に轢かれるなんてよ。それでわかるだろ。幸運はいつだってカネに勝る。幸運があれば、カネは勝手にやって来る」
デロンダが天を仰ぎ、いった。「ええ、噓、ドッドソンなの?」
「ああ、おれはフアネル・ドッドソンだが、おまえは声色からすると、デロンダだな」
「ムショにいるんじゃなかったの?」
「ムショにいるいわれはねえ。犯罪に手を染めていたのは昔の話だ。今じゃれっきとしたビジネスマンだが、おまえの知ったことじゃねえ。惨めたらしいてめえのありさまがしっかり見えてるなら、〈キャンディー・ケイン〉でオッパイ拍手なんかしてねえだろうによ」
「そっちはまだ車のトランクに詰め込んでる手垢にまみれた偽物のグッチ・ハンドバッグを売ってんの?」
「いや、おまえの手垢にまみれたプッシーみたいにただでくれてやるのさ」
悪口の応酬に十分間も付き合える気分でもなく、アイゼイアはいった。「何かあったのか、ドッドソン?」
「仕事(ケース)があるってわけよ」ドッドソンがいった。「困ってる人を助けて、ひょっとしたら命も救えるかもしれねえ」
「へえ、そうなのか?」アイゼイアはいったそばから後悔した。ばかにしているような印象を与えるのに、自分が抑えきれなかった。ドッドソンがこらえているのがわかる。ばかみてえにでかい脳みそのくそ生意気な野郎めとののしりたいのだろうが。
「クライアントが話をしたいってよ」ドッドソンがいった。「おまえのクライアントとはちがって、その人はカネを持ってる。バトリス・コールマンなんかは店で買ってきたブルーベリー・マフィンで代金を払ったそうじゃねえか」
「別の仕事をはじめる時間はない」アイゼイアはいった。
「どこかで会って、細かい話をしようぜ」
「いったとおり、時間がない」
「時間をざっくり割いてくれってんじゃねえ。ほんの五分ばかり話を聞いてほしいだけだ」
「もう行かないと」
「行く? どこへさ?」
「あんたから逃げるってこと」デロンダがいった。「あんたに用はないってことよ、おばかさん」
「またな」アイゼイアはいった。電話を切る間際、くたばれアイゼイア、というドッドソンの声が聞こえた。
白いピックアップ・トラックが学校の向かいの赤線の前に駐まっていた。こいつは〝赤線の前駐車禁止〟の表示が見えないのかと思いながら、マルティネス巡査はそのピックアップのうしろにパトロール・カーを停めた。電話をしているだけならいいのだが、と思った。ドラッグでハイだったり、酔っぱらっていたり、マスをかいていたりするなよ。あと二十分でシフトが終わるというのに、違反報告を作成して、レッカー車を待つことになれば、あと一時間は帰れない。今日は三十一歳の誕生日だ。子供たちは祖母の家に預けてあるし、グラシエラはミディアム・レアのリブアイ、ガーリック入りマッシュポテト、そして、面積がサンドイッチ用ジップロックくらいしかない透け透けのネグリジェを用意して、家で待っている。
男の様子を見るまで、マルティネスは胸を膨らませていた。男はそわそわしていて、ブタのように汗をかき、喉が渇いて死にそうなときに四リットル容器入りのレモネードを見るような目つきで、校舎を見つめている。〝怪しいことなどひとつもない〟とマルティネスは自分にいい聞かせた。〝うわ、これは体臭か?〟
「こんちは、お巡りさん」男がいった。
「ここで何をしているのですか?」マルティネスはいった。男はチャーリー・ブラウンのようなでかい頭を動かさず、まるで答えは向こうのツツジの茂みにあるとでも思っているかのように、まっすぐ前を見つめている。「あの、ここで何をしているのかと訊いたのですが」マルティネスはいった。
「何もしちゃいない」男がいった。「ただこうして座ってる。法律は破ってない」朝露を低速で撮影したかのように、男の顔に新しい汗の粒が浮き出ている。
「お子さんがこの学校に通っているのですか?」マルティネスはいった。
「いやいや、子供はいないよ」危うく弾に当たりそうだったかのような口調で、男がいった。
マルティネスは顔を前に出してウインドウをのぞき、素早くトラックの中に目を走らせ、一瞬だけボウリング・バッグに視線を止めてから男に戻した。「免許証、保険証、登録証を見せてください」彼はいった。男がいわれたものを取り出し、差し出した。「未履行の逮捕状はありますか?」マルティネスはいった。
「おれが何をしてたっていうんだよ、お巡りさんよ? 何もしてはいねえだろ」
「未履行の逮捕状は?」
「ねえ、ねえよ」
「キーをダッシュボードに置いて、車内から出ないでください」
「何もしてねえだろうが。マジかよ、座ってるだけだぜ」
マルティネスはボイドの免許証を受け取り、パトロール・カーに戻った。このばかのせいで帰宅が遅くなったら、思いつくかぎりの違反をつけてやる。
ボイドは両手でハンドルを握り、檻に閉じこめられて怒り狂ったチンパンジーのように揺すりながら、「ちくしょう!」とわめいていた。ぜんぶ行き当たりばったりだったこれまでとはちがって、今度は何もかも順調だったのに。
はじめて少女を襲ったとき、ボイドはポートランドに住んでいた。ヘイデン・アイランド・マリーナのボート用桟橋のあたりで釣りをしていたとき、水玉模様の水着とライムグリーンのサングラスを身に付けた小さな子が女子トイレに入ろうとしているのに気付いた。その子は大声で泣き叫び、殴っても黙らなかった。二度目はハロウィーンの夜だった。ボイドは愛想よく見せようと、大きな耳がついたウサギのお面をつけていた。ボイドが選んだ子は杖を持ち、判事のような黒い長衣(ローブ)を着ていた。ボイドは通りを歩いていた少女をつかみ、生け垣の中に引きずっていった。少女はトラのように抵抗し、二度噛み付いてきたので、やはり殴るしかなかった。三度目は少女を学校から家までつけていき、玄関から強引に家に入り込んだ。少女を寝室まで追いかけていったところで、少女の兄が起きてしまった。そいつは〈ワイルド・ビルズ・ホテル・アンド・カジノ〉で夜勤の警備員として働いていた。そして、妹にスペリング大会で勝ち取ったトロフィーで何度も殴らせようと、ボイドの手首をねじり上げて無理やり膝を折らせた。刑務所病院に搬送されていたとき、ボイドは今度は計画を立てようと思った。
ボイドは強姦未遂で四十一カ月を喰らい、スネーク・リバー刑務所に入れられ、当然、性犯罪者として登録された。州から出る許可を仮保釈保護観察官に求め、カリフォルニアに着いたら報告しなければならなかったのだが、ボイドはどちらも怠った。今ごろボイドの名前がコンピューター画面に出てきているから、あの警官はボウリング・バッグの中身を調べるだろう。それで終わり。ゲーム・オーバーだ。黒人やメキシカンと一緒に刑務所に入れられて、誰にも罪状を悟られないように祈って耐え忍ばないといけない。なぜかはわからないが、人殺しは無事でも彼のような並みの連中は袋だたきにされるか、強姦される。ふつうは両方いっぺんにやられる。あんなのはごめんだ。二度と。
サイド・ミラーで、パトロール・カーのそばに立って無線機で話している警官の姿が見える。いやなことを聞いているのだと表情からわかる。ボイドは上体を動かさないように気をつけて手を伸ばし、ボウリング・バッグのジッパーを少しだけあけると、手を中に滑り込ませ、骨取り用ナイフの生温かい細い把手をつかんだ。
ボーモントはマーガレット・チョーを脇にすっぽり抱きかかえて、物置から出てきた。この韓国人コメディアンは赤いミニスカートと黒い網目のストッキングという格好だった。挑みかかるかのように両手を腰に当ててそっくり返り、ただのでぶ女だったころに尻のことでからかわれて、くたばれと怒鳴りつけたときのように唇を突き出している。店の正面に行くと、ボーモントはアイゼイアが雑誌棚の前で《LAタイムズ》を読んでいるのに気付いた。身じろぎひとつしないので、潮だまりにたたずんで獲物が泳いでくるのを待っているシラサギを思い出した。イースター・バスケットに入っている二個のハムみたいな尻をした軽そうな女が、冷蔵庫をのぞき込んでいる。
「ソーダを取ってもいい、アイゼイア?」デロンダがいった。
「好きなものを取ればいい」アイゼイアがいった。
養子にもらった娘でも抱くかのように、ボーモントはマーガレットに腕を回して立っていた。「どうだい、この子」彼はいった。「おれが組み立ててやったんだ」
「何なの、その子?」デロンダがいった。
「アジア系の女にはまってるとは知らなかったな」ボーモントはそういった。どうしてそんなものがほしくなったのか、アイゼイアが教えてくれないものかと思ったが、教えなかった。
デロンダとマーガレットがにらみ合っていた。「誰かわかった」デロンダがいった。「〈マンダリン・パレス〉のウエイトレスでしょ」
アイゼイアは等身大パネルの広告を〈イーベイ〉で見つけた。売り手はどんな人でもどんなものでもつくりますと謳っていた。人間、ペット、植物、風景、体の一部。マーガレット・チョーだってつくれる。値段は十八ドル、加えてデロンダがカウンターに載せたドクター・ペッパー、レッド・バインズ、ピーナッツ・バター・チーズ・クラッカーで四ドル五十セント。
アイゼイアはズボンの前ポケットから束にした札を取り出し、何枚か取り分けた。自分でオーダーしてもよかったのだが、UPS(注:アメリカの運送会社)が玄関に置いていったら、誰かが盗んでいく。UPSの置いていった荷物を盗むことしかしないやつがいることを、彼は知っていた。
「手間をかけさせてすまない」アイゼイアはいった。
「手間なんかなかったよ」ボーモントがいった。「お役に立ててよかった」
アイゼイアはボーモントの前では気まずさを感じた。アイゼイアが天才少年だったころも、兄のマーカスが死んだあとに起こった抗争が街を恐怖に陥れたときもボーモントは知っていて、暮らしを立て直したアイゼイアが犯罪者以外の誰からも称賛される一人前の男になるところも見守ってきた。ボーモントもアイゼイアのファンのひとりだが、アイゼイアは自分の過去や恥部を知られているのがいやだった。
「元気そうだな、アイゼイア」ボーモントがいった。「よかった」
「ありがとう、ボーモント。また来るよ」
アイゼイアはマーガレットを受け取り、出入り口に向かった。ボーモントは訊かずにはいられなかったらしい。「そんなもの、何に使うんだ?」ボーモントがいった。
「プレゼントだ」アイゼイアはいった。
ボイドは自分のアパートメントに車で戻っているとき、その子がキンボールを歩いているところに出くわした。好みからすると少しばかり年上だが、カーメラより痩せてるし、髪は背中の真ん中くらいまで伸びている。近くには誰もいない。この暑さでみんな家に引っ込んでいる。学校の前にいたときはもう終わりだと思ったが、例の警官は、カンボジア・タウンのあたりで発砲事件が発生して警官がひとり倒れたとの連絡を無線で受けた。カーメラを逃すのは悔しいが、カーメラの身に何かあれば、誰がやったのかあの警官にはわかる。
痩せた少女は携帯電話でぺちゃくちゃ喋っている。ボイドがボウリング・バッグのジッパーを最後まで引くと、バッグの口があんぐりとあいた。
アイゼイアは店を出て、路肩に駐めていたアウディに向かって歩き出したが立ち止まり、少女が前を歩き過ぎるのを待った。小学校の高学年くらいで、小枝のように細くて、この暑さなど気にもしないで、極細のジーンズ、ダウンベスト、アグのブーツという格好だ。この年ごろの子はいちばんのお気に入りをすり切れるまで着る。ピンクの携帯電話で話していて、笑いながらこういった。「ええ、マジで? ラモンはあの子が好きでもないのに」
少女は話を一瞬たりとも止めずにマーガレットのパネルにほほ笑み、そのまま歩き続けた。アイゼイアがアウディのきしるドアをあけたとき、ピックアップ・トラックが歩くような速度でのろのろと通り過ぎた。十年ほど前に製造された白のシルバラードで、サイドの青いレーシング・ストライプが禿げかけていて、クォーター・パネルが大きくへこんでいる。エンジンがつっかえるような音を立てている。燃料噴射装置だな、とアイゼイアは思った。運転している男はロゴのついた帽子をかぶっていた。前歯が一本抜けていて、日焼けした顔がてかっている。何かをじっと見ている。何が起きようとしているのか、アイゼイアは予見しておくべきだった。なぜ男はこれほどのろのろと走っているのか、アイゼイアもデロンダも見ていないのなら、誰を見ているのか? だが、このときはすべて見逃していた。その〈マンダリン・パレス〉のウエイトレスにヤラせてもらうのかとか、〝ムー・シュー〟って中国語でイヌの意味なのかとデロンダに話しかけられているあいだ、カネになる仕事がどうしてもほしいし、どうやってマーガレットのパネルを後部シートに入れようかと考えていたから、気が散っていた。
アイゼイアが車から出て、デロンダが乗り込んだとき、あるにおいがして、その場で凍りついた。クロロフォルムは無臭だとどこかで読んだことがあるが、実はにおいがある。ほんのり甘い香りが混じったアセトンのようなにおいだ。つっかえがちなエンジンが全開で動く音が聞こえて、アイゼイアは右に目を向けた。さっきのピックアップが猛スピードで走り出していた。角を鋭角に曲がるとき、リアタイヤが勢いよく路肩を乗り越えた。丸くて光を反射するものが後部バンパーに貼ってある。さっきの少女が消えていた。ピンク色の携帯電話だけが歩道に残されている。
「まずい」アイゼイアはいった。
三十秒後、アウディもミシュラン・タイヤをきしらせ、ゴムの煙を上げ、尻を振って角を高速で曲がっていた。アイゼイアが車の向きを直し、アクセルを踏みしめると、三百四十馬力のエンジンが巨大スズメバチの巣のようにブーンとうなった。デロンダがシートに押し付けられ、水色の爪でドアの枠をつかみ、ダッシュボードに食い込ませた。「何してんのよ、アイゼイア?」
ボイドはうまくやり遂げたことがまだ信じられず、何も考えずに運転していた。アドレナリンが血管にどっと流れ込み、息切れした鳥のような音が抜けた歯の隙間から漏れ、心臓がどくどくと高鳴っていたせいで、トラックがでかい穴を踏んでバウンドしたのも気付かなかった。少女は気を失って、うしろのエクストラ・キャブのシートにだらりと横たわり、シートによだれを垂らしている。あのクロロフォルムはマジで効きがいい。少女は電話でのお喋りに夢中で、ボイドがうしろから近づいていっても気付かなかった。ボイドは片手で少女の顔にスポンジを押し付け、もう一方の手を腰に回した。少女が足をばたつかせ、細い腕を振り回していたが、エクストラ・キャブに乗せたころには、体から力がすっかり抜けていた。誰にも見られていない。ブロックを走ってきたとき、車の中に首を突っ込んでいた黒人と、そばに立って話をしていた女がいたが、こっちに目を留めてはいないだろう。今では機嫌も良くなり、ボイドはシートで体を上下に弾ませたり、指をハンドルに打ち付けて笑ったりした。「つかまえたぜ」彼は叫んだ。「嘘だろ、つかまえたぜ!」
本noteでは『IQ』を特集中。今後の更新をどうぞお楽しみに!
【書誌情報】
タイトル:『IQ』
原題:IQ
著者:ジョー・イデ
訳者:熊谷千寿
本体価格 : 1,060円+税/発売中
ISBN : 9784151834516
レーベル名 : ハヤカワ・ミステリ文庫