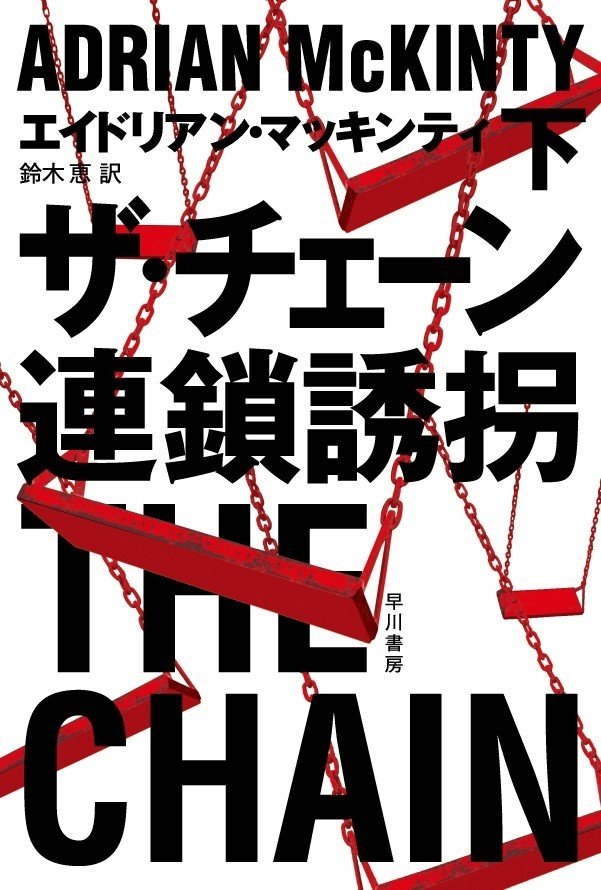娘を返してほしければ、他人の子供を誘拐しろ――傑作小説『ザ・チェーン 連鎖誘拐』衝撃の冒頭部を掲載
現在好評発売中の〝誘拐〟スリラー小説『ザ・チェーン 連鎖誘拐』より、激烈なインパクトの冒頭部分を公開いたします。
1
木曜日、午前七時五十五分
バス停に腰をおろして自分のインスタグラムの〝いいね〟をチェックしていたので、銃を持った男に気づいたときには、男はもうほとんどカイリーの横まで来ている。
学校鞄を放り出して湿地へ逃げられるかもしれない。こっちは十三歳のすばしこい女の子だし、プラム島の沼沢地や流砂なら残らず知っている。朝の海霧も出ているし、男は太っていて鈍くさそうだ。追いかけてくれば人目を引くし、八時のスクールバスが来る前には絶対に諦めるだろう。
それだけのことが一秒のあいだに頭を駆けぬける。
男はもう真ん前に立っている。黒いスキーマスクをかぶり、銃をカイリーの胸に向けている。カイリーははっと息を呑んで携帯を落っことす。どう考えても冗談や悪ふざけではない。もう十一月なのだから。ハロウィーン(十月三十一日)は一週間前に終わっている。
「これが何かわかるか?」男は訊く。
「銃」とカイリーは言う。
「きみの胸に向けられた銃だ。叫んだり、暴れたり、逃げようとしたりしたら、撃つぞ。わかったか?」
カイリーはうなずく。
「ようし。じゃ、おとなしくしてるんだ。この目隠しをつけろ。きみのお母さんがこれから二十四時間以内にすることが、きみの生死を分けることになる。きみを解放するときに……解放するとしたら、こちらの顔を憶えられていちゃ困るからね」
カイリーは震えながら、パッドのはいった伸縮性のあるその目隠しをつける。
一台の車が前に停まり、ドアがあく。
「乗るんだ。頭をぶつけないようにして」男は言う。
カイリーは手探りで車に乗りこむ。ドアが閉まる。心が千々に乱れる。乗ってはいけないことはわかっている。女の子はみんなそうやっていなくなる。そうやって毎日いなくなっている。乗ってしまったらおしまいだ。乗ってしまったら、永遠に見つからない。乗っちゃだめ、身を翻して逃げなきゃ。逃げろ、逃げろ。
もう遅い。
「シートベルトを締めてやって」運転席から女の声がする。
カイリーは目隠しをしたまま泣きだす。
男が後部席のカイリーの横に乗りこんできて、カイリーにシートベルトを装着する。
「頼むからおとなしくしててくれよ。痛い目に遭わせたくはないんだ」
「何かのまちがいだよこれ」とカイリーは言う。「ママはお金なんか持ってない。新しい仕事はまだ始めてないし──」
「黙らせて!」運転席の女がさえぎる。
「お金の問題じゃないんだ、カイリー」と男が言う。「とにかくしゃべらないで。いいね?」
車は砂と小石をばらばらと巻きあげて急発進し、猛然と加速してギアを上げていく。
プラム島橋を渡るのが音でわかり、スクールバスの喘息にかかったようなうなりとすれちがうのが聞こえて、カイリーは顔をしかめる。
「ゆっくり行け」と男が言う。
ドアが自動でロックされ、カイリーはチャンスを逃したことを悟る。シートベルトをはずし、ドアをあけて転がり出ることもできたのに。やみくもな恐怖が襲ってくる。「どうしてこんなことするの?」と泣き声で言う。
「なんと言ってやればいいんだ?」男は訊く。
「何も言わないで。静かにさせて」女は答える。
「カイリー、しゃべっちゃだめだ」男は言う。
車は猛スピードで走っている。たぶんニューベリーポートの近くのウォーター通りだろう。カイリーは意識的に深呼吸をする。学校の瞑想(マインドフルネス)の授業でカウンセラーがやってみせたように、吸って吐いて、吸って吐いてと。生きていたければ、あわてないで注意を凝らしていなくては。彼女は八年生の特別進級クラスにいる。みんなから頭がいいと言われ
ている。冷静になってまわりのことによく気をつけていて、チャンスが来たらそれを活かすべし。
あのオーストリアの子は無事だったし、クリーヴランドの子たちもそうだった。それに、十四歳のときに誘拐されたあのモルモン教徒の子がインタビューに答えるのも、《グッド・モーニング・アメリカ》で見た。あの子たちはみんな助かった。みんな運がよかった。でも、たぶん運だけじゃないだろう。
息が止まりそうな恐怖の波をまたひとつこらえる。
車がニューベリーポートの一号線の橋にさしかかる音がする。メリマック川を渡ってニューハンプシャー方面へ行こうとしているのだ。
「そんなにスピードを出すな」と男が低い声で言う。車は数分間ゆっくりと走るが、また徐々にスピードを上げはじめる。
カイリーは母親のことを考える。今朝は癌の先生に診てもらうためにボストンへ出かけている。かわいそうに、こんなことがあったら──
「ああ、まずい」運転している女が突然、おびえたように言う。
「どうした?」男が訊く。
「いま州境でパトロールカーが待ちかまえてた」
「だいじょうぶ、きみは制限速度で……ああ、やばい、ライトを点けて追いかけてくる」と男は言う。「停まれと言ってる。スピードを出しすぎたんだ! 停まらないと」
「わかってる」女は答える。
「だいじょうぶだよ。誰もまだこの車に盗難届なんか出しちゃいないさ。ボストンのあの横町に何週間もあったんだから」
「やばいのは車じゃなくて、その子。銃を貸して」
「何をするつもりだ?」
「あたしたちに何ができる?」
「言い逃れできるよ」男は言い張る。
「誘拐されて目隠しをされた子が後ろに乗ってるのに?」
「この子は何も言いやしないさ。そうだろ、カイリー?」
「うん。約束する」とカイリーは泣き声で言う。
「静かにさせといてよ。顔からそれをはずして、頭を低くして下を見させといて」女は言う。
「眼をぎゅっとつむってるんだ。声を出すなよ」と男は言い、目隠しを取って、カイリーの頭を押しさげる。
女は車を脇に寄せて停める。パトロールカーは後ろに停まったようだ。女はルームミラーで警官を見ているらしく、「ナンバーを記録簿に書きとめてる。きっと無線で問い合わせもしたはず」と言う。
「だいじょうぶ。きみが話せばうまくいくさ」
「こういうパトカーにはみんなドライブレコーダーがついてるんじゃなかった?」
「どうかな」
「警察はこの車を捜すかも。乗っていた三人を。車を納屋に隠さなくちゃいけない。もしかすると何年も」
「そうあわてるなって。あいつはスピード違反で切符を切ろうとしてるだけだ」
車からおりて近づいてくる州警察官のブーツの音が聞こえる。
女が運転席側の窓をおろす音がする。「まずい」とささやく。
警官の足音が近づいてきて、あけた窓の横で止まる。
「何か問題でもありました?」女が訊く。
「奥さん、どのくらいスピードを出してたかわかってます?」警官が訊く。
「いいえ」
「八十三キロですよ。ここは四十キロ制限のスクールゾーンです。標識を見落としたんでしょう」
「ええ。このあたりに学校があるなんて知りませんでした」
「標識があちこちにありますよ」
「ごめんなさい、ぜんぜん気づかなかった」
「免許証を見せてくだ……」警官は言いかけてやめる。カイリーは自分が見つめられているのがわかる。全身ががたがた震えている。
「すみません、お隣にいるのは娘さんですか?」警官は男に尋ねる。
「ええ」
「お嬢さん、すみませんが、顔を見せてもらえます?」
カイリーは顔を上げるが、眼は固くつむったままだ。まだ震えている。警官は何かがおかしいのに気づいている。一瞬の間があり、そのあいだに警官も、カイリーも、女も、男も、次に何をすべきか決断する。
女がうなり声をあげ、それから一発の銃声が轟く。
2
木曜日、午前八時三十五分
これは半年ごとの定期検診だということになっている。すべてが良好で、乳癌が再発していないのを確認するための検査だということに。だからカイリーには心配しないでと言ってある。体調はすごくいいし、経過はほぼまちがいなく順調だからと。
内心ではもちろんレイチェルは、順調ではないのかもしれないと気づいている。検診はもともと感謝祭(十一月の第四木曜日)の前の火曜日に予定されていたのだが、先週ラボで血液検査をしてもらったところ、その結果を見たリード医師から、予定を早めて今日来るように言われたのだ。朝一番に。カナダのノヴァスコシア出身のリード医師は、冷静で落ちついた気難しい女性で、あわてて大騒ぎをするような人ではない。
そのことは考えまいとしながら、レイチェルは州間高速九十五号線を南へ向かっている。
心配して何になる? 自分は何も知らないのだ。リード先生は感謝祭にカナダへ帰るつもりで、診察を早めたのかもしれない。
体調は悪くない。というより、この二年間でいちばんいい。ひと頃はまるで悪運に見込まれたような気がしたものだが。そんなことはみんなもう終わった。離婚は過去の話だ。
いまは哲学の講義の原稿を書いて、一月から始める新しい仕事の準備をしている。薬物療法で抜けた髪もほぼ元どおりになったし、体力もついて、体重も増えてきている。一年分の精神的負担はもう払いおえた。自分はあのてきぱきした有能な女に戻っている。仕事をふたつ掛け持ちしてマーティにロー・スクールを卒業させ、プラム島の家を手に入れた女に。
あたしはまだ三十五歳だ。人生はこれからだ。
レイチェルは縁起をかついで木製のものに触ろうと、ダッシュボードの緑色のところをぽんとたたく。でも、どうせプラスチックだろう。ボルボ二四〇の荷物スペースに溜めこまれたガラクタのなかには、古いオーク材の杖もあるのだが、それに手を伸ばしたばかりに手脚や命をなくしてはしょうがない。
携帯を見ると、時刻は八時三十六分。カイリーはバスをおりて、スチュアートと一緒に校庭をのんびり歩いている頃だろう。レイチェルは今朝ずっと言わずにいた他愛ないジョークをカイリーにメールする。〝考えられないもの(アンシンカブルな)をどうやって考える(シンクする)か?〟
一分たってもカイリーから返信がないので、答えを送る。〝氷山で〟
それでも返信なし。
〝わかった? 氷山で沈める(シンクする)〟とメールしてやる。
わざと無視しているのだろう。でも、スチュアートは絶対に笑っているはずだ。レイチェルはにやりとしながらそう思う。スチュアートはいつも彼女のくだらないジョークに笑ってくれる。
八時三十八分、道が渋滞してくる。
遅刻するのはいやだ。これまで遅れたことはない。州間高速道をおりて一号線で行くべきだろうか?
そういえば、カナダ人は別の日に感謝祭を祝うのだ、とレイチェルは思い出す。リード医師に呼ばれたのは、検査結果が思わしくなかったからだ。「だめだめ」と彼女はつぶやいて首を振る。もうそういうマイナス思考の悪循環に陥るつもりはない。自分は前へ進んでいる。かりにまだ病の王国へのパスポートを持っているとしても、そんなものに縛られたりはしない。それはもうウェイトレスの仕事や、自動車配車サービスUberの運転手
や、マーティの手管にはまることと併せて卒業した。
自分はいまようやく能力をフルに発揮している。やっと教師になったのだ。初回の講義のことを考える。ショーペンハウアーは万人には難しすぎるだろうか。冒頭でサルトルと〈ドゥマゴ〉のウェイトレスのジョークを──
携帯が鳴り、レイチェルはぎくりとする。
〝発信者不明〟と表示されている。
スピーカーフォンで電話に出る。「もしもし?」
「ふたつのことを肝に銘じておけ」とボイスチェンジャーでゆがめられた声が言う。「ひとつ。おまえは最初ではないし、断じて最後でもない。ふたつ。目的は金ではなく──〈チェーン〉だ」
何かのいたずらにちがいない、脳の一部はそう言っている。だがもっと深いところ、小脳のもっと大昔からある部分は、純然たる動物的恐怖としか言いようのない反応を示しはじめている。
「番号をおまちがえだと思いますが」と彼女はやんわり言う。
声はかまわず先を続ける。「五分後に、レイチェル、おまえに生涯でもっとも重要な電話がかかってくる。車を路肩に停める必要がある。落ちついている必要がある。詳細な指示があるはずだ。バッテリーが充分にあることと、指示を書きとめるためのペンと紙があることを確かめろ。簡単な指示だと言うつもりはない。これからの毎日はきわめて困難なものになるだろう。だが〈チェーン〉はおまえに、かならず最後までやり遂げさせるはずだ」
レイチェルは寒けを覚える。口の中に古い銅貨の味が広がる。頭がくらくらする。「警察に電話しますよ──」
「よせ。警察であれなんであれ、法執行機関には知らせるな。おまえならやれる、レイチェル。おまえがこれをぶち壊しにするような相手だと考えていたら、われわれはおまえを選んではいない。おまえに要求されることはいまは不可能に思えるかもしれないが、おまえの能力ならかならずできる」
冷たいものが背筋を走る。未来がちらりと垣間見える。恐るべき未来が、どうやらあと数分で姿を現わすようだ。
「誰なのあなた?」彼女は訊く。
「われわれが誰なのか、どんなことができるのか、頼むから知らないままでいてくれ」
通話が切れる。
発信者が誰なのかもう一度見てみるが、番号はやはり表示されない。でも、あの声は。機械的にわざとゆがめられ、自信たっぷりで、冷たく、傲慢だった。生涯でもっとも重要な電話というのはどういうことだろう? レイチェルはミラーで後方を確認すると、本当にもう一度電話がかかってきた場合に備えて、追い越し車線から真ん中の車線に移動する。
赤いセーターからほつれた糸を神経質につまんだとき、アイフォンがふたたび鳴る。
またしても発信者不明。
緑色の通話キーを押す。「もしもし?」
「レイチェル・オニール?」別の声が言う。女の声だ。ひどくぴりぴりしているように聞こえる。
〝いいえ〟と言いたくなる。実はまた旧姓を──レイチェル・クラインを──使いはじめているのだと言って、迫りくる凶事を逃れたくなるが、そんなことをしても無駄なのはわかっている。自分が何を言おうが何をしようが、最悪のことが起こったという知らせをこの女から告げられるのを、阻むことはできないのだ。
「ええ」とレイチェルは言う。
「申し訳ないけれど、あなたに悪い知らせがある。指示を書きとめる紙とペンはある?」
「何があったの?」いまや本当におびえて、彼女は訊く。
「娘さんを誘拐した」
3
木曜日、午前八時四十二分
空が落ちる。落ちてくる。息ができない。したくない。あたしの娘。まさか。そんなはずはない。誰もカイリーを連れていったりはしていない。この女の話し方は誘拐犯みたいには聞こえない。嘘だ。「カイリーなら学校にいます」とレイチェルは言う。
「いいえ。わたしが預かってる。誘拐した」
「そんなばかな……冗談でしょ」
「大真面目よ。バス停でさらったの。いま写真を送ってあげる」
目隠しをされて車の後部席に座っている少女の画像が、添付されて送られてくる。着ている黒のセーターと薄茶色のウールのコートは、今朝カイリーが家を出ていったときに着ていたのと同じものだし、そばかすだらけのとんがり鼻と、赤いメッシュのはいった茶色の髪も、たしかにカイリーだ。まちがいない。
気分が悪くなり、視野が揺らぐ。ハンドルから手を離す。警笛が次々に鳴らされるなか、ボルボは車線をそれていく。
女はまだしゃべっている。「取り乱さないで、わたしの言うことをよく聞いてちょうだい。何もかもわたしのやったとおりにやること。掟をすべて書きとめて、そこからはずれないこと。掟を破ったり、警察に電話したりしたら、あなたは責任を取らされるし、わたしも責任を取らされる。あなたの娘は殺され、うちの息子も殺される。だからわたしがこれから言うことを、すべて書きとめて」
レイチェルは眼をこする。頭の中に轟きが湧き起こり、大波がいまにも崩れ落ちてきそうになる。木っ端微塵にうち砕かれそうになる。この世で最悪のことが本当に、実際に起ころうとしている。いや、本当に起こったのだ。
「カイリーと話をさせてよ、この人でなし!」レイチェルはそうわめくと、ハンドルをつかんでボルボを立てなおし、十八輪の大型トレーラーを数センチの差でよける。それから最後の車線を横切って路肩まで行く。警笛と罵声を浴びながら、急停止してエンジンを切る。
「カイリーはいまのところ無事」
「警察に通報するよ!」レイチェルは叫ぶ。
「だめ、それはだめ。お願いだから落ちついて、レイチェル。あなたのことをすぐに冷静さを失うタイプだと思っていたら、わたしはあなたを選んではいない。徹底的に調べたの。
だからハーヴァードのことも、癌から回復したことも知っている。新しい仕事のことも。あなたは有能な人だから、これをめちゃくちゃにしたりはしないはず。だってめちゃくちゃにしたら、結果はものすごく単純。カイリーは死に、うちの息子も死ぬ。さあ、紙を用意して、これから言うことを書きとめて」
レイチェルはひとつ深呼吸をして、ハンドバッグから手帳をつかみ出す。「どうぞ」
「あなたはいま〈チェーン〉に組みこまれている。わたしたちどちらも。〈チェーン〉は自分を守ろうとする。だからまず、警察はだめ。警察にしゃべったら、〈チェーン〉を操っている人たちはそれに気づいて、わたしにカイリーを殺して別の標的を探せと指示してくるし、わたしもそうする。彼らには、あなたもあなたの家族もどうでもいい。大切なのは〈チェーン〉の安全だけ。わかった?」
「警察はだめ」レイチェルは呆然として言う。
「次は、使い捨て携帯。匿名の使い捨て携帯をたくさん買って、電話をかけるたびにひとつずつ使えるようにして。わたしがいまやっているみたいに。いい?」
「ええ」
「それから、Tor(トーア)のインターネット・ブラウザをダウンロードして。匿名性が高いから、普通のブラウザじゃのぞけない闇(ダーク)ウェブにアクセスできる。ちょっと危ないけれど、あなたならやれる。トーアで〈インフィニティプロジェクツ〉を探して。書きとめてる?」
「ええ」
「〈インフィニティプロジェクツ〉というのは、たんなる仮の名前だから、何も意味しない。でも、そのサイトにはビットコインの口座がある。トーアなら五、六カ所でビットコインをクレジットカードか電信送金で買える。〈インフィニティプロジェクツ〉の送金番号は2289744。メモして。お金はいったん送金されたら追跡できない。〈チェーン〉があなたに要求しているのは二万五千ドル」
「二万五千ドル? どうやってそんな大金──」
「わたしの知ったことじゃない。高利貸しに借りようが、ふたつめのローンを組もうが、請負殺人をやろうが、なんでもいい。とにかく工面して。お金を払ったら、前半は終了。後半はもっとたいへんよ」
「なに、後半って?」レイチェルは恐る恐る尋ねる。
「わたしはこう伝えることになってる。あなたは最初でもなければ最後でもない。あなたは〈チェーン〉の一部で、これが始まったのはずっと昔のこと。わたしがあなたの娘を誘拐したのは、そうすれば息子を解放してもらえるから。息子はわたしの知らない男女に誘拐されて、監禁されている。あなたは標的を選んで、その家族をひとり誘拐して、〈チェーン〉を継続させなくてはいけない」
「ちょっと! あなた正気で──」
「黙って聞いて。これは大事なことだから。あなたは誰かを誘拐して、その子を〈チェーン〉上で自分の娘と置き換えるの」
「どういうこと?」
「標的を選んで家族のひとりを誘拐し、標的が身代金を支払って代わりの誰かを誘拐するまで、監禁しておかなくちゃいけないということ。これとそっくり同じ電話を、自分の選んだ相手にかけてちょうだい。わたしがあなたにしているのとそっくり同じことを、あなたの標的にもするわけ。あなたが誘拐を実行して身代金を支払ったら、うちの息子はすぐに解放される。あなたの標的が誰かを誘拐して身代金を支払ったら、娘さんはすぐに解放される。単純でしょ。そうやって〈チェーン〉は永久に稼働しつづけるの」
「え? でも、誰を選ぶの、あたし?」レイチェルはすっかりおびえて訊く。
「掟を守る人。警官はだめ。政治家やジャーナリストも。そういう人たちは指示に従わない。誘拐を実行して身代金を払い、口を閉じたまま〈チェーン〉を動かしつづけてくれる人を選んで」
「どうしてあたしがそんなことをするってわかるわけ?」
「あなたがしなければ、わたしはカイリーを殺して、別の誰かでやりなおす。わたしがヘマをしたら、彼らはうちの息子を殺してから、わたしも殺す。わたしたちはもうあと戻りできないの。はっきり言わせてもらうけど、レイチェル。わたし、ほんとにカイリーを殺すから。自分にはできると、いまはっきり悟った」
「お願い、そんなことしないで。あの子を逃がして、お願い、お願いだから。母親から母親へのお願い。あの子はすばらしい子よ。あたしにはこの世にあの子しかいない。心から愛してるの」
「なら、それをあてにしてるから。ここまでわたしが言ったことはわかった?」
「ええ」
「じゃあね、レイチェル」
「だめ! 待って!」レイチェルは叫ぶが、女はすでに電話を切っている。
4
木曜日、午前八時五十六分
レイチェルは震えだす。気分が悪くなり、吐き気がし、嘔吐する。まるで治療を受けていた頃と同じだ。そうすればよくなるという希望を胸に、毒を投与させ、体を焼かせていた頃と。
左側を車が絶え間なくごうごうと通過していくが、レイチェルは異星に不時着してとうに死んだ探検家のように、身じろぎもせずに座っている。女が電話を切ってから四十五秒にしかならないのに、まるで四十五年のように感じる。
電話が鳴り、レイチェルはぎくりとする。
「もしもし?」
「レイチェル?」
「はい」
「ドクター・リードだけど。九時に待っていたのに、まだ階下(した)の受付に来ていないわね」
「遅れてるんです。渋滞で」
「気にしないで。この時間はいつもホラー映画なみだから。何時頃になりそう?」
「え? あ……今日はうかがえません。だめなんです」
「ほんとう? あらまあ、そう──あしたならいいかしら?」
「いえ。今週はちょっと」
「レイチェル、血液検査のことで相談をしたいから、こっちへ来てもらいたいの」
「もう切りますね」レイチェルは言う。
「ねえ、こういうことは電話じゃ話したくないんだけど、最新の検査結果を見ると、CA15‐3の値がすごく上昇してる。どうしても相談──」
「だめなんです。ではまた」レイチェルがそう言って電話を切ると、ルームミラーに回転灯が映る。マサチューセッツ州警のがっちりした黒髪の警官が、パトロールカーからおりてボルボ二四〇に近づいてくる。
レイチェルはすっかり途方に暮れて、そのままじっとしている。涙が頬で乾いていく。
警官が窓をたたき、レイチェルは一瞬ためらってから窓をおろす。
「すみませんが」と警官は言いかけ、そこで彼女が泣いていたことに気づく。「あ、すみませんが、故障ですか?」
「いえ。ごめんなさい」
「そうですか、この路肩は緊急車輛専用ですよ」
この人に話そう、と彼女は思う。何もかも話そう。だめだめ、それはだめ。あいつらはカイリーを殺す、絶対に殺す。あの女ならやる。「停めちゃいけないのはわかってたんですけど。医者から電話がかかってきて。あたし──癌が再発しちゃったみたいなんです」
警官は事情を察して、ゆっくりとうなずく。「どうですか、このまま運転を続けられますか?」
「ええ」
「違反切符は切りませんが、どうか先へ進んでください、お願いします。奥さんが車線に出るまで、車の流れを止めておきますから」
「ありがとう」
レイチェルはイグニションのキーをまわし、くたびれたボルボはごほごほと始動する。警官は走行車線の車を停めており、レイチェルはなんの困難もなく走りだす。一キロ半ほど走ると次の出口があったので、そこで高速をおりる。南へ向かわなければ病院で診てはもらえないが、そんなことはいまは念頭にない。まったくどうでもいい。カイリーを取りもどすこと、それが太陽と星々であり、全宇宙だ。
九十五号線の北行きに乗りなおし、猛然とボルボを駆る。この車をこれほど飛ばすのは初めてだ。
低速車線から、中速車線、高速車線へ。
時速百キロ、百十キロ、百二十、百二十五、百二十八、百三十。
エンジンが悲鳴をあげているが、レイチェルの頭にあるのは、行け、行け、行け、だけ。
用事があるのは北だ。銀行でお金を借りろ。使い捨て携帯を買え。銃でもなんでも、必要なものを手に入れて、カイリーを取りもどせ。
果たしてレイチェルは誘拐の連鎖に囚われてしまうのか? カイリーはどうなってしまうのか? 超スピーディーな傑作スリラー『ザ・チェーン 連鎖誘拐』は大好評発売中です!
【書誌情報】
タイトル:『ザ・チェーン 連鎖誘拐』上下
著者:エイドリアン・マッキンティ 訳者:鈴木恵
原題:THE CHAIN
価格 :各780円+税 ISBN:9784151833045/9784151833052
※書影等はAmazonにリンクしています。