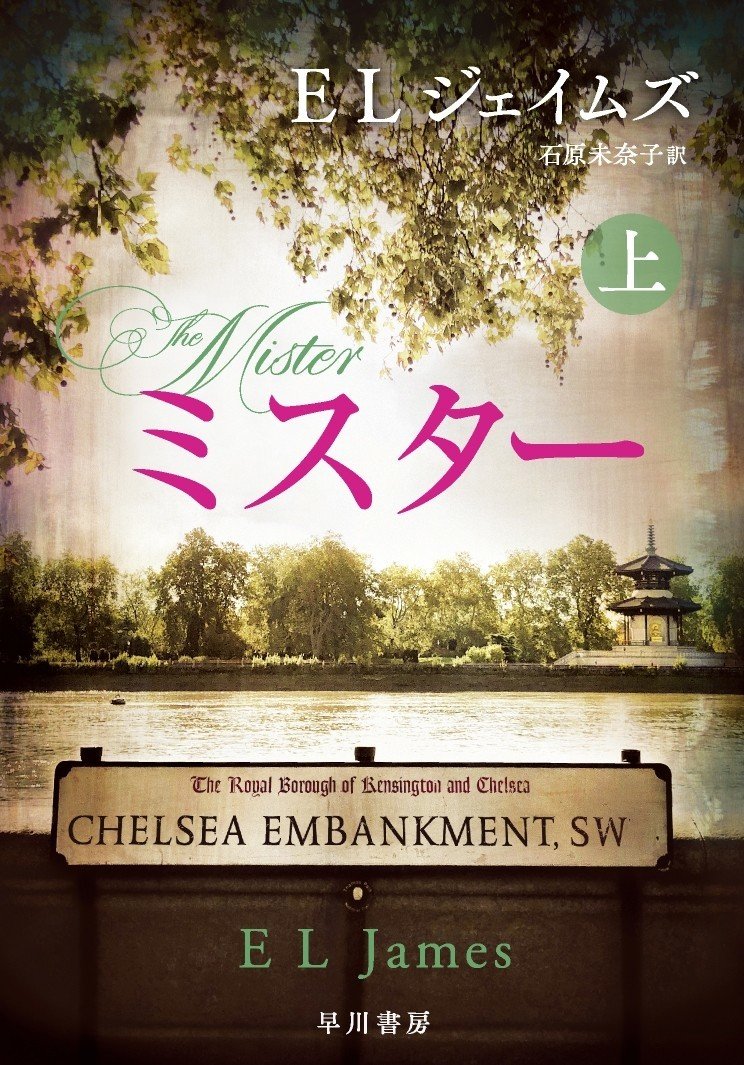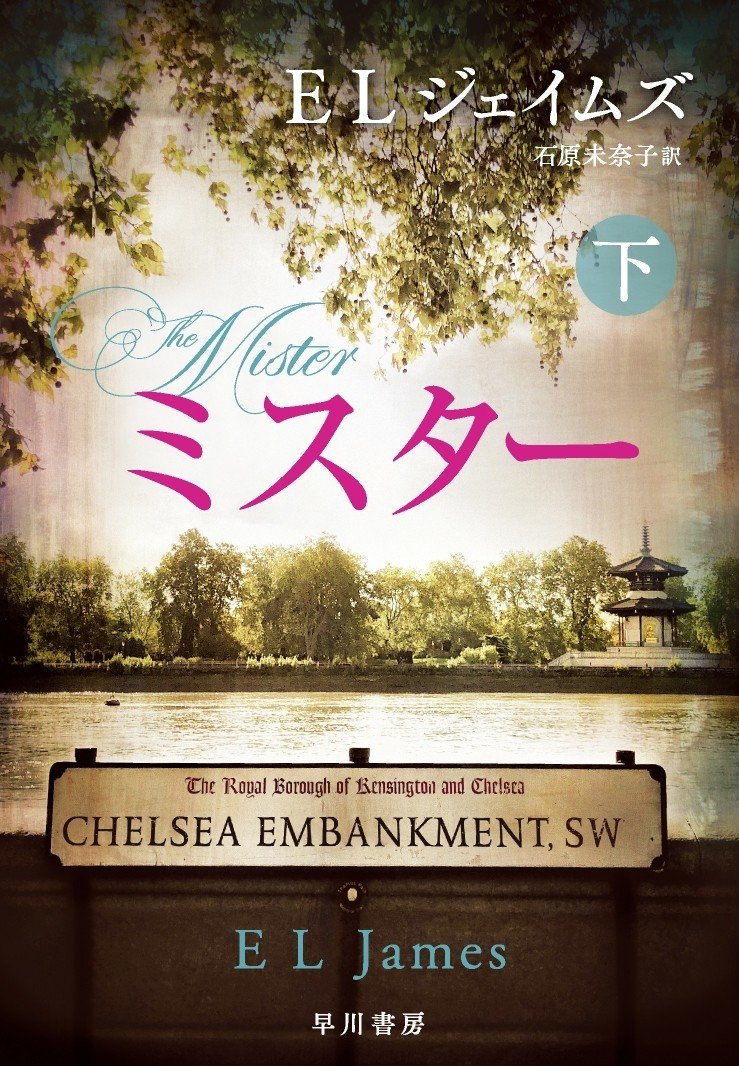〈フィフティ・シェイズ〉シリーズ著者新作『ミスター』一部抜粋その2 〈おれの名前は?〉篇
全世界累計1.5億部突破『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ著者 E L ジェイムズの新作『ミスター』The Mister が12月4日に発売されました。そこから一部抜粋の第2弾をお送りします。前回、〈キスしてしまった!〉篇では、ヒロインの貧しいがピアノの才能を持つ美女アレシア視点でした。今回は、ヒーローの貴族のプレーボーイ、マキシムの視点のシーンをご紹介します。
『ミスター』The Mister(上・下)
E L ジェイムズ 石原未奈子 訳
***
手を出さずにはいられない。どうしても。
いいから放っておいてやれ。
それに、少し触れただけで凍りつかせてしまったじゃないか。おれは暗い気持ちですごすごとリビングルームに戻った。彼女は純粋におれのことが嫌いなのだ。
そんなのは初めてじゃないか?
おそらく。これまで女性相手に手こずったことはない。おれにとって女性は常に気軽な娯楽だった。多額の預金残高と、チェルシーにあるフラットと、整った顔と、貴族の血筋のおかげで、苦労したことはなかった。
一度たりとも。
それが今回は。
食事に誘ってはどうだろう?
なにしろ彼女はまともな食事をしたほうがよさそうに見える。
だがもし、ノーと言われたら?
そうしたら、せめて答えはわかるじゃないか。
リビングルームの、天井から床まで届く窓の前を行ったり来たりしていたおれは、足を止めてしばし平和塔を眺め、勇気を呼び覚まそうとした。
なぜこんなに難しい? なぜ彼女なんだ?
たしかに美しいし、才能もある。
そしてこちらに関心がない。
もしかしたら、それだけのことなのかもしれない。
ノーと言った初めての女性。
だが実際にノーと言われてはいないし、チャンスをくれるかもしれない。
食事に誘え。
深く息を吸いこんで、ゆっくり廊下へ戻った。すると、洗濯かごを抱えた彼女が暗室の前に立ち、閉じたドアをじっと見つめていた。
「そこは暗室だ」言いながらそちらへ歩いていった。
きれいな茶色の目がおれの目を見あげた。きっと部屋のなかに興味があるのだろう。そういえば、ここは掃除しないようにとクリスティーナに言ったことがある。おれ自身、最後になかへ入ったのはずいぶん前だ。
「見せてもいい」いつものように彼女が後じさらなかったので、うれしくなった。「見たいか?」
アレシアがうなずいたので、おれは洗濯かごに手を伸ばした。指と指が触れたとたん、心臓が飛び跳ねる。「貸せ」ぶっきらぼうに言ってかごを受け取り、激しい鼓動を静めようとした。かごを背後の床に置いて、暗室の明かりをつけると、脇にさがってアレシアをなかへ通した。
アレシアを出迎えたのは小さな部屋だった。赤い照明がついていて、嗅いだことのない化学的なにおいと、長く使われていない空間特有のほこりっぽいにおいがする。黒いカウンターキャビネットが壁の一面を占め、その上には大きなプラスチック製のトレイがのせられている。キャビネットの上方には棚があり、瓶や紙の束や写真がひしめいていた。棚の下には物干し綱が一本渡されていて、洗濯ばさみがいくつかぶらさがっている。
「ただの暗室だ」彼が言ってスイッチを押すと、頭上の薄暗い明かりがついて、赤い光が消えた。
「写真、ですか?」アレシアは尋ねた。
彼がうなずく。「趣味でね。仕事にしようかと思ったときもあった」
「アパートメントにある写真は──あなたが撮ったんですか?」
「ああ。全部。いくつか仕事の依頼もあったが……」声が途切れた。
風景写真とヌード写真。
「父は写真家だった」彼はそう言って振り返り、カメラがいくつも収められているガラス製の棚のほうを向いた。扉を開けて、一つを取りだす。前面に〈ライカ〉という名称が記されているのが、アレシアにも見えた。
おれはカメラを目に当てて、レンズ越しにアレシアを見た。色濃い目、長いまつげ、高い頬骨、わずかに開いたふっくらした唇。下半身が固くなる。
「きれいだ」ささやくように言って、シャッターを押した。
アレシアは驚いたように口を開け、両手で頬を覆って首を振ったが、笑みは隠せなかった。おれはもう一枚、撮った。
「本当だよ。見てごらん」カメラの背面をアレシアのほうに差しだして、像を見せてやる。アレシアは細かに自分をとらえたデジタル画像をしばし見つめていたが、やがておれのほうを見あげた。とたんにおれは溺れた──色濃い瞳の魔法に。「やっぱり」つぶやくように言った。「はっとするほどきれいだ」手を伸ばしてアレシアのあごを傾け、少しずつ顔を近づけていった。少しずつ。もしそうしたいなら逃げられるように。ついに唇と唇が触れた瞬間、アレシアが息を呑んだので、おれは身を引いた。アレシアが目を見開いて、指先で自分の唇に触れる。
「いまのはおれの気持ちだ」ささやくように言った。心臓が激しく脈打つ。
おれをひっぱたくか? ここから逃げだすか?
ところがアレシアはじっとこちらを見つめるだけだった。淡い光のなかに立つ姿は、この世のものとも思えない。彼女がおずおずと手を伸ばしてきて、指先でおれの唇をなぞった。おれは目を閉じて凍りつき、やさしく触れる指先の感覚が全身に広がっていくのを感じた。
息さえ止めていた。
アレシアを怖がらせたくなかったから。
羽のように軽く触れる指先を、いたるところで感じる。
そう、いたるところで。
自分を抑える前に、腕のなかに引き寄せて抱きしめていた。やわらかな体がぴったりと寄り添ってきて、ぬくもりが全身に染み渡る。
ああ、なんと気持ちいい。
スカーフの下に指を滑りこませてそっと頭から取り去ると、うなじの部分の三つ編みをつかまえて軽く引っ張り、上を向かせた。「アレシア」ささやくように名前を呼んで、もう一度キスをした。やさしく、ゆっくりと、怖がらせないように。アレシアは腕のなかでじっとしていたが、やがてそろそろと両手をあげておれの二の腕をつかみ、目を閉じて受け入れた。
おれがキスを深め、舌で唇を翻弄すると、アレシアは口を開いた。
ありがたい。
ぬくもりと優雅さと甘い誘惑の味がした。小さな舌はためらいがちで、おっかなびっくりだ。じつに魅惑的で、興奮させられる。
自分を抑えなくては。いまは彼女のなかにうずめたい一心だが、彼女がそれを許すとは思えない。身を引いて、唇越しに尋ねた。「おれの名前は?」
「ご主人さま(ミスター)」ささやき声で答えたアレシアの頬を、親指で撫でおろした。
「マキシムだ。言ってごらん」
「マキシム」かすれた声が応じた。
「いい子だ」彼女の訛りで名前を呼ばれるのは、なんとも耳に心地よかった。
ほら、それほど難しくなかっただろう?
そのとき突然、しつこく玄関をたたく大きな音が響いた。
(E L ジェイムズ『ミスター』上巻 第8章より)
『ミスター』The Mister(上・下)
E L ジェイムズ 石原未奈子 訳
早川書房 四六判並製/電子書籍版
各1500円+税
2019年12月4日発売
(※書影はAmazonにリンクしています)
***
こちらの記事もどうぞ
・全世界累計1.5億部突破『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』シリーズ著者、待望の最新刊『ミスター』!
・〈フィフティ・シェイズ〉シリーズ著者新作『ミスター』一部抜粋 〈キスしてしまった!〉篇