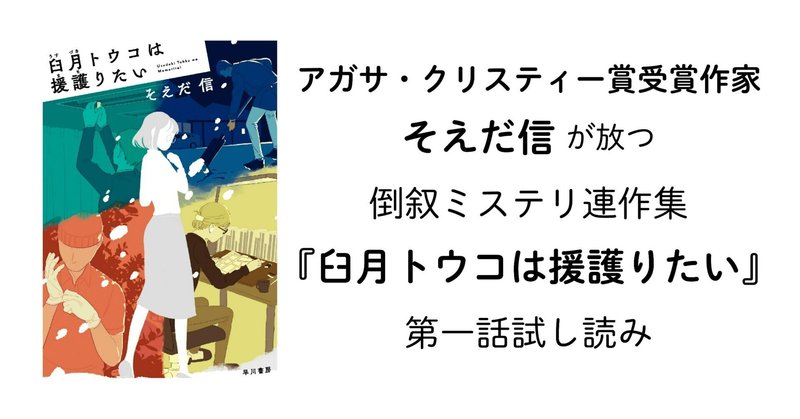
アガサ・クリスティー賞受賞作家、そえだ信が放つ、倒叙ミステリ連作集『臼月トウコは援護りたい』第一話試し読み
2020年に『掃除機探偵の推理と冒険』(受賞時タイトル「地べたを旅立つ」)で第10回アガサ・クリスティー賞を受賞した新鋭、そえだ信の最新作『臼月【うすづき】トウコは援護【まも】りたい』が6月22日(水)に刊行されます。
4篇からなる倒叙ミステリ連作集となっている本作。第一話「ゲームの裏の冷徹」を本ページから試し読みいただけます! 異色の「探偵」臼月トウコの活躍をどうぞお楽しみください。
第一話 ゲームの裏の冷徹
──臼月トウコの援護── 二月
店を出ると、ネオンの交錯する夜空に、粉雪が舞い始めていた。頭を白く彩らせた歩行者が、靴の踏み出し先を探すように頼りない足どりを進める。その進行を邪魔せんばかりに、酔いの回った女子社員たちはきゃっきゃと踊るようにへし合い、たむろしていた。
「社長──。こっち、並んでくださーい」
駆け寄り呼ばれて、桐川芳人はすでに歩き出しかけていた足を止めた。
「何だ、おい」
「お祝いの記念写真でーす」
横に身を寄せた若い女が指を二本立て、桐川も慌てて毛糸の手袋の指でそれに倣う。向かった女のケータイがかしゃりとシャッター音を鳴らす。
周りの何人もの男女が、わあ、とそこに笑い声を被せる。
少し離れてそれに背を向け、一人の男が歩き出していた。
「あれ、副社長、帰られるんですかあ?」
「ああ、僕は酔った。失礼」
振り返らないままに片手が振られ。黒いコートの背中がふらふら危なっかしい足どりで、駅へ向かって遠ざかっていく。
それを追う視線は、わずかで。
人通りの絶えない街路に、なおも賑やかな笑いが飛び交い続けていた。
「じゃあ、ほんと悪いが黒辺、後は頼む」
傍らで寒そうに肩をすぼめている部下を振り返って、桐川は肩を叩いた。
「今度また埋め合わせをするからな。これ、二次会の足しにしてくれ」
「済みません」
福澤諭吉翁の肖像五葉分を手渡されて、黒辺は実直な顔を笑みに緩めた。
「おーいみんな、社長から二次会のカンパいただいたぞお」
「ありがとうござーす」
「社長、太っ腹ー」
社員たちから口々に、酔いの回った歓声が返る。
じゃ、と手を振って、桐川は駅とは逆の側へ踵を返した。
裏小路を急いで回れば追いつけるはずだ、と素速く頭の中で見当をつけながら。
「おい正内、起きろよ」
車を停めて助手席の肩を揺すっても「むうう」と低い唸りが返るだけだった。予定通りと頷いて、桐川はヘッドライトを消した。住宅裏の狭い路地の圧雪が、たちまち闇に沈む。
エンジンも切り、運転席のドアを開こうとして、手を止めた。
正面の少し離れた小路に、歩行者の姿が現れたのだ。フロントガラス越しの視界を、焦げ茶のジャケットの男が一人、やや足速に横切っていく。すぐ横の町内会館の建物陰にその姿が消えるまで、桐川は息を潜めて辛抱強く待った。
そこからゆっくり頭の中で三十まで数えて、ドアを開いた。
改めて二階建て建築の屋根の具合を仰ぎ見て頷き、助手席側へ回る。
「おい、着いたぞ。降りろ」
やはり「むうう」と唸るだけの黒いコートの腕を引き、腋(わき)に肩を入れて抱き起こした。
「もうすぐベッドだぞ。冷たくて、気持ちいいぞ」
目の前に広がる建物裏の白い積雪に、足を入れる。容赦なく短靴(たん ぐつ)の縁から冷たい侵入が突き刺さってきたが、気にしている余裕はない。
すでにいくつか屋根からの落雪の兆しが刻まれた雪面に、肩を貸した男の身体を下ろした。もう何年もつき合わせていた馴染みの顔が仰向けに、吹きさらしの積雪にわずかに沈む。「ううん」と唸って、黒いコート姿は都合よく、自ら大の字になっていた。
「ゆっくり休めよ」
首に巻かれていた毛糸のマフラーを引き上げ、鼻と口を覆ってやる。顔横に回した不安定なその余り分は、屋根から落ちて砕けたらしいザラメ状の氷を集めて固定できた。
あとは周囲の雪を集め、両手両足から全身にかけて覆いつくして、完成だ。
ほとんど首から上だけを残して雪に埋もれた友人の眠り姿を見下ろして、桐川は頷いた。すっかり雪に濡れた手袋と靴の中は不快だが、出来上がりは満足だ。
成果をもう一度見回して、車に戻る。トランクに常備したスコップを出して、道路脇の雪を集める。雪かきの要領で今の作業跡の方へ放り、足跡のほとんどを埋めていくのだ。ただし、いくつかの靴跡の窪みは不明瞭ながら残るように。
すべての作業は、数分のうちに終わった。
運転席に戻り、エンジンをかける。発車しようとして、一瞬、背筋に冷たいものが走った。目の端に、異様なものが引っかかり捉えられていた。
助手席に残された、黒い鞄だった。
危ない。忘れていたら、たいへんなことになるところだった。
気を落ち着けて、その遺留品を道路脇に放り投げた。改めて作業成果を見回し確認して、桐川は運転席に座り直した。
着信表示を見ると、予想通りの番号だった。小ぶりの通話機を、桐川は耳に近づけた。
「やあ、祐治さんか」
「おう。遅くなって済まない、何とか終わらせたよ。そっちはどうだ、来れそうか?」
従兄の新嶋祐治は、やや疲れの滲む声を機械越しに返してきた。
「ああ、こっちも予想通り宴会は九時前で終わったんで、帰宅していたところだよ」
「ならよかった。しかし、いいのか? 二次会もあったんじゃないのか」
「言ったろう。二次会まで社長が付き合ったんじゃ、連中羽を伸ばせないさ。おちおち上司の悪口も肴にできない」
「まあ、そりゃそうだ。じゃあこれから来れるんだな? しかしそうか、酒が入ってるんじゃ運転できないか」
「タクシーでも拾うさ」
「待たせた詫びに、迎えに行くぞ。三日ほど机に縛り付けられていて、さっき原稿を上げたばかりだからな。身体を動かしたいところだ」
「ひさしぶりの運動ってわけか。悪いね、助かる」
「そっちのマンションまで行けばいいか?」
「いや。駅前の方が動きやすいだろう。ここから五分くらいだ、少し歩いて酔い醒ましするさ」
「苫小牧駅前だな。よし、それなら──」
声の途中で、相手の背後に大勢の人声が沸き上がった。桐川は、さらに耳を近づけた。
「何だ、この声」
「テレビだよ」
苦笑いの口調で、新嶋の声がわずかに離れた。後ろを振り向いたらしい。遠く話しかけている相手は、妻だろう。そして、すぐに声が戻る。
「例の、冬季オリンピックのアイスホッケーさ」
「そうか、三位決定戦、今日だったか」桐川も苦笑になった。「テレビを点けていないんで、忘れていたよ」
「日本初のアイスホッケーのメダルが懸かっているんだぞ。この瞬間テレビを点けていない苫小牧市民は、お前くらいじゃないのか」
「それは大袈裟だろうが。歓声が沸いてるってことは、得点入ったの?」
「いや、惜しいところで逃したようだ。ついさっきも相手ゴール前で競(せ)り合いが続いて、もっと盛り上がっていたんだがな。第二ピリオドに入って、まだ0対0だ」
「それじゃ、祐治さんもテレビの前を離れられないんじゃないのか?」
「車のテレビを観ながら行くさ。話を戻すが、苫小牧駅なら二十分くらいで行ける」
「じゃあ、頼む。しかし、運転気をつけてよ。また雪が降ってきている」
「そうか、分かった」
「安全第一でね。多少遅れても構わないから」
「了解だ」
切断スイッチを押して。ついでに覗いた液晶に示された時刻は、二十一時四十六分だった。腰を伸ばして、桐川は支度を始めた。
青いユニフォームが敵ゴール前に殺到して、広い室内に一斉に悲鳴じみた喚声が上がった。スティックが振られ、振られ、青と白の人像が揉み合い、圧し合い。遠い異国の映像では、大画面にもかかわらずパックの行方も分からなくなっている。それでも詰めかけた数十名の群衆に、ややしばらくの喚声が引き続いた。
「わーーーーーーーーー」
「ああーーーー残念ーーーー」
異様に長く感じられた競り合いの数秒間、忘れていた息を人々は吸い直した。そしてそれがまた、長々と溜息として吐き出される。
「もう一押し、だったのに──」
乗り出した上体が、一斉に立て直され。その拍子。
頭上に、ざざあ、と轟音が響き渡った。
「わ、何だあ?」
「屋根の雪だべ」
「俺らの熱気で、雪も落ちたかあ」
ややあって、緊張が緩んだ集団に笑いの波が広がっていった。
北海道苫小牧市登良遠の町内会館、大広間。老若男女六十名余りが集って、冬季オリンピックアイスホッケーの試合をテレビ観戦しているところだ。もともとアイスホッケーが盛んな地域ということに加え、今大会は地元中学出身の選手が二名出場しているとあって、この期間は地区を挙げてのお祭り騒ぎになっていた。しかもこの土曜の夜は、日本初のアイスホッケーのメダルが懸かっている三位決定戦ときているのだから、『俺らの熱気』というのもまんざら冗談と言いきれない熱狂状態だった。
人々の頭上に、なおも数秒間ずるずると雪の滑る音が続いた。例年を上回る降雪量で、大きなトタンの片流れ屋根上に厚く堆積していた雪と氷が、一斉に滑り落ちているようだ。
大画面の中で、今度は敵方が日本ゴールに殺到していた。息を飲んで、観衆は再び上体を乗り出していた。攻めと守りが交互して、0対0のまま第二ピリオドが終了した。
「あと二十分かい──」
「けばってってくれよう……」
パイプ椅子の観衆の間に、抑えた、祈るような声が行き来する。
インターバルの間に、やがて広間にもやや落ち着いた空気が漂い出していた。
そんなとき、がたんという音に人々は横手を振り返った。入口のガラス戸に、緊張した表情の中年男が顔を出していた。
「おい、誰か来てくれ。男衆、何人か」
「どうしたい、斉藤さん」前列に座っていた初老の町内会長が声を上げた。「この後、大事なところなんだぞ」
「裏の小路に黒い鞄が転がってた。この建物裏に向かって、足跡みたいなのある。誰か雪に埋まってんのかもしれねえ」
「何だと?」
数人の男が、慌てて立ち上がった。一人が部屋隅にあった大きな懐中電灯を持ち上げる。
先を争うように、男たちは裏手に回った。正面と違って街灯もなく、やや離れた製紙工場の煙突の影やすぐ近くのゴルフ練習場の金網が月明かりの空にそびえて、大人でも不気味に感じる場所だ。
懐中電灯を差し向けると、降雪とさっきの落雪でほとんどかき消されているが、確かに不完全な足跡のようなものが道路から建物裏の方へ切れぎれに続き、屋根下にいくつも転がった雪の固まりで途絶えているのが見えた。二度三度、光の輪が往復して、その雪の固まりを照らし出す。と、
「おい!」
一人が、押し殺した声で叫んだ。
「大変だ!」
雪の隙間に、黒い靴が突き出して見えているのだ。その向こうに持ち主の足が続いているのは、ほぼ明らかだった。
「おい、シャベル持って来い!」
「誰か、救急車呼べ!」
たちまち、会館中が蜂の巣をつついたような大騒ぎになっていた。
かかってきた電話でその凶報を受けたのは、桐川が日曜の朝刊を開いたときだった。従兄の家から戻った自宅で、『アイスホッケー日本、惜敗』『惜しくもメダルならず』とスポーツ新聞と見紛う鮮やかさの見出しに埋め尽くされた一面を斜め読みしていたところで、サイドボードの上の機械が電子音を上げ始めた。
かけてきたのは、総務担当の黒辺亨だった。副社長の正内豊介が死体で発見されたと、警察から連絡があったという。
「確かな話か?」
まだアルコールの霞が残る頭を振って、桐川は問い返した。
「何でも、帰宅途中の雪の中に埋まっているのが見つかったと。屋根からの落雪の下敷きになったようで」
これから警察署へ確認に行くという黒辺に、
「頼む。俺もすぐ行くから」
応えて、桐川は電話を切った。
──そうか、死んだか。
頭に浮かんできたのは、ただ反復確認の音声だけだった。思っていた以上に、喪失感も達成感も持ち上がってはこなかった。
妙にだるさの残る手足を半ば習慣のままに動かして、とりあえずパソコンの中を確認する。必要な操作をして、身支度のために立ち上がった。
羽織ったコートのポケットに手を入れると、不快な冷たい感触が返ってきた。前夜の面倒事が過ぎり直す頭を軽く振って、濡れた手袋を取り出した。それは手近な棚の上に広げ置き、新しい色違いを引き出しから取り出す。ほとんど機械的なままに支度を調えて、ようやく雪道を歩き出したところで、友人の追憶が頭に戻ってきた。
桐川と正内、あと大学時代の友人数名を中心に、苫小牧でゲームソフト会社『KID SOUND SOFT』を興して、もうすぐ六年になる。恋愛シミュレーションアドベンチャーゲームの形態に少しずつ独自の仕掛けを盛り込んでそこそこの売上げを続けていたのが、昨年ようやく一つのソフトで全国的に大きなヒットを記録した。練られたシナリオももちろんだが、各場面で使われる音楽を簡易作曲機能でプレイヤーがオリジナルのものに変えることができるという仕様が、大きな話題を呼んでいた。そのソフト『のぞみシンフォニー』が、今年度のフロンティアゲーム大賞で企画賞を受賞した。昨夜はその受賞祝いと、次回作『かなえラプソディー』のマスターアップの祝いを兼ねた宴だった。社員二十余名のほとんどが参加して、もちろん副社長の正内も出席していた。陽気に普段以上の酔態を見せて、一次会の店を出て帰宅の途に着いたはずだった。
もちろん新作のマスターアップというだけで、業務が一息つくわけではない。前夜とこの日の午前中だけやや羽を伸ばして、すぐこの日曜昼過ぎからは社員のほとんどが出社して、出荷作業に当たる予定になっていた。正内の主な担当は純粋にゲーム作成の部分なので、マスターアップ後には影響が少ないというのが不幸中の幸いと言える。経営者の思考に徹して、桐川は意識的に冷徹にこの日の業務を吟味した。
苫小牧警察署には、すでに正内の同居している両親と黒辺が到着していた。以前からの顔見知りなので、すぐに桐川は薄暗い廊下で両親と挨拶を交わした。三十を過ぎたばかりの一人息子を突然失って、正内夫妻は哀しみより先に茫然自失といった様子だ。
「ご遺体は、確認されたんですね?」
潜めた声で父親に訊ねると、無言で頷きが返ってきた。本人にまちがいないということらしい。職員に確認すると、検視中で、家族以外は遺体に会えないという返事だった。
「登良遠の町内会館裏の雪山だそうです、発見されたのは」
両親から少し離れた廊下の隅で、黒辺が報告した。
「確か、JRの登良遠駅から正内の自宅へ歩いて帰る途中だな、町内会館は」
桐川が確認すると、黒辺は頷き返した。
「ええ、だから酔ってその辺に寝転がってしまったところへ、屋根からの落雪に襲われたんじゃないかと」
「先週あれだけ雪が積もったから屋根にかなりあったのは分かるが、それにしても運が悪いことになるな」
「たまたま昨夜はアイスホッケーの応援で会館を使っていたので、その暖房のせいで雪が落ちたと見られているようです」
「何とも本当に」桐川は顔をしかめた。「運が悪いとしか言いようがないな」
話しているところへ足音が聞こえて、桐川は廊下を振り向いた。背は低いががっしりした体格の男が一人、近づいてきていた。私服警察官らしい。
「被害者の会社の方、ですか?」
「ええ。社長の桐川といいます。こちらは、黒辺」
「刑事課の、笠置です」ほとんど長方形に近いいかつい顔の中年刑事は、軽く頭を下げた。「昨夜は、会社の方々で飲み会だったとか?」
「ええ」桐川は頷いた。「自社製品の賞受賞と新作完成祝いということで。駅の南口前の『スリル』という居酒屋で──」
確認のために、部下を振り返った。
「一次会が終わったのは、九時前だったよな?」
小柄な黒辺は、社長の横から見上げて頷いた。
「ええ。八時五十分ってとこだと思います」
「そこで正内さんは帰ったと?」
「そのはずだな?」
もう一度振り返ると、黒辺は頷きを返した。
「ええ。正内さんは二次会には来ていませんでした」
「酔った足どりで歩き出すのは見た記憶があるからな。多分あのままJRで帰ったんだろう」
桐川は、四角顔の刑事に向かい直った。
「と言うことは、桐川さんも二次会には行かなかったわけですか」
「ええ、私はその後用事があったので。すぐ自宅に帰りました」
「他の社員の方々は、みんな二次会へ? 何時頃までですか?」
「社長と副社長の他に二三人は、一次会で帰ったかというところですかね。二次会はまたその近くのスナックで、九時過ぎから十二時過ぎまででした」
考えながら、黒辺が応えた。
「参加者の名前が、必要ですか?」
「ええ、できましたら」
「これは、事故なんでしょう? 」桐川は眉をひそめた。「死亡時刻のかなり前に別れたはずの面子、などというのが必要なんですか?」
「ああ、済みません。一応、参考のために」
「事故と確定できていないわけですか?」
「まだ捜査を始めたばかりですからね、何とも断言はできません。我々としては、あらゆる可能性を考えたいと思っています」
「ふうん」不承不承、桐川は頷いた。「じゃあ、黒辺に参加者の名簿を作らせて、後で届けさせましょう」
「そうしてもらえると、助かります」
無骨な顔をやや愛想に緩めて、刑事は軽く頭を下げた。
「それから──失礼ですが、桐川さんのその後の行動も、できたら教えていただけますか」
「そんなのも必要なんですか?」
「ええ。一応、参考のために」
慇懃無礼ともとれる刑事の仕草に、桐川は顔をしかめた。
「自宅──一人暮しのマンションですがね。そちらへ帰って、その後白老の従兄の家へ呼ばれて行っていました。昨夜はそこへ泊まって、さっき、朝九時頃家へ帰ってきたところです」
「白老ですか」刑事は、手帳に書き付けていた。「するとこっちからだと、登良遠とは真逆の方向ですね」
「そうなります」
「従兄さんの家へは、前からの予定で?」
「さっきも言った受賞の祝いをしてやると、前から言っていたんですけどね。向こうも仕事が押していて、ライターをしているんですが昨日まで原稿書き、明後日からは新しい取材旅行へ出発と忙しいんで、祝いをするなら昨日しかない、無事原稿が上がったら祝宴を決行するから待機していろ、ということになっていました」
「なるほど」
「そういうことでこっちの宴会の後で帰宅して待っていたら、夜九時半頃かな、向こうから電話がかかってきて、打合せをして、従兄の方から車で迎えに来て、あっちの家へ連れていかれたというわけです」
「なるほど、なるほど」
従兄の名前と住所まで記録して、刑事は手帳を閉じた。
「よく分かりました」
「ところで、聞いていませんでしたが」桐川は首を傾(かし)げながら問い返した。「正内が雪に埋まっているのが見つかったというのは、何時頃なんですか?」
「夜十時前、ということですね。アイスホッケーの応援に会館に集まっていた人たちが、日本チームの攻撃で盛り上がったところで屋根の雪が落ちた。その直後に遅れてそこへやってきた地区の人が正内さんのバッグが道に転がっているのを見つけて、みんなで雪山を見にいって人が埋まっているのを発見したと。発見の直前、おそらくはやはりその落雪のときに死亡していたようです」
「それなら、こっちの二次会に参加した連中も、それから私も、そっちには関わりないということになりますね」
「お話の通りなら、そういうことになりそうですね」
「では。死体の状況は、他人に何かされた形跡でも?」
「いや」刑事は首を振った。「何とも言えないところではありますが、今のところ手足を拘束されていたとか、事前に何処か負傷していたなどの形跡は見つかっていませんね」
「じゃあ──」
「ただ一つ気になっているのが」
「何です?」
「首にしていたマフラーが、発見時被害者の口に入り込んでいました。まるで、猿轡でもしたみたいに」
「猿轡ですか? マフラーを口に噛ませて、縛ってあったわけですか?」
「いや、両端は揃って雪に埋まっていましたが、縛ってあった形ではなかったようです」
「それじゃあ、猿轡とは言えないでしょう。首を振ったくらいでほどけてしまいそうな。首に巻いていたマフラーが、偶然ずり上がって口に入った。あるいは昨夜は気温が低くてときどき雪も降っていたから、最初から口の辺りにマフラーを巻いていたかもしれない」
「まあ、そうなんですけどね」あっさり、刑事は頷いた。「それでも結果的には、そのマフラーが猿轡の形になっていたために被害者は意識があっても大声で助けを呼べなかったかもしれない。大の字の形で寝そべっていたところへ落雪で潰されたと見られていますが、誰かが被害者を大の字に転がして、両手両足の上に雪を積んで逃げられないようにしていたという可能性も考えられなくはない」
「へええ」
「まあ、一つの可能性というだけですけどね」
面白くなさそうに、刑事は顔をしかめた。
「まあ──」桐川は、考えながら応じた。「そういう、つまり他殺の可能性、ですか? あり得るんなら、十分に捜査をしてください。今言ったように、会社の関係者はほぼ関わりないと思いますが」
「そうですね」刑事は、もう一度頷いた。「慎重に調べさせてもらいます」
正内の両親に挨拶して、この場は引き上げることにした。葬儀などに関しては何でも協力すると申し出たが、とりあえず今日明日は遺体が戻らない予定だということだ。
「何だか嫌な感じですね、あの刑事」
警察署を出て雪道を歩きながら、黒辺がぼやいた。
「他殺を疑っているってんですか? 何だか社長やうちの会社の人間を疑っているみたいな口ぶりで」
「言っていたように、まだ何でも可能性を考えているだけ、と信じたいがな」首を振って、桐川は溜息をついた。「こっちは無二の親友で仕事仲間を失ったってのに、しんみりさせてももらえない感じだな」
「まったく、失礼ですよね。特に社長にとって、あの正内さんがどんなに大切な仲間か、知りもしないで。業界内でもずっと、一心同体のパートナーと呼ばれているってのに」
「まったくだ」
胸にちくりとした痛みが染みるのを堪えながら、桐川はもう一度嘆息した。
「しかし、感傷に浸ってだけいるわけにもいかない。新作の出荷は、ショップもこんなことで待ってはくれないからな」
「大雪ふぶきなんてものさえ、何一つ言い訳にはさせてもらえませんね」
「明日までに第一便全数発送、俺は明日は雑誌の打合せだったな」
懐から手帳を出して、桐川は確認した。
「ですね」黒辺も手帳を出して目を走らせた。「ああそうだ、今日明日は二野宮が休みなので、スケジュール確認は僕の方にしてください」
「そうか。二野宮、祖母の法事と言ってたな」
いつも社長秘書の役を務めているイラスト担当の女性社員の申し出を、桐川は思い出した。
「昨日の帰り際にも、こんな忙しいときに済みませんと、恐縮していましたよ」
「ぶっちゃけ、うちが忙しくないときなんかないからなあ。都合があるときは、思い切るしかない」
「まったくです」
もう午を回っていて、間もなくこの日の作業予定が始まるところだった。警察署とは駅を挟んで逆側にある北口すぐのビルへ、二人は足を急がせた。
当然、副社長の訃報は社員に知れ渡っていた。簡単に桐川から次第の説明をして、今はとにかくと出荷作業を開始した。
夕方近くになって二名の刑事が訪れて、それぞれ短時間ながら社員は順に話を訊かれることになった。別室に呼ばれて戻ってきた社員たちの話では、日頃の正内の様子と前日の行動を訊かれた程度のようだ。
それでも全員が少しずつ時間をとられて、作業は予定より遅れることになった。刑事たちが帰った後、桐川は黒辺を始め重鎮数名と打合せをした。
「少し遅れているが、明日必死こいてやれば終わる程度かな」
桐川のやや冗談めかした物言いに、黒辺は硬い顔で頷く。
「ですね、おそらく」
「今日時間を延ばしてやるのも、一案だが」
桐川は、ゆっくり部下たちを見回した。
「あんなことがあって落ち着かないところで無理して、ミスがあったら元も子もないしな。修羅場は今日に始まったことじゃない。今日は上がりにして、一度落ち着いて明日続きをやることにしよう」
「まあ、そうですね」出荷責任の河原が頷いた。「しかし、明日の締め切りはもう譲れませんよ。それこそ、必死こいて終わらせるつもりにならないと」
「だな」
全員が頷き合って。作業場に戻って、打ち切りを言い渡した。帰り支度を始める社員たちから離れて、桐川は社長室へ向かった。
パソコンディスプレーの並ぶ机の間を抜けようとすると、椅子の背にコートを掛けたまま黒辺が自分の引き出しを覗いていた。「くそ──今日は厄日かい」
「どうしたんだ?」
「あ──いえ」顔を上げて、黒辺は苦笑いになった。「たいしたことじゃ──愛用の万年筆が見当たらないってだけです。紛失だとしたら、今日はとことんついていない感じで」
軽く首を振ってから、桐川の目指す先に気がついたようだ。
「あれ、社長はまだ──?」
「考えることがあるんでな。俺はもう少し残る」桐川は即答した。「君らは帰ってくれ。これは俺しかできない、正内の抜けた今後の手順を見直さなけりゃならない」
「ああ──」
何か言いたげな表情になりながら、やや間を置いて黒辺は頷いた。社長の言い分に、反論は思いつかなかったようだ。
「ただしかし社長、根詰めすぎないでくださいよ。今後のことがありますし。今社長に倒れられたら、うちはお終いです」
「分かってるよ」
肩をすくめて、桐川は苦笑を返した。
部下が言い返せないのも、当然なのだった。普通の社長副社長の業務と、わけが違う。この会社の根幹であるゲームソフトの企画立案は、これまですべて桐川と正内二人だけで行ってきていたのだ。
黒辺の口にしていた「一心同体」という表現も、表向きには大袈裟でも冗談でもないことが知られていた。『KID SOUND SOFT』の製作してきたゲームの監督・シナリオ担当はすべて『蓬蓬介人』という名前になっている。桐川と正内の合作用のペンネームだ。文字通りの意味でこの会社は、二人が「一心同体」で運営してきていたのだ。
小柄で猫背気味、一見したところ風采の上がらない正内豊介は、ストーリー作りとプログラミングに抜きん出た技量を持っていて、社員一同からも尊敬を抱かれ続けていた。
青年実業家として外見上も長身で知的、爽やかと表現されることの多い桐川芳人は、作り手と売り手双方の才能を武器にして、ここまで会社を成長させてきたと評価されていた。
同年齢ながらさまざまな面で対照的な二人だが、互いに不足している点を補い合って、自社の両輪となってこの数年間を走り続けてきたことになる。そして今回の製品のヒットと受賞でその働きも報われ、いよいよ軽快に前進を続けるものと、内外ともに期待されていた。
しかしそれも、両輪のバランスが保たれている限り、の話だ。
「レノン・マッカートニーでも……あるまいし」と、肩をすくめて正内豊介は言った。「こ……こんな話が、そうそううまく、長続きする……なんて、あり得ないさ」
「どういうことだ?」
桐川の問い返しに、相棒はしばらく押し黙った。
「何か、あったのか?」
年末の社長室での、会話だった。駅前通りの華やかなネオンサインを映す窓に、雪片の影がちらつき見え出していた。外には賑賑しい音声が行き交っているはずだが、二重ガラスの内側はうって変わった不自然な沈黙が漂い降りている。
相手の言いたいことは、ほぼ見当がついていた。無駄な時間を省きたい気が募って、桐川は静まる池に石を投じた。
「『フロバー』か?」
向かいのソファで俯いていた長年の友人は、ひくりと視線をもたげた。
「あ……ああ」
通称『フロバー』=『frolicking birds社』は、東京の大手ゲームソフト会社だ。──前年の『KID SOUND SOFT』のヒットを受けて、製作の『蓬蓬介人』に興味を寄せているらしい。
そういう噂は以前から耳にしていた。
「い……移籍の誘い、受けている」
「なるほど、な」
ソファ横に引き出したビジネスチェアの上で、桐川は脚を組み替えた。社員が帰った後の社長室で『蓬蓬介人』としての打合せをするときの、いつもの位置取りだ。
「つまり、腹は決めているわけか、正内君は」
昔からこの二人の間で、相手を『君』付けで呼ぶのは、よほど不自然に改まったときかからかいの意味か、だ。どちらかというと後者寄りに、できれば冗談で通過したい願望を込めて、桐川は友人を横目で見た。
しかし、不器用な相棒は、ただ油の切れた機械のような頷きを返しただけだった。
「あ……ああ」
「──そう、か」
溜息を殺して、横目で窺った先で、相手はまた視線を落としていた。
「考え直せないのか?」静かに、呼びかけてみた。「俺も、会社も困るのは分かっているだろう? 俺にはお前が必要だ。こんなところで袂を分かちたくないぞ」
「分かって……る」
重く、頷きが返った。
「しかし僕には、向こうの環境の方が力を発揮できる……と思うんだ」
「………」
「シナリオ……とプログラミング統括……その辺に、専念させてくれる、と」
「なるほど、な」
「……で、僕の名前でシナリオが書ける」
「………」
「や……」相手の顔を見て、正内は手を振った。「こっちでのことは、言わないぜ、金輪際」
「それは……当然、だ」桐川は顔をしかめた。「法的規制があるとは言えないが、この世界での仁義ってのはまちがいなくある」
「あ……ああ」
この事態を予想していなかった、わけではない。しかし──まるで絵に描いたような、と言うよりマンガの中にでも放り込まれたような陳腐極まりない窮地に、桐川は苦笑しか出ない心持ちになっていた。
他人に知られるわけには、いかないのだ。現状の『蓬蓬介人』が、ほぼ一人のものになっている、ことなど。
確かに二人でアマチュアとして製作を始め、会社を興し──その時点では、ゲームの企画製作作業はほぼ共同のものだった。しかし製作数を重ねるに従って、その比率は五―五から七―三、九―一、十―〇と変化していた。
桐川の方が、会社の経営面、営業に、力点を置かなければならなかった事情はある。それ以上に、回数を重ねるに従って、二人の才能の差が明らかになってきていたとも言える。社交的な面では劣るが、正内には明らかにストーリー作りとゲーム企画の斬新な発想、それを実現するプログラミングの才能があった。『簡易作曲機能』をゲームに盛り込むなど、思いつきだけは誰でもするかもしれないが、あれほど鮮やかに実現することはこの男以外にできなかっただろう。その機能を自家生産で実現した通称『SCシステム』を見せられたときには、ずっと一緒に歩んできた桐川でさえ、目を疑ったものだ。
「言わないから……金輪際」
同じ言葉を、相手はくり返した。
くり返されることで、かえって桐川の胸中に不安は広がっていた。
確かに、長年の友人は信じたい。信じられるかもしれない。しかし──。
『フロバー』の社長、刈谷という男に、桐川は数度会ったことがある。それ以上に、さまざまな方向から評判を耳にしている。一言で言って、競争相手を叩くことに手段は選ばない経営者だ。おそらく、いや疑いなく、その懐に取り込まれた暁には、駆け引きなど知らない正内ごとき、たちまち裸にされてしまうことだろう。
『KID SOUND SOFT』が最大のブレーンを失うだけで、済まない。製作と経営の双方に秀でたトップ、桐川の名が地に堕ちることになるのが、目に見えているのだ。
その事態だけは、避けなければならない。
言葉を換えて説得を試みても、しかし正内の決心を揺るがすことはできなかった。この男の地味な外見の奥の剛愎さは、誰よりも桐川が知り抜いていることでもある。
相応の報奨を見直す、という提案にも、半ば困惑の苦笑が返るばかりだった。
「向こうの環境の方が力を発揮できる……と思うんだ」
頑迷な男は、さっきと同じ言葉をくり返した。
「苦手な営業で結果が出せないからと、差をつけられることもないし」
古い話を持ち出しやがって、と桐川は内心舌を打った。
会社創業当時は、そういうこともあった。全員が製作も営業もしなければ、回らない。意識向上のために、製品を扱ってくれるショップの開拓に社長副社長を含めた全社員での競争を導入したのは、桐川の提案だった。その点では、確かに正内は成績下位だったはずだ。
「もちろん……中途半端で飛び出すなんて、無責任はしないよ」
結論づけるように、正内は首を頷かせながら言った。
「今扱っている新作は、完成まで責任を持つ。退職時期も、迷惑が少ないように年度末、三月限りにする」
この男らしく、さんざん検討した結果で打ち明けているのだ。決心を変えさせることは難しい、と桐川は思った。もちろん、この事態を阻止する法的手段などもあり得ない。
腹を括るしかない、と桐川は嘆息した。
「言わないから……金輪際」
何度目かの同じ、空虚なくり返しが。雪片の影が流れる窓ガラスに、溶け込み消えていった。
足先に衝撃を感じて、目を開いた。スリッパの先端が、机の脚に触れていた。首を巡らすと、見慣れた社長室のデスクの前だ。目の前の机上には、過去に製作したソフトの記録の数々。朝方まで目を通しながらこの先を考えていた、そのままの形で寝落ちていたらしい。
ゆっくりと、桐川は首を回した。
時計を見ると、九時半近い。月曜の業務はもう始まっている。おそらく黒辺辺りが社長室を覗いて事情を察し、そのままにしていてくれたのだろう。
本日の全社員の業務は、改めて社長の指示を仰ぐまでもなく、昨日の続きの出荷作業だ。誰も起こしに来ていないということはつまり、無事その形で始まっているということだ。
窓の外枠には、また新しく雪がこびりついていた。昨夜も降ったり止んだりをくり返していたが、一段と積雪を増したらしい。
今日の出荷完了は厳守。社長としては、午前中に雑誌の打合せ。頭に予定を反芻しながら、改めて手帳も確認する。まちがいない。
そう言えば。桐川は思い出していた。いつも秘書役の二野宮が、今日は休みのはずだ。午前十時半に駅前のホテルでゲーム雑誌の編集長と会う。そういうときの慣例で連れていく秘書役が、今日はいないことになる。
別に、一人でも構わないのだが。ここ数年習慣にしていた形を後退させるのは、妙に躊躇われた。気にすることもない気はするが、何となく会社、あるいは社長の格を落としてしまう、というような。
誰でもいい。形だけでも、連れていくか。思いながら、桐川は腰を上げた。
洗面所で顔を洗い、服装を整えて事務所に入った。予想通り、出荷作業で全社員はほとんど修羅場の様相だった。ここから一人を連れ出すのは無理か、と桐川は思い直していた。
「あ、社長」これも手を動かしていた黒辺が、振り向いた。「お早うございます」
「お早う」やや決まり悪く、桐川は笑いを返した。「遅れて、済まない」
「そっちはそっちで徹夜だったんでしょう? そのまま休んでいただこうと思ったんですが、例の打合せがあるので、そろそろ呼びに行こうかというところでした」
「いろいろご配慮ありがとう、だな」
ざわざわと、行き交う社員たちの喧噪は切れ間ない。
しかし。少しばかり違和感を覚えて、桐川は室内を見回した。
「ちょっと、あんた、寄らないでよ」
「わ、すみません、すみません」
「こら、触るな、それ」
「わ、わ、すみません、すみません」
「おい──あれ、え、え──どうなった、これ? 何処いった?」
「わ、わ、わ、すみません、すみません、すみません」
何だ?
桐川は首を捻った。修羅場とは言っても、職員たちにとってはやり慣れた工程の作業だ。これほどに怒号や詫び声が飛び交うのを、これまで聞いた記憶がない。
「おい、あれ? 何だ、消えてるぞ、このデータ」
「え、え、わ、すみません──でも、何も触っていませんですよ」
「ああ、いいから下がっていてくれ」
怒号の方は、とりどりながらいつも見慣れた部下たち。詫びの声をくり返しているのは──
見たことのない若い女だった。
黒いショートヘアに、青縁の眼鏡。手脚が不自然なほど細長く、何処かカトンボを連想させる。それが、忙しない社員たちの間をじたばた右往左往していた。
「何だ、あの女は?」
振り返って訊ねると、黒辺が顔をしかめた。
「いえ、あの──少し前に聞いていたでしょう、正内さんの知り合いの紹介で、見習を入れたいって話は」
「ああ──言ってたな。来るの、今日だったか?」
「だったようです。僕も失念していましたが。で、見ての通り今日はゆっくり仕事を説明する余裕もないので、ごく簡単な作業を手伝わせていたんですが」
「見るからに、邪魔にしかなっていないようだな」
「本当に、シール貼りなんていう子どもでもできる作業をさせていたはずなんですよ。しかし、ものの三十分もたたないうちに、あの有様で」
「その作業で周りに悪影響できるなど、ある意味才能かもしれないな」
「はあ……」
一つの机の上に、発送用のシールを貼る道具一式が並べられている。その前で作業していた女は、何かの拍子で一歩下がったまま、周りの喧噪に流され押されて元の位置に戻れなくなっているようだ。
どんな不器用、要領が悪いんだ、あいつは。遠くから見て、桐川は首を捻っていた。
それに、さっき何か、物騒な言葉が聞こえていなかったか? 何処でもそうだろうが、とりわけソフト開発会社にとって、パソコン内のデータは命より大切なものだ。誤って電源を落とすなどしてそれを消してしまったら、取り返しのつかない事態を招くこともあり得る。
顔をしかめて、桐川は黒辺に声をかけた。
「二野宮の代わりの秘書役、誰でもいいから一人連れ出そうと思っていたんだが」
「ああ、はい」
「どう見ても、あの見習しかいないようだな、適任は」
「はあ、確かに」黒辺は何とも言えない苦笑いになった。「連れ出してもらえば、周りも助かりそうですが。今度は、社長の方の足手まといになりそうですよ」
「こっちは、黙って立たせているだけでもいいだろうからな」
こちらから見た限り、作業用に軽装の他の社員に混じって、当の新人はリクルート用の紺のパンツスーツのようだ。その意味でも見てくれの上では他より適任と言える。
「じゃあ、お願いします」黒辺は、真顔で見返した。「連れていってください」
「分かった」
「おおい、臼月君」
黒辺が、手を挙げて呼ばわった。
「あ──、はいい──」
裏返った声を返して、青縁眼鏡の女が顔を上げた。
「こっちへ来てくれー」
「は──いい──」
ショートヘアが、隣の職員の陰に一瞬消え。
「わ、すみません、すみません」
「こら、触るな、それ」
「わ、わ、すみません、すみません」
ひとしきりの詫び声と怒号をくり返し、次第に近づいてきた。
「すみません、すみません──」
すぐ前の大柄の社員の陰から、にょっきりお河童(かつぱ)の丸顔が覗いた。
「はは、は、はい──来ました、です」
「落ち着きなさい」溜息をついて、黒辺が言い渡した。「紹介していなかったな、こちら、うちの桐川社長だ」
「は、はい──社長さん?」
素っ頓狂な声とともに、頭が九十度程度下がった。
「臼月トウコです」黒辺が、桐川に告げた。「臼月君はこの後、社長にお供しなさい」
「は、はい──」
もう一度、桐川に向けて頭が下がる。
「よろしくお願いします、です、でした──」
何ともわけの分からない喋り方、だ。桐川は、顔をしかめた。齢(とし)は二十を超えたばかりというところ、だろうか。おそらくは敬語の使い方も分からず、初めての場所で混乱しまくっているということだろうが。
言葉遣いを教えるだけで、かなり難渋しそうな人材だ。社員年齢層の低い会社ということもあって、せめて外部に対して薄っぺらに見られないようにと、日頃から桐川は社員に言葉遣い、応対の常識を外れないよう指導を徹底してきていた。その点で、使い物になるまでにかなり手間がかかりそうに思える。これも何処の会社でも似たり寄ったりだろうが、新人にまず期待されるのは確実な電話応対ということになるのだが。いくら会社の現住所が「おばんでした」の土地柄とは言え、「よろしくお願いしますでした」はさすがに通用しないだろう。
「マスコミ関係の人と会うのに出かけるが」桐川は、注意を与えた。「お前は、黙って従っていればいい。声は出すな」
「は、は、は、はいい──」
返事一つをとっても、指導が必要なようだ。とりあえず今日は、「声を出すな」を徹底するしかなさそうだ。
「五分ほど外を歩くことになる。上に着るものを持ってきなさい」
「は、は、はいい──」
ばたばたと足音高く、ロッカールームへ駆け出していった。
「は」が一回分減ったことを、向上と考えていいだろうか。
ばたばたと両手を振り回し、ロッカールーム方向へ向き直る。その拍子に引っかけられた机の上の書類が雪崩れ落ちそうになって、慌てて黒辺が押さえていた。
「まったく──」小柄な総務担当は、思わずのようにぼやいた。「昨日から碌なことがない。今日の作業も油断していると、何が起きるか分からんぞ」
「あ、でもお──」いきなり、新人女が振り返った。「悲観的、ダメですよお。自分を信じる──諦めちゃダメ、です」
「はあ?」
黒辺が目を丸くしているうちに、紺のスーツ姿は作業人員の群れに紛れて見えなくなっていた。『お前がそんなことを言うか?』明らかにそんなことを言いたげな総務担当の口元に、出かけた言葉は宙に浮いて取り残された格好だ。
苦笑混じりに首を捻って、桐川も脇に置いていたコートを持ち上げた。
「あれ?」溜息をついた黒辺が、揃え直していた書類の陰を覗いて声を上げた。「こんなところにあった」
ひょこりと摘まみ上げたのは、桐川も見覚えのある日頃この男がよく使っている万年筆だ。
「よかったじゃないか、見つかって」
「昨日から運気下降線かと諦め感覚だったんですが、少しだけ持ち直した気分ですね」
「だといいな」
面白くない出来事が続く中で、確かにささやかながらも朗報と言えそうな話題だ。このままうまく事が運べばと思いながら、古馴染みの部下と桐川はわずかな笑いを見交わした。
行き先は駅南口すぐのホテルなので、駅舎内のコンコースを通って歩く限り、ほとんど外の風に当たることもない。北口の階段を昇り、改札口を右手に見て歩きながら、桐川は新人の女に確認した。
「正内の紹介と聞いたが、知り合いなのか?」
「あ、あ、いえ──」
細長い手脚を鯱張らせながら横を歩く白いダウンコートの女は、前方を直視したまま応えた。
「存じ──知り──知らない、でした。その──知り合いの知り合い?」
「つまり、直接正内は知らないわけか」
「は、はい──」
また、「は」が一回分減った。この次は「はい」だけになっていればよいが。
「お前──臼月だったか。何でうちの会社を希望したんだ?」
「は──その──御社の実績と将来性に魅力を感じ──」
「自分の言葉で言え」
「ふあ、や、その──」隣で、視線が天井に泳いだ。「ゲーム作りが──面白そう、だから?」
疑問形になってやがる。
「そもそもお前、うちでどんなものを作っているか、知っているのか?」
「は、はいい──」
残念。今度は減らなかった。
「その──御社のホームページは隅から隅まで拝見──」
「ホームページか」
実際にゲームに触れたことはないらしい。
「特に社長さんのブログは、熟読され──させ──いただき──」
「あれか」
思い返しても、載せているのは業務に関係ない雑文がほとんどだ。
「確か、五年分くらいあるはずだが」
「はい──全部熟読──面白く──」
そんな時間があったら、他の勉強なりできるだろうに。軽く、桐川は首を垂れた。
「お前何か、特技とか、この仕事への適性みたいなのはあるのか?」
「え、と……特技……」また、視線が天に泳ぐ。「……自分の気配を消せる?」
「そんな特技、仕事の役には立たん」
頭が痛くなってきた。
南口の階段を降りる。目的のホテルは、すぐ先に見えてきていた。積雪の地上に降り立った、ところを測ったように、懐に小さな電子音が生まれた。スマートフォンを取り出してみると、会社からの着信だ。
「何、どうした?」
耳に当てると、黒辺の声が返ってきた。
「済みません、つい今、その編集長の相馬さんから連絡がありました。申し訳ないが、伺えない。新千歳空港の積雪で、飛行機が降りれないそうです」
「何だ、そりゃ」
「本日の予定はキャンセル、追って改めて相談したいということです」
「飛行機の都合って、もっと早く連絡を寄越せそうなもんじゃないか?」
「ですよねえ。先方もその点は恐縮していましたが、雪害というものの経験がなくて要領が分からなかったと」
「それにしてもしかし──まあ、ここで愚痴を言ってもしかたないな。戻るか」
「ああそれと、もう一件なんですが。警察から連絡がありました。昨日の笠置という刑事が、社長と話したいと。出かけていると応えると、行き先を訊かれたので、答えました。そうしたら、これからそこの南口の方へ行くということです」
「何だ──?」
桐川は、顔をしかめていた。
「分かった。この辺で会わなかったら、無視して戻る」
通話を切る。すぐ後ろで、臼月はきょとんと立ちつくしていた。
「キャンセル、だってさ」
肩をすくめて、桐川は辺りを見回した。通話しながら無意識に数歩前へ進んでいたようで、立っている位置は駅前の交叉点、横断歩道の手前だ。向かいに目をやると。背広にコート姿のずんぐりした小男が、信号待ちしていた。ばっくれるのは、無理のようだ。
信号が変わり、すぐにこちらを見つけたようで、笠置刑事は片手を挙げて足速に横断してきた。
「どうも済みません、会社に電話したらこちらだと言うので。ちょっと話、いいですか?」
「何か、ありましたか?」
「寒いですね。ちょっとこの上、行きましょう」
階段を上がって駅のコンコースへ戻ると、壁際に灰皿を置いたら喫煙所になりそうなちょっとした空所があった。
「いや、札幌から短期応援に来ている身分なので、この辺に詳しくないんですがね」
言い訳じみた断りを入れながらそちらへ寄って、四角顔の刑事はひょいと桐川の背後を見た。若い女が黙ってついてきている。
「ああ。今日から見習で会社に来ている、臼月といいます」
紹介すると、笠置は頷いた。
「ああ、なるほど。道理で、昨日はお見かけしなかったわけですな。刑事課の笠置です」
刑事の会釈に、臼月はただ困ったようにぴょこんとお辞儀を返した。
「で、何でしょう」
「いや、やっぱりいろいろ調べるとですね」笠置は頭をかいて応えた。「どう見ても、亡くなった正内さんと一番親しいのは桐川さんということになるようで」
「それは、そうかもしれませんね」
「それで、相談したいんですわ」
「しかし、あれは正内がうっかり寝込んだという事故なんでしょう?」
「何ともまあ、そこは」
「何かおかしなことでも見つかったんですか? やっぱり、事前にあいつが縛られてでもいたとか」
「そんな形跡はありませんでした、やっぱり」
「睡眠薬とか、何か薬を飲まされていた?」
「そんなものも検出されませんでしたね。かなりの量のアルコールだけです」
これ見よがしに、桐川は溜息をついた。
「それだけじゃあ、やっぱり事故としか思えないでしょう」
「まあそれでも、少し知恵を貸してもらえませんか。どうにも、あの一昨日の夜の彼の行動、疑問がありまして」
「何でしょう」
「彼が、どうやってあの登良遠の町内会館まで行ったか、なんですがね」
「あ、あ、登良遠町内会館?」いきなり、隣の女が手を挙げていた。「行ったこと、あります、です」
「お前は、口を出さなくていい」
「は、はいい──」
「どうやってって──」改めて、桐川は刑事に応えた。「駅から歩いて、じゃないんですか? 駅から家までいつも歩いて帰る途中、と聞きましたが。せいぜい歩いて十分かそこらなんでしょう?」
「まあ、そうなんですが」薄い苦笑いで、笠置刑事も続ける。「そうだとすると問題なのは、登良遠駅までどうやって行ったか、です」
「JRで、じゃないんですか? ここから一駅ですよね」
「ええ。札幌行きの普通列車で苫小牧発二十一時五分というのがある。登良遠着は二十一時十二分」
「ちょうどいいですね。駅前の一次会終了で、みんなと別れたのが二十時五十分頃。真っ直ぐここへ来て、その汽車に乗ったと」
「それがあり得ないっぽいんで、困っているのです」
笠置は、また頭をかいた。
「あり得ない? 何故です」
「ここで乗車するには、その改札に入るしかないですわな」コンコースの先、中央付近左側の改札を指さす。「それには、絶対この通路を通ります」
「そう、ですね」
悪い予感が、桐川の背筋を冷たく昇り出していた。
「詳しく教えるわけにはいかないんですが、この通路には何箇所か、防犯カメラがついているんです」
「それを、調べたんですか?」
「はい。特に改札口向きのカメラは、ずっと全部の出入りを撮(うつ)している。少なくともあの夜二十時四十分から二十一時十分の間、正内さんの姿格好に該当する客はどのカメラにも映っていません」
ふう、と桐川は息をついた。熱心に調べたものだ、この刑事。
「そこの辺り、絶対見落としなどの可能性はないわけですか?」
「ですねえ。カメラの死角はない。正内さんがよっぽどそれと分からない変装でもしたら、別ですが。知り合いも見ていないところでそんな悪戯(いた ずら)をしそうな性格ですか、彼は?」
「ないでしょうねえ、あいつにそんな嗜好は」
「だとしたら」わざとらしく、刑事は首を傾げた。「彼は、いったいどうやって現場まで行ったんでしょう?」
「普通に考えたら、タクシーですか。あいつはあの晩、いつにないほど酔っていた。歩き通す自信がなくなったと」
無駄だろうなと思いながら、桐川は案を出してみた。
「今のところ、そのようなタクシーは見つかっていません。市内のタクシー会社、個人も含めて全部当たりましたが」
やはり。桐川は、内心肩をすくめた。
「とすると、分かりませんね、私には」
「でしょう?」
笠置は片目を細めた。
「とりあえず、登良遠に二十一時十二分着のJRに乗っていたということなら、まあ不思議はないんですがね。駅から歩いて十分程度、千鳥足なら二十分近くかかるかもしれないくらいで現場。あの町内会館付近は普段は人通りも結構あるんだが、あの夜は二十一時五分のアイスホッケーの試合開始から後は、ほとんど外を歩く者もいなかったようだ。ただ一人、あの裏を回って遅れて会館に来た人がいました。落雪の前だから、あそこに何か転がっていたら気がついただろうと言っている。それがだいたい二十一時二十五分。正内さんがあそこに転がったのはだから、二十一時二十五分から四十二分までの間と考えられます」
「四十二分というのは、屋根の落雪の時刻ですか」
「ですね。日本チームが最初にゴールのチャンスを得た直後ということで、ほぼ正確に出ています」
「だから、JRを降りて歩いてちょうどくらい、と」
「そうなりますな。ああ、さっきのタクシーを拾ったという説。もしそうだとしたら家まで行かずにあの会館辺りで降りたというのも不自然だし、ここからあの現場まで車だと冬道で安全運転したとしてもだいたい十五分で着きます。みんなと別れてすぐタクシーを拾ったとしたら、二十一時二十五分より早くあそこに着くことになりそうですな」
「そう、なりますね」
「さて、それで分からない。彼はどうやって現場まで行ったんでしょう?」
「私に分かるわけ、ないじゃないですか」
顔をしかめて、桐川は横を向いた。
「怖い顔しないでくださいよ、相談しているだけなんだから」
笠置は、苦笑いになった。
「社長さん、いつもそんな怖い顔なんですか?」
「そんなこと──」
「社長さんは、怖い人じゃないですよお」
いきなり、思いがけない素っ頓狂な声が割って入った。刑事も虚を衝かれたように、視線の向きを、神経質にも見える素振りで変えている。
もちろんこの場にいたもう一人、すぐ後ろに待機して忘れ去られていた桐川の連れ、新人女だった。
「社長さんこう見えても、お茶目なところだってあるんですよお」
胸の前に両拳を握りしめて、声に力を込める。こちらに味方してくれているつもり、らしいが。
桐川は、困惑で瞬きを忘れていた。
この今日初対面の女に、俺の何が分かる?
「社長さんのブログで読んだです」
桐川の疑問が聞こえたように、臼月は力を込めて断言した。
「社長さん、学生時代から結構悪戯もしていたって。得意技は、宴会で水割りに見せかけて烏龍茶飲んで酔った振りすることだ、です。二時間くらいの宴会なら、まずばれずに通せる、です」
「はあ?」
そんなことブログに書いたっけか。いや、こいつが知っているということは確かに、何処かに書いたんだろうが。
「そして自分は酔った振りして素面で、誰かにこっそりアルコール濃くしたの飲ませて酔い潰す、です」
きょとんとしたまま、刑事は黙って桐川の顔を見た。
「学生らしい、お茶目な悪戯、です」
得意げに、新人は結論づける。
「お前──」
重々しく、桐川は溜息をついた。
「こんなところで、そんなどうでもいい話、するな」
「あ、は──」
「それから、外の人に対して、社長に『さん』付けするな。非常識だ」
「は、は、はい──」
「分かったら、下がっていろ、お前」
「は──」
目を丸くしたカトンボがぎくしゃくと後退して、視界の外に消えた。
溜息を残したまま、桐川は刑事に向き直った。
「冗談ですよ、今のは」
「ああ──」きょときょと、落ち着きなく笠置の目が動いていた。「しかし、すると──」
「何だって言うんです?」
「いや、話を戻すと──」決まり悪げに、笠置は苦笑に戻った。「彼が現場まで行った方法で一番もっともらしいのは、誰かの車に乗せられて、ということになりますな」
「そんな──断言できますか?」
「しかし車だと、今タクシーについて言ったと同じく、実際より早く着きすぎてしまう可能性が高い」
「そう、なりますね」
「ここでもし車の運転手に意図があって、本来JRで行った場合の時刻に合わせようと考えたとしたら、遠回りするなり時間稼ぎをして、現場に二十一時二十五分頃着くのが妥当ということになる。さらにそうして着いた後、二十五分頃に通行人があったのをやり過ごして、それから被害者を現場に転がしたとしたら、ちょうど話が合う」
「それは、うまくいきすぎでは?」
「しかしこれなら、実際起きたことと矛盾はなくなりますな」
桐川は、溜息を返した。
「まあ、一つの仮説として成立しそうだというのは認めましょう。そうすると、その仮説に合う犯人は、二十一時二十五分に車で現場に行くことができた人物、ですか」
「そういうことでしょうな」
「ということはやはり、うちの関係者は除外されると思っていいんでしょうね」
「う──ん……」
微妙な表情で、笠置は無精髭が浮きかけた頬を撫でた。
「そう、言い切れないわけですか?」
「まあ、現状では何とも……ね」
横に逸れかける刑事の視線を、桐川は正面から見返した。
「正直に言ったらどうなんですか、刑事さん」
「ん?」
「関係者の中で、刑事さんは私を疑ってここへ来ているんじゃないんですか?」
意を決して、視線を固定して。
「想像ですが、その二十一時三十分前後の時間、一人でいたのが私だけだとか。他の社員は二次会の最中、帰った数名は皆家族と同居で門限のある若い女で、その頃には帰宅していたでしょうから」
「まあ──」
唇を曲げて、刑事は肩をすくめた。
「そんなところですな」
「しかし私だって、二十一時四十分過ぎに自宅で従兄から電話を受けているんですよ。さっきから聞いている刑事さんの手際のよさからして、もう従兄から確認はとっているんでしょう?」
「それは、はい」
「私もアルコールが入っている状況だったから正確に細かくは覚えていませんが、自宅の固定電話を受けたのが二十一時四十分過ぎというところだったと思いますよ」
「二十一時四十四分というところでしょうな。従兄の新嶋さんの話では、電話中にアイスホッケーの試合で二度目に日本がゴールチャンスになった。電話が繋がったのは、一度目と二度目のチャンスの間と」
「そうでした」
「そこで新嶋さんが車で迎えに来る約束をして、この駅前で桐川さんを拾ったのが二十二時十分頃。これも新嶋さんが車載テレビでアイスホッケーを観ていて、第三ピリオドが始まる前のインターバルの時間だったと。何ともアイスホッケーのお陰であちらこちら時刻がはっきりして、大助かりですな」
「まあ、そうですね」
「だから、あなたが問題の時刻に現場にいたと考えるのは難しいのはまちがいないわけですがね。しかし気を悪くしないで客観的事実として聞いていただきたいんですが、あの時刻現場にいた可能性がまあわずかにもある関係者ということになると、一番に最有力候補になるのがあなたであることは確かなんですよ」
「まあ──」渋い顔を、桐川は横に振った。「そういうことになるのは、分かりますがね。それでも、あり得ないということは認めていただきたい」
「さっき言った、正内さんを車で運んだ人物がいたとしたら、ですがね」気にしない様子で、笠置は続けた。「まず一次会の終わった九時前頃に車が用意できていて、正内さんに怪しまれずに乗車させることができた人物ということになる。まさか正内さんが駅に向かう途中で酔い潰れて意識のない状態なのを、無理矢理乗せたということはないでしょう。あの時刻は人通りが多かったはずで、そうなったらまず誰かの記憶に残ってしまう」
「まあ、そうでしょうね」
「桐川さんの自車の駐車場は、この駅のすぐ近くだということですよね。自宅マンションも、歩いてすぐ」
「それは、そうですが?」
「酔いの回った正内さんに『そんなに酔っているんじゃ歩くのは無理だ、車に乗せてやるから待っていろ』と言って待たせておいて、車を持ってくる。怪しむことなく乗車させる、ということができる一番の候補は、まちがいなくあなたでしょうな。これが計画的なものだとすれば、一次会で自分は酒を飲まない、相手には普段以上に飲ませる、ということが必要になりますが、偶然ながらさっき、あなたにそういうことができるということが判明した。もしかすると桐川さんの『酔った振り』の技を正内さんも知っていて、『実は今日これから従兄の家に行く予定があるから、俺は飲んでいないんだ』と言えば、信用されたかもしれない」
「凄い想像ですね。しかし──」
「ええ」笠置は苦笑いで頷いた。「そこまでは想像が当てはまるんですが、後ろの方が無理くさいんですよね。二十一時二十五分過ぎに現場で作業をしてそれから急いで戻ってきたとして、自宅で二十一時四十四分に電話に出るのは、ほとんどぎりぎりだ」
「それも、忘れてもらっちゃ困りますけど」渋い顔で桐川は口を入れた。「その二十一時四十四分というのも、たまたまですからね。従兄とは、別に電話を受ける時間を示し合わせてあったわけじゃない。九時頃にはおそらく宴会が終わるから、その後なら何時でもいいから従兄の都合が可でも不可でも電話をくれ、ということにしてあったんです」
「確かに、新嶋さんもそう言っていましたね」
「だから私は、九時過ぎにはいつ自宅に電話がかかってくるか分からない、という状況にいたわけですよ。そんな離れた場所で犯罪行為をしていて、帰る前に電話がかかってきて留守がばれたとしたら、それで墓穴を掘ってしまうことになるじゃないですか」
「そういうことになりますねえ」
溜息をついて、刑事はわずかに横を向いた。
「それに、二十一時二十五分頃から酔っている男を雪の上に転がして、手足に雪を乗せて動けなくして、偶然屋根から落雪があるのを待つ、ですか? 時間的にも忙しすぎるし、不確実極まりないし、無茶苦茶じゃないですか。昨日も話をしていましたが、マフラーが猿轡のようになっていたというのも、偶然なわけでしょう? ただ口に噛ませて結びもしないで置いていたんじゃ、いつずれて大声を上げられるかも分かったものじゃない」
「ですなあ」笠置は軽く首を振った。 「マフラーは、軽く結んであったのが結果的に緩む、ということが起きただけかもしれないが」
「軽くなんて、そんな大変なときにいい加減なこと、やりますか?」
「あ、でもお──」
いきなり、後ろから声が割り込んでいた。
「それ、固く固定、できますですよねえ」
首を折って。それから桐川は、背後を覗いた。
「下がっていろと、言ったはずだが?」
「あ、はいい──下がりました、です、よ?」
足元を見ると、カトンボ女の位置は──確かにさっきより一歩程度下がっている、か?
「固定できるって、どうするんだ?」
正面から、目を丸くした刑事が問い返した。
「雪に半分埋まってた、ですよねえ」カトンボ女は、両手を顔の横でぱっと開いた。「雪の固まりか氷みたいの二つ用意して、濡らした雪を挟んで押さえれば、すぐくっつくです。それでその、マフラーですかあ? 頭の後ろで押さえたら、動かないです」
桐川は、頭の中が白く霞む感覚に襲われていた。
「なるほど」刑事は頷いた。「埋まっていた人を掘り出すときに、マフラーに氷がついていたくらいは気にしないで剥がしてしまったかもしれないな」
「でしょう?」
自慢そうに、笑いになっている。
こいつ、社長の足を引っ張っている自覚はないのか?
細かく頭を振り、深呼吸して、
「そんな当てにならない仕掛け、しますかねえ」桐川は口を入れた。「それにそんなことしていたら、ますます時間が浪費される。少なくとも、電話の時間が気になっている私なら、ますますあり得ないですよ」
「ですねえ」笠置も、顔をしかめた。「自宅で電話を待つ必要があるなら、ですねえ」
おそらく、話はこれで終わらない。桐川が思っていると、まだ諦めない輝きの横目が、戻った。
「しかし──」
ためを作って、刑事は続けた。
「最近は便利なものがありますよね。自宅の固定電話に、自動で携帯に転送するという機能がついていたりする」
やはり、食いついた。
ゆっくり瞬きをして、桐川はそれに応えた。
「それは──」
「いえ、それ、ダメダメですよお」
また後ろから割り込みがあって、桐川は前にのめりかけていた。
「いや、ダメダメとは?」
その声の主に、目を瞠って刑事は問い返した。
「その、固定電話の携帯への転送、ですう。電話の転送機能だと、転送した通信記録、残ってしまう、です。後で電話会社調べたら分かってしまう、です」
まあ、概ね桐川の言いたい通りのことを言ってくれていた。そうしてみると、この役立たずとしてはすこしばかり有益な発言を初めてした、と評価してもよさそうだ。こんなトンデモ女さえ気がつく穴を、桐川が意識せずに実行したとは、刑事も考えないだろう。そういう意味でむしろ、桐川本人の説明より説得力があるかもしれない。
「でもお、その代わりい──」
──? まだ、続きがあるのか?
「電話回線をパソコンに繋いであれば、インターネット経由でスマホやノートに自動転送するシステム、ありますですよお。これなら、電話会社の方に記録、残らないです」
桐川の頭の中が、ますます白く澱んできた。
「ほう」刑事は目を丸くした。「そんなものもあるのかい? それで、固定電話と同じように通話できる?」
「そういう宣伝だったです。よく聞けば少しくらい音の違いあるかもしれないですけどお、周りうるさかったりとかしたら、分からないんじゃないかと思うです」
「ほう」
笠置は、ちらと桐川の顔を見た。
「電話中、新嶋さんの家ではテレビが鳴っていたそうでしたな」
重く、息を吸い直し。黙って、桐川は肩をすくめた。
「で、そのシステムなら記録が残らない? パソコンのハードディスクから消してしまえば終わりということになるのかな?」
「そうですう」にっこりと、臼月は応えていた。
「それでも、専門家に消去の跡を調べさせれば、何か痕跡ぐらいは見つかるかもしれないな」
「ですねえ」
ゆっくり、桐川は後ろを向いた。
「おい」
「はい?」
「ちょっと、来い」
「は、はいい──?」
「ちょっとだけ、失礼」
刑事に断って、桐川は新人部下の肩を押した。少し離れた階段脇へ寄って、きょとんとした丸顔を睨(にら)み下ろす。
「お前は今仮採用の身分だがな、会社の利益に反する行為をした者は採用を取り消す、という条文がある。もちろん、社長の不利益というのも同義だ」
「ひゃ──」
「何が利益か不利益か、判断つかないことが多いと思うからな。余計な発言をするな。黙っていろ」
「は、はい──です」
「いいな」
言い置いて、刑事の横へ、戻った。
「失礼しました」
「はあ」苦笑で、笠置は頭をかいていた。「大変ですな、社長さんも」
「お陰様で──と言うのは、おかしいですか」
「いろんな面を検討しなければならないのはまちがいないところですが、まあとにかく」ますます苦笑を深めて、肩をすくめる。「有益な会話のお陰で、少し状況が見えてきましたな。少なくとも可能性としては、あなたが現場にいることはあり得ることになる」
「こじつければ、という程度じゃないですか。さっきから指摘しているように、最初から最後まで不確実、偶然に頼りすぎている。そんないい加減なこと、少しでもものを考える奴なら、計画的にやるもんですか」
「ですな」頷いて、刑事は認めた。「しかしですね、私の想像通りなら、この犯人の計画はかなり流動的に作ってあった気もするんですわ」
「どういうことです?」
「被害者と長年の付き合いがあって、どのくらい酔わせれば寝込んでしまうか見当がついていたかもしれない。しかし酔っているところを車に乗せたとしても、睡眠薬もなしに絶対寝込んでしまうかの確信は持てないはずだからね。首尾よく車の中で正体なく眠ってしまわなければ、計画は中止にしたかもしれない。寝かせた場所もいくつか候補を考えていて、今にも落雪が起きそうな場所ということでその場で決めたのかもしれないが、それだって絶対落雪するという確信はなかったはずだ。うまい場所が見つからなければ中止にしたかもしれないし、もしかしたら落雪がなくても凍死させれればいいというつもりだったかもしれない」
きろ、と刑事は桐川の顔を覗いた。
「あなたは、不確実、偶然に頼りすぎている、と言うがね。絶対あの夜決行しなければならないという切羽詰まった事情がなかったとしたら、その程度の流動性で動き出すことはあったんじゃないかと思う。とにかくこの犯行──犯行だとしたら、だけどね──都合が合わなければ何処ででも中止できそうだし、被害者を雪に固定しているところを目撃されるか、そこにいたという証拠を残したかしない限り、後から何とでも言い抜けができる格好だからね。一番極端な話、眠っている被害者を車から降ろして雪の中に運ぶ途中で目覚めて暴れ出されたとしても、酔ったお前が具合悪そうだから介抱していたとか、そんな言いつくろいだってできるに違いない」
黙って、桐川は相手を睨み返していた。
「まったくの想像だけでも加えさせてもらえば、ですね」視線を逸らさず、笠置は続けた。「たとえ犯人がずっと電話を待つ態勢を続けていなければならない状態だったとしても、この流動性の中では何とか対処できたでしょうな。誘いの電話が後始末に間に合わない早いタイミングでかかってきたとしたら、やはり犯行は中止して、正直に友人を送る途中だから少し待ってくれと言えばいい。結果として二十一時四十四分という電話は一番好都合なタイミングで、ひと通りの作業が終わった後で受けたことになるんじゃないか。現場近くで受けたとして、それから駅前の駐車場まで車で戻って、用意していたウイスキーの小瓶でもあおって酒臭い息で迎えに来た車に拾われる、というのが十分可能でしょうな」
もう一度、桐川は相手を睨んでいた。ややあって、目を逸らし。
「馬鹿馬鹿しい。想像がたくましいと言うか」
肩をすくめ、大きく息をついて桐川は唇を曲げた。
「それにしても、今刑事さんも認めましたね。さっきからいろいろ当て付けがましく言っているが、私が現場にいたという証拠もなく、犯人扱いはできませんよね」
「それはそうですな、確かに」小刻みに頷いて、刑事は認めた。「まあ方針は見えたので、地道に証拠を探していくことにしますわ」
「それでは頑張ってください」桐川は、もう一度肩をすくめて見せた。「ああそれにしても、さっきハードディスクがどうのと言っていましたが、その程度の臆測で我が家のパソコンを調べに来るなり、そんな令状みたいの、下りるものなんですか?」
「難しいかもしれませんな」刑事も、肩をすくめた。「しかし難しくても、何でもやってみるしかないかな」
「正直に教えてくださったお礼に、無駄骨になる前に断りを入れておきますが」
片目を細めて、桐川はわずかに笑った。
「つい先日、うちのハードディスクが一個いかれてしまいましてね。腹立ち紛れに破壊して、燃えないゴミの回収を待っているところです。これ、別に法に触れていないですよね?」
「そうですな。現時点で、とがめる理由はない」軽く、笠置は両手を挙げて開いた。「ここではこれ以上、打つ手なしかな。別に今日ここで決着をつけるつもりもなかったんで、どちらかというと思った以上の収穫でしたが」
「それは──よかった、とお応えすればいいんですかね」
「まあ、またお会いします」
ひらひらと手を振って、刑事は階段に向かった。
「当分は諦めませんので、よろしく」
「二度とお目にかからないことを、願っていますよ」
「それは多分、無理ですな」
両手をコートのポケットに入れて、笑って刑事は歩き出した。
粉雪交じりの風が吹き上がってくる階段に、履き古した革靴が、かつんと下ろされた。
予想外に、攻め込まれたが。何とかこのラウンドは、イーブンというところだろうか。
ひととき安堵して、桐川は逆方向に向き直った。
ところへ。
脇をすり抜けて階段方向に駆け寄る、白い影があった。白い──ダウンコート?
慌てて、桐川は振り向いた。
階段数歩前に、両脚を踏ん張って。
「お待ち──待た──待ってほしい、です」
刑事の背へ向けて、カトンボ女が声をかけていた。
何をする気だ? こいつ。
数段下りたところで、笠置が振り向いた。
「何だい?」
「社長は犯人じゃない、です」
「──そう──かね」
「証明できる、です」
「何を言ってる、お前?」
ようやく、桐川は声をかけていた。
「証明?」
ゆっくりと、笠置は階段を昇り直してきた。
「ここで説明できるってのかい」
「はいい──です」
「聞こうか」
「は、はい──」
犯人じゃない証明──だと? 聞こえる意味合いは、ありがたいが。
桐川は眉を寄せて、考えた。
──悪い予感、しかしない。
「どういう証明だね?」
問いかける刑事を、青縁眼鏡の女は真っ直ぐ見返している。
「社長のブログ、読んだです」
「──またかい!」
期せずして、桐川と笠置の言い返しが、重なった。
しかし臼月は、怯む様子もなく続けた。
「去年の夏のことだ、です」
ちらと顔を見合わせて、桐川と笠置は無言で続きを待った。
「サッカーのワールドカップ予選が行われていた、です。社長はマンションで夜中、仕事をしていた。そしたらサッカーのテレビ中継が夜中あって、マンションの上下左右の部屋が騒ぎまくって、窓を閉めていてもうるさくて仕事にならなかった、書いていた、です」
「ああ」思わず、桐川は反応していた。「書いたな、そんなこと。それがどうした?」
「一昨日は、アイスホッケーがあったです」
「あったな、確かに」
「サッカーとは違うけど、上下左右全部じゃなくても、きっと何処かは大騒ぎしていたです」
「まあ──」笠置は頷いた。「苫小牧では、その可能性は充分高いだろうな」
「どんなふうに騒いでいたか、社長が思い出して、そっちの家の人と突き合わせれば、社長がそのとき部屋にいた証明、なるです」
「な──」
ゆっくりと、桐川の頭の中に、白いものが広がってきた。
何だって──?
何を言った? この女──。
向かいで、笠置刑事も真剣な顔で考え込んでいる。
「証明、なりますですよね?」
えへん、とばかりに臼月は、薄い胸を張った。
「臼月──」
「はい?」
「失せろ」
「は?」
「俺の前から、消えろ」低い唸り声を、桐川は絞っていた。「二度と顔を見せるな!」
「え──え?」
「聞こえないか!」
拳を持ち上げると、
「ひゃ──」
後退るや、カトンボ女は、二十センチ程度真上にぴょんと跳び上がった。
「わ、わ、わ──」
そして、慌てて階段に向けて駆け出す。
「すみません、すみません、すみません──」
転がるように駆け下り、
下り、下り──。
黒いお河童頭が、階段下に。
──消えた。
ふうう、と息をついて。桐川は、目を戻した。
刑事は、難しい顔で考え続けている。
「従兄さん、新嶋氏が──」きろ、と鋭い目がもたげられた。「あの日の電話の件、結構細かく覚えていて、話してくれたんですがね」
「………」
「あの日の桐川さんは、電話の後ろでテレビの歓声が聞こえるまでアイスホッケーの試合を忘れていたようだった。少なくとも、そのとき聞こえたゴールチャンスのシーンとその直前のシーンは、知らないという返事だった」
「……覚えて、いませんが……」
「もしそのとき部屋にいて、直前に隣から歓声が聞こえたとしたら、気づいていないはずがありませんな」
「……さあ」
「まあ、ご近所に話を訊いてから、改めて確認させてもらいますか」
「しかし──」桐川は、唸った。「もしのもし、万が一、そうだったとしても──それで私が現場にいたという証明にはならないでしょう」
「それは、そうですな。部屋にいなかった可能性が高いというだけで」
「犯人扱いは、できませんよ。私が現場にいたという証拠でも出ない限り」
「それは、そうでしょうな」
数度頷いて、刑事は両手をポケットに戻した。
「まあそれでも、一歩前進、かな」
苦虫を、桐川は噛み潰した気分になっていた。
何でこんな──追い詰められる?
しかしまだ、辛うじてセーフ圏内、だ。
思っている、
ところへ。
「あの──」
不吉な声が、聞こえた。
目を瞠り、向き直ると。
下り階段の段縁から、青縁眼鏡の目から上だけが覗いていた。
「今度こそ、今度こそ、大、大丈夫、です」
怒鳴りつけようとした、桐川の声は喉に絡まり、詰まった。
「何だね?」
不審そうに目を細めて、笠置が問い返していた。
「社長は犯人じゃない、です」
「──そう──かね」
「証明できる、です」
何を言ってる?
「聞こうか」
刑事が、頷き返した。
「登良遠町内会館、近くに製紙工場、あるです」
「ああ、あるね」
「隣にゴルフ練習場あって、そこの除雪、会館裏に運んでいるです」
「ほう、そうなのかい」
「製紙工場の煙、安全基準満たしてても、特殊な成分含んでる、です」
「ああ──」
「ゴルフ練習場、決まった融雪剤使っている、です」
「──なるほど」
刑事の声が、遠く。ますます、桐川の脳内は、白く。
「社長のあの日のコートや手袋に、そんなの検出されなければ、無実の証明、です」
──バカか。
桐川は、思った。
「あの日のコートと手袋、分かるです。今朝聞いたです。ケータイで記念写真撮ってた女子、いたですから──」
ゆっくりと、
桐川は階段に向けて、足を踏み出した。
「ひ──」
その形相を見て、臼月の顔が固まった。
「──失・せ・ろ」
「ひ──」
階段で、手足の細長い女は、二十センチ程度真上にぴょんと跳び上がった。
「わ、わ、わ──」
そして、慌てて階段下に向けて駆け出す。
「すみません、すみません、すみません──」
転がるように駆け下り、
下り、下り──。
今度こそ、
駅舎の外まで、駆け出していった。
細長い手足をぎくしゃく振り回して、ぴょんぴょん跳ねるように横断歩道を渡って。その白い背が小さく消えるまで、桐川は追い睨み続けていた。
あの女──。
歯軋りをする思いで、桐川は考えた。
いったい、何の呪いだ?
「お見うけした、その様子からすると──」
背後から、声がかかる。
「当夜の手袋はまだ処分前、家か会社か、ですか」
「………」
「ハードディスクのように、処分される前に──」
懐を探って、笠置は携帯電話を取り出した。
「急いで調べた方が、いいでしょうな」
ぼんやり、ぼんやり──。白い脳内に、思い出せなくなっていた。
あの女──
誰の紹介、だったっけ?
――――――――
この続きは書籍版でお楽しみください。

