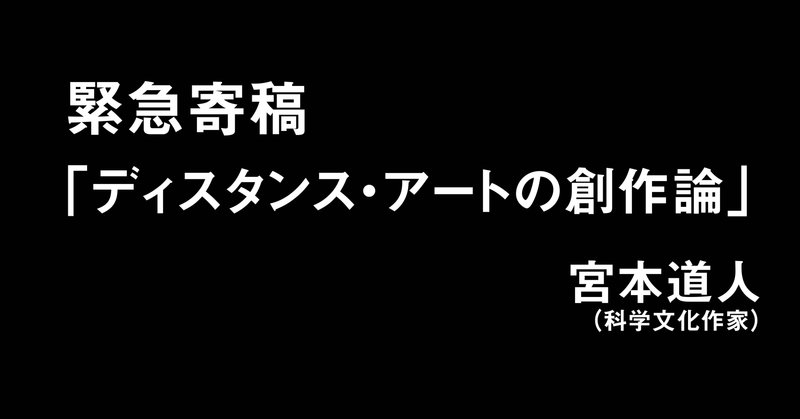
【緊急寄稿】コロナが芸術にもたらした未曾有の変異をとらえるために――「ディスタンス・アートの創作論」宮本道人(科学文化作家)
小説家パオロ・ジョルダーノが非常事態宣言下のイタリアで『コロナの時代の僕ら』を生み出したように、いま様々な表現者・作り手が未曾有の状況とそれぞれに向き合い、新たな作品を発表している。星野源「うちで踊ろう」、ZoomとYouTubeを使った「視聴者全員で演出する演劇」、ジャルジャルのリモート漫才、アイドルグループによるリモートライブ……それら「ディスタンス・アート」は何を描き、どのように鑑賞され、未来にいかなる影響をもたらすのか? 超リモート社会を舞台にしたアイザック・アシモフ『はだかの太陽』や「DEATH STRANDING」など「ディスタンス時代以前」の作品も参照しつつ、フィクションと現実の関係に迫る。科学文化作家・宮本道人氏による緊急寄稿。
ディスタンス・アートの創作論
宮本道人(科学文化作家)
1 ディスタンス・アートの意味
ディスタンス時代が訪れた。
この困難な時代には、これまでとは異なる、全く新しい創作論が必要になってくる。
すでに世の中には、時代に適応した新しい創作手法が続々と生まれている。
本論では、そんな取り組みの特徴を分析してゆく。
また、このディスタンス時代以前に存在した作品で、現状況にも繋がるような作品についても考察してゆく。
このような作品群を、本論では便宜的に「ディスタンス・アート」と呼ぶことにする。
ここでの「アート」は広義の意味で用いており、フィクションやエンタメ作品をかなり広く包含するものと捉えて頂きたい。
さらに本論では、2020年の新型コロナウィルス流行以降を「ディスタンス時代」と呼んでいる。
これはディスタンス時代以後の作品と以前の作品を、便宜的に区別するためである。
なお、本論はかなり急いで書き飛ばしたものであるため、各作品について簡単な紹介しかできていない。
ディスタンス・アートは日々新しい作品が現れている。
この論も書いている間も、どんどんアップデートが必要になってしまい、こうして外に発表するのが遅くなってしまった。
2か月ほどという短期間でここまで芸術が変異したという事例は、驚くべきことだ。
歴史を見ても、ここまでの勢いで芸術が変異したというのは、過去にないのではないか。
そのようなわけで、本論もそれほど精度が追求できているとは言えないことにはご留意頂ければ有り難い。
むしろ本論を叩き台として、皆で一緒にこのトピックについて議論していければと考えている。
より良い「ディスタンス・アート」を早めに構築するカギが理解できれば、重く苦しい時間を減らすことができるかもしれない。
ぜひこの論を肴に「○○が載ってなかった!」など、それぞれの想いを語り合って頂ければ幸いである。
さて、本論は以下のように構成されている。
1 ディスタンス・アートの意味
2 ディスタンス・アートの形式
3 ディスタンス・アートの鑑賞
4 ディスタンス・アートの題材
5 ディスタンス・アートの未来
6 参考文献・謝辞
各トピックで、ディスタンス・アートの性質を並列に切り分けて分類していく形式で論を進めているので、どこから読んで頂いても構わない。
それではいよいよ、考察に入っていこう。
2 ディスタンス・アートの形式
ディスタンス・アートの形式面での特徴は、
A 画面分割や複数画面
B PC画面や通話を見せる
C 映像を繋いでいく
D WEBカメラ内での表現
E 自宅の使用
などが挙げられる。
これらは別々に存在する場合もあるし、同時に存在する場合もある。
以下、それぞれの特徴を順に見てゆく。
A 画面分割や複数画面
画面を分割して見せたり、複数画面を並べる手法である。
特筆すべき作品に、
lyrical school REMOTE FREE LIVE vol.1
がある。
この作品はアイドルグループであるlyrical schoolが4/9にYouTubeに投稿した動画である。
各メンバーが別々にスマホで長回し撮影してパフォーマンスを行い、それを並べてリモートライブを成立させる手法で制作されている。
Zoom等の遠隔通話ツールではラグがまだまだ酷いため、このように、撮影の際には同時性にはこだわらず、各人が撮影したものを後でつなげるという手法が有効である。
リモートセッションの文化は過去にも様々なものが作られてきたが、この長さを別々に撮影して並べたものは、過去に類を見ないのではないかと思われる。
音楽動画としては、
在日ファンク(在宅ファンク) / 「はやりやまい」
の画面構成も興味深かった。
左右には横長動画が並び、真ん中にボーカルの浜野謙太の縦長動画が置かれている。
特に、浜野謙太がそのカメラを自ら持って動かしながらダンスを見せるのが印象的であった。
また、
でんぱ組.inc テレワークMV「なんと!世界公認 引きこもり!」
も重要な作品である。
画面のはめ込みの方法が単に縦型動画を並べたものではなく、様々な工夫がされているのが面白い。
メンバーやクリエイターがテレワークで作品を制作していった過程がTwitterで追えたのも斬新であった。
ほかに、
オーケストラのリモートの取り組みをまとめた記事に
があるので、それを見てゆくのも面白いだろう。
これらの流れを考える上では「スプリットスクリーン」という技法が参考になる。
その名の通り、画面分割をする手法で、古くから様々な映画で用いられてきた。
現在のディスタンス時代が始まる以前にも、MVに画面分割を用いた例はもちろんある。例えば、
SOUR '日々の音色 (Hibi no neiro)'
などが挙げられる。
また、複数の画面が並ぶという意味では、
ナム・ジュン・パイク
のビデオ・アートの作品群から得られる示唆もあるだろう。
B PC画面や通話を見せる
PC画面やビデオ通話でのインカメラ動画や画面共有を見せて、それを作品とする手法である。
興味深い取り組みに、きださおり氏が行った「のぞきみZOOM」がある。
ビデオ通話でのやり取りの中で謎が現れ、それを観客が自分で考えて謎を解いていくことができる作りになっている。
ほかに、劇団ノーミーツがTwitterに投稿した
「ZOOM飲み会してたら怪奇現象起きた…」
ZOOM飲み会してたら怪奇現象起きた… #劇団ノーミーツ#ZOOM演劇 #StayHome pic.twitter.com/twrzGCzQws
— 劇団ノーミーツ@5月23/24旗揚げ公演 (@gekidan_nomeets) April 9, 2020
の動画は、短いながらもインパクトを作ることに成功していた。
また、漫才の業界では、
ジャルジャルが行った「リモート漫才する奴」
は、リモートでいち早く漫才を行った例である。
リズムが重要な芸を披露し、むしろそのズレをネタ化したり、「固まってるトラップ」など、ビデオ通話の問題点を笑いに変える手法が特徴的であった。
その後ジャルジャルは
「ハズレの先生にリモート授業される奴」
という、大量のメンバーを用いたリモート漫才を行ったり、リモートならではの漫才の可能性を追求している。
WEB通話の特性を活かしたゲームも発案されている。
例えば「テレゲーム」という、Zoomを用いたゲームを作る集団がある。
特に文化的な側面で興味深かったものの1つが「ザ・ミュート」というゲームである。
このゲームの動画はTwitterで少し問題視され、すぐに削除されてしまったため、現在は見ることができない。
このゲームについては不快に感じる方もでており、それは本意ではありませんので公開をとりやめました。申し訳ありません。こちらのツイートも削除させていただきます。 https://t.co/jHe7tgSnxO
— タンサン朝戸 (@tansanasa) April 30, 2020
どのようなゲームだったかというと、Zoomを使った通話の間に、いつの間にか少しずつメンバーが自分の声をミュートにしていき、最後まで気づかず話していた者が負けというゲームである。
このゲームは、ゲーム自体の性質の是非はともかく、使い方によってはZoomでの「いじめ」が有り得るという点を浮き彫りにしたのが非常に印象的であった。
過去の作品をZoom化するということも行われた。
森翔太がTwitterに投稿した動画では、「東京物語」をZoom化するということが行われていた。
Zoom東京物語 pic.twitter.com/sAIOBpBgws
— 森翔太 Shota Mori (@ShotaM0ri) April 28, 2020
以上のような、PCやスマホでの通話を作品化するという手法は、これもまたディスタンス時代以前に、当然存在する。
特筆すべき作品として、映画の「search サーチ」が挙げられる。
失踪した娘を探す父親が、様々な人とビデオ通話を行う様子が、全編モニター上で展開される作品である。
この映画の製作者ティムール・ベクマンベトフはこのような手法を「スクリーンライフ」という名前で提案しており、今後も本手法を用いた作品制作を行うようだ。
また、タテ型スマホに最適化されたミュージックビデオとして話題になった
RUN and RUN / lyrical school 【MV for Smartphone】
も、ディスタンス時代以前にディスタンス・アートを先取りしていた作品として重要である(そして、先にあげたlyrical schoolの動画でもある)。
SNSを用いたやり取りを模した、非常に斬新なメタフィクション的作品である。
ディスタンス時代以前のゲームでは、
Her Story
が、PC画面フィクションの極北である。
こちらはビデオ通話を行うわけではないが、とあるビデオを見ながら、メール等を行う様子が作品になっている(ミステリ作品であり、ネタバレを避けるために詳述は省く)。
C 映像を繋いでいく
映像を順に繋いでいく手法である。
この手法では、インドで作られた4分半のショートショート映画
Family
が重要な作品である。
インド映画のスター達が、各々の家で撮影したものをつなぎ合わせて作った動画であり、Twitterで公開されていて、インドのモディ首相も薦めている。
別々に撮っているのだが、一緒にいるように見せるべく、簡単な工夫がされている。
また、世界各地の人がトイレットペーパーをパスしてゆく動画
The Great Toilet Paper Toss 2020 (Gone Global!)
も印象的であった。経緯は
がまとめている。
映像を繋ぐのは、特に同じ国に限る必要がないため、グローバルに作品制作が行われる点が面白い。
このような手法の理解には、
モンタージュ
の概念が役立つかもしれない(映画に詳しい人なら知らない人はいないと思うが、まったくそのようなものを知らない読者のために書いておく)。
複数の映像を繋いで、連続したシーンを作るという、映画の基本となる技法である。
D WEBカメラ内での表現
1人での屋内撮影が多くなるため、自宅のWEBカメラを用いて工夫を行うことが多くなった。これにより、固定カメラの中で、演出に工夫を行う必要が生じた。WEBカメラだけでなく、スマホのインカメ固有の表現などもここには含まれる。
実際のカメラ内に映るもので自己表現を行ったり、顔を覆うマスクを自己表現に用いたりするものもあるほか、背景変更を用いた表現も多様化している。
ユニークな取り組みに
即興公演#02「背景でがんばって臨場感出す演劇」【劇団テレワーク】
がある。
ビデオ通話ツールのZoomで背景が変更できることを活かし、様々なシチュエーションで演劇を行っている。
「背景」自体も、キャンバスのように扱われていくかもしれない。インスタライブのフィルターなども、この一種である。
例えば、Zoomなどのストリーム配信にエフェクトを掛けられるソフトmemixなどはその可能性を秘めている。
背景を固定した上でカメラを動かすという荒業もあり、先にあげた「テレゲーム」の集団は音楽に合わせてカメラの方を動かす「Zoomダンス」をやっていた。
音楽に合わせて、カメラの方を動かして踊るZoomダンスをやってみたけど面白かった!!
— タンサン朝戸 (@tansanasa) April 18, 2020
簡単にできるので遊んでみてください!
他にもZoomなどで遊べるテレゲームをいろいろ配信していました!#テレゲームhttps://t.co/pQ56EnTuQK pic.twitter.com/OVqfkGopOP
E 自宅の使用
在宅を強いられているため、家にあるもので作品を作らざるを得なくなっている。
超おうち時間 SUSHIBOYS
は、家にあるものだけを用いて音楽制作を行った好例である。
デヴィッド・F・サンドバーグ監督とその妻で女優のロッタ・ロステン氏によるショートムービー
Shadowed - Short Horror
は、自宅で撮影され、光と影を効果的に用いるだけで、非常に恐ろしく美しいホラー映像を作り上げることに成功している。
また、集団制作においては、自宅の使用に伴い、俳優自身による自主的演出の比重が上がる。
例えば、行定勲監督が作成したショートムービー「きょうのできごと a day in the home」を見ながらこのことを考えてほしい。
このムービーでは有名な俳優が自宅で演技をしているのだが、俳優個人個人が自宅を用いるという珍しい事態が起こっている。かつ、監督はその場でカットをして指示を出して後で繋ぎ合わすといったことも難しいため、自ら演出を考えて動くことが必要になっている。
そして、このような条件下の実写映画においては、資本は内容に大きな差をもたらさないことも多い。
あまり有名でない監督・俳優も、有名な監督・俳優も、使える条件にはそれほど差がない。
(とはいえ、WEBカメラやインターネット回線の値段、自宅の部屋の多さ、家族の有無などは差を生むことには注意すべきである)
このような演出を考える際は、映画史における即興演劇や素人の起用などの歴史をたどり、現在の演出と比較してみるのも面白いであろう。
しかし、それは本論の域を超えるため、どなたか詳しい方の論を待つことにしたい。
3 ディスタンス・アートの鑑賞
ディスタンス・アートは、鑑賞方法にも変化が出てきている。
「鑑賞」といっても、双方向性が大きな特徴であることが、ここでの主眼である。
A 視聴者の指示を参考にする
B 自分の動画を並べる
C 次の参加者を指示する
D 鑑賞している人物の鑑賞
E 鑑賞場所の自由度
などの特徴が挙げられる。
以下、それぞれの特徴を順に見てゆく。
A 視聴者の指示を参考にする
即興公演#01「視聴者全員で演出する演劇」【劇団テレワーク】
は、かなり尖った企画であった。YouTubeで視聴者のコメントを拾い、その場で演技を進めていくスタイルを取っている。
劇団テレワークは先にも名を出した劇団であるが、この状況下で何ができるかを様々な手法で試していて非常に先鋭的であるため、この状況下で最も注目すべき集団かもしれない。
B 自分の動画を重ねる
動画を横においてセッションしているように見せるムーブメントとして、
星野源 – うちで踊ろう Dancing On The Inside
があった。
これには様々なアーティストが、自らの動画を横に置くということを行った。
さらにこれは、安倍首相がムーブメントに乗ったことも話題になった。
友達と会えない。飲み会もできない。
— 安倍晋三 (@AbeShinzo) April 12, 2020
ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして、今この瞬間も、過酷を極める現場で奮闘して下さっている、医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げます。 pic.twitter.com/VEq1P7EvnL
この動画が炎上したことも特筆に値する。
何が炎上の原因だったのかは、1つの考えとして、以下のような分析がなされていて、参考になる。
本論は、この安倍首相の動画の「是非」については判断を行わない。
しかし、ディスタンス・アートを論じる文脈でこれを見るとすると、1つのポイントとして、この動画では画面の左右がリンク・同期していないことが挙げられる。
もちろん星野源の動画には、岡崎体育や大泉洋など「リンクがうまくできなかった」ことを笑いに変えた手法でのコラボも存在した。
しかし、そこにはあくまで「リンク」の存在が前提となっていた。
この安倍首相の動画には、そもそも最初から「リンク」が全く無視され、片側ずつを切り分けても何も問題ないというのが、ある種の奇妙さを生んでいる原因の1つであろう。(この指摘は限界研の杉田俊介さんとの対話の中でお聞きしたことを参考にした)
また、安倍首相の動画から派生した動画として、
安倍首相にチャンネルを変えられる男【ゆゆうた】
タイマール (陰キャラフィットネスCEO)@inkya_fit氏がTwitterに投稿した動画
遠隔操作 pic.twitter.com/uYbL9jQiB9
— タイマール (陰キャラフィットネスCEO) (@inkya_fit) April 14, 2020
などがある。
いずれも、安倍首相がTVのリモコンを操作することがネタにされている。
なお、余談であるが、星野源の動画では動画を上下で切って勝手に下半分を別の動画に置き換えるという斜め上の事例も登場した。
エナツの祟り・翌桧ダンク冬雪【あすなろだんくふゆゆき】@jt_dunk氏がTwitterに投稿した、
豆腐の容器を開けるのに悪戦苦闘する星野源さん
豆腐の容器を開けるのに悪戦苦闘する星野源さん pic.twitter.com/r4MS914RQe
— エナツの祟り・翌桧ダンク冬雪【あすなろだんくふゆゆき】 (@jt_dunk) May 1, 2020
の動画を見て頂きたい。
このような文化はある種、ヒップホップに始まり、様々なジャンルに広がったサンプリング文化の新しい形とも言えるだろう。
サンプリングについては、以下のブログなどに詳しい。
実際、ヒップホップがこの状況下でどのようなムーブメントを生んだかという例を少し挙げておく。
ほかの人の作った音に自分の音を重ねるムーブメントの1つに、「ビートジャック」というものがある。
(これは、ここまでで言及してきた、自分の動画を横に並べて出す方式ではない)
例えば、Tokyo Drift Freestyleという、TERIYAKI BOYZの楽曲「TOKYO DRIFT」をビートジャックする動画が盛んである。
日本では例えば、ここまで2回言及してきたlyrical schoolが参加している。
lyrical school / TOKYO DRIFT FREESTYLE
C 次の参加者を指示する
これはTwitterで、「#自撮りつなぎ」「#うたつなぎ」と言われているようなムーブメントである。
昔から「バトン」「チェーンメール」などと呼ばれていたものに似ているが、他の人から見える規模の大きいSNS環境でこのような動きがあるのは大きい特徴である。
「#うたつなぎ」に関しては、その起源を辿った記事などもあり、参考になる。
とはいえ、このような強制的コラボレーションの在り方に対しては否定的な意見もあり、参加する際には気をつけなくてはならないだろう。
(バトンは受け取るがそのあと人には回さないというスタンスの方もいる)
D 鑑賞している人物の鑑賞
ゲーム実況はずっと昔からディスタンス・アートの最前線であり続けてきた。
例えば2人のVTuberがゲームを行い、それを見る形式の動画から考えてみよう。2018年に投稿されたこの動画、
【初コラボ】ヨメミ×アカリのデスマッチ!!
を見れば分かるように、ゲーム画面と同時に、それぞれゲームを行っているキャラクターを鑑賞するということが行われる。
この動画ではVTuberになるという変換も遊びの1つであり、重層的な遊びが行われているのも特徴である。
詳しくは拙編著『プレイヤーはどこへ行くのか』所収の拙論「リアリティ・ミルフィーユに遍在するVTuberたち 複数キャラクター同時プレイ論」をを参照してほしい。
E 鑑賞場所の自由度
在宅を強いられるのに伴い、「鑑賞場所」にも変化が起きた。
仮想空間で動き回りながら同時鑑賞するというスタイルのバリエーションも増えている。
例えばゲーム「フォートナイト」で、ラッパーのTravis Scottが開催したコンサートでは、現実空間ではできないような体験を提供していた。
ビデオ通話ツールにも変化が起きている。
例えばspatial.chatというバーチャルビデオチャットツールが登場したのだが、これはYouTubeの画面を複数映しながらビデオ通話ができる。
この際、近くにいる者同士での音が大きく聞こえたり、YouTube画面から離れるとその音が小さくなるなど、実空間を模したような音の感覚を得ることができる。
今後のツールの発展によっては、フェスのようなものをこのツールを用いて開催することも可能かもしれない。
また、実空間で政治活動ができなくなったことで、仮想空間に政治活動が移動することも起きた。
「どうぶつの森」での香港の活動家の動きを参照してほしい。
このような動きの可能性は、かつてコリイ・ドクトロウ『リトル・ブラザー』というSFでも描写されていた。
鑑賞場所の変化は、仮想空間上だけではない。
かつてあった「ドライブインシアター」のような形がリバイバルしているところもある。
例えばこのTwitter投稿からは、車ならではの音楽の楽しみ方が生まれていることがわかる。
hardstyle social distance pic.twitter.com/QhVw2n03x3
— gabbereleganza (@gabbereleganza) May 1, 2020
在宅での楽しみ方自体も変化している。
Nintendo Switchや、そのソフトの「リングフィットアドベンチャー」が在庫切れを起こしているように、在宅での運動とセットでの需要が生まれている。
また逆に、家族が一つの家にずっと居るという状況にあるため、家の中での自由度は下がり、家で「静かに」楽しめるものが重視されているということも付記しておきたい。
4 ディスタンス・アートの題材
いま作品を作る人間は、ディスタンスをどう考えるか、どうしても意識せざるを得ないだろう。
多かれ少なかれ、物語で人が集まるシーンの描き方について悩んでいるクリエイターがほとんどではないだろうか。
そこでここでは、ディスタンス・アートの題材について考える。
A ディスタンス社会の問題点を考える
B パンデミックもの
C アーキテクチャとしての距離
D ディスタンス時代の生き方
E 結果としてディスタンス時代を止める可能性がある題材
などの題材を、順に考えてゆこう。
A ディスタンス社会の問題点を考える
ここまで何度も挙げてきた「劇団テレワーク」は、題材の面でも非常に尖った作品を生み出している。例えば、
本公演#01「最高のテレワークマナー」【劇団テレワーク】
は、テレワークの問題点をあぶり出すものである。
ディスタンス時代以前の、古い作品にもヒントがある。
例えば、1957年に刊行された『はだかの太陽』。
舞台となる星では、地球人がウィルスを運んできたらしいという状態で、人と人との接触が極端に嫌がられており、夫婦でも別居が当然となっている。すべてリモートワークと遠隔操作ロボットで成り立つ世界なのだ。当時はVRなんて概念がないので、テレビ電話みたいなもので社会が成立している。
という設定を聞けば分かる通り、これはディスタンス時代以前に書かれているが、「ディスタンス時代のミステリ」の可能性を示したものである。
SFやミステリはどのようにディスタンス社会を想像してきたか。そこではどのような問題が起こり得るのか。
このようなことを考えるのは、これからのフィクションを作る上で有用である。
例えば、AIミステリやVRミステリ、ドローンミステリにはヒントがあるだろう。
このようなミステリについては、参考になる書籍に
『サイバーミステリ宣言』
がある。この本ではサイバーミステリの様々なパターンが考察されており、ディスタンス時代のミステリの可能性を考える上で役に立つであろう。
B パンデミックもの
パンデミックものも、ディスタンス・アートの一つとして捉えられる。
現在、ディスタンス・アートの多くはパンデミックものの一形式として見られている向きがあるが、それはむしろ逆なのではないか。
ディスタンス時代の始まりとして、covid-19を見ることが必要なのだ。
例えばゾンビ映画では、感染者を近寄らせないようにすることが描かれるが、それはディスタンス・アートの手法の1つとして分類できる。
しかし、パンデミックものを論じようとすると、この論考と同じ長さくらいの尺が必要になってしまう。
このようなウィルス・フィクションは、様々な人が紹介し始めているし、Wikipediaにも「ウイルスを題材にした作品」というページがあるので、そちらを参照して頂きたい。
ここでは代表例として、1つのゲームを紹介する。
Plague Inc.
というゲームである。
Plague Inc.では、最強のウィルスを作り出し、人類を絶滅させることが目指される。
このゲームは2012年にリリースされたゲームであるが、今回のcovid-19の流行に際し、ユーザーが「シナリオクリエイター」機能を用いて対応シナリオを作成したり、開発元自体も現在、専門家の監修のもとアップデートを行うことを発表している。
その中では「ソーシャル・ディスタンス」などを対策に用いて伝染病の感染拡大を防ぐモードの開発が目指されているそうだ。
Plague Inc.はアメリカ疾病予防管理センターから評価されていたり、WHOに寄付していたり、社会的存在として大きな影響力を持っている。
題材の取り方として、参考になる事例の一つであろう。
C アーキテクチャとしての距離
「とりあえず距離を取らせる」というだけでも、ディスタンス・アートの題材として十分である。
例えば「ウォーリーをさがせ!」を勝手にディスタンス化した風刺画が作られたという事例があった。
また、小池都知事の発言「密です」が反響を呼び、様々なパロディが作られた。中でも
密です3D
は大きな話題となった。
集まっている市民を「密です」の掛け声の元に離れさせていくというゲームである。
ほかにも、ストーリー自体に距離が内包されていなくても、偶発で生まれる距離も存在する。
これはディスタンス時代以前のゲームであるが、
World of Warcraft(WoW)
というMMORPGゲームがある。
そこでむかし発生した「汚れた血事件」は、はからずもゲーム内で感染症のシミュレーションが行なわれた事例として話題となった。
どのような事件かというと、ゲームに実装された敵のキャラが、周囲にもダメージを感染させる攻撃技を仕掛けてきて、これによってゲーム内世界が意図しないパンデミックに陥ってしまったという事件である。
つまりゲーム内においても、ディスタンスを取らないといけなくなる可能性はあるのである。
D ディスタンス時代の生き方
多くの作品で、ディスタンス時代の生き方を提示するストーリーが描かれ始めた。
中でも秀逸だったのが、
短編映画『カメラを止めるな!リモート大作戦!』
である。
映像を繋ぐ手法での映像制作自体をストーリーにしており、それ自体ディスタンス時代の創作論(そしてそのパロディでもある)にもなっている。
在宅勤務の様子を描く漫画も現れた。例えば、
在宅勤務がだんだん辛くなってくるOLの話
などが挙げられる。
また、海外での動向は追いきれていないため、あくまでニュースの紹介にとどまるが、マペット人形劇でもディスタンス時代が反映されていたり、
米法廷ドラマでも、FaceTimeやZoomを活用し、外出禁止の社会が描かれるエピソードが制作されるそうだ。
では、ディスタンス時代以前に、ディスタンス時代の生き方を考えていた作品には、どのようなものがあるのだろうか。
DEATH STRANDING
というゲームは、一つの事例として考えられるかもしれない。
特殊な災害によって分断された世界で、配達人が世界を支えているという設定であり、SF・ファンタジー的世界観ではあるが、ディスタンス社会の一つの生き方を描いていると言えよう。
E 結果としてディスタンス時代を止める可能性がある題材
狭義の「ディスタンス・アート」という言葉は、ディスタンスが何かしらの形で形式or内容面に関係しているものを指すことになると思うが、それ以外にも別の形のディスタンス・アートが有り得るのではないかというのが、この項のミソである。
その一つの例が、それ自体がディスタンス状況を終わらせるものを目的とした作品である。
ここで挙げたいのが、タンパク質の構造をゲーマーに解かせるオンラインゲーム
Foldit
である。
このゲームはゲームでありながらも、実際にこれまでウィルスの構造解析などで成果を挙げてきた。
そして今回のcovid-19に対しても、解析プロジェクトが始まっている。
もしもこれが役に立つ日が来れば、このゲームはディスタンス社会に終焉をもたらす一助になるわけであり、その意味でこれはディスタンス・アートの一種と言えるかもしれない。
5 ディスタンス・アートの未来
ここまでディスタンス・アートの特徴を順に分析してきたが、では果たしてこの作業にはどのような意味があるのか、ここから少し考えてみたい。
まず考えるべきは、ディザスターが起こると、従来の形でアートが作れなくなる可能性である。
その先に、どのようなフィクションが有り得るのかを先に考えておくことは、文化を生き延びさせる上で重要なのではないだろうか。
今回のcovid-19の流行に対して短期的にどう対処するかを考えるにはウィルス・フィクションのほうが役に立つのかもしれないが、今回のような状況は長期的に何度も起こり得ると思われ、そこにはディスタンス・アートについて考えておくことが有用になる。
このcovid-19の第二波、第三波といったことはもちろん、強毒性鳥インフルエンザがこれから世界的な大流行を起こす可能性も考えられるし、またその他にもテロリズムや戦争において生物兵器が使われる可能性は十分にある。
21世紀はディザスターの世紀になる。今回のcovid-19の流行で分かったように、一部の地域が持っているリスクが世界に一瞬で拡散し得る。ウィルス以外でも、在宅を強いられるディザスターはあるかもしれない。
そんな時に、すぐに完全に家に引き込もれる体制に移行できる社会の構築が必須であるが、そこで並行してディスタンス・アートが進化していなかったら、社会は精神的余裕を失ってしまうであろう。
このような「予防的批評」とでも呼ぶべき批評スタイルは、様々なディザスターに対して考察すべきものなのかもしれない。
さらに、ディスタンス・アートを考えるということは、単にウィルス流行に対する文化を考えるだけにはとどまらない広がりもある。
例えば、いまローカルでなくWEBコンテンツに力を入れることは、世界と繋がるチャンスにもなる。
世界中で今後、ディスタンス・アートは共通の文化になってゆくだろう。
また、さらに言えば、これは宇宙時代の文化にもなり得る。
引きこもることは宇宙飛行士試験と共通する部分もあるではないか。
ディザスターによってアートがダメージを受けてしまうということは、おそらく長期的に見ると社会にとって大きなダメージになり得る。
ドイツでは先日、文化相が「アーティストは今、生命維持に必要不可欠な存在」と発言し、フリーランサーや芸術家、個人業者への支援を始めたという。
実際にこれが効果を上げているかは分からないが、その姿勢自体には見習うべきところがあるであろう。
また、covid-19への対応で冷静な対応が話題となった千葉市長は、以前WIREDのインタビューで、市政の中で『ニューロマンサー』を意識していると話していた。
緊急事態に冷静に対処できるのはSF読みだからか!と思うのはフィクション好きのエゴかもしれないが、実際こうしてフィクションが市政に影響することもあるわけである。
アートを通して政治を議論することは、実際の政治について議論するよりも良いケースも考えられる。
現実の対象に対しては思い入れによって議論が「捌け口」のようになってしまう場合も多いが、アートを媒介して議論することで、一定の距離を保ちながら考察することも可能になる。
ディザスターへの対処の仕方をフィクションから考えるというのは、その意味で重要な役割を持ち得ると考えられる。
ただ、ここで誤解して欲しくないのは、本論は「役に立つ」アートが重要と主張するものではない、ということだ。
どんなアートに対しても、「このアートは役に立つ」「このアートは役に立たない」と切り分けるのではなく「このアートは何の役に立てられるだろう」「このアートはどうやったら役に立てられるだろう」と方法論を模索することが大切なのである。
アートから現実を逆算して考察する能力や、未来から現在を逆算して役立てる能力が、いま求められている。
本論を読んで共感して頂いた皆さまは、ぜひ一緒にそのようなことを考えて頂ければ幸いである。
6 参考文献・謝辞
本論で直接参考にしたものは文章中にそのまま出典を示している。
ここではその他、参考になるものとして、いくつか僕自身が書いたものや、僕自身が関わっているプロジェクト等を挙げておく。
●共著『東日本大震災後文学論』所収の拙論「対震災実用文学論 東日本大震災において文学はどう使われたか」
震災に対するフィクションの有用性を5つに分類して論じているため、ディザスターに対するフィクションの有用性を論じる本論とも通じるところがある。
●共著『ビジュアル・コミュニケーション』所収の拙論「実験室化する世界 映像利用研究が導く社会システムの近未来」
映像を用いたコミュニケーションについて、科学技術の側面から考察を行っている。
●編著『プレイヤーはどこへ行くのか デジタルゲームへの批評的接近』
ゲームやゲーム実況を論じており、ディスタンス・アートを考える上で参考になる。
「リアリティ・ミルフィーユに遍在するVTuberたち」「叙事的ゲームのインターフェース」等の拙論所収。
●VTuberげんかいくんとして、アッガイズチャンネルのジョージさんとコラボ配信した動画「ウイルスVS人類VSフィクション」
ウィルス・フィクションについて考察している。
●ミステリ雑誌〈ジャーロ〉に書いた拙論
・ミステリと人工知能
・ミステリと仮想現実
AIとVRが登場するミステリについて論じており、ディスタンス社会の課題を考える上でも参考になる部分があるかもしれない。
●草野原々氏とのWEB対談「ディザスターの想像力」
大災害を扱った様々なフィクションについて全12回語り合い、何か現実に役立てられる見方はないか考察した。
●AIxSFプロジェクト
中国やアメリカでSFの実用性がどのように扱われているか、SFプロトタイピングの可能性などを研究中。
参考文献は以上である。
また、本論の作成にあたっては、筑波大学の大澤博隆氏、限界研の杉田俊介氏・蔓葉信博氏・竹本竜都氏・藤井義允氏、漫画家のハミ山クリニカ氏から貴重なご助言を頂いた。ここに記して感謝申し上げます。
(2020年5月3日)
宮本道人(みやもと・どうじん)
1989年東京生まれ。科学文化作家。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。博士(理学)。
筑波大学システム情報系研究員、東京大学大学院新領域創成科学研究科客員連携研究員、変人類学研究所スーパーバイザー、株式会社ゼロアイデア代表取締役。
開かれた科学文化を作るべく研究・評論・創作。編著『プレイヤーはどこへ行くのか』、協力『シナリオのためのSF事典』など。
人工知能学会誌にて原案担当漫画「教養知識としてのAI」連載中。日本バーチャルリアリティ学会誌にて対談「VRメディア評論」連載中。SFマガジンにて共同企画「SFの射程距離」連載中。
国際マンガ・アニメ祭 REIWA TOSHIMA マンガミライハッカソンにて原作担当漫画「Her Tastes」が大賞・太田垣康男賞をW受賞。現代思想2019年8月号に共著小説「呑み込まれた物語」掲載。ユリイカ・週刊読書人・実験医学・情報処理学会誌などに寄稿。
Twitter: @dohjinia
●関連記事

