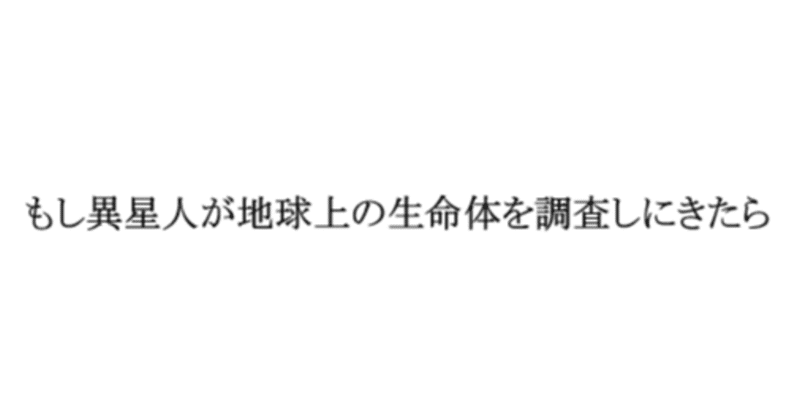
もし異星人が地球上の生命体を調査しにきたら
もし異星人が地球上の生命体を調査しにきたら、適当なサンプルをレーザー光線で吸い上げて、さっそく解剖、などということはしない(ついでにいうと、肛門にばかり異様な興味を抱いたりもしない)。〝レーザー吸い上げ〟のような荒っぽい方法を使うのは、新米の研究者だけだ。あとで指導教官からお仕置きを食らうこと、間違いなしだ(罰として、垂れた鼻を引っぱられるか何かだろう)。研究の対象にしたい動物をたださらってきたところで、生息している環境と照らし合わせなければ、その動物について知ることなどできない。
異星からきた研究者がベテランであれば、まず、その動物が生息している場所に関してできる限りの情報を集めるはずだ。いやなんなら、生息環境をまるごとレーザー光線で吸い取り、自分の星へ持ち帰って、じっくりと観察する。「エイリアン科学大学」の卒業生は、生態学に精通しているから、有機体は複雑なメカニズムを備えているものの、進化する中で暮らしてきたのとは別の環境に置かれると、本来とは異なる行動を起こすことも多く、たいてい、ぎこちない動きしかできない、とわかっている。
真っ当な調査方法の原則に従いつつ、異星人の研究チームは、必要なものをごっそり持ち去って、苦労を重ね、やがて地球人のゲノムから「フェノム」まで徹底的に解明し、進化で培った自然な行動パターンも掌握するだろう。フェノムとは、特定の動物がこなせる動作全体をさし、突き詰めれば、ゲノムによって指示が出され、進化の中で暮らしてきた環境の範囲内で実行される。たとえば、あなたの携帯電話のゲノムは電子回路(あるいは、その回路の設計図)であり、フェノムは、その電話が持ついろいろな機能すべて──取扱説明書に列挙してあるような事柄──だ。地球上の生物にはあいにく説明書がないが、異星人はまさにその種のことを解き明かしたい。
ところが、いたって妥当なはずのルールにのっとって人間を研究すると、予想外の展開になる。部族をまるごと拐かし、集落のあった山もごっそり移転したにもかかわらず、不可解な事態にぶつかってしまう。というのも、昔さらってきた、言語も音楽も持たない原始人と、あらたに連れてきた、言葉をしゃべり歌をうたう現代人とを比較して、どこが新しくなったのか調べたところ……なんと、区別を見いだせなかったのだ。生物学的な差異はなし、と異星人の研究チームは結論を出す。同一の動物である。生息環境の違いが原因なのだろうか? いいや、そうではない。持ってきた山は、前回も今回もこれといった違いがないように見える。同じ生物、同じ環境。なのに、現代のヒトは、原始的なホモ・サピエンスから長足の進歩を遂げている。まあ、進歩かどうかは別にしても、とにかく違う。
異星人は、角を抱えて悩むはずだ。いったい、なぜだ? どうして現代のヒトは根本的に異なる振る舞いをするんだろう? どんなわけで言語や音楽を持つにいたったのか? 言語とも音楽とも縁のない原始のヒトは、非常に頭脳がすぐれているものの、類人猿の範疇にほぼ収まっていた。なのに、今回さらってきたヒトは、どこか重大な違いがあって、別の生き物に思える。生物学的にも生態学的にも一致していながら、高等さがまったく異なり、別種として分類すべきと感じられる理由は何か?
現代人は明らかに、言語と音楽をなんらかのかたちで〝習得〟したにちがいない。けれど、そう考えると、また悩みがふくらんでしまう。何かを教え込むだけで、ほぼ別種の生き物に変化させることなど、可能なのか? 異星人はさらに研究を進めて、言語や音楽が驚くほど複雑だと気づく。これほどのややこしさは、自然淘汰で生みだされたと見るのがふさわしい。動物が何かの動作を適切にこなせるようになるのは進化の結果であり、現代のヒトがこんなに言語や音楽の扱いに長けているのも、そのせいだろう……。しかし、異星における生態学の研究成果に照らすと、動物のからだが、その動作の複雑な処理に見合うつくりになっていない限り、無理やり覚え込ませることはできないはずだ。鹿をいくら訓練しても、鼠を捕まえて食べるようにはならない。犬をトレーニングして、猿のように木登りさせることも不可能。人間にしても同じで、特訓したところでファックス機の送受信音を理解できたりはしない。自然淘汰を経て生き残るだけの価値を持たない能力は、身につけさせることができないのだ。ヒトの脳はそれほど万能にできた学習装置ではないから、本来、言語や音楽のようなひどく複雑な事柄をあらたに習得することはできそうにない。にもかかわらず、現代の人間は、言葉を話したり音楽を聞いたりと、いとも簡単にやってのける……。異星人の研究者たちは途方に暮れてしまう。
理屈からいって、言語や音楽は、人間の脳の中に生まれつき組み込まれているはずがない。また、生息環境から身につけた習慣でもない。かといって、学習可能なほど単純でもない。人間のどこかに、言語や音楽を処理する仕掛けがひそんでいるはずだが、自然淘汰でも学習の成果でもないとすれば、いったいどこから湧き出す能力なのか?
異星人の研究者のひとりが、ふと思いつく。言葉や音楽を持たない祖先と、現代の人間との違いを生んだのは、やはり、一種の淘汰かもしれない。ただし、自然による淘汰ではなく、文化による淘汰だ、と。つまり、生きるうえで必要なものを取捨選択するのとは違い、人工的につくりだしたものを生きるうえで使いやすいように取捨選択していく。人工的なつくりものは、ある意味で生物に似ていて、時間が経過するにつれ、生き延びたり滅びたりして進化を遂げる。人間が生みだしたこの生命体のようなもの(専門用語で呼ぶなら「ミーム」)は、自然界で生存競争を繰り広げる生物と同様、巧妙な適応化に伴い、極度に複雑な仕組みになって、隅々まで工夫の凝らされた傑作に仕上がっていく可能性を持つ。
「わかったぞ!」と、異星人の研究者は叫ぶ。現代のヒトが言語や音楽を学び取る一方、言語や音楽のほうも、共生環境の中で磨きあげられている。もともとヒトは言語も音楽も持っていなかったけれど、ともに進化した結果、生物学的な枠を超えた出来栄えのものを手に入れた。生物学上は原始時代のホモ・サピエンスと同じでありながら、現代のヒトは、もはや異なる存在になっている。その原因は、体内の構造変化でもなければ、外界の自然環境でもない。ヒトの生みだした言語や音楽が、まるで生命体のように進化して、ヒトと共生している。共生関係にあれば当然、パートナーに合わせてさらなる進化を続けていく。そのパートナーとはつまり──わたしたちの脳だ。
では、異星人の研究者の目から見て、わたしたちはいったい何者なのか? 遺伝子から肉体の仕組みにいたるまでは、生物学が教えてくれる。しかし、それだけでは足りない。異星人が人間ひとりではなく生息環境をまるごと攫わなければいけなかった点からもわかるだろう。適切な環境があってこそ、わたしたちは生物として成り立つ。けれども、そこまでなら、地球上の生命体すべてにあてはまる。人類を研究する際には、人体の仕組みと生息環境を総合してもまだ不足、と心得ておく必要がある。共生する文化まで合わせて考察しなければならない。ほかのどんな動物よりも取り扱いが難しい。人間がどんな生き物であるかは、解剖したり生息環境を調べたりすればある程度まで判明するだろうが、さらに深く見ると、自ら生みだしてともに進化してきた事物ともからみ合っている。言語や音楽をはじめ、高度に文化的な進化を遂げた知識の総体が、遺伝子や生息環境と同じくらい、現代の人類を形成する素になっているのだ。ヒトの謎を解くための鍵は、言語などの文化的な所産の奥にも潜む。
異星人の研究者という想定を通じて、わたしたちが何者であるかがより明確になってきたと思う。現代人の本質は、共生する文化に根ざす。文化が発展してわたしたちの脳の中へ入り込み、既存の能力を転用しながら、あらたなものをつくりだしてきた。そうしてできた目に見えない文化的な〝生き物〟が、人間とたがいに影響を与え合いつつ、ともに進化を続けている──というのが、異星人の研究チームの結論だろう。宇宙には、共生する事物どうしの相互作用が数多くあることを知っているはずだ。
こうした〝生き物〟が、文化による淘汰を経て、人間の脳にふさわしく進化したにちがいない。そこまで理解した異星人は、続いて、この〝生き物〟がどうやって脳内に侵入したのかを知ろうとする。「文化的な共生要素は、どんな方法で脳の内部と接触しているのだろう?」やがて、答えが見つかる。「そうか! 自然界を模倣しているんだ」
(マーク・チャンギージー『〈脳と文明〉の暗号――言語と音楽、驚異の起源』中山宥訳より抜粋)

