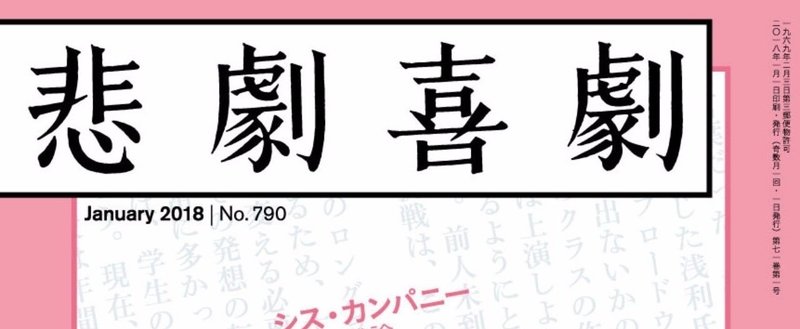
【特別寄稿】佐々木敦「松原俊太郎は現代日本演劇における新たなる劇作家の時代を切り拓くだろう」(悲劇喜劇2018年1月号)
以下、悲劇喜劇2018年1月号より。
松原俊太郎は「戯曲の時代」を幻視する
佐々木敦(批評家)
劇作家不遇の時代だと思う。
演劇は幾つもの要素から成り立っているが、現在活躍中の演劇作家の多くが「劇作家、演出家」であり(更に「劇団主宰」であることも多い。この「劇団」という語の定義もかつてとは違うのだが)、戯曲を書くこととそれを演出することがひと続きの作業であるとされていることがしばしばである。むろん前からそういう人は居たわけだが、近年ますますこの傾向は強まっていると言える。
このことは、一方では日本でもっとも権威と効力のある演劇賞が「岸田國士戯曲賞」であるがゆえに、既存戯曲の演出を主に手掛ける才能ある演劇人(多田淳之介、中野成樹、三浦基など)がその栄誉に浴すことがかなわないという問題を生んでおり、尚且つその岸田賞の候補に挙げられる作品の多くが「劇作家、演出家」による、それも事前に書かれた「戯曲」ではなく「上演台本」になっているという些か奇妙な事態を生じさせてもいる。
つまり、今の演劇シーンでは劇作家の存在感が希薄なのだ。もちろん現在においても、たとえば長田育恵のように劇作のみを手掛ける者もいるが、とりわけ新人の場合、戯曲のみによって世に出ることは構造的にかなり困難になってしまっているのが現状である。
そんな中、愛知県芸術劇場が主催する「AAF戯曲賞」は、全国公募型の戯曲賞として有意義なものだと言える。新たな劇作家の登竜門になり得るからだ。とはいえ、この賞もまた近年の最終候補の顔ぶれを見ると「劇作家、演出家」の「上演台本」が大勢を占めつつあるのだが。しかし同賞は少なくとも現時点でひとり、現在では稀少と言ってよい、いわば純粋劇作家を世に送り出した。松原俊太郎である。
松原俊太郎は、AAF戯曲賞がそのコンセプトを見直し審査員を一新した最初の回だった第15回をまったくのオリジナルの戯曲『みちゆき』で受賞した。この作品は同賞の規定により審査員のひとりである三浦基の演出で三浦の劇団「地点」によって上演され、その後、松原は地点の本公演のために新作戯曲『忘れる日本人』を書き下ろした。聞けば第3作もすでに控えているという。三浦はAAFの選評で松原を「大型新人の登場」と絶賛し、「日本語でここまで劇を紡ごうとしていること、この文体を日本人が書いているということにすごく希望を持ちました」と述べていた。三浦が長らく物故作家の名作戯曲ばかりを上演してきたことを思うと、松原との出会いがどれほど大きなものであったかがわかる。地点はいうなれば「座付作者」を得たのである(とはいえ三浦はこのような見方を否定しており、他の演出家も松原戯曲を取り上げることを強く推奨している)。
私は松原とはまだ一度も会ったことがないのだが、聞けば彼はもともと小説家を志していたのだという。確かに『みちゆき』『忘れる日本人』を読んでみても、その日本語戯曲としての紛れもない特異性、独自性は、上演というリアライゼーションを一顧だにしていないかにさえ思える、いわば「文学」的な佇まいによるところが大きい。
誤解のないようにすぐに言い添えておくが、これはもちろん松原が「戯曲」を「演劇」から完全に切り離して単なる文字の連なりとして書いたということではない。むしろ彼は明確なヴィジョンを持っているかに見える。しかしそれ自体が現実の上演とはあらかじめ摩擦を起こすようなものなのである。上演への抵抗としての戯曲。そして三浦基が自ら演出を買って出たのは、これゆえだったのだと私は思っている。
松原の戯曲は、演出家への静かな挑戦として存在している。ただ口に出して読むだけではどうにもならない、凝集した謎の物体のようなテクストなのだ。戯曲『みちゆき』はAAF戯曲賞のホームページにPDFで公開されており、『忘れる日本人』は地点の雑誌『地下室』草号1~3に分載されている。
そしてここに松原俊太郎の小説「またのために」が登場した。彼の小説を読んだのは初めてのことである。実に興味深いことに、彼の戯曲を読んだときの印象とは真逆に、彼の小説はすこぶる演劇的だと私には思えた。それはつまり、複数の声の交錯としてのテクストということである。戯曲であれば、ト書きと台詞という峻別が前提として機能しているが、小説の場合はそうはいかない。ここでの地の文と丸括弧()の関係性は極めて独特であり、油断も隙もならない。舞台上において、少なくとも発話者の姿(誰が語っているのか?)は明瞭である。しかし小説はそうではない。小説は見えない。だが聞こえはする。「またのために」の作者は、このことにすこぶる意識的である。そして、にもかかわらず、ここではテレビの画面=映像が、ほとんど舞台装置と言ってもいい重要な役割を果たしているのだ。この倒錯ぶり!
松原俊太郎は、現代日本演劇における、新たなる劇作家の時代を切り拓くだろう。それは同時に、演劇と文学の共闘の可能性を、今あるものとはまた違ったかたちで開示するものに他ならない。
●佐々木敦の当エッセイと、松原俊太郎の書き下ろし短篇小説「またのために」は、『悲劇喜劇』2018年1月号(12/7発売)に掲載。
●略歴 佐々木敦(ささき・あつし)批評家。HEADZ主宰。2013年から2016年まで早稲田大学文化構想学部客員教授。新刊に『新しい小説のために』(講談社)、『筒井康隆入門』 (星海社新書)。他の著書として『ニッポンの思想』『あなたは今、この文章を読んでいる。』『ニッポンの音楽』『ゴダール原論』『例外小説論』『ニッポンの文学』など。2017年9月、山下澄人作、飴屋法水演出の『を待ちながら』(HEADZ/アゴラ企画・こまばアゴラ劇場)をプロデュース。
●略歴 松原俊太郎(まつばら・しゅんたろう)作家、雑誌『地下室』主筆。一九八八年五月生。熊本県熊本市出身。神戸大学経済学部卒。地点『ファッツァー』で演劇と出会う。二〇一五年、処女戯曲『みちゆき』で第十五回AAF戯曲賞(愛知県芸術劇場主催)大賞を受賞。二〇一七年四月、戯曲『忘れる日本人』が地点によりKAATにて上演。演劇計画Ⅱ(京都芸術センター主催)の委嘱劇作家として戯曲『カオラマ』第一稿を演劇計画Ⅱ公式ウェブサイトで公開。二〇一八年二月二十六〜三月十一日(休演日:三月一日、三月七日)に書き下ろし戯曲『正面に気をつけろ』が地点によりアンダースローにて初演予定。

