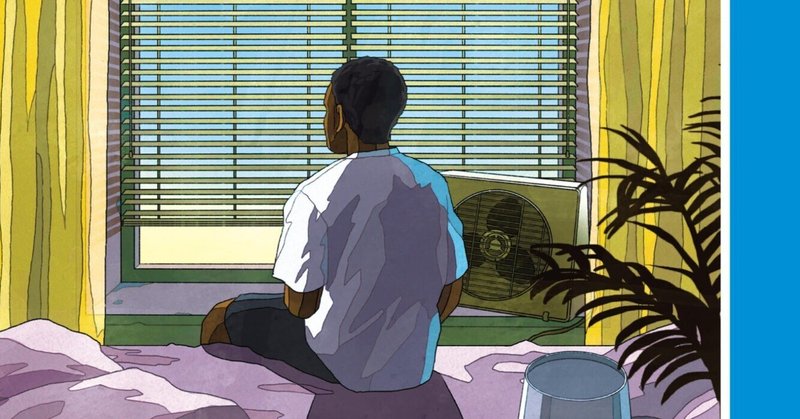
クィアの人々の「リアルな生活」に、作家として言葉と物語を与えること──ブッカー賞最終候補作『その輝きを僕は知らない』解説(早稲田大学教授・佐久間由梨)
英国最高の文学賞ブッカー賞2020年度の最終候補の5作に、デビュー作でありながら選出された『その輝きを僕は知らない』(原題:REAL LIFE、翻訳:関麻衣子)は、中西部の都市の大学院に通う黒人のゲイの学生と、その周囲で揺れ動く人間関係を描いた作品です。

装画:カチナツミ 装幀:田中久子
あらすじ:ある輝かしい夏の日。中西部の名門大学の大学院で、生物化学の研究をするウォレスは二つの“死”に直面していた。一つは、二週間前に亡くなった父の死。もう一つは、夏のすべてを費やした線虫の培地にカビが生え、瀕死状態となっていること。しかし、ウォレスはこれっぽっちも悲しみを感じていなかった。感情と向き合うことを避けていた中、同級生の同性の友人と一夜を共に過ごした。ウォレスの中に眠っていた過去のトラウマ、温もりへの渇望が目を覚ました──。
著者のブランドン・テイラーは1989年、アメリカ南部生まれ。本書は、保守的なキリスト教の教えが根付く地域でクィアとして生きてきた著者の経験が色濃く反映された作品です。
この記事では、本書の原題でもある「リアルライフ(本物の人生)」というワードに込められた著者の想いと、白人の割合が多いアメリカ中西部独特のマイノリティの生きづらさ、そしてクィアの生きづらさを著者がどう描いているかについて、早稲田大学教授(アメリカ文学)の佐久間由梨さんに解説いただきます。
◆作品と著者について
ブランドン・テイラーの初めての小説『その輝きを僕は知らない』(原題:Real Life)は、2020年にペンギングループのリバーヘッド・ブックスから刊行され、同年に栄誉あるブッカー賞の最終候補作に選ばれた。当時、テイラーはまだ31歳。アイオワ大学創作科で修士号を取得したばかりだった。

『その輝きを僕は知らない』はテイラーの初めての邦訳作品となるため、作者の経歴から紹介したい。ブランドン・テイラーは1989年にアメリカ南部のアラバマ州で生まれ、州都モンゴメリーから近い田舎町で育った。テイラーはアフリカ系アメリカ人で、家族は貧しく、両親は文字を読むことができなかった。テイラーは性的マイノリティ(クィア)で、アメリカ南部は、そんなテイラーにとっては生きづらい場所だった。保守的なキリスト教の教えが根づく南部では、同性愛は罪とされる。テイラーが少年期を回想するエッセイに記しているように、神からの怒りや軽蔑を感じる教会に行くことを、少年時代にテイラーは何よりも恐れていた。

ⒸBill Adams
南部から逃げだすことばかりを考えていたというテイラーの夢が叶うときがやってくる。アラバマ州のオーバーン大学を卒業し、中西部に位置するウィスコンシン州にある州立大学、ウィスコンシン大学マディソン校の大学院(生物化学科)に合格したのだ。後にテイラーはそのときの気持ちについて語っている──「『ああ、やっと南部を離れることができる、[中西部では]みな自分に優しくしてくれるだろう』と思っていました」。しかし、テイラーは2013年に入学したウィスコンシン大学を去り、アイオワ大学に移る決断をした。中西部への理想が幻滅へと変わり、やがて辛い現実へと一変するまでの経緯は、実体験に基づく本小説に物語化されているとおりだ。テイラーは本小説を、ウィスコンシン大学に在学中、5週間という驚くほどの短期間で書きあげた。
2017年にアイオワ大学創作科に進学した前後の活躍には目覚ましいものがある。非営利のデジタル出版社による文芸誌〈エレクトリック・リテラチャー〉の「おすすめの本」コーナーの編集や、文芸サイト〈リテラリー・ハブ〉のライターを務め、〈The Rumpus〉や〈Catapult〉などのオンライン文芸誌、〈Out〉などのLGBTQのライフスタイルをめぐる雑誌にも寄稿している。『その輝きを僕は知らない』はブッカー賞の最終候補に加え、全米批評家協会賞のデビュー作部門の最終候補になり、全米図書賞を主催する全米図書協会が科学技術への理解を深めるために設立した「科学+文学」プログラムでも受賞をはたした。2021年に刊行された2作目となる短篇集Filthy Animals(未訳)はベストセラーになり、優れた短篇作品集に贈られるストーリー賞を受賞している。この先のさらなる活躍が楽しみな作家のひとりだ。
さて、デビュー作の原題にもなっている「リアル・ライフ」というフレーズは、テイラーの人生、作家としての意識、影響された文学伝統、作品の特色を表す、巧みな比喩になっている。
◆テイラーの人生──「本物の人生」を生きること
作者テイラー、そして小説の主人公ウォレスは、ともにクィアの黒人男性で、南部を離れ中西部の大学院に進学した。「リアル・ライフ(本物の人生)」を生きなおすために、2人が南部を離れる決断をしたともいえそうだ。南部では同性愛者であることを隠して、嘘の自分を生きざるをえなかった。でも、中西部では嘘偽りのない「本物の人生」を歩んでいくことができるかもしれない。「リアル・ライフ」というフレーズには、こうした期待感が込められている。
◆作家としての意識──クィアの人々の「リアルな生活」を描くこと
「リアル・ライフ」というフレーズには、クィアの人々の「リアルな生活」に、作家として言葉と物語を与えたいという想いも込められている。テイラーはクィア作家としての挑戦をめぐるエッセイに、「私たちの経験を、オーガニックで、リアルで、真実であると感じられるような方法で書きたいのです」と記す。こうした目的意識は、クィアの人々の「リアルな生活」をめぐる文学作品が少なく、入手も困難であるという現状を反映してのものだ。
10代のころ、テイラーはオンラインでゲイ小説のリストを発見し、書店に買いにいったのだという。リストの一冊にあげられていた同性愛者の黒人作家であるジェイムズ・ボールドウィンの小説『ジョヴァンニの部屋』を探したが、どのコーナーにも見つからない。店員に尋ねると、「そういったものはここには置いていません、ネットで買ってください」と、恥を知れといわんばかりの口調で冷たくあしらわれてしまう。これが保守的な南部の書店チェーンの現実なのだ。

パリに滞在中のアメリカ人青年デイヴィッドは、ある夜、バーテンダーをする青年ジョヴァンニと知り合い、安アパートで同棲生活を始める……。
だから、テイラーがクィアの人々のリアルに触れるような作品を執筆しはじめたことは、ごく自然な流れであるといえる。テイラーは影響を受けた文学作品3冊を紹介しているが、いずれもが保守的な地域で成長する同性愛者の少年たちの苦悩についてのものだ。
韓国系アメリカ人のアレグザンダー・チーによる小説『エディンバラ──埋められた魂』(村井智之訳、扶桑社、2014年)では、韓国系アメリカ人の少年が性的虐待のトラウマに悩まされながら同性愛者としてのセクシュアリティをみいだしていく。
ガラード・コンリーによる回想録Boy Erased: A Memoir(2016年、未訳。2018年に『ある少年の告白』として映画化されている)には、アーカンソー州の保守的な地域に生まれた作者が同性愛の治療プログラムに送られたときの経験がつづられる。
ニック・ホワイトによる小説How to Survive a Summer(2017年、未訳)では、ミシシッピ州で牧師の父を持つ同性愛者の主人公が、同性愛の治療施設で過ごした10代を忘れようともがいている。
ボールドウィン、チー、コンリー、ホワイトと4名を並べてみると、同性愛が悪とされるキリスト教の世界で育った少年たちのリアルな生活や苦しみを描いた物語に、テイラーが創作モデルをみいだしていることがわかる(ジェイムズ・ボールドウィンの継父もキリスト教の説教師だった)。本小説はこうしたクィア文学の系譜にある。
◆本小説の特色──「中西部のリアル」を記すこと
『その輝きを僕は知らない』では、「リアル・ライフ」というフレーズが、セクシュアリティだけではなく人種問題へと結びつけられていく。物語のあらすじは、テイラーの自伝のようでもある。アフリカ系アメリカ人でクィアでもある主人公ウォレスは、南部アラバマ州の貧困家庭出身だ。人種(黒人)、セクシュアリティ(同性愛者)、階級(貧困層)という複数の要素において差別の対象となりうることを自覚するウォレスの苦悩は、誰にも言えない秘密によってもなお深まる。幼少期、ウォレスは両親の友人の男性から性的虐待を受けていた。ウォレスを守ることなく傍観した父親、性的虐待がウォレスの落ち度なのだとののしった母親、ウォレスの同性愛を背教行為とみなす信心深い祖父母。おぞましい過去、暴力や貧困、無知と偏見により理解がない家族、そうした全てと決別すべく、ウォレスは中西部の大学院に進学した。新しい自分に生まれ変われることを夢見て。
「中西部のリアル」は、期待を胸に進学したウォレスが中西部で味わうことになるマイクロアグレッション(マイノリティにたいして無意識のうちに偏見ある態度をとることや、意図せずに傷つける発言をすることを意味する)により暴きだされていく。人権意識が高い学生たちが集う名門大学院においては、一部の例外を除けば、あからさまな人種差別発言をする人々は少ない。だが、人種差別はより感知されにくい形へと姿を変え、日常の端々に現れ、ウォレスを傷つけ、大学院を辞めようかと悩むところまで追いつめる。そんなウォレスを励まそうとするフランス人で同性愛者でもある大学院生のロマンの言葉遣いはまさに、マイクロアグレッションの一例だ。ロマンは、黒人のウォレスが白人よりも優遇されていること、人種という「欠陥」にもかかわらず合格させてくれた大学に恩があることを忘れずに、退学を思いとどまるべきだと説得する。ウォレスはこれを、助言を装いながらウォレスを過小評価する人種差別発言として受け取り、一人傷つく。
ウォレスの研究指導をする白人女性シモーヌも、助言と励ましを装った言葉により存在するはずの人種差別を覆い隠そうとする。ウォレスは人種が原因で研究仲間に見下された口調で話しかけられてしまうことを訴え改善を求める。しかしシモーヌは、その原因がウォレスの人種にあるのではなく、彼の努力不足や実力不足にあるのだからもっと頑張るようにと励まし、人種差別を個人責任の問題へとすりかえようとする。たとえ人種差別が存在することが明らかな場合でも、白人は周囲の白人を気遣い、傍観と沈黙でやりすごそうとする。
小説には特定の大学名は記されていないが、湖沿いのテラスの情景描写から、2つの湖に挟まれた地峡地帯にあるウィスコンシン大学マディソン校がモデルになっていることがわかる。

フットボールの試合の日には赤いユニフォームを着たファンでテラスが埋め尽くされる。
テイラーがマディソン校に在籍していたのは2013年からの3年間ほど。実は、テイラーが入学する2年前まで、私もマディソン校の博士課程に5年間在籍していた。白人が大多数を占める大学とはいえ、英文学科でアフリカ系アメリカ文学を研究していた私は、アフロ・アメリカン・スタディーズの授業に参加することも多く、有色人種のクラスメートがいる環境で学んだ。だが、理系学部では状況は異なっていたのだろう。テイラーは生物化学科の90人ほどの学生のうち唯一の黒人学生だったというし、小説のウォレスは生物化学科創設以来30数年で初の黒人学生だったと記される。
はずかしながら、私はこれまでウィスコンシン大学マディソン校の人種比率を意識したことすらなかった。小説を読んだあとデータを調べ、多様性と包摂を掲げる母校の内実を知り驚いてしまった。2021年の時点でアフリカ系アメリカ人学生の割合は学部・大学院ともに2%ほど、アフリカ系アメリカ人の教員は3%ほど。白人学生は学部で65%、大学院で50%以上だった。
大学キャンパスで黒人学生を侮辱する事件が多発していることも知った。2016年以降、抗議の動きがはじまり、SNS上では#TheRealUW(#真のウィスコンシン大学)というハッシュタグで、キャンパス内の人種差別の経験が共有されるようになった。ハッシュタグと本小説のタイトルの両方に、「リアル」という語があるのは偶然なのだろうか。いずれにせよ、小説と同じく、#TheRealUWも中西部に潜む人種差別のリアルを可視化しようとしているのだ。

◆本小説の特色──マイノリティの「本物の現実」を想像できるのか
「リアル・ライフ」というフレーズには、マイノリティが他のマイノリティの「本物の現実」を想像することができるのかを問う意図もあると考えられる。アメリカのマイノリティと聞くと、そこには白人は含まれないと思われるかもしれない。しかし、本小説の白人の登場人物たちを見ればわかるとおり、たとえ白人であっても、性別、セクシュアリティ、階級といった点でマイノリティの属性を持っていることも多い。そんな一枚岩ではない白人たちを大多数とする世界に、ウォレスや中国系のブリジットなどの有色人種が加わることで、異なるマイノリティの属性を持つ人々が織りなす複雑な人間模様が浮かびあがってくるのだ。数名の登場人物の造形を見てみると次のようになるだろう。
◆ウォレス──同性愛者で南部の貧困層出身の黒人男性
◆ミラー──南部の貧困層出身の白人男性。異性愛者として自己認識しているが、ウォレスと性的関係を持つ
◆ブリジット──医者とIT企業に携わった両親を持つ中国系アメリカ人女性
◆デーナ──研究室では最も若手の白人女性
中産階級以上で異性愛者の白人男性を頂点とする社会において、これらの登場人物はみな、黒人、同性愛者、貧困層出身、アジア系、あるいは女性であるというマイノリティの属性を持っている。白人女性デーナについては説明が必要かもしれない。デーナは一見するとウォレスを差別するマジョリティ側にいるが、彼女には理系分野の女性であるというマイノリティの属性があり、だからこそ同じマイノリティであるウォレスをライバル視してしまうことがほのめかされている。デーナはウォレスを「ミソジニスト(女性嫌悪者)」と呼び、「女は新種の黒人で新種のホモ野郎ってことなんでしょ(women are the new niggers, the new faggots)」(P.101-102より)と侮蔑表現でののしる。このセリフには「どうせ女性が権利を獲得できるのは、黒人と同性愛者の後ってわけなんでしょ」というニュアンスがある。ウォレスのような黒人で同性愛者でもある男性が被害者ヅラをすることで優遇され、それにより白人女性の権利獲得が後回しにされてしまうことへの怒りをぶちまけているのだ。
登場人物の大半が何らかのマイノリティ性を持っているにもかかわらず、みな他のマイノリティの苦しみを想像することができない。たとえば、ウォレスとミラーには貧困層出身という共通点があり、身体と心で互いにひかれあってはいるものの、信頼関係を築くことはできない。ウォレスとブリジットという有色人種同士の親しい友人間にすら「硬い壁」がある──
その壁にふたりとも身体を押しつけているけれど、破ることはできず、本物の現実には触れられない
他のマイノリティの「本物の現実」を想像し、それに触れることは、あまりにも難しい。
テイラーは、マジョリティ対マイノリティという単純化された図式を超えて、ときに暴力的にもなるマイノリティ同士の人間関係や分断を、複雑なニュアンスや感情を伝えることのできる会話や性描写、鋭い観察眼と分析力を持つ語りにより、小説世界に再現するのだ。
◆多様性時代の文学と文学賞
最後に、本小説が最終候補として選ばれた2020年のブッカー賞が、史上最も多様なラインアップで話題になったことも追記したい。最終候補六作品のうち4作が有色人種、4作が女性作家によるもので、異性愛者の白人男性による作品は一つもなかった。審査委員長の黒人女性マーガレット・バズビーは、同年のブッカー賞候補作の中には「文化的変化の瞬間」を象徴するものもあると述べた。白人男性作家が中心だった文学賞という制度は、マイノリティの属性を持つ作家たちが躍進する場へと変化しつつある。
2016年、テイラーも「アメリカを再び偉大にしよう」というトランプ前大統領の言葉を批判的に援用した「全米図書賞を再び『偉大に』する必要がない理由」というエッセイで、白人男性ばかりが受賞できる文学賞という制度は変わるべきだと主張していた。「アメリカ文学は変化し、より多様になっています。制度も遅れをとることなく、因襲的に疎外されてきたコミュニティの作品を認めはじめることが重要です。そうすることで、私たちの文化は生き生きと活気づいたものであり続けることができるでしょう」
表面的には多様性と包摂が尊重されているものの、現実には差別が残り、マイノリティ同士が分断する現代。そんな時代に、文学作品は何を描き、何を伝えていけるのか。文学賞という制度はどうあるべきか。テイラーの作品を手掛かりに考えてみることもできそうだ。(🄫佐久間由梨)
───────────────
解説を執筆するにあたり、以下のウェブサイトを参考にしました。
***
『その輝きを僕は知らない』は早川書房より好評発売中です。

