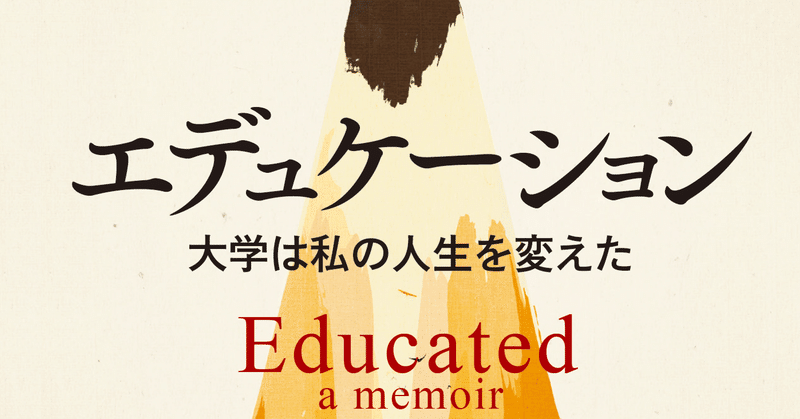
【特別公開】『エデュケーション』第17章——「ホロコーストって、どういう意味なんですか?」
全世界800万部超。狂信的モルモン教徒の両親により、学校に通うことを禁じられた少女が、ケンブリッジ大学で博士号を得るまでの壮絶な半生を自ら綴る、タラ・ウェストーバー[著]/村井理子[訳]『エデュケーション――大学は私の人生を変えた』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)の第17章を抜粋し、特別公開いたします。
兄の支援のもと勉強を続け、ACT〔アメリカン・カレッジ・テスト〕で高得点を記録し、ブリガム・ヤング大学への入学を果たした主人公、タラ。しかし、彼女は17年間の人生で両親の教育によって身につけていた「常識」が歪な形をしていたことを、入学してすぐに痛感することになり——

第17章 聖なるままで
一月一日、母が新しい生活の場まで私を送り届けてくれた。あまり多くは持ってはいかなかった。ホームメイドの桃の瓶詰めを一ダース、寝具類、それからゴミ袋に詰めた服だけだった。州間高速道路を飛ばしながら、風景が様変わりし、険しくなっていくのを眺めていた。ベア・リバー山脈の起伏に富んだ黒い頂が、カミソリのように鋭いロッキー山脈に姿を変えていく。大学は地球から突き出した白い大山塊、ワサッチ山脈の中心部に位置していた。とても美しい山だったけれど、私にとってその美しさは攻撃的で、まるで威嚇されているようだった。
私のアパートメントはキャンパスから一マイルほど南に位置していた。キッチン、リビングルームに加えて小さなベッドルームが三部屋あった。もう一人の住人の女性はクリスマス休暇から戻ってきていなかった──それが女性だと知ったのは、ブリガム・ヤング大学では、すべての住居が性別によって分けられていたからだ。荷物を車から運び入れるのにものの数分しかかからなかった。母と私は所在なげにキッチンに立っていたが、しばらくして母は私を抱きしめると、あっという間に車で去っていった。
私は誰もいない静かなアパートで、三日間を過ごした。でも、実際のところまったく静かとは言えなかった。どこに行ってもやかましいのだ。街で数時間以上過ごしたことはそれまで一度もなく、ひっきりなしに侵入してくる聞いたこともないような騒音から自分を守ることは不可能だった。横断歩道の信号の音、サイレンのけたたましい音、エアブレーキのシューッという音。歩道をいく人びとのささやき声でさえ私の耳には別々の音として届いていた。山頂の静寂に慣れていた私の耳は、すっかり疲弊していた。
一人目のルームメイトが現れたときには、すでにひどい睡眠不足になっていた。彼女の名前はシャノンで、通りを挟んだ場所にある美容学校で学んでいた。派手なピンク色のパジャマズボンに、細いストラップがついた体にフィットする白いタンクトップを着ていた。私は剥き出しになった彼女の肩をじっと見つめた。このような服装の女性たちに出会ったことは前にもあった──父は彼女らを異教徒と呼んでいた。不道徳さが伝染でもするかのように、私は異教徒の女性には近づかないようにしていた。そういった女性がまさに私の部屋にいる。
シャノンは明らかにがっかりした様子で私を眺めまわした。私は大きなフランネルのコートとぶかぶかのジーンズという格好だった。「あんた、いくつ?」と彼女は聞いた。「新入生よ」と私は答えた。一七歳だとは認めたくなかったし、私は高校三年生のはずなのだ。
シャノンは流しまで歩いていった。彼女の背中には「ジューシー〔セクシーという意〕」という文字が書いてあった。それは私には受け入れがたいものだった。自分の部屋に向かって後ずさりながら、もごもごと、もう寝ると伝えた。
「いいじゃん」と彼女は言った。
「教会は早いから。私はいつも遅くまで起きてるけど」
「あなた、教会に行くの?」
「あたりまえじゃん。あんたも行くでしょ?」
「もちろん行っているけど。でもあなたが、本当に?」
彼女は私をじろりと見て、唇を噛かんだ。そして「教会は八時だから。おやすみ!」と言った。
寝室のドアを閉めた私は混乱していた。あの彼女が、どうしたらモルモン教徒だっていうの?
父は異教徒はありとあらゆる場所にいると言っていた──モルモン教徒の多くですら異教徒で、彼らはそれを知らないだけなのだと。私はシャノンのタンクトップとパジャマを思い出し、突然、ブリガム・ヤング大学の学生はすべて異教徒なのではないかと不安になった。
翌日、もう一人のルームメイトが到着した。彼女の名前はメアリーで、三年生で幼児教育について学んでいた。彼女は床に届く長さのスカートという、私が日曜日のモルモン教徒に期待する格好をしていた。彼女の服装は私にとっては合い言葉のようなものだった。それは彼女が異教徒ではないという信号に思えて、しばらくは孤独を感じることがなかった。
ただそれも、その夜までのことだった。メアリーは突然ソファから立ち上がると、「明日から授業がはじまるから、食料品を買いだめしないと」と言った。そして家を出て、一時間後に紙袋を二つ抱えて戻ってきた。安息日に買い物をすることは禁止されている──私はそれまで、日曜日にはガム程度のものしか買ったことがなかった。でもメアリーは神の戒律を破るものだと認めるふうもなかった。何ごともなかったかのように、卵やミルクやパスタを紙袋から出して共用冷蔵庫に詰めていた。それからメアリーはダイエットコークの缶を取り出した。それは父が神の健康への忠告に反するものだと常々言っていた飲みものだ。私はふたたび部屋に逃げ帰った。
*****
翌朝、乗るバスを間違えた。なんとか学校にたどりついたときには、講義は終わりに近づいていた。繊細な顔立ちをした細身の教授が、最前列近くの唯一空いていた席を手で示してくれるまで、私はぎこちなく教室の後ろに立っていた。周囲の視線を感じながら席についた。その授業はシェイクスピアに関するもので、私がそれを選択したのは、シェイクスピアという名前は聞いたことがあったし、それは良い兆しだと思ったからだ。しかし講義に参加してみれば、私はシェイクスピアのことなど何ひとつ知らないことに気づいただけだった。聞いたことがある言葉、それだけのことだった。
ベルが鳴ると、教授が私の机のところまでやってきた。「ここはあなたが来る場所じゃないわ」と彼女は言った。
私は困惑しながら教授を見つめていた。もちろん、私が来るべき場所ではなかったけれど、彼女はどうやってわかったのだろう? いまにも彼女にすべてを白状しそうになっていた──それまで一度も学校に行ったことがなかったこと、高校の卒業に必要な要件をしっかりと満たしていなかったこと──でも彼女は「ここは四年生のクラスだから」と言った。
「四年生のクラスがあるんですか?」と私は言った。
私がジョークでも言ったみたいに、教授は目をくるりとまわした。「ここは三八二教室。あなたは一一〇教室でしょ」
彼女が言ったことを理解するのに、私はキャンパスじゅうを歩き回らなければならなかった。自分の授業の時間割を調べ、そしてはじめて授業名の横に数字が書いてあることに気づいた。
教務課に行くと、新入生を対象としたコースのすべてが定員に達していると知らされた。数時間ごとにネットをチェックして、誰かがキャンセルしたらその授業を受講すればいいのだと言われた。その週の終わりまでには、英語初級、アメリカ史、音楽、宗教の授業になんとか滑り込むことができたが、西洋芸術史のクラスは大学三年生レベルに留まることになってしまった。
新入生の英語のクラスは、「エッセイ形式」と呼ばれるものについて話しつづける、二〇代後半の明るい女性が担当していた。彼女によれば、それはすでに高校で学んだはずのものだった。
つぎのクラスはアメリカ史で、預言者のジョセフ・スミスにちなんで名づけられた講堂で授業は行われた。合衆国建国の父については、父から教えてもらっていたので、アメリカ史は簡単だと思っていた──ワシントン、ジェファーソン、マディソンのことは知っていた。でも教授はほとんど彼らについて言及せず、その代わりに「哲学的基盤」について語り、それまで一度も聞いたことがなかったキケロとヒュームの諸作品について話していた。
次回の授業のはじめには読解の小テストがあると伝えられた。私は二日間をかけて、教科書にぎっしり詰まった文章からなにかしら意味を読み取ろうともがいたが、「公民的人文主義」や「スコットランド啓蒙」のような言葉がブラックホールのようにページ上に点在し、ほかの言葉をすべてその穴に吸い込んでしまった。テストを受けたが、全問不正解だった。
その失敗は私の心に残りつづけた。それは、自分がなんとかやっていけるか、私が受けた教育が十分だったかどうかを推しはかる最初のハードルだった。テストのあとでは、答えははっきりと出たように思えた。十分ではなかったのだ。その事実に気づくことで、自分の生い立ちに怒りを感じるべきなのかもしれないが、そうはならなかった。父に対する忠誠心は、私たちの距離に比例して高まっていた。山の上では、私は反逆者でいられた。でもここでは、このやかましくて、明るい場所、悪魔を装った異教徒に囲まれた場所では、私は父が与えてくれたすべての真実と教義にすがりついた。医師たちは地獄の申し子だった。ホームスクールは神の掟だったのだ。
小テストでの失敗は、古い信念への私の新たな献身に何の影響も及ぼさなかった。しかし西洋芸術史の講義での失敗は違った。
その朝、教室につくと、明るい陽光が高い壁の窓から柔らかく差し込んでいた。私はハイネックのブラウスを着ていた女子の横の席を選んだ。彼女の名前はヴァネッサだった。
「一緒にいようよ」と彼女は言った。「このクラスで新入生なのは私たちだけみたいだから」
小さな目と尖った鼻が特徴的な年老いた男性が窓を閉め、講義をはじめた。彼がスイッチを入れると、プロジェクターの白い光が部屋じゅうを照らした。それは絵画の映像だった。教授はその構図、筆の運び、そして歴史について語りはじめた。そしてつぎの絵画を見せ、そのつぎを見せ、またつぎを見せた。
そしてプロジェクターは奇妙な映像を映し出した。色あせた帽子とオーバーコートを着ている男性の絵だ。その男性の後ろには、そびえ立つようなコンクリートの壁があった。小さな紙を顔の近くに持っていたが、男性がそれを見ている様子はない。彼はこちらを見ていたのだ。
もっと詳しく見ようと、講義のために購入した画集を開いた。その絵の下に、ある言葉がイタリック体で書かれていたが、私にはその意味が理解できなかった。真んなかに書かれたそのブラックホールのような文字列は、残りのすべてを呑み込んでいた。ほかの生徒が質問する姿を見て、私も手を上げた。
教授が私を指名した。私は文章を大きな声で読み上げ、そしてその文字列で立ち止まった。
「この言葉、よくわからないんですけど」と私は言った。「どういう意味なんですか?」
部屋じゅうが沈黙した。静けさでもなく、騒音をかき消したのでもなく、それは完全な、暴力的なまでの静寂だった。紙がこすれる音も、鉛筆が出すさらさらとした音も聞こえなかった。
教授は口を固く結んだ。「もう結構です」と彼は言い、自分のメモに視線を戻した。
残りの時間、私は身動きひとつできなかった。自分の靴を見つめつづけ、いったい何が起きてしまったのかと考えた。そしてなぜ、私が顔を上げるたびに、まるで化け物を見るように誰かが私をじろじろと見ているのだろうと考えた。もちろん、私は化け物だったのだ。そして私はそれを知っていた。でも、どうやって彼らがそれを知ったのかが理解できなかったのだ。
ベルが鳴り、ヴァネッサがバッグにノートを突っ込んだ。そして一瞬動きを止めて、そしてこう言った。「からかうべきじゃないわ。ジョークじゃないんだからね」私が答える前に、彼女は立ち去った。
全員が出ていくまで私はそこに座っていた。コートのチャックがひっかかってしまったふりをして、誰とも目を合わせないですむようにしていた。そして私は、「ホロコースト」という文字を検索するため、コンピュータ室に急いだ。
そこにどれだけの時間座り込んで、その記述を読んでいたのかわからないけれど、ある時点で、私はもう十分だと思った。背もたれに体を預けて、天井を見た。きっとショック状態だったのだろう。しかしそれは、恐ろしいできごとを知るに至ったショックだったのか、自分の無知を悟ったことに対するショックだったのか。私にはわからなかった。収容所でもなく、穴でも、ガス室でもなく、私は母の顔を思い浮かべていた。感情の波に圧倒されていた。それまでいっさい経験したことがなかった強烈な感情で、いったいそれが何なのか、理解できなかった。母にわめき散らしたい気持ちだった。実の母に対してそのような感情を抱いた自分自身に、私は怖くなった。
記憶をたどった。「ホロコースト」という言葉は完全に未知なものではなかったように思えたのだ。たぶん母は、二人でバラの実を摘んでいたとき、ホーソンのチンキ剤を作っていたとき、私に教えてくれていたのだろうと思う。ずっと昔、ユダヤ人がどこかで殺害されたというあいまいな知識は私にもあったように思う。でもそれは、小さな紛争だったと考えていた。父がよく話していた、専制的な政府によって五人の殉教者が命を落としたボストン虐殺事件のような。そんな勘違いをするなんて──五人と六〇〇万人はあまりに大きな差だ──ありえないと思った。
つぎの講義の前にヴァネッサを見つけたので、ジョークについて謝罪した。言い訳はしなかった。なぜなら言い訳などできなかったからだ。ただ、申し訳ないことをした、二度としないとしか言えなかった。その約束を守るため、私は学期末まで一度も挙手することはなかった。
土曜日、私は宿題を山積みにして机に向かっていた。安息日をないがしろにすることはできなかったから、その日のうちにすべて終わらせなければならなかった。
午前と午後を使って歴史の教科書を読み解こうとしたが、うまくいかなかった。夜になって、英語の授業用に自分についてのエッセイを書こうとしたが、それまで一度もエッセイを書いたことがなかったし──誰にも読まれていない、罪と後悔についてのエッセイは別だが──どうやって書いたらいいかもわからなかった。教師が言った「エッセイ形式」という言葉の意味がさっぱりわからなかったのだ。私は何行か書いては消し、そしてふたたび書きはじめた。真夜中すぎまでそれをくり返した。
やめるべきだとわかっていた──だってもう神の時間になったのだから──でも音楽理論の課題にも手をつけておらず、提出期限は月曜の朝七時だった。安息日は寝て起きたときにはじまるのだという理屈をでっちあげ、私は勉強を続けた。
机に突っ伏した状態で目が覚めた。部屋はすでに明るかった。シャノンとメアリーがキッチンにいる音が聞こえた。私は日曜日用のドレスを着て、教会まで三人で歩いて向かった。学生集会の日だったので、誰もがルームメイトと一緒に座ることになっていた。私はルームメイトと一緒に信徒席についた。シャノンがすぐに、後ろに座っている女の子とおしゃべりをはじめた。私は教会のなかを見まわして、膝上のスカートをはいている女性の多さにショックを受けた。
シャノンと話をしていた女の子は、午後に映画を観においでと誘ってくれた。メアリーとシャノンは同意したが、私は首を振った。日曜日に映画は観ないからだ。
シャノンは目をまわして見せた。「彼女ってほんっとに信心深いから」と彼女はささやいた。
父がみんなとは別の神を信仰していたことは知っていた。子供のころから、町に住む人たちと同じ教会に所属してはいても、私たちの信仰は違うのだと知っていた。人びとは慎み深さを信じていたが、私たちはそれを実践していた。人びとは神の治癒力を信じていたが、私たちは神の手に自らのけがを委ねた。人びとはキリストの再臨に備えるべきと信じていたが、私たちは実際に準備していた。記憶をたどってみても、真のモルモン教徒とよべるのは私の家族しかいなかったけれど、それでもどうしたわけか、この大学で、そしてこの教会のなかで、私ははじめてほかの信徒との隔たりの大きさを感じたのだ。いまは理解できる。私は自分の家族か異教徒のどちらか一方の側に立つことはできたが、そのあいだには足場がなかったのだ。
礼拝が終わり、私たちは日曜学校に向かった。シャノンとメアリーは一番前に近い席に座った。二人は私の席をとっておいてくれたけど、安息日の約束を破ったことを考えると、そこには座れなかった。大学にきて一週間も経っていないというのに、神の時間を一時間も盗んでしまったのだ。たぶんこれが、父が私にここに来てほしくなかった理由なのだろう。彼女たちのような、信心が足りない人たちと暮らしたら、私が同じようになってしまうと知っていたのだ。
シャノンが私に手を振ると、TシャツのVネックの胸元が下がった。私は彼女を通りすぎてそのまま歩きつづけ、シャノンとメアリーからできるだけ遠く離れた教会の片隅まで行った。懐かしい光景に私は安堵を憶えた。幼いころの私も、日曜学校の他の子供たちから離れ、ひとり教室の隅にたたずんでいたものだった。同じ光景がいま再現されていた。この場所に来てはじめて感じたその懐かしさを、私は楽しんだ。
——————————
本書の詳細は▶こちらへ
◆書籍概要
『エデュケーション――大学は私の人生を変えた』
著者: タラ・ウェストーバー
訳者:村井理子
出版社:早川書房
本体価格:1,360円
発売日:2023年2月7日
◆著者紹介
タラ・ウェストーバー(Tara Westover)
1986 年、アイダホ州生まれ。モルモン教徒・サバイバリストの両親のもと、学校にも病院にも通わず育つが、兄の影響で大学入学を決意。2004 年ブリガム・ヤング大学に入学、2008 年卒業。その後ゲイツ・ケンブリッジ奨学金を授与され、2009 年にケンブリッジ大学で哲学の修士号を、2014 年には歴史学の博士号を取得。2018 年に発表した本書は記録的なベストセラーとなり、著者は2019 年『TIME』誌「世界で最も影響力のある100 人」に選出された。2020 年よりハーバード大学公共政策大学院上級研究員。
◆訳者紹介
村井理子(むらい・りこ)
翻訳家・エッセイスト。1970 年静岡県生まれ。琵琶湖湖畔で、夫、双子の息子、ラブラドール・レトリーバーのハリーとともに暮らす。訳書にトウェイツ『ゼロからトースターを作ってみた結果』、ランド『メイドの手帖』、リン『ダメ女たちの人生を変えた奇跡の料理教室』など。著書に『家族』『ハリー、大きな幸せ』『村井さんちの生活』『兄の終い』『村井さんちのぎゅうぎゅう焼き』など。

