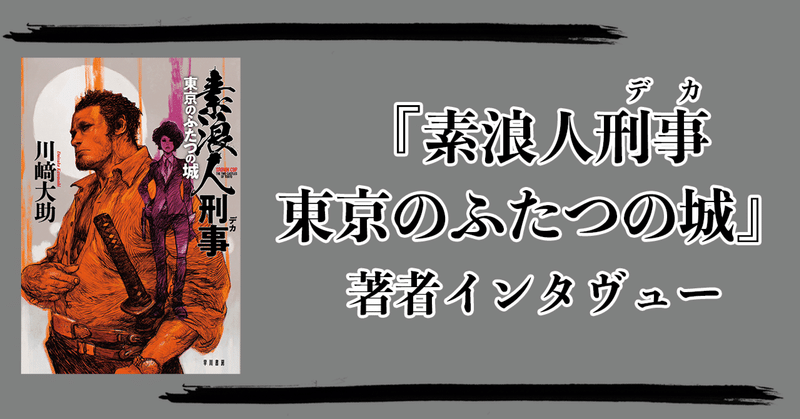
大政奉還がなされず、2020年代まで徳川幕府が続く日本の物語――『素浪人刑事(デカ) 東京のふたつの城』刊行記念 著者 川﨑大助インタヴュー

川﨑大助氏の最新作『素浪人刑事(デカ) 東京のふたつの城』が早川書房より刊行されました。音楽ライター、編集者としても活躍する著者の新作は、現代の徳川幕府が舞台のノワール警察小説です。
明治維新がなく、400年を超えて徳川幕府が統治する、2020年代の日本。征夷大将軍の下、刑事は腰に帯刀していた。組織からはぐれた刑事・桑名十四郎が、将軍家にまつわる謀略の渦中に巻き込まれていく。
こちらの記事では「ミステリマガジン」5月号(2024年3月25日発売予定)に掲載のインタヴューを先行公開いたします。
■フィクションを書いたきっかけ
──ミステリマガジン読者に向けて、川﨑さんのプロフィールを伺いたいと思います。
川﨑 一九八〇年代終わりから《ロッキング・オン》というロック雑誌で原稿を書いていました。最初は洋楽の知識しかなかったんですけど、折しもバンドブームが起こりまして、イカ天とかもあって人手はいくらでも欲しい、そうしたところから邦楽も手掛ける音楽系の売文業を始めました。キャリアの途中で、自費出版でインディーマガジンの《米国音楽》を創刊しました。一九九三年ですね。当時は雑誌も本も売れる時代でしたが、とくにCDがめちゃくちゃ売れて、業界は右肩上がりでした。それが終わったのが一九九九年で、とにかく新人をデビューさせて、小売店にCDを押しつけ、返品すればいいという荒い商売の底が抜けたのだと思います。
──その後、『東京フールズゴールド』でフィクションを書かれるわけですが、経緯を教えていただけますか。
川﨑 そもそも、二〇〇四年ぐらいから書き溜めていたものがあったんです。音楽業界で見たような魅力的な人物、一般社会的には迷惑な奴かもしれないけど愛すべき人間を、フィクションの中に息づかせることができるんじゃないかと思って組み立てていったものが『東京フールズゴールド』です。元ミュージシャンの一人称で、一度は売れたことがあるのだけど、その後レコードプロデューサーになり、色々なレコード会社に詐欺のようなことをやっているろくでもない男が主人公で。人生を追いこまれた彼が、最後にどうするかというピカレスクです。真面目に小説を書くのは初めてで、書き方がわからず、一人称がやりやすいだろうと思いこんで、「俺」の一人称・現在形で書きました。興味を持ってくれた河出書房新社の編集者に読んでもらったら、おもしろかった、いけるかもという話になった。でも僕が七百枚ぐらいかと思ってたら「千枚あるじゃないですか!」と怒られて(笑)。
──『東京フールズゴールド』は、ミステリ的な犯罪小説の趣もありますが、どのような作品を読まれていたんでしょうか。
川﨑 小学生のころからシャーロック・ホームズものやアガサ・クリスティー作品はもちろん、あらゆるところに手を伸ばす感じだったんですけど、ポケミスのエド・マクベイン〈87分署〉シリーズの井上一夫さん訳との出会いは大きかったですね。それからリチャード・スタークも、決定的だった。公立図書館にある程度そろっていたので、むさぼり読みました。
その頃に、どうやら読めないタイプの小説があると気づいたんです。日本人が書いた小説で、一行目二行目で、これはダメだな、と思って投げだすことがままあって。最初は理由がわからなかったんですけど、僕は文体で読むところがあるようで。この人の論理や喋り方は違うなと思うと、入り込めない。でも翻訳作品だとそれは非常に少ないんです。特に英語からの翻訳だと、自分とは多少合わないなと思っても、原文はこうなのかなと想像しながら読んだりできる。
どうやら僕は、子供のころから、自分自身の文体をずっと探していたのかもしれませんね。日本語の使い方とか、持っていき方みたいなところで、原典があったうえでそれを日本語に落とし込むという人のものだと、周波数がよく合ったというか。片岡義男さんや村上春樹さん、長谷川四郎さんのように、翻訳も手掛けている人の作品ですね。
──『東京フールズゴールド』の後のお話を伺えますか。
川﨑 同作の初稿を書き上げたあと、誰も相手にしてくれないので、とにかく小説を発表するには自分でやるしかない、場所を作るしかないなと思い、《IN THE CITY》というペーパーバック型の雑誌を創刊し、そこに短篇を書きました。版元はBEAMSのカルチャー部門が写真集などを出していて、「活字もあったほうがいいですよ」「ニューヨークだったら、カポーティがディスコに行くようなカッコいい感じで」とアプローチしました(笑)。企画が進んでいく中で、都会的な小説誌の旗手として誰をフィーチャーするといいだろう、「そうだ、片岡義男さんだ」と思ってお声がけをしました。
──川﨑さんは片岡さんとの接点はあったのでしょうか。
川﨑 直接の接点はなかったんです。一読者としての僕が最初に覚えているのは、ツル・コミックの『うでずもう選手スヌーピー』の巻末エッセイを片岡さんが書かれていたこと。車に乗って、大きなスヌーピーのぬいぐるみを乗せて、メキシコの国境へ行って入ろうとするけれど、警官に「大麻を買ってくるんだろう? 帰ってきたらその犬の腹をかっさばいてやる」といわれて、スヌーピーがかわいそうだから行かなかったという話なんです(笑)。一九七四年、自分が九歳の頃に読んで、この人の書き方ってカッコいいなと思ったんです。それから角川文庫の片岡さんの作品を読んで、ああいう文章を書かれているご本人はどういう人なのかすごく興味があった。そこを《IN THE CITY》を通じてお付き合いさせていただくあいだに、役得というか、身近で学ばせてもらいました。自分が日常的に接している日本と、フィクションの世界との合わせ方というか、活字の上での落とし込み方が、「片岡さんの場合は、そういうことだったのか」という理解をさせてもらった。外国文学をむさぼり読んで、ガンガン買っていた自分、片岡さんの文章を読んでいた自分への「答え合わせ」を得て、なるほどと理解し、自分のやり方を見つけていったところはあります。
──具体的にはどういうことでしょうか。
川﨑 片岡節というものがあるんですよね。実際は神保町の喫茶店で原稿を書いているのだけど、初期の片岡さんは、設定がそこから遠ければ遠いほど「書きやすかった」そうなんです。だから若者が気ままにアメリカを旅しているようなストーリーが重要だった。ただ、書いているのは日本語だし、それ以前の時代、五〇年代とかの日本映画や娯楽小説の言葉遣いが片岡さんの小説に大きな影響を与えていると思うんですけど、それを咀嚼してああいう風に持っていくわけです。そのやり方というのは、目の前に現実に見えているものを「あるある」とお互い安易に納得し合って終わり、ではない。逆にそこは、気にしてはいけない。馴れ合いはいらない。誰もが「わかる」商店街の風景が目の前にあったとしても、それを「どう描くか」というところの「溜め」が重要というか。人が普通見ようとしない部分まで顕微鏡的に見る視線と、さらにはそれが「かくあるべきものなのか?」と問うことを同時におこない続けているような、ストイックな厳しさが、片岡義男の小説内の商店街になる。だからときに非人情的な、無機質と思えるような風景になるのだと、僕は解釈しました。
■『素浪人刑事(デカ) 東京のふたつの城』について
──その川﨑さんの新作が『素浪人刑事(デカ) 東京のふたつの城』です。
川﨑 考えてみると初のSFです。いわゆるクライムノベルの要素が入っているものはいっぱい書いたのですが、モロにやったことはないし、個人的には日本の警察組織が好きではないので警察小説を書いたこともない。ただ、アイデア自体はずっとあったんです。小説を書き始める前、二、三十年前ぐらいから。徳川幕府がずっと続いていて、武士とは軍人であり警察官だから、現代においても腰に刀を差している。冒頭と結末のアクションシーンはその頃から頭にありました。
このアイデアがそもそも生まれたのは、NHKの大河ドラマへの反発からじゃないかなと思うんです。あまり僕は大河ドラマは観ないのですが、実家にいたころは親が観ていて、つい一緒にという経験はあった。それなりに楽しめる作品もあったんですけど、しかしあれが毎年続いていることへの、居心地の悪さと気持ちの悪さは感じていた。歴史を題材に、あんなフィクションをやってもいいのかと。戦国時代や明治維新、つまりは史実をおもに題材にしていますが、結局のところ偉人伝になってるじゃないですか。歴史の暗部への反省も、批評的視点もない。史実が必ず肯定的な評価へと落ちついていくわけで、江戸時代の講談みたいというか。
──武将なりを主人公にして〝ドラマチックに〟しないといけないですしね。
川﨑 そうなんですよ。アメリカンニューシネマの時代に、観ると後悔するような西部劇ってあったじゃないですか? 騎兵隊がネイティヴ・アメリカンを虐殺するとか。スコセッシの『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』もなかなかすごい映画でしたし。そうした傾向のものは、NHKはやらない。
言うなれば「明治維新絶対教」であり「徳川家康絶対教」。史実を偉人物語にして、まるごと肯定するというドラマを、日本では毎年毎年やり続けているわけです。要するに歴史観の刷り込みですよね。たとえば明治維新の後に戦争が続き、周辺諸国にとっては「ふざけるな」という負の部分に関しても、「まあいいじゃないか」というのが、大河ドラマの基本姿勢としか思えなくて。そこに僕は、大きな引っ掛かりがあった。たかがドラマかもしれませんが、想像力を制限されているようにすら感じて。だから僕は大河ドラマを観て楽しむよりも、「あった」とされている歴史のどこかの部分が「もしも、違う展開になっていたら?」と想像してみることのほうに、意義を感じたんでしょう。「絶対教」の教義の外や裏っかわにある日本を思い描いた。
『高い城の男』みたいな発想ですよね。でも日本が太平洋戦争で勝った話を、日本人の僕が書いても面白くない。気色悪い。それよりも明治維新のほうが、いじりがいがある。そう思ったんですが、どうも「絶対教」のせいか、そこは手をつけてはいけない聖域みたいになっているんじゃないかと。一種の禁忌があるのでは、とぼんやりと思ったんです。
そこですごくやる気が出てきまして、いろいろ妄想しているうちに、刑事が刀を腰に差していて、斬り合いはやるのだけど、銃が社会にあったら普通は併用するよな、とか。すると次第にアクションシーンが浮かんでたんです。
──確かに、刀と銃が共存しているのは面白いですね。
川﨑 銃と刀が入り混じっている。併存している世界だということが、この小説のリアリティを支えている重要なパーツのひとつです。実際に現実世界の日本軍も第二次大戦終結まで刀を装備し、使用していましたしね。
こうした世界観とアクションの手ざわりの元は頭の中にあったんですけれども、そこからなかなか、ストーリーとして発展していかなかった。どうにも話が大きくなりそうで、攻めあぐねていたというか。そんなときに、マイケル・シェイボンの作品に出会ったんです。
──そのタイミングで『ユダヤ警官同盟』を読まれたと。
川﨑 いわゆる改変歴史ものですね。この小説世界では、イスラエルという国が存在しない。一九四八年の戦争に負けて、数百万人のユダヤ人が米アラスカ州内に設けられた特別区に暮らしている。イスラエル建国に再挑戦するシオニストの陰謀も地下で巡っている……と、そんな設定のなか、一人の警察官が殺人事件を追っていく。つまり小さなところから入っていって、かなり大きなところまで話がつながる。自分が考えているものも、あまり大きく構えずに進めればいい。たとえば『ブレードランナー』のデッカードも、彼自身は大きなことを考えているわけではない。主人公の足取りから見えてくる範囲で小説になるんじゃないかと気づいたんです。これはいけるかもしれないと思い、本格的に準備をしました。
日本人の歴史観でユニークなところは「虚実ないまぜ」の戦国武将の話なんかを、一種の思想的背景にまで持ち上げちゃう人が少なくないことで。山岡荘八の『徳川家康』が座右の一冊という財界人や会社経営者って、普通にいるじゃないですか? とくに珍奇な人あつかいもされずに。でもこれがアメリカでもし「わしはデイビー・クロケット伝が座右の一冊で……」なんて経営者がいたら、ちょっとまずいかもしれない。文学は文学としてあっていいし、評伝や自伝もあってもいいのだけど、フィクショナルな英雄伝を「思想書」あつかいするのは、危険きわまりない幼稚さに思える。でもそれが日本の大河ドラマの根本ですよね。「あったこと」を肯定し続ける歴史エンターテイメントという。
しかしエンタメだったとしても「それ以外の観点」の批評性も、あって然るべきだと思うんですよね。それがないと、日本の歴史ものは、いつまで経っても『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』の地平には立てないし、かくあるべき現代性を備えたストーリーにはなり得ないんじゃないか、と。
そう思った時に、ずっと存続している徳川幕府が治める日本像が、自分のなかでくっきりと見えてきた。今の日本では考えられない反転した世界なのだけど、掘っていけばいくほど、現実の日本人の本質が浮かびあがってくる……そんな手応えを感じつつ、書いていきました。
──そこで見えてきた日本人の本質とは?
川﨑 端的に言うと、人心は江戸時代とほとんど変わっていないんですよ。江戸時代の二百六十年間というのは、時計の針が止まったままピタッと温存されたような世界だったわけですが、どうやら、まだ続いている。明治になって突然の文明開化で、表向きは急に近代化したのかもしれないのだけど、その弊害は逆に大きくて。そして結局本質的なところでは、今の世相や社会問題じゃないですけど、封建時代とあまり変わっていないんじゃないかという気がしています。
たとえば侍が元来持っている残虐性や暴力性、それをことさらに賛美するような精神性というのは、もちろん徳川幕府が続いている作中世界のほうが露骨ではあるんですが、じつは現実世界の日本も、かなり近いですよね。日本刀や侍、みんないつになっても大好きです。日本政府のアメリカに対しての服従姿勢すら、じつは「侍っぽい」のかもしれない。だから現在のこの体制が、終戦の一九四五年から数えて二百六十年ぐらいは続くんじゃないかな、なんて時々思います。
純粋なエンターテインメントのつもりで書いてはいたのですが、どうやら徐々に「今の日本と近い」という要素が、自然に浮かび上がってきたようです。読者には、この観点も面白がってもらえれば嬉しく思います。
■改稿を経て新たな構成に
──第一稿から四百枚ほど増え、第二稿の段階で新たに構成が固まっていきました。
川﨑 そうですね。機動隊とのどつき合いというのは、この世界を舞台にした別のストーリーで考えていたことなんですけれども、これはいけると思って、結果、サブタイトルにつながる構成ができていきました。僕の場合、長篇だと絶対にそうなんですけど、最初にカッチリ構成していても、途中で変わっていくんですよね。キャラクターが勝手に動き出すじゃないですけれども、書いているうちに、より見えてくることがある。「この登場人物は、本当は、陰でこんなことしていたのか」なんてあとから気づくとか、よくあります。
──大河ドラマ的な歴史観に対する反発は、初稿の段階からもあったのでしょうか。
川﨑 それありきですから。武士が刀を持ってうんぬんというのは、非常に日本的な男らしい世界なんですが、そうした直線的なカタルシスだけだとつまらない。主人公、桑名十四郎は剣も銃も達者なんですが、しかしいろいろな点で弱さがある。この弱さが、彼の場合「やさしさ」につながっていくんですが、周囲のピシッとした女性に助けられてナンボというバランスで。そして組織からはみ出して、組織と衝突せざるを得ない地点に追いこまれていく……だから日本的な題材ではあるんですが、大河ドラマ的な価値観じゃないところをこそ目指していくフィクションなんです。
西部劇だと思って観ていたら、ニューシネマだったみたいな。『明日に向って撃て!』には、決してジョン・ウェインは出てこない。この小説の主人公も、侍ではあるんですが、今の日本社会でNHKの大河ドラマ的なものとして認められているものとは違う種類の、何かを背負っている。
──徳川幕府が続いているという中の警察組織は、どのように設定したのでしょうか。
川﨑 僕は日本を舞台にした警察小説をほとんど読んでいないので、警察小説で自分に一番馴染みがあるジェイムズ・エルロイの世界観が下地になりました。エルロイの警察がらみ小説で僕が大好きなところは、出てくる警察官がみんな悪い奴ばかりだという点で。この悪人性もまた、弱さですよね。
イギリス人のDJの友人が来日した時、渋谷かどこかの交番の警官を見て「こんなに平和そうな日本なのに、なんで交番にいる人がみんな銃を持っているのか」とショックを受けてたんですよ。ガンコントロールがかなりしっかりしているイギリスでは、特別武装チーム以外の制服警官は銃を持っていない。警棒だけを装備するという伝統がありますから。
だからある種、日本では、銃はいつでも我々に向けられるものかもしれない。暴徒鎮圧の任務を帯びた機動隊員同様、まるで侍みたいに「腰に武器を帯びた」状態で市民を威圧し続けている、のかもしれない。だから刀を持った警官がいれば、僕の小説のようになるに違いない。武士だから庶民より偉いんだし、そもそも「切捨御免」とかあるんだし。
というような想像力を活かすパレットとして、エルロイ的な警察官が跋扈する日本は最適だったかなと思います。
──第二稿以降の構成で、大きく変わったのはどういう点でしょうか。
川﨑 第一稿は、主人公の桑名が事件を追うのだけれども、どうにもならないから決闘をして決着をつける、というだけの小さな話でした。しかし、彼がぶち当たった「謎」の周囲にあったはずの陰謀に気がつきまして。事件を追う刑事が、大きなシステムと衝突してしまう、より大きなストーリーが浮かび上がってきました。そこから「この世界の根幹」へと結果的に続く旅へと向かっていくことになる。
しかしそうなると、彼は決定的に組織から浮いてしまう。つまり刑事なれど「素浪人」の立場になってしまうわけですね。だから、仲間とつながる、そこに価値を見出すような状況にはできたかなと思います。
現代なのに刀を腰に差している、という素っ頓狂な状態にあるだけに、人物像にはリアリティを持たせたくて。刀を持って非現実的に暴れる話は漫画やアニメでいっぱいありますけれど、それとは違う、生々しさがほしかった。痛みを感じるアクションというか。うだつが上がらない中年男が、現実の我々と近いような皮膚感覚のもと、熱い寒いといったことを感じながら、とんでもない事態に対処してくわけです。この点でカバーイラストの寺田克也さん、すごいですよね。桑名をそういう顔に描いてくださっているんです。強面なだけじゃない、何か考えていそうな顔を。
──徳川幕府が続いているという設定でありながら、小説も音楽も海外のものに触れてきた川﨑さんが書かれたからこそのオリジナリティがありますね。
川﨑 徳川幕府が続いていたらというのは、日本社会を描く際のひとつの誇張の手段のつもり……だったんですが、正直、そっちの方が日本社会はまともだったんじゃないか、と思うことも最近よくあります。今よりはもっと、裏表なく、ごく普通の立憲君主国に近い体制へと発展できたんじゃないかな、とか。今の日本の歪んだ権力構造よりは、この小説世界のほうが、普通に可視化されたシンプルな圧政なのでは、とか。だから昔の左翼学生が『あしたのジョー』を読んでいたような感じで読んでもらえればいいですよね。
とはいえエンターテイメントとして書いたので、面白がっていただくのがなによりです。僕はロックのアルバムを聴く時に、このアーティストは普段こういう発言をしているから汲み取って……とかいったところからは、まず入らない。普通に針を落として、ノレるところはノッて、楽しみます。そんなふうに接してもらえると、とてもありがたいです。
(インタヴュー収録日/2月20日 於:早川書房)
◆書誌情報
タイトル:素浪人刑事(デカ) 東京のふたつの城
著者:川﨑大助(かわさき・だいすけ)
ISBN:978-4-15-210303-1
発売日:2024年2月21日
◆あらすじ
明治維新が頓挫し大政奉還されず、2020年代まで徳川幕府が存続している日本。そこでは軍人同様、刑事もまた腰に刀を帯びた「さむらい」だった。ある日、停職中の刑事である桑名十四郎の眼前で、旧知の情報屋ホセが射殺される。背後には、幕府存続に関わる警察上層部の謀略があった。移民ヤクザ、汚職警官、草の者、忍び、そしてエリート警察部隊……「素浪人」の立場のまま個人的な捜査を進める桑名の前に、闇のネットワークが立ち塞がる。
◆著者紹介
1965年生まれ。88年、ロック雑誌《ロッキング・オン》にてライター・デビュー。93年、インディー雑誌〈米国音楽〉を創刊。編集、発行、グラフィック・デザイン、レコード・プロデュースを手掛ける。2010年より小説発表開始。おもな著作に、長篇小説『東京フールズゴールド』、音楽書『僕と魚のブルーズ 評伝フィッシュマンズ』『教養としてのパンク・ロック』などがある。本作が長篇第2作となる。

